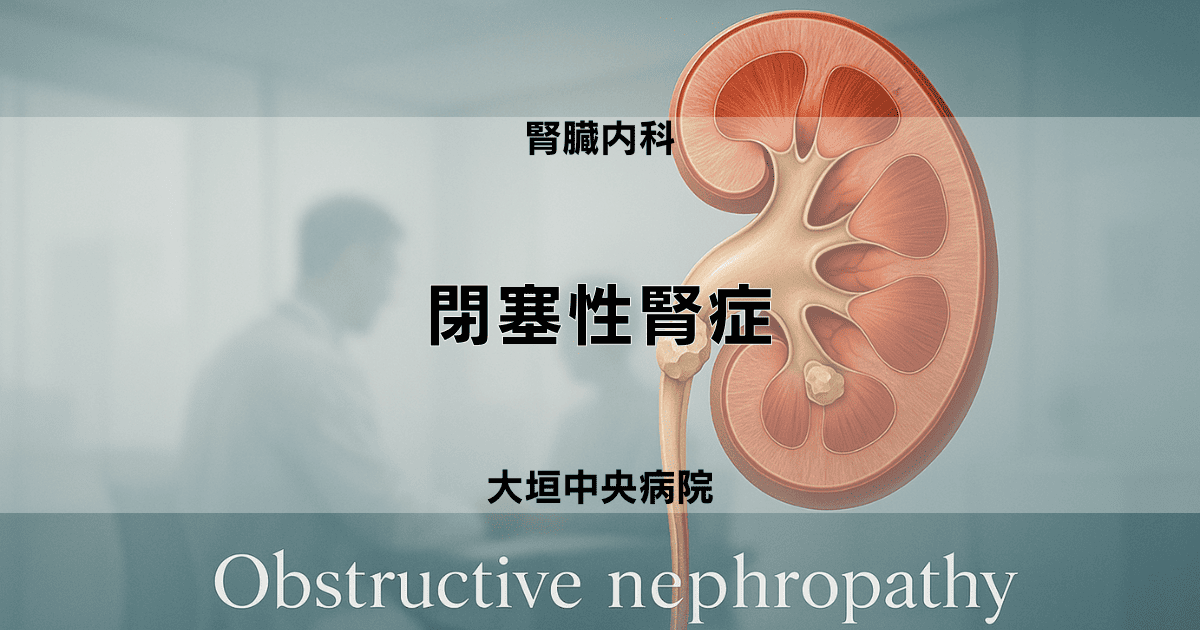閉塞性腎症とは、尿路のどこかに生じた物理的な詰まりによって尿の流れが阻害され、腎臓に負荷がかかる病態のことです。
尿路は腎臓から尿管、膀胱、尿道へと続き、これらのどこかで通り道が狭くなったり閉じたりすると、腎機能が低下し、放置すれば慢性腎不全に至る可能性があります。
閉塞を起こす原因には結石や腫瘍、前立腺肥大症などがあり、高齢者や泌尿器疾患を抱える方でリスクが高まることが多いです。
この疾患は痛みや血尿などの顕著な症状が出るケースもあれば、自覚症状に乏しく進行することもあり、気づかないうちに腎臓がダメージを受ける可能性があります。
閉塞性腎症の病型
閉塞性腎症は、尿路のどの部位がどのように詰まるかによっていくつかのタイプに分類でき、詰まりが起こる位置、閉塞の程度、閉塞の一時性か慢性的かといった要素によって臨床的な経過や症状が変わり、治療戦略も大きく異なります。
上部尿路性閉塞
上部尿路性閉塞は、腎臓から膀胱に至る尿管の部分で詰まりが生じるタイプです。
尿管結石や腫瘍によって内腔が狭くなる場合や、外部からの圧迫で通り道が狭くなる場合があり、腎臓から出た尿がスムーズに流れず、腎盂や尿管が拡張して水腎症の状態が起こり、腎機能の低下を招く可能性があります。
下部尿路性閉塞
下部尿路性閉塞は、膀胱や尿道に原因があるケースで、男性の場合は前立腺肥大症や前立腺がんが典型的であり、膀胱出口や尿道周辺が圧迫されて尿が出にくくなります。
女性の場合は骨盤内臓器の下垂や腫瘍などで尿道周辺が狭窄することがあり、排尿障害を自覚しやすいですが、高齢者では症状を見過ごすこともあります。
両側性と片側性の違い
閉塞が両方の尿管に及ぶ場合や、尿道や膀胱など単一の部位で閉塞があっても両側の腎臓に影響が及ぶ場合は、両側性の閉塞と考えられます。両側性の方が腎機能の悪化が急速に進む傾向が高く、緊急の処置が必要になることが少なくありません。
一方、片側の尿管だけが詰まる片側性閉塞では、閉塞側の腎機能のみが低下しますが、長期にわたると残存腎機能全体にも負荷がかかることがあります。
急性と慢性
急性閉塞性腎症は、尿管結石や急な血塊によって急激に尿路が塞がることで発症し、激しい痛みや血尿を伴うことが多いです。
慢性閉塞性腎症は、徐々に狭くなる尿路や前立腺肥大症などの影響で長期間かけて進行するパターンであり、はっきりとした痛みが少ないため、症状が目立たないまま進行するケースがあります。
主な病型に関して患者さんが意識しておきたい点
- 上部尿路性では結石や腫瘍、狭窄によって尿管の通過障害を起こしやすい
- 下部尿路性では前立腺肥大や膀胱・尿道の狭窄で排尿障害が顕在化する
- 両側性か片側性かで、腎機能へのダメージの度合いが異なる
- 慢性的に進む場合は痛みが少なく、無症状で発見が遅れることもある
上部尿路性閉塞と下部尿路性閉塞の大まかな違い
| 分類 | 代表的原因 | 病変部位 | 主な症状・所見 |
|---|---|---|---|
| 上部尿路性閉塞 | 尿管結石、尿管腫瘍など | 腎盂、尿管 | 腰背部痛、水腎症、血尿 |
| 下部尿路性閉塞 | 前立腺肥大症、膀胱腫瘍など | 膀胱、尿道 | 排尿困難、残尿感、頻尿など |
病型によって特徴があり、どのレベルで尿の流れがブロックされるかによって症状や治療方針が変化します。
閉塞部位の判定に役立つ手がかり
- 側腹部~背部にかけて強い痛みを伴う場合は上部尿路結石を疑いやすい
- 排尿時の違和感や残尿感が長引く場合は下部尿路の狭窄を想定しやすい
- 両側の腎機能が急激に低下する場合は両側性閉塞を考慮
- 血尿が出るが痛みがない場合は慢性的な閉塞進行の可能性を検討
閉塞性腎症の症状
閉塞性腎症の症状は、閉塞の場所や程度、急性か慢性かなどの要因によって多岐にわたります。
はっきりした痛みがあるケースだけでなく、実際には軽度の違和感や尿量変化だけで進行している場合もあり、気づかずに放置すると腎機能が失われるリスクが高いです。
疼痛と不快感
腎結石などによる急性閉塞では、側腹部から腰背部にかけて鋭い痛みが突然走ります。
いわゆる「疝痛発作」と呼ばれる激痛で、我慢できないレベルの痛みを経験する人もいますが、前立腺肥大症や慢性的な下部尿路閉塞では、はっきりとした痛みは生じにくく、下腹部の軽い違和感やおしり周囲の圧迫感などが続く程度です。
血尿
血尿は尿の通過障害や結石の物理的刺激、腫瘍などによって尿路が傷つくことで起こり、見た目でわかる場合(肉眼的血尿)と、尿検査でのみ確認できる場合(顕微鏡的血尿)があります。
痛みを伴う血尿なら結石などの急性疾患を疑い、痛みが少ない血尿なら腫瘍などの可能性も視野に入れことが必要です。
血尿が疑われるときに意識しておきたいポイント
- 明らかに赤茶色やピンク色などの変色があれば医療機関で相談する
- タンパク尿や尿細胞成分の有無を検査で確認すると発生源を推定しやすい
- 疼痛の有無や発作のタイミングと関連づけて発症を記録する
血尿に関連した主な原因疾患
| 原因疾患 | 血尿の特徴 | 併発しやすい症状 |
|---|---|---|
| 尿管結石 | 発作的な痛みが伴うケース多い | 側腹部から背中への激痛 |
| 前立腺肥大症 | 目立つ痛みは少ない | 排尿困難、頻尿など |
| 腎腫瘍 | 痛みが少ない場合もある | 体重減少、倦怠感など |
| 膀胱炎や膀胱結石 | 下腹部痛や排尿時痛みが強い場合 | 頻尿、残尿感 |
尿量の変化と排尿困難
尿路の詰まり具合によっては、尿量そのものが減少したり、排尿までに時間がかかったり、腹圧をかけないと尿が出にくくなる場合があります。
男性の場合、前立腺肥大症が進行すると排尿時間が長くなり、夜間の頻尿が目立ってくることが珍しくありません。尿の勢いが弱くなったり、中断してしまったりすることも、下部尿路閉塞のサインです。
注意しておきたい排尿時のトラブル
- いつもより尿のキレが悪く、中断されやすい
- 1回の排尿量が減って少しずつしか排出できない
- 夜間だけやたらと尿意を覚え、睡眠を妨げられる
- 排尿直後でも残尿感が持続し、すっきりしない
全身症状
慢性的に腎機能が低下すると、倦怠感や食欲不振、むくみ、高血圧などの症状が現れることがあり、特に高血圧は、腎臓から分泌されるホルモンバランスが乱れることによって促進され、動脈硬化の進行にもつながる可能性があります。
急性型と慢性型それぞれでみられやすい症状
| 型 | 主な症状・所見 | 経過の特徴 |
|---|---|---|
| 急性型 | 激しい腰背部痛、血尿 | 突発的に痛みが発生する場合 |
| 慢性型 | 排尿困難、夜間頻尿、疲れやすさ | 痛みが少なく気づきにくい |
原因
閉塞性腎症を引き起こす原因は多様であり、年齢や性別、基礎疾患の有無などによって大きく異なり、尿路が物理的に狭くなったり遮断されたりすることを直接の要因とし、それをもたらす疾患や状態は複数あります。
尿路結石
尿路結石は腎臓内で形成された結石が尿管や膀胱へ移動し、通り道を塞ぐことがあり、ミネラルや老廃物が結晶化してできるため、水分摂取量の不足や食生活の乱れ、体質などが結石形成に影響を与えます。
特に腎臓や尿管での結石が大きくなると、尿が下流へ流れにくくなり、水腎症や腰背部痛を起こすので注意が必要です。
前立腺肥大症や前立腺がん
男性の高齢者に多い前立腺肥大症は、前立腺が大きくなることで膀胱出口や尿道を圧迫し、下部尿路性閉塞を招きます。
長期にわたって排尿障害が続くと、膀胱に残尿が溜まりやすくなり、尿路感染や腎機能低下に結びつくことがあり、さらに前立腺がんが進行すると同様のメカニズムで閉塞を生じる可能性があります。
高齢男性の閉塞性腎症を考える際にチェックしておきたい点
- 排尿時に勢いが弱い、途切れるなどの初期症状
- 夜間に複数回起きるほどの頻尿
- 残尿感や下腹部の張り
- 進行すると腎機能が低下してむくみや高血圧が目立つ
前立腺肥大症と前立腺がんの比較
| 項目 | 前立腺肥大症 | 前立腺がん |
|---|---|---|
| 好発年齢 | 60代以降に増加 | 50代~60代以降 |
| 主な症状 | 排尿困難、夜間頻尿、残尿感 | 初期無症状~排尿障害など |
| 病態の進展 | 緩やかに症状が強くなる | 進行度により転移リスクあり |
腫瘍や癌
腎盂や尿管にできる腫瘍、膀胱がん、骨盤内臓器の腫瘍などが尿路を圧迫したり、直接狭窄をつくったりする場合があり、腫瘍が大きくなるほど尿路閉塞のリスクは高まり、血尿や腰痛、体重減少などが出るケースもあります。
悪性腫瘍の場合は進行によって周囲組織への浸潤が起こりやすく、閉塞が広範囲になることがあります。
先天性や外傷性の狭窄
先天的な尿管の形態異常や、生まれつき尿道が狭いなどの疾患でも閉塞性腎症は起こり得、また、過去の外傷や手術痕が瘢痕化し、尿管や尿道の狭窄を生じて慢性的な閉塞をもたらすことも考えられます。
主な原因疾患や状態
| 原因疾患・状態 | 主な特徴 | 閉塞の部位 |
|---|---|---|
| 尿路結石 | 腎臓や尿管内での結晶化 | 上部尿路 |
| 前立腺肥大症・前立腺がん | 男性高齢者に多く、排尿障害を招く | 下部尿路(膀胱出口~尿道) |
| 腎盂・尿管・膀胱腫瘍 | 腫瘍の増大や浸潤で尿路を圧迫 | 上部または下部尿路 |
| 先天性や外傷性狭窄 | 生まれつきの形態異常や外傷後の瘢痕化 | 尿管、膀胱、尿道など |
閉塞性腎症を予防する上で気に掛けること
- 水分をしっかり摂取し、結石形成を抑える
- 中高年男性は排尿時の違和感を見逃さず早期受診する
- 不調が続く場合は泌尿器系の腫瘍や先天性異常の可能性を検討
- 健康診断や画像検査で異常が指摘された場合は追加検査を計画
閉塞性腎症の検査・チェック方法
閉塞性腎症を疑う場合、泌尿器系の機能を調べるために複数の検査を組み合わせて総合的な判断を行い、尿路の構造や腎機能、結石や腫瘍の有無を確認し、閉塞の原因と程度を明らかにすることが目標です。
尿検査
尿検査は手軽に実施できる初歩的な検査であり、尿中の血液やタンパク、白血球などを調べることで結石や感染、出血の有無などを推定します。
もし血尿が認められた場合は、原因が結石による物理的刺激なのか腫瘍による出血なのかなどを次の検査で確認することになります。
尿検査からわかる情報
- 潜血の有無とその程度
- 尿路感染を示唆する細菌や白血球
- pHなどの理化学的性状(結石の種類推定に役立つ)
尿検査で確認する主な項目
| 検査項目 | 意義 | 代表的な異常値からの推定 |
|---|---|---|
| 尿潜血 | 結石、腫瘍、炎症などで出血が起こる | +になる場合、結石や腫瘍の可能性 |
| 尿蛋白 | 糸球体障害や腎機能低下などの有無 | 一定以上だと腎障害が進んでいるか |
| 尿沈渣 | 尿中の細胞成分や結晶、細菌の観察 | 結晶が見られれば結石を疑う |
| pH | 結石形成や感染環境を推定 | アルカリ性だと感染結石を疑う |
画像検査
画像検査は閉塞性腎症を診断する上で非常に重要な手段で、超音波検査(エコー)は放射線被ばくがなく、腎臓や膀胱の形態、尿管の拡張、水腎症の有無を比較的簡便に把握できます。
さらにCT(コンピュータ断層撮影)は、結石や腫瘍の存在、サイズ、位置関係を精密に評価が可能です。MRIも軟部組織の描出に優れ、悪性腫瘍の浸潤度合いを確認するときに活用します。
画像検査を受ける際の心得
- 超音波検査は短時間で済むが、検者の技量によって評価が左右されやすい
- CTは結石の診断精度が高く、造影CTでは腎機能や腫瘍血管を詳しく調べられる
- MRIは時間がかかり費用もかさむが、ソフト組織の詳細がわかりやすい
画像検査の種類
| 検査法 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 超音波検査 | 被ばくがなく簡便 | 腎臓や膀胱の形態、水腎症の有無など |
| CT | 結石や腫瘍の評価が正確 | 結石の検出、悪性病変の位置診断 |
| MRI | 軟部組織描出に優れる | 腫瘍の浸潤評価、CT造影剤使用困難例 |
| IVP(静脈性尿路造影) | 造影剤を使い尿路全体を透視 | 近年はCTに代替されることが多い |
血液検査と腎機能評価
血液中のクレアチニンや尿素窒素(BUN)、eGFR(推定糸球体濾過量)などを測定すると、腎臓のろ過機能がどの程度保たれているかを把握でき、閉塞が進むとこれらの値が徐々に悪化し、重症例では急性腎不全に陥る可能性があります。
また、電解質バランスや貧血の有無も確認し、全身状態を総合的に評価します。
尿路内視鏡検査
必要に応じて、実際に内視鏡を尿道から挿入して膀胱や尿管の内部を観察し、結石や腫瘍などの詳細を確認する場合があります。直接視で観察するため、原因病変の性質を把握しやすく、そのまま治療に移行することも可能です。
ただし体への負担もあるため、画像検査や症状から判断し、適切なタイミングで検討します。
治療方法と治療薬について
閉塞性腎症の治療は、原因となる閉塞を取り除く方法と、腎臓機能を守り合併症を防ぐためのサポート療法の2つの軸で進行し、結石や腫瘍など可逆的な要因がある場合は、それを除去または縮小させる処置が最優先と考えられます。
結石除去・砕石療法
尿路結石が原因の閉塞性腎症の場合、結石の位置やサイズに応じて衝撃波砕石術(ESWL)や内視鏡下砕石術などを検討し、ESWLは体外から衝撃波を当てて結石を細かく砕き、自然排出を促す方法であり、体の負担が少ないです。
内視鏡下砕石術は内視鏡を尿道から挿入して直接石を確認しながら砕き取る方法で、石が大きい場合やESWLが困難なケースに用いられます。
結石治療の際に覚えておきたいリスト
- 結石の性質(カルシウム系か尿酸系かなど)によって治療方法が異なる
- 砕石後は石片の自然排出を助けるために十分な水分摂取が重要
- 大きな石や硬い石、複数ある場合は複合的な治療が必要になる
結石除去法と適応例
| 治療法 | 方法の概要 | 適応例 |
|---|---|---|
| 衝撃波砕石術(ESWL) | 体外から衝撃波で結石を粉砕 | 2cm未満程度の結石が対象になることが多い |
| 内視鏡下砕石術 | 尿管鏡や膀胱鏡で直接結石を砕いて除去 | 大きな結石やESWLが困難な部位の結石 |
| 腎瘻造設+砕石 | 腎臓に穴を開けて管を通し結石を除去 | 上部尿管や腎杯内に大きな結石がある場合 |
前立腺肥大症・腫瘍性病変の治療
男性の高齢者に多い前立腺肥大症が原因の場合、薬物療法としてα1遮断薬(タムスロシンなど)や5α還元酵素阻害薬(デュタステリドなど)を使用し、前立腺を縮小または尿道圧迫を緩和することが一般的です。
症状が進んでいる場合は、経尿道的前立腺切除術(TURP)やレーザー治療などの外科的手段も検討します。
前立腺肥大症で使用する主な薬剤
| 薬剤分類 | 代表薬剤 | 作用 | 主な副作用 |
|---|---|---|---|
| α1遮断薬 | タムスロシンなど | 尿道や前立腺平滑筋を弛緩させる | めまい、血圧低下、倦怠感など |
| 5α還元酵素阻害薬 | デュタステリドなど | 前立腺を小さくし、尿道圧迫を減らす | 性機能低下、乳房肥大など |
膀胱や尿管の腫瘍が閉塞の原因であれば、内視鏡手術や外科的切除、放射線療法、化学療法などを組み合わせて治療し、尿路を確保しつつ腫瘍の進行を抑える方針となります。
ステント留置や膀胱ろうなどの尿路確保
結石や腫瘍による閉塞が重度の際や、短期間で排尿障害を改善する必要がある場合は、尿管ステントや腎瘻を作成して人工的に尿の流れを確保することがあります。
尿管ステントは、尿管内に細い管を置いて通路をキープする方法で、腫瘍などで外部から圧迫される場合にも有効です。膀胱にカテーテルを挿入して直接尿を外に導く膀胱ろうも、急性期の対応として利用します。
尿路確保の方法に関して押さえておきたい点
- ステントやカテーテルは長期留置で感染や閉塞のリスクがあるため、定期交換が必要
- 体外からのドレーン管理がある場合は衛生管理や取り扱いに注意
- 腎機能を温存するための応急措置として、根本治療と並行して行うことが多い
薬物治療による腎機能保護と対症療法
高血圧を合併する場合はACE阻害薬やARBなどを使用し、血圧をコントロールして腎臓への負担を軽減し、感染症が併発しているときは抗生物質を投与し、急性期の炎症を抑えます。
排尿困難に対しては利尿剤を使うケースもありますが、状態に応じて副作用とのバランスを検討しながら慎重に行うことが重要です。
閉塞性腎症の治療期間
閉塞性腎症の治療期間は、結石が比較的小さく、砕石術や薬物療法だけで速やかに排石できるケースでは、数週間から1カ月程度の短期間で落ち着く場合があります。
前立腺肥大症や悪性腫瘍など、慢性的に進行する要因がある場合は、長期的なフォローアップを続けながら治療を継続することが必要です。
急性期と慢性期
急性閉塞では、結石や血塊によって突然尿管がふさがったり、腫瘍が急速に大きくなって排尿困難に陥ったりするため、即座に排尿経路を確保しなければなりません。
急性期の処置は数日から数週間で終了することが多いですが、その後も再発や合併症のチェックのため、定期的な検査が大切です。
急性期の治療期間中に意識しておきたいリスト
- 結石が原因なら、砕石後の石片排出状況を確認するため数回の画像検査を受ける
- 感染を伴う場合は抗菌薬の内服期間や点滴治療で1~2週間程度の入院が必要なこともある
- 尿管ステントを留置した場合は交換時期を守り、長期放置での感染や閉塞を避ける
前立腺肥大症や腫瘍の治療期間
前立腺肥大症では、薬物療法によって徐々に症状を緩和するのに数カ月以上かかることが多く、手術療法を選択しても術後の経過観察が続きます。
腫瘍の場合は外科的切除や放射線療法、化学療法などを組み合わせるため、一連の治療が半年から1年以上になるケースもあります。
主な治療法と目安の治療期間
| 治療法 | 期間の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 薬物療法(α1遮断薬など) | 数カ月~継続的に使用 | 徐々に排尿障害を緩和、長期服用が一般的 |
| 経尿道的前立腺切除術(TURP) | 入院1~2週間程度、術後フォロー | 排尿症状の改善効果が高い、術後管理が重要 |
慢性閉塞性腎症の経過観察
腫瘍や前立腺肥大症以外でも、尿道狭窄や先天性異常などで慢性的に閉塞傾向がある方は、定期的に画像検査や腎機能評価を受けながら数年単位でフォローアップを続ける場合があります。
腎機能が安定している間も、生活習慣の改善や再閉塞の早期発見を重視することが大事です。受診することで治療の選択肢が増え、腎機能を守るチャンスも高まるため、違和感があったら医師の診断を受けてください。
閉塞性腎症薬の副作用や治療のデメリットについて
閉塞性腎症の治療で用いる薬剤や処置には有効性がある一方、一定の副作用やデメリットがあります。
薬を飲むことで別の不調が現れたり、外科的処置によって合併症が起きたりするリスクを踏まえて、医師と相談しながらバランスを見つけることが大切です。
α1遮断薬などの前立腺治療薬の副作用
前立腺肥大症に用いられるα1遮断薬(タムスロシンなど)は、尿道の平滑筋を緩めて排尿を楽にする効果がありますが、血圧を下げる作用もあるため、めまいや立ちくらみを起こしやすくなるケースがみられます。
5α還元酵素阻害薬(デュタステリドなど)は、前立腺を縮小させる効果をもたらしますが、性欲減退や勃起障害などが生じる可能性があります。
主な前立腺治療薬の副作用をリスト
- α1遮断薬:めまい、倦怠感、血圧低下
- 5α還元酵素阻害薬:リビドー低下、勃起機能変化、乳房の痛みや膨らみ
衝撃波砕石術や内視鏡下砕石術のリスク
結石を砕くESWL(体外衝撃波砕石術)は体への侵襲が比較的小さいとされますが、腎周囲の出血や一過性の血尿が起こる可能性があります。
内視鏡下砕石術では、処置中に尿管や膀胱などの粘膜を傷つけたり、術後に感染や出血を起こしたりするリスクがあります。
砕石治療に伴う主なリスク
| 治療法 | 主なリスク | 発生した場合の対処 |
|---|---|---|
| ESWL | 血尿、一過性の腎周囲出血、痛み | 水分補給、鎮痛薬投与、経過観察が中心 |
| 内視鏡下砕石術 | 粘膜損傷、感染、術後出血 | 抗生物質投与、場合によって追加処置 |
外科的手術や尿路ステント留置のデメリット
前立腺手術(経尿道的前立腺切除術など)や腫瘍切除などの外科治療は、一定の入院期間や術後管理が必要です。
手術では出血や感染だけでなく、排尿機能や性機能に影響を及ぼす可能性があり、尿管ステント留置では、異物を体内に置くために感染やステント閉塞が起こるリスクがあり、定期的な交換がいります。
手術やステント留置時に留意したいポイント
- 手術部位の合併症(出血や感染)に注意
- 入院や安静が必要になるため、生活・仕事への影響がある
- ステント留置時には、違和感や頻尿が続くことがある
- 一定期間ごとにステントを交換しなければ閉塞や感染につながる
薬物相互作用や全身状態への影響
閉塞性腎症の患者の中には、高血圧や糖尿病、心疾患などの基礎疾患を抱えて複数の薬を服用している人が多く、薬同士の相互作用や副作用の増幅に注意が必要です。
腎機能が低下すると薬物の代謝や排泄が遅れ、副作用が出やすくなる場合もあります。
閉塞性腎症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
画像検査や内視鏡検査の費用目安
CTやMRIなどの画像検査は1回数千円~1万円程度の自己負担が目安となるケースが多く、造影剤を使う場合はさらに費用が上乗せされます。
内視鏡検査についても、使用する機材や施行時間、合併症対策などによって金額に幅がありますが、数千円~1万円程度の自己負担になる場合が多いです。
複数の検査を組み合わせると合計費用が増加しますが、精密診断には欠かせない手段として位置づけられます。
結石除去や前立腺手術などの処置費用
体外衝撃波砕石術(ESWL)は、1回あたり数万円程度の費用が全額だと見込まれますが、保険適用で3割負担の場合は1万円前後の支払いとなることが多いです。
内視鏡下砕石術や腫瘍切除、前立腺手術などは入院を伴うケースもあり、入院期間や術式によって数万円~十数万円程度の自己負担が発生する例があります。
| 処置 | 全体の費用目安 | 自己負担(3割負担の場合) |
|---|---|---|
| 体外衝撃波砕石術(ESWL) | 数万円~10万円程度 | 1万円~3万円程度 |
| 経尿道的前立腺切除術(TURP) | 10万円~20万円程度 | 3万円~6万円程度 |
| 内視鏡下腫瘍切除 | 処置時間や範囲で変動大 | 数万円~十数万円程度 |
薬剤費や通院費
前立腺肥大症の薬剤は毎月の処方で数千円前後の自己負担が発生することが多く、長期的な服用が続く場合は累計金額が増えます。
抗菌薬や降圧薬などを併用するとさらに費用がかかり、定期的な通院時には血液検査や尿検査の費用も上乗せされます。
ステント留置や腎瘻などの対症療法
尿管ステントや腎瘻造設術を行う場合は、手技料や材料費が保険適用となるため3割負担で受けられるケースがほとんどです。ステントの交換が必要となると、年に数回の処置が加わり、そのたびに数千円~1万円前後の自己負担が発生します。
以上
参考文献
Ohashi R, Shimizu A, Masuda Y, Kitamura H, Ishizaki M, Sugisaki Y, Yamanaka N. Peritubular capillary regression during the progression of experimental obstructive nephropathy. Journal of the American Society of Nephrology. 2002 Jul 1;13(7):1795-805.
Klahr S. Obstructive nephropathy. Internal medicine. 2000;39(5):355-61.
Inoue T, Okada H, Takenaka T, Watanabe Y, Suzuki H. A case report suggesting the occurrence of epithelial–mesenchymal transition in obstructive nephropathy. Clinical and experimental nephrology. 2009 Aug;13:385-8.
Gao X, Mae H, Ayabe N, Takai T, Oshima K, Hattori M, Ueki T, Fujimoto J, Tanizawa T. Hepatocyte growth factor gene therapy retards the progression of chronic obstructive nephropathy. Kidney international. 2002 Oct 1;62(4):1238-48.
Washino S, Hosohata K, Oshima M, Okochi T, Konishi T, Nakamura Y, Saito K, Miyagawa T. A novel biomarker for acute kidney injury, Vanin-1, for obstructive nephropathy: a prospective cohort pilot study. International journal of molecular sciences. 2019 Feb 19;20(4):899.
Kaneto H, Ohtani H, Fukuzaki A, Ishidoya S, Takeda A, Ogata Y, Nagura H, Orikasa S. Increased expression of TGF-β1 but not of its receptors contributes to human obstructive nephropathy. Kidney international. 1999 Dec 1;56(6):2137-46.
Fukuda K, Yoshitomi K, Yanagida T, Tokumoto M, Hirakata H. Quantification of TGF-β1 mRNA along rat nephron in obstructive nephropathy. American Journal of Physiology-Renal Physiology. 2001 Sep 1;281(3):F513-21.
Kitamoto K, Machida Y, Uchida J, Izumi Y, Shiota M, Nakao T, Iwao H, Yukimura T, Nakatani T, Miura K. Effects of liposome clodronate on renal leukocyte populations and renal fibrosis in murine obstructive nephropathy. Journal of pharmacological sciences. 2009;111(3):285-92.
Omori H, Kawada N, Inoue K, Ueda Y, Yamamoto R, Matsui I, Kaimori J, Takabatake Y, Moriyama T, Isaka Y, Rakugi H. Use of xanthine oxidase inhibitor febuxostat inhibits renal interstitial inflammation and fibrosis in unilateral ureteral obstructive nephropathy. Clinical and experimental nephrology. 2012 Aug;16:549-56.
Fukasawa H, Yamamoto T, Togawa A, Ohashi N, Fujigaki Y, Oda T, Uchida C, Kitagawa K, Hattori T, Suzuki S, Kitagawa M. Down-regulation of Smad7 expression by ubiquitin-dependent degradation contributes to renal fibrosis in obstructive nephropathy in mice. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2004 Jun 8;101(23):8687-92.