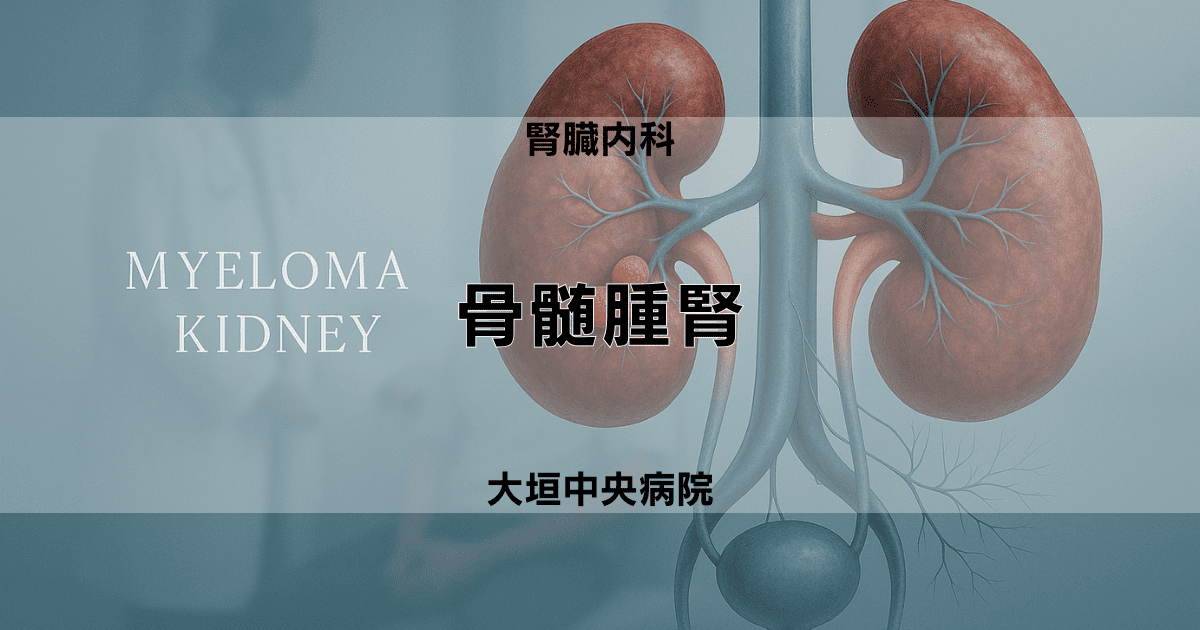骨髄腫腎とは、多発性骨髄腫が原因で腎臓にさまざまな障害が生じる病態の総称であり、血液中に増加した異常なタンパク質が腎機能を損ねることによって、体内の老廃物や水分の排出バランスが乱れる点が大きな特徴です。
多発性骨髄腫自体は骨髄を主な病変部位とする腫瘍性疾患ですが、その合併症として生じる腎障害が重症化すると、慢性的に透析が必要になる可能性もあり、生活の質に大きく影響を与えます。
この病気は珍しい印象を持たれがちですが、実際には発症する患者さんが少なくなく、早期発見と適切な治療を受けることが大切です。
骨髄腫腎の病型
骨髄腎腫の病型は多発性骨髄腫の性質や、腎臓のどの部分がどのように障害を受けるかによってさまざまに分類されます。
多発性骨髄腫では、免疫グロブリンと呼ばれるタンパク質の一種が異常に増殖し、そのうちの一部が尿や血液の流れに乗って腎臓に負荷をかけるため、特有の腎障害が生じます。
多発性骨髄腫の概要と腎障害との関連
多発性骨髄腫は、形質細胞ががん化して起こる血液腫瘍の一種で、骨髄内で増殖した異常細胞が産生する免疫グロブリン(M蛋白とも呼ばれます)が、腎臓の機能を妨げることが特徴的です。
異常に増加したタンパク質は腎尿細管や糸球体に負担をかけ、腎機能の低下につながります。
代表的な病型の例
骨髄腫腎には、複数の病型が存在しますが、代表的なものとして以下のようなタイプが挙げられ、特定の病型に該当するかどうかによって、治療の優先度や腎臓への影響度合いが異なります。
代表的な骨髄腫腎の病型と特徴
| 病型名 | 特徴 |
|---|---|
| 直接毒性型 | 腎臓内で免疫グロブリンが沈着し、尿細管に障害を及ぼす場合が多い。 |
| 間接障害型 | 免疫グロブリン以外の要因(尿酸やカルシウム上昇)による障害が中心。 |
| 連鎖的合併症型 | 腎障害に加え、骨病変や貧血など他の症状が同時に進行しやすい。 |
| 進行性腎不全型 | 腎機能が急速に悪化し、人工透析が必要になるリスクが高い。 |
病型による予後の違い
直接毒性型は、免疫グロブリンが腎臓に直接悪影響を及ぼすことで急速に腎機能が低下するケースが比較的多く、早い段階から積極的な薬物療法が必要になります。
間接障害型は、タンパク質以外に血中に蓄積したカルシウムや尿酸が原因になりやすいですが、根本となる骨髄腫のコントロールが進むと腎機能も改善する場合があります。
いずれの場合も発見の遅れや治療の遅れは症状を悪化させる要因となるので、自覚症状がない段階でも定期的な検査を受けることが重要です。
骨髄腫腎の理解と他疾患との区別
腎疾患には、糖尿病性腎症や高血圧性腎障害などさまざまな種類があるため、骨髄腫腎が原因となっている場合でも、他の腎症との鑑別が必要です。
とくに血液検査でM蛋白の上昇が認められたり、尿検査でBence Jones蛋白(軽鎖タンパク)が検出された場合は、骨髄腫腎を強く疑います。
血中クレアチニンの上昇や腎臓の画像診断で形態的な変化が認められるケースも少なくありませんが、最終的には骨髄生検などで多発性骨髄腫の確定診断を行ってから治療方針を決める流れになります。
骨髄腫腎の病型を把握するときに意識したいポイント
- 多発性骨髄腫の型(IgG型、IgA型、軽鎖型など)によって合併症が異なる。
- 骨髄腫腎の進行速度は個人差が大きく、同じ病型でも症状に幅がある。
- 腎機能低下を放置すると全身状態が悪化しやすいため、早期発見と治療がカギとなる。
骨髄腫腎の症状
骨髄腫腎の症状は、多発性骨髄腫の進行具合や免疫グロブリンの影響度合いにより多岐にわたりますが、腎機能が低下することで体に余分な水分や老廃物が蓄積し、全身の不調を招くことが大きな特徴です。
腎障害が進行すると、疲労感が抜けなかったり、むくみが強くなったりするため、仕事や日常生活に支障をきたすケースがみられます。
腎機能低下による代表的な症状
腎機能が低下すると、尿量の変化や血液検査の数値変化だけでなく、体調の変化が顕著に現れ、特に注意して観察したい症状としては、血圧の上昇、足や顔のむくみ、倦怠感、吐き気、食欲不振などが挙げられます。
骨髄腫腎の進行具合によっては、こういった症状が徐々に強くなり、生活の質が低下しやすいです。
骨髄腫腎による主な自覚症状と背景要因
| 自覚症状 | 背景要因 |
|---|---|
| 倦怠感 | 老廃物が体内に蓄積し、エネルギー代謝が低下する |
| むくみ | 腎機能低下でナトリウムと水分を排出しにくくなる |
| 吐き気・食欲不振 | 体内の有害物質増加や血液の酸性化などが関与する |
| 集中力の低下 | 体調不良による睡眠障害や日中の疲れが影響する |
これらの症状は、他の慢性腎臓病にも共通してみられます。骨髄腫腎が疑われる場合は、同時に多発性骨髄腫に特有の症状である骨痛や貧血の有無なども注意深く観察することが大切です。
骨の痛みや骨折リスクとの関連
多発性骨髄腫では、骨の変質や骨量の減少が生じやすく、骨髄腫腎と同時に骨折リスクが高まるケースがあります。とくに背骨(脊椎)や肋骨、大腿骨などに痛みが生じると、日常生活に大きな支障をきたす可能性が高くなります。
骨に関するトラブルが腎機能低下と重なると、体力が落ちやすく、感染症にもかかりやすくなる点に注意が必要です。
血液異常や貧血の影響
骨髄腫腎を伴う多発性骨髄腫では、血液の赤血球や血小板が減少する影響で貧血や出血傾向を起こしやすくなり、さらに、異常な免疫グロブリンが増加すると、白血球の働きも乱れやすく、感染症にかかりやすくなる面があります。
腎機能障害と組み合わさると体内のバランスが崩れ、肺炎や尿路感染症などが長引くケースがみられるので、日々の体調管理とこまめな受診が重要です。
日常生活での支障と注意点
骨髄腫腎による腎機能低下が進むと、体の疲れが取れにくくなったり、吐き気や食欲不振から栄養不足に陥りやすくなります。
仕事を続けるうえで、通勤や長時間の業務が負担になり、睡眠障害が起こることもあるため、日常生活全般にわたってケアが必要です。
また、こまめな水分補給は大切ですが、腎機能が著しく低下している場合は水分や塩分の摂取量を医師と相談しながら調整しましょう。
骨髄腫腎の症状を把握するときに意識したい点
- 倦怠感やむくみなど、腎不全の典型的な症状が徐々に出現する。
- 骨の痛みや骨折リスクが高まることがある。
- 感染症への抵抗力が低下し、風邪や肺炎などが重症化しやすい。
- 吐き気や食欲不振が続く場合は、栄養バランスが崩れないように工夫する必要がある。
上記のような症状が思い当たる場合や、慢性的な体調不良が続く場合は、早めに受診して検査を受けることをおすすめします。
骨髄腫腎を疑う目安と早期受診が重要な理由
| 疑う目安 | 早期受診が重要な理由 |
|---|---|
| 長引く倦怠感やむくみ | 腎機能低下は放置すると急速に悪化する可能性がある |
| 不明な骨痛や体の痛み | 骨折や骨変形につながるリスクが高い |
| 血液検査で免疫グロブリン異常 | 免疫機能の乱れや感染リスクの上昇が懸念される |
骨髄腫腎の原因
骨髄腫腎の主な原因は、多発性骨髄腫における異常免疫グロブリン(とくに軽鎖)の産生過剰です。
通常、体内の免疫グロブリンは病原体などを排除するために必要ですが、骨髄腫では異常な形質細胞が増殖し、正常な免疫機能とは異なるM蛋白を大量に産生し、M蛋白が腎臓に負荷をかけることで、骨髄腫腎の発症リスクが高まります。
異常免疫グロブリンの蓄積
多発性骨髄腫で増加する免疫グロブリンのうち、軽鎖と呼ばれる部分は小さな分子量で腎臓のろ過装置を通りやすい特徴がありますが、大量に存在すると尿細管上皮に沈着して障害を起こしやすくなります。
尿に排出されるタンパク質量が増えることで尿蛋白が検出されるだけでなく、尿細管そのものがダメージを受けて腎不全へと進行するリスクが高まります。
異常免疫グロブリンの増加においてよく知られている例を挙げます。
- IgG型やIgA型などの重鎖が増えるタイプ
- 軽鎖のみが増えるライトチェーン型(Bence Jones蛋白が増加)
ライトチェーン型は、腎臓への直接的な負荷が大きいと考えられており、早期から腎機能障害を起こすパターンが報告されています。
高カルシウム血症との関連
多発性骨髄腫では、骨の破壊により血中カルシウム濃度が上昇しやすく、高カルシウム血症を伴うケースがあり、カルシウムが高い状態になると、腎臓は水分の再吸収を調整しづらくなり、腎機能を悪化させる原因の1つになります。
骨髄腫腎に限らず、高カルシウム血症はさまざまな臓器機能に影響を及ぼすため、重症化しないよう適切な治療でコントロールすることが重要です。
脱水や感染症の影響
骨髄腫腎の原因の1つとして、脱水や感染症が引き金となり腎機能を低下させるケースもあります。
発熱などにより水分摂取量が減る状態や、嘔吐・下痢などで脱水が進む状態が続くと、腎臓への血流量が減少し、もともと弱っている腎機能がさらに悪化しやすくなります。
また、骨髄腫による免疫力低下で重症化しやすい感染症(肺炎など)を併発すると、体力が奪われて腎臓に負担をかけるため、慎重な管理が必要です。
遺伝要因や生活習慣
多発性骨髄腫自体の原因はまだ完全に解明されていませんが、遺伝的要因や生活習慣、環境要因の複合的な影響が指摘されています。
特定の遺伝子変異が存在する家族歴がある場合や、長期にわたる喫煙、肥満などはリスクを高める一因です。
ただし、これらのリスク要因があったとしても必ずしも骨髄腫腎になるわけではないので、定期的な健康診断や早めの受診が早期発見に繋がります。
骨髄腫腎の原因として考慮すべきポイント
- M蛋白のうち、軽鎖が腎障害を引き起こしやすい。
- 高カルシウム血症や感染症、脱水で症状が急激に進むことがある。
- 遺伝要因や環境要因、生活習慣が複合的に影響する。
原因を正しく理解しておくと、治療に取り組む際の予防策や再発の防止策を考えるうえで役立ちます。
骨髄腫腎を進行させる主なリスク要因
| リスク要因 | 骨髄腫腎への影響 |
|---|---|
| 異常免疫グロブリン増加 | 腎尿細管への沈着やフィルター機能の破綻 |
| 高カルシウム血症 | 腎臓の濾過能力を低下させて症状を悪化させる |
| 脱水状態 | 血流減少により腎障害が加速しやすくなる |
| 感染症 | 体力低下や免疫力低下により腎不全リスクが増す |
検査・チェック方法
骨髄腫腎を疑う場合、腎機能の状態や多発性骨髄腫の有無を確認するために、血液検査や尿検査、画像検査などを行い、これらの検査結果を総合的に見ながら、骨髄検査で多発性骨髄腫の診断を確定し、病状を把握します。
検査の組み合わせによって腎障害の程度や合併症の有無を見極めることが大切です。
血液検査と尿検査のポイント
血液検査では、腎機能を示すクレアチニンや尿素窒素(BUN)、電解質バランスを確認し、さらに、M蛋白や免疫グロブリンの濃度を調べるために総蛋白やアルブミン、免疫固定法などの検査を行うことが一般的です。
尿検査では、Bence Jones蛋白の有無や蛋白尿の量、尿沈渣の確認も重要な指標となります。
血液検査や尿検査で確認する主な項目
- 血清クレアチニンと推算GFR(eGFR)
- 血中免疫グロブリン濃度(IgG、IgA、IgM、軽鎖など)
- 尿蛋白やBence Jones蛋白の有無
- 血清カルシウム、尿酸、LDHなどの付随検査
画像診断と腎臓の状態評価
腎臓に異常が疑われる場合は、エコー(超音波)検査やCT、MRIなどで腎臓の大きさや形態を確認し、多発性骨髄腫では骨の病変も併発するため、骨病変の評価を目的にX線やMRIを活用するケースが多いです。
骨髄腫腎が原因で腎臓が萎縮していたり、結石や嚢胞が見つかる場合もあるので、画像検査で腎臓周辺のトラブルを含めて総合的に判断します。
主な画像検査
| 画像検査 | 判明しやすい所見 |
|---|---|
| 腎エコー | 腎臓の大きさ、腎結石の有無、腎血流の評価など |
| CTスキャン | 腎臓の形態異常、腫瘤の確認、リンパ節の腫大など |
| MRI | 骨病変の有無、軟部組織への浸潤状況、骨折リスクなど |
骨髄検査の重要性
骨髄腫腎を診断するうえで不可欠なのが骨髄検査(骨髄穿刺や骨髄生検)で、骨髄液を採取して形質細胞が増えているかどうか、どの程度の割合で異常細胞が存在するかを直接確認します。
骨髄検査の結果は多発性骨髄腫の確定診断に役立ち、同時に染色体異常や遺伝子解析を行うことで予後や治療選択の参考になる場合があります。
定期的な検査とモニタリング
骨髄腫腎は症状が進みやすく、腎機能が急速に低下することがあるため、診断後は定期的に血液検査や尿検査を行い、治療効果や腎機能の推移をモニタリングします。治療薬の副作用を早期に発見する目的でも、定期的な検査は大切になります。
治療中に何らかの異変(倦怠感の増強や血中クレアチニンの急上昇など)があれば、早めに担当医へ相談し、検査スケジュールを早めるなどの対応が望ましいです。
骨髄腫腎のチェックで定期的に確認すべき項目
| チェック項目 | 意義 |
|---|---|
| 血清クレアチニン | 腎機能の基本的な指標 |
| eGFR | 腎臓のろ過機能を推定し、経時的変化を把握 |
| 血清カルシウム | 骨破壊や高カルシウム血症の管理に重要 |
| 免疫グロブリン濃度 | M蛋白の動向把握や治療効果の評価 |
| Bence Jones蛋白の有無 | 骨髄腫腎の再発や進行度合いを推測しやすい |
原因確定のためには血液検査や尿検査だけでなく、骨髄検査を組み合わせた総合的なアプローチが欠かせません。定期的な検査で腎機能や病状の推移を把握し、適切なタイミングで治療の見直しを行うことが大切です。
検査やチェック方法において注意したい点
- 血液検査では腎機能マーカーだけでなく、免疫グロブリンやカルシウム値なども総合的に評価する。
- 尿検査でBence Jones蛋白が検出された場合、骨髄腫腎の疑いが強い。
- 画像検査では腎臓と骨の状態を同時に確認する。
- 骨髄検査は多発性骨髄腫の確定診断に直結する重要な検査である。
骨髄腫腎の治療方法と治療薬について
骨髄腫腎の治療は、多発性骨髄腫の進行を抑えつつ、腎機能を保護することを目標に行われます。
治療法には、化学療法や分子標的薬などの薬物療法に加え、腎機能に配慮した血液浄化療法などを組み合わせるケースがあり、骨髄腫自体の活動性を抑制することで、腎障害の悪化を防ぎ、症状の改善を目指します。
化学療法(抗がん剤)の活用
多発性骨髄腫の治療では、メルファランやシクロホスファミドなどのアルキル化剤、ステロイド薬(デキサメタゾンなど)、プロテアソーム阻害薬(ボルテゾミブなど)が主に使用されることが多いです。
これらを組み合わせることで腫瘍細胞の増殖を抑え、免疫グロブリンの産生を減少させる効果が期待できます。
治療レジメンの組み合わせ
- メルファラン+ステロイド
- シクロホスファミド+ボルテゾミブ+ステロイド
- レナリドミド+ステロイド
使用する抗がん剤の種類や量は、患者さんの年齢や腎機能、合併症の有無などに応じて検討します。
代表的な抗がん剤
| 抗がん剤名 | 主な特徴 |
|---|---|
| メルファラン | アルキル化剤の一種、経口投与や点滴で使用される |
| シクロホスファミド | 細胞増殖を抑制、白血球減少などの副作用に注意 |
| ボルテゾミブ | プロテアソーム阻害薬で腫瘍細胞のタンパク分解を阻害 |
| レナリドミド | 免疫調整薬で腫瘍細胞の増殖を抑える |
分子標的薬や免疫療法の選択肢
化学療法に加えて、分子標的薬(カルフィルゾミブなど)や免疫チェックポイント阻害薬、抗CD38抗体などの治療薬も開発が進み、骨髄腫に効果的と報告されているものがあります。
これらの薬は、腫瘍細胞が増殖するための特定の経路や分子を標的にして攻撃するため、従来の化学療法と比較して異なる副作用プロファイルを持つことが特徴です。
腎機能が低下している患者さんでも投与量を調整したり、モニタリングを行いながら治療するケースが増えています。
腎機能を保護するための支持療法
骨髄腫腎は腎機能低下が著しい場合、透析療法や血液濾過などの血液浄化療法を併用して、体内の老廃物や異常タンパク質を除去する方法をとることがあります。
また、高カルシウム血症を抑制するために、ビスホスホネート系薬剤(ゾレドロン酸など)を使用することもあり、ビスホスホネートは骨の破壊を抑え、カルシウムの流出を抑制しながら、骨関連症状の発生を減らす役割があります。
ただし、腎機能が低い方に投与するときは注意が必要です。
骨髄腫腎で行うサポーティブケア
| サポーティブケア | 目的 |
|---|---|
| 血液浄化療法(透析・濾過など) | 老廃物や異常タンパクを排出して腎負担を軽減する |
| ビスホスホネート使用 | 骨吸収を抑えて高カルシウム血症を予防する |
| 体液・電解質バランスの管理 | 脱水や電解質異常を防いで全身状態を安定させる |
| 感染症対策 | 免疫力低下に備え、肺炎や尿路感染症を防ぎやすくする |
個別化された治療計画
骨髄腫腎の治療は、一律に同じ方法を行うわけではなく、患者さん個人の病状や腎機能のレベル、年齢、合併症などを考慮しながら計画を立てます。
たとえば、高齢の方や腎機能が著しく低下している方には、化学療法の強度を落として投与間隔を調整する場合もあります。
最近は、複数の治療薬を組み合わせた包括的な治療計画で、骨髄腫腎の進行を抑えられる可能性が高まっているため、主治医と相談しながら自分に合った治療を進めることが重要です。
骨髄腫腎の治療で意識したい点
- 骨髄腫自体の活動を抑えることで腎機能のさらなる悪化を防ぐ。
- 分子標的薬や免疫療法を含む治療薬を組み合わせることで効果を高める。
- 腎機能を保護するためのサポーティブケアや透析も適宜検討する。
- 患者個人の状態に応じて治療強度や投薬量を調整する。
骨髄腫腎の治療期間
骨髄腫腎の治療期間は、多発性骨髄腫のステージや合併症の程度、治療方法などによって大きく異なります。
多発性骨髄腫の治療は長期にわたることが一般的であり、寛解を得た後も再発の可能性を考慮して経過観察を続ける必要があるため、患者さんの体調や社会生活と両立させる配慮が欠かせません。
初期治療から寛解導入まで
多発性骨髄腫と診断された時点で、骨髄腫腎の症状が認められる場合には、早期に化学療法や分子標的薬による治療を開始し、腎機能の回復を目指します。
初期治療は数か月から半年程度にわたり行うケースが多く、治療効果が得られた場合は腎機能がある程度改善することも期待でき、寛解導入とは、血中のM蛋白レベルや症状が大きく改善し、病勢が落ち着いた状態です。
初期治療の一般的な期間と目標
| 治療ステージ | 期間の目安 | 目標 |
|---|---|---|
| 初期治療 | 数か月〜半年程度 | 骨髄腫の勢いを抑えて腎機能の悪化を最小限に抑える |
| 寛解導入 | 個人差大 | 血中M蛋白や症状を大幅に減少させ、生活の質を向上する |
維持療法や再発防止の観点
寛解導入後は、再発防止のために維持療法を行い、レナリドミドなどの薬剤を低用量で継続投与することで、腫瘍細胞の増殖を抑え、腎機能の安定化を図る方針です。
維持療法の期間は数か月から数年単位で続くこともあり、治療中は定期的に腎機能や血液検査を行いながら、副作用の有無や再発の兆候をチェックします。
治療期間と生活の調整
骨髄腫腎の治療は長期化しやすいため、患者さん自身や家族の負担も大きくなりがちです。通院や投薬スケジュールを組む際には、仕事や家事、介護などとの両立を考慮しながら医師や医療スタッフと相談しましょう。
治療期間を考えるうえで押さえておきたいリスト
- 初期治療で腫瘍細胞をしっかりと抑え、腎機能回復を促す。
- 寛解導入後は維持療法を続けながら再発リスクを下げる。
- 定期的に検査を受け、薬の効果や副作用を確認する。
- 家族や職場との調整をしつつ、治療を長期的に継続できる環境を整える。
骨髄腫腎の治療は、単純に「何か月で完治」というものではなく、寛解と再発を繰り返すことも多い疾患なので、長期的な視点で取り組む心構えが望まれます。
副作用や治療のデメリットについて
骨髄腫腎の治療に用いられる薬剤には、化学療法薬や分子標的薬、ステロイドなど多岐にわたり、いずれの薬剤にも副作用があるため、治療効果と副作用リスクを天秤にかけながら、投与量や治療期間を調整する必要があります。
抗がん剤・分子標的薬の主な副作用
抗がん剤(メルファランやシクロホスファミドなど)は、腫瘍細胞だけでなく正常な細胞にも影響を及ぼす可能性があるため、骨髄抑制や脱毛、吐き気、倦怠感などがみられやすいです。
プロテアソーム阻害薬(ボルテゾミブなど)では、末梢神経障害が起こるリスクがあり、手足のしびれや痛みなどを訴える患者さんがいて、分子標的薬でも免疫力の低下や感染症リスクの増加などが生じるケースがあります。
主な骨髄腫治療薬とよくみられる副作用
| 治療薬 | 代表的な副作用 |
|---|---|
| メルファラン | 骨髄抑制、脱毛、消化器症状 |
| シクロホスファミド | 骨髄抑制、嘔気・嘔吐、脱毛 |
| ボルテゾミブ | 末梢神経障害(手足のしびれ等)、血小板減少 |
| レナリドミド | 血栓症リスク上昇、骨髄抑制、発疹など |
ステロイド薬による副作用
ステロイド(デキサメタゾンなど)は腫瘍細胞を抑制し、炎症をコントロールする一方で、高血糖や骨粗鬆症、精神症状(不眠や気分変動)などがリスクです。
長期使用の場合は、感染症への抵抗力が低下する点や糖尿病の悪化など、内分泌系のトラブルに注意が必要で、特に骨髄腫腎を持つ方は、腎機能への負荷や電解質バランスの乱れにも気を配りながら投与量を調整します。
治療のデメリットと注意点
治療そのものが長期化するうえ、入院や頻回の通院が必要になる場合が多いため、患者さんや家族の経済的・身体的・精神的負担が大きくなることがデメリットの1つです。
体調が安定しない時期が続いたり、副作用で思うように日常生活を送れなくなったりすると、仕事や家庭の予定を調整する必要が生じます。
さらに、治療薬が奏功しない場合や副作用が強い場合は、ほかの治療レジメンに切り替える必要があり、その過程でも体調の変化や費用面での負担が増える可能性があります。
副作用やデメリットに関する留意点
- 抗がん剤や分子標的薬は骨髄抑制や末梢神経障害などが代表的な副作用。
- ステロイド薬は高血糖や骨粗鬆症、精神症状のリスクがある。
- 治療期間が長くなりやすく、通院や経済的な負担が増える。
- 副作用のために治療を中断する場合は、腎機能悪化や再発リスクを考慮しながら次の手段を選ぶ必要がある。
骨髄腫腎の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
治療薬の保険適用と費用
多くの抗がん剤や分子標的薬、ステロイド薬は保険適用となっており、一般的には3割負担または1割負担などの自己負担割合で受けられます。
| 治療薬・治療法 | 月あたりの自己負担目安(円) |
|---|---|
| 抗がん剤(メルファラン等) | 10,000〜20,000 |
| ボルテゾミブなどの注射製剤 | 20,000〜40,000 |
| レナリドミドなどの内服薬 | 30,000〜70,000 |
| ビスホスホネート薬(月1回程度) | 5,000〜10,000 |
検査費用
骨髄腫腎の診断や経過観察には、血液検査や尿検査、画像検査などを頻繁に行う場合があり、保険適用であっても以下の検査費用が月々数千円〜1万円程度かかる可能性があります。
骨髄穿刺や生検などの検査も1回数千円〜数万円程度の負担になることがあり、実施頻度と併せて検討しましょう。
透析や血液浄化療法の費用
骨髄腫腎が進行して透析や血液濾過が必要になる場合は、週に数回の通院を継続し、血液浄化治療を行います。
| 治療・検査内容 | 保険適用後の自己負担目安(円) | 頻度・備考 |
|---|---|---|
| 化学療法 | 10,000〜70,000/月 | 薬剤の種類・組合せで変動 |
| 分子標的薬 | 20,000〜80,000/月 | 注射製剤は高額な傾向 |
| 血液検査・尿検査 | 1,000〜10,000/回 | 頻度が高いほど増額 |
| 画像検査(CT・MRI等) | 3,000〜10,000/回 | 検査機関による差あり |
| 骨髄穿刺・生検 | 数千円〜数万円/回 | 麻酔や実施方法で変動 |
| 透析・血液濾過 | 数千円〜数万円/月 | 週数回の通院が必要 |
以上
参考文献
Katagiri D, Noiri E, Hinoshita F. Multiple myeloma and kidney disease. The Scientific World Journal. 2013;2013(1):487285.
UCHIDA M, KAMATA K, OKUBO M. Renal dysfunction in multiple myeloma. Internal medicine. 1995;34(5):364-70.
Yamabe K, Inoue S, Hiroshima C. Epidemiology and burden of multiple myeloma in Japan: a systematic review. Value in Health. 2015 Nov 1;18(7):A449.
Shimazu Y, Kanda J, Takakuwa T, Onda Y, Fukushima K, Hotta M, Fuchida SI, Uoshima N, Shimura Y, Tanaka H, Ohta K. The impact of renal function on initial therapy in transplant-ineligible multiple myeloma patients. Annals of Hematology. 2024 Aug 21:1-1.
Kuzume A, Tabata R, Terao T, Tsushima T, Miura D, Narita K, Takeuchi M, Matsue K. Safety and efficacy of daratumumab in patients with multiple myeloma and severe renal failure. British journal of haematology. 2021 May 15;193(4).
Dias NE. Acute myeloma kidney. Kidney international. 1995;48:1347-61.
Heher EC, Rennke HG, Laubach JP, Richardson PG. Kidney disease and multiple myeloma. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2013 Nov 1;8(11):2007-17.
Sanders PW. Pathogenesis and treatment of myeloma kidney. The Journal of laboratory and clinical medicine. 1994 Oct 1;124(4):484-8.
Leung N, Nasr SH. Myeloma-related kidney disease. Advances in chronic kidney disease. 2014 Jan 1;21(1):36-47.
Hutchison CA, Batuman V, Behrens J, Bridoux F, Sirac C, Dispenzieri A, Herrera GA, Lachmann H, Sanders PW, International Kidney and Monoclonal Gammopathy Research Group. The pathogenesis and diagnosis of acute kidney injury in multiple myeloma. Nature Reviews Nephrology. 2012 Jan;8(1):43-51.