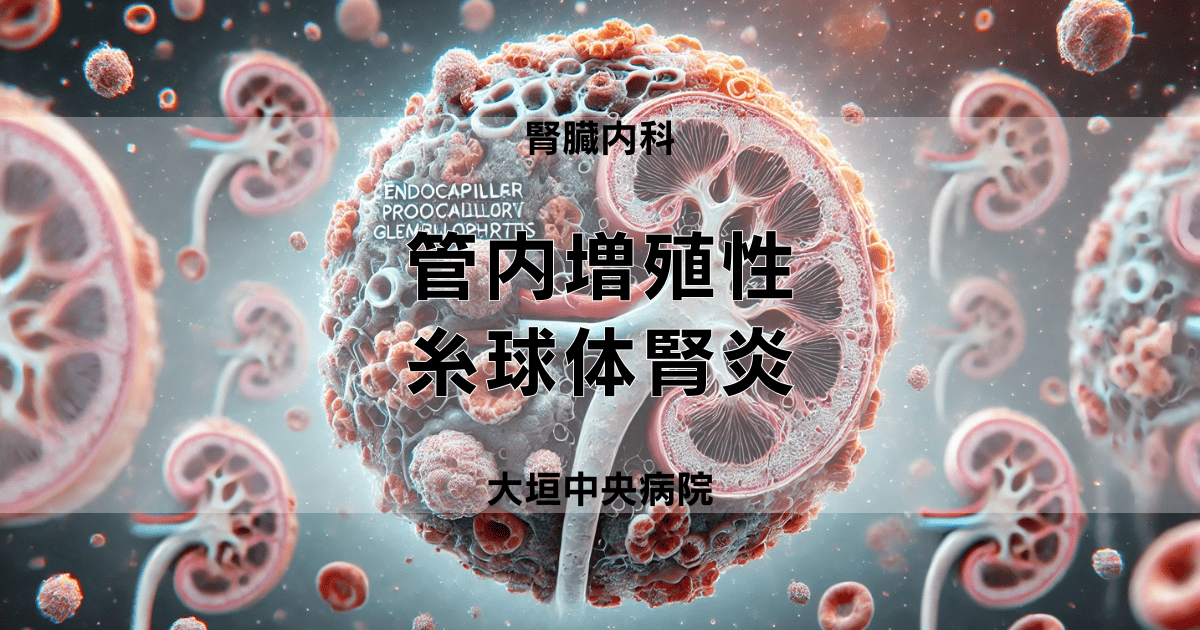管内増殖性糸球体腎炎とは、糸球体の中に存在する細い血管の内側(管内)で炎症が生じ、細胞が増殖してしまうことで腎機能に影響を及ぼす病態の総称であり、急性腎炎症候群の一つとして扱われることも多い疾患です。
急性発症のケースが多く、感染症や免疫反応の影響で腎臓の糸球体に炎症が起こり、血尿やタンパク尿などが出現しやすくなるという特徴があります。
この病気は早期に正確な診断を受けて適切な治療を開始することが大切で、状態によってはステロイド薬や免疫抑制剤などの強力な薬を使います。
管内増殖性糸球体腎炎の病型
管内増殖性糸球体腎炎は、急性腎炎症候群や慢性腎炎症候群として臨床上捉えられることもあり、糸球体の病理像によっていくつかの病型に区分されます。
急性糸球体腎炎型
管内増殖性糸球体腎炎のなかでも、最も典型的に見られる病型の一つが急性糸球体腎炎型です。
主に溶連菌感染などののどの感染症後に起こる急性糸球体腎炎が代表例とされ、感染後1~3週間程度で、血尿やタンパク尿、高血圧や浮腫などが同時に現れます。
急性糸球体腎炎型では、免疫複合体の沈着が糸球体の毛細血管内皮やメサンギウム領域に強く認められ、内皮細胞が増殖して管腔が狭くなります。
感染関連糸球体腎炎型
この病型は、溶連菌以外の微生物感染やウイルス感染など広範な感染症に伴って発症する場合があり、特に高齢者や慢性疾患を抱える方に多いです。
慢性の皮膚感染症や、感染性心内膜炎、B型肝炎などが背景にあるときに管内増殖性の変化が糸球体に生じて、急性腎炎症候群または亜急性の経過を示す場合があります。
| 病型 | 代表的な原因・背景 | 特徴的な病理像 |
|---|---|---|
| 急性糸球体腎炎型 | 溶連菌感染後 | 毛細血管腔内の内皮細胞増殖が顕著で、補体価が低下することが多い |
| 感染関連糸球体腎炎型 | 感染性心内膜炎、B型肝炎など | 慢性・亜急性の経過をとり、糸球体内に免疫複合体が広範に沈着 |
| その他の免疫複合体型 | 特定の自己免疫疾患 | 全身性エリテマトーデスなどで糸球体内に免疫複合体が沈着 |
膜性増殖性糸球体腎炎(MPGN)との鑑別
管内増殖性糸球体腎炎と膜性増殖性糸球体腎炎は、共に糸球体の組織像として増殖性の変化が認められますが、MPGNでは基底膜の肥厚・二重化が見られる点が特徴的です。
一方、本疾患では主に糸球体の内側(内皮細胞やメサンギウム)での細胞増殖が主体となるため、病理検査で両者を見分けるられます。
免疫複合体の役割
多くの管内増殖性糸球体腎炎では、免疫グロブリンや補体成分が腎生検標本で染色され、免疫複合体の存在が示唆されます。
これらは感染症を含む外来抗原に対する免疫応答の結果生成されたものであり、糸球体の毛細血管内やメサンギウム領域に沈着して炎症を引き起こし、内皮細胞増殖や腎機能障害の原因です。
管内増殖性糸球体腎炎の症状
管内増殖性糸球体腎炎の特徴的な症状として、急性の腎炎症候群が挙げられ、特に血尿やタンパク尿が代表的で、高血圧や浮腫を伴う場合が多く、まれに急速進行性糸球体腎炎の様相を呈して腎機能が急速に悪化するケースも否めません。
急性腎炎症候群の発現
血尿やタンパク尿、高血圧、浮腫という4大症状を典型的に示すものが、急性腎炎症候群です。
管内増殖性糸球体腎炎の場合、感染後(溶連菌など)しばらくして急激にこれらの症状が出現することが多く、皮膚や咽頭の感染を起点とする溶連菌感染後急性糸球体腎炎などがよい例となります。
血尿
血尿は外来受診の際に最も頻度の高い発見症状となり得ます。肉眼的に赤くなる血尿は稀でも、顕微鏡レベルで潜血陽性となることがよくあり、糸球体由来の血尿は赤血球円柱などが確認されると診断の一助です。
無症状でも検尿で判明することがあり、学校や職場の健康診断で見つかるケースもあります。
| 症状 | 詳細 | 原因の関連性 |
|---|---|---|
| 血尿 | 尿の赤色変化、顕微鏡的潜血 | 毛細血管壁の炎症により血液成分が漏出 |
| タンパク尿 | 泡立ちが強い尿 | 糸球体のろ過機能障害による蛋白漏出 |
| 浮腫 | まぶたや下腿にむくみが生じる | 塩分・水分貯留、低アルブミン血症 |
| 高血圧 | 血圧上昇 | 腎血流量の低下やレニン系の活性化 |
腰痛や倦怠感
腎臓の炎症が強い場合、腰背部に鈍い痛みや張りを感じるケースがありますが、痛みに関しては個人差が大きく、中にはまったく感じない人もいるため、一概には言えません。
また、腎機能低下により老廃物の除去がうまく行えなくなると、倦怠感や疲れやすさを訴える方もいます。
全身症状
感染に伴う発熱や関節痛などの全身的な症状が併発することがあり、とくに体力が落ちている方や小児・高齢者は注意が必要で、腎炎の初期段階で微熱や倦怠感を示す場合は、感冒などの軽い感染症との区別が難しいこともあります。
全身症状が長引くときは腎機能の評価が必要です。
急速進行性腎炎(RPGN)との関連
まれに、管内増殖性糸球体腎炎が急速に腎機能低下を起こし、RPGN(急速進行性糸球体腎炎)のような経過を辿ることがあります。
1~2週間のうちにクレアチニン値やBUNなどの腎機能指標が著しく悪化し、透析が必要になるリスクもあるので、早急に専門的治療が重要です。
原因
管内増殖性糸球体腎炎の大部分は、感染後に形成された免疫複合体が腎糸球体内の細い血管に沈着することで引き起こされ、感染源としては、溶連菌が最も有名ですが、ブドウ球菌やウイルス、慢性炎症性病変が背景にある場合もあります。
溶連菌感染後
小児や若年者にみられる典型的な病態として、溶連菌感染後急性糸球体腎炎が挙げられ、咽頭炎や扁桃炎、膿皮症など溶連菌感染が起きた後、約1~3週間の潜伏期間を経て腎炎が急に発症します。
この場合、咽頭培養やASO(抗ストレプトリジンO)価の上昇などが確認されることが多く、補体価のC3低下がよく報告されます。
感染性心内膜炎
感染性心内膜炎は、心臓の内膜(特に弁)に細菌が付着して炎症を引き起こす疾患ですが、細菌やその産生毒素、あるいは免疫複合体が血流に乗って全身へ広がり、腎糸球体に損害を与えることがあります。
左房弁や左心室弁に病変がある場合、全身の循環を介して腎臓に達しやすいです。
| 原因・背景 | 具体的な微生物・病態 | 発症メカニズム |
|---|---|---|
| 溶連菌感染後 | 溶連菌(主にA群β溶血性レンサ球菌) | 免疫複合体が糸球体内に沈着し内皮細胞を増殖させる |
| 感染性心内膜炎 | ブドウ球菌、連鎖球菌など | 細菌エンドトキシンや免疫複合体が腎糸球体に沈着 |
| ウイルス性肝炎 | B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス | 慢性炎症と免疫反応を通じて糸球体にダメージが及ぶ |
| 自己免疫疾患 | SLE(全身性エリテマトーデス)など | 自己抗体や免疫複合体が糸球体内で炎症を引き起こす |
膠原病・自己免疫疾患
全身性エリテマトーデス(SLE)などの膠原病でも管内増殖性の腎炎所見が見られることがあります。
自己免疫反応で作られた免疫複合体が腎臓に沈着し、組織学的に管内増殖性の特徴を示すケースで、腎だけでなく全身に多彩な症状が現れることもあり、総合的に診断・治療を進めることが大切です。
その他の細菌・ウイルス感染
ブドウ球菌やクラミジア、マイコプラズマなど、さまざまな微生物が原因で管内増殖性糸球体腎炎を引き起こす可能性があるとも報告されています。
慢性的な感染病巣(例えば、長期にわたって続く皮膚病変や骨髄炎など)があると、そこから慢性的に免疫複合体が生成されて糸球体に障害が及ぶ場合もあります。
管内増殖性糸球体腎炎の検査・チェック方法
正確な診断には、尿検査・血液検査・腎生検など多角的なアプローチが欠かせません。腎臓病は自覚症状が乏しい場合が多く、検査結果の詳細が診断と治療方針決定に大きく影響を与えます。
尿検査
管内増殖性糸球体腎炎でまず行うのが一般的な尿検査です。
血尿やタンパク尿の程度を把握し、赤血球円柱の有無、尿中細胞成分の形態などを顕微鏡で確認し、とくに赤血球円柱は糸球体由来の血尿を示唆し、この病気の可能性を大きく高める所見になります。
血液検査
血清クレアチニンやBUNなど腎機能を示す値のほか、補体価(C3、C4)や免疫グロブリン、ASO価、抗DNase Bなどの感染マーカーを測定する場合があります。
管内増殖性糸球体腎炎ではC3などの補体成分が低下するケースが多く、原因となる感染病原体を推定する手がかりにもなり、また、炎症の度合いを把握するためにCRPなどもチェックすることが多いです。
| 検査項目 | 意味 | この病気との関連 |
|---|---|---|
| 尿蛋白 | 蛋白尿の有無と量 | 糸球体ろ過障害の指標 |
| 尿潜血・赤血球円柱 | 血尿の有無、赤血球形態、円柱の存在 | 糸球体由来血尿を疑う重要な手がかり |
| 血清クレアチニン | 腎機能の指標 | 腎機能低下が進行しているかを確認 |
| 補体価(C3、C4など) | 免疫複合体反応の程度や経過を示す | この病態ではC3が低下しやすい |
| ASO、抗DNase B | 溶連菌感染の指標 | 溶連菌後急性糸球体腎炎を疑う際に有用 |
画像検査
腎臓の形態や大きさを見るために、超音波(エコー)検査を行い、一般に、糸球体疾患では腎臓の大きさには大きな変化がない場合が多いですが、急性期には腫大がみられる可能性があります。
また、必要に応じてCTやMRIなどの検査を行い、腎臓以外の病変(感染巣など)を検索することも考慮されます。
腎生検
最終的に組織学的診断を確定するためには腎生検が大きな役割を果たし、腎生検の組織を光学顕微鏡や電子顕微鏡、免疫蛍光などで観察し、糸球体における内皮細胞増殖や免疫複合体の沈着を確認します。
管内増殖性糸球体腎炎という病理診断が確定できる一方、MPGNなど類似病態との鑑別や、進行度評価にも有用です。
- 腎生検には局所麻酔を行い、背中から細い針を用いて腎組織を採取する手技が一般的
- 合併症として出血のリスクがあるため、止血機能を確認したうえで実施する
- 病理検査の結果が出るまで1~2週間かかることが多い
病理診断のポイント
光学顕微鏡では、糸球体毛細血管腔が内皮細胞やメサンギウム細胞の増殖によって狭窄し、白血球浸潤などが見られます。
免疫蛍光染色ではIgG、IgM、C3などの沈着パターンが見られ、さらに電子顕微鏡でメサンギウムや内皮下に電子密度の高い沈着物が確認される場合があります。
管内増殖性糸球体腎炎の治療方法と治療薬について
治療方法の選択は病態の重症度、原因となる感染や自己免疫機序の有無、患者の年齢・合併症などにより、基本的には免疫複合体の生成や沈着を抑制し、炎症を軽減することが目標となるため、ステロイドや免疫抑制薬の使用が考慮されます。
急性期の治療
軽症~中等症程度であれば、安静・塩分制限・利尿薬や血圧管理を中心とした内科的管理が行われます。
特に溶連菌感染後の場合は、抗菌薬を用いて残存する菌を除去し、補体価や腎機能の回復を見守るアプローチが一般的で、溶連菌感染後急性糸球体腎炎の大半は治療反応が良好であり、完全寛解に至るケースも多いです。
ステロイド・免疫抑制剤の使用
重症例や急速進行性腎炎のような経過を辿る場合、ステロイド(プレドニゾロンやメチルプレドニゾロン)を用いたパルス療法や、免疫抑制剤(シクロホスファミドやタクロリムスなど)の併用が検討され、過剰な免疫反応が抑制され、糸球体へのダメージを食い止められることが期待できます。
| 治療薬 | 作用・特徴 | 使用目的 |
|---|---|---|
| 抗菌薬(ペニシリン系) | 溶連菌やブドウ球菌などの除菌 | 感染源を制御し、再感染や慢性化を防ぐ |
| ステロイド(PSLなど) | 強い抗炎症作用で免疫反応を抑える | 急性期の炎症コントロール |
| 免疫抑制剤(CYCなど) | B細胞やT細胞の活性を低下させる | 重症例や自己免疫性背景が疑われる場合に使用 |
| 利尿薬(フロセミドなど) | 余分な水分・ナトリウムを排出し、浮腫を軽減 | 高血圧や浮腫のコントロールを目的 |
血圧管理と水分管理
高血圧や浮腫がある場合は、塩分制限や利尿薬を適切に使い、腎臓への負担を軽減し、また、急性期には水分やたんぱく質の摂取制限が求められる場合もあり、栄養士や薬剤師を含めたチーム医療が有効です。
- 塩分を控えた食事(目安として1日6g未満)
- 血圧が高い場合はカルシウム拮抗薬やACE阻害薬を用いる
- 浮腫がひどいときは利尿薬を用い、腎機能と電解質をモニタリングする
血漿交換や透析
極めて重症の場合や、急速進行性腎炎を疑う状況では、血漿交換や吸着カラムによる免疫複合体の除去が検討されることがあります。
大学病院など高度医療施設で実施されることが多く、透析が一時的に必要となるケースもあり、早期の総合的対応が重要です。
管内増殖性糸球体腎炎の治療期間
治療期間は原因や重症度によって大きく異なり、溶連菌感染後急性糸球体腎炎の場合は抗菌薬を投与し、急性期を過ぎれば数週間~数カ月で寛解に至ることが多いです。
ただし、再燃や慢性化に注意し、しばらく通院フォローが必要となることもあります。
急性期(1~2カ月)
急性期の最初の数週間は症状が強く出やすく、血尿やタンパク尿、高血圧、浮腫などが顕著です。
ステロイドや免疫抑制剤を開始した場合は少なくとも1~2カ月間の継続投与が一般的で、症状の軽減や検査値(クレアチニン、補体価)の改善を確認しながら投薬量を調整します。
慢性期・回復期(3~6カ月)
急性期を乗り越えた後も、血尿やタンパク尿が完全に消失するまで3~6カ月程度はかかることがあり、自己免疫性の背景が強い場合はもっと長引くこともあります。
定期的な外来受診で尿検査と血液検査を行い、適宜薬剤の減量や中止の判断を行います。
- 完全寛解(尿所見正常化、腎機能正常化)までは数カ月単位のフォローアップが必要
- 自覚症状が消えても医師の指示があるまで薬を自己判断で中断しない
- 感染や再燃のリスクを減らすため、体調管理と感染予防に注意
再発や残存障害
まれに、管内増殖性糸球体腎炎が再発する例や、若干のタンパク尿や血尿が残存し慢性糸球体腎炎へ移行する場合がありますが、管理や治療を継続することで腎機能を保ち、重篤な慢性腎不全への進行を防ぐことを目指します。
| 治療期間のステージ | 期間の目安 | 主な治療内容と管理 |
|---|---|---|
| 急性期(1~2カ月) | 症状出現~2カ月ほど | ステロイドや免疫抑制薬、抗菌薬などを使用し急性期症状を抑える |
| 回復期(3~6カ月) | 急性期後~6カ月ほど | 薬の減量や中止を検討しながら定期的に尿・血液検査で経過観察 |
| 長期フォロー(6カ月以降) | 6カ月以降~数年 | 再発や慢性化を防ぐために定期外来でフォローする |
――――――――――――――――――――――――――
管内増殖性糸球体腎炎薬の副作用や治療のデメリットについて
管内増殖性糸球体腎炎の治療では、ステロイドや免疫抑制剤、抗菌薬などの投与が主に行われますが、いずれも有効性と同時に副作用のリスクがあります。
ステロイドの副作用
高用量や長期使用の場合、ステロイド特有の副作用が出現するリスクが高まります。代表的なものとして、ムーンフェイス(顔のむくみ)、食欲亢進、体重増加、高血圧、骨粗鬆症、易感染性などが挙げられます。
急性期には抗炎症効果が高い反面、投与量の管理が難しく、副作用とのバランスを考慮しながら治療を行うことが必要です。
免疫抑制剤の副作用
シクロホスファミドやタクロリムス、ミコフェノール酸モフェチルなどが代表的で、これらの薬は免疫系全体を抑制するため、感染症にかかりやすくなったり、骨髄抑制(白血球や血小板の減少)といった副作用を起こす可能性があります。
定期的に血液検査を行い、白血球数や肝機能などをモニタリングしながらの使用が大切です。
- 免疫抑制剤使用中は、風邪やインフルエンザなど感染症に特に注意
- 長期使用の場合、腫瘍発生リスク増加の報告もあるためフォローアップが大切
- 薬の相互作用に注意し、併用する他の薬についても主治医に相談
抗菌薬の副作用
溶連菌感染後急性糸球体腎炎などを対象に、ペニシリン系やマクロライド系などの抗菌薬を使用する場合があります。
抗菌薬は比較的安全性が高いとされていますが、アレルギー反応や腸内細菌叢の乱れによる下痢、まれに重篤な皮膚症状や肝障害などが起こるリスクも忘れてはなりません。
治療デメリット
- 長期通院が必要:慢性化や再発リスクがあるため、定期的な検査と診察が必要となり、通院負担が生じる
- 生活制限:食事療法(塩分制限やたんぱく質制限)、安静度の指示など、日常生活に一定の制限がかかる
- 医療費負担:ステロイドや免疫抑制剤などの薬剤コストに加え、定期検査費用も積み重なり出費が増える
| 治療の主薬 | 主な副作用とデメリット | 対策 |
|---|---|---|
| ステロイド | ムーンフェイス、易感染性、骨粗鬆症など | 投与量の漸減、定期検査、骨密度検査など |
| 免疫抑制剤 | 感染リスク増加、骨髄抑制、肝機能障害など | 血液検査、感染予防対策、投薬量調整 |
| 抗菌薬 | アレルギー、腸内細菌叢の乱れなど | 皮膚症状や消化器症状に注意し、異常時は早めに相談 |
| 利尿薬 | 脱水、電解質異常、腎機能低下のリスク | 水分補給バランスや血清電解質の定期モニタリング |
管内増殖性糸球体腎炎の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険適用の範囲
初期の検査(尿検査、血液検査、画像検査)、腎生検(入院が必要な場合が多い)、ステロイドや免疫抑制剤などの薬物療法、必要に応じた透析や血漿交換などの高度医療に至るまで、ほぼ全てが保険診療に含まれます。
治療費の目安
- 外来通院:数千円程度/1回
定期受診や検査、薬剤処方などで1回につき数千円の負担になるケースが一般的です。 - 腎生検入院:合計で数万円~十数万円程度
腎生検を伴う入院は2~3日ほどかかることが多く、検査や病理診断の費用も含めて数万円~十数万円程度の自己負担額になる可能性があります。 - ステロイド・免疫抑制剤費用:1か月あたり数千円~数万円
薬剤の種類や用量によりコストは変わります。例えば、プレドニゾロンの比較的低用量なら毎月数千円の負担で済む一方、高額な免疫抑制剤を長期にわたって使用する場合は月数万円になることもあります。
| 治療内容 | 保険適用後の自己負担目安(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 外来通院(検査含む) | 1回あたり3,000~5,000程度 | 検査内容や病院の規模、地域による差がある |
| 腎生検(短期入院) | 数万円~十数万円 | 病理診断費や入院費を含む |
| ステロイド、免疫抑制剤 | 月あたり3,000~30,000以上 | 薬の種類と用量、期間により大きく変動 |
| 血漿交換など特別治療 | 数万円~さらに高額になる場合も | 専門施設で実施するため費用が高くなることが多い |
以上
参考文献
Kanauchi M, Dohi K. Endocapillary proliferative glomerulonephritis. Ryoikibetsu Shokogun Shirizu. 1997 Jan 1(16 Pt 1):113-6.
Komatsuda A, Ohtani H, Nimura T, Yamaguchi A, Wakui H, Imai H, Miura AB. Endocapillary proliferative glomerulonephritis in a patient with parvovirus B19 infection. American journal of kidney diseases. 2000 Oct 1;36(4):851-4.
Arai M, Mii A, Kashiwagi T, Shimizu A, Sakai Y. The severity of glomerular endothelial cell injury is associated with infiltrating macrophage heterogeneity in endocapillary proliferative glomerulonephritis. Scientific reports. 2021 Jun 25;11(1):13339.
Fujita E, Nagahama K, Shimizu A, Aoki M, Higo S, Yasuda F, Mii A, Fukui M, Kaneko T, Tsuruoka S. Glomerular capillary and endothelial cell injury is associated with the formation of necrotizing and crescentic lesions in crescentic glomerulonephritis. Journal of Nippon Medical School. 2015 Feb 15;82(1):27-35.
Uchida T, Oda T, Watanabe A, Yamamoto K, Katsurada Y, Shimazaki H, Tamai S, Kumagai H. Transition from endocapillary proliferative glomerulonephritis to membranoproliferative glomerulonephritis in a patient with a prolonged human parvovirus B19 infection. Clin Nephrol. 2014 Jul 1;82(1):62-7.
Yuan M, Tan Y, Li J, Yu X, Zhang H, Zhao M. Urinary sediments could differentiate endocapillary proliferative lupus nephritis and endocapillary proliferative IgA nephropathy. International Immunopharmacology. 2021 Jan 1;90:107122.
Jindal KK. Management of idiopathic crescentic and diffuse proliferative glomerulonephritis: evidence-based recommendations. Kidney international. 1999 Jun 1;55:S33-40.
Watanabe H, Osawa Y, Goto S, Habuka M, Imai N, Ito Y, Hirose T, Chou T, Ohashi R, Shimizu A, Ehara T. A case of endocapillary proliferative glomerulonephritis with macrophages phagocytosing monoclonal immunoglobulin lambda light chain. Pathology international. 2015 Jan;65(1):38-42.
Hisano S, Kiyoshi Y, Tanaka I, Tokieda K, Niimi K, Tsuru N, Takebayashii S, Iwasaki H. Clinicopathological correlation of childhood IgA glomerulonephritis presenting diffuse endocapillary proliferation. Pathology international. 2004 Mar;54(3):174-80.
Nasr SH, Satoskar A, Markowitz GS, Valeri AM, Appel GB, Stokes MB, Nadasdy T, D’Agati VD. Proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgG deposits. Journal of the American Society of Nephrology. 2009 Sep 1;20(9):2055-64.