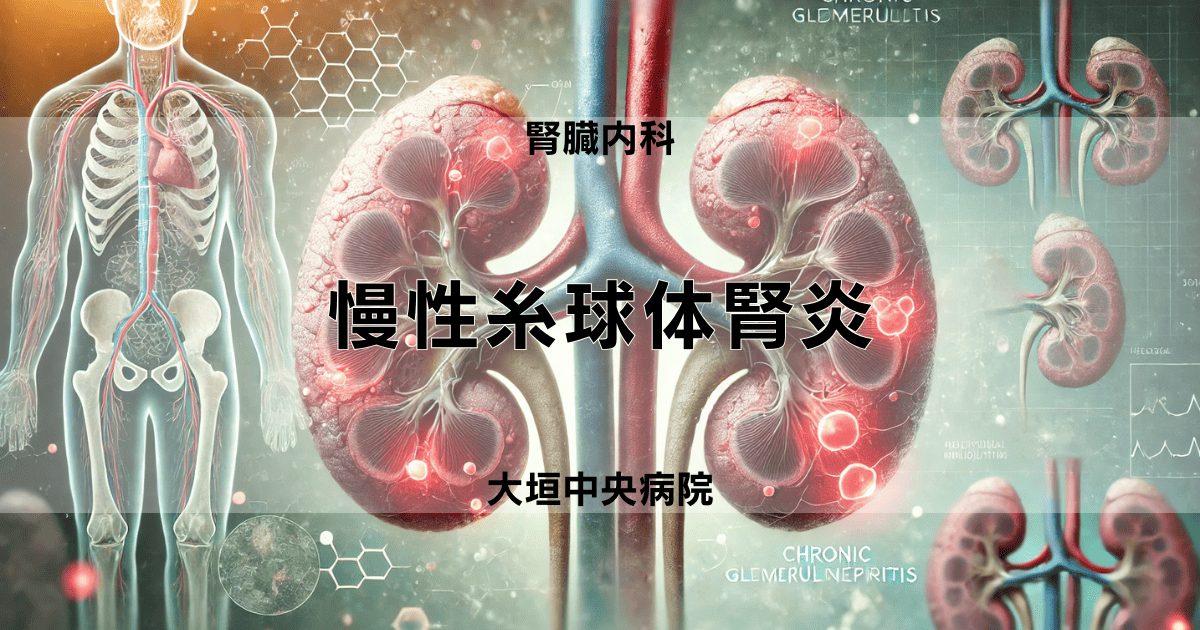慢性糸球体腎炎とは、腎臓内の糸球体と呼ばれる血液ろ過の仕組みに慢性的な炎症が起こり、長期的に腎機能が低下してしまう状態です。
尿の異常や疲労感、むくみなどが出現しやすい一方で、初期には症状が目立たず、受診のタイミングを逃してしまう方もいます。
放置すると腎機能が大きく低下し、日常生活に支障をきたす場合もあり、早期発見と正しいケアが重要です。
慢性糸球体腎炎の病型
慢性糸球体腎炎にはいくつかの病型があり、それぞれに特徴や進行のしかたが違い、医師が病型を把握すると治療方針を決めやすくなり、日常生活での注意点も明確になります。
糖尿病性腎症との関連
糖尿病を持つ方は、血糖値のコントロール不良によって糸球体がダメージを受け、慢性的な炎症を起こし、血管全体に負担がかかるため、血液がスムーズにろ過されにくくなり、腎機能が低下しやすくなります。
糖尿病が原因となっている場合は、まず血糖値を安定させるための治療が重要で、長期的には血圧管理や適切な食事療法も必要になるケースが多いです。
糖尿病性腎症に関わる治療と生活上のポイント
- 血糖値を把握し、適度な運動を心がける
- 定期的な血圧測定と塩分制限を検討する
- 不要な加工食品や菓子類を控えめにする
- 定期検診を欠かさず受ける
このような小さな積み重ねが、病気の進行を遅らせるきっかけになります。
糖尿病性腎症の大まかなステージと特徴
| ステージ | 血清クレアチニン値などの変化 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 1 | 正常範囲 | 微量アルブミン尿が出始めることあり |
| 2 | やや上昇 | たんぱく尿が明確に確認される |
| 3 | 中等度の上昇 | 腎機能が徐々に低下し、むくみが強まる |
| 4 | 高度の上昇 | 尿毒症状が目立ち、透析が視野に入る |
IgA腎症との結びつき
IgA腎症は、糸球体に免疫グロブリンAが沈着することで慢性的な炎症を生じる病型です。
小さな血尿やたんぱく尿が続き、風邪など上気道感染後に症状が強くなる場合もよく見ら、進行速度は緩やかですが、長期間放置すると腎不全へ移行する可能性があるので、早い段階で免疫調節薬や食事管理を組み合わせたアプローチを行います。
IgA腎症の症状
- 血尿が断続的に続く
- 軽度のむくみが目立つ
- 喉の感染や風邪の後に血尿が増える
- 比較的若い世代でも見られる
IgA腎症は検査で診断を確定しやすいですが、症状が軽度に留まることもあり、受診を先延ばしにしがちな点には注意が必要です。
膜性腎症の特徴
膜性腎症は、高齢者に比較的多くみられる病型の1つで、糸球体基底膜に免疫複合体が沈着して起こり、顕著なたんぱく尿があり、血清アルブミンが下がることでむくみが生じやすくなるのが特徴です。
原因が明らかでない原発性膜性腎症もあれば、がんや感染症がきっかけとなる続発性膜性腎症もあります。
膜性腎症の大まかな経過や合併症
| 項目 | 原発性膜性腎症 | 続発性膜性腎症 |
|---|---|---|
| 原因 | 明確な基礎疾患がないことが多い | がんや慢性感染症、膠原病などによる |
| たんぱく尿 | 大量に出ることが多い | 病因によって程度が異なる |
| 治療目標 | 尿蛋白の減少とむくみの軽減 | 原因疾患の治療と並行し腎症状をコントロール |
| 予後 | 半数程度が自然軽快することもある | 原因が深刻な場合、慢性化しやすい |
膜性増殖性糸球体腎炎の概要
膜性増殖性糸球体腎炎は、糸球体基底膜やメサンギウム領域が増殖し、腎臓全体に強い炎症反応が続く病型で、さまざまな免疫異常や感染症、遺伝的要素が複雑に絡み合う場合が多く、治療にも時間がかかるケースがあります。
たんぱく尿や血尿、浮腫などの症状が徐々に顕在化し、高血圧を伴う例もよく見られ、根本的な免疫コントロールや生活管理が大切であり、医師との連携が重要となる病型です。
膜性増殖性糸球体腎炎を疑ったときに気をつける点
- 早めに腎臓専門医を受診する
- 家族歴や自己免疫疾患の有無を整理しておく
- 血圧記録をこまめにつける
- 感染症の兆候や持病の管理を徹底する
ただし、細かな病型分類や具体的な診断には専門的な検査が必要になります。
慢性糸球体腎炎の症状
慢性糸球体腎炎では、腎臓のろ過機能が徐々に低下していくことで、全身に影響が及び、自覚症状が出にくい段階もありますが、いくつかの兆候を見逃さないことが早期発見につながります。
尿の異常に注目
最初に気づきやすいのは、尿にまつわる異常で、血尿やたんぱく尿が続く、泡立ちが強くなる、尿の色が変わるなどのサインが見られるときは要注意です。
早朝の尿だけでなく、日中の尿も観察すると、変化をより把握しやすくなります。
尿に表れるサイン
- 尿が濁っている
- 尿にうっすらと赤みがある
- ときどき茶褐色になる
- 泡立ちが長く消えない
これらが断続的に続く場合、腎臓になんらかのダメージがある可能性を考える必要があります。
尿検査時の主要な指標
| 項目 | 略称 | 主な意味 |
|---|---|---|
| 尿たんぱく | PRO | 糸球体障害やタンパク漏出を示唆 |
| 尿潜血 | BLD | 血尿の有無をチェック |
| 尿比重 | SG | 尿の濃さや腎濃縮力を確認 |
| 尿沈渣 | – | 細胞や円柱の有無を検査 |
むくみと体重増加
腎機能の低下により、体に水分やナトリウムがたまりやすくなるため、むくみが起こり、特に朝起きた時のまぶたや、夕方になると足首が腫れるなどの訴えが多く、靴のきつさで気づく方もいます。
また、同じ食生活をしていても体重が増えることがあり、尿量の減少などで余分な水分が体内に蓄積している場合があります。
むくみが疑われるときに意識したいポイント
- 一日の水分摂取量をメモしてみる
- 塩分や加工食品の摂取を見直す
- 足や顔のむくみ具合をチェックする
- 夕方や就寝前に脚のだるさを感じないか振り返る
自分では軽度と思っていても、実は腎機能の低下が進んでいる可能性があるため、定期的な検査が欠かせません。
高血圧と倦怠感
腎臓は血圧調整に深く関わる器官なので、慢性糸球体腎炎が進むと高血圧を合併しやすくなり、血圧が高い状態が続けば、頭痛や動悸、息切れといった症状を伴う方もいるため、生活の質が低下しがちです。
また、腎機能の低下によって老廃物が排出されにくくなると、全身のだるさや疲労感が強まり、倦怠感は単なる過労だけではなく、腎臓の異常を示すサインかもしれません。
腎臓と血圧の関係を簡単
| 指標 | 腎機能が正常な場合 | 慢性糸球体腎炎で低下した場合 |
|---|---|---|
| 血圧調整 | レニン-アンジオテンシン系が安定 | レニン分泌の異常で高血圧が持続 |
| 老廃物排出 | 尿量がしっかり確保される | 尿量低下や体液貯留で疲労感が強くなる |
| 電解質 | カリウムやナトリウムのバランス良好 | 不均衡になりやすく不整脈などのリスク増 |
進行による合併症
慢性糸球体腎炎が進行すると、腎臓以外の合併症も引き起こされる可能性があり、貧血や骨粗鬆症、心血管疾患などが代表例で、これは腎臓が担うホルモン分泌や電解質管理が崩れるためです。
尿毒症という重篤な状態に至ると、透析治療を検討しなければならないケースもあるので、放置は大変危険です。
進行期に想定されるリスク
- 貧血が長く続いて体力が低下する
- 骨のミネラルバランスが崩れやすくなる
- 心不全や冠動脈疾患が発症しやすくなる
- むくみや高血圧がさらに悪化する
最初はわずかな症状でも、じわじわ体の機能を損ねる恐れがあります。
原因
慢性糸球体腎炎は、ひとくちに言っても多様な要因が絡んで発症し、遺伝的な素因や自己免疫異常、感染症、生活習慣など、さまざまな誘因が腎臓の糸球体を傷つけます。
自己免疫異常や免疫複合体
IgA腎症のように、自己免疫が関与しているタイプは、体内でつくられた抗体が糸球体に沈着することで始まり、糸球体が炎症を起こし、じわじわと機能が落ちていくのが典型です。
こうした免疫複合体が沈着する背景には、遺伝的要因やウイルス感染の影響などが考えられ、単純にひとつの原因だけでは説明しにくい面があります。
免疫系が関わるケースの共通点
- 持続的な炎症反応が見られる
- 抗体や補体の異常を示す検査結果が出る
- 家族内発症の例も一部にある
- 全身性の症状が併発することがある
免疫異常が原因である場合、免疫抑制剤を使う選択肢が浮上するため、正確な診断が鍵になります。
自己免疫型慢性糸球体腎炎に関連しやすい要因
| 要因 | 具体例 | 影響 |
|---|---|---|
| 免疫複合体 | IgA、IgG、IgM など | 糸球体に沈着し炎症を引き起こす |
| 補体低下 | C3、C4 などの補体レベルが低下 | 炎症や組織障害を助長する |
| 自己抗体 | ANCA、抗核抗体 など | 血管炎や膠原病との関連が深い |
| 遺伝的素因 | 特定のHLA型や家族歴がある場合など | 発症リスクが高まる可能性がある |
感染症の後遺症や二次性疾患
溶連菌感染やB型肝炎、C型肝炎などの感染症がきっかけで、糸球体が炎症を起こすことがあり、病原体に対する免疫反応が強すぎて腎臓を巻き込む形になったり、ウイルスそのものが糸球体にダメージを与えたりと、メカニズムはさまざまです。
また、がんや膠原病などの慢性疾患の一部として、続発的に糸球体腎炎を発症するケースも報告されています。
特に感染症が原因の場合、早期に感染を治癒させることや、再感染を防ぐことが非常に重要ですが、すでに腎機能にダメージが及んだ場合は、あわせて腎臓のケアを行う必要があります。
感染症や二次性疾患に関連する例
- 溶連菌感染後急性糸球体腎炎が慢性化
- B型肝炎関連腎炎、C型肝炎関連腎炎
- 膠原病(SLEなど)に伴う二次性腎炎
- がん関連の糸球体病変
原因を追求するときは、患者の既往歴や合併症を丁寧に確認し、必要な検査を進めることが鍵です。
生活習慣による負担
生活習慣、特に食塩や動物性たんぱく質の過剰摂取、慢性的な高血圧、喫煙などは、腎臓へ大きな負荷をもたらし、糖尿病と高血圧がある人は、腎臓のろ過機能がより損なわれやすく、慢性糸球体腎炎を併発するリスクが上がります。
塩分制限や適度な運動習慣の確立は、病気の進行を食い止めるうえで大切です。
生活習慣に注目して見直すべき項目
- 塩分摂取量を控える
- タバコを吸う習慣があれば禁煙を検討する
- 飲酒量を管理し、過度なアルコールは避ける
- 週に数回は有酸素運動を行う
こうした改善が腎臓だけでなく、心血管や代謝面の健康管理にも寄与します。
生活習慣の改善効果
| 生活習慣の変更 | 期待できる効果 | 留意点 |
|---|---|---|
| 塩分制限 | 血圧低下、むくみ軽減 | 継続的な意識が大切 |
| 禁煙 | 腎血流の改善、血管機能保護 | 禁煙外来やサポートを活用すると良い |
| 節酒 | 血圧と体重コントロール | 肝機能や糖代謝への負担も軽くなる |
| 適度な有酸素運動 | 血圧安定、体重管理 | 無理せず、息が上がりすぎない程度に |
遺伝的要素と年齢要素
一部には遺伝的要素が強く関与するタイプもあり、家族内で似たような腎疾患を持つ場合は要注意です。
また、高齢になるほど腎臓の予備機能が低下しやすいため、ささいな炎症でもダメージが蓄積しやすく、慢性化しやすい現実があります。
遺伝や加齢を意識するときに考慮すべき点
- 家族に腎臓病の既往があるか調べる
- 60歳以上は腎機能低下を意識して定期的に検査を受ける
- 血液・尿検査の結果を保管し、経年変化をチェックする
- 体力の衰えとともに食事内容を見直す
このように原因が複合的に絡む場合が多いため、自己判断はせず医療機関を受診してください。
慢性糸球体腎炎の検査・チェック方法
慢性糸球体腎炎を疑ったとき、あるいは進行状況を把握したいときには、いくつかの検査を組み合わせて評価し、尿検査や血液検査、画像検査、腎生検など、その人の症状や病歴に応じて必要なステップを踏むことになります。
尿検査での基本的な確認
尿検査は腎臓の状態を手軽に把握できる手段であり、まず最初に行われることが多いです。
尿たんぱくや尿潜血、比重、沈渣などを総合的に見て、どのくらい腎臓がダメージを受けているかを推測し、持続的にたんぱく尿や血尿が出ている場合は、精密検査のきっかけとなります。
尿検査でチェックする主要な項目
- 尿たんぱく 糸球体の障害度を推察
- 尿潜血 血尿の有無を評価
- 尿比重 濃縮力や水分バランスを判断
- 尿沈渣 赤血球や円柱の種類を確認
以上の結果が基準値から外れているかどうかを見極め、問題がある場合はより詳しい検査に進みます。
代表的な尿検査所見
| 所見 | 異常結果の例 | 意味 |
|---|---|---|
| 尿たんぱく | 1+ 以上が持続 | 糸球体障害や尿細管障害の可能性 |
| 尿潜血 | (+++) など大量反応 | 血尿があり腎・尿路疾患を示唆 |
| 尿沈渣 | 赤血球円柱や顆粒円柱が多い | 糸球体レベルの損傷を示す |
| 尿比重 | 1.005以下 or 1.030以上 | 腎濃縮力の異常や脱水を推測 |
血液検査で腎機能を推定
血液検査では、血清クレアチニンや血中尿素窒素、推算GFR(糸球体濾過量)などを測定して腎機能を評価し、貧血や電解質の異常、免疫指標の変化も調べることで、原因や進行度を把握しやすくなります。
さらに、特定の免疫異常が疑われる場合は、IgAや補体レベルなども詳細にチェックします。
血液検査で重視する主な項目
- 血清クレアチニン 腎ろ過能力の指標
- BUN(血中尿素窒素) タンパク代謝産物の排泄状態
- eGFR 糸球体濾過量の推定値
- 免疫学的検査(IgA、補体) 免疫関与の可能性を検討
検査値が標準からどれだけ乖離しているかで、治療開始のタイミングや方針を考慮していきます。
画像検査や腎エコー
腹部エコーやCT、MRIなどの画像検査では、腎臓の形態や大きさ、腫れの有無、結石などの合併所見を確認し、とくに腎エコーは非侵襲的で実施しやすいため、多くの医療機関で広く活用されます。
慢性化している場合は、腎臓が萎縮している、皮質と髄質の境界が不明瞭になるなど、特有の所見を認めることもあります。
画像検査でチェックするポイント
- 腎臓の大きさと左右差
- 皮質・髄質の厚みと境界
- 嚢胞や結石の有無
- 血流状態の変化
画像所見だけでは原因の特定が難しい場合も多いため、他の検査結果との総合判断が必要です。
腹部エコーとCT・MRIの特徴
| 項目 | 腹部エコー | CT・MRI |
|---|---|---|
| 被ばくリスク | なし | CTはX線被ばくがあり、MRIはなし |
| 画像の詳細度 | やや限定的 | 高解像度で詳細な評価が可能 |
| リアルタイム性 | リアルタイムで血流や動きを観察 | 静止画または断層像で正確に把握 |
| 検査時間 | 比較的短時間 | 機種や部位によっては長め |
腎生検の必要性
原因や病型をより正確に知るために、腎生検を検討する場合があり、腎臓の組織の一部を採取して顕微鏡で詳しく調べ、腎組織における炎症や免疫沈着の状態を直接確認できます。
腎生検を受ける際に考慮すべき点
- 血液凝固機能や貧血の程度
- 高血圧のコントロール状況
- 検査後の安静や入院の要否
- サンプル不足による再検の可能性
腎生検は確定診断や治療方針の決定に役立つ一方、まれに合併症が発生するリスクもあります。
治療方法と治療薬について
慢性糸球体腎炎の治療は、病型や症状の進行度、原因となる背景疾患に応じて選択肢が変わり、基本となるのは、腎臓に負担をかけない生活習慣の確立と、必要に応じた薬物療法の組み合わせです。
生活習慣の改善が土台
いかなる病型であっても、腎臓への過度な負担を減らすことが大切で、塩分制限やタンパク質の適量摂取、肥満解消、血圧管理などの取り組みが、病気の進行を遅らせる一助となります。
また、禁煙や節酒なども血管の健康を保つ上で有益です。
生活習慣を見直すうえで着目すべき点
- 毎食の塩分量を5g以下に近づける
- 肉類だけでなく魚や大豆製品を適度に取り入れる
- ウォーキングなどの運動で体力を維持する
- 血圧手帳をつけて数値管理を習慣化する
こうした地道な改善は、薬物療法の効果を高めることにもつながります。
食事管理のポイント
| 食事要素 | 具体的ポイント | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 塩分 | しょうゆや味噌を控え、香辛料やだしを活用 | 血圧低下、むくみ軽減 |
| タンパク質 | 肉・魚だけでなく卵や豆腐からの摂取も意識 | 過剰摂取を避け、筋肉維持に役立つ |
| カリウム | 野菜や果物の摂取で不足を補う | 電解質バランスを整えて血圧安定 |
| 水分 | 医師の指示に従い、むくみが強い場合は調整 | 体液量の管理で腎負担を軽減 |
血圧管理と降圧薬
高血圧があると腎臓へのダメージが加速するため、降圧薬の使用が検討されるケースが多く、ACE阻害薬やARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)は、腎保護作用が期待できるため、慢性糸球体腎炎ではよく使われる薬です。
降圧薬のメリットと注意点
- 血圧を安定させることで腎臓のろ過機能を保護
- 尿たんぱく減少効果により進行が緩やかになる
- 過度な低血圧に陥らないよう定期的に数値を確認
- 副作用として咳やめまいが生じることがある
降圧薬使用時には、医師や薬剤師と相談しながら、薬剤調整や飲み忘れ防止を心がけてください。
免疫抑制剤やステロイド療法
IgA腎症や膜性腎症など、免疫系が深く関与している慢性糸球体腎炎では、ステロイドや免疫抑制剤の使用が選択肢に上がります。
炎症を抑え、腎臓の組織破壊を最小限にとどめることを目指すため、病気の活動性が高い段階で導入することが多いです。
免疫抑制治療時に留意すべき点
- ステロイドの減量計画を守り、急に中断しない
- 感染症に注意し、うがいや手洗いを徹底する
- 血糖値や血圧、骨密度の変化を随時チェックする
- 医療スタッフと連携し副作用発現を早期発見する
薬の強さや投与期間は患者ごとに異なるため、自己判断は避けて医療機関でのフォローを受けてください。
主な免疫抑制薬とステロイド
| 薬剤種類 | 例 | 作用機序 |
|---|---|---|
| ステロイド | プレドニゾロンなど | 免疫反応を抑制し、炎症を抑える |
| 免疫抑制剤 | シクロスポリン、タクロリムス等 | T細胞などの免疫細胞活性を抑え腎障害を軽減 |
| 免疫調整薬 | ミコフェノール酸モフェチル等 | 抗体産生を抑制し、組織損傷を制限 |
| 抗血小板薬 | アスピリンなど | 血流を改善し、糸球体内の血栓を予防 |
利尿薬やその他のサポート療法
むくみや体液貯留が著しい場合には、利尿薬を活用して体内の余分な水分を排出することがあり、また、高カリウム血症が見られる場合には、カリウム吸着薬を使用し、急激な電解質バランス異常を防ぎます。
補助的な薬を使うタイミング
- 重い浮腫が続く時に利尿薬を使用
- 高カリウム血症が急速に進む時にカリウム吸着薬を考慮
- 貧血が顕著ならエリスロポエチン製剤を投与
- 骨粗鬆症のリスクが高い時にビタミンD製剤を検討
これらの治療を総合的に組み合わせ、腎臓の状態を維持しながら合併症を防ぎます。
慢性糸球体腎炎の治療期間
慢性糸球体腎炎は、腎機能が段階的に損なわれていくため、治療が長期にわたる場合が多く、病型や重症度、治療開始のタイミングなどによって、効果の現れ方や治療期間には大きな差があります。
病型や重症度による違い
軽症から中等度のIgA腎症や、初期段階で見つかった高血圧性腎硬化症の場合は、生活習慣改善と降圧薬の使用で進行が抑えられるケースが多いです。
その一方、膜性腎症や膜性増殖性糸球体腎炎などで炎症が激しい場合や、大量のたんぱく尿がある場合は、免疫抑制療法を長期間行う必要が出てくるので、治療が長引くほど、定期的な通院や検査へのモチベーション維持が課題となります。
病型別のおおまかな治療期間の目安
| 病型 | 治療期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 軽度のIgA腎症 | 数か月~1年程度で落ち着くことも | 定期的に尿検査と血液検査を行う |
| 膜性腎症 | 半年~数年単位でステロイド治療 | 病状次第で免疫抑制剤を併用する |
| 糖尿病性腎症 | 血糖コントロールを継続的に行う | 一生涯の管理が必要となる場合多い |
| 膜性増殖性糸球体腎炎 | 長期にわたる免疫療法が必要 | 炎症が落ち着くまでに数年かかる |
治療効果の判定
慢性糸球体腎炎の治療効果を評価する基準には、尿たんぱく量や血清クレアチニン値、eGFRの推移などが用いられますが、指標が改善に向かったからといって、すぐに薬を中断すると再燃のリスクが高まるため、医師の指示に従いながら慎重に判断します。
特に免疫抑制療法では、薬の減量も段階的に行うのが一般的です。
治療効果判定に用いられる指標の変化
- 尿たんぱくが0.3g/日以下になる
- 血清クレアチニンが基準値に近づく
- eGFRが安定的に維持される
- むくみや高血圧の症状が改善する
短期間で目に見える改善がなくても、悪化を防ぐだけでも治療の成果といえるケースが多々あります。
長期フォローアップの重要性
慢性糸球体腎炎は再燃を繰り返すこともあるため、症状が落ち着いていても定期的なフォローアップが大切で、3か月や6か月ごとのペースで尿検査や血液検査を実施し、小さな変化を見逃さないようにすることが腎不全の予防につながります。
また、生活習慣の維持や食事管理も、症状が落ち着いた後にこそ継続する意義があります。
定期フォローアップで意識するポイント
- 血圧や体重を日々記録して相談材料にする
- 体調やむくみ、疲労感の変化をノートにつける
- 検査結果の推移を医師と一緒に確認する
- 早期に異常が見つかれば治療の選択肢が広がる
慢性糸球体腎炎薬の副作用や治療のデメリットについて
薬物療法は慢性糸球体腎炎の進行を抑えるために有効な手段ですが、副作用が皆無というわけではあく、長期にわたる治療では、薬のメリットとデメリットを正しく理解しすることが大切です。
ステロイドの副作用
ステロイドは炎症を強力に抑える反面、むくみや血糖値上昇、骨粗鬆症、胃潰瘍など、幅広い副作用が懸念され、また、精神面への影響(不眠や気分変動など)も起きることがあるため、投与量や期間を厳密に管理する必要があります。
急に服用をやめるとリバウンドや副腎不全が生じる可能性があり、自己判断での中断は危険です。
ステロイドの副作用を最小化する工夫の例
- 少量から開始し、状況に応じて漸増または漸減する
- カルシウムやビタミンDの補給で骨密度をサポート
- 血糖値や体重、精神状態を定期的にチェックする
- 胃薬を併用して胃腸障害を緩和する
ステロイド使用時に注意すべきポイント
| ポイント | 留意点 | 回避策・ケア方法 |
|---|---|---|
| 感染リスクの上昇 | 免疫力が低下し、風邪や肺炎にかかりやすい | 予防接種やマスクの着用、手洗い徹底 |
| 骨粗鬆症 | 骨のカルシウム吸収が阻害され骨がもろくなる | ビタミンD摂取や適度な運動 |
| 血糖コントロール異常 | 高血糖になりやすく、糖尿病の悪化リスク | 血糖測定を定期的に行い、食事調整 |
| 精神面の不安定 | うつ状態や不眠症、興奮などが出現する | 医師と相談し、必要時に投薬やカウンセリング |
免疫抑制薬による注意点
シクロスポリンやタクロリムスなどの免疫抑制薬は、自己免疫の過剰反応を抑える一方、感染症を招きやすい副作用があり、血中濃度を正しく保つ必要があり、定期的な血液検査で薬物濃度を測定しながら投与量を調整します。
また、腎毒性をもつものもあるため、むしろ腎機能を悪化させるリスクがあり、厳重な管理が必要です。
免疫抑制薬使用時に気をつけたいポイント
- 専門医による定期的な血液検査で濃度をチェック
- 発熱やのどの痛みなど、感染症の初期兆候に敏感になる
- 併用薬やサプリメントとの相互作用を確認
- 幻覚やしびれなど、神経症状がないか意識する
降圧薬や利尿薬の不都合
降圧薬は全身の血圧を下げる作用があるため、めまいやふらつきが起こる場合があり、利尿薬は脱水や電解質異常を引き起こし、特に高齢者では注意が必要です。
いずれもバランスを崩すと腎臓に負担をかけることがあるので、定期的な検査や医師の指示に沿うことが重要になってきます。
降圧薬・利尿薬使用時に想定される副作用やデメリット
| 薬剤 | 主な副作用 | 具体例 |
|---|---|---|
| ACE阻害薬 | 空咳、血管浮腫 | エナラプリル、リシノプリルなど |
| ARB | 低血圧、めまい | ロサルタン、バルサルタンなど |
| 利尿薬 | 脱水、低カリウム血症 | フロセミド、トリクロルメチアジドなど |
慢性糸球体腎炎の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険適用の範囲
病院で受ける一般的な検査(血液・尿・画像検査)や薬の処方は、医師が必要と判断した場合は保険適用で、腎生検などの侵襲的検査も、診断上必要とされれば保険の対象です。
ただし、健康診断や人間ドックでの任意検査、先進医療にあたる特殊な治療は保険が効かず、全額自己負担となる可能性があります。
保険適用の範囲で確認しておきたい点
- 医師の診断がある検査や治療が基本的にカバーされる
- 処方薬も医師の指示があれば3割負担などで済む
- 特殊検査や特殊注射は自己負担の場合もある
- 保険外の部分については事前に見積もりを確認
主な保険適用検査や治療内容
| 項目 | 保険の扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 血液・尿検査 | 医師が必要と判断する場合は適用 | 検診などのオプション検査は自己負担 |
| 画像検査 | 腎エコー、CT、MRIなど医療上必要なら適用 | PETなどの一部検査は保険外の場合もあり |
| 腎生検 | 診断・治療方針確立に必要なら適用 | 入院費や麻酔費を含めた費用を確認 |
| 薬剤処方 | 降圧薬、ステロイド、免疫抑制薬など適用 | 市販のサプリや健康食品は保険外 |
治療費の目安
治療費は病型や重症度、通院回数、使用薬剤などによって変動します。
| 項目 | おおよその自己負担額(3割負担) | 備考 |
|---|---|---|
| 月1回の外来診察 | 1,000円~2,000円程度 | 血液検査・尿検査含む場合 |
| 降圧薬などの処方 | 月3,000円~5,000円程度 | ジェネリック使用でさらに低減可能 |
| ステロイド治療 | 数千円~数万円 | 用量や投与期間で幅がある |
| 腎生検(入院含む) | 数万~10万円程度 | 病院や個人負担割合による違いが大 |
公的サポート制度や医療費控除
慢性糸球体腎炎の治療費がかさむ場合は、高額療養費制度や医療費控除を活用することで経済的負担を軽減でき、また、難病指定の対象となる病型や重症度であれば、自治体や国の助成制度が受けられる場合もあります。
- 高額療養費制度は自己負担上限を超えた分が返還される
- 医療費控除は年間10万円以上の医療費を支出した場合に適用
- 難病指定制度の対象かどうかを主治医に問い合わせる
- 社会福祉協議会などでの相談窓口も検討する
以上
参考文献
Koyama A, Yamagata K, Makino H, Arimura Y, Wada T, Nitta K, Nihei H, Muso E, Taguma Y, Shigematsu H, Sakai H. A nationwide survey of rapidly progressive glomerulonephritis in Japan: etiology, prognosis and treatment diversity. Clinical and experimental nephrology. 2009 Dec;13:633-50.
Nakagawa N, Mizuno M, Kato S, Maruyama S, Sato H, Nakaya I, Sugiyama H, Fujimoto S, Miura K, Matsumura C, Gotoh Y. Demographic, clinical characteristics and treatment outcomes of immune-complex membranoproliferative glomerulonephritis and C3 glomerulonephritis in Japan: A retrospective analysis of data from the Japan Renal Biopsy Registry. PLoS One. 2021 Sep 14;16(9):e0257397.
Brack M, Schroeder C, Fooke M, Schlumberger W, Sarang SS, Miller GW, Grant DF, Schnellmann RG, Gussak HM, Gellens ME, Gussak I. Nationwide and long-term survey of primary glomerulonephritis in Japan as observed in 1,850 biopsied cases. Nephron. 1999;82(3):205-13.
Yamagata K, Iseki K, Nitta K, Imai H, Iino Y, Matsuo S, Makino H, Hishida A. Chronic kidney disease perspectives in Japan and the importance of urinalysis screening. Clinical and experimental nephrology. 2008 Feb;12:1-8.
Imai E, Yamagata K, Iseki K, Iso H, Horio M, Mkino H, Hishida A, Matsuo S. Kidney disease screening program in Japan: history, outcome, and perspectives. Clinical journal of the American Society of Nephrology. 2007 Nov 1;2(6):1360-6.
Yamagata K, Yagisawa T, Nakai S, Nakayama M, Imai E, Hattori M, Iseki K, Akiba T. Prevalence and incidence of chronic kidney disease stage G5 in Japan. Clinical and experimental nephrology. 2015 Feb;19:54-64.
Arimura Y, Muso E, Fujimoto S, Hasegawa M, Kaname S, Usui J, Ihara T, Kobayashi M, Itabashi M, Kitagawa K, Hirahashi J. Evidence-based clinical practice guidelines for rapidly progressive glomerulonephritis 2014. Clinical and experimental nephrology. 2016 Jun;20:322-41.
Nakagawa N, Hasebe N, Hattori M, Nagata M, Yokoyama H, Sato H, Sugiyama H, Shimizu A, Isaka Y, Maruyama S, Narita I. Clinical features and pathogenesis of membranoproliferative glomerulonephritis: a nationwide analysis of the Japan renal biopsy registry from 2007 to 2015. Clinical and experimental nephrology. 2018 Aug;22:797-807.
Imai E, Matsuo S, Makino H, Watanabe T, Akizawa T, Nitta K, Iimuro S, Ohashi Y, Hishida A. Chronic Kidney Disease Japan Cohort study: baseline characteristics and factors associated with causative diseases and renal function. Clinical and experimental nephrology. 2010 Dec;14:558-70.
Nakamura T, Ushiyama C, Hirokawa K, Osada S, Inoue T, Shimada N, Koide H. Effect of cerivastatin on proteinuria and urinary podocytes in patients with chronic glomerulonephritis. Nephrology Dialysis Transplantation. 2002 May 1;17(5):798-802.