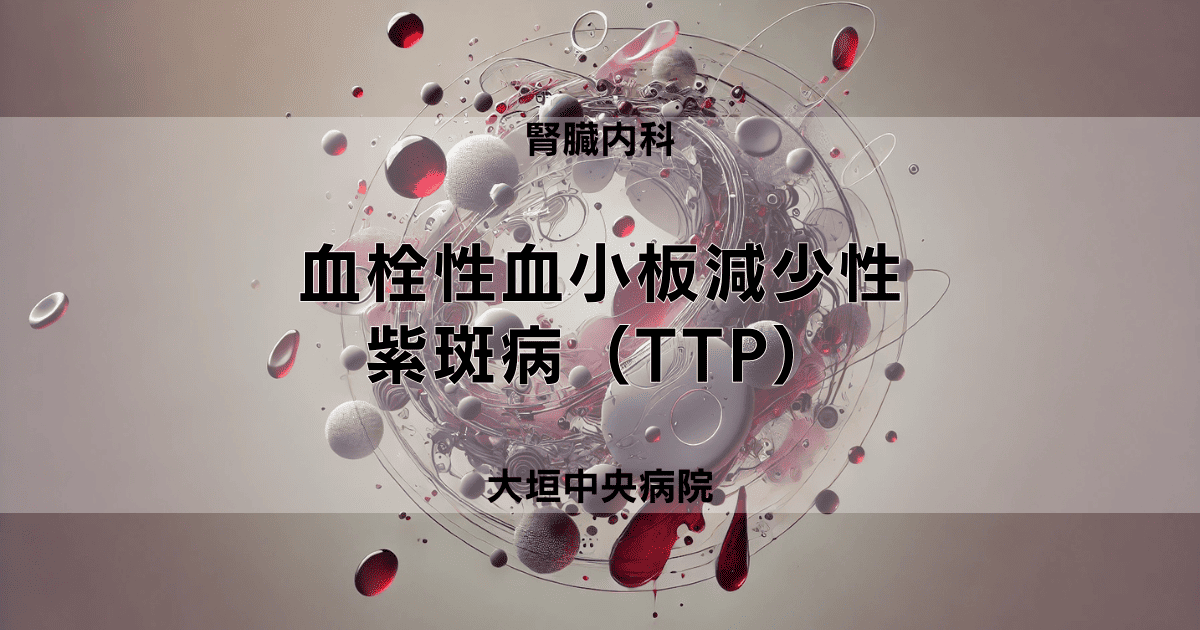血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)とは、血液を固めるために重要な役割を担う血小板が減少し、全身の微小血管に血栓が形成される病気です。
血小板の不足が進むと皮膚や粘膜などに紫斑が出現し、さらには腎臓や脳をはじめとする様々な臓器に影響を及ぼす可能性があります。
症状が突然現れるケースもあり、日常生活における体調変化を見逃さない意識が大切です。
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)の病型
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)には、生まれつきの要因によって血液凝固に関与する酵素がうまく働かないタイプと、後天的なメカニズムによって発症するタイプがあり、それぞれ異なる経過をたどります。
先天性TTPの特徴
生まれつきの遺伝的要因によって、ADAMTS13と呼ばれる酵素がうまく機能しないタイプを先天性TTPと呼び、血小板同士が過度に集まりやすくなり、微小血管内で血栓が形成されやすい状態です。
幼少期から症状が見られるケースがあり、特に日常生活の中で疲労が抜けにくいと感じることもあります。幼少期は病気の発見が遅れると重症化しやすいので、家族が注意深く観察しながら体調の変化を把握することが重要です。
後天性TTPの特徴
後天性TTPは、大人になってから免疫の異常などをきっかけにADAMTS13酵素に対する自己抗体が現れ、酵素活性が妨害される結果として血小板の異常凝集が進むタイプです。
突如として発症し、急激に症状が進むこともあるため、以前は健康だった人が急に体の異変を感じる場合があります。治療に関しては、自己抗体を抑えるための薬物や血漿交換などを行うことが多いです。
病型による経過の違い
先天性か後天性かによって、治療開始のタイミングや症状の現れ方が異なり、先天性の場合は幼少期から長期的に軽度な症状が現れやすい一方、後天性の場合は比較的急激に重症化へ移行する傾向があります。
ただし、両方の病型ともに血小板数が顕著に下がるときは、内出血や臓器障害など重い合併症が生じるリスクが高いです。
| 病型 | 発症時期 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 先天性TTP | 幼少期に多い | 遺伝的要因 |
| 後天性TTP | 成人後に多い | 自己抗体による酵素阻害など |
発症頻度と再発のリスク
TTPは決して患者数が多いとは言えない病気ですが、先天性・後天性ともに再発リスクがある点には注意が必要です。特に後天性の場合、自己抗体が一時的におさまっても、体調やストレスの状況によって再び異常をきたすことがあります。
再発を防ぐためには、病型に即した定期的な検査と医師の指示を守ったセルフケアが重要です。
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)の症状
TTPを発症すると、普段の生活ではあまり経験しないような症状が同時多発的に生じる可能性があります。血小板の減少により出血傾向が強まるだけでなく、全身の微小血管に血栓が形成される影響で、多様な臓器に障害が出ることもあるからです。
出血傾向に関連する症状
血小板は出血を止めるために重要な働きを担いますが、TTPによって血小板数が減少すると、身体のあちこちで出血が起こりやすくなり、皮膚に点状出血や紫斑が見られたり、歯磨きの際に歯茎から出血しやすくなります。
鼻出血も起こりやすくなることがあり、急に出血が増えると驚くこともあるでしょう。そうした時は慌てずに、血小板数の確認や病院での検査を早めに検討することが大切です。
- 衣類や寝具が血で汚れやすくなる
- 軽い打撲で大きなアザができる
- 歯科治療で出血が止まりにくい
- すり傷からの出血が長引く
神経症状や意識障害
TTPは脳の微小血管に血栓が生じる場合があり、頭痛、めまい、しびれなどの神経症状が生じることがあり、重症化すると意識障害やけいれんが起こり、命に関わる危険な状態に至る可能性も否定できません。
初期段階では軽い頭痛や集中力の低下といった症状から始まるケースもあり、見過ごしがちです。日常的に続く頭痛や神経症状がある場合は、一度医療機関に相談してください。
神経症状が見られたときに気をつけるポイント
| 症状 | 注意が必要な理由 |
|---|---|
| 頭痛やめまい | 脳への血栓形成の可能性を示唆する |
| 意識の混濁 | 脳の広範囲で障害が進行する兆候 |
| 言語障害 | 中枢神経系の機能低下を疑わせる |
| けいれん発作 | 重度の脳血管障害の兆候の一つ |
腎臓機能への影響
TTPの特徴的な症状の一つとして、腎臓が血栓の影響を受けて正常に機能しづらくなるケースが挙げられ、腎臓での血流障害が進むと、老廃物が体内に蓄積しやすくなり、むくみや倦怠感、尿量減少などの症状が出やすくなります。
腎不全に進行すると、体内の水分バランスと電解質バランスが乱れ、全身状態が悪化しやすいです。
腎機能障害の度合いを推測するには、定期的に尿検査や血液検査でクレアチニン値などを確認することが重要です。
特に朝起きたときに手指や顔まわりのむくみが顕著な場合や、尿の回数や色が明らかに変化していると感じる場合は検査を検討してください。
全身倦怠感や食欲不振
TTPでは、血液循環や臓器の働きに負担がかかるため、全身の倦怠感や食欲不振を訴えることが少なくありません。体が重く感じたり、ちょっとした動作でも疲れやすくなったり、体重が急に減る場合もあります
症状は非常にあいまいで、風邪やほかの病気と区別がつきにくい面がありますが、出血傾向や腎機能の異常などほかの症状と併せて現れた場合はTTPの可能性を考慮しましょう。
原因
TTPの原因は複雑なメカニズムが絡み合っており、先天性TTPと後天性TTPで発症理由が異なる点が特徴ですが、いずれのタイプでも共通するのが、血小板の凝集を防ぐADAMTS13酵素の活性低下です。
ADAMTS13酵素の役割
ADAMTS13酵素は、血液中で巨大化したフォン・ウィルブランド因子を切り離す働きを担い、血小板が過度に凝集しないよう調整する大切な存在です。
もしこの酵素の働きが弱まると、巨大因子が血小板を次々と集めてしまい、微小血管内で血栓ができやすくなります。
正常に機能している状態では、血小板の数と凝固機能のバランスが保たれますが、酵素が不足していると一気にバランスが崩れ、血栓が多発しながら逆に血小板数が急激に減少する危険があります。
ADAMTS13酵素とフォン・ウィルブランド因子の関係
| 項目 | 働き |
|---|---|
| フォン・ウィルブランド因子 | 血小板を微小血管壁に接着させる役割を担う |
| ADAMTS13酵素 | 巨大化した因子を切り離して血栓形成を抑制 |
先天性TTPの原因メカニズム
先天性TTPでは、ADAMTS13酵素を産生する遺伝子に変異があるため、酵素自体が欠損または大幅に機能低下しているケースが多いです。遺伝形質として受け継がれるため、家族内で複数の患者がいることも考えられます。
先天性の場合は、幼少期から酵素活性が低い状態が続くために、軽度から中等度の症状を慢性的に抱えることがある一方、ある時を境に急激な悪化をきたすことがあります。
家族内発症のリスクが高い状況で配慮したい点
- 親族にTTPの診断歴がある
- 年齢に比して血小板数が低めと言われたことがある
- 幼少期から皮下出血や疲労感が頻繁にある
もし親戚に同様の症状がある場合、定期的な血液検査で酵素活性を確認してください。
後天性TTPの原因メカニズム
後天性TTPでは、自己免疫の異常によりADAMTS13酵素に対する抗体が作られることで、酵素活性が抑えられてしまうことが主な原因です。免疫系の混乱によって自己抗体が増えやすい状態は、他の自己免疫疾患にも関連が見られる場合があります。
ストレスやウイルス感染、一部の薬剤などがきっかけで自己抗体を作りやすい体質に変化し、突然発症するケースもあるため、日常の体調管理や既往歴の把握が重要です。
後天性TTPを起こす可能性がある因子
| 因子 | 具体例 |
|---|---|
| 免疫バランスの乱れ | 自己免疫疾患、強いストレス |
| 薬剤 | 一部の抗がん剤や免疫調整薬など |
| ウイルス感染 | インフルエンザやその他ウイルス感染症 |
発症リスクを高める要因
TTPを発症しやすくする要因としては、遺伝的背景や自己免疫の問題以外にも、妊娠や出産がきっかけとなる例があります。
妊娠時は体内のホルモンバランスや血液凝固系に変化が生じやすいので、もともとADAMTS13酵素が不十分な人は注意が必要です。
また、重度の感染症にかかったり、外科手術の後など体力や免疫力が落ちているタイミングで発症リスクが上がる可能性もあります。
リスクを下げるためには、規則正しい生活リズムや食習慣、適度な運動などで体調を整え、免疫機能を安定させることが大切です。
それでも体調の変化が大きいと感じたときは、早めに血液検査を受けて現在の状態を客観的に確認することを意識してください。
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)の検査・チェック方法
TTPの診断や経過観察では、血液検査と画像検査などを組み合わせて総合的に評価します。特に血小板数や赤血球の破壊状態(溶血)の有無、そしてADAMTS13活性の測定が決め手になる場合が多いです。
血液検査で分かるポイント
血液検査では、血小板数、赤血球数、ヘモグロビン濃度などの基本的な指標に加え、赤血球の破壊が進んでいるかを推察するための間接ビリルビンやLDH(乳酸脱水素酵素)などの値も確認します。
TTPでは血小板数が低下するだけでなく、溶血による貧血が目立つのが特徴です。これらの数値に加えて、血液塗抹標本を顕微鏡で観察すると、破砕赤血球(シュイストサイト)が増えているかどうかが確認できます。
血液検査で注目する指標
| 検査項目 | 意味 |
|---|---|
| 血小板数 | 出血傾向の把握に直結 |
| LDH | 赤血球破壊や臓器障害の程度を反映 |
| 間接ビリルビン | 溶血の進行度を示唆 |
| 血液塗抹標本(破砕赤血球) | 特徴的な赤血球の変形を視覚的に確認 |
ADAMTS13活性の測定
TTPの確定診断において最も重要とされるのが、ADAMTS13活性の測定で、酵素活性が著しく低下している、あるいは酵素に対する自己抗体が検出された場合は、TTPの可能性が高まります。
ADAMTS13活性測定に関連して、以下のようなチェックが行われることがあります。
- 抗ADAMTS13抗体の有無
- ADAMTS13抗体の種類
- 酵素活性の残存率(%)
後天性TTPを疑う場合は特に自己抗体の有無がポイントになるため、免疫学的な検査との連携が重要です。
画像検査の活用
TTPは微小血管血栓が全身に広がり、臓器に影響を及ぼす病気で、臓器ごとに症状が進んでいるかどうかを確認するため、CTやMRIなどの画像検査を追加して脳や腎臓、肝臓などの状態を調べることがあります。
脳のMRI検査で虚血性の病変を認めるときは、TTPによる脳微小血管の障害が疑われる場合があり、腎臓の機能低下を示唆する検査結果が出た際は、腎臓の血流状態を確認するために造影検査を行います。
臓器ごとの画像検査で確認可能な主なポイント
| 対象臓器 | 主な検査手法 | 検査でわかること |
|---|---|---|
| 脳 | MRI、MRA | 虚血性病変、出血の有無 |
| 腎臓 | 腹部エコー、CT | 血流障害の程度、腫大の有無 |
| 肝臓 | CT、MRI | 肝実質の状態、塞栓の可能性 |
継続的なモニタリングの重要性
TTPは再発のリスクがあり、症状が治まったように見えても、血液データや臓器の状態に注意を払い続ける必要があります。
定期的に血液検査や症状の自己観察を行い、異常値が出始めた段階で早めに医師へ相談すると、重症化を防ぎやすいです。
モニタリングを行う上で意識したいポイント
- 定期検査の日程をカレンダーやスマホで管理する
- 日々の体調変化や出血傾向をメモして受診時に伝える
- 服薬中の薬や健康食品の有無も報告する
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)の治療方法と治療薬について
TTPは早期に治療に取りかかるほど、重症化や合併症を回避する可能性が高くなります。
治療は主に、血漿交換やステロイドなどによる免疫調整が柱となり、重症例では血液を入れ替えるような方法や、特殊な抗体製剤の使用を検討するケースもあります。
血漿交換療法
血漿交換は、TTPにおける基本的な治療の1つです。患者さんの血漿を取り除きながら、新鮮凍結血漿に置き換えることでADAMTS13酵素を補給し、血小板の異常凝集を抑えます。
後天性TTPで自己抗体が存在する場合でも、一時的に抗体を体外に排出する効果が期待でき、治療は通常、数日から数週間続けて行うことが多く、治療中は経過を見ながら回数や期間を調整します。
血漿交換療法を行ううえでの主な利点
- 不足したADAMTS13酵素の補填
- 自己抗体の除去をめざす
- 急性期の血小板減少を速やかに改善する
ただし、血漿製剤に対するアレルギー反応などのリスクもあるため、治療中は厳重な観察が必要です。
免疫抑制療法(ステロイドなど)
後天性TTPの多くでは、ADAMTS13酵素を攻撃する自己抗体の存在が問題になるため、ステロイドなどの免疫抑制剤を用いて抗体の産生を抑えることが重要です。
ステロイドは、高用量で短期間集中的に投与して病状の改善を図る場合や、低用量で長期間継続する場合など、患者さんの状態に合わせて投与方法を変化させます。
自己抗体の活動を抑えると、ADAMTS13酵素が再び機能しやすくなるため、血小板数の回復を促進しやすいです。
ステロイド治療に関して考慮したいポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 投与スケジュール | 短期集中 or 長期維持療法 |
| 副作用リスク | 感染症、糖尿病、骨粗しょう症など |
| 経過観察の必要性 | 血液データ・臓器機能の定期的チェック |
抗体製剤や新しい分子標的治療薬
近年では、ADAMTS13酵素に対する自己抗体の働きを直接制御する目的で、抗CD20抗体製剤(リツキシマブ)などが使われる機会があります。
自己免疫疾患の治療に応用される薬剤で、リンパ球を減らすことで異常な自己抗体の産生を抑える方法で、重症例や再発例などで従来のステロイド治療や血漿交換のみでは効果が不十分な場合に検討されるケースが多いです。
また、一部ではADAMTS13酵素に似た働きを行うように設計された新規治療薬や、血小板の凝集を抑制する分子標的治療薬の研究も進んでおり、患者さん一人ひとりの病態に合わせた治療方針を検討できるようになってきました。
補助療法や支持療法
TTPでは、貧血や出血、臓器障害など多岐にわたる問題を同時に抱えることがあり、メインの治療に加えて補助療法が行われることがあります。
例えば重度の貧血が見られる場合は赤血球輸血で体内の酸素供給能力を高める、あるいは血小板数が極端に少なく出血が止まりにくい場合は緊急で血小板輸血を実施し、腎機能障害が進むときは人工透析の導入を検討することもあります。
補助療法で検討される可能性のある項目
- 赤血球輸血
- 血小板輸血
- 人工透析
- 高血圧治療薬や利尿薬の使用
治療期間
TTPの治療期間は、患者ごとの病型や症状の重さ、治療の反応速度などに左右され、急性期には数週間にわたって集中的な治療を行い、その後は再発を防ぐために定期的な経過観察と必要に応じた治療の継続が必要なことが多いです。
急性期から回復期までの流れ
TTPの急性期は、血小板減少や溶血などが進んで全身の状態が不安定になるので、血漿交換やステロイド投与を積極的に行い、症状のコントロールを目指します。
この急性期治療は、一般的に数日から数週間程度続くことが多く、症状が改善して血小板数が回復してきたら回復期に移行します。
回復期では薬剤の量や血漿交換の頻度を調整し、症状の再燃がないことを確認しながら徐々に治療を軽減していきます。
急性期から回復期までの目安
| 期間区分 | 治療内容の例 |
|---|---|
| 急性期 | 血漿交換頻回実施、ステロイド高用量投与など |
| 回復期 | 治療強度を徐々に下げる、血液検査の頻度を下げる |
再発予防のための維持療法
後天性TTPの場合は、再発を防ぐために低用量のステロイドを継続したり、定期的に抗体製剤を投与したりといった維持療法を行うことがあります。
再発リスクの高さや自己抗体の残存度合いなどを考慮しながら、医師が最適な治療計画を立てます。維持療法の期間は数か月から数年単位に及ぶこともあり、患者さん自身の生活スタイルや合併症の有無なども考慮して決定することが大切です。
維持療法の目的
- 自己抗体の再上昇を防ぐ
- 血小板数を安定させる
- 長期的な臓器障害の進行を抑える
治療期間中の通院頻度
急性期の治療中は入院が必要となるケースが多く、退院後も週に1回や月に1回など頻度を決めて通院し、血液検査や診察を受けることが一般的です。
再発や副作用を早期にキャッチする意味でも、医師の指示に沿って定期的に通院することが推奨されます。
通院中にチェックすることが多い内容
- 血小板数の推移
- ADAMTS13活性の数値
- 臓器機能や副作用の有無
- 日常生活での出血傾向や体調変化
こうした情報を一元管理することで、治療方針をより的確に立てやすくなります。
完全寛解と長期フォローアップ
TTPは適切な治療を受けると、多くの場合で症状をコントロールできるようになります。
ただし、先天性の場合は酵素活性が根本的に低い状態が続くため、定期的な治療が続くことがありますし、後天性の場合でも自己抗体が再び活性化すると再発のリスクがあります。
そのため、一時的に血小板数が安定しても油断せず、長期的なフォローアップを意識することが大切です。
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)薬の副作用や治療のデメリットについて
TTPの治療に使われる薬は、免疫を抑える作用や血液成分に影響を与える性質があるため、副作用やデメリットがゼロというわけではありません。
治療効果を得るために必要な薬であっても、使い方によっては体への負担を大きくするリスクがあります。
ステロイドの副作用
TTP治療で頻用されるステロイド薬は、強い抗炎症作用と免疫抑制作用を持つ反面、長期使用や高用量使用によって副作用が現れる可能性があります。
感染症に対する抵抗力の低下、高血糖や骨粗しょう症、精神的な不安定などが挙げられ、防ぐために、医師はできるだけ副作用を抑える投与計画を立てるよう配慮します。
ステロイドの副作用を軽減するための対策
- 定期的な血液検査や骨密度検査で健康状態をチェックする
- 感染症の初期症状に気づいたら早めに受診する
- 投与量を徐々に減らしていく「タペリング」を行う
副作用を恐れて服薬を自己中断すると、TTPの病状が再燃する可能性があるため、医師の指示と説明をよく理解したうえで治療を続けることが重要です。
抗体製剤の副作用
リツキシマブなどの抗体製剤は、異常な自己抗体を産生するBリンパ球を減らす目的で使われます。
この治療は有効性が期待できる一方、投与時の点滴でアレルギー反応やインフュージョンリアクション(点滴速度に関連する副反応)が起こるリスクがあります。
また、長期的な免疫低下によって感染症にかかりやすくなる恐れもあるため、体調管理に注意が必要です。
抗体製剤で注意したい主な副作用
| 副作用の種類 | 内容 |
|---|---|
| インフュージョンリアクション | 点滴時の発熱、悪寒、発疹など |
| 免疫力の低下 | ウイルス・細菌感染症のリスク増大 |
| アレルギー反応 | 皮膚発疹、呼吸困難など |
血漿交換や輸血関連のリスク
血漿交換や輸血による治療では、感染症やアレルギー反応のリスク、血管穿刺時の出血や血栓形成のリスクなどがあり、また、血漿交換中は血液が体外に出るため、血行動態に影響が出て低血圧やめまいを感じることがあります。
血漿交換や輸血関連の治療を行うときに考慮したい点
- 清潔な環境を保ち、感染予防策を徹底する
- 設備の整った専門施設で治療を受ける
- 少しでも体調の異常を感じたら医師に伝える
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
血漿交換療法にかかる費用
血漿交換は特殊な装置を用いるため、1回あたりの治療費が比較的高額で、日本の医療保険制度の下で治療を受けた場合でも、自己負担額が1回につき数千円から数万円になることがあります。
| 治療回数 | 自己負担額の目安 (3割負担の場合) |
|---|---|
| 1回 | 約5,000~30,000円 |
| 10回 | 約50,000~300,000円 |
実際の費用は治療内容や病院によって違いがあり、事前に医療機関で確認するのが確実です。
ステロイドや免疫抑制剤の費用
ステロイドは比較的安価で入手しやすい薬剤ですが、高用量や長期投与になると薬剤費は徐々に増加し、免疫抑制剤や抗体製剤などを併用する場合は、1か月あたり数千円から数万円程度の自己負担額となることがあります。
特に抗体製剤は薬価が高額になりやすい傾向があり、使用頻度が多いほど負担が大きくなる点に留意が必要です。
| 治療薬 | 自己負担額の目安 (1か月あたり) |
|---|---|
| ステロイド | 数百円~数千円 |
| 免疫抑制剤 | 数千円~数万円 |
| 抗体製剤 | 数万円~数十万円 |
治療計画は医師が総合的に判断するため、費用負担と治療効果のバランスを考えながら薬を選択することになります。
検査・入院費用
TTPは診断の段階で血液検査やADAMTS13活性の検査を行い、入院して集中的な治療を受けることもあるため、検査費用や入院費用がかかることがあります。
検査費用の目安
- 血液検査:1回につき数百円~数千円
- 画像検査(CT、MRIなど):数千円~1万円程度
- 特殊検査(ADAMTS13活性など):数千円~数万円
以上
参考文献
Matsumoto M, Miyakawa Y, Kokame K, Ueda Y, Wada H, Higasa S, Yagi H, Ogawa Y, Sakai K, Miyata T, Morishita E. Diagnostic and treatment guidelines for thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) in Japan 2023. International Journal of Hematology. 2023 Nov;118(5):529-46.
Matsumoto M, Yagi H, Ishizashi H, Wada H, Fujimura Y. The Japanese experience with thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome. InSeminars in hematology 2004 Jan 1 (Vol. 41, No. 1, pp. 68-74). WB Saunders.
Matsumoto M, Bennett CL, Isonishi A, Qureshi Z, Hori Y, Hayakawa M, Yoshida Y, Yagi H, Fujimura Y. Acquired idiopathic ADAMTS13 activity deficient thrombotic thrombocytopenic purpura in a population from Japan. PLoS One. 2012 Mar 12;7(3):e33029.
Miyakawa Y, Imada K, Ichikawa S, Uchiyama H, Ueda Y, Yonezawa A, Fujitani S, Ogawa Y, Matsushita T, Asakura H, Nishio K. The efficacy and safety of caplacizumab in Japanese patients with immune-mediated thrombotic thrombocytopenic purpura: an open-label phase 2/3 study. International Journal of Hematology. 2023 Mar;117(3):366-77.
Sakai K, Wada H, Nakatsuka Y, Kubo M, Hayakawa M, Matsumoto M. Characteristics behaviors of coagulation and fibrinolysis markers in acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. Journal of Intensive Care Medicine. 2021 Apr;36(4):436-42.
Mori Y, Wada H, Tamaki S, Minami N, Shiku H, Ihara T, Omine M, Kakisita E. State-of-the-Art Review: Outcome of Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Hemolytic Uremic Syndrome in Japan. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 1999 Apr;5(2):110-2.
Joly BS, Coppo P, Veyradier A. Thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood, The Journal of the American Society of Hematology. 2017 May 25;129(21):2836-46.
Kremer Hovinga JA, Coppo P, Lämmle B, Moake JL, Miyata T, Vanhoorelbeke K. Thrombotic thrombocytopenic purpura. Nature reviews Disease primers. 2017 Apr 6;3(1):1-7.
George JN. Thrombotic thrombocytopenic purpura. New England Journal of Medicine. 2006 May 4;354(18):1927-35.
Lämmle B, Hovinga JK, Alberio L. Thrombotic thrombocytopenic purpura. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2005 Aug 1;3(8):1663-75.