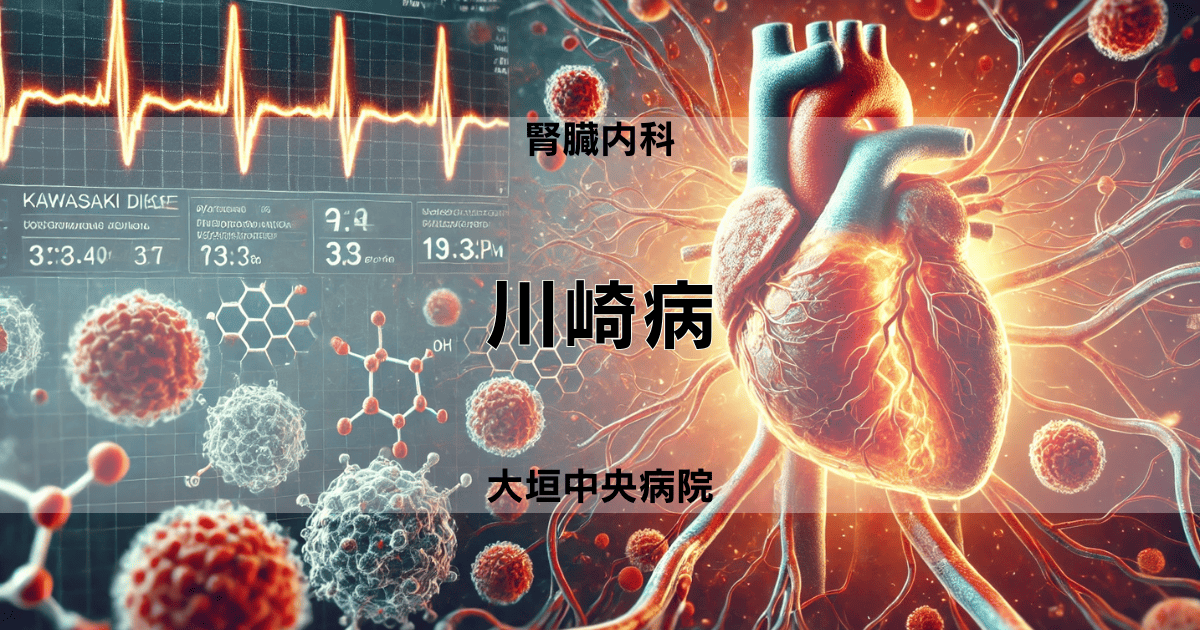川崎病とは、比較的幼い子どもに多く見られる炎症性の疾患で、全身の血管、特に冠動脈に影響を及ぼす可能性があり、対処を行わないと後遺症に悩むこともあるため注意が必要です。
子どもの発熱や発疹が続くときに川崎病を疑う場合があり、治療の遅れは心臓への負担につながります。
川崎病の病型
川崎病には全身の血管に炎症が生じる特徴があり、特に心臓の冠動脈に動脈瘤ができるリスクが知られています。病型は複数に分類されていて、主症状や経過などによって重症度が異なります。
典型的川崎病と不全型川崎病の違い
川崎病には、典型的川崎病と不全型川崎病という分類があり、典型的なものは、高熱や目の充血、口唇の発赤などの症状がはっきりと現れ、医師が診断しやすいパターンに当てはまることが多いです。
一方で不全型川崎病は、一部の症状がそろわないケースで、発熱のみが持続したり、特定の部位にのみ変化が出たりすることがあるので診断が遅れる可能性もあります。
不全型川崎病の例を挙げると、唇の発赤は見られず、発熱と発疹だけが続く場合や、手足の腫れがはっきりしないケースなどがあります。
典型的川崎病と不全型川崎病の主な特徴
| 分類 | 主な症状や特徴 | 診断の難しさ |
|---|---|---|
| 典型的川崎病 | 主要症状がすべて揃いやすい | 比較的判断しやすい |
| 不全型川崎病 | 主要症状の一部が欠けている場合が多い | 症状が揃わず難しい |
このように病型の違いによって診断の難易度も変わり、早期に医療機関を受診して医師の判断を仰ぐことが大切です。
全身型と冠動脈障害の有無
川崎病は全身の血管炎という性質をもちますが、特に心臓への影響が大きいことで知られていて、冠動脈瘤の有無を基準に、重症度が左右されることもあります。
治療開始が遅れたケースや治療がうまくいかなかったケースでは冠動脈に瘤が生じ、その後の心臓病のリスクにつながる可能性が高まります。
早めに免疫グロブリン治療などを行って炎症を抑えられれば、冠動脈瘤のリスクを下げることが可能です。
心臓エコーなどを用いて冠動脈の状態をチェックし、瘤が見られるかどうかを確かめます。
川崎病は炎症が全身に及ぶケースもあり、発疹や結膜充血、口腔内の症状などが目立つ場合もあれば、血液検査で炎症マーカーが高値を示す程度のときもあるため、個々の病状に合わせた対応が必要です。
病型ごとの経過と合併症
川崎病の経過は一般的に急性期、亜急性期、回復期のように区切れますが、病型ごとに合併症のリスクに違いがあります。
典型的な川崎病でも治療が遅れると冠動脈瘤の形成に至るリスクが上がり、不全型では症状が軽微である分見逃しが発生しやすく、気づいたときには既に冠動脈にダメージが及んでいる可能性があります。
また、発熱や発疹などの症状が軽くなると安心してしまうことがありますが、炎症が体内に残り続けるケースもあるため、自己判断で経過観察を打ち切るのではなく、医療機関を通じて細かくチェックすることが重要です。
川崎病の経過区分
| 区分 | 主な症状の推移 | 合併症の注意点 |
|---|---|---|
| 急性期 | 高熱、発疹、口唇の発赤、結膜充血などが強く出る | 炎症が急速に進むため早期発見・治療がカギ |
| 亜急性期 | 症状がやや落ち着き始めるが冠動脈瘤が形成されやすい | 心臓検査を丁寧に行い後遺症を防ぐ |
| 回復期 | 発熱や発疹が消退し、血液検査値も徐々に正常化 | 見た目の症状が消えるが後遺症の経過観察が重要 |
病型ごとに重視したいポイント
川崎病の病型を把握したうえで、治療や経過観察において重視すべきポイントは以下の通りです。
- 発熱や発疹など目立つ症状がなくなっても心臓の検査が必要
- 結膜充血や唇の赤みなど初期症状が見られずとも、不調が続けば受診を検討
- 血液検査での炎症反応や冠動脈エコーの状態を定期的に確認
- 不全型の場合、判断が難しいため小児科医や専門医の知見が役立つ
患者さんや保護者は病型に関する情報を知っておくことで、経過や治療内容に対して理解を深められ、医師とのコミュニケーションもスムーズになります。
病型に関して気をつけたい点
- 症状が全て揃わない不全型では発見が遅れやすい
- 血管炎が落ち着いても冠動脈のダメージを見逃さない
- 後遺症のリスクは主に冠動脈瘤の有無に影響を受ける
川崎病の症状
川崎病は子どもの全身に炎症が及ぶ病気ですので、発熱だけでなく皮膚や目、口唇、手足など複数の部位に症状が出現する可能性があります。よく見られる典型症状を理解しておくと、早めの判断と受診につながりやすくなります。
高熱とその特徴
川崎病では、39度前後の高熱が5日以上続くことが多く、解熱剤を用いても下がりにくいという特徴があります。高熱に伴い子どもがぐったりして食欲が落ちたり、水分摂取が難しくなったりすることで、脱水を引き起こすリスクも高まります。
熱がなかなか下がらない場合、単なる風邪やインフルエンザとは異なる疾患を疑う機会となるため、体温を細かく記録したり、症状の変化を確認したりすることが大切です。
川崎病と発熱の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発熱の程度 | 39度前後まで上昇 |
| 発熱の持続期間 | 5日以上続く場合が多い |
| 解熱剤の効果 | 効果が限定的で下がりにくい傾向 |
高熱があることで眠れずに体力を消耗しやすく、二次的な合併症を招く恐れもあるため、早期の受診やケアが欠かせません。
目の充血や口唇の発赤
川崎病では結膜の充血が生じやすく、白目の部分が真っ赤になる場合があり、眼の痛みや視力低下を伴うことはあまりありませんが、不快感を訴えることがあります。
また、唇の赤みや乾燥、ひび割れ、イチゴ舌と呼ばれるベロの赤みも典型的な症状で、こうした症状は通常の風邪ではあまり見られない特徴でもあるため、医師が初期診断の際に重要視するポイントです。
目や口の症状は、炎症による血管拡張や粘膜の変化により起こると考えられていて、過度な乾燥やこすり過ぎは症状を悪化させる可能性があるので、ケアを行う際には刺激を与えすぎないように注意が必要です。
目や口の症状で注意したいこと
- 充血が両目同時に生じるケースが多い
- 口唇がひび割れて出血しやすい場合もある
- 舌が赤くぶつぶつになるイチゴ舌に注目
手足の腫れや皮膚の変化
川崎病の特徴的な皮膚症状として、手足のむくみや指先・足先の皮膚が赤く腫れることがあり、さらに、病状が進むと指先や足先の皮がむけてくる場合もあり、この脱皮のような現象が一連の病態の中で起こります。
こうした皮膚の変化は、病気の経過を追ううえで目安になり、特に亜急性期から回復期にかけて見られるものです。
全身に発疹が出現することもあり、顔や胸、背中などに赤みが広がります。かゆみを伴うこともあれば、痛みや熱感を感じることもあるため無理にかいたり刺激したりしないように注意が必要です。
川崎病の皮膚症状の時期と特徴
| 時期 | 主な症状 | 注意点 |
|---|---|---|
| 急性期 | 手足の軽度の腫れや発赤 | 炎症が強まると腫れが悪化 |
| 亜急性期 | 指先や足先の皮むけが見られる | 皮膚がむけ始めてトラブルも |
| 回復期 | 発疹や腫れが改善傾向にある | 痕が残らないか確認 |
首のリンパ節腫脹
川崎病の特徴のひとつに、首周りのリンパ節が腫れることがあります。一般的に、風邪や溶連菌感染などでもリンパ節の腫れが起こる可能性はありますが、川崎病では片側の大きなリンパ節腫脹が見られることが多いです
。痛みを伴うこともあり、首が動かしにくかったり寝返りで痛みを訴えたりする場合があります。
リンパ節の腫れは全身的な炎症反応を示すサインの一つなので、熱や発疹、結膜充血などの症状とあわせて鑑別することが重要です。
こうした複数の症状が組み合わさったときには川崎病を強く疑い、血液検査や心臓の検査を受ける必要が出てきます。
原因
川崎病の原因については未解明な部分が残されており、ウイルスや細菌など感染症との関連、遺伝的素因、免疫反応など、さまざまな仮説が検討されています。
1つの要因だけでなく、複数の要因が組み合わさって川崎病の発症に至っていると考える見解もあります。
免疫反応との関連
川崎病では全身の血管に炎症が起こるため、自己免疫反応が関係しているのではないかと指摘されていて、免疫システムが何らかの異常を起こし、血管の内壁にダメージを与えている可能性があります。
ウイルスや細菌に感染したあとに川崎病を発症する例もあるため、感染をきっかけに免疫反応が暴走するケースも考えられます。
ただし、原因病原体が特定されているわけではなく、インフルエンザや溶連菌などの特定の微生物と決定的に関連しているという証拠は見つかっていないため、あくまでも多因子性の疾患として捉えるのが一般的です。
川崎病と免疫反応の関係
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 炎症の中心 | 血管壁への炎症 |
| 免疫のかかわり | 自己免疫反応の過剰活性化の可能性 |
| 感染との関連 | ウイルスや細菌による誘因が仮説として検討される |
遺伝素因の影響
同じ家族内で川崎病が発症するケースが報告されており、遺伝的な要因も無視できないと考えられていますが、明確な遺伝パターンがあるわけではなく、特定の遺伝子だけが強く関与しているわけでもないようです。
一部の人が川崎病を発症しやすい体質を持っている可能性は指摘されていますが、感染や環境要因なども絡んで発症に至るため、遺伝だけを原因として断定するのは難しいです。
遺伝素因に関するポイント
- 家族内発症の報告が少数ながら存在
- 特定の民族や人種に多いわけではない
- 遺伝だけでなく環境因子との相互作用が考えられる
環境要因と発症時期
川崎病は冬から春先にかけてや、夏場などに集中的に患者数が増える傾向があるとの報告もあり、これは、ウイルスなどの感染流行や気温・湿度の変化が関連しているのではないかと推察されています。
また、都市部に多いという説もあり、人の集まりやすい環境が発症リスクを高めているのではないかという見方があります。
しかし、明確に「この環境要因があるから川崎病が発症する」という因果関係は示されていません。大規模調査によってさまざまな要因が考えられるものの、未解明な部分が多いのが現状です。
実際の研究動向
川崎病の原因究明に向けて国内外で盛んに研究が行われており、病原体や免疫のメカニズム、遺伝的背景など多角的に調べられています。
発症メカニズムをより明確にできれば、川崎病の予防や治療法のさらなる進歩にもつながると期待されています
。ただし、現時点では特定のウイルスや細菌を主要因として断定するだけのエビデンスはないため、総合的な要因の積み重ねが川崎病を引き起こすと考えるのが妥当です。
検査・チェック方法
川崎病の診断には、症状の確認や血液検査、画像検査などを組み合わせて総合的に判断し、特に冠動脈への影響を評価するために、心臓エコー検査が欠かせない手段です。
問診と身体診察
医師は症状の経過を詳しく聞き取り、発熱の程度や期間、発疹の有無、目の充血、口唇の状態、首のリンパ節の腫れ、手足の腫れなどを総合的に判断します。
問診で確認する主な内容
- 発熱の開始日と体温の最高値
- 発疹や口唇の変化などの初発症状
- 結膜充血の有無と程度
- 食欲や元気の程度
血液検査
川崎病が疑われた場合には、白血球数、CRP(C反応性タンパク)などの炎症指標、血小板数などを測定して、体内の炎症レベルを把握し、急性期には白血球や血小板が増加し、CRPも高値になるケースが多いです。
さらに、肝機能や腎機能のチェック、血清アルブミン値の確認など、多角的な血液検査を行うことで、全身状態の把握に努めます。
川崎病に関連する主な血液検査項目
| 検査項目 | 意味・目的 | 川崎病での変化 |
|---|---|---|
| 白血球数 | 炎症や感染の指標 | 急性期に増加 |
| 血小板数 | 血液凝固や炎症状態の把握 | 急性期から回復期に増加 |
| CRP | 炎症の活動性を示す | 高値を示しやすい |
| ALB(アルブミン) | 栄養状態や炎症を反映 | 低下することがある |
画像検査(心エコー)
川崎病の重大な合併症として冠動脈瘤の形成が挙げられるため、心臓エコー(超音波検査)は診断と経過観察において非常に重要です。
心エコーを用いると冠動脈の拡張や瘤の有無を調べることができ、治療効果の評価や後遺症のリスク判定に役立ちます。検査自体は痛みがなく、小児でも実施しやすい方法です。
また、必要に応じて心電図検査や胸部X線撮影、MRIなどを行い、冠動脈以外の心臓や肺の状態を確認することもあり症状の、重症度によっては、より詳細な画像検査を実施して全身の状態を把握する場合もあります。
尿検査・その他
血液検査と並行して、尿のたんぱくや潜血、比重などを確認し、腎臓への影響を調べることがあり、全身性の炎症が起こっているため、他の臓器機能に異常が出ていないかどうかを多面的にチェックすることが大切です。
稀ですが、脳脊髄液検査が必要なケースもあり、髄膜炎様の症状を呈する場合や合併症が疑われる場合には専門的な検査を追加します。
川崎病の治療方法と治療薬について
川崎病の治療は、早期に炎症を抑えて冠動脈瘤などの合併症を予防することが狙いです。代表的な治療に免疫グロブリン療法(IVIG)やアスピリンの投与があり、重症度や個々の反応に応じて調整を行います。
免疫グロブリン療法(IVIG)
免疫グロブリンは人の血液から取り出した成分で、投与によって体内の過剰な免疫反応を抑制し、血管の炎症を軽減します。急性期に大量の免疫グロブリンを点滴で投与することで、冠動脈へのダメージを最小限に抑える可能性が高まります。
投与は数日間にわたって行うケースが多く、副作用として発熱や発疹、アレルギー反応がまれに起こることがありますが、医療機関で慎重に観察しながら治療を進めるため、重大な事故は比較的少ないです。
免疫グロブリン療法の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投与経路 | 点滴静注(IVIG) |
| 効果発現 | 投与後早期に炎症が鎮まることが多い |
| 主な副作用 | 発疹、アナフィラキシー反応、発熱など |
アスピリン投与
川崎病では血小板の増加や炎症による血管内皮のダメージが生じ、血栓ができやすい状態になることがあります。アスピリンは抗炎症作用と抗血小板作用を持つ薬剤で、川崎病の急性期から回復期にかけて使用されます。
急性期には高用量で抗炎症作用を狙い、症状が落ち着いてきたら用量を低めに調整して血栓予防を図ることが一般的です。
ただし、アスピリンは胃腸への負担や、まれにライ症候群という重篤な副作用が報告される可能性があるため、用量や使用期間を医師が細心の注意を払って管理します。
アスピリン使用時の留意点
- 胃腸への刺激があるため食後の服用が望ましい
- インフルエンザなど他のウイルス感染症との併発に注意
- 医師の指示を守って適切な用量を継続
ステロイド療法や追加治療
免疫グロブリン療法を行っても熱や炎症が治まらない難治性川崎病の場合、ステロイドの併用や追加の免疫グロブリン投与を検討することがあります。
ステロイドは強い抗炎症作用を持つ薬剤ですが、副作用のリスクもあるため、慎重に投与を行うことが重要です。
また、重症化が疑われるケースでは、血漿交換療法などの特別な治療を行う場合もあり、専門医の判断に基づいてさまざまなアプローチが試みられます。
冠動脈拡張術や外科的治療
冠動脈瘤が大きくなり、血流障害が起きるリスクが高い場合には、冠動脈拡張術やバイパス手術が検討されることがあります。これはごく一部の重症例に限られますが、川崎病による後遺症で狭窄や閉塞が見られるときに行われます。
川崎病の治療期間
川崎病は早期に治療を開始できれば、比較的短期間で急性期の症状が落ち着く場合が多いですが、冠動脈への影響などによっては長期の経過観察が必要になることもあります。
急性期と亜急性期の治療
急性期の高熱や強い炎症症状が続く期間はおおむね1週間程度とされており、この間に免疫グロブリン療法や高用量アスピリン投与を行います。
症状が落ち着けば亜急性期へ移行しますが、この時期は冠動脈瘤が形成されやすいタイミングでもあるため、冠動脈エコーなどで状態をこまめに確認します。
治療効果が順調に出ていれば、発熱が治まり、血液検査の数値も回復に向かい始めますが、炎症が残っているときや冠動脈に異常が認められるときには追加治療が必要です。
急性期と亜急性期の概要
| 区分 | 期間の目安 | 主な治療 |
|---|---|---|
| 急性期 | 発熱開始から約1週間 | 免疫グロブリン療法、高用量アスピリン |
| 亜急性期 | 1週間以降~数週間 | 冠動脈瘤の有無をチェック、薬用量調整 |
回復期からの経過観察
回復期はおよそ1か月前後にわたって続き、症状がほぼ治まった後も冠動脈の状態を定期的に確認します。
アスピリンは低用量に切り替えて血栓予防を続けることが多く、血液検査や心エコーの結果を見ながら段階的に薬を減らしていくことがあります。
この段階で特に問題がなければ、外来通院の頻度も少しずつ減らし、日常生活へ復帰します。
回復期に重視したいこと
- 体力の回復と十分な睡眠・栄養補給
- 心エコーや血液検査による冠動脈瘤のチェック
- 医師の許可が出るまでは激しい運動を避ける
長期フォローアップ
川崎病の後遺症として、冠動脈瘤が形成されてしまった場合や、軽度の拡張が残っているケースでは、長期にわたって循環器のフォローアップを受ける必要が出てきます。
冠動脈瘤の大きさによっては、スポーツ活動の制限や生活習慣の注意が求められることがあるため、医師の指導に従って定期的な検査を受けることが大切です。
症状が完全に落ち着いて冠動脈にも問題がないと診断されれば、特別な制限は少なくなりますが、成長期に心臓に大きな負担がかかる運動をする際は注意が必要です。
治療期間の目安と実情
川崎病の治療は数週間から1か月程度が目安になりますが、重症度や個人差によって前後します。冠動脈瘤のリスクが高い方は長期通院が必要になり、一方で早期発見と治療が奏功して後遺症も残らず回復するケースも少なくありません。
保護者は医師と密に連絡を取りながら、入院期間や通院スケジュールを調整していくことが大切です。
川崎病薬の副作用や治療のデメリットについて
川崎病の治療で使われる主な薬剤として、免疫グロブリン(IVIG)やアスピリン、ステロイドなどが挙げられますが、これらに伴う副作用や治療を行う上でのデメリットもあります。
免疫グロブリン(IVIG)の副作用
IVIGは血液製剤であるため、アレルギー反応や発熱、頭痛、発疹などの副作用がまれに見られます。
治療中は医療スタッフが体温や血圧、呼吸状態などを細かく確認し、副作用が起こった場合には点滴速度を調整したり、一時的に中断したりして対処します。
重大な副作用は少ないですが、完全にゼロではないため、医療機関での監視下で治療を進めることが必要です。
IVIGの主な副作用と対処法
| 副作用 | 具体的症状 | 対応方法 |
|---|---|---|
| アレルギー反応 | 皮膚のかゆみ、発疹、呼吸困難など | 点滴速度を落とす、中断、抗アレルギー薬の投与 |
| 発熱や頭痛 | 体温上昇、頭痛、倦怠感 | 解熱鎮痛薬の投与、経過観察 |
アスピリンの副作用
アスピリンには抗炎症作用と抗血小板作用がある一方で、胃腸障害やまれにライ症候群を引き起こす可能性があります。
胃が荒れやすくなるため、吐き気や嘔吐、胃痛を訴えることがあり、場合によっては内服を一時中断したり、用量を減らしたりすることがあります。
また、インフルエンザなどのウイルス感染症と併発するときは、アスピリンの使用を慎重に判断しなければなりません。
アスピリンの副作用リスク
- 胃潰瘍や胃腸障害
- ライ症候群(極めてまれ)
- 出血傾向の増大
ステロイド使用のリスク
難治性川崎病や重症化が疑われるケースでステロイドを併用する場合がありますが、ステロイドには感染症にかかりやすくなる、血圧や血糖値が上昇しやすいなどのリスクがあります。
短期間の使用がほとんどで、医師が注意深く管理しますが、長期化すると骨の弱化や成長への影響が出る可能性もあるため、メリットとデメリットを天秤にかけて判断することが大切です。
川崎病の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
免疫グロブリン(IVIG)の費用
川崎病における免疫グロブリン療法は、基本的に保険適用の範囲内で実施されますが、IVIGそのものが高額な治療薬であるため、自己負担割合(小児医療制度による減免がある場合も含む)によっては高めの費用が生じる可能性があります。
大規模病院などで入院してIVIGを数日間受けるケースでは、薬剤費や点滴費用、入院費などを合わせて数万円から十数万円程度になることが多いです。
IVIGに関する治療費の目安(保険適用後)
| 治療内容 | 費用の目安 | コメント |
|---|---|---|
| IVIG薬剤費 | 数万円~ | 体重による投与量で変動 |
| 点滴や管理費 | 数千円~数万円 | 入院日数により変動 |
アスピリンやその他内服薬
アスピリンやその他の内服薬に関しては、保険診療内での処方となり、一般的な自己負担額で済むケースがほとんどで、小児用アスピリンの場合、金額自体は安価で、数百円から千円程度に収まることが多いです。
アスピリンなどの費用の目安
- アスピリン:数百円程度
- 抗アレルギー薬や胃薬:合計で1,000~2,000円程度
- 用量や薬剤の組み合わせによって変動
検査費用
川崎病の診断や経過観察のために行う血液検査や心エコー、X線検査なども保険適用です。血液検査は数千円程度、心エコー検査は複数回行う場合があるため、1回あたり数千円から1万円程度の自己負担が発生することがあります。
検査費用の目安(保険適用後)
| 検査項目 | 1回あたりの費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 血液検査 | 数千円 | 検査項目数で変動 |
| 心エコー | 数千円~1万円程度 | 施設や検査の詳細内容で変動 |
| X線検査 | 数千円程度 | 胸部X線、心臓の大きさや肺の状態を確認 |
入院費用の総額
川崎病の初期治療では入院を必要とするケースが少なくありません。入院中は治療薬や検査、管理費用などがまとめて請求され、1週間から10日程度の入院であれば、自己負担割合によっては総額で10万円~20万円程度です。
実際の費用は病院の規模や差額ベッドの利用状況、個室料金などで差があります。子どもの医療費助成制度が適用される場合もあるので、保護者はお住まいの自治体の制度を確認し、担当部署に問い合わせるとよいでしょう。
以上
参考文献
Burns JC, Kushner HI, Bastian JF, Shike H, Shimizu C, Matsubara T, Turner CL. Kawasaki disease: a brief history. Pediatrics. 2000 Aug 1;106(2):e27-.
Makino N, Nakamura Y, Yashiro M, Sano T, Ae R, Kosami K, Kojo T, Aoyama Y, Kotani K, Yanagawa H. Epidemiological observations of Kawasaki disease in Japan, 2013–2014. Pediatrics International. 2018 Jun;60(6):581-7.
Fujita Y, Nakamura Y, Sakata K, Hara N, Kobayashi M, Nagai M, Yanagawa H, Kawasaki T. Kawasaki disease in families. Pediatrics. 1989 Oct 1;84(4):666-9.
Uehara R, Belay ED. Epidemiology of kawasaki disease in Asia, Europe, and the United States. Journal of epidemiology. 2012 Mar 5;22(2):79-85.
Harnden A, Takahashi M, Burgner D. Kawasaki disease. Bmj. 2009 May 5;338.
Nakamura Y, Yashiro M, Uehara R, Oki I, Kayaba K, Yanagawa H. Increasing incidence of Kawasaki disease in Japan: nationwide survey. Pediatrics International. 2008 Jun;50(3):287-90.
Maddox RA, Holman RC, Uehara R, Callinan LS, Guest JL, Schonberger LB, Nakamura Y, Yashiro M, Belay ED. Recurrent Kawasaki disease: USA and Japan. Pediatrics International. 2015 Dec;57(6):1116-20.
Hirata S, Nakamura Y, Yanagawa H. Incidence rate of recurrent Kawasaki disease and related risk factors: from the results of nationwide surveys of Kawasaki disease in Japan. Acta paediatrica. 2001 Jan;90(1):40-4.
Yanagawa H, Kawasaki T, Shigematsu I. Nationwide survey on Kawasaki disease in Japan. Pediatrics. 1987 Jul 1;80(1):58-62.
Rowley AH, Shulman ST. The epidemiology and pathogenesis of Kawasaki disease. Frontiers in pediatrics. 2018 Dec 11;6:374.