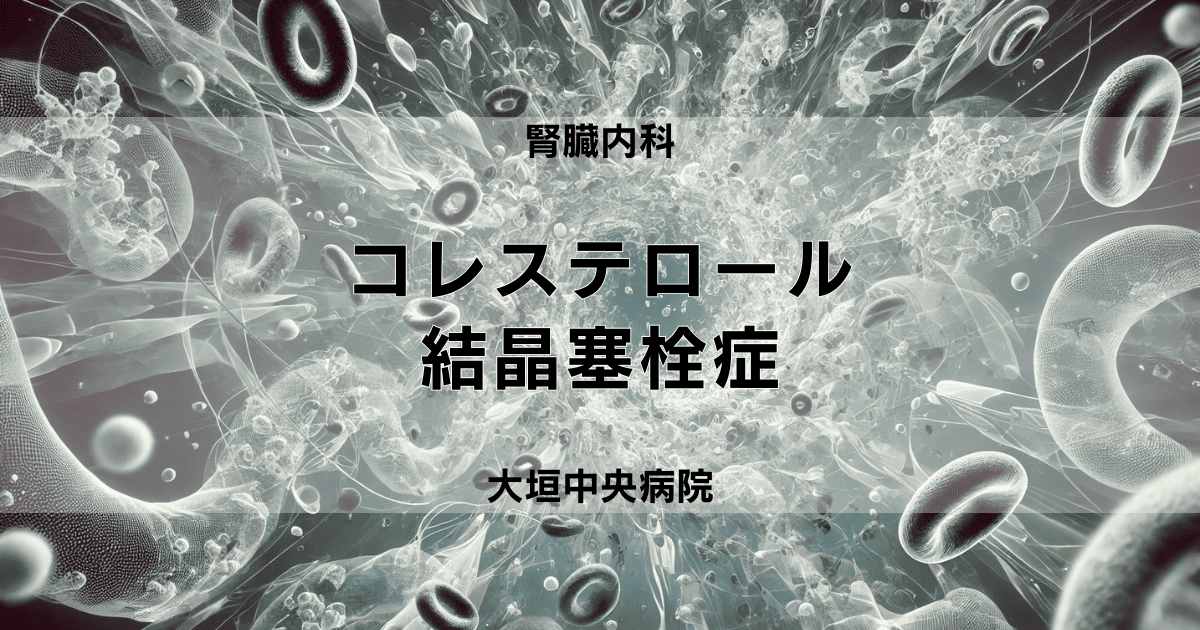コレステロール結晶塞栓症とは、血液中にあるコレステロールの結晶片が何らかのきっかけで血管内に飛び出し、末梢の細い血管をふさいでしまうことで多様な臓器障害を起こす病気の総称です。
動脈硬化が進んだ血管壁から結晶が剥がれる場合もあり、目立った症状がないままじわじわと進行することもあるため、早めに正確な知識を得て適切な医療につなげることが大切になります。
病型
コレステロール結晶塞栓症は、動脈硬化によって生じたコレステロール結晶が血流に乗り、全身のさまざまな部位の小動脈に詰まることで症状を呈し、血管のどの部分に影響が及ぶかによって、症状や経過の仕方が異なります。
動脈硬化性プラーク由来型
動脈硬化が強い大動脈や主要な中枢動脈から、コレステロール結晶の小片が剥離して末梢血管に入り込み、その部位で閉塞を引き起こす型です。
心臓カテーテル検査や血管内手術などで血管が刺激され、プラークが破綻することが契機となる場合があり、高齢者や喫煙歴が長い方に多くみられやすい傾向があります。
主な病型に関するポイント
- 大動脈由来プラークの破綻に伴って結晶が流出しやすい
- 腎臓、皮膚、消化管など多様な臓器を侵す可能性がある
- 動脈硬化を背景に持つ人ほど注意が必要
- カテーテル検査や外科的介入後に症状が顕在化しやすい
動脈硬化性プラーク由来型に関連しやすい要素
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 動脈硬化リスク | 喫煙、高血圧、糖尿病、高LDLコレステロール血症などの危険因子 |
| カテーテル操作の影響 | 血管壁への機械的刺激によってプラークや結晶が剥離する可能性 |
| 関係する臓器・部位 | 腎臓、皮膚、下肢末梢動脈、消化管など幅広い部位 |
| 経過の特徴 | 比較的ゆっくりと病状が進むことが多いが、急激に進むこともあり臓器障害を引き起こしやすい |
腎障害を伴う型
コレステロール結晶塞栓症のなかでも腎臓の小動脈を狙ったように詰まらせてしまい、急性あるいは慢性の腎不全を招く例があり、血清クレアチニン値の上昇やタンパク尿によって発見されることが多いです。
腎臓が障害されると、全身の状態や血圧のコントロールにも影響が及ぶため、慎重なフォローが必要になります。
皮膚病変を主体とする型
皮膚の末梢小動脈が詰まり、青紫色の網目状皮斑や潰瘍などの病変を生じるタイプで、急性期には網状皮斑や皮膚の壊死、慢性期には潰瘍形成や痛みを伴ってくることがあります。
足先や下肢から発症し、複数箇所に広がる場合もあるため、早期の観察と適切な対応が大切です。
| 観察ポイント | 注意すべき症状・状態 |
|---|---|
| 皮膚の色調 | 網状の青紫色斑、赤黒い変化 |
| 皮膚の温度変化 | 詰まった部位の冷感や虚血による温度低下 |
| 潰瘍の有無 | 血流障害が重度の場合に壊死や潰瘍へ進行する可能性 |
| 痛みの程度 | 虚血による鋭い痛みや持続的な不快感 |
消化管病変を中心とする型
結晶が消化管の小動脈に詰まり、腹痛や下血、栄養吸収障害などが起こされるタイプで、見過ごされがちな腹部不快感や食欲不振が続き、検査を行うと血管内のコレステロール結晶塞栓が発覚することがあります。
消化管壁に生じた虚血によって潰瘍や穿孔が生じ、深刻な合併症につながることもあるため注意が必要です。
コレステロール結晶塞栓症の症状
この病気は、詰まる血管の部位や範囲によって症状に多彩なバリエーションがあり、特定の症状だけから診断を確定するのは難しい場合があり、些細なサインを見落とさず、総合的に判断することが重要です。
腎障害や皮膚症状にとどまらず、全身に影響が及ぶ可能性がある点を理解する必要があります。
腎機能低下に伴う症状
コレステロール結晶塞栓症で腎機能が低下すると、全身倦怠感やむくみ、血圧の変動などが生じやすくなります。
特にクレアチニン値が急に上昇し、透析が必要になるケースもあるため、早期の血液検査や尿検査を実施して変化を捉えることが大切です。
腎臓に関連した症状
- 朝起きたときのまぶたや足のむくみ
- 排尿量の変化(特に夜間頻尿や排尿回数の減少)
- 血圧の変動(特に急激な上昇)
- 全身のだるさや疲労感
腎障害は進行性の場合があり、日常生活の質を大きく損ないやすいため、早い段階で医師の診察を受ける意義が大きいです。
皮膚症状と肢端の違和感
皮膚に網状の青紫色斑が出現することや、足先が冷たく感じられることが多く、中には、しびれや疼痛を訴える方もおり、それをきっかけに血液検査や血行動態の評価に踏み出すケースが少なくありません。
皮膚症状は見た目でも把握しやすいため、病気の早期発見に役立つ一方で、糖尿病など別の原因による末梢循環障害との鑑別が必要になることがあります。
代表的な皮膚症状や下肢症状
| 症状 | 主な特徴 |
|---|---|
| 網状皮斑 | 紫や青色の網目状斑で、冷感や痛みを伴うこともある |
| 潰瘍形成 | 慢性的な血流不足により皮膚が壊死、潰瘍化する |
| しびれや感覚低下 | 血管の閉塞や神経への影響による可能性 |
| 足の冷感 | 血行障害で温度が下がり、末端部が冷える |
消化器症状と全身倦怠感
ときに、腹痛や下痢、食欲不振といった消化器症状からコレステロール結晶塞栓症が疑われるケースもあります。
血流障害によって消化管壁が虚血状態に陥ると、栄養の吸収不良を伴うことがあり、体重減少や倦怠感が続き、さらに下血を起こす場合は、すぐに医療機関へ相談することが大切です。
眼や脳への影響
あまり頻度は高くありませんが、網膜の小動脈が詰まって網膜障害を招き、視力低下や視野欠損を起こすケースも報告されています。
また、脳の小動脈に詰まれば、一過性脳虚血発作や脳梗塞のような症状が出ることもあり、手足の麻痺や言語障害が突然出現した場合には、早急な診断と治療が必要です。
コレステロール結晶塞栓症の原因
コレステロール結晶塞栓症は、主に動脈硬化病変を背景として結晶が血中に飛び出し、さまざまな部位の末梢血管をふさぐことで発生します。
血管内カテーテル操作や手術後に生じることが多く、体内に蓄積されたコレステロールの状態や血管の脆弱性も大きく影響します。
動脈硬化とプラーク破綻
血管壁にプラークと呼ばれるコレステロールを含む塊が形成されると、内側から血管が狭くなるだけでなく、プラークの表面が傷つくと内容物の結晶が血中に飛び散ります。
高血圧や高LDLコレステロール血症、喫煙などが動脈硬化を促進する代表的な要因で、血管外科手術や心臓カテーテルなどで物理的に血管を刺激することで、プラークが破綻しやすくなります。
動脈硬化を進行させやすい代表的な生活習慣や疾患
- 喫煙習慣
- 脂質異常症(特にLDLコレステロールの上昇)
- 高血圧
- 糖尿病
動脈硬化が顕在化すると、血管の内側が硬く脆くなり、小さな刺激でもプラークから結晶が剥がれる危険性が高まり、とりわけ、加齢やその他の基礎疾患を持つ人では注意が必要です。
手術やカテーテル検査後の発症
心臓カテーテル検査や大動脈瘤の手術などで血管内に器具を挿入するときに、動脈壁が傷つきやすくなり、プラークがある部位に器具が触れたり、血管を拡張したりすることで、コレステロール結晶が遊離してしまうことがあります。
大動脈や腎動脈の強い動脈硬化を持つ方の場合、検査や手術が終了した直後から数週間以上経ってから症状が現れることもあるため、長期的な経過観察が大切です。
コレステロール結晶塞栓症が起こりやすい要因
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 術前の動脈硬化の程度 | プラークが多いほど結晶剥離のリスクが高い |
| 術式の種類 | 大動脈の操作を伴う手術、ステント留置など血管内操作がある場合に多い |
| 術後の管理体制 | 血圧コントロールや抗血小板薬の使用など継続治療の管理が不十分だとリスク増 |
| 患者の基礎疾患および年齢 | 高齢者、糖尿病、慢性腎臓病などを持つ人ほど注意が必要 |
血管の脆弱化要因
体質的に血管が脆い方や長年の生活習慣病によって血管の内皮機能が低下している場合、わずかな機械的刺激でもプラークが破綻しやすい状態になります。
炎症性疾患や免疫異常などで血管壁の保護機能が損なわれている場合も、コレステロール結晶塞栓症の発症に関与することがあります。
未知の要因や複合要因
すべてのケースにおいて、はっきりと「これが原因だ」と特定できるわけではありません。
複数の要因が複雑に絡み合って発症に至るケースもあり、動脈硬化以外の血管病変や凝固異常などが背景に潜んでいることも考えられるため、診断においては総合的な評価が大事です。
検査・チェック方法
この病気を疑った場合、原因検索と重症度評価を同時に行うことが必要で、症状の多彩さゆえ、単一の検査だけで診断確定できるわけではなく、複数の検査を組み合わせることが通例です。
血液検査と尿検査
血液検査では、炎症を示すCRPの上昇や好酸球増多、腎機能を評価するクレアチニン値や尿素窒素(BUN)の変化を観察します。
コレステロール結晶塞栓症では、好酸球が増えるケースが比較的多いとされ、尿検査でも尿中に蛋白や潜血が確認される場合があり、変化がみられると、腎障害や全身性の炎症反応が疑われるため、さらなる精密検査のきっかけとなります。
初期段階でよく行う血液検査の項目
- 好酸球数(増加しているかどうか)
- クレアチニン値、BUN(腎機能評価)
- CRP値(炎症の指標)
- 脂質プロファイル(LDL、HDL、トリグリセリド)
血液と尿の双方の結果を照らし合わせ、腎臓に異常があるのか、全身性の炎症がどの程度かといった情報を総合的に判断します。
画像診断
症状の部位や疑われる病型に応じて、CTやMRIなどの画像検査を行い、腹部CTや造影MRIによって、腎臓や消化管などの血流状態や虚血の有無を確認します。
大動脈に動脈硬化性プラークが多い場合、エコー(超音波)やCTでその状態を把握し、危険因子の程度を推測でき、また、心臓カテーテル検査の追加評価が検討されることもあります。
画像診断で着目する主なポイント
| 検査方法 | 着目するポイント |
|---|---|
| CT検査 | 腎動脈や大動脈のプラーク、臓器の虚血状態の確認 |
| MRI検査 | 消化管や脳・脊髄などの血管変化、臓器の炎症所見の評価 |
| 超音波検査 | 大動脈壁のプラーク評価、腎臓のサイズや血流を把握 |
| 血管造影検査 | 小動脈レベルの血流障害や塞栓部位を詳細に確認する |
組織生検
皮膚症状や腎障害が顕著なときに行われることがあるのが、生検による組織学的検査で、皮膚生検や腎生検で、血管内にコレステロール結晶が存在しているかを直接確認します。
この方法は侵襲的な検査ではありますが、診断の確定に非常に有用な手段です。組織学的に結晶の二重屈折像などが見られれば、コレステロール結晶塞栓症であることがはっきりします。
病歴や生活習慣の詳細確認
検査だけでなく、患者の病歴や生活習慣について聞き取り、動脈硬化のリスクがどれだけあったのかを確認し、過去に心臓や血管の手術、カテーテル検査を受けたかどうか、喫煙歴があるかどうかなど、あらゆる情報が診断の手助けです。
医師との対話で、思わぬところから発症リスクの糸口が見つかるケースもあります。
コレステロール結晶塞栓症の治療方法と治療薬について
コレステロール結晶塞栓症の治療は、原因となる動脈硬化への対応を含む全身管理と、実際に障害を受けた臓器に応じた対症療法の組み合わせが中心です。
薬物療法
ステロイド薬(副腎皮質ステロイド)は炎症を抑える目的で用いられ、特に皮膚症状が強い場合や腎臓の炎症が顕著な場合、ステロイド薬による病勢コントロールが図られることが多いです。
高脂血症の改善を目的としてスタチン系薬剤が処方されることもありますが、すでに血管内に飛び出しているコレステロール結晶自体を溶解させる効果は限定的です。
高血圧がある場合は降圧薬、血小板凝集を抑制するために抗血小板薬が併用される場合もあり、総合的な内科的治療となります。
使用される代表的な薬剤
| 薬剤群 | 目的や作用機序 |
|---|---|
| 副腎皮質ステロイド | 強い抗炎症作用。病変部の炎症や免疫反応を抑える |
| スタチン系薬剤 | LDLコレステロールの合成を抑制し、動脈硬化の進行を抑える |
| 抗血小板薬 | 血小板の凝集を抑制し、追加的な血管閉塞を予防する |
| 降圧薬 | 高血圧をコントロールし、血管への負荷を減らす |
外科的・血管内治療
コレステロール結晶塞栓が大動脈瘤などの明らかな病変部位から生じている場合、その病変の外科的修復や血管内治療(ステントグラフト留置など)を検討することがあります。
ただし、既に全身に飛び散った結晶を取り除くことは困難であり、主に再発予防を目的とした処置が中心で、術後には、さらにプラークや結晶が剥離しないよう注意深い管理が必要です。
補助療法や対症療法
腎不全が進行した場合は、透析治療が必要になるケースもあり、皮膚潰瘍があれば、創傷ケアや感染管理が重要です。
消化管病変がある場合は、栄養状態を保つためのサポートが必要になるなど、各症状に合わせたケアが加わり、痛みが強いときは鎮痛薬を使用し、日常生活の質を維持する工夫が行われます。
生活習慣の見直し
薬物療法や外科的治療と並行して、患者さん自身が生活習慣を見直すことが重要です。喫煙の中止や食事内容の改善(塩分・コレステロールの摂取バランスを考慮する)、適度な運動など、基本的な生活習慣の修正が求められます。
- 禁煙(喫煙は動脈硬化リスクを高める大きな要因)
- 適度な有酸素運動(ウォーキングや軽いジョギングなど)
- 血圧・血糖管理(高血圧や糖尿病がある場合は特に注意)
- バランスの良い食事(コレステロールや塩分の摂取に留意)
治療期間
治療期間は、どの程度臓器障害が進んでいるかや再発リスクの大きさによって大きく異なり、数週間から数カ月で病勢が落ち着く場合もあれば、腎不全などが進行して長期的に治療を要することもあります。
急性期治療から慢性期管理への移行
急性期には、炎症を抑える薬物療法や臓器機能のサポートが中心となり、症状が落ち着いてきた段階で、再発予防や合併症対策に重点を移します。
急性期の治療には数週間~数カ月を要することがあり、その後も定期的な検査や通院で経過観察を続ける形です。
急性期と慢性期に着目した治療およびケア
| 時期 | 主な治療・ケア内容 |
|---|---|
| 急性期 | ステロイドなどの抗炎症薬、血管内治療や透析などの臓器サポート |
| 慢性期 | 再発防止のための薬物継続、生活習慣改善、定期検査 |
部位別の経過差
腎障害が顕著な場合は、腎機能の回復が限定的なことが多く、透析治療を含めた長期ケアが必要になるケースもあります。
皮膚病変だけの場合は、潰瘍や壊死が治癒するまでに数カ月を要することがありますが、十分に管理していれば命にかかわるリスクは比較的低いです。
一方で、消化管や脳への塞栓が生じた場合には、合併症の管理にも注意を払わなければなりません。
治療期間に影響するその他の要因
患者の年齢や基礎疾患の有無、治療開始のタイミングも治療期間を左右し、早期発見・早期治療を行うほど、合併症のリスクが低減し、回復が早まることが期待できます。
医療側だけでなく、患者さん自身のセルフケア意識や通院継続の重要性も治療期間を短縮する鍵です。
コレステロール結晶塞栓症薬の副作用や治療のデメリットについて
コレステロール結晶塞栓症の治療には、多彩な薬剤や治療方法が組み合わされることが多く、それぞれに副作用やデメリットがあります。
副腎皮質ステロイドの副作用
ステロイド薬は強力な抗炎症作用を持ち、急性期の病変コントロールに役立つ一方で、長期使用による副作用が指摘されていて、代表的なものは、血糖値の上昇、骨粗しょう症、易感染性などです。
急に中止するとリバウンドが起こる可能性があるため、医師の指示に従って減量や中止のタイミングを調整します。
ステロイド薬の主な副作用
- 血糖コントロールの乱れ(糖尿病悪化)
- 骨密度低下による骨折リスク増加
- 免疫力低下に伴う感染症への注意
- 精神面への影響(不眠、気分変調など)
スタチン系薬剤の注意点
スタチン系薬剤はLDLコレステロールを下げる目的で広く用いられていますが、まれに筋肉痛や肝機能障害などの副作用が生じる場合があります。
服用期間が長期に及ぶことが多いため、定期的な血液検査で肝機能やCK(クレアチンキナーゼ)の値を確認し、異常があれば薬剤変更を検討します。
抗血小板薬による出血リスク
抗血小板薬は血小板の凝集を抑制して血管閉塞を予防する反面、出血傾向が増す可能性があり、外傷や消化管の潰瘍がある方は注意が必要です。
特に長期服用時には、鼻出血や皮下出血など軽度の出血を繰り返しやすくなる場合があり、こうした兆候を見逃さないようにすることが大切になります。
コレステロール結晶塞栓症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
検査費用の目安
血液検査や画像検査、組織生検など、コレステロール結晶塞栓症の診断には複数の検査が必要です。
| 検査項目 | 費用(自己負担3割) |
|---|---|
| 血液検査(基本) | 数千円程度 |
| 画像検査(CTやMRI) | 5,000円~10,000円程度 |
| 組織生検 | 10,000円~20,000円程度 |
ただし、検査が重複したり、高度な特殊検査を行ったりする場合は、さらに費用が増えます。
薬剤費の目安
コレステロール結晶塞栓症の治療薬としては、ステロイド、スタチン、抗血小板薬、降圧薬など多種にわたり、保険適用後の薬剤費用としては、1カ月あたり数千円から1万円台になる場合が多いです。
外科的治療や入院費用
血管内治療や大動脈瘤手術などの大きな処置が必要なケースでは、保険適用後の自己負担分でも数万円から数十万円になることがあり、合併症や再手術などが加わるとさらに増加する可能性があります。
以上
参考文献
Masuda J, Tanigawa T, Nakamori S, Sawai T, Murata T, Ishikawa E, Yamada N, Nakamura M, Ito M. Use of corticosteroids in the treatment of cholesterol crystal embolism after cardiac catheterization: a report of four Japanese cases. Internal Medicine. 2013;52(9):993-8.
Ishiyama K, Sato T, Taguma Y. Low‐density lipoprotein apheresis ameliorates renal prognosis of cholesterol crystal embolism. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2015 Aug;19(4):355-60.
Ishiyama K, Sato T. Efficacy of LDL apheresis for the treatment of cholesterol crystal embolism: A prospective, controlled study. Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2022 Apr;26(2):456-64.
Kondo Y, Kanzaki M, Ishima D, Usui R, Kimura A, Usui K, Amoh Y, Takeuchi Y, Kumabe T, Ako J, Miyaji K. Cholesterol crystal embolism-related cerebral infarction: Magnetic resonance imaging and clinical characteristics. Eneurologicalsci. 2021 Dec 1;25:100388.
Tanaka H, Yamana H, Matsui H, Fushimi K, Yasunaga H. Proportion and risk factors of cholesterol crystal embolization after cardiovascular procedures: a retrospective national database study. Heart and Vessels. 2020 Sep;35:1250-5.
Koyama Y, Kojima K, Abe M, Okumura Y. Cholesterol Crystal Embolism in a Patient with Spontaneous Ruptured Aortic Plaques Identified by Non-Obstructive General Angioscopy. International Heart Journal. 2024 May 31;65(3):586-90.
Yamashita J, Nosaka T, Takahashi K, Naito T, Ofuji K, Matsuda H, Ohtani M, Hiramatsu K, Kobayashi M, Nakamoto Y. Cholesterol crystal embolism in multiple organs after transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma: An autopsy case report. Medicine. 2022 Sep 30;101(39):e30769.
Meyrier A. Cholesterol crystal embolism: diagnosis and treatment. Kidney international. 2006 Apr 2;69(8):1308-12.
Scolari F, Tardanico R, Zani R, Pola A, Viola BF, Movilli E, Maiorca R. Cholesterol crystal embolism: a recognizable cause of renal disease. American Journal of Kidney Diseases. 2000 Dec 1;36(6):1089-109.
Li X, Bayliss G, Zhuang S. Cholesterol crystal embolism and chronic kidney disease. International journal of molecular sciences. 2017 May 24;18(6):1120.