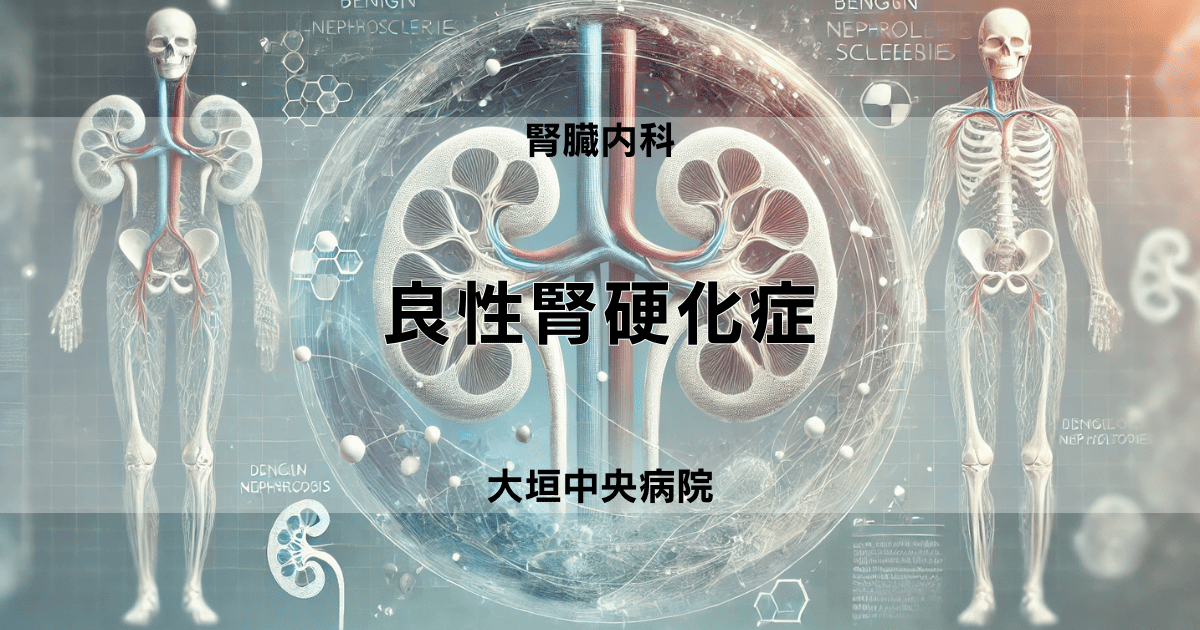良性腎硬化症とは、高血圧や加齢などを背景として、腎臓内の小動脈が少しずつ硬く変性し、ゆるやかに腎機能が低下していく病気です。
はっきりした症状がないまま長期にわたって進行するため、気づかないうちに腎機能が落ちている可能性があります。
発見が遅れると慢性腎不全に近づき、日常生活に大きな影響を及ぼす場合がありますが、血圧管理や食習慣の改善、必要に応じた薬物療法を行うことで、腎機能の低下を緩やかにして生活の質を維持することが期待されます。
良性腎硬化症の病型
良性腎硬化症は、主に高血圧による腎血管のダメージがゆっくりと蓄積することで起こりますが、進行度合いや背景によっていくつかの病型に分けられることがあります。
高血圧性腎硬化の特徴
高血圧が長期間持続すると、腎臓の細い動脈が徐々に硬く変性し、血流を確保するための柔軟性が失われていき、腎臓のろ過機能にも影響が及び、最終的に腎機能が下がってしまうのが高血圧性腎硬化の特徴です。
高齢者や塩分摂取量の多い食生活の方で見られることが多く、高血圧の管理状況によって進行スピードが大きく左右されます。
高血圧性腎硬化を疑う要因
- 血圧が長期間にわたって高めの状態が続いている
- 家族に高血圧や心血管系疾患の歴史がある
- 食事で塩分を多くとる習慣がある
- 偏った食生活やストレスが多く、血圧のコントロールが不十分
高血圧性腎硬化の進行を食い止めるには、血圧を安定させることが大切で、生活習慣の改善や医師の指導による薬物療法が欠かせません。
| 主な病型 | 背景因子 | 進行速度 | 合併症の例 |
|---|---|---|---|
| 高血圧性腎硬化 | 長期的な血圧上昇 | ゆるやかな進行 | 慢性腎不全、心血管障害 |
| 加齢性腎硬化 | 血管の老化・軽度高血圧 | 加齢とともに進む | 軽度の蛋白尿、腎機能低下 |
| ほかの要因による腎硬化 | 糖尿病や脂質異常など | 個人差が大きい | 多臓器合併症、腎不全リスク上昇 |
加齢性腎硬化の特徴
加齢によって全身の動脈硬化が進む中で、腎臓の細い動脈も少しずつ硬くなっていく場合があり、加齢性腎硬化と呼び、軽度の血圧上昇を伴う高齢者では特に注意が必要です。
加齢性腎硬化はゆるやかに進むため、明らかな症状が出ないことも多いですが、以下の要素に当てはまるときは詳しいチェックを検討します。
- 高齢になってから血圧がわずかに上昇した
- 以前は正常だったクレアチニンや蛋白尿の値が、徐々に異常範囲に入ってきている
- むくみやだるさが時々出現する
加齢性腎硬化は急激に悪化することは少ないですが、体力や他の臓器の働きが衰えている場合、合併症によって腎機能がさらに落ちるリスクがあるため、油断できません。
合併要因による腎硬化
糖尿病や脂質異常症といった生活習慣病を抱えていると、腎臓へのダメージが重複し、高血圧性腎硬化や加齢性腎硬化の進行を加速させることがあります。
糖尿病性腎症が同時に進行している場合は、蛋白尿が顕著になるなど、症状が重く出やすく、合併要因による腎硬化の場合は、複数の治療アプローチを同時に行う必要があるため、主治医との連携がより重要です。
| 合併要因 | 腎臓への影響 | 悪化のリスク |
|---|---|---|
| 糖尿病 | 糸球体のろ過機能を圧迫する糖尿病性腎症 | 進行が速く、蛋白尿が増加しやすい |
| 脂質異常症 | 動脈硬化の促進による血管ダメージ | 血管硬化が進みやすく腎障害増幅 |
| 痛風・高尿酸血症 | 尿酸が高い状態で血管に負担がかかる | 腎血流障害により腎機能低下が加速 |
症状
良性腎硬化症は、初期の段階では目立った症状がほとんどなく、健康診断やほかの疾患の検査を受けたときに偶然発覚する例も珍しくありません。
ただし、ゆるやかに腎機能が低下していく過程では、血圧や全身状態に微妙な変化が見られることがあり、注意深く観察することで早期対応が可能となる場合があります。
初期の特徴的な所見
初期の良性腎硬化症は、数値上の異常としては、わずかなクレアチニン上昇や軽度の蛋白尿などが見られる程度であり、自覚症状は乏しいです。
しかし、この段階で気づけば、生活習慣改善や適度な薬物療法により、腎機能をできるだけ守ることが期待できます。
良性腎硬化症の進行段階と主な症状
| 進行段階 | 主な症状や検査所見 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期 | 自覚症状ほぼなし、血圧や軽度検査異常 | クレアチニンわずかに上昇、蛋白尿±程度 |
| 中期 | むくみやだるさ、軽度の高血圧症状 | 血圧が安定せず、尿蛋白+~++ |
| 後期 | 明確な腎不全症状(倦怠感、頻尿など) | 透析や腎移植を検討するケースもある |
高血圧に伴う体の変化
良性腎硬化症の背景には高血圧が潜んでいることが多く、長期的な高血圧状態は以下のような症状やサインを起こす可能性があります。
- 朝起きた際の頭痛や後頭部の重さ
- 動悸やめまい、肩こりの持続
- 些細なことで息切れを感じやすい
- いらいら感や睡眠の質の低下
高血圧そのものは、初期には自覚しにくいため「サイレントキラー」と呼ばれますが、こうした日常的な不調が続く場合、高血圧による腎臓への負担を疑い、血圧測定や検査を受けたほうがよいでしょう。
高血圧が持続することで起こりうる主な合併症
- 心肥大や心不全など心臓への負担増
- 脳出血や脳梗塞など脳血管障害リスクの上昇
- 眼底出血や視力低下の要因となる高血圧性網膜症
- 動脈瘤の形成など、全身の血管に及ぶ障害
中期~後期の症状
良性腎硬化症が中期以降に進むと、尿検査での蛋白尿が顕著になり、全身のむくみや疲労感が日常的に感じられるようになることがあり、さらに、後期になると慢性的な腎不全の症状が出てきて、以下のような問題が生じやすくなります。
- 尿量の減少、夜間頻尿の増加
- 全身のむくみがとれにくくなる
- 食欲不振や吐き気、体重減少
- 皮膚のかゆみや貧血による倦怠感
- 高度になると意識障害や呼吸苦を伴う場合もある
こうした症状は、明らかに日常生活を妨げるレベルになるため、「最近なんとなく体調がすぐれない」状態から徐々に「はっきりと具合が悪い」状態へと変わっていくのが特徴です。
日常生活の中でのサイン
良性腎硬化症の進行度に応じて、日常の些細な場面で体の変化を感じることがあり、例えば以下のようなシチュエーションがあります。
- 以前よりも塩辛いものや甘いものに敏感になり、むくみが増した
- 少し動いただけで疲れやすく、体が重い
- 入浴や運動時に動悸が強く出て息苦しさを覚える
- 夜中に何度もトイレに行くため、睡眠不足になる
これらのサインを見逃さず、早めに医療機関で検査を受けることで、腎機能低下を抑える治療開始のタイミングを逃しにくくなります。
良性腎硬化症の原因
良性腎硬化症は、主に血圧が高い状態や動脈硬化が長く続くことで、腎臓内部の細小動脈が硬化し、ろ過機能が徐々に失われていく疾患です。
ただし、高血圧だけでなく、塩分摂取過多や糖尿病・脂質異常症などの合併症、さらには加齢や遺伝要因などが複雑に絡む場合もあります。
血圧管理の不備
良性腎硬化症の根本的な原因として最も大きいのが、高血圧状態を放置してしまうことです。
血管は本来、一定の柔軟性を保ちながら血圧の変動に対応しますが、慢性的に高圧がかかると血管壁が厚く硬くなりやすく、腎臓の血管も例外ではありません。
腎硬化が進行しやすい状況
- 塩分を多く含む食事が好きで、毎日摂取量が多い
- ストレスや生活リズムの乱れが継続している
- 運動不足による肥満や内臓脂肪の蓄積がある
- 遺伝的に高血圧になりやすい家系
血圧の状態と腎臓への負荷
| 血圧レベル | 腎臓への負担 | 腎硬化進行リスク |
|---|---|---|
| 正常血圧(上130未満) | ほぼ問題ない | 低い |
| 軽度高血圧(上130~139) | やや負担増加 | 徐々に硬化リスクが上昇 |
| 中等度以上(上140以上) | かなり大きな負担 | 良性腎硬化症が進行しやすい |
遺伝的・家族的要因
家族に高血圧や腎臓病の既往がある場合、遺伝的に腎硬化が起こりやすい素因がある可能性があります。
遺伝要因だけでなく、家庭内での食生活や塩分の使い方、運動習慣など環境的な要素も共有されるため、家族性に良性腎硬化症が見られるケースは珍しくありません。
家族的要因を示唆する例
- 親や祖父母が腎臓病で長く通院していた
- 家族の多くが血圧の薬を服用している
- 食事が全体的に濃い味付けで育った
- 血縁者に糖尿病や脂質異常症の方が多い
これらの状況に当てはまる人は、早期から血圧測定を習慣にし、異常があれば医療機関で相談してください。
生活習慣病との関連
良性腎硬化症が高血圧だけでなく、糖尿病や脂質異常症など他の生活習慣病と組み合わさると、腎機能の悪化が加速する場合があります。
糖尿病性腎症は、糸球体に大きな負担をかけるため、高血圧によるダメージと相まって腎障害が早期に進行する危険性があります。
また、脂質異常症は動脈硬化の促進を通じて腎血管を傷める可能性があるため、複数の生活習慣病を併発している方はより慎重なケアが必要です。
影響を及ぼしやすい生活習慣病
| 生活習慣病 | 腎臓への主な影響 | 結果 |
|---|---|---|
| 糖尿病 | 糸球体の過剰ろ過、血管障害 | 尿蛋白増加や腎機能急速な低下 |
| 脂質異常症 | 動脈硬化を促進し血管を硬化させる | 腎血流の低下、腎機能悪化のリスク |
| 痛風・高尿酸血症 | 尿酸による血管・腎臓へのストレス | 腎血流障害や腎結石などの可能性 |
加齢とストレス
年齢を重ねることで血管が老化し、自然と動脈硬化が進行し、これに伴って、軽度の高血圧や腎機能の衰えが生じ、それが重なると良性腎硬化症が起こりやすくなります。
また、過度なストレスはホルモンバランスや自律神経の乱れを起こし、高血圧に拍車をかけることがあります。
加齢とストレスが相乗的に腎臓への負担を増やすため、意識的に生活リズムを整え、リラクゼーションを取り入れるなどの対処を行うことが重要です。
加齢とストレスに起因するリスク
- 年齢とともに血圧が上昇しやすくなる
- 食欲不振や睡眠不足が重なると代謝が乱れて血圧が高止まりする
- ストレスで喫煙や飲酒などに頼る頻度が高くなる
- 老化で腎血管の柔軟性が低下し、少しの血圧上昇でも腎臓に大きな負担
こうした背景に気づかず日々を過ごしていると、腎硬化がゆるやかに進んで後戻りが難しくなるケースもあります。
検査・チェック方法
良性腎硬化症は、長期的な視点で腎機能をチェックし、症状の有無にかかわらず早期発見につなげることが大切です。医療機関では血液検査、尿検査、画像検査などを組み合わせて総合的に評価し、必要に応じて追加検査を行います。
血液検査と尿検査の意義
腎機能を評価する基本的な検査は、血液検査と尿検査です。
血液検査では、クレアチニンや血中尿素窒素(BUN)などの数値を確認し、そこから推定GFR(eGFR)を算出して腎ろ過能力を把握し、尿検査では、蛋白や潜血の有無が腎臓へのダメージを示す手がかりとなります。
代表的な血液検査・尿検査項目
- 血清クレアチニン:腎ろ過機能が低下すると上昇
- eGFR:正常値(90以上)からどの程度下がっているかで重症度を推定
- 尿蛋白:持続的に陽性なら腎障害が強く疑われる
- 尿潜血:微量でも続く場合は腎実質の障害を考慮
値の変化が小さくても、経時的に追うことで腎硬化の進行度をつかみやすくなります。
血液・尿検査の主な項目と目安
| 検査項目 | 正常値の目安 | 良性腎硬化症での変化 |
|---|---|---|
| クレアチニン(男性) | 約0.6~1.1 mg/dL | ゆるやかな上昇傾向 |
| クレアチニン(女性) | 約0.5~0.9 mg/dL | ゆるやかな上昇傾向 |
| eGFR | 90 mL/min/1.73㎡ 以上が理想 | 60以下に低下する場合が多い |
| 尿蛋白 | 陰性 or ± くらいまでが一般的 | +~++以上が続く可能性 |
| 尿潜血 | 陰性 | 微量~陽性になるケースがある |
画像検査による評価
腎エコー(超音波検査)は、腎臓の形状や大きさ、血流の状況を簡易に確認できる方法で、被ばくがないため定期的に実施しやすく、腎萎縮や血管の動脈硬化の有無をある程度確認できます。
より詳しい検査が必要な場合はCTスキャンやMRIを使うこともありますが、造影剤の使用が腎機能低下を招く恐れがあるため、医師の判断で慎重に進められます。
代表的な画像検査
| 検査名 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 腎エコー | 超音波を使い腎臓の状態を映し出す | 被ばく無し、簡便、低コスト | 肥満や腸ガスで画像不明瞭 |
| CTスキャン | X線を利用し多角度から断層画像を撮影 | 他の臓器も同時に評価しやすい | 被ばく、造影剤リスク |
| MRI | 磁気共鳴で詳細な軟部組織の画像を得る | 被ばく無し、正確性が高い | 時間と費用がかかる |
血圧測定と家庭でのモニタリング
血圧管理が良性腎硬化症の進行を抑えるカギとなるため、医療機関での血圧測定だけでなく、自宅での日常的な測定を推奨されることが多いです。
特に朝起きた直後と夜寝る前の血圧は重要な指標であり、血圧計を用いて数値を記録し、主治医に報告すると治療の方針を立てやすくなります。
家庭血圧測定で注意するポイント
- 朝は起床後1時間以内、排尿を済ませて1~2分安静にしてから測定
- 夜は就寝前に落ち着いてから測る
- 腕帯のサイズや巻き方を確認し、心臓の高さで測定
- 測定結果をノートやアプリで継続的に記録
自宅での安静時血圧が病院での測定値よりも高い「仮面高血圧」や、逆に白衣高血圧で数値が高めに出るケースもあるため、家庭血圧のデータは診断・治療計画に役立つ重要な情報です。
追加の負荷試験や詳細検査
場合によっては、腎機能の限界や血管の状態をより詳しく調べるために、運動負荷試験やレニン・アルドステロン系の測定、24時間蓄尿検査などを行うことがあります。
- 24時間蓄尿:1日の尿量と蛋白、ナトリウム、クレアチニン排泄量を詳細に把握
- レニン・アルドステロン系測定:血管収縮やナトリウム保持に関わるホルモンバランスをチェック
- 大動脈のCT・MRI:腎動脈狭窄など二次性高血圧の原因を調べる
検査結果を総合的に把握することで、より適切な治療戦略を立案できる可能性が高まります。
良性腎硬化症の治療方法と治療薬について
良性腎硬化症を治療する際、まず念頭に置くのは血圧のコントロールで、高血圧によって血管と腎臓が傷みやすい状態をいかに緩和するかが、腎機能を守るカギです。
同時に、糖尿病や脂質異常症などの合併症を抱えている場合は、それらの治療も並行して行う必要があります。
生活習慣の改善
治療の土台として欠かせないのは、食事・運動・禁煙などの生活習慣改善です。特に塩分制限は血圧を下げるうえで大切で、1日5~6gを目安にコントロールすることがよく推奨されます。
味付けを薄味にしたり、加工食品の摂取を控えたりすると同時に、適度な有酸素運動を取り入れることで血圧や体重を安定させやすくなります。
| 改善項目 | 具体的アプローチ | 期待できるメリット |
|---|---|---|
| 塩分制限 | 減塩調味料の利用、だしの活用など | 血圧低下による腎負担の軽減 |
| 適度な運動 | ウォーキングや軽いジョギング、筋トレなど | 血管の柔軟性向上、体重管理 |
| 禁煙 | タバコをやめる | 動脈硬化予防、全身の血流改善 |
| ストレス対策 | 趣味やリラクゼーション法を取り入れる | 血圧上昇防止、ホルモンバランス安定 |
| アルコール制限 | 飲み過ぎを控え、適量の範囲にとどめる | 高血圧リスクの減少、肝機能保護 |
抗高血圧薬の使用
血圧が高い状態が続くと腎硬化の進行が早まるため、医師は多くの場合、抗高血圧薬の処方を検討します。
主な薬としては、ACE阻害薬やアンジオテンシンII受容体拮抗薬(ARB)、カルシウム拮抗薬、利尿薬などがあり、腎保護効果を期待できる薬が優先的に選ばれることが多いです。
抗高血圧薬の代表的な種類
- ACE阻害薬:アンジオテンシンIIの産生を抑え、血管拡張と腎保護を促す
- ARB:アンジオテンシンII受容体をブロックし、血圧を下げる
- カルシウム拮抗薬:血管平滑筋を弛緩させ、血圧を低下
- 利尿薬:余分な水分と塩分を排出し、循環血液量を減少させる
服用量や組み合わせは、患者の年齢、腎機能、合併症の有無などを総合的に考えて決定されます。
腎保護効果の高い薬剤選択
良性腎硬化症では、血圧を下げるだけでなく、腎臓への負担を軽減する作用が重視され、ACE阻害薬やARBは、糸球体内圧を下げる効果が期待できるため、腎保護効果が比較的大きいと考えられています。
タンパク尿が見られる場合にも有用とされることがあり、薬物選択の中心に置かれることが多いです。
代表的な抗高血圧薬
| 薬剤分類 | 代表的な薬例 | 主な作用 | 副作用例 |
|---|---|---|---|
| ACE阻害薬 | エナラプリル、リシノプリルなど | アンジオテンシンII産生抑制、腎保護 | せき、血管浮腫 |
| ARB | ロサルタン、バルサルタンなど | アンジオテンシンII受容体遮断 | めまい、高カリウム血症 |
| カルシウム拮抗薬 | アムロジピン、ニフェジピンなど | 血管平滑筋の弛緩 | 顔面紅潮、足のむくみ |
| 利尿薬 | ヒドロクロロチアジドなど | 余分な水・塩分の排出 | 電解質異常、脱水 |
併発疾患への対応
糖尿病や脂質異常症など、他の生活習慣病を持っている場合は、それらの管理も同時に進めることが必要です。
糖尿病性腎症が進行している方には、血糖値のコントロールが腎保護の観点からも極めて重要ですし、脂質異常症がある場合はスタチン系薬剤などを使って動脈硬化の進行を抑制します。
良性腎硬化症の治療期間
良性腎硬化症は、ゆるやかに腎機能が低下していく慢性疾患であるため、短期的に終わる治療ではなく、長期間にわたるフォローが求められます。
早期発見で安定するケース
初期の段階で血圧のコントロールに着手できれば、腎硬化の進行を抑え、長期にわたって安定した腎機能を保てる可能性が高まります。
定期的な検診や家庭血圧測定によって早めに異常をとらえた場合、生活習慣改善と薬物療法が功を奏して、腎機能をある程度の水準で維持できるケースがあります。
治療開始時期と予想される経過
| 治療開始時期 | 腎機能状態 | 経過の傾向 |
|---|---|---|
| 初期 | クレアチニンや血圧のわずかな異常 | 進行を抑えやすく、生活の質を保ちやすい |
| 中期 | 蛋白尿やむくみが見られる | 薬物療法と生活指導が不可欠、合併症に注意 |
| 後期 | 腎不全の一歩手前または透析準備 | 大掛かりな治療が必要になり、日常生活に制限が出る |
個人差の大きい進行速度
良性腎硬化症の進行速度は個人差が大きく、数年で一気に腎機能が悪化する人もいれば、10年以上安定した状態を保つ人もいて、遺伝や生活習慣、合併症の有無、治療への取り組み方など、複数の要因が重なって進行度合いに違いが出ます。
進行速度を左右しやすい要因
- 血圧がどの程度安定しているか
- 塩分制限や運動習慣が実践できているか
- 糖尿病や脂質異常症などを併発しているか
- 遺伝的に腎臓が弱い傾向があるか
- 喫煙習慣やストレスの程度
総合的に見て、患者自身が治療や生活指導に前向きに取り組むほど、進行を遅らせる可能性が高まります。
定期的な通院と検査
良性腎硬化症の治療期間中は、医師が指示する頻度で通院し、血液検査や尿検査を受けることが不可欠です。
初期や状態が安定している時期は3~6か月に1回程度の受診で済む場合がありますが、蛋白尿が増える、血圧がなかなか下がらない、むくみが顕著になるなどの異常が見られるときは、通院頻度を高めて細かく観察するケースもあります。
通院頻度と検査内容の目安
| 通院頻度 | 主な検査内容 | 状況 |
|---|---|---|
| 3~6か月に1回 | 血液検査(クレアチニン、eGFRなど)、尿検査 | 血圧や腎機能が比較的安定している場合 |
| 1~2か月に1回 | 血液検査、尿検査、場合によって画像検査 | 血圧コントロール不良、蛋白尿増加など |
| 月1回以上 | 上記に加え、負荷試験や詳細な画像検査など | 腎機能が著しく低下、透析検討の可能性 |
良性腎硬化症薬の副作用や治療のデメリットについて
良性腎硬化症の治療には、血圧を下げる薬をはじめ複数の薬剤が選択される可能性がありますが、どの薬にも副作用のリスクがあります。
抗高血圧薬の代表的な副作用
ACE阻害薬やARBは、腎保護効果を期待できる一方で、せきやめまい、まれに血管浮腫などの副作用が報告されています。
カルシウム拮抗薬では足のむくみや顔のほてり、利尿薬では電解質異常や脱水など、薬の種類によって症状は異なり、副作用が強く出る場合は、医師に相談し、薬の種類や用量を調整してもらうことが大切です。
- ACE阻害薬:乾いたせき、めまい
- ARB:高カリウム血症、めまい
- カルシウム拮抗薬:動悸、足のむくみ
- 利尿薬:電解質バランス崩れ、脱力感
薬を変更する際も、血圧が乱高下しないよう注意が必要なので、自己判断ではなく医師の指示に従ってください。
塩分やアルコール制限によるストレス
高血圧管理では塩分制限が必須となる場合が多く、外食や宴会、旅行などで満足に食事を楽しみにくいと感じる方もいます。
また、アルコールを控えなければならないケースでは、飲酒の機会やコミュニケーションの場面でストレスが増すことがあります。
しかし、健康的な生活リズムと食事を続けることが、長期的には腎機能を守り、自由に動ける時間を伸ばすことにつながるため、周囲の協力を得ながら上手に乗り越える工夫が大切です。
塩分・アルコール制限でストレスを緩和する例
- 減塩調味料やハーブ、酸味を活用し、味に変化を持たせる
- 外食ではメニューを工夫し、塩分表示のある店を選ぶ
- アルコールの代わりにノンアルコール飲料を試してみる
- 家族や知人にも状況を理解してもらい、食事の協力を得る
制限を「我慢」だけでとらえず、味やスタイルを工夫して楽しみに変換できるかどうかが長続きのポイントです。
生活習慣病管理の多剤併用
糖尿病や脂質異常症などの治療薬を併用する場合、複数の薬を同時に飲み分ける煩雑さや、薬同士の相互作用で副作用が出るリスクが高まるというデメリットがあります。
主治医や薬剤師に現在服用中の薬を正確に伝えておくことで、重複や相互作用を避ける調整ができ、自己判断でサプリメントを始めるなどの場合も含め、摂取しているものを全て報告しておくと安全です。
良性腎硬化症の保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
薬剤費と検査費
抗高血圧薬だけであれば、1か月で数千円程度の自己負担になるケースが多いですが、処方される薬の種類や量によって変動します。
また、血液検査や尿検査の基本的なセットは1回あたり数百円~数千円程度です。画像検査(CTやMRI)を実施する場合は、その回だけ数千円から1万円以上の費用がかかります。
治療費の目安(保険適用後の3割負担時)
| 治療・検査項目 | 月あたり or 1回の費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 抗高血圧薬(1種類) | 約1,000~3,000円 | 種類や用量によって変動 |
| 利尿薬(追加分) | 約500~2,000円 | 併用時の量・種類で変動 |
| 血液・尿検査(1回) | 約500~2,000円 | 検査項目が多いほどコスト増 |
| 腎エコー(1回) | 約1,500~3,000円 | 病院やクリニックの設定による |
| CT/MRI(1回) | 約3,000~10,000円 | 造影剤使用、検査範囲の広さで変化 |
通院頻度と合併症の影響
良性腎硬化症が中期~後期に進んだ場合、通院頻度が増え、検査内容も精密化するため、医療費がかさみやすいです。
さらに、糖尿病や脂質異常症、痛風など他の疾患を同時に治療している場合は、それぞれの薬剤費・検査費も上乗せされることになります。
治療費が増えやすいケース
- 血圧が高止まりし、薬の種類や量が増えた
- 蛋白尿やむくみが強くなり、頻繁に検査が必要
- 合併症が新たに発覚して薬が追加になった
- 画像検査を定期的に行う必要が出てきた
費用が上昇するタイミングで相談せずに治療を中断すると、さらに病状が悪化するリスクもあるため、主治医や医療スタッフに率直に状況を伝えましょう。
以上
参考文献
Sumida K, Hoshino J, Ueno T, Mise K, Hayami N, Suwabe T, Kawada M, Imafuku A, Hiramatsu R, Hasegawa E, Yamanouchi M. Effect of proteinuria and glomerular filtration rate on renal outcome in patients with biopsy-proven benign nephrosclerosis. PLoS One. 2016 Jan 25;11(1):e0147690.
Shiraishi N, Kitamura K, Kohda Y, Iseki K, Tomita K. Prevalence and risk factor analysis of nephrosclerosis and ischemic nephropathy in the Japanese general population. Clinical and experimental nephrology. 2014 Jun;18:461-8.
Yamanouchi M, Hoshino J, Ubara Y, Takaichi K, Kinowaki K, Fujii T, Ohashi K, Mise K, Toyama T, Hara A, Shimizu M. Clinicopathological predictors for progression of chronic kidney disease in nephrosclerosis: a biopsy-based cohort study. Nephrology Dialysis Transplantation. 2019 Jul 1;34(7):1182-8.
Sumida K, Takeda A, Furuichi K, Uesugi N, Ubara Y, Sato H, Sugiyama H, Shimizu A, Yokoyama H. Clinicopathological discordance in biopsy-proven nephrosclerosis: a nationwide cross-sectional study of the Japan Renal Biopsy Registry (J-RBR). Clinical and Experimental Nephrology. 2022 Apr;26(4):325-32.
Furuichi K, Shimizu M, Yuzawa Y, Hara A, Toyama T, Kitamura H, Suzuki Y, Sato H, Uesugi N, Ubara Y, Hoshino J. Nationwide multicenter kidney biopsy study of Japanese patients with hypertensive nephrosclerosis. Clinical and Experimental Nephrology. 2018 Jun;22:629-37.
Suzuki H, Kobayashi K, Ishida Y, Kikuta T, Inoue T, Hamada U, Okada H. Patients with biopsy-proven nephrosclerosis and moderately impaired renal function have a higher risk for cardiovascular disease: 15 years’ experience in a single, kidney disease center. Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease. 2015 Jun;9(3):77-86.
Haruhara K, Tsuboi N, Kanzaki G, Koike K, Suyama M, Shimizu A, Miyazaki Y, Kawamura T, Ogura M, Yokoo T. Glomerular density in biopsy-proven hypertensive nephrosclerosis. American Journal of Hypertension. 2015 Sep 1;28(9):1164-71.
Amano H, Koike K, Haruhara K, Tsuboi N, Ogura M, Yokoo T. Time-averaged proteinuria during follow-up and renal prognosis in patients with biopsy-proven benign nephrosclerosis. Clinical and Experimental Nephrology. 2020 Aug;24:688-95.
Takebayashi S, Kiyoshi Y, Hisano S, Uesugi N, Sasatomi Y, Meng J, Sakata N. Benign nephrosclerosis: incidence, morphology and prognosis. Clinical nephrology. 2001 May 1;55(5):349-56.
Vikse BE, Aasarød K, Bostad L, Iversen BM. Clinical prognostic factors in biopsy‐proven benign nephrosclerosis. Nephrology Dialysis Transplantation. 2003 Mar 1;18(3):517-23.