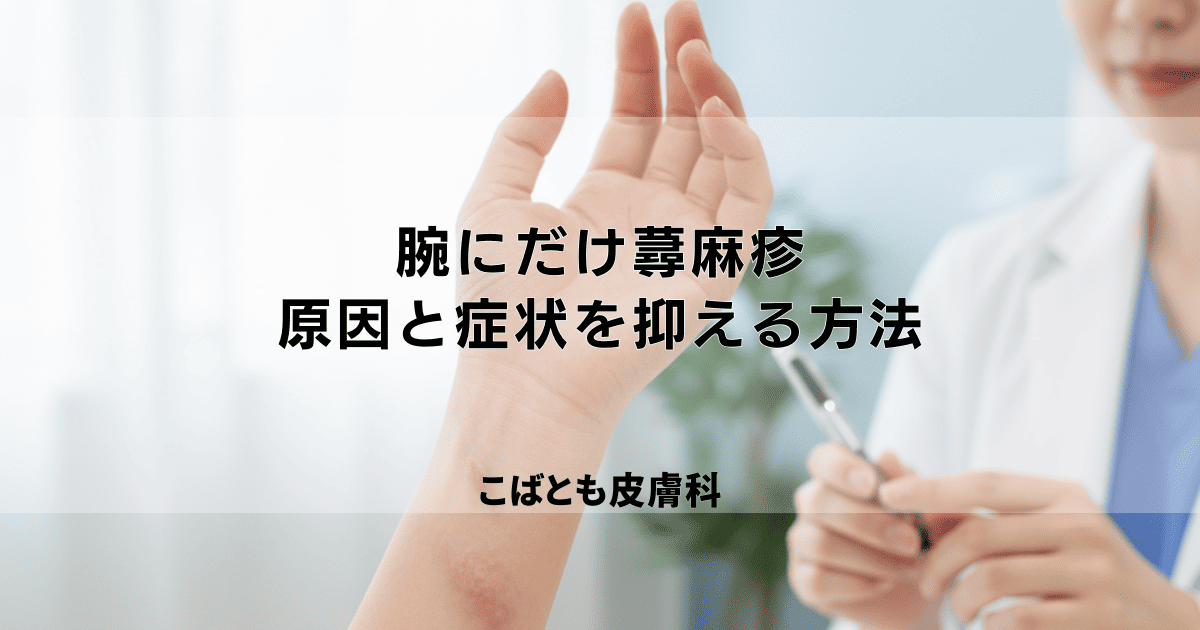ふと気づくと、腕に虫刺されのような赤いふくらみができていて、強いかゆみを感じるのは、蕁麻疹かもしれません。
特に腕は、衣服との摩擦や日光、様々な物質との接触など、外部からの刺激を受けやすく、蕁麻疹の症状が顕著に現れやすい部位の一つです。
突然現れる発疹と耐えがたいかゆみに、何か悪い病気ではないかと大きな不安を感じる方もいるでしょう。
この記事では、なぜ腕に蕁麻疹ができるのか、その背景にあるさまざまな原因から、つらい症状を少しでも和らげるための対処法まで、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
腕に現れる蕁麻疹の正体とは
腕に突然現れる赤い発疹やかゆみは、多くの人を悩ませる蕁麻疹の典型的なサインで、多くの場合は一過性のものです。
症状の正体と、なぜ腕という特定の部位に現れやすいのか、背景にある体の反応を深く理解することが、適切な対処への第一歩となります。
蕁麻疹の基本的な症状
蕁麻疹は、皮膚の真皮にあるマスト細胞が何らかの刺激で活性化し、ヒスタミンなどの化学伝達物質を放出することによって起こります。
ヒスタミンが血管に作用すると、血液の成分である血漿が血管の外に漏れ出し、皮膚が一時的に赤く盛り上がり、これが膨疹(ぼうしん)の正体です。
同時に、ヒスタミンは知覚神経を刺激するため、焼けつくような、あるいはチクチクするような強いかゆみが生じます。膨疹の大きさや形は様々で、数ミリ程度の点状のものから、融合して地図のように広がることもあります。
最大の特徴は、一つ一つの発疹が通常24時間以内に、ときには数時間で跡形もなく消える点です。しかし、場所を変えて繰り返し出現するため、症状が何日も続いているように感じることがあります。
蕁麻疹の主な症状
- 皮膚の赤み(紅斑)
- みみず腫れのような皮膚の盛り上がり(膨疹)
- 強いかゆみ、時に焼けるような感覚やチクチク感
- 症状が現れては消えるのを繰り返す(移動性)
なぜ腕だけに症状が出やすいのか
蕁麻疹が全身ではなく腕だけに集中して現れることには、明確な理由があり、腕は、体の他の部位に比べて、常に外部環境にさらされている時間が長い部位です。
衣類の袖口による持続的な摩擦や圧迫、夏場の強い紫外線、カバンを腕にかけることによる機械的な刺激、あるいは庭仕事で植物に触れたり、調理中に特定の食材に触れたりする機会も多いでしょう。
物理的・化学的な刺激が、蕁麻疹の直接的な引き金(誘因)になることは少なくありません。アレルギーの原因物質に触れた場合も、その接触した腕の部分に限定して症状が出ることがあります。
急性蕁麻疹と慢性蕁麻疹の違い
蕁麻疹は、症状が続く期間によって大きく二つに分類され、発症してから6週間以内に症状が治まるものを急性蕁麻疹、それ以上続く場合を慢性蕁麻疹と呼びます。
急性蕁麻疹は、特定の食品、薬剤、ウイルス感染(風邪など)が原因で起こることが多く、特に小児によく見られます。原因がはっきりしている場合は、避けることで再発を防げます。
慢性蕁麻疹は成人に多く、約7割以上は原因を特定できない「特発性」で、原因が不明なまま症状が続くため、患者さんの心身への負担は大きく、長期的な視点での治療と付き合い方が必要です。
急性・慢性の違い
| 分類 | 症状の持続期間 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 急性蕁麻疹 | 6週間以内 | 食物、薬剤、ウイルス・細菌感染など |
| 慢性蕁麻疹 | 6週間以上 | 原因不明(特発性)が多い、物理的刺激、自己免疫など |
腕の蕁麻疹を起こす主な原因
腕に現れる蕁麻疹の原因は、アレルギー反応として起こるものから、物理的な刺激、さらには心身のコンディションまで、さまざまな要因が複雑に関係しています。
アレルギー性の原因物質
特定の物質(アレルゲン)に対して体が免疫反応を起こし、蕁麻疹として現れるのがアレルギー性蕁麻疹です。原因物質が体内に入る、あるいは皮膚に接触することで、マスト細胞からヒスタミンが大量に放出され、症状が現れます。
食べ物では、サバなどの青魚、エビ・カニなどの甲殻類、卵、乳製品、そば、ピーナッツなどがよく知られてて、また、植物(ウルシなど)や金属、化粧品、ゴム(ラテックス)製品などが腕に直接触れることで発症する接触性蕁麻疹もあります。
原因が疑われる場合は、何を摂取し、何に触れたかを記録しておくことが診断の大きな手がかりとなります。
アレルギー反応を起こしやすい物質の例
| 分類 | 具体例 | 接触・摂取経路 |
|---|---|---|
| 食物 | サバ、エビ、カニ、卵、そば、ナッツ類、小麦 | 経口摂取 |
| 植物 | ウルシ、イラクサ、ギンナン | 皮膚への接触 |
| その他 | 金属、ゴム(ラテックス)、化粧品、薬剤(抗生物質、解熱鎮痛薬など) | 皮膚への接触、経口摂取 |
物理的な刺激による発症
アレルギー以外の原因として非常に多いのが、物理的な刺激によって誘発される蕁麻疹で、特定の刺激が加わった部位にのみ症状が現れるのが特徴です。
皮膚を強く掻いたり、衣類でこすれたりした跡が赤くみみず腫れになるのは機械性蕁麻疹(皮膚描記症)と呼ばれます。
他にも、腕時計やベルトによる圧迫で数時間後に腫れが生じる遅延性圧蕁麻疹、急に冷たい空気に触れたり冷水に入ったりすることで誘発される寒冷蕁麻疹、逆に入浴や運動で体が温まることで生じる温熱蕁麻疹など、様々な種類があります。
物理的刺激の種類と具体例
| 刺激の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 機械的刺激 | 衣類の摩擦、圧迫(腕時計、下着)、掻くこと、振動 |
| 温度刺激 | 温熱(入浴、暖房器具)、寒冷(冷たい外気、冷水) |
| その他 | 日光(紫外線)、水、発汗 |
ストレスや疲労との関連性
心身の状態も、蕁麻疹の発症や悪化に深く関わっていて、過度な精神的ストレスや、睡眠不足、過労といった肉体的な疲労が蓄積すると、自律神経や免疫系のバランスが乱れます。
体の内部環境の変化が、皮膚の血管やマスト細胞を不安定にし、普段なら問題にならないような些細な刺激にも過敏に反応するようになり、蕁麻疹を発症しやすくなったり、既存の症状が悪化したりするのです。
はっきりとした原因が見当たらないのに蕁麻疹を繰り返す場合、生活の中のストレスや疲労が大きく影響している可能性を考える必要があります。
内臓の不調が隠れている可能性
頻度は決して高くありませんが、蕁麻疹が体内の疾患のサインとして現れることもあります。
甲状腺機能亢進症などの甲状腺疾患や、全身性エリテマトーデス(SLE)といった膠原病、ヘリコバクター・ピロリ菌感染症を含む慢性的な感染症、そして、まれに内臓の悪性腫瘍などが背景に隠れているケースです。
なかなか治らない慢性的な蕁麻疹で、全身の倦怠感や発熱、関節痛など、皮膚以外の症状を伴う場合は、単なる皮膚の問題と自己判断せず、一度医療機関で詳しく調べることが大切です。
症状で判断する蕁麻疹の種類
蕁麻疹は、その原因や症状の現れ方によっていくつかの種類に分類され、ご自身の症状がどのタイプに近いかを知ることで、原因の推測や対策のヒントが得られます。
食べ物や薬が関与するアレルギー性蕁麻疹
特定の食べ物や薬を摂取した後に、比較的短時間で症状が現れ、原因となるアレルゲンを摂取してから数分から数時間以内に、腕を含む全身にかゆみを伴う発疹が広がります。
原因がはっきりしているため、その物質を避けることで予防が可能です。もし特定のものを食べた後や薬を飲んだ後に決まって症状が出る場合は、このタイプを疑い、何を摂取したか時間とともに記録しておくと診断の助けになります。
中には、特定の食物を摂取した後に運動することで初めて症状が出る、食物依存性運動誘発アナフィラキシーという特殊なタイプもあります。
汗や日光が引き金となるコリン性・日光蕁麻疹
運動や入浴、精神的な緊張などで汗をかいたときに現れるのがコリン性蕁麻疹で、アセチルコリンという神経伝達物質が関与していると考えられています。
一つ一つの膨疹が1mmから4mm程度と小さく、赤みを帯びた領域に点状に多発するのが特徴で、腕の内側や胸、背中などによく見られます。
日光蕁麻疹は、日光に当たった腕などの部分に限定して赤みやかゆみが生じ、日光の特定の波長(主にUVA)に反応して起こります。夏場の屋外活動などで発症しやすく、長袖の着用や日焼け止めで対策することが重要です。
衣類の圧迫や摩擦による機械性蕁麻疹
皮膚がこすれたり、圧迫されたりした部分に症状が現れるタイプです。腕では、腕時計のベルト部分や、きつい袖口、バッグの持ち手が当たる部分などに線状の発疹が出やすくなります(皮膚描記症)。
症状の現れ方には個人差があり、刺激を受けてすぐに出る即時型もあれば、数時間経ってから赤く腫れてきて、時には痛みを伴う遅延性圧蕁麻疹もあります。後者は、重い荷物を運んだ後や、長時間固い椅子に座った後のお尻などに見られます。
ゆったりとした服装を心がけるなど、皮膚への刺激を減らす工夫が効果的で、このタイプの蕁麻疹は、原因となる物理的刺激を特定し、避けることが最も有効な対策です。
蕁麻疹の種類と特徴
| 蕁麻疹の種類 | 主な誘因 | 症状の特徴 |
|---|---|---|
| アレルギー性蕁麻疹 | 食物、薬剤、添加物 | 原因物質摂取後、短時間で発症。全身に出やすい。 |
| コリン性蕁麻疹 | 発汗(運動、入浴、緊張) | 小さな膨疹が多発する。チクチクしたかゆみ。 |
| 機械性蕁麻疹 | 摩擦、圧迫 | 刺激が加わった部位に一致して線状・面状に発症。 |
| 日光蕁麻疹 | 日光(紫外線) | 日光に当たった部位(露出部)に発症。 |
| 特発性蕁麻疹 | 不明 | 原因が特定できず、症状を6週間以上繰り返す。 |
原因が特定しにくい特発性蕁麻疹
さまざまな検査を行っても、はっきりとした原因が見つからない蕁麻疹を特発性蕁麻疹と呼び、慢性蕁麻疹の7割以上がこのタイプに該当すると言われ、多くの患者さんを悩ませています。
原因が分からないため、不安に感じる方も多いかもしれませんが、近年では自己免疫、つまり自分の体の成分に対して免疫が反応してしまう状態が関与しているケースがあることも分かってきました。
症状をコントロールするための治療法は確立されており、抗ヒスタミン薬が治療の基本となります。
ストレスや疲労、生活リズムの乱れなどが症状を悪化させる要因になることもあるため、薬による治療と並行して、生活習慣全体を見直すことも大切です。
自分でできる応急処置とセルフケア
腕に蕁麻疹の症状が現れたとき、皮膚科を受診するまでの間、つらいかゆみを少しでも和らげたいものです。ここでは、ご自身でできる応急処置と、症状を悪化させないための日常生活での注意点について、説明します。
症状を和らげるための冷却方法
かゆみが強いときは、患部を冷やすのが簡単かつ効果的な方法です。冷たい刺激によってかゆみを伝える知覚神経の働きが一時的に鈍くなり、また、血管が収縮することで炎症の原因となるヒスタミンの広がりを抑えることができます。
保冷剤や氷を清潔なタオルやハンカチで包んだもの、あるいは冷たいシャワーを患部に数分間あてるのがよいでしょう。ただし、冷やしすぎは血行障害や凍傷の原因になることもあるため、1回10分程度が目安です。
重要な注意点として、寒冷蕁麻疹の場合は、冷やすことで逆に症状が悪化してしまうため、この方法は絶対に避けてください。
冷却時のポイント
- 保冷剤などはタオルで包み、直接肌に当てない
- 1回10分程度を目安にする
- 感覚がなくなるほど冷やしすぎない
- 寒冷蕁麻疹の疑いがある場合は行わない
かゆみを増幅させないための注意点
強いかゆみがあると、無意識のうちに掻きむしりたくなりますが、それは症状を悪化させる最たる行為です。
掻くという物理的な刺激そのものが、マスト細胞をさらに活性化させ、ヒスタミンの追加放出を促しかゆみが増し、発疹が広がるという「イッチ・スクラッチサイクル(かゆみと掻破の悪循環)」に陥ります。この悪循環を断ち切ることが重要です。
爪を短く切り、掻く代わりに冷やしたり、かゆい部分の周辺を指の腹で軽く押したりして気を紛らわせましょう。
また、アルコールの摂取や香辛料の多い食事は、全身の血行を良くして皮膚の温度を上げ、かゆみを増強させるため、症状が出ている間は控えてください。
かゆみを悪化させる行動
| 行動 | 理由 |
|---|---|
| 患部を掻きむしる | 物理的刺激により炎症が悪化し、かゆみが増す悪循環に陥る |
| 熱いお風呂に長く入る | 体温上昇と血行促進により、かゆみが強くなる |
| アルコールを摂取する | 血管が拡張し、皮膚の赤みや炎症、かゆみを増強させる |
日常生活で心がけたい皮膚への配慮
蕁麻疹の症状を抑え、再発を防ぐためには、日頃から皮膚に優しい生活を心がけることが大切です。
衣類は、肌触りの良い綿やシルクなど、刺激の少ない天然素材を選び、締め付けの強いデザインや、化学繊維、ウールなどは皮膚への刺激となることがあるので注意しましょう。
体を洗うときは、ナイロンタオルなどでゴシゴシこすらず、洗浄成分の優しい石鹸をよく泡立てて、手でなでるように優しく洗うようにしてください。
また、精神的なストレスや肉体的な疲労を溜めないよう、十分な睡眠と休息を取り、自分なりのリラックス方法を見つけることも、皮膚のコンディションを安定させる上で非常に重要です。
市販薬で対処する際のポイント
急な蕁麻疹の症状に対して、まずは市販薬で様子を見たいと考える方もいるでしょう。薬局やドラッグストアでは、蕁麻疹に対応したさまざまな薬が販売されています。
蕁麻疹に効果的な市販薬の選び方
市販薬を選ぶ際は、パッケージの効能・効果の欄に「じんましん」と明記されているものを選びましょう。治療の基本は、かゆみの原因となるヒスタミンの働きをブロックする「抗ヒスタミン薬」です。
飲み薬(内服薬)は体の中から作用し、腕だけでなく全身に広がりつつある蕁麻疹に効果を発揮します。
塗り薬(外用薬)は、抗ヒスタミン成分や局所のかゆみを抑える成分、清涼感を与えるメントールなどが含まれており、かゆみが特に強い部分への補助的な使用に適しています。
ただし、ステロイド成分を含む塗り薬は、蕁麻疹の膨疹そのものへの効果は限定的であり、自己判断での長期連用は避けるべきです。内服薬を基本とし、塗り薬はかゆみ対策のサポートと考えるのが良いでしょう。
市販薬の主な種類と特徴
| 種類 | 主な成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| 内服薬 | 抗ヒスタミン成分 | 体の中からかゆみや発疹を抑える。眠気の出にくい第二世代が主流。 |
| 外用薬 | 抗ヒスタミン成分、鎮痒成分、抗炎症成分 | 局所のかゆみを素早く抑える。あくまで補助的な役割。 |
薬を使用する前に確認すべきこと
市販薬を使用する前には、必ず添付文書(説明書)を隅々まで読み、記載されている用法・用量を厳守することが何よりも重要です。
特に、他に薬を服用している方、緑内障や前立腺肥大などの持病のある方、妊娠中や授乳中の方、高齢者、お子様が使用する場合は、購入前に必ず薬剤師や登録販売者に相談してください。
抗ヒスタミン薬の中には、眠気を起こすものがあるため、車の運転や危険を伴う機械の操作をする前は服用を避ける必要があります。自分の体質や生活状況を正しく伝え、安全に薬を使用しましょう。
市販薬使用前の確認リスト
- 用法・用量は正しいか
- アレルギー歴や副作用歴はないか
- 他に服用している薬との飲み合わせは問題ないか
- 妊娠・授乳中、持病など、相談が必要な条件に当てはまらないか
- 眠気の副作用についての注意は確認したか
市販薬で改善しない場合の目安
市販薬を3〜5日間、用法・用量を守って正しく使用しても症状が全く改善しない、あるいは発疹の範囲が広がるなど悪化するようであれば、使用を中止して速やかに皮膚科を受診してください。
また、一度症状が治まっても、薬の使用をやめるとすぐに再発を繰り返す場合も、専門医による診断が必要です。
市販薬はあくまで初期対応や一時的な症状緩和のためのものであり、根本的な原因の特定や慢性的な症状のコントロールには限界があります。
症状が長引く場合は、自己判断を続けずに医療機関に相談することが、結果的に早期改善への近道です。
皮膚科を受診するべきタイミング
ほとんどの蕁麻疹は数時間から数日で自然に消えますが、中には緊急を要するケースや、専門的な治療が望ましい場合があります。どのような状態になったら皮膚科を受診するべきか、タイミングをしっかりと把握しておきましょう。
息苦しさやめまいを伴う危険なサイン
蕁麻疹の症状に加えて、まぶたや唇が腫れあがる(血管性浮腫)、息苦しさ、声のかすれ、めまい、倦怠感、激しい腹痛や吐き気などの症状が現れた場合は、アナフィラキシーと呼ばれる重篤なアレルギー反応の可能性があります。
これは、血圧低下や気道のむくみを起こし、命に関わることもある非常に危険な状態です。
特に、食べ物や薬、ハチに刺された後などに症状が出た場合は、ためらわずに救急車を呼ぶか、救急外来を受診する必要があります。
注意すべき全身症状(アナフィラキシーの兆候)
- 呼吸困難、息苦しさ、ゼーゼーする喘鳴
- 顔やまぶた、唇、舌の著しい腫れ
- めまい、意識が遠のく感じ、血の気が引く
- 激しい腹痛や嘔吐、下痢
症状が数日以上続く場合
一つ一つの発疹は24時間以内に消えるのが蕁麻疹の特徴ですが、次々と新しい発疹が現れて、全体として症状が数日以上続いているように見えることがあります。
市販薬を使っても改善が見られない、かゆみが強くて夜も眠れない、日中の仕事や勉強に集中できないなど、日常生活に支障が出ている場合は、我慢せずに皮膚科を受診しましょう。
皮膚科受診を考えるべき症状
| 症状 | 受診を推奨する理由 |
|---|---|
| 市販薬を数日使っても改善しない | 原因の特定や、より効果的な処方薬による治療が必要な可能性がある |
| 強いかゆみで眠れない、集中できない | 生活の質(QOL)が著しく低下しており、積極的な治療介入が望ましい |
| 発疹の範囲が徐々に広がっている | 症状が進行しているサインであり、専門的な診断と治療が必要 |
蕁麻疹を繰り返すときの受診の重要性
症状が出たり消えたりを6週間以上にわたって繰り返す場合は、慢性蕁麻疹の可能性が高く、慢性蕁麻疹は原因の特定が難しいことが多く、自己判断での対処は困難です。
皮膚科では、症状を抑えるための薬物療法だけでなく、症状を悪化させる要因(悪化因子)を問診から丁寧に見つけ出し、それらを避けるための生活指導も含めた総合的なアプローチを行います。
自己判断で市販薬を使い続けるのではなく、専門医のもとで正しい診断を受け、適切な治療を継続することが、症状のコントロールと完治への最も確実な道です。
皮膚科で行う検査と治療法
皮膚科を受診すると、まずは詳しい問診から始まり、必要に応じて検査を行って原因を探ります。その上で、個々の症状や原因に合わせた治療を進めていきます。
蕁麻疹の原因を特定する検査
診断の基本は、どのような時に、どのような症状が出るのかを詳しくお聞きする問診で、症状を記録した日記などがあれば、非常に有用な情報です。
アレルギーが疑われる場合は、血液検査で特定のアレルゲンに対するIgE抗体の有無を調べたり、原因として疑われる物質を皮膚に直接つけて反応を見る皮膚テスト(プリックテストなど)を行ったりすることがあります。
物理性蕁麻疹が疑われる場合は、実際に皮膚をこすったり(皮膚描記症の誘発)、氷をあてたり(寒冷蕁麻疹の誘発)して症状が再現されるかを確認する検査もあります。
また、他の疾患を除外するために、一般的な血液検査(血球数、炎症反応など)を行うこともあります。
皮膚科での主な検査
| 検査名 | 検査内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 血液検査(特異的IgE抗体検査) | 特定のアレルゲンに対するIgE抗体を測定する | アレルギーの原因物質を特定する |
| 皮膚テスト(プリックテストなど) | アレルゲン液を皮膚に垂らし、小さな針で傷をつける | 即時型アレルギー反応を直接確認する |
| 誘発テスト | 圧迫、寒冷、温熱などの物理的刺激を加える | 各種の物理性蕁麻疹の診断を行う |
主な治療法である抗ヒスタミン薬
蕁麻疹治療の中心となるのが、抗ヒスタミン薬の内服で、かゆみや膨疹の原因となるヒスタミンの働きを、受容体でブロックすることで症状を強力に鎮めます。
近年開発された第二世代の抗ヒスタミン薬は、従来の第一世代の薬に比べて、眠気や口の渇きといった副作用が大幅に軽減されており、1日1回の服用で効果が持続するものが主流です。
医師は患者さんの症状の強さやライフスタイルに合わせて、薬を選択します。標準的な量で効果が不十分な場合は、医師の判断で薬の量を増やしたり(添付文書で認められた範囲で)、種類の異なる薬を組み合わせたりすることもあります。
症状に合わせた外用薬の活用
基本的には抗ヒスタミン薬の内服が治療の中心ですが、かゆみが特に強い部分に対しては、補助的に外用薬(塗り薬)を処方することがあり、かゆみを抑える成分や、弱いステロイド成分が含まれたものが使われます。
ただし、これらは蕁麻疹の膨疹そのものを根本的に治す力は限定的で、あくまでつらいかゆみを一時的に和らげる対症療法としての位置づけです。内服薬と併用することで、かゆみの悪循環を断ち切り、生活の質を改善する助けとなります。
日常生活での注意点(医師からの指導)
- 原因や悪化要因が分かっている場合はそれを徹底して避ける
- ストレスや疲労を溜めず、規則正しい生活を送る
- バランスの取れた食事と十分な睡眠を確保する
- 症状が出ているときはアルコールや香辛料の強い食べ物を控える
- 肌への刺激が少ない、ゆったりとした衣類を選ぶ
治療期間と完治までの道のり
急性蕁麻疹の場合、原因が特定できれば、避けることで数日から数週間で治癒することがほとんどです。一方、慢性蕁麻疹の場合は、症状をコントロールしながら、数ヶ月から数年単位で根気よく治療を続ける必要があります。
治療の目標は、まず抗ヒスタミン薬で症状が全く出ない状態(寛解状態)を目指し、その状態を数ヶ月維持することです。その後、医師の指導のもとで、数週間から数ヶ月かけて徐々に薬の量を減らしていきます。
症状が出ないからといって自己判断で急に薬をやめてしまうと、高確率で再発するため、医師の指示に従って焦らず治療を続けることが完治への最も大切な鍵となります。
腕の蕁麻疹に関するよくある質問
- 腕の蕁麻疹は他の人にうつりますか?
-
うつりません。蕁麻疹は、ウイルスや細菌による感染症とは異なり、体内の免疫反応や物理的な刺激によって起こる皮膚の反応です。
発疹に触れたり、同じタオルを使ったり、同じ空間にいたりしても、他の人にうつる心配は全くありません。
- 症状が出ているときにお風呂に入っても大丈夫ですか?
-
入浴自体は問題ありませんが、入り方に注意が必要です。熱いお湯に長く浸かると体が温まり、血行が促進されることでかゆみが悪化することがあります。
ぬるめのお湯(38〜40度程度)で、短時間のシャワー程度に済ませるのがよいでしょう。また、体を洗う際は、石鹸をよく泡立てて優しく手で洗い、ナイロンタオルなどでゴシゴシこすらないように気をつけてください。
- 季節によって蕁麻疹は出やすくなりますか?
-
影響を受けることがあります。夏は、汗をかくことによるコリン性蕁麻疹や、日光による日光蕁麻疹が起こりやすくなります。
冬は空気が乾燥して皮膚のバリア機能が低下し、衣類の摩擦などの刺激に敏感になったり、冷たい外気に触れることで寒冷蕁麻疹が誘発されたりすることがあります。
季節の変わり目は、寒暖差で自律神経が乱れやすく、蕁麻疹が悪化する方もいます。
- 食事で気をつけることはありますか?
-
特定の食べ物にアレルギーがある場合を除き、厳格な食事制限は通常必要ありません。
ただし、ヒスタミンを多く含む食品(サバ・マグロなどの青魚、豚肉、ほうれん草など)や、体内でヒスタミンの放出を促す食品(チョコレート、トマト、香辛料、アルコールなど)は、症状を悪化させる可能性があります。
症状がひどいときは、これらの食品を少し控えてみると、症状が落ち着くことがあります。
以上
参考文献
Itakura A, Tani Y, Kaneko N, Hide M. Impact of chronic urticaria on quality of life and work in Japan: results of a real‐world study. The Journal of dermatology. 2018 Aug;45(8):963-70.
Hide M, Hiragun T. Japanese guidelines for diagnosis and treatment of urticaria in comparison with other countries. Allergology International. 2012;61(4):517-27.
Hide M, Uda A, Maki F, Miyakawa N, Kohli RK, Gupta S, Krupsky K, Balkaran B, Balp MM. Prevalence and Burden of Chronic Spontaneous Urticaria in Japan: A Cross-Sectional Study. Journal of Clinical Medicine. 2025 Feb 11;14(4):1162.
Nakatani S, Oda Y, Washio K, Fukunaga A, Nishigori C. The Urticaria Control Test and Urticaria Activity Score correlate with quality of life in adult Japanese patients with chronic spontaneous urticaria. Allergology International. 2019;68(2):279-81.
Fukunaga A, Kishi Y, Sunaga Y, Arima K. Prevalence, Comorbidities, and Current Management of Chronic Spontaneous Urticaria in Japan: Retrospective Claims Database Study. The Journal of Dermatology. 2025 Sep 10.
Fukunaga A, Kishi Y, Arima K, Fujita H. Disease control and treatment satisfaction in patients with chronic spontaneous urticaria in Japan. Journal of Clinical Medicine. 2024 May 17;13(10):2967.
Hide M, Fukunaga A, Suzuki T, Nakamura N, Kimura M, Sasajima T, Kiriyama J, Igarashi A. Real-world safety and effectiveness of omalizumab in Japanese patients with chronic spontaneous urticaria: A post-marketing surveillance study. Allergology International. 2023;72(2):286-96.
Tanaka T, Hiragun M, Hide M, Hiragun T. Analysis of primary treatment and prognosis of spontaneous urticaria. Allergology International. 2017;66(3):458-62.
Yagami A, Furue M, Togawa M, Saito A, Hide M. One‐year safety and efficacy study of bilastine treatment in Japanese patients with chronic spontaneous urticaria or pruritus associated with skin diseases. The Journal of dermatology. 2017 Apr;44(4):375-85.
Takahashi H, Fukunaga A, Hayama K, Sasajima T, Fujishige A, Ichishita R, Tomimatsu N, Hua E, Varanasi V, Burciu A, Hide M. Long term safety and efficacy of ligelizumab in the treatment of Japanese patients with chronic spontaneous urticaria. Allergology International. 2025;74(1):136-43.