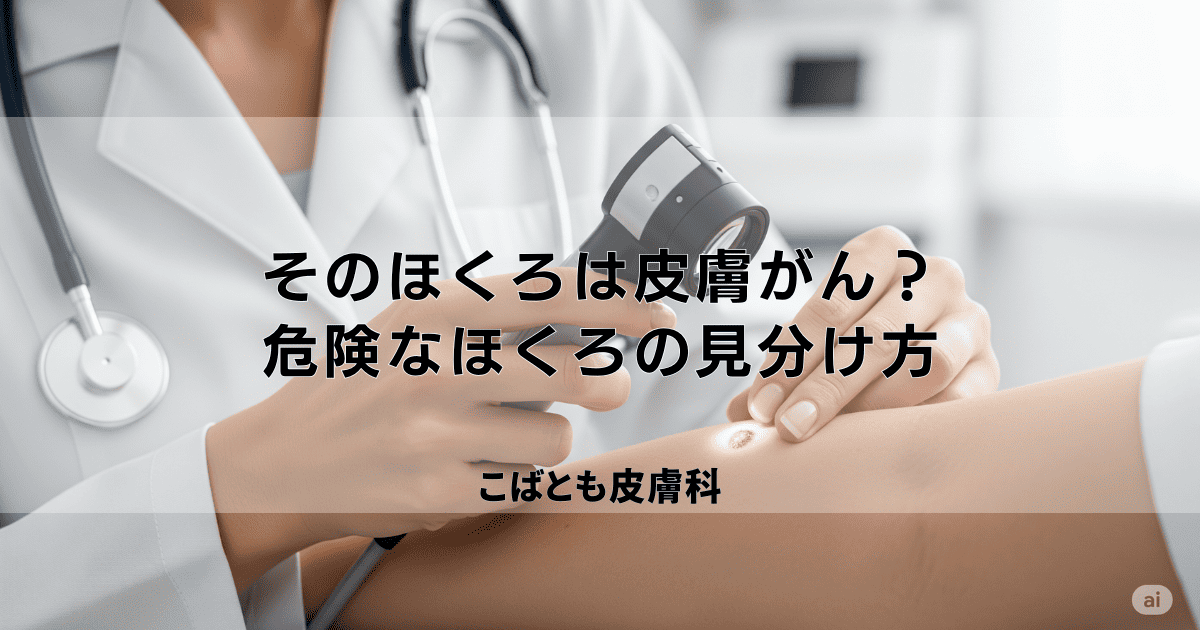ふと気づくと、いつの間にかできているほくろは、体のどこにでもある、ごくありふれたものです。ほとんどは心配のない良性のものですが、中には悪性の皮膚がん、特にメラノーマ(悪性黒色腫)の初期症状である可能性が隠されています。
普通のほくろと危険な皮膚がんのサインを、一体どう見分ければよいのでしょうか。
この記事では、誰でも簡単にチェックできる国際的な指標ABCDEルールを中心に、危険なほくろの見分け方を詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
普通のほくろと皮膚がんの基本的な違い
皮膚には、生涯を通じて様々なできものが生じ、代表であるほくろは、ほとんどの場合、心配のいらない良性の母斑細胞母斑です。しかし、中には悪性の腫瘍、つまり皮膚がんがほくろやシミのような顔をして潜んでいることがあります。
ほくろ(母斑細胞母斑)の正体
一般的にほくろと呼ばれるものは、医学的には色素性母斑あるいは母斑細胞母斑といい、メラニン色素を産生するメラノサイト(色素細胞)に由来する母斑細胞が、皮膚の一部で増殖してできた良性の腫瘍です。
生まれつきあるもの(先天性)や、幼児期以降に紫外線などの影響で出現するもの(後天性)など様々で、色や形、大きさも多岐にわたります。
多くのほくろは、出現してから数年かけて少しずつ成長しますが、ある程度の大きさになると成長が止まるのが一般的です。
また、年齢とともに色が薄くなったり、逆に盛り上がってきたりと、長い年月をかけてゆっくりと変化することもありますが、変化は非常に緩やかです。基本的には体に害を及ぼすことはなく、医学的な治療の必要もありません。
皮膚がんとは何か
皮膚がんは、皮膚を構成する様々な細胞が、紫外線や化学物質、ウイルス感染、遺伝的要因など、何らかの原因で遺伝子に傷がつき、無秩序に増殖を始めた悪性の腫瘍です。発生する細胞の種類によって、いくつかの種類に分類されます。
皮膚がんは、初期の段階ではほくろやシミ、湿疹、イボなどと見分けがつきにくいことがあり、発見が遅れる原因にもなります。
しかし、良性のほくろと異なり、皮膚がんは細胞の増殖に歯止めがきかないため、放置すると周囲の正常な組織を破壊しながらどんどん大きくなります。
さらに進行すると、リンパ管や血管を通ってリンパ節や他の臓器に転移し、生命を脅かすことがあるのが最大の違いです。
良性のほくろと皮膚がんの主な相違点
| 項目 | 良性のほくろ | 皮膚がん(特にメラノーマ) |
|---|---|---|
| 対称性 | おおむね左右対称の整った形 | 形が左右非対称でいびつ |
| 境界 | 輪郭がはっきりして滑らか | 輪郭がギザギザ、色がにじみ出している |
| 色調 | 均一な黒色または茶褐色 | 色むらがある(濃淡や複数の色が混在) |
なぜ早期発見が重要なのか
多くの皮膚がんは、早期に発見し治療を行えば、比較的予後が良いとされています。
皮膚がんの中でも悪性度が高いとされるメラノーマは、がん細胞が皮膚の浅い部分(表皮内)にとどまっているステージ0や、ごく浅い真皮までしか浸潤していないステージIのうちに治療を開始することが極めて重要です。
この段階であれば、手術によって95%以上が治癒しますが、がんが皮膚の深い部分にまで達したり、リンパ節や内臓に転移したりすると、治療が複雑になり、生存率も大きく低下します。
普段から自分の皮膚の状態に関心を持ち、小さな変化を見逃さないことが、何よりも大切です。
危険なサインを見逃さない ABCDEルールとは
普通のほくろと、皮膚がんの一種であるメラノーマを見分けるための、国際的に用いられている分かりやすい指標がABCDEルールです。これは、形状、境界、色調、大きさ、変化という5つのチェックポイントの頭文字をとったものです。
ご自身のほくろを鏡で見る際や、ご家族の背中などをチェックする際に、ぜひこのルールを一つ一つ当てはめてみてください。
A (Asymmetry) 形状の非対称性
最初のチェックポイントは、ほくろの形です。良性のほくろは、多くが整った円形や楕円形をしており、中心で線を引くと左右がほぼ同じ形になる、いわゆる左右対称の形をしています。
メラノーマの場合は、形がいびつで、左右非対称であることが多く、まるで地図の海岸線のように複雑な形をしていたり、絵の具を紙に垂らしたように、不規則な形にじわじわと広がっているように見えます。
綺麗な円形とは言えない、歪んだ形は最初の危険信号です。
B (Border) 境界の不整
次にほくろの輪郭、つまり正常な皮膚との境界線に注目します。良性のほくろは、境界がくっきりとしており、滑らかな線で囲まれていて、どこからどこまでがほくろなのか、はっきりと認識できます。
それに対してメラノーマは、境界線がギザギザ、あるいはノコギリの刃のようになっていたり、インクがティッシュににじんだようにぼやけていたり、一部がしみ出しているように見えたりします。
輪郭がはっきりしない、正常な皮膚との境目が曖昧なほくろは、がん細胞が周囲に染み出すように広がっている可能性を示唆しており、注意深く観察することが必要です。
C (Color) 色彩の濃淡
3つ目のポイントはほくろの色で、良性のほくろは、通常、黒一色、あるいは茶褐色一色と、全体の色調が均一です。多少の濃淡はあっても、全体として一様な色に見えます。
メラノーマの場合は、一つのほくろの中に、黒、茶色、焦げ茶色といった複数の色合いが混じり合っている、いわゆる色むらが見られます。
さらに進行すると、青みがかった色(青色部)や、がん細胞が自己退縮して色が抜けた部分(白色部)、炎症を反映した赤みがかった部分(赤色部)などが混在することもあります。
濃い部分と薄い部分が混在しているような、多彩な色調を持つほくろは危険なサインの一つです。
ABCDEルールのチェック項目
| ルール | チェックするポイント | 危険なサインの例 |
|---|---|---|
| A: Asymmetry | 形状の対称性 | 形がいびつで左右非対称 |
| B: Border | 境界の明瞭さ | 輪郭がギザギザ、にじみ出し |
| C: Color | 色調の均一性 | 濃淡が混じった色むら、多彩な色調 |
D (Diameter) 直径の大きさ
大きさも重要な指標で、良性のほくろの多くは、直径が5mm以下です。生まれつきある大きなほくろなど、良性でも6mmを超えるものはたくさんありますが、一つの目安として、直径が6mmを超えるものは注意が必要です。
特に、子供の頃からあったわけではなく、大人になってから出現したほくろで、大きさが6mmを超えている場合は、一度皮膚科で診てもらうことをお勧めします。
鉛筆のお尻についている消しゴムの直径が約6mmなので、一つの基準として、それより大きいかどうかをチェックしてみましょう。
E (Evolving) 形状や大きさの変化
最後のEは、他の4項目と並んで最も重要なポイントです。これは、ほくろの形状、大きさ、色、硬さ、盛り上がり具合などが時間とともに変化することを指します。
以前は平坦だったほくろが数ヶ月の間に急にドーム状に盛り上がってきた、色がまだらに濃くなった、あるいは逆に一部の色が抜けてきた、急に大きくなってきた、といった変化は、がん細胞が活発に増殖していることを示唆する重要なサインです。
また、これまでは何も症状がなかったのに、かゆみや痛み、出血、じくじくするといった症状が出てきた場合も、同様に危険な変化と捉える必要があります。
ほくろに見える主な皮膚がんの種類と特徴
皮膚がんにはいくつかの種類があり、それぞれ発生する細胞や見た目の特徴、進行の速さなどが異なります。ほくろと見間違えやすい代表的な皮膚がんを知っておくことで、セルフチェックの精度を高め、より早期の発見につなげることができます。
メラノーマ(悪性黒色腫)
メラノーマは、メラニン色素を作る細胞であるメラノサイトが悪性化したもので、皮膚がんの中でも特に悪性度が高いことで知られています。
日本人の場合、欧米人と異なり、紫外線が直接当たりにくい足の裏や手のひら、手足の爪の下などに発生する末端黒子型(Acral lentiginous melanoma)の割合が高いのが特徴です。
初期は、黒褐色のシミやほくろのように見えますが、進行するとABCDEルールに合致する特徴が現れてきます。早期発見が極めて重要で、発見が遅れるとリンパ節や内臓に転移しやすい非常に危険ながんです。
日本人に多いメラノーマの発生部位
- 足の裏(足底)
- 手のひら(手掌)
- 手足の爪の下(爪甲下)
- 体幹
- 顔面
基底細胞がん
基底細胞がんは、皮膚がんの中で最も発生頻度が高いがんです。表皮の一番深い層にある基底細胞や、毛包を構成する細胞から発生します。
高齢者の顔面、特に鼻の周り、まぶた、耳など、長年にわたり日光によく当たってきた部位にできやすいです。初期は、少し盛り上がった直径数ミリの黒っぽいほくろのように見え、表面に真珠のような光沢を伴うことがよくあります。
ゆっくりと進行し中心部がへこんで潰瘍になり、出血を繰り返すこともあります。進行は非常にゆっくりで、転移することは稀ですが、局所での破壊性が強いため、放置すると骨や軟骨まで破壊してしまいます。
基底細胞がんの特徴
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| 好発年齢 | 高齢者(特に60歳以上) |
| 好発部位 | 顔面(鼻、まぶた、耳など日光曝露部) |
| 見た目 | 黒色で光沢のある結節、中心が潰瘍化しやすい |
有棘細胞がん
有棘細胞がんは、表皮の中層にある有棘細胞から発生するがんで、基底細胞がんに次いで発生頻度が高く、日光によく当たる顔面や頭部、手背などにできやすいです。
長年の日光によるダメージの蓄積である日光角化症や、やけどの痕、治りにくい皮膚潰瘍、放射線治療の跡などから発生することもあります。
見た目は様々で、赤いブツブツや硬いしこり、治りにくいびらん、カリフラワー状の塊など、ほくろとはあまり似ていないことが多いですが、時に色素沈着を伴い黒っぽく見えることもあります。
進行すると悪臭を放ったり、リンパ節などに転移する可能性があります。
ボーエン病
ボーエン病はごく早期の有棘細胞がん、表皮内がんに分類されます。がん細胞が表皮の中にとどまっている状態で、この段階では転移の心配はありません。
境界がはっきりした円形や多角形の、少しカサカサした赤いシミのように見えることが多く、湿疹やたむしと間違われて、ステロイド軟膏などを長期間塗られていても治らない、といった経緯で発見されることもあります。
時に褐色や黒っぽい色調を帯びることもあり、ほくろと見間違える可能性もゼロではありません。放置すると、一部が進行性の有棘細胞がんに移行することがあります。
皮膚科で行われる専門的な診断方法
ABCDEルールなどによるセルフチェックで少しでも気になるほくろを見つけたら、自己判断で様子を見続けるのではなく、必ず皮膚科専門医の診察を受けることが重要です。
皮膚科では、専門的な機器や検査を用いて、良性か悪性かを正確に診断し、診断の精度は近年飛躍的に向上しています。
視診と問診
診察の基本は、まず医師が直接ほくろの状態を目で見て確認する視診と、患者さんから詳しくお話を伺う問診です。
いつからあるのか、大きさや色に変化はあったか、かゆみや痛みなどの自覚症状はあるか、過去に過度な日焼けを経験したことはないか、ご家族に皮膚がんになった人はいるか、といった情報が、診断の重要な手がかりです。
問診で伝えるべきポイント
- ほくろに気づいた時期
- 最近の大きさ・色・形の変化の有無
- かゆみ、痛み、出血などの症状
- 過去の日焼け歴(特に水ぶくれになるようなひどい日焼け)
- 家族の皮膚がんの既往歴
ダーモスコピー検査
ダーモスコピーは、ダーモスコープという特殊な拡大鏡を使って、ほくろを詳しく観察する検査です。
皮膚の表面の光の乱反射を抑えるジェルやスプレーを塗布した上で観察することで、肉眼では見えない皮膚の内部の色素の分布(色素ネットワーク)や血管のパターンを詳細に観察することができます。
検査により、良性のほくろと悪性の皮膚がん、特にメラノーマの鑑別精度が飛躍的に向上しました。患者さんに痛みなどの負担は一切なく、その場で診断が可能です。経験豊富な皮膚科医が行えば、診断精度は90%以上とも言われています。
ダーモスコピーによる良悪性の判断基準
| 所見 | 良性を示唆 | 悪性(メラノーマ)を示唆 |
|---|---|---|
| 色素ネットワーク | 規則的で均一な網目模様 | 不規則で途切れている、太さが不均一 |
| ドット・グロビュール | 辺縁に規則的に分布する点や塊 | 中心部にも不規則に分布 |
| 血管パターン | コンマ状血管など規則的な血管 | 点状・線状血管、多形性血管など多彩な血管 |
皮膚生検(病理組織検査)
ダーモスコピー検査などを行っても診断が確定できない場合や、悪性が強く疑われる場合には、確定診断のために皮膚生検を行います。
これは、局所麻酔をした上で、病変の一部または全部をメスで切り取り、顕微鏡で詳しく調べる病理組織検査です。
切り取った組織をホルマリンで固定し、薄くスライスして染色した標本を、専門の病理医が観察し、がん細胞の有無や種類、がんの深さ(浸潤度)などを診断します。皮膚がんの診断における最終的かつ最も確実な方法です。
画像検査(CT、MRI、PETなど)
皮膚生検の結果、悪性度の高い皮膚がんと診断され、転移の可能性がある場合には、リンパ節や他の臓器への転移の有無を調べるために、CTやMRI、PETといった画像検査を追加で行うことがあります。
検査により、がんの進行度(ステージ)を正確に把握し、最適な治療方針を決定します。メラノーマでは、治療方針を決定する上で画像検査が大変重要です。
心配なほくろが見つかったらどうすればいい?
ご自身のセルフチェックで、少しでもABCDEルールに当てはまるような心配なほくろを見つけたら、むやみに不安がる必要はありませんが、放置せずに適切な行動をとることが大切です。
まずは皮膚科を受診する
何よりもまず行うべきことは、皮膚科専門医のいる医療機関を受診することです。形成外科や美容外科などでもほくろの相談は可能ですが、皮膚がんの正確な診断、特にダーモスコピーを用いた専門的な診察は、皮膚科医の専門領域です。
インターネットの情報だけで自己判断したり、効果の不明な民間療法を試したりするのは絶対にやめましょう。
診断の結果もし皮膚がんであったとしても、早期であればあるほど治療の選択肢は多く、体への負担も少なく、完治する可能性も高くなります。
受診時に伝えるべきこと
診察を受ける際には、医師に正確な情報を伝えることが、適切な診断につながります。
問診のポイントに加え、もし可能であれば、ほくろの過去の写真(例えば、数年前の旅行の写真に写り込んでいるなど)があれば、変化の様子が客観的にわかるため、非常に有用な情報となります。
スマートフォンなどで、気になるほくろの写真を定期的に撮影し、日付とともに記録しておくのも良い方法です。
診断後の治療の流れ
診断の結果、良性のほくろであった場合は、医学的には治療の必要はありません。美容的な理由で切除を希望する場合は、炭酸ガスレーザーによる治療や、メスによる切除手術などの選択肢があります。
皮膚がんと診断された場合は、がんの種類や進行度に応じた標準的な治療を行います。基本的には、病変部を安全な範囲(マージン)を含めて完全に取り除くための外科手術が第一選択です。
手術の方法や入院の有無は、がんの種類や大きさ、場所によって異なります。
皮膚がんの主な治療法
| がんの種類 | 主な治療法 | 補足 |
|---|---|---|
| メラノーマ | 外科的切除(広範囲切除)、センチネルリンパ節生検 | 進行度に応じて薬物療法(免疫チェックポイント阻害薬など) |
| 基底細胞がん | 外科的切除 | 転移は稀。局所のコントロールが重要。 |
| 有棘細胞がん | 外科的切除 | 進行度に応じて放射線治療や薬物療法を併用。 |
皮膚がんを予防するためにできること
すべての皮膚がんを完全に予防することはできませんが、発症のリスクを減らすために日常生活でできることはあります。皮膚がんの最大の原因とされる紫外線から肌を守ることが、最も効果的な予防策です。
紫外線対策の重要性
皮膚がんの多くは、長年にわたって紫外線を浴び続けることによるDNAのダメージが蓄積して発症します。子供の頃に浴びた紫外線の総量が、将来の皮膚がん発症リスクに大きく影響すると言われています。
紫外線にはUVAとUVBがあり、UVBは皮膚の表面に強く作用して日焼けやシミの原因となり、UVAは皮膚の奥深くまで届いてシワやたるみの原因となりますが、両者ともに皮膚がんの発症に関与しています。
子供の頃から、生涯にわたって紫外線対策を習慣にすることが重要です。
紫外線対策法
- 日焼け止めの使用
- 帽子の着用
- 日傘の使用
- 長袖・長ズボンの着用
- サングラスの着用
日焼け止めの正しい選び方と使い方
日焼け止めは、日常生活ではSPF30、PA++程度、屋外でのレジャーやスポーツなど、日差しの強い場所で長時間過ごす場合はSPF50+、PA++++といったように、場面に応じて使い分けるのが効果的です。
また、表示されている効果を十分に得るためには、十分な量をむらなく塗りましょう。顔であればパール粒2個分程度が目安で、汗をかいたりタオルで拭いたりした後は、効果が落ちてしまうため、2〜3時間おきにこまめに塗り直すことが大切です。
紫外線は一年中降り注いでいるため、夏場だけでなく、年間を通して使用を心がけましょう。
定期的なセルフチェックの習慣
月に一度は、入浴後などに、全身の皮膚を自分でチェックする習慣をつけてください。明るい場所で、大きな鏡と手鏡を使って、正面だけでなく、背中、お尻、うなじ、頭皮、足の裏、指の間など、普段目の届きにくい場所もしっかりと観察します。
ABCDEルールを思い出しながら、新しくできたほくろはないか、既存のほくろに変化はないかを確認し、この地道なセルフチェックが、皮膚がんの早期発見に非常に有効です。
セルフチェックで確認する部位
| 部位 | 確認のポイント |
|---|---|
| 顔・首・頭皮 | 髪をかき分けて頭皮もしっかり見る |
| 腕・手・指・爪 | 手のひら、指の間、爪の下も忘れずに |
| 背中・お尻 | 手鏡や家族の協力を得て確認する |
よくある質問(FAQ)
ほくろと皮膚がんに関して、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
- 子供のほくろも皮膚がんになりますか?
-
子供に皮膚がん、特にメラノーマが発生することは極めて稀です。
子供のほくろは、体の成長とともに大きくなったり、色が濃くなったり、少し盛り上がってきたりすることがありますが、これはがん化ではなく、生理的な変化であることがほとんどです。
ただし、生まれつきある巨大なほくろ(巨大色素性母斑)は、将来的にメラノーマを発症するリスクが通常より高いため、定期的な皮膚科での経過観察が必要です。
過度な心配は不要ですが、急激な変化など気になることがあれば、一度皮膚科で相談すると安心です。
- ほくろを刺激するとがん化するというのは本当ですか?
-
ほくろを日常的にいじったり、誤って傷つけたりしたからといって、それが直接的な原因となって、良性のほくろが悪性化(がん化)するという明確な医学的根拠は現在のところありません。
しかし、もともと悪性であったメラノーマを、良性のほくろと勘違いして刺激し続けることで、出血したり、増殖を早めたりする可能性は考えられます。
いずれにせよ、気になるほくろはむやみに触らず、専門医の診察を受けることが最善です。
- 足の裏のほくろは危ないと聞きましたが本当ですか?
-
日本人のメラノーマは、足の裏に発生する頻度が最も高いことが知られているため、足の裏のほくろは危ないという説が広まっています。しかし、足の裏にあるほくろの全てが危険なわけではありません。
多くは、歩行による慢性的な刺激でできた良性のほくろです。重要なのは、場所がどこであれ、ABCDEルールに当てはまるような変化が見られるかどうかです。
足の裏は自分で観察しにくい場所なので、特に入浴時などに意識してチェックする習慣をつけると良いでしょう。
- ほくろ除去は皮膚科と美容外科、どちらが良いですか?
-
ほくろ除去の目的によって選択が異なります。まず大前提として、ほくろが悪性のものではないかを正確に診断することが最も重要です。皮膚がんの可能性がある場合、診断と治療は保険診療を行う皮膚科の専門領域です。
ダーモスコピーによる診察を受け、悪性の可能性が完全に否定された上で、純粋に美容的な目的で除去を考えるのであれば、美容外科や美容皮膚科も選択肢になります。
ただし、少しでも悪性の疑いがある場合や、診断に確信が持てない場合は、まず保険診療を行っている皮膚科を受診し、必要であれば病理検査も可能な切除手術を受けることが大切です。
以上
参考文献
Ali AR, Li J, Yang G. Automating the ABCD rule for melanoma detection: a survey. IEEE Access. 2020 Apr 28;8:83333-46.
Tanaka T, Yamada R, Tanaka M, Shimizu K, Oka H. A study on the image diagnosis of melanoma. InThe 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 2004 Sep 1 (Vol. 1, pp. 1597-1600). IEEE.
Lee JH, Park JH, Lee JH, Lee DY. Early detection of subungual melanoma in situ: proposal of ABCD strategy in clinical practice based on case series. Ann Dermatol Vol. 2018;30(1).
Levit EK, Kagen MH, Scher RK, Grossman M, Altman E. The ABC rule for clinical detection of subungual melanoma. Journal of the American Academy of Dermatology. 2000 Feb 1;42(2):269-74.
Rotte A, Bhandaru M. Melanoma—diagnosis, subtypes and AJCC stages. InImmunotherapy of melanoma 2016 Dec 22 (pp. 21-47). Cham: Springer International Publishing.
Nagaoka T, Nakamura A, Kiyohara Y, Sota T. Melanoma screening system using hyperspectral imager attached to imaging fiberscope. In2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 2012 Aug 28 (pp. 3728-3731). IEEE.
Kato J, Horimoto K, Sato S, Minowa T, Uhara H. Dermoscopy of melanoma and non-melanoma skin cancers. Frontiers in medicine. 2019 Aug 21;6:180.
Blum A, Rassner G, Garbe C. Modified ABC-point list of dermoscopy: a simplified and highly accurate dermoscopic algorithm for the diagnosis of cutaneous melanocytic lesions. Journal of the American Academy of Dermatology. 2003 May 1;48(5):672-8.
Togawa Y. Dermoscopy for the diagnosis of Melanoma: an overview. Austin J. Dermatol. 2017;4:1080.
Majumder S, Ullah MA. A computational approach to pertinent feature extraction for diagnosis of melanoma skin lesion. Pattern Recognition and Image Analysis. 2019 Jul;29(3):503-14.