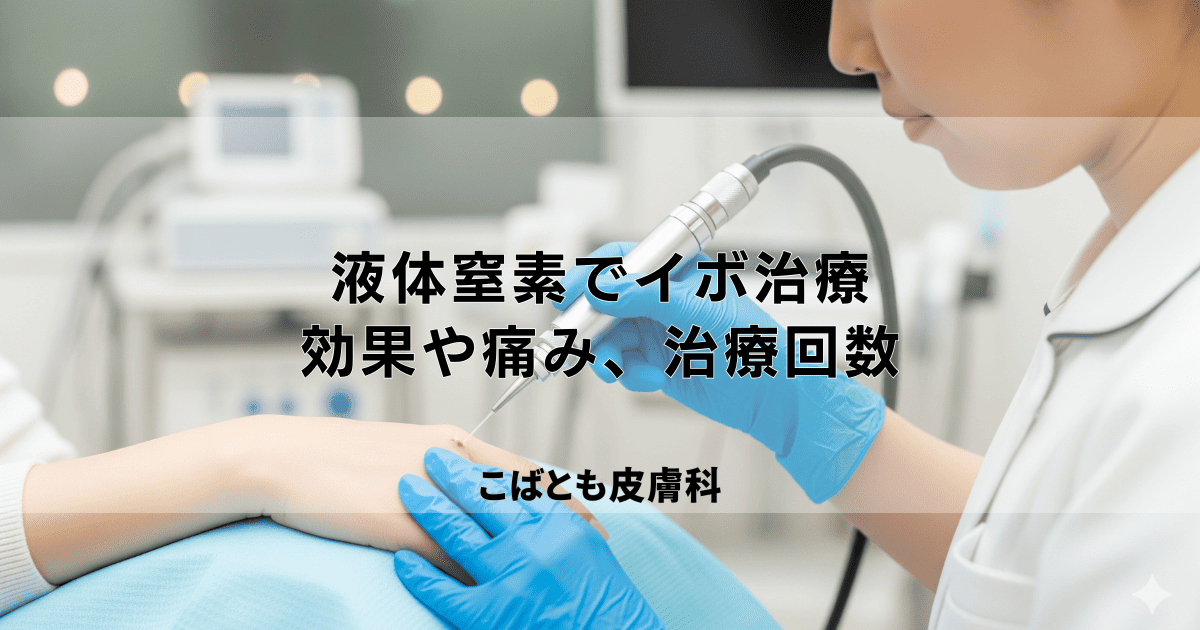ふと気づくと、指や足の裏に硬いできもの、それはウイルス性のイボかもしれません。イボは放置すると大きくなったり、他の場所にうつったりすることがあります。
皮膚科でのイボ治療にはいくつか方法がありますが、最も一般的に行われているのが液体窒素を用いた凍結療法で、マイナス196℃という超低温の液体窒素でイボの細胞を凍結させて壊すというものです。
この記事では、液体窒素治療の効果はいつから実感できるのか、治療には痛みが伴うのか、完治までには何回くらいの通院が必要なのか、といった皆さんの疑問に詳しくお答えします。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
イボとは何か?原因と種類
イボと一言でいっても、実はさまざまな種類があり、原因も異なり、多くの人が魚の目やタコと混同しがちですが、正体は全く別のものです。正しい治療を行うためには、まずイボの正体を知ることが大切です。
イボの正体はウイルス感染症
一般的にイボと呼ばれるものの多くは、尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)という皮膚の病気です。これは、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスが、皮膚にあるごく小さな傷口から侵入して感染することで発症します。
感染した細胞は異常に増殖し、皮膚の表面が盛り上がって硬いできものとなります。魚の目やタコは、特定の場所に継続的な圧力がかかることで角質が厚くなるもので、ウイルス感染が原因ではありません。
イボの種類と見分け方
イボにはいくつかの種類があり、それぞれ見た目やできやすい場所に特徴があります。皮膚科では、医師が視診でどの種類のイボかを判断し、治療方針を決定します。
イボの主な種類と特徴
| 種類 | よくできる場所 | 見た目の特徴 |
|---|---|---|
| 尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい) | 手足、指、膝、肘 | 表面がザラザラした硬い盛り上がり。最も一般的なタイプ。 |
| 足底疣贅(そくていゆうぜい) | 足の裏 | 体重で押されて平ら。よく見ると黒い点々(血管の血栓)が見える。 |
| 扁平疣贅(へんぺいゆうぜい) | 顔、首、手の甲 | 肌色か薄茶色で、平たく少し盛り上がる。若い女性に多い。 |
特に足の裏にできる足底疣贅は、魚の目と間違われやすいですが、削ると点状の出血が見られるのが特徴で、自分で判断せず、皮膚科専門医に相談することが重要です。
なぜイボはうつるのか
イボはウイルスが原因であるため、感染力を持っています。イボを触った手で体の他の部分を触ると、小さな傷があればウイルスが入り込み、新しいイボができてしまうことがあり、これを自家接種と呼びます。
また、家族など他の人との接触によってもうつる可能性があり、特に皮膚のバリア機能が低下している場合や、湿った環境では感染しやすいです。
感染の主なきっかけ
- プールや公衆浴場の足ふきマット
- 家族間でのタオルやスリッパの共有
- イボを自分でいじったり、削ったりすること
- カミソリでの自己処理
感染を防ぐためには、イボをむやみに触らないこと、そして家族と生活用品を共有しないように心がけることが大切です。
放置するリスク
小さなイボだからと油断して放置すると、さまざまな問題が生じる可能性があります。まず、ウイルスが増殖し、イボが徐々に大きくなったり、数が増えたりします。
足の裏のイボは、大きくなると歩くときに痛みを伴うようになり、日常生活に支障をきたすこともあり、また、見た目が気になるだけでなく、知らず知らずのうちに周りの人にうつしてしまうリスクも高まります。
イボに気づいたら、数が少なく、小さいうちに治療を始めることが、早期治癒への近道です。自己判断で市販薬を使い続けると、かえって悪化させることもあるため、早めに皮膚科を受診しましょう。
皮膚科で行うイボの液体窒素治療(凍結療法)とは
皮膚科でのイボ治療として、最も標準的に行われているのが液体窒素を用いた凍結療法で、非常に低い温度を利用してイボの組織を破壊します。
多くの皮膚科クリニックで採用されており、保険適用で受けられる手軽さから、第一選択肢となることが多い治療法です。
液体窒素治療の基本的な考え方
液体窒素治療は、マイナス196℃の液体窒素を綿棒やスプレー式の器具に含ませ、イボに直接当てることで、ウイルスに感染した細胞ごと凍結させる治療法です。細胞は急激に凍結されると、内部の水分が氷の結晶となり、細胞膜が破壊されます。
この物理的な破壊によって、ウイルスに感染した異常な細胞を死滅させることが目的です。治療後、死滅した組織はかさぶたとなり、新しい皮膚が再生されるとともに自然に剥がれ落ち、イボを根本から取り除いていきます。
治療の流れ
皮膚科での液体窒素治療は、比較的短時間で完了し、事前の準備も特に必要ありません。一般的な治療の流れは以下のようになりますが、イボの状態によっては医師が処置を追加することもあります。
液体窒素治療の基本的な手順
| 手順 | 内容 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 診察と準備 | 医師がイボの状態を確認。角質が厚い場合は、メスやハサミで軽く削る。 | 1〜2分 |
| 2. 凍結処置 | 液体窒素を浸した綿棒をイボに数秒間押し当てる。これを数回繰り返す。 | 1〜5分 |
| 3. 処置後の説明 | 治療後の注意点や次回の来院時期について説明を受ける。 | 1〜2分 |
イボの大きさや数にもよりますが、処置自体の時間はごくわずかで、角質を削る際に痛みはほとんどありません。凍結処置を数回繰り返すのは、イボの組織の深部まで確実に凍結させるためです。
なぜ液体窒素がイボに効くのか
液体窒素がイボに効果的な理由は、単に細胞を物理的に破壊するだけではありません。
凍結によってダメージを受けた細胞は、体内で異物として認識され、体の免疫システムが活性化され、ウイルスに対する攻撃力が高まるという二次的な効果も期待できます。
液体窒素治療は、直接的な組織破壊と、間接的な免疫賦活作用という二つの側面からイボにアプローチし、この体の防御反応をうまく引き出すことが、再発を防ぎ、治療を成功させるための鍵です。
液体窒素治療のメリット
- 保険が適用されるため費用の負担が少ない
- 治療時間が短く、事前の麻酔が不要
- 傷跡が残りにくい
- 小さな子供や妊婦の方でも受けられる場合がある
これらのメリットから、多くのイボ治療で液体窒素が選ばれています。
液体窒素治療の効果と治療回数の目安
液体窒素治療を始めると、いつ効果が出るのか、何回くらい通院すれば治るのかは、誰もが気になるところです。治療の効果や必要な回数は、イボの大きさ、できた場所、そして個人の免疫力などによって大きく異なります。
治療効果が現れるまでの期間
液体窒素治療の効果は、治療直後に現れるわけではありません。治療後、イボは白く変化し、数時間から数日で赤黒くなり、水ぶくれやかさぶたを形成し、1〜2週間かけてかさぶたが自然に剥がれ落ちます。
このとき、イボの組織も一緒にはがれ落ちることで、イボが小さくなったり、色が薄くなったりといった変化が見られます。1回の治療で完全に治ることは稀で、通常はこのサイクルを何度も繰り返します。
効果のサインとして、イボの中心に見られる黒い点々(血栓化した毛細血管)が減ってくることが挙げられ、これがなくなれば、治癒が近い証拠です。
完治までの平均的な治療回数
イボ治療は根気が必要です。完治までの回数は個人差が大きいですが、一般的な目安としては5回から10回程度の治療を要することが多いです。数回の治療で治る人もいれば、難治性で20回以上の治療が必要になる人もいます。
特に、ウイルスが深く根を張っている場合や、長年放置していたイボは治療に時間がかかる傾向があります。医師は毎回イボの状態を観察し、治療の効果を見ながら今後の計画を立てていきます。
途中で諦めずに、医師の指示に従って治療を続けることが何よりも大切です。
イボの大きさや場所による回数の違い
治療回数は、イボの大きさやできた場所によっても変わり、小さくてできたばかりのイボは、比較的少ない回数で治りやすいです。
大きくて角質が厚いイボ、特に体重がかかる足の裏のイボは、液体窒素の冷却効果が深部まで届きにくいため、治療に時間がかかることが多くなります。
部位や大きさによる治療回数の目安
| イボの状態 | 特徴 | 治療回数の傾向 |
|---|---|---|
| 小さく新しいイボ(直径5mm未満) | 指先など角質が薄い場所 | 少ない(5回前後) |
| 大きいイボ(直径1cm以上) | 長期間放置している | 多い(10回以上) |
| 足の裏のイボ | 角質が厚く、ウイルスが深い | 非常に多い(15回以上) |
また、顔や首などの皮膚が薄い場所では、 瘢痕のリスクを避けるために、一度の治療を弱めに行うことがあり、治療回数が多くなることもあります。
治療間隔の重要性
液体窒素治療は、適切な間隔を空けて継続することが効果を高める上で非常に重要です。一般的には、1〜2週間に1回のペースで通院します。
この間隔は、治療によってダメージを受けた皮膚が回復し、次の治療を受けられる状態になるまでの時間に基づいています。間隔が空きすぎると、その間にウイルスが再び増殖してしまい、治療が振り出しに戻ってしまう可能性があります。
逆に、間隔が短すぎても、皮膚への負担が大きくなりすぎるため良くありません。医師から指示された通院スケジュールを守ることが、効率的な治療につながります。
液体窒素治療に伴う痛みと副作用
液体窒素治療は効果的な方法ですが、痛みや副作用が全くないわけではありません。痛みへの対処法や、副作用が現れた際の適切なケアについて知っておきましょう。
治療中の痛みの程度
液体窒素を当てている最中やその直後には、ピリピリとした、あるいは焼けるような痛みを感じることが一般的で、これは、超低温によって皮膚の細胞が凍傷を起こすために生じる正常な反応です。
痛みの感じ方には個人差が大きく、イボの場所によっても異なり、皮膚が薄い指先などは痛みを感じやすく、角質が厚い足の裏は比較的痛みを感じにくい傾向があります。
痛みの強さの目安(個人差があります)
| 場所 | 痛みの感じやすさ | 痛みの特徴 |
|---|---|---|
| 指先、爪の周り | 強い | 鋭く、響くような痛み |
| 手のひら、手の甲 | 中程度 | ジンジン、ピリピリする痛み |
| 足の裏 | 弱い〜中程度 | 鈍い痛み、圧迫感 |
治療中の痛みは数秒から数分で終わりますが、痛みに弱い方や小さなお子様の場合は、医師に相談することで治療の強さを調整してもらえることもあります。
治療後の痛みと対処法
治療後の痛みは、数時間から長い場合で1〜2日続くことがあり、ズキズキとした拍動性の痛みが特徴です。多くの場合、日常生活に大きな支障はありませんが、痛みが強い場合は我慢せずに適切な対処をしましょう。
まずは、保冷剤などをタオルで包み、患部を冷やすと痛みが和らぎ、それでも痛みが収まらない場合や、夜眠れないほど痛む場合は、市販の鎮痛剤(アセトアミノフェンやイブプロフェンなど)を服用することも一つの方法です。
ただし、薬を服用する際は、必ず用法用量を守ってください。心配な場合は、治療を受けたクリニックに電話で相談しましょう。
水ぶくれができた場合のケア
液体窒素治療後によく見られる副作用の一つに、水ぶくれ(水疱)があり、凍結によって皮膚の組織がダメージを受け、その下に体液が溜まることで生じます。水ぶくれは治療がしっかり効いている証拠でもありますが、扱いには注意が必要です。
水ぶくれは、外部の刺激や細菌から傷口を守る役割を果たしているため、自分で潰したり、針で刺したりするのは絶対にやめてください。
中の液体にはウイルスは含まれていませんが、無理に破るとそこから細菌が入り込み、感染症(化膿)を起こす原因になります。自然に破れた場合は、清潔なガーゼで保護し、クリニックに相談しましょう。
大きな血豆(血疱)ができて痛みが強い場合も、自己判断せず受診してください。
その他の副作用と注意点
水ぶくれ以外にも、いくつかの副作用が起こる可能性があります。
治療後の主な副作用と対処法
| 副作用 | 症状 | 対処法 |
|---|---|---|
| 色素沈着 | 治療部位がシミのように茶色くなる。 | 数ヶ月から1年程度で自然に薄くなることが多い。紫外線対策が重要。 |
| 色素脱失 | 治療部位が白く色が抜ける。 | 回復しにくいことがある。強い治療で起こりやすい。 |
| 瘢痕(はんこん) | 治療部位が傷跡として残る。 | ケロイド体質の人は注意が必要。医師に事前に伝える。 |
副作用のリスクはゼロではありませんが、皮膚科医は、イボの状態や部位に応じて治療の強さを適切に調整することで、リスクを最小限に抑えるよう努めます。何か気になる変化があれば、遠慮なく相談しましょう。
液体窒素治療後の経過とアフターケア
液体窒素治療は、治療そのものだけでなく、治療後の経過を正しく理解し、適切なアフターケアを行うことが非常に重要です。
治療後の皮膚がどのように変化していくのか、そして日常生活でどのような点に気をつければよいのかを知ることで、回復を早め、再発を防ぐことにつながります。
治療直後からかさぶたになるまで
治療後の皮膚は、時間とともに変化していきます。
治療後の一般的な経過
| 期間 | 皮膚の状態 |
|---|---|
| 治療直後〜数時間 | 赤み、腫れ、痛みが出る。 |
| 治療後1〜3日 | 水ぶくれや血豆(血疱)ができることがある。 |
| 治療後3日〜1週間 | 水ぶくれが徐々にしぼみ、黒っぽいかさぶたになる。 |
この期間は、患部を清潔に保つことが大切です。水ぶくれができていなければ、特に絆創膏などで保護する必要はありませんが、衣類などで擦れる場所はガーゼなどで保護するとよいでしょう。
かさぶたが取れた後の皮膚の状態
治療後1〜2週間ほどで、かさぶたは自然に剥がれ落ち、このとき、無理に剥がさないように注意してください。無理に剥がすと、新しくできている皮膚を傷つけたり、まだ残っているウイルスを広げてしまったりする可能性があります。
かさぶたが取れた後の皮膚は、ピンク色で少しへこんでいるように見えることがありますが、これは正常な治癒の過程です。
時間とともに周りの皮膚と同じ色、同じ高さに戻っていき、かさぶたが取れた時点でイボが完全になくなっていることもあれば、まだ芯が残っていることもあります。残っている場合は、次回の治療で再度凍結処置を行います。
日常生活での注意点
液体窒素治療を受けた当日から、日常生活に大きな制限はありませんが、いくつか注意すべき点があります。
治療後の日常生活での注意
- 入浴は当日から可能ですが、患部を強くこすらないようにしましょう。
- 運動も基本的には問題ありませんが、痛みが強い場合や足の裏の治療で大きな水ぶくれができた場合は控えましょう。
- プールは、患部が完全に治癒するまでは控えるのが望ましいです。
- 患部への紫外線対策を心がけ、色素沈着を防ぎましょう。
医師から特別な指示があった場合は、従ってください。特に、水ぶくれが破れたり、化膿の兆候が見られたりした場合は、速やかにクリニックに連絡しましょう。
再発を防ぐために大切なこと
イボ治療で最も重要なことの一つが、再発を防ぐことです。液体窒素治療で見た目上イボがなくなったように見えても、皮膚の深いところにウイルスが残っていると、しばらくして再発することがあります。
再発を防ぐためには、医師が完治と判断するまで、自己判断で治療を中断しないことが不可欠です。
再発予防のために心がけたいこと
- 医師の指示通りに通院を続ける
- 皮膚を清潔に保ち、保湿を心がける
- 小さな傷を作らないように注意する
- 栄養バランスの取れた食事と十分な睡眠で免疫力を維持する
イボは、皮膚のバリア機能が低下し、体の免疫力が落ちているときにできやすくなります。日頃から健康的な生活を送り、皮膚の健康を保つことが、根本的な再発予防につながります。
液体窒素以外のイボ治療法との比較
液体窒素治療はイボ治療の基本ですが、イボの種類、場所、個人の体質などによっては、他の治療法が選択されることや、併用されることがあります。代表的な治療法をいくつか紹介し、液体窒素治療と比較してみましょう。
サリチル酸(塗り薬・貼り薬)
サリチル酸は、角質を軟化させて溶かす作用を持つ薬剤です。スピール膏という商品名で市販もされていますが、皮膚科ではより高濃度のものを処方でき、硬くなったイボの角質を柔らかくし、少しずつ剥がしていくことで治療します。
角質が厚くなる足の裏のイボや、痛みに弱い子供の治療で液体窒素治療と併用されることが多いです。毎日交換する必要があるため手間がかかりますが、痛みがほとんどないのが大きなメリットです。
ただし、効果は緩やかで、治癒までには時間がかかります。
レーザー治療
レーザー治療には、炭酸ガスレーザーや色素レーザーなど、いくつかの種類があります。炭酸ガスレーザーは、イボを蒸散させて削り取る方法で、一度の治療で除去できることが多いのが特徴です。
色素レーザーは、イボに栄養を送っている血管を破壊することで、イボを兵糧攻めにする方法です。レーザー治療は、液体窒素治療で効果が見られない難治性のイボや、多数のイボを一度に治療したい場合に適しています。
ただし、多くの場合、保険適用外で自費診療となるため、費用が高額になる傾向があり、また、治療後には傷跡が残るリスクや、色素沈着が起きる可能性があります。
電気焼灼法
電気焼灼法は、電気メスを使ってイボを焼き切る治療法です。局所麻酔をした後に行うため、治療中の痛みはありません。比較的大きなイボや、茎のように飛び出したイボの治療に用いられることがあります。
レーザー治療と同様に、一度で除去できることが多いですが、治療後に傷跡が残りやすく、保険適用にならない場合もあります。
他の治療法とのメリット・デメリット比較
どの治療法を選ぶかは、イボの状態や患者さんの希望を考慮して、医師が総合的に判断します。それぞれの治療法の特徴を比較してみましょう。
主なイボ治療法の比較
| 治療法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 液体窒素治療 | 保険適用、短時間、傷跡が残りにくい | 痛みを伴う、複数回の通院が必要 |
| サリチル酸 | 痛みが少ない、自宅で処置可能 | 治療期間が長い、皮膚がかぶれることがある |
| レーザー治療 | 一度で終わることが多い、難治性イボに有効 | 自費診療で高額、傷跡や色素沈着のリスク |
他にも、ヨクイニン(ハトムギのエキス)の内服を併用して免疫力を高める方法や、ブレオマイシンという薬剤を局所注射する方法など、さまざまな選択肢があります。
まずは基本となる液体窒素治療を受け、効果を見ながら他の治療法を検討するのが一般的です。
皮膚科を受診するタイミングとクリニックの選び方
イボに気づいたとき、市販薬で様子を見るべきか、すぐに病院に行くべきか迷う方も多いでしょう。ここでは、受診のタイミングと、安心して治療を任せられるクリニック選びのポイントについて解説します。
イボに気づいたら早めに受診を
結論から言うと、イボと疑われるできものを見つけたら、できるだけ早く皮膚科を受診することをお勧めします。イボはウイルス性のため、放置している間に大きくなったり、数が増えたり、家族にうつしてしまったりする可能性があるからです。
特に、以下のケースに当てはまる場合は、早急に専門医の診察を受けてください。
- 急速に大きくなっている
- 数が増えている
- 痛む、出血する
- 顔やデリケートな部分にできた
自分で魚の目かイボか判断がつかない 早期に治療を開始すれば、それだけ治療期間も短く、費用や体の負担も少なく済みます。
市販薬との違い
ドラッグストアでは、イボに効能があるとされる市販薬(サリチル酸絆創膏など)が販売されています。手軽に試せるため魅力的ですが、使用には注意が必要です。
市販薬は、ウイルスに感染していない周りの健康な皮膚まで傷つけてしまい、かえって炎症を広げたり、イボを悪化させたりするリスクがあります。
また、そもそもイボではない別の皮膚疾患(悪性の可能性も含む)であった場合、発見が遅れることにもなりかねません。皮膚科では、医師が正確な診断を下した上で、そのイボに最も適した治療法を選択します。
信頼できる皮膚科を選ぶポイント
イボ治療は、一度で終わらないことが多いため、継続して通いやすい、信頼できるクリニックを見つけることが大切です。
クリニック選びで確認したいポイント
- 皮膚科専門医が在籍しているか
- 治療法について丁寧に説明してくれるか
- 複数の治療選択肢を提示してくれるか
- 質問や相談がしやすい雰囲気か
- 通いやすい場所にあるか
よくある質問(Q&A)
最後に、イボの液体窒素治療に関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 治療は保険適用されますか?
-
はい、ウイルス性イボに対する液体窒素治療(凍結療法)は、健康保険が適用される標準的な治療で、費用の自己負担は1割から3割となります。
治療費は、イボの数や大きさによって多少変動し、初診料や再診料、処方箋料などが別途必要です。
保険適用と自費診療の料金目安(3割負担の場合)
項目 料金の目安 備考 液体窒素治療 約700円〜1,500円 イボの数により変動。 初診料・再診料 約1,000円〜3,000円 別途必要。 レーザー治療 約5,000円〜(1個) 多くは自費診療。 詳細な費用については、受診するクリニックに直接お問い合わせください。
- 子供でも液体窒素治療は受けられますか?
-
小さなお子様のイボ治療にも液体窒素は用いられますが、治療には痛みを伴うため、お子様が治療に耐えられるかどうかが一つの判断基準になります。
痛みのために治療が難しい場合は、無理に行わず、サリチル酸の外用など、痛みの少ない他の治療法を選択することもあります。
医師がお子様の年齢や性格、イボの状態を総合的に判断し、保護者の方と相談しながら最適な治療法を決めていきます。
- 治療した日に運動やお風呂は入れますか?
-
治療当日の入浴やシャワーは問題ありません。ただし、患部をゴシゴシこすらず、優しく洗い流すようにしてください。
運動についても、痛みがなければ特に制限はありませんが、足の裏を治療した場合や、大きな水ぶくれができて痛みが強い場合は、当日の激しい運動は避けた方が無難です。
- 顔やデリケートな部分のイボも治療できますか?
-
顔や首、陰部などのデリケートな部分にできたイボも液体窒素治療の対象です。ただし、これらの部位は皮膚が薄く、色素沈着や傷跡が残りやすいため、より慎重な治療が求められます。
医師は、治療の強さを通常よりも弱めに設定したり、治療間隔を調整したりするなど、副作用のリスクを最小限に抑えるための工夫をするため、体の他の部分に比べて治療回数が多くなる傾向があります。
美容的な側面も重要になるため、治療前に医師とよく相談し、納得の上で治療を進めることが大切です。
以上
参考文献
Hutchinson PE, Bleiker TO. Liquid nitrogen cryotherapy of common warts: cryo‐spray vs. cotton wool bud. British Journal of Dermatology. 2002 Jun;146(6):1110-.
Shimizu A, Mieko K, Yamaguchi K, Niwa O, Ishigaki Y, Sakurai M. Detection of human papillomavirus in plantar warts and its impact on outcome. The Journal of Dermatology. 2025 Jan;52(1):175-8.
Tagami H, Aiba S, Rokugo M. Regression of flat warts and common warts. Clinics in Dermatology. 1985 Oct 1;3(4):170-8.
Khozeimeh F, Alizadehsani R, Roshanzamir M, Khosravi A, Layegh P, Nahavandi S. An expert system for selecting wart treatment method. Computers in biology and medicine. 2017 Feb 1;81:167-75.
Lipke MM. An armamentarium of wart treatments. Clinical medicine & research. 2007 Jan 8;4(4):273-93.
Mulhem E, Pinelis S. Treatment of nongenital cutaneous warts. American family physician. 2011 Aug 1;84(3):288-93.
Dall’Oglio F, D’Amico V, Nasca MR, Micali G. Treatment of cutaneous warts: an evidence-based review. American journal of clinical dermatology. 2012 Apr;13(2):73-96.
Berth‐Jones J, Hutchinson PE. Modern treatment of warts: cure rates at 3 and 6 months. British Journal of Dermatology. 1992 Sep 1;127(3):262-5.
Berman B, Weinstein A. Treatment of warts. Dermatologic Therapy. 2000 Sep;13(3):290-304.
García‐Oreja S, Álvaro‐Afonso FJ, García‐Álvarez Y, García‐Morales E, Sanz‐Corbalán I, Lazaro Martinez JL. Topical treatment for plantar warts: A systematic review. Dermatologic therapy. 2021 Jan;34(1):e14621.