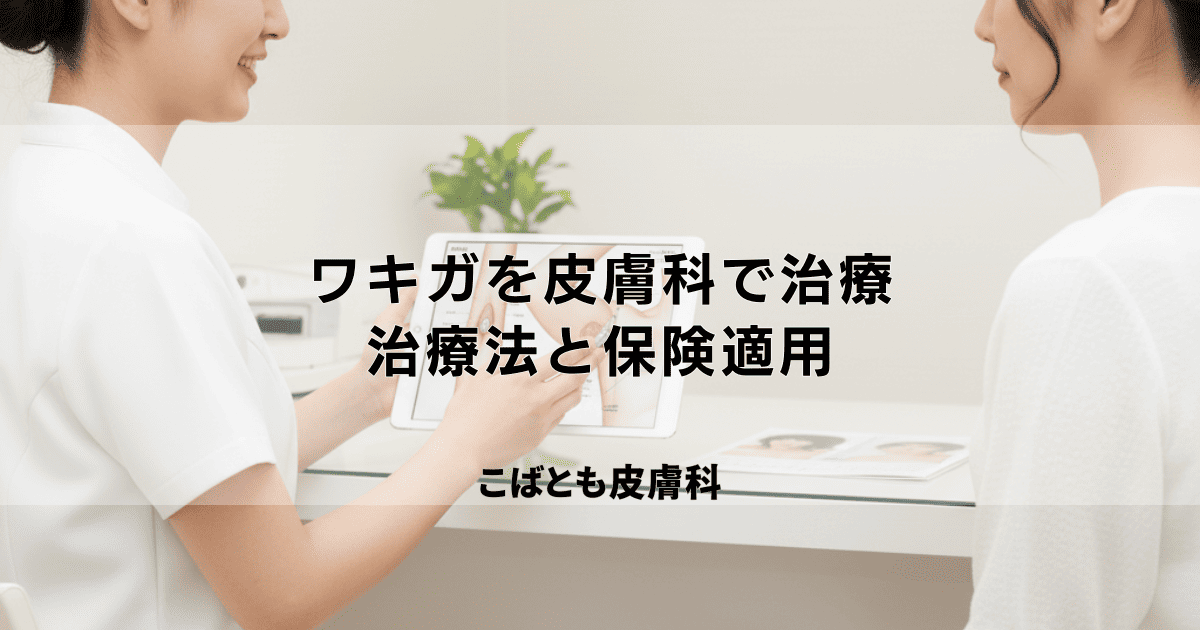自分のニオイはなかなか気づきにくいものですが、ふとした瞬間にワキのニオイが気になり、強い不安を感じる方は少なくありません。
人混みや密室、緊張する場面では「周りの人に気づかれているのではないか」と過剰に意識してしまい、対人関係に消極的になってしまうこともあります。
ワキガは皮膚科の診断と専門的な治療を受けることで、悩みを大きく軽減し、自信を取り戻すことが可能です。
この記事では、ワキガが発生する根本的な原因やご自身でできるチェック方法、皮膚科で行われる治療法の内容や費用について、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
ワキガ(腋臭症)とはどのような状態か
ワキガは医学的に腋臭症(えきしゅうしょう)と呼ばれ、ワキの下から独特の強いニオイが発生する状態です。
エクリン腺とアポクリン腺という性質の異なる2種類の汗腺があり、ワキガのニオイには、このうちのアポクリン腺から分泌される汗が深く関わっています。
ニオイが発生する仕組みと原因
ワキガのニオイの主な発生源であるアポクリン腺は、生まれた時から活動しているわけではありません。
思春期を迎え、性ホルモンの分泌が活発になるとともに、アポクリン腺も刺激を受けて活動を開始するため、幼少期には全く気にならなかったニオイが、中学生や高校生になる頃から急に強くなり、本人や周囲が気づき始めるケースが多いです。
アポクリン腺の数や大きさ、活動の活発さは、生まれつきの遺伝的要素によってほぼ決まっていて、両親のどちらかがワキガ体質である場合、体質は子供にも遺伝する確率が高くなる傾向にあります。
また、精神的なストレスや緊張を感じた時にかく精神性発汗も、アポクリン腺を強く刺激するため、緊張する場面で一時的にニオイが強まることがあります。
さらに、日々の食生活も影響を与えます。肉類や乳製品など動物性のタンパク質や脂質を多く含む食事を続けていると、アポクリン腺が刺激されやすくなり、ニオイを増強させる一因です。
2つの汗腺の違い
| 特徴 | エクリン腺 | アポクリン腺 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 体温調節のための発汗 | フェロモンの名残、個体の識別 |
| 汗の成分 | 99%以上が水分、わずかな塩分 | タンパク質、脂質、糖質、鉄分など |
| 分布場所 | 唇や爪などを除く全身の皮膚 | ワキの下、耳の中、乳輪、デリケートゾーン等 |
| ニオイ | 分泌直後はほぼ無臭 | 独特の強いニオイ(スパイシー臭、ミルク臭など) |
多汗症との違いについて
ワキガとよく混同されやすい症状に多汗症があります。多汗症は、体温調節に必要な量を超えて、エクリン腺から異常に多くの汗が分泌される状態です。ワキの下だけでなく、手のひらや足の裏、頭部などにも現れることがあります。
多汗症の汗は水分がほとんどでニオイ自体は少ないのですが、もしワキガ体質の方が多汗症を併発している場合、問題が複雑です。
大量のエクリン汗が、アポクリン腺から出たニオイの元となる濃い汗をワキ全体、あるいは衣服へと広範囲に広げてしまうため、ニオイが周囲に拡散しやすくなり、より強く感じられてしまいます。
自分でできる簡単なセルフチェック
自分がワキガかもしれないと気になった場合、いくつかの特徴的なサインを確認することで、ある程度の目安をつけることができますが、あくまで簡易的な自己チェックであり、医学的な確定診断ではありません。
正確な状態を知るには、専門知識を持った皮膚科医による診察が不可欠で、特に耳垢の状態は、アポクリン腺の活動レベルを知る上で非常に信頼性の高い指標となります。
アポクリン腺は耳の中(外耳道)にも多く分布しているため、ワキガ体質の方は耳の中のアポクリン腺も活発で、耳垢が湿ってキャラメル状になっていることが多いです。
ワキガ体質の可能性チェックリスト
- 耳垢が常に湿っている(キャラメル状、またはドロドロしている)
- 両親や兄弟、祖父母など血縁者にワキガの人がいる
- 白いシャツや下着のワキ部分に、洗っても落ちにくい黄ばみができる
- 第二次性徴(思春期)を迎えてから急にニオイが気になりだした
- 緊張やストレスを感じると、ワキから冷や汗のようなベタっとした汗が出る
皮膚科専門医による診断方法
皮膚科では、患者さんの主観的な悩みだけでなく、客観的な医学的所見に基づいて総合的にワキガの診断を行います。問診、視診、触診に加え、実際にニオイの程度を確認する検査を行うことで、より確実な診断へと導きます。
問診で確認する重要なポイント
初診時の問診では、ニオイが気になり始めた時期、ご家族に同様の症状を持つ方がいるか(遺伝的背景の確認)、季節や状況によるニオイの変化、普段行っている対策(制汗剤の使用頻度や種類)などを確認します。
また、過去にかかった大きな病気や手術歴、現在服用中の薬、アレルギー体質の有無なども、安全に治療を進める上で欠かせない情報です。
手術を視野に入れている場合は、出血傾向がないか、麻酔薬に対するアレルギーがないかなどを慎重に確認します。
ガーゼテストによる客観的な評価
診断において最も直接的かつ重要なのが、実際のニオイの確認です。多くのクリニックで行われるガーゼテストは、清潔なガーゼを患者さんのワキに数分間挟んでいただき、ガーゼに移ったニオイを医師が直接嗅いで判定する方法です。
より正確な状態を把握するため、少し運動をして汗をかいた後に実施することもあります。このテストにより、ニオイの有無だけでなく、強さを客観的なレベルで評価することが可能です。
ニオイの強さの判定基準
| レベル | 状態 | 周囲への影響と判定 |
|---|---|---|
| 軽度 | 鼻をワキに直接近づけると、わずかにニオイがわかる程度。 | 日常生活で他人が気づくことはほとんどありません。 |
| 中等度 | 電車で隣に座るなど、近い距離(約50cm以内)にいるとニオイがわかる。 | 密室や近距離での会話時に、周囲の人が気づく可能性があります。 |
| 重度 | 部屋に入ってきただけでニオイがわかる、あるいは離れていても強くニオイを感じる。 | 多くの人が容易に気づき、本人の社会生活に支障をきたす可能性があります。 |
視診と触診でわかること
医師は、ワキの下の皮膚の状態も詳細に観察します。アポクリン腺が発達している方は、ワキ毛が太く濃い傾向にあり、一つの毛穴から複数の毛が生えていたり、毛穴自体が大きく目立ったりすることがあります。
また、長年の衣類との摩擦や自己処理の影響で、ワキの皮膚に色素沈着が見られることも少なくありません。触診では、皮膚の厚みや柔らかさ、皮下組織の状態を確認します。
これは、もし手術を行うことになった場合、皮膚をどのように切開し、どの程度の範囲を剥離(はくり)する必要があるか、術後の回復は順調に進みそうかなどを予測するための重要な材料です。
皮膚科で受けられる主な治療法
皮膚科で行うワキガ治療には、ニオイの強さ、患者さんの希望するゴール(完全にニオイをなくしたいのか、気にならない程度に減らしたいのか)、許容できるダウンタイム、予算などに応じて、多彩な選択肢があります。
外用薬や制汗剤による保存的療法
比較的軽度のワキガの方や、手術や痛みを伴う治療を今は希望しないという方には、まず医療機関専用の外用薬を用いた保存的療法から開始し、よく処方されるのが塩化アルミニウム液です。
この薬剤は、汗腺の出口に作用して一時的に角栓(フタ)を作り、物理的に汗の出口を塞ぐことで発汗を強力に抑制し、汗の絶対量が減ることで、ニオイの拡散も抑えられます。
また、ワキガの原因菌を殺菌・抑制する抗生物質入りのクリームや、ニオイ物質の発生を抑える外用薬などを併用することもあります。
ただし、効果はあくまで使用している間だけの一時的なものです。
注射による多汗症・ワキガ治療
ボツリヌス菌が作り出す天然のタンパク質(ボツリヌストキシン)を有効成分とする薬剤を、ワキの皮膚の浅い部分に数カ所注射する治療法です。
ボツリヌス菌には、脳から汗腺に伝えられる「汗を出せ」という神経の指令をブロックする働きがあり、主にエクリン腺からの発汗を劇的に抑える効果が高く、多汗症治療の第一選択肢として広く行われています。
ワキガの方の場合、アポクリン腺への直接的な効果は限定的ですが、エクリン汗が減ることでニオイが周囲に拡散しにくくなり、またワキの下の湿気が減ることで細菌が繁殖しにくい環境になるため、ニオイが軽減される効果が期待できます。
注射は5〜10分程度で終了し、当日からほぼ普段通りの生活ができますが、効果は永続的ではなく、個人差はありますが通常4ヶ月から9ヶ月程度です。
医療機器を用いた切らない治療
「手術は怖いけれど、長期間続く効果が欲しい」という方に人気なのが、マイクロ波や超音波などのエネルギーを利用した医療機器による治療です。
代表的なミラドライなどは、皮膚の上から特定の波長のエネルギーを照射し、熱によって皮下にあるアポクリン腺とエクリン腺の両方を破壊します。一度熱で破壊された汗腺は基本的に再生しないため、手術に準ずる半永久的な効果が期待できます。
皮膚を切開しないため、術後の固定が不要か、あってもごく短期間で済み、翌日から仕事や学校に行けるなど、日常生活への影響が非常に少ないのが大きなメリットです。
根本的な解決を目指す手術療法
ニオイの元凶であるアポクリン腺を、物理的に体外へ取り除いてしまう手術で、現在、最も確実な効果が得られる治療法です。
医師が直接ワキの皮膚の下を目で見て、一つひとつアポクリン腺を除去していくため、取り残しが非常に少なく、高い完治率を誇ります。
その反面、皮膚を切開するため、どうしてもワキの下に数センチの傷跡が残るリスクがあります。
また、術後は皮膚と皮下組織をしっかり癒着させるために、1週間程度ワキを強く固定して安静を保つ必要があり、その間は腕を上げる動作などが大きく制限されます。
仕事や学業を一定期間休む必要があるなど、スケジュールの調整が必要になる点も考慮しなければなりません。
主な治療法の特徴比較
| 治療法 | 効果の持続性 | ダウンタイム(回復期間) | 傷跡のリスク |
|---|---|---|---|
| 外用薬・制汗剤 | 一時的(使用継続が必要) | なし | なし |
| 注射治療(ボトックス等) | 数ヶ月~半年程度(反復が必要) | ほぼなし(当日からシャワー可) | 注射針の跡が数日残る程度 |
| 医療機器治療(ミラドライ等) | 半永久的 | 数日~1週間程度(腫れ・痛み) | ほとんどなし |
| 手術療法(剪除法) | 半永久的 | 1~2週間程度(固定・安静が必要) | ワキのシワに沿って残る可能性あり |
保険適用となる剪除法(皮弁法)
日本国内のワキガ治療において、一定の基準を満たす場合に健康保険が適用される標準的な手術が「剪除法(せんじょほう)」、別名「皮弁法(ひべんほう)」です。
ニオイの原因を物理的に除去するため、現在行われている様々なワキガ治療の中で、最も確実性が高く、再発率も低い治療法と位置づけられています。
保険適用となる条件
すべてのワキガ治療に保険が適用されるわけではなく、剪除法が保険適用となるには、医師の診察によって明確に腋臭症(ワキガ)であると診断される必要があります。
単に本人が「ニオイが気になる」と感じているだけでは不十分で、ニオイが医学的に見て「悪臭が著しく、他人の就業や日常生活に支障を生じる事実がある」と判断されるほどの、中等度から重度の症状であることが条件です。
問診での日常生活への影響度の確認に加え、ガーゼテストで医師が実際に強いニオイを確認することなどが判断基準となります。
軽度のワキガと診断された場合は、保険適用外(自由診療)となることもあるため、まずは診察を受けてご自身の症状が保険適用の対象となるかを医師に確認してもらうことが第一歩です。
剪除法の手術費用と目安
保険が適用される場合、手術費用の患者負担額は原則として医療費総額の3割となります。
医療機関の規模や地域によって多少の変動はありますが、目安として片ワキの手術で約2万円前後、両ワキ同時に行う場合で約4万円前後となることが一般的です。
これに加え、初診料、再診料、術前に行う血液検査などの検査費用、術後の感染予防のための抗生物質や痛み止めの薬代、ガーゼ代などが別途必要になります。
また、入院設備のある病院で手術を受け、数日間の入院を選択した場合は、入院に関する費用も加算されます。
手術の流れと術後の経過
手術は通常、局所麻酔で行われ、意識ははっきりしていますが、ワキの痛みは感じません。手術時間は、両ワキで1時間半から2時間程度で、手術が終わった直後から、大切な術後ケアが始まります。
皮膚の下に血液が溜まって血腫(けっしゅ)ができるのを防ぎ、剥離した皮膚を再び皮下組織にしっかりと生着させるため、ワキの下にテニスボール大の綿球などを挟み、包帯やテープで強く圧迫固定します。
固定は非常に重要で、術後3日から1週間程度は継続し、その間、腕を肩より上に上げることができず、着替えや食事、入浴などの日常生活に大きな制限がかかります。
抜糸は術後1週間から2週間後に行われ、その後も数ヶ月は、皮膚が硬くなったり、つっぱり感があったり、色素沈着が残ったりすることがありますが、時間の経過とともに徐々に柔らかくなり、目立たなくなっていきます。
術後に注意が必要な期間の目安
| 時期 | ワキの状態 | 生活上の制限と注意点 |
|---|---|---|
| 術後当日~3日目 | 強力な圧迫固定中 | 絶対安静。腕を動かせないため、前開きの服が必要。入浴不可(下半身シャワーは可能な場合も)。 |
| 術後4日目~1週間 | 固定継続または少し軽めの固定へ | 腕の可動域はまだ制限される。医師の許可が出れば全身シャワーが可能に。 |
| 術後2週間目以降 | 抜糸完了、創部の回復期 | 日常生活はほぼ通常通りに戻るが、激しいスポーツや重い荷物を持つことはまだ控える。ワキのマッサージを開始することも。 |
自由診療によるワキガ治療
保険適用の剪除法は確実性が高い反面、術後の厳しい生活制限や、どうしても残ってしまう傷跡のリスクを伴うため、健康保険が適用されない自由診療(自費診療)での治療も多く選ばれています。
ボトックス注射の費用と特徴
ワキガ治療を目的としたボトックス注射は、多くの場合自由診療です(※重度の「原発性腋窩多汗症」の診断基準を満たす場合に限り、特定の製剤で保険適用となることがあります)。
自由診療での費用は、使用する薬剤の種類(厚生労働省承認薬か、海外並行輸入品かなど)や注入量によって、1回あたり約3万円から10万円程度の幅があります。
施術時間は5〜10分程度と非常に短く、注射直後から普段通りの生活に戻れます。
ただし、効果は永続的ではないため、常に快適な状態を保つには半年に1回程度のペースで定期的に再施術を受ける必要があり、長期的な視点でのランニングコストを考慮に入れておくことが必要です。
ミラドライなど機械治療の費用と特徴
皮膚の外側からマイクロ波などのエネルギーを照射して汗腺を破壊するミラドライなどの治療は、切らない根本治療で、費用は両ワキ1回の施術で約20万円から40万円程度が相場です。
また、より確実な効果を求めて2回目の照射を行う場合の保証プランなどを設けているクリニックもあります。施術時間は麻酔や冷却時間を含めて約1時間から1時間半程度です。
術後の大掛かりな固定は不要で、当日からシャワーが可能、翌日からは仕事や学校にも復帰できるなど、日常生活への支障が最小限で済みます。術後に起こる腫れや痛み、皮膚の違和感は、多くの場合1〜2週間程度で自然に治まっていきます。
その他の自由診療による手術
クリニックによっては、独自の工夫を凝らした手術方法を自由診療で提供しているところもあります。
皮膚に開けた数ミリの小さな穴から細い管を挿入し、アポクリン腺をかき出したり吸い出す吸引法や、特殊な回転刃がついた器具を皮膚の下に入れて、内側から皮膚を薄く削り汗腺を除去するシェービング法(削除法)などがあります。
剪除法に比べて皮膚を切開する幅が小さく、傷跡が目立ちにくいというメリットがあります。
しかし、医師が直接目で見て確認しながら一つひとつ汗腺を取り除くわけではないため、剪除法と比較すると、どうしても汗腺の取り残しが生じるリスクがやや高いです。
自由診療を選ぶ主な理由
- 仕事や育児が忙しく、手術のためにまとまった長い休みを取ることが難しい
- ノースリーブの服や水着を着る機会が多く、ワキの下に目立つ傷跡を残したくない
- 術後の不自由な固定期間や、運動・入浴などの生活制限をできるだけ避けたい
- メスを使う手術に対する恐怖心が強く、より身体的負担の少ない方法を選びたい
- 定期的な通院回数を減らし、一度か二度の通院で治療を完結させたい
納得できる皮膚科の選び方
ワキガ治療は、担当する医師の技術や経験、クリニックの設備によって、治療結果や満足度が大きく左右されます。
後悔のない治療を受けるためには、単に「費用が安いから」「家から近いから」といった理由だけで選ぶのではなく、信頼できる医療機関を慎重に見極めることが大切です。
クリニック選びで確認したいポイント
まず、担当医が「日本皮膚科学会認定 皮膚科専門医」や「日本形成外科学会認定 形成外科専門医」といった資格を持っているかを確認することは、一定の技術水準を知る一つの目安です。
また、クリニックの公式ウェブサイトなどで、ワキガ治療に対する医師の考え方、これまでの治療実績や症例数、実際に治療を受けた患者さんの経過写真(症例写真)などを確認するのも良いでしょう。
さらに、料金体系が明瞭で、追加費用の有無について事前にしっかり説明があるか、万が一のトラブル時や再発時の保証制度・アフターケア体制が整っているかも、安心して治療を受けるための重要なチェックポイントです。
クリニック選びのチェックリスト
| 確認項目 | チェックポイント | 重要度 |
|---|---|---|
| 医師の専門性 | 皮膚科または形成外科の専門医資格を有しているか | 非常に高い |
| 説明の丁寧さ | メリットだけでなく、リスクや副作用も隠さず説明してくれるか | 非常に高い |
| 料金の明瞭さ | 麻酔代や薬代、アフターケア代を含めた総額が明確か | 高い |
| 治療実績 | 豊富な経験と実績があり、それを公開しているか | 中程度 |
カウンセリングの重要性
実際に治療を受けるかどうかを決定する前のカウンセリングは、医師との相性を確認し、信頼関係を築く上で非常に重要な機会です。
良い医師は、患者さんの悩みに真摯に耳を傾け、希望するライフスタイルに合わせた治療法を提案してくれ、また、治療法が持つリスクや術後に起こりうる合併症、ダウンタイムの過ごし方などについても、丁寧に説明してくれます。
一方的に治療を勧めるのではなく、複数の選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリットを納得いくまで説明してくれるクリニックを選びましょう。
カウンセリングで聞くべきこと
- 自分の現在の症状レベルと、それに最も適した推奨治療法は何か
- 治療にかかる費用の総額(検査代、薬代、再診料なども含む)と支払い方法
- 治療に伴う具体的な痛み、予想されるリスクや合併症の内容
- 術後の仕事復帰の目安や、入浴・運動などの具体的な生活制限の期間
- 万が一、効果に満足できなかった場合や再発した場合の再治療・保証制度の有無
ワキガ治療に関するよくある質問
ワキガ治療を検討されている多くの患者さんから寄せられる、代表的な疑問や不安についてお答えします。
- 治療の痛みはどれくらいですか?
-
ほとんどの治療で局所麻酔を使用するため、治療中に鋭い痛みを感じることはほぼありません。麻酔の注射をする際、最初にチクッとした痛みと、薬剤が入ってくる時の押されるような感覚がありますが、短時間で済みます。
術後、麻酔の効果が切れてくると鈍い痛みが出ることがありますが、あらかじめ処方される痛み止め(鎮痛剤)を服用することで、日常生活に支障がない程度にコントロールできることがほとんどです。
- 未成年でも治療を受けることは可能ですか?
-
未成年の方でも治療を受けることは可能ですが、未成年の方が治療を受ける場合は、原則として保護者の方の同意が必要となり、カウンセリングや治療当日の同伴が求められることが一般的です。
まだ体が成長途中にあるお子様の場合、あまり早期に手術を行うと、成長とともに新たなアポクリン腺が発達して将来的に再発するリスクがわずかながら高まる可能性があります。
医師は本人の悩みの深さと身体的な成長段階を慎重に見極め、最適な治療時期や方法をアドバイスします。まずは保護者の方と一緒に専門医のカウンセリングを受け、将来を見据えた治療計画を立てることが大切です。
- 一度治療すれば再発することはありませんか?
-
医師が直接目で見てアポクリン腺を除去する剪除法であれば、取り残しがない限り再発の可能性は極めて低く、半永久的な効果が期待できます。
しかし、手術で完全に取りきれなかったごくわずかなアポクリン腺が、時間の経過とともに再び活動し始めたり、成長期などで新たな腺が発達したりすることで、ニオイが多少戻ってしまう可能性はゼロではありません。
医療機器による治療も高い効果が持続しますが、外科手術に比べると、わずかに再発のリスクが高いとされる場合があります。
どの治療法にも「絶対(100%)」はないことを理解し、それぞれの治療法が持つ再発リスクの程度について、事前に医師から十分な説明を受けておくことが重要です。
以上
参考文献
Morioka D, Nomura M, Lan L, Tanaka R, Kadomatsu K. Axillary osmidrosis: past, present, and future. Annals of plastic surgery. 2020 Jun 1;84(6):722-8.
Morioka D, Ohkubo F, Amikura Y. Clinical features of axillary osmidrosis: A retrospective chart review of 723 J apanese patients. The Journal of dermatology. 2013 May;40(5):384-8.
Kuwahara H, Kubomura K, Tsurugaya Y, Akaishi S. Clinical Efficacy of Sofpironium Bromide in Reducing Odor Intensity in Axillary Osmidrosis Complicated by Primary Axillary Hyperhidrosis: A Cohort Study. International Journal of Dermatology and Venereology. 2025 Jun 1;8(2):72-6.
Homma KI, Maeda K, Ezoe K, Fujita T, Mutou Y. Razor-assisted treatment of axillary osmidrosis. Plastic and reconstructive surgery. 2000 Mar 1;105(3):1031-3.
Tanaka R, Morioka D, Akamine S, Shimizu T, Kadomatsu K. Safety and efficacy of surgical treatments for axillary osmidrosis: a retrospective cohort study comparing conventional open excision with cartilage-shaver closed curettage. Plastic and Aesthetic Research. 2020 Apr 10;7:N-A.
Nagasao T, Andoh Y, Nakajima T. A new technique in operations for axillary osmidrosis. Plastic and reconstructive surgery. 2004 Sep 1;114(3):822-3.
Sakisaka M, Takushima A. Effectiveness of Sofpironium Bromide in Patients with Primary Axillary Hyperhidrosis Who Experienced Residual or Recurrence of Axillary Odor after Surgery for Axillary Osmidrosis. Journal of Plastic and Reconstructive Surgery. 2025 Jan 27;4(1):13-9.
Kim D, Kim J, Yeo H, Kwon H, Son D, Han K. Treatment of axillary osmidrosis using a subcutaneous pulsed Nd-YAG laser. Archives of plastic surgery. 2012 Mar;39(02):143-9.
Ozawa T, Nose K, Harada T, Muraoka M, Ishii M. Treatment of osmidrosis with the Cavitron ultrasonic surgical aspirator. Dermatologic surgery. 2006 Oct 1;32(10):1251-5.
Ichikawa K, Miyasaka M, Aikawa Y. Subcutaneous laser treatment of axillary osmidrosis: a new technique. Plastic and reconstructive surgery. 2006 Jul 1;118(1):170-4.