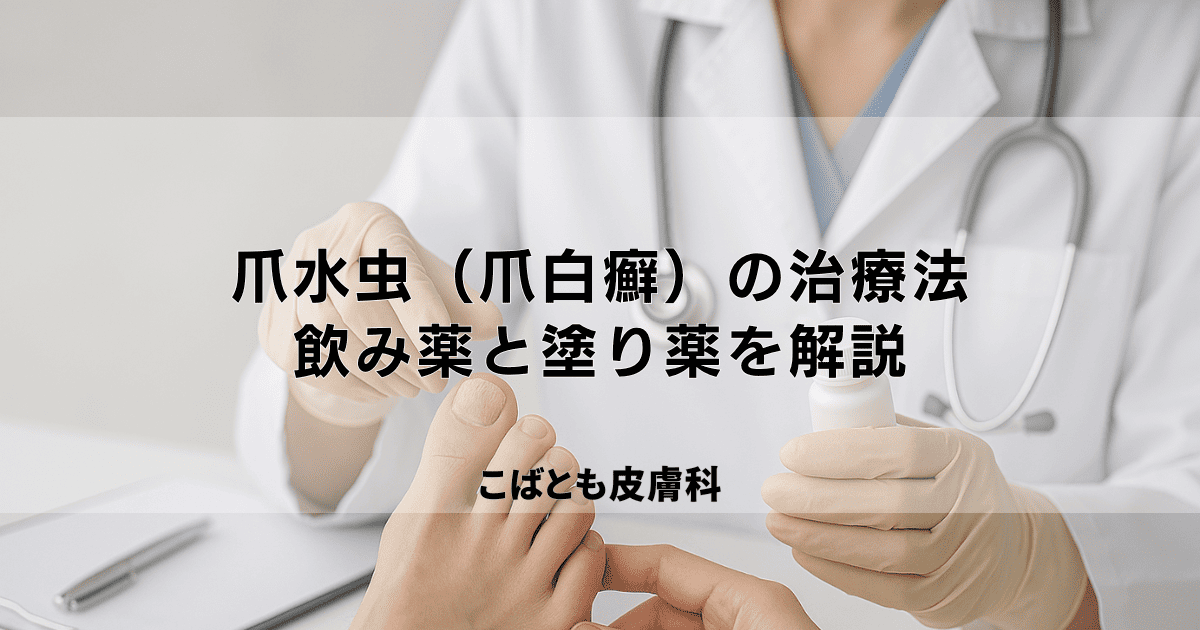ふと足の爪を見たらなんだか色が濁っている、爪が厚くなった気がする。そういった些細な変化は、もしかすると、爪水虫(爪白癬)のサインかもしれません。
爪水虫は、かゆみなどの自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行してしまうことが多い厄介な病気です。
この記事では、爪水虫の気になる初期症状から、原因、放置するリスク、皮膚科で行われる正しい治療法まで、詳しく解説します。
飲み薬と塗り薬の違いや、再発させないための生活習慣のポイントも紹介しますので、爪の異変に悩む方はぜひ参考にしてください。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
もしかして爪水虫?気になる初期症状とは
爪水虫は、初期の段階では痛みやかゆみといったはっきりした症状が現れにくいため、自分では気づきにくく、爪には少しずつ変化がみれます。日頃から自分の爪を観察し、些細なサインを見逃さないことが早期発見につながります。
爪の色の変化(白や黄色への濁り)
健康な爪は薄いピンク色で、透明感があります。爪水虫の最も一般的な初期症状は、透明感が失われ爪が白く濁ったり、黄色っぽく変色したりすることです。多くの場合、爪の先端や側面から変化が始まり、徐々に根元の方へと広がっていきます。
マニキュアを塗っている女性は、落とした時に初めて爪の色の変化に気づくことも少なくありません。爪の色が以前と違うと感じたら、注意が必要です。
爪が厚くなる・もろくなる
白癬菌が爪の中で増殖すると、爪の成分であるケラチンが破壊され、爪の正常な成長が妨げられ、爪が異常に厚みを増すことがあります。
厚くなった爪は、爪切りで切りにくくなったり、靴を履いた時に圧迫されて痛みを感じたりする原因にもなります。
また、爪がもろくなり、ポロポロと欠けやすくなることもあり、爪の厚さや硬さに変化が出てきたら、それも爪水虫を疑うサインの一つです。
初期症状のセルフチェックリスト
| チェック項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| 爪の色が白、または黄色っぽく濁っている | ||
| 爪の透明感がなくなり、ツヤが失われた | ||
| 以前より爪が厚くなった、またはもろくなった | ||
| 爪の表面に縦や横の筋が入っている | ||
| 爪を切ると、白い粉のようなものが出る |
爪の表面に筋が入る・デコボコする
爪水虫が進行すると、爪の表面に白い筋状の線が現れることがあり、白癬菌が爪の層の間に入り込んでできるものです。さらに症状が進むと、爪の表面がデコボコと波打ったようになり、形そのものが変形してしまうこともあります。
爪の形が変わるほどの状態になると、治療にも時間がかかる傾向があるため、表面の変化に気づいた段階で早めに対処することが望ましいです。
初期症状を見分けるポイント
爪水虫の初期症状は、多くの場合足の親指から始まり、すべての指に同時に症状が出ることは比較的まれです。また、かゆみなどの自覚症状はほとんど伴いません。
足の皮がむけたり、かゆみが出たりする足水虫(足白癬)を併発していることも多いため、足の裏や指の間の状態も合わせて確認すると良いでしょう。
爪の変化は加齢や他の病気でも起こることがありますが、複数の症状が当てはまる場合は、爪水虫の可能性を考えて専門医に相談することが大切です。
爪水虫(爪白癬)の正体と感染の原因
爪にやっかいな変化を引き起こす爪水虫、正体は一体何でしょうか。感染経路や、どのような環境でうつりやすいのかを説明します。
原因は白癬菌というカビの一種
爪水虫の正体は、白癬菌(はくせんきん)という皮膚糸状菌の一種、つまりカビで、白癬菌は、皮膚や爪の主成分であるケラチンというタンパク質を栄養源にして生きています。
白癬菌が足の皮膚に感染したものが足水虫、爪の中に侵入して増殖したものが爪水虫(爪白癬)です。白癬菌は、高温多湿な環境を好むため、特に靴や靴下で蒸れやすい足は、菌にとって格好の住処となります。
足水虫からの移行が最も多い
爪水虫に感染する最も一般的なルートは、すでに感染している足水虫からの移行です。足の皮膚で増殖した白癬菌が、爪の先端や側面などのわずかな隙間から入り込み、爪の下で増殖を始めます。
足水虫を治療せずに放置していると、知らないうちに白癬菌が爪にまで感染範囲を広げてしまうので、爪水虫の治療と同時に、足水虫の治療も行うことが非常に重要です。
感染リスクを高める環境
| 場所 | 主な感染源 | 理由 |
|---|---|---|
| 家庭内 | 足ふきマット、スリッパ | 家族に水虫の人がいると、共有物から感染しやすい。 |
| 公衆浴場・ジム | 床、脱衣所のマット | 不特定多数の人が裸足で利用するため菌が付着しやすい。 |
| 靴の中 | 長時間履いた靴やブーツ | 高温多湿になり、白癬菌が増殖しやすい環境になる。 |
感染しやすい環境と人の特徴
白癬菌は、感染者の皮膚や爪から剥がれ落ちた角質の中に潜んでいるため、多くの人が裸足で利用する公衆浴場やスポーツジムの床、プールのサイドなどは感染のリスクが高い場所です。
また、革靴やブーツなど通気性の悪い靴を長時間履く人も、足が蒸れて白癬菌が増殖しやすいため注意が必要です。
足に傷があったり、糖尿病や免疫不全などの持病があったりすると、体の抵抗力が落ちているため、より感染しやすくなる傾向があります。
家族内感染のリスク
家庭内に爪水虫や足水虫の人がいる場合、家族への感染リスクは非常に高く、白癬菌を含んだ皮膚や爪のかけらは、家の中の様々な場所に落ちています。
特に、湿気の多いお風呂の足ふきマットや、家族で共有するスリッパは、主要な感染源となります。
家族の誰かが水虫と診断された場合は、他の家族も感染していないか確認し、マットやスリッパをこまめに洗濯・交換するなど、家庭内での感染対策を徹底することが大切です。
放置は危険?爪水虫が引き起こす問題
かゆみがないからといって、爪水虫をそのままにしておくのは大変危険です。見た目の問題だけでなく、体の健康や周囲の人々にも様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
見た目の悪化と整容的な悩み
爪水虫を放置すると、爪の変色や変形はますます進行します。爪は分厚く、濁り、表面はボロボロになっていき、最終的には爪が正常な形を失い、まるで木の皮のようになってしまうこともあります。
このような爪の状態は、見た目に大きく影響するため、サンダルを履くのをためらったり、温泉やプールに行くのを諦めたりと、精神的な苦痛や社会生活における制約につながることが少なくありません。
爪水虫の進行段階
| 段階 | 主な状態 | 自覚症状 |
|---|---|---|
| 初期 | 爪の先端や側面に濁りや変色が見られる。 | ほとんどない。 |
| 中期 | 濁りが爪全体に広がり、厚みが増してくる。 | 爪が切りにくくなる。 |
| 重度 | 爪が著しく厚くなり、変形・変色が進む。もろく崩れる。 | 歩行時に痛みを感じることがある。 |
歩行時の痛みや不快感
爪が異常に厚くなると、靴の中で指先が圧迫されるようになり、圧迫により歩くたびに痛みを感じたり、常に違和感を覚えたりすることがあります。
痛みをかばって不自然な歩き方をしていると、膝や腰に負担がかかり、二次的な体の不調を引き起こす可能性も考えられます。爪の健康は、快適な歩行を支える上でも重要な要素です。
細菌感染症(蜂窩織炎など)のリスク
爪水虫によって爪が変形したり、もろくなったりすると、爪と皮膚の間に隙間ができやすくなります。また、併発している足水虫によって皮膚に亀裂や傷ができることもあります。
隙間や傷から細菌が侵入すると、深刻な細菌感染症である蜂窩織炎(ほうかしきえん)などを引き起こす危険性があるので注意が必要です。
蜂窩織炎になると足が赤く腫れ上がり、強い痛みと高熱を伴います。糖尿病など免疫力が低下している方は重症化しやすいため、爪水虫の放置は避けましょう。
他者への感染源となる可能性
爪水虫を放置しているということは、常に白癬菌を自分の体で培養し、周囲にまき散らしているのと同じことです。家庭内の床やマット、スリッパなどを介して、大切な家族やパートナーに水虫をうつしてしまう可能性が非常に高くなります。
自分一人の問題と軽視せず、周囲への感染を防ぐという観点からも、責任を持って治療に取り組むことが大切です。
爪の異変に気づいたら何科を受診すべきか
爪にこれまで述べたような異変を見つけた時、どの病院の何科に行けば良いのか迷う方もいるでしょう。正しい診断と治療を受けるためには、適切な診療科を選ぶことが第一歩です。
まずは皮膚科への相談が基本
爪は皮膚の一部が硬く変化したものであり、爪水虫の原因である白癬菌も皮膚に感染するカビの一種です。爪の色の変化、厚み、変形など、爪に関する異常に気づいたら、迷わず皮膚科を受診してください。
皮膚科医は、爪の病気に関する専門的な知識と診断技術を持っており、適切な検査と治療を提供してくれます。
なぜ皮膚科が専門なのか
皮膚科では、爪の見た目だけで判断するのではなく、爪の一部を採取して顕微鏡で調べる検査(鏡検)を行います。検査によって、白癬菌の有無を直接確認し、爪水虫であるかどうかを確定診断します。
他の爪の病気と見分けるためにも、この専門的な検査は非常に重要です。また、治療薬の選択や副作用の管理など、治療全体を通して専門的な視点からサポートを受けることができます。
爪の異常で考えられる他の病気
- 爪甲鉤彎症(そうこうこうわんしょう)
- 乾癬(かんせん)
- 爪扁平苔癬(つめへんぺいたいせん)
- 爪下血腫(そうかけっしゅ)
- 悪性黒色腫(メラノーマ)
自己判断での市販薬使用のリスク
ドラッグストアなどでは、水虫用の市販薬が数多く販売されていますが、爪水虫に効果があるとされる市販の塗り薬は、ごく初期の軽症な場合に限られます。
多くの場合、市販薬では有効成分が硬い爪の内部まで十分に浸透せず、効果は期待できません。また、そもそも爪の変形が水虫ではない他の病気が原因だった場合、市販薬を使い続けることで発見が遅れ、病状を悪化させてしまう危険性もあります。
他の爪の病気との見分け
爪が厚くなったり変形したりする病気は、爪水虫だけではありません。加齢や靴による圧迫で爪が厚く硬くなる爪甲鉤彎症や、全身の皮膚疾患である乾癬の症状が爪に現れることもあります。
まれに、爪の下にできる皮膚がん(悪性黒色腫など)が、黒い筋や変色として現れることもあります。このような病気は治療法が全く異なるため、専門医による正確な診断が何よりも大切です。
安易に爪水虫と決めつけず、まずは皮膚科を受診してください。
皮膚科で行う爪水虫の検査と診断
皮膚科を受診すると、爪水虫かどうかをはっきりさせるための検査が行われます。見た目だけでは判断が難しい場合でも、科学的な根拠に基づいて診断を確定させます。
診断を確定させるための顕微鏡検査
爪水虫の診断で最も基本的かつ重要なのが、顕微鏡を用いた直接鏡検法(ちょくせつきょうけんほう)です。
症状が出ている爪の一部を採取し、水酸化カリウム(KOH)溶液で爪の成分を溶かしたのち、顕微鏡で白癬菌がいるかどうかを直接観察する検査します。
検査で白癬菌が見つかれば、爪水虫であると確定診断でき、検査結果はその日のうちに分かることがほとんどです。
顕微鏡検査の大まかな流れ
| 手順 | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 1. 検体採取 | 爪の濁っている部分や、もろくなっている部分を削り取る。 | 数分 |
| 2. 処理 | 採取した検体をスライドガラスに乗せ、KOH溶液を滴下する。 | 10~20分 |
| 3. 観察 | 顕微鏡で白癬菌の菌糸や胞子を探す。 | 数分 |
検査の手順と痛みについて
検査のための検体採取では、爪の濁った部分や、爪と皮膚の間にある角質を、ハサミやメス、専用の器具などを使って少量削り取ります。爪自体には神経が通っていないため、この処置で痛みを感じることはほとんどありません。
少し削られる感覚がある程度で、痛みに対して不安がある方も、心配せずに検査を受けてください。
検査で何がわかるのか
顕微鏡検査の最大の目的は、白癬菌の存在を確認することです。白癬菌特有の枝分かれした糸状の菌糸や、連なった胞子が見えれば、爪水虫と診断されます。
どんなに見た目が爪水虫らしくても、検査で菌が見つからなければ、他の病気の可能性を考えることになります。
培養検査が必要な場合
顕微鏡検査で菌が見つからないものの、臨床的に爪水虫が強く疑われる場合や、原因となっている菌の種類を特定したい場合には、培養検査を追加で行うことがあります。
これは、採取した検体を菌が育ちやすい培地で数週間培養し、生えてきたカビの種類を同定する検査です。結果が出るまでに2週間から4週間ほどかかりますが、より正確な診断や、治療薬の選択に役立ちます。
爪水虫の治療法 – 飲み薬と塗り薬の選択
爪水虫の治療の基本は、原因である白癬菌を退治する抗真菌薬を使うことです。治療法には、主に飲み薬(内服薬)と塗り薬(外用薬)があり、患者さんの症状やライフスタイルに合わせて最適な方法を選択します。
治療の基本は抗真菌薬
爪水虫の治療に用いる薬は、すべて白癬菌の増殖を抑えたり、殺菌したりする作用を持つ抗真菌薬です。爪は硬く、薬が浸透しにくいため、根気強く治療を続けることが何よりも大切です。
治療の目標は、白癬菌に感染した古い爪が、新しく生え変わる健康な爪に完全に置き換わることで、治療には数ヶ月から1年以上の期間が必要となります。
塗り薬(外用薬)による治療
近年、爪への浸透性が高い爪水虫専用の塗り薬が登場し、治療の選択肢が広がりました。1日1回、爪の表面に直接塗布し、爪の表面だけでなく、爪と皮膚の境目にもしっかりと塗ることがポイントです。
塗り薬の利点は、肝臓への負担など全身的な副作用の心配がほとんどないことです。ただし、薬が爪の奥深くまで届きにくい場合もあり、爪の根元まで病変が及んでいる場合や、爪が著しく厚くなっている場合には効果が出にくいことがあります。
主な爪水虫治療薬の比較
| 種類 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 塗り薬(外用薬) | 全身的な副作用が少ない。手軽に始められる。 | 効果が限定的な場合がある。毎日塗る手間がかかる。 |
| 飲み薬(内服薬) | 高い治療効果が期待できる。爪全体に効果が及ぶ。 | 肝機能障害などの副作用の可能性がある。定期的な血液検査が必要。 |
飲み薬(内服薬)による治療
飲み薬は、体の中から血流に乗って有効成分を爪まで届け、内側から白癬菌の増殖を抑えるので、分厚い爪や、爪の根元まで広がった爪水虫に対しても高い治療効果が期待できます。
現在、主に使われる飲み薬には、毎日服用するタイプと、1週間に1回服用するタイプ(パルス療法)があります。ただし、飲み薬は肝臓で代謝されるため、まれに肝機能障害などの副作用が起こることがあります。
治療開始前と治療中は、定期的に血液検査を行い、安全性を確認しながら治療を進めることが重要です。
飲み薬と塗り薬の使い分け
どちらの治療法を選択するかは、爪水虫の重症度、病変の範囲、患者さんの年齢や持病の有無、ライフスタイルなどを総合的に考慮して、医師が判断します。
一般的に、症状が爪の先端に限局している軽症例では塗り薬が、病変が広範囲に及ぶ場合や爪が厚く変形している重症例では飲み薬が選択されることが多いです。
また、他の薬との飲み合わせの問題で飲み薬が使えない方や、定期的な通院や血液検査が難しい方には、塗り薬での治療を検討します。場合によっては、両者を併用することもあります。
治療中の生活で心がけたいことと再発予防
爪水虫の治療は、薬を飲む、あるいは塗るだけで終わりではありません。治療効果を高め、つらい再発を防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことが不可欠です。
根気強い治療の継続が最も重要
爪水虫の治療は、新しい健康な爪が生えそろうまでの長い道のりです。足の爪は伸びるのが遅く、完全に生え変わるには1年から1年半ほどかかります。
途中で爪がきれいになってきたように見えても、まだ爪の奥には白癬菌が潜んでいる可能性があり、自己判断で治療を中断してしまうと、残った菌が再び増殖し、再発の原因となります。
医師が完治と判断するまで、根気強く治療を続けることが何よりも大切です。
足を清潔で乾燥した状態に保つ
白癬菌は湿った環境を好みます。足を清潔に保ち、乾燥させることが、菌の増殖を抑え、治療を助ける基本です。毎日入浴やシャワーで、石鹸を使って足の指の間まで丁寧に洗いましょう。
洗った後は、タオルで水分をしっかりと拭き取ることが重要で、特に指の間は水分が残りやすいので、意識して拭いてください。
日常生活での再発予防策
| 項目 | 具体的な対策 | 目的 |
|---|---|---|
| 足の清潔 | 毎日、指の間まで丁寧に洗い、よく乾かす。 | 白癬菌の栄養源となる垢や汚れを取り除く。 |
| 履物 | 通気性の良い靴を選び、毎日同じ靴を履かない。 | 靴の中の湿度を下げ、菌の増殖を防ぐ。 |
| 共有物 | 足ふきマットやスリッパの共有を避ける。 | 家族への感染や、家族からの再感染を防ぐ。 |
履物や足ふきマットの管理
一日中履いた靴の中は、汗で蒸れて白癬菌にとって絶好の環境になっています。できるだけ通気性の良い靴を選び、毎日同じ靴を履き続けるのではなく、複数の靴をローテーションさせて、履かない靴は十分に乾燥させましょう。
靴下も、吸湿性の高い綿や麻などの素材がおすすめで、また、家庭内での感染を防ぐため、水虫の人は家族と別のマットを使うのが理想的です。
家族への感染を防ぐために
自分が治療中であることは、同居する家族にも伝え、協力を得ることが重要です。スリッパや爪切りなどの共有は避けましょう。
また、家の中をこまめに掃除し、床に落ちている皮膚のかけら(垢)を取り除くことも、感染拡大の防止につながります。もし家族にも水虫が疑われる症状があれば、一緒に皮膚科を受診することを勧めましょう。
家族全員で水虫を治療することが、家庭内での感染サイクルを断ち切る最も確実な方法です。
爪水虫に関するよくある質問
最後に、爪水虫の治療に関して、患者さんからよくいただく質問と答えをまとめました。
- 治療期間はどのくらいかかりますか
-
治療期間は、爪の生え変わる速さに依存するため、個人差があります。一般的に、手の爪で約半年、足の爪では1年から1年半程度の期間が必要です。
爪の根元まで病変が広がっている場合や、爪が厚く変形している場合は、より長い期間がかかる傾向があります。焦らず、医師の指示に従って根気よく治療を続けることが完治への一番の近道です。
- 治療費はどのくらいかかりますか
-
爪水虫の検査や治療は、健康保険が適用されます。自己負担額は、年齢や所得に応じて1割から3割となります。費用は、診察料、検査料、処方される薬の種類や量によって異なります。
飲み薬で治療する場合、定期的な血液検査の費用も必要です。
治療費の目安(3割負担の場合)
- 初診料・検査料:2,000~3,000円程度
- 再診料(月1回):500~1,500円程度(血液検査含む)
- 薬代(1ヶ月分):塗り薬 2,000~3,000円程度、飲み薬 3,000~6,000円程度
※上記はあくまで一般的な目安であり、医療機関や処方内容によって異なります。
- 薬の副作用はありますか
-
塗り薬の場合、塗った場所がかぶれたり、赤くなったりといった皮膚症状が出ることがまれにありますが、重篤な副作用の心配はほとんどありません。
飲み薬の場合は、胃腸障害(吐き気、下痢、腹痛など)や、まれに肝機能障害が起こる可能性があるため、安全に治療を行うために、定期的な血液検査が必須です。
- 完治したかどうかはどう判断しますか
-
完治の判断は、自己判断で行うべきではありません。見た目がきれいになっても、まだ菌が残っている可能性があるからです。完治の最終的な判断は、医師が行います。
爪が根元から先端まですべて健康な爪に生え変わったことを確認した上で、再度、顕微鏡検査を行い、白癬菌が完全にいなくなったことを確認して、治療終了です。
以上
参考文献
Tanuma H. Current topics in diagnosis and treatment of tinea unguium in Japan. The Journal of Dermatology. 1999 Feb;26(2):87-97.
Iwanaga T, Ushigami T, Anzawa K, Mochizuki T. Pathogenic dermatophytes survive in nail lesions during oral terbinafine treatment for tinea unguium. Mycopathologia. 2017 Aug;182(7):673-9.
Noguchi H, Matsumoto T, Hiruma M, Asao K, Hirose M, Fukushima S, Ihn H. Topical efinaconazole: a promising therapeutic medication for tinea unguium. The Journal of Dermatology. 2018 Oct;45(10):1225-8.
Miura Y, Takehara K, Nakagami G, Amemiya A, Kanazawa T, Kimura N, Kishi C, Koyano Y, Tamai N, Nakamura T, Kawashima M. Screening for tinea unguium by thermography in older adults with subungual hyperkeratosis. Geriatrics & Gerontology International. 2015 Aug;15(8):991-6.
Miyajima Y, Satoh K, Uchida T, Yamada T, Abe M, Watanabe SI, Makimura M, Makimura K. Rapid real-time diagnostic PCR for Trichophyton rubrum and Trichophyton mentagrophytes in patients with tinea unguium and tinea pedis using specific fluorescent probes. Journal of dermatological science. 2013 Mar 1;69(3):229-35.
Ogasawara Y, Hiruma M, Muto M, Ogawa H. Clinical and mycological study of occult tinea pedis and tinea unguium in dermatological patients from Tokyo. Mycoses. 2003 Mar 4;46(3‐4):114-9.
Asz-Sigall D, Tosti A, Arenas R. Tinea unguium: diagnosis and treatment in practice. Mycopathologia. 2017 Feb;182(1):95-100.
Noble SL, Forbes RC, Stamm PL. Diagnosis and management of common tinea infections. American family physician. 1998 Jul 1;58(1):163-74.
Moriarty B, Hay R, Morris-Jones R. The diagnosis and management of tinea. Bmj. 2012 Jul 10;345.
Wollina U, Nenoff P, Haroske G, Haenssle HA. The diagnosis and treatment of nail disorders. Deutsches Ärzteblatt International. 2016 Jul 25;113(29-30):509.