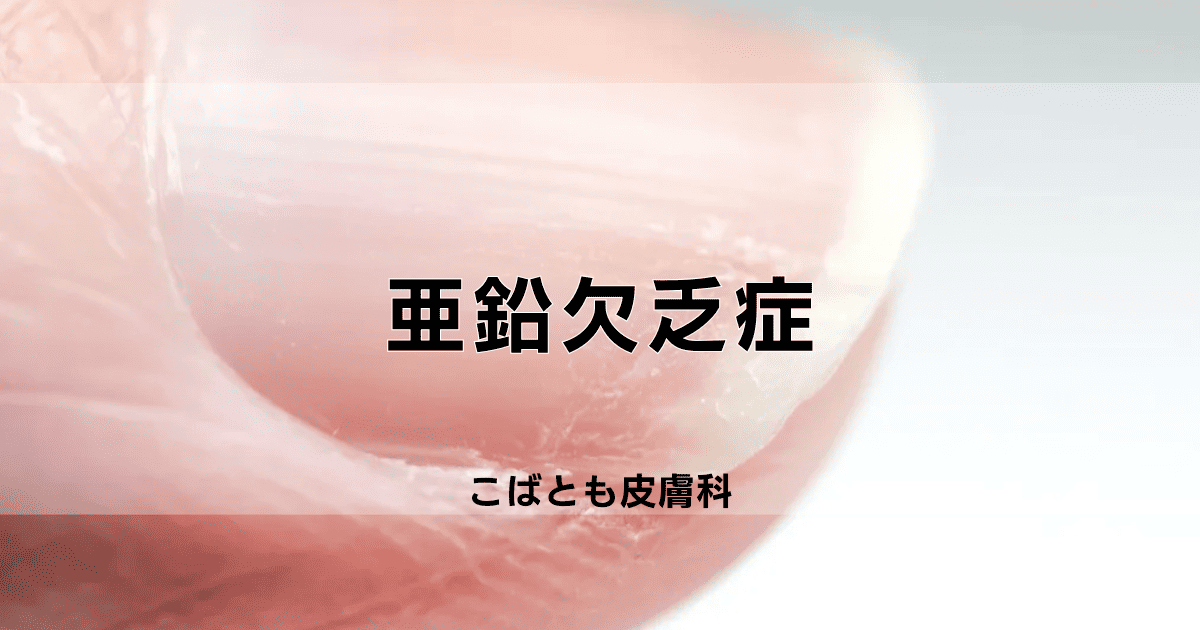亜鉛欠乏症(zinc deficiency)とは、体内における亜鉛の量が著しく低下することで起こる代謝異常症です。
亜鉛は、DNA合成や細胞分裂、タンパク質代謝などの重要な生体機能に不可欠な微量元素で、200種類以上の酵素の活性化に関与していてます。
亜鉛が不足すると、皮膚症状として湿疹や痤瘡、脱毛などが現れるほか、味覚障害や免疫機能の低下、創傷治癒の遅延など、全身にわたる多様な症状が生じます。
小児期における亜鉛欠乏は、身体発育や知能発達に重大な影響を与え、また成人においても生活の質を著しく低下させる要因です。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
亜鉛欠乏症の症状
亜鉛欠乏症では、皮膚炎や味覚障害、成長障害など、全身にわたる多様な症状が現れることから、早期発見と対応が重要です。
皮膚における症状の特徴
皮膚症状は亜鉛欠乏症における最も顕著な徴候の一つで、手指や足趾の周囲、口唇部、肛門周囲などに特徴的な症状が現れ、慢性的な亜鉛不足により皮膚のバリア機能が低下し、乾燥肌や湿疹様の発疹が生じ、冬季や乾燥時期に悪化します。
皮膚の炎症は、初期段階では軽度の発赤や痒みを伴う程度ですが、進行すると角化性の病変や落屑(皮膚の剥離)が目立つことが多いです。
| 好発部位 | 主な皮膚症状 |
|---|---|
| 手指・足趾 | 落屑・亀裂 |
| 口唇部 | 口角炎・口唇炎 |
| 肛門周囲 | 発赤・びらん |
| 爪周囲 | 爪囲炎・爪甲脱落 |
味覚・嗅覚における変化
味覚障害は亜鉛欠乏症の典型的な症状の一つで、甘味や塩味、苦味などの基本味覚の識別能力が低下し、味覚の変化は、食事の美味しさを感じにくくなるだけでなく、食欲不振や体重減少にもつながります。
嗅覚の異常も味覚障害と同様に見られることがあり、香りの感受性が低下したり、異臭を感じたりする症状が出現することもあります。
味覚障害の症状
- 味を感じにくい
- 味の区別がつきにくい
- 金属味を感じる
- 味が変化して感じる
- 味がしなくなる
消化器系の症状と食欲への影響
消化器系の症状として、食欲不振や下痢、腹部不快感などが現れることがあり、症状は栄養状態の悪化を生じさせる要因で、慢性的な食欲低下は、必要な栄養素の摂取不足を招き、さらなる亜鉛欠乏を起こします。
| 消化器症状 | 関連する症状 |
|---|---|
| 食欲不振 | 体重減少・疲労感 |
| 下痢 | 脱水・電解質異常 |
| 腹部不快感 | 嘔気・膨満感 |
| 消化不良 | 栄養吸収障害 |
免疫機能と創傷治癒への影響
免疫機能の低下は、感染症に対する抵抗力の減弱や創傷治癒の遅延として現れ、高齢者や基礎疾患を持つ方では注意が必要です。
創傷治癒の遅延は、手術後の回復期間の延長や褥瘡(床ずれ)の治りにくさにもつながります。
免疫機能低下に関連する症状
- 風邪をひきやすい
- 傷の治りが遅い
- 皮膚感染症を起こしやすい
- 口内炎ができやすい
- 細菌感染症にかかりやすい
亜鉛欠乏症の原因
亜鉛欠乏症は、食事からの亜鉛摂取不足、消化管からの吸収障害、または体内での代謝異常など、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。
栄養学的要因による亜鉛欠乏
現代社会における食生活の多様化や偏りは、微量元素である亜鉛の慢性的な摂取不足を起こすことがあり、特に植物性タンパク質中心の食事では、フィチン酸による亜鉛の吸収阻害が重要な課題です。
食事性の亜鉛欠乏は、偏食や特定の食事制限、あるいは経済的な理由による食事内容の制限など、様々な社会的背景とも密接に関連しています。
亜鉛含有量が豊富な食品
- 牡蠣などの貝類
- 牛肉や豚肉などの赤身肉
- ナッツ類やマメ科植物
- 胚芽を含む穀物製品
- チーズなどの乳製品
| 食品分類 | 亜鉛含有量(mg/100g) | 生体利用率 |
|---|---|---|
| 貝類 | 10-150 | 高 |
| 肉類 | 3-8 | 中〜高 |
| 穀物類 | 1-3 | 低〜中 |
| 野菜類 | 0.1-1 | 低 |
消化管における吸収障害
消化管からの亜鉛吸収は、消化器系疾患や手術後の状態によって著しく低下することがあり、炎症性腸疾患や腸切除後の患者さんにおいて顕著な影響が認められます。
消化管での亜鉛吸収を阻害する要因
- 炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎)
- 腸管切除後症候群
- 慢性下痢症
- 消化管の炎症性疾患
- 膵臓機能障害
| 吸収阻害要因 | 影響度 | 主な発症リスク |
|---|---|---|
| 腸管炎症 | 高 | 慢性的 |
| 手術後 | 中〜高 | 一時的〜永続的 |
| 薬剤性 | 中 | 可逆的 |
代謝性要因と全身性疾患
全身性の疾患や代謝異常は、体内での亜鉛の利用効率や排出に影響を与え、亜鉛欠乏を引き起こすメカニズムが解明されつつあります。
腎臓病や肝臓病などの慢性疾患は、体内の亜鉛代謝に深刻な影響を及ぼし、尿中への亜鉛排泄増加や体内での利用障害を通じて、二次的な亜鉛欠乏を生じさせることが臨床研究により明らかになってきました。
薬剤性および環境因子
特定の薬剤の長期使用や環境要因による亜鉛欠乏のリスクは、近年の医学研究において注目を集めていますが、利尿薬や免疫抑制剤の使用は、体内の亜鉛バランスに大きな影響を与えることが分かっています。
環境因子による亜鉛欠乏は、土壌中の亜鉛含有量の地域差や、食物連鎖を通じた微量元素の偏在などの生態学的要因が関与していて、化学物質や重金属による環境汚染は土壌中の亜鉛に影響を与え、食物連鎖全体を通じた亜鉛摂取量の低下につながることも解明されてきました。
亜鉛欠乏症の検査・チェック方法
亜鉛欠乏症の診断においては、血清亜鉛値の測定による確定診断に加えて、問診や身体所見による総合的な臨床診断が重要です。
血液検査による診断方法
血清亜鉛値の測定は亜鉛欠乏症の診断において最も信頼性の高い方法であり、朝食前の空腹時に採血を行うことで、より正確な数値を得られます。
血液検査では、血清亜鉛値が基準値(成人の場合、通常60~110μg/dL)を下回っているかどうかを確認しますが、採血時の状態や時間帯によって数値が変動することがあるため、複数回の測定が必要です。
血清亜鉛値の測定前には、少なくとも10時間以上の絶食が必要で、前日の夜9時以降は水以外の摂取を控えることで、より信頼性の高い検査結果を得られます。
| 年齢区分 | 基準値(μg/dL) | 判定基準 |
|---|---|---|
| 新生児 | 50~90 | 重症:40未満 |
| 小児 | 55~100 | 中等症:40~55 |
| 成人 | 60~110 | 軽症:55~60 |
| 高齢者 | 65~120 | 要観察:60~65 |
検査結果の解釈において注意すべき点として、急性炎症反応の存在が挙げられ、感染症や手術後、外傷後などの炎症状態では、血清亜鉛値が一時的に低下することがあります。
また、妊娠中や経口避妊薬の服用、重度の貧血、低アルブミン血症などの状態でも、血清亜鉛値に影響が出ることがあるため、これらの要因を考慮に入れることが必要です。
問診による症状チェック
問診では、患者さnの生活習慣や食事内容、既往歴などを詳しく聴取し、亜鉛欠乏症に特徴的な症状の有無や経過を確認し、亜鉛欠乏症の可能性を評価するとともに、他の疾患との鑑別診断も同時に進めていく必要があります。
味覚異常に関する問診では、味覚の変化の種類や程度、発症時期、進行の速さなどを詳細に聞き取り、特に金属味や異味症の有無については注意深く確認を行うことが大切です。
皮膚症状については、発症部位や症状の進行過程、季節変動の有無、これまでに使用した外用薬とその効果などについて、時系列に沿って詳しく聴き取りを行っていきます。
問診時の主要確認項目
- 味覚異常の有無と程度
- 皮膚症状の発現部位と経過
- 食欲不振や体重変化の有無
- 消化器症状の詳細
- 既往歴や服用中の薬剤
消化器症状に関しては、食欲不振、嘔気、腹痛、下痢などの症状について、頻度や強さ、食事との関連性などを確認し、症状の重症度を評価します。
また、服薬歴の聴取では、利尿薬や糖尿病治療薬、胃酸抑制薬などの亜鉛の吸収や代謝に影響を与える可能性のある薬剤の使用状況を詳しく確認します。
さらに、既往歴としては、消化管手術の有無、炎症性腸疾患、慢性肝疾患、腎疾患などの基礎疾患について調べ、二次性の亜鉛欠乏症の可能性も考慮に入れることが重要です。
身体所見による評価
身体診察では、皮膚症状や口腔内の状態、爪の変化などを詳細に観察し、所見を総合的に評価することで、亜鉛欠乏症の臨床診断の精度を高められます。
皮膚の診察においては、四肢末端部や関節部、圧迫部位などを重点的に観察し、発赤、落屑、亀裂、色素沈着などの所見を記録することが大切です。
また、口腔内の診察では、舌の状態、口角炎の有無、口腔粘膜の変化などを観察し、舌乳頭の萎縮や舌炎の程度については、写真撮影による経過観察も考慮に入れます。
| 診察部位 | 確認項目 | 特徴的所見 |
|---|---|---|
| 皮膚 | 炎症・乾燥 | 発赤・落屑 |
| 口腔 | 粘膜状態 | 口角炎・舌炎 |
| 爪 | 変形・脆弱性 | 白斑・縦線 |
| 毛髪 | 脱毛・性状 | 脆弱化・枝毛 |
爪の診察では、白斑、縦線、横線などの変化を観察するとともに、爪の硬度や脆弱性についても評価し、経時的な変化の記録を行い、毛髪の診察においては、脱毛の程度や分布、毛髪の性状変化などを確認し、成長期にある小児では、成長障害との関連性の観察を行います。
栄養評価と食事調査
栄養状態の評価では、体重変化や筋肉量、体脂肪率などの身体計測に加えて、食事内容の聞き取りを行い、亜鉛摂取量の推定を行います。
食事内容の聞き取りでは、食事記録法や24時間思い出し法などを用いて、できるだけ正確な食事摂取状況の把握に努め、特に亜鉛を多く含む食品の摂取頻度に注目することが重要です。
食事調査での確認事項
- 一日の食事回数と量
- 主な摂取食品の種類
- 偏食の有無と程度
- 調理方法の傾向
- サプリメントの使用状況
食事記録の評価では、単に摂取量だけでなく食品の組み合わせや調理方法なども考慮に入れ、亜鉛の吸収を阻害する要因がないかどうかも確認し、また、アルコール摂取量や喫煙習慣についても聞き取ります。
亜鉛欠乏症の治療法と治療薬について
亜鉛欠乏症の治療は、主に酢酸亜鉛水和物やポラプレジンクなどの亜鉛製剤を用いた薬物療法を継続し、体内の亜鉛量を正常値まで回復させることを目指します。
薬物療法の基本
酢酸亜鉛水和物は、消化管からの吸収効率が高く、体内での利用性に優れているため、多くの医療機関で第一選択薬として使用されており、治療効果は数多くの臨床研究によって実証されています。
中でも、血中濃度の安定性と持続性において優れた特性を示すことから、長期的な治療においても安定した効果が期待できることが分かってきました。
| 薬剤名 | 一般名 | 標準投与量 | 投与回数 |
|---|---|---|---|
| ノベルジン | 酢酸亜鉛水和物 | 25-50mg | 2-3回/日 |
| プロマック | ポラプレジンク | 75-150mg | 2回/日 |
| 硫酸亜鉛 | 硫酸亜鉛水和物 | 50-100mg | 1-2回/日 |
投与量の調整と血中濃度モニタリング
治療開始後は、定期的な血清亜鉛値の測定を通じて投与量の微調整を行い、血清亜鉛値の測定は治療開始から1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後など、段階的に実施することで、治療効果の判定と経過観察に重要な指標です。
治療薬の主な種類と特徴
- 酢酸亜鉛水和物 吸収効率が高く、長期投与に適している
- ポラプレジンク 胃粘膜保護作用も併せ持つ
- 硫酸亜鉛 速やかな血中濃度上昇が期待できる
- グルコン酸亜鉛 副作用が比較的少ない
- クエン酸亜鉛 生体利用率が比較的高い
年齢や病態に応じた投与設計
小児における治療では、年齢や体重に応じた慎重な投与量の設定が必要で、成長発達への影響を考慮した投与計画が重要です。
高齢者では、腎機能や肝機能の状態を考慮しながら、個々の患者さんの状態に合わせた投与量の調整を行っていきます。
| 年齢区分 | 投与量調整 | 注意点 |
|---|---|---|
| 小児 | 体重換算 | 成長への影響 |
| 成人 | 標準投与量 | 併用薬との相互作用 |
| 高齢者 | 漸増方式 | 腎機能への配慮 |
薬の副作用や治療のデメリットについて
亜鉛欠乏症の治療では、経口亜鉛製剤の投与による銅欠乏や消化器症状、注射用亜鉛製剤による投与部位の炎症など、様々な副作用やリスクがあります。
経口亜鉛製剤の一般的な副作用
経口亜鉛製剤の服用では、消化器系の不快症状が比較的高い頻度で発現し、特に空腹時の服用では胃部不快感や嘔気などの症状が出現しやすいです。
胃腸障害の程度は個人差が大きく、軽度の胃もたれ程度から、時として服薬継続が困難になるような強い胃痛や嘔吐を伴うことがありますが、症状は食後服用への変更で改善します。
| 副作用 | 発現頻度 | 好発時期 |
|---|---|---|
| 胃部不快感 | 約30% | 投与開始直後 |
| 嘔気・嘔吐 | 約20% | 空腹時服用時 |
| 腹痛 | 約15% | 投与開始1週間以内 |
| 下痢 | 約10% | 不定期 |
銅欠乏症のリスクと対策
亜鉛の長期投与により、体内の銅の吸収が阻害され、銅欠乏症を起こす可能性があり、相互作用は特に高用量の亜鉛製剤を使用する際に注意が必要です。
銅欠乏症の初期症状としては貧血や白血球減少などの血液学的異常が現れやすく、定期的な血液検査によるモニタリングを実施することで、早期発見につながります。
予防的な観点から、長期投与が予想される患者さんには、あらかじめ銅を含有する総合ミネラルサプリメントの併用を検討することもありますが、その際は亜鉛と銅の服用時間を分けることが大切です。
銅欠乏症の主な症状
- 貧血症状(めまい、易疲労感)
- 白血球減少による感染リスク上昇
- 骨密度低下
- 皮膚色素沈着
- 神経症状(しびれ、痺れ)
その他の全身性副作用と注意点
亜鉛製剤の投与に伴い、まれに全身性の副作用が生じることがあり、アレルギー反応や過敏症には注意深い観察が求められます。
高用量投与や急速投与により、一過性の発熱や倦怠感、頭痛などの症状が現れることがあり、症状は投与速度の調整や投与量の見直しによって改善することが多いです。
腎機能障害のある患者さんでは、亜鉛の排泄が遅延する可能性があり、血中濃度のモニタリングをより慎重に行う必要が出てきます。
- 全身性副作用の種類
- 発熱・倦怠感
- めまい・頭痛
- 皮膚掻痒感
- アレルギー反応
- 血圧変動
また、亜鉛製剤と他の薬剤との相互作用にも注意が必要であり、特にキレート剤や鉄剤、カルシウム製剤などとの併用では、亜鉛の吸収が低下することがあります。
保険適用と治療費
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
薬剤費用の内訳
酢酸亜鉛水和物やポラプレジンクなどの亜鉛製剤は、標準的な投与量での治療では、1ヶ月あたりの薬剤費の自己負担額は3,000円から8,000円程度です。
| 薬剤名 | 一般名 | 30日分薬価 | 自己負担額(3割) |
|---|---|---|---|
| ノベルジン | 酢酸亜鉛水和物 | 24,000円 | 7,200円 |
| プロマック | ポラプレジンク | 15,000円 | 4,500円 |
| 硫酸亜鉛 | 硫酸亜鉛水和物 | 12,000円 | 3,600円 |
血液検査費用
定期的な血清亜鉛値の測定は、治療効果のモニタリングに欠かせない検査です。
| 検査項目 | 検査頻度 | 検査費用 | 自己負担額(3割) |
|---|---|---|---|
| 血清亜鉛値 | 月1回 | 5,000円 | 1,500円 |
| 銅濃度 | 3ヶ月毎 | 4,000円 | 1,200円 |
| 一般生化学 | 3ヶ月毎 | 8,000円 | 2,400円 |
以上
参考文献
Hambidge M. Human zinc deficiency. The Journal of nutrition. 2000 May 1;130(5):1344S-9S.
Tuerk MJ, Fazel N. Zinc deficiency. Current opinion in gastroenterology. 2009 Mar 1;25(2):136-43.
Prasad AS. Clinical manifestations of zinc deficiency. Annual review of nutrition. 1985 Jan 1;5:341-63.
Hambidge KM, Krebs NF. Zinc Deficiency: A Special Challenge1. The Journal of nutrition. 2007 Apr 1;137(4):1101-5.
Yanagisawa H. Zinc deficiency and clinical practice. Japan Medical Association Journal. 2004 Aug;47(8):359-64.
Black MM. Zinc deficiency and child development. The American journal of clinical nutrition. 1998 Aug 1;68(2):464S-9S.
Golub MS, Keen CL, Gershwin ME, Hendrickx AG. Developmental zinc deficiency and behavior. The Journal of nutrition. 1995 Aug 1;125:2263S-71S.
Sandstead HH. Zinc deficiency: a public health problem?. American Journal of Diseases of Children. 1991 Aug 1;145(8):853-9.
Maxfield, Luke, Samarth Shukla, and Jonathan S. Crane. “Zinc deficiency.” (2018).
Prasad AS, Fitzgerald JT, Hess JW, Kaplan J, Pelen F, Dardenne M. Zinc deficiency in elderly patients. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.). 1993 May 1;9(3):218-24.