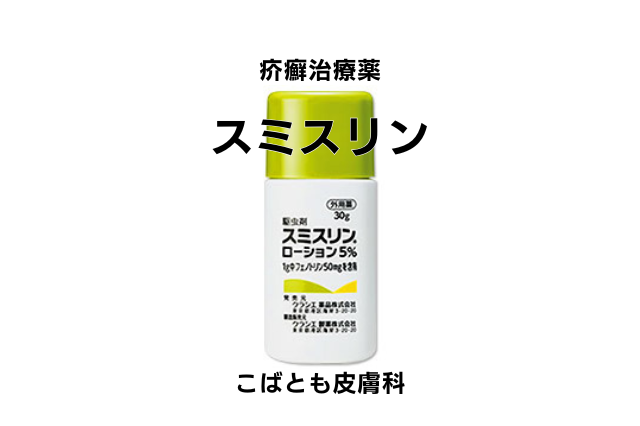フェノトリン(スミスリン)とは、主にヒゼンダニという寄生虫が皮膚に寄生して起こる疥癬(かいせん)や、アタマジラミ、ケジラミの駆除に用いられる外用薬(塗り薬)です。
有効成分であるフェノトリンが、寄生虫の神経系に作用して麻痺させることで、確実な殺虫効果を発揮します。特に、夜も眠れないほどの激しいかゆみを引き起こす疥癬の治療において、標準的な治療薬の一つとして重要な役割を担っています。
この記事では、フェノトリン(スミスリン)がどのように作用するのか、効果や正しい使い方、治療期間、考えられる副作用について、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
フェノトリン(スミスリン)の有効成分と効果、作用機序
フェノトリン(スミスリン)がなぜ特定の寄生虫に効果的なのか、有効成分の働きと効果の仕組みにを説明します。
有効成分フェノトリンとは
フェノトリンは、ピレスロイド系と呼ばれる殺虫成分の一つです。ピレスロイド系の成分は、除虫菊という植物に含まれる天然の殺虫成分ピレトリンの構造を基に、より効果が高く、安定性が増すように化学的に合成されたものです。
フェノトリンは、人間などの哺乳類に対する毒性が低い一方で、昆虫やダニ類に対しては強力な殺虫作用を示すため、医療用医薬品だけでなく、家庭用の殺虫剤などにも広く利用されています。
医療用として用いられるスミスリンは、フェノトリンを有効成分とする外用薬です。
主な効果と適応疾患
フェノトリン(スミスリン)は、皮膚に寄生する外部寄生虫の駆除を目的として使用します。
| 適応疾患名 | 原因となる寄生虫 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 疥癬(かいせん) | ヒゼンダニ | 夜間に強くなる激しいかゆみ、赤いブツブツ、線状の皮疹 |
| アタマジラミ症 | アタマジラミ | 頭部のかゆみ、フケのような卵の付着 |
| ケジラミ症 | ケジラミ | 陰部のかゆみ、下着に付着する血の染み |
皮膚科では主に疥癬の治療に処方されますが、シラミの駆除にも有効です。
作用機序
フェノトリンは、寄生虫の神経細胞にあるナトリウムチャネルという、神経の興奮伝達に重要な役割を果たすイオンの通り道に作用します。
ナトリウムチャネルにフェノトリンが結合すると、チャネルが閉じるべきタイミングで閉じなくなり、開きっぱなしの状態になり、神経が過剰に興奮し続け、やがて寄生虫は痙攣を起こして麻痺し死に至ります。
人間などの哺乳類のナトリウムチャネルは、寄生虫のものとは構造が少し異なるため、フェノトリンの影響を受けにくく、これが選択的な毒性につながっています。
他の治療薬との違い
疥癬の治療には、フェノトリン(スミスリン)のような外用薬の他に、内服薬も用いられます。
- イベルメクチン(ストロメクトール): 内服薬。体の内側から血流に乗って全身の皮膚に作用し、ヒゼンダニを駆除します。塗り薬の手間がないのが利点ですが、卵には効果がありません。
- クロタミトン(オイラックス): 外用薬。かゆみを抑える効果と、ヒゼンダニに対する殺虫効果を併せ持ちます。効果はフェノトリンより穏やかです。
- イオウ剤: 外用薬。古くからある治療薬で、角質を溶かす作用と殺虫作用があります。においが強いなどの欠点があります。
フェノトリンは、内服薬が使用しにくい妊婦や小児の疥癬治療において第一選択となることが多い、安全性の高い外用薬です。
使用方法と注意点
フェノトリン(スミスリン)は、効果を最大限に引き出すために、正しい手順でかつ適切な量を、体の隅々まで塗布することが非常に重要です。
全身への正しい塗布方法
疥癬の治療でフェノトリンを使用する場合、症状が出ている部分だけでなく、首から下の全身に塗布する必要があります。ヒゼンダニは症状がない部分にも潜んでいる可能性があるためです。
塗布の基本手順
- 入浴・清拭: 塗布前に入浴するか、体を拭いて皮膚を清潔にします。
- 塗布開始: 首から下、足の指の先まで、塗り残しがないように薬を塗り広げます。
- 細かい部分も丁寧に: 指の間、足の裏、爪の周り、お尻の割れ目、陰部、脇の下など、しわになりやすい部分は特に念入りに塗ってください。
- 顔や頭は不要: 通常、顔や頭にはヒゼンダニは寄生しないため、塗る必要はありません。ただし、角化型疥癬などで顔にも症状がある場合は、医師の指示に従ってください。
- 塗布完了: 塗り終わったら、薬が乾くまで少し待ちます。
塗布量と放置時間
1回の塗布で、成人の場合は1本(スミスリンローション5% 30g)のほぼ全量を使用するのが目安です。量が少ないと効果が不十分になる可能性があり、薬を塗った後は、すぐに洗い流してはいけません。
塗布後12時間以上放置し、その後に入浴やシャワーで洗い流します。時間を置くことで、有効成分が皮膚の角質層に浸透し、ヒゼンダニを確実に殺虫できます。
塗布後の注意点
薬を塗布した後の過ごし方にも、いくつか注意点があります。
| 注意事項 | 具体的な対応 |
|---|---|
| 手洗い | 薬を塗った後、食事やトイレなどで手を洗った場合は、その都度、手に薬を塗り直す必要があります。 |
| 衣類 | 塗布後は、清潔な衣類やパジャマを着用してください。 |
| 副作用の確認 | 塗布した部分に強い刺激感やかぶれなどの症状が出ないか注意し、異常があれば医師に相談してください。 |
小児や高齢者への使用
小児や高齢者に使用する場合も基本的な使い方は同じでが、小児は自分で塗ると塗り残しが出やすいため、保護者の方が丁寧に塗ってあげることが大切です。皮膚が弱い方は、刺激感が出やすいことがあるため、注意深く観察してください。
フェノトリン(スミスリン)の適応対象となる患者さん
フェノトリン(スミスリン)は、特定の外部寄生虫による皮膚疾患と診断された方々に処方されます。どのような方が治療の対象となるのか、また、体の状態によって特にこの薬が選択される場合について説明します。
疥癬(かいせん)と診断された方
フェノトリン(スミスリン)の最も重要な適応は、ヒゼンダニが原因の疥癬です。
医師が診察し、特徴的な皮疹(赤いブツブツ、疥癬トンネル)や、夜間に増強する激しいかゆみといった症状から疥癬を疑い、顕微鏡検査で虫体や卵を確認して確定診断を下した場合に、治療の対象となります。
自己判断で湿疹の薬などを使用しても改善しない、激しいかゆみが続く場合は、疥癬の可能性を考えて皮膚科を受診することが重要です。
妊婦や授乳婦の疥癬治療
妊娠中の方や授乳中の方が疥癬になった場合、治療薬の選択には特に慎重な配慮が必要です。内服薬であるイベルメクチンは、胎児や乳児への安全性が確立されていないため、原則として使用を避けます。
一方、フェノトリンは皮膚からの吸収がごくわずかで、全身への影響が少ないため、妊娠中・授乳中の疥癬治療における第一選択薬です。治療による有益性が危険性を上回ると医師が判断した場合に、この薬が選択されます。
小児の疥癬治療
小児、特に乳幼児が疥癬になった場合も、フェノトリンが第一選択薬となります。内服薬のイベルメクチンは、体重15kg未満の小児に対する安全性が確立されていないためです。
フェノトリンは、乳児から使用できる安全性の高い薬剤として、小児の疥癬治療で広く用いられています。
アタマジラミ・ケジラミ症の患者さん
フェノトリンは、シラミに対しても高い殺虫効果を示します。
| 適応疾患 | 主な対象者と症状 |
|---|---|
| アタマジラミ症 | 主に学童期の小児に集団発生することが多い。頭部のかゆみ、髪にフケのような卵が固着する。 |
| ケジラミ症 | 主に性行為によって感染する。陰毛部のかゆみが主症状。 |
シラミ症と診断された場合も、フェノトリンによる治療の対象となります。使用方法は疥癬とは異なり、専用のシャンプータイプの製品(市販薬として入手可能)を用いることが一般的です。
フェノトリン(スミスリン)の治療期間
フェノトリン(スミスリン)による治療は、薬を塗るタイミングと、その後の経過観察が非常に大切です。ここでは、治療に必要な期間や、治療終了の判断について解説します。
1週間間隔での反復治療
フェノトリンは、ヒゼンダニの成虫と幼虫には効果がありますが、卵には効果がありません。 1回の塗布だけでは、生き残った卵から新しい幼虫が孵化してしまい、治療が完了しないので、卵が孵化するタイミングを狙って追加の治療を行います。
基本的な治療スケジュール
- 初回塗布(1日目): まず1回目の塗布を行い、現在活動しているヒゼンダニの成虫と幼虫を殺虫します。
- 待機期間: その後、薬を塗らずに1週間過ごします。この間に、初回塗布時に卵だったものが孵化します。
- 2回目塗布(8日目): 初回塗布からちょうど1週間後に、2回目の塗布を行います。これにより、新たに孵化した幼虫をすべて駆除します。
この2回の治療サイクルによって、ヒゼンダニを全滅させることを目指します。
治療終了後の「後症状」について
治療が成功してヒゼンダニが完全にいなくなった後も、かゆみや湿疹様の症状が数週間から1ヶ月程度続くことがあります。
これは、皮膚の中に残ったヒゼンダニの死骸や糞に対するアレルギー反応が原因で起こるもので、疥癬後掻痒(かいせんごそうよう)と呼ばれ、治療失敗や再発ではなく治癒過程の一環です。
このかゆみに対しては、別途、抗ヒスタミン薬の飲み薬やステロイドの塗り薬が処方されます。
治療効果の判定
治療が成功したかどうかは、以下の点で総合的に判断します。
| 判断基準 | 確認内容 |
|---|---|
| 新たな皮疹の停止 | 治療開始後、新しい赤いブツブツや疥癬トンネルが出現しなくなること。 |
| かゆみの性質の変化 | 夜も眠れないほどの激しいかゆみが、我慢できる程度のかゆみに変化し、徐々に軽減していくこと。 |
| 顕微鏡検査 | 治療終了から2~4週間後に、再度皮膚を採取して顕微鏡で調べ、虫体や卵がいないことを確認します(治癒確認)。 |
副作用やデメリット
フェノトリン(スミスリン)は、皮膚からの吸収が少なく、全身への影響がほとんどないため、比較的安全性の高い薬とされていますが、外用薬であるため、塗布した部分の皮膚に好ましくない反応が現れることがあります。
主な副作用
報告されている副作用のほとんどは、塗布部位に限定される皮膚の症状です。
| 主な副作用 | 症状 |
|---|---|
| 接触皮膚炎(かぶれ) | 薬を塗った部分に、赤み、かゆみ、ぶつぶつ、腫れなどが現れます。 |
| 皮膚刺激感 | ピリピリ、ヒリヒリとした刺激を感じることがあります。特に、もともと湿疹がある部分や、掻き壊して傷になっている部分では感じやすいです。 |
| 発赤 | 塗布した部分の皮膚が赤くなります。 |
| 乾燥 | 皮膚が乾燥し、カサカサすることがあります。 |
症状は、薬の成分そのものに対する刺激やアレルギー反応によって起こります。
副作用が起きた場合の対処法
もし、上記のような副作用と思われる症状が現れた場合は、まずは医師に相談することが重要です。かぶれの症状が強い場合や、刺激感が我慢できない場合は、使用を中止する必要があります。
医師は、症状を診察し、副作用であると判断した場合は、かぶれを抑えるためのステロイド外用薬を処方したり、他の治療薬(内服薬など)への変更を検討したりします。
全身性の副作用は極めてまれ
フェノトリンは、皮膚から体内に吸収される量がごくわずかであるため、内服薬で見られるような全身性の副作用(肝機能障害や血液障害など)が起こる心配はほとんどありません。
この安全性の高さが、妊婦や小児の治療でフェノトリンが選択される大きな理由です。
デメリット
フェノトリン治療の最大のデメリットは、使用方法の手間と時間にあります。
治療上のデメリット
- 全身塗布の手間: 首から下の全身に、塗り残しなく薬を塗る作業は、かなりの時間と労力を要します。
- 12時間の放置: 薬を塗った後、12時間洗い流せずに過ごす必要があり、その間のべたつきや不快感があります。
- 塗り直しの必要性: 放置時間中に手を洗うと、薬を塗り直さなければなりません。
- 家族の協力: 高齢者や小児など、一人で塗るのが難しい場合は、家族や介護者の協力が大事です。
フェノトリン(スミスリン)で効果がなかった場合
医師の指示通りに薬を塗布したにもかかわらず、かゆみが改善しない、あるいは新たな皮疹が出続けてしまう場合、いくつかの原因が考えられます。
自己判断で「効かない」と諦めるのではなく、原因を突き止め、適切な対策を講じることが大切です。
考えられる原因
治療がうまくいかない場合、薬剤そのものに問題があることよりも、使い方や環境に原因があることがほとんどです。
| 主な原因 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 不完全な塗布 | 指の間や爪の周り、陰部など、細かい部分に塗り残しがある。使用量が少なすぎる。12時間経たずに洗い流してしまった。 |
| 再感染 | 治療が成功しても、同居している家族やパートナーが未治療の疥癬患者である場合、そこから再び感染してしまう。 |
| 環境からの再感染 | 患者が使用した寝具や衣類に潜んでいたヒゼンダニから、再度感染してしまう(可能性は低いがゼロではない)。 |
| 診断が異なる | そもそも症状の原因が疥癬ではなく、湿疹・皮膚炎など別の病気である。 |
薬剤抵抗性(薬が効かない耐性を持つヒゼンダニ)の可能性も理論的にはありますが、非常にまれです。
再感染を防ぐための環境整備
治療を成功させるためには、薬剤の使用と並行して、生活環境中のヒゼンダニを減らす努力が重要です。
- 衣類・寝具の洗濯: 治療を開始する日(薬を洗い流した後)に、それまで身につけていた衣類や使用していたシーツ、タオルなどをすべて交換し、洗濯します。50℃以上のお湯に10分以上浸けるか、高温設定の乾燥機にかけるとより確実です。
- 掃除: 部屋の隅々まで丁寧に掃除機をかけ、ヒゼンダニを含んだ可能性のある皮膚の落屑(あか)を取り除きます。
- 隔離: 洗濯や熱処理が難しいものは、大きなビニール袋に入れて2週間ほど密閉しておくと、ヒゼンダニは死滅します。
家族や接触者の同時治療
疥癬の治療で最も大切なのは、患者さんと濃厚な接触があった人(同居家族など)が、症状の有無にかかわらず同時に検査・治療を行うことです。
誰か一人でも未治療の人がいると、そこが感染源となってピンポン感染を繰り返し、いつまでも治癒に至りません。
他の治療薬への変更
正しい方法でフェノトリンを使用し、環境整備や同時治療も行ったにもかかわらず効果が見られない、というまれなケースでは、他の治療薬への変更を検討します。
内服薬であるイベルメクチンへの切り替えや、フェノトリンとイベルメクチンを併用する強化療法などがあります。
他の治療薬との併用禁忌
複数の薬を使用している場合、薬同士の相互作用(飲み合わせや塗り合わせ)は気になる点です。フェノトリン(スミスリン)を使用する際の併用に関する注意点について解説します。
基本的に併用禁忌の薬はない
結論から言うと、フェノトリン(スミスリン)には、添付文書上、絶対に一緒に使ってはいけないとされている併用禁忌薬(内服薬・外用薬ともに)はありません。
これは、フェノトリンが皮膚に塗る外用薬であり、体内へ吸収される量がごくわずかで、全身に作用する他の薬との相互作用を起こす可能性が極めて低いからです。
高血圧や糖尿病などの生活習慣病で飲み薬による治療を受けている方も、通常は問題なくフェノトリンを使用できます。
他の外用薬との併用について
注意が必要なのは、他の塗り薬を同じ部位に使用する場合です。疥癬によるかゆみや掻き壊しがひどく、湿疹を併発している場合、殺虫目的のフェノトリンと、炎症を抑えるステロイド外用薬が一緒に処方されることがあります。
外用薬併用の際の注意点
- 使用順序: どちらを先に塗るか、医師の指示に従ってください。一般的には、フェノトリンを塗布して12時間後に洗い流してから、ステロイド外用薬を開始することが多いです。
- 自己判断で混ぜない: 2種類の薬を手のひらで混ぜて塗ることは、それぞれの効果を減弱させる可能性があるため避けてください。
- 使用部位: 医師から指示された部位以外には使用しないでください。
刺激を増強させる可能性のあるもの
フェノトリン自体に皮膚刺激性があるため、角質を溶かす作用のある薬(サリチル酸や尿素など)を同じ部位に使用すると、刺激感が強く出ることがあります。また、アルコールを含むローションなども、同様に刺激を増す可能性があります。
医師や薬剤師への情報提供の重要性
安全な治療のため、診察時にはご自身が使用している薬の情報をすべて医師に伝えることが重要です。お薬手帳を持参すると、市販薬やサプリメントも含めて、使用中の薬剤を漏れなく正確に伝えることができ、より安全な治療につながります。
フェノトリン(スミスリン)の保険適用と薬価について
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険適用の対象疾患
日本において、医療用医薬品であるフェノトリン(スミスリンローション5%)が健康保険の適用として認められているのは、疥癬の治療のみです。
アタマジラミやケジラミの駆除を目的とする場合は、同様の成分を含む市販薬(スミスリンシャンプーなど)を薬局で購入することになり、自費での購入となります。
薬価の目安
| 薬剤名 | 規格 | 薬価(1gあたり) | 1本(30g)あたりの薬価 |
|---|---|---|---|
| スミスリンローション5% | 30g | 49.60円 | 1,488.0円 |
成人の場合、1回の治療で1本(30g)をほぼ使い切るため、標準的な2回治療では合計2本(60g)が必要となり、自己負担額は薬価の1~3割です。
以上
参考文献
Yamaguchi S, Yasumura R, Okamoto Y, Okubo Y, Miyagi T, Kawada H, Takahashi K. Efficacy and safety of a dimethicone lotion in patients with pyrethroid‐resistant head lice in an epidemic area, Okinawa, Japan. The Journal of dermatology. 2021 Sep;48(9):1343-9.
Executive Committee of Guideline for the Diagnosis and Treatment of Scabies, Ishii N, Asai T, Asahina A, Ishiko A, Imamura H, Kato T, Kanazawa N, Kubota Y, Kurosu H, Kono T. Guideline for the diagnosis and treatment of scabies in Japan Executive Committee of Guideline for the Diagnosis and Treatment of Scabies. The Journal of Dermatology. 2017 Sep;44(9):991-1014.
Chosidow O. Scabies and pediculosis. The Lancet. 2000 Mar 4;355(9206):819-26.
Prendiville JS. Scabies and lice. Harper’s Textbook of Pediatric Dermatology. 2011 Jun 3;1:72-1.
Burkhart CG, Burkhart CN. Safety and efficacy of pediculicides for head lice. Expert opinion on drug safety. 2006 Jan 1;5(1):169-79.
Downs AM, Stafford KA, Hunt LP, Ravenscroft JC, Coles GC. Widespread insecticide resistance in head lice to the over‐the‐counter pediculocides in England, and the emergence of carbaryl resistance. British Journal of Dermatology. 2002 Jan 1;146(1):88-93.
Orion E, Matz H, Ruocco V, Wolf R. Parasitic skin infestations II, scabies, pediculosis, spider bites: unapproved treatments. Clinics in dermatology. 2002 Nov 1;20(6):618-25.
Wendel K, Rompalo A. Scabies and pediculosis pubis: an update of treatment regimens and general review. Clinical Infectious Diseases. 2002 Oct 15;35(Supplement_2):S146-51.
Patel PU, Tan A, Levell NJ. A clinical review and history of pubic lice. Clinical and Experimental Dermatology. 2021 Oct 1;46(7):1181-8.