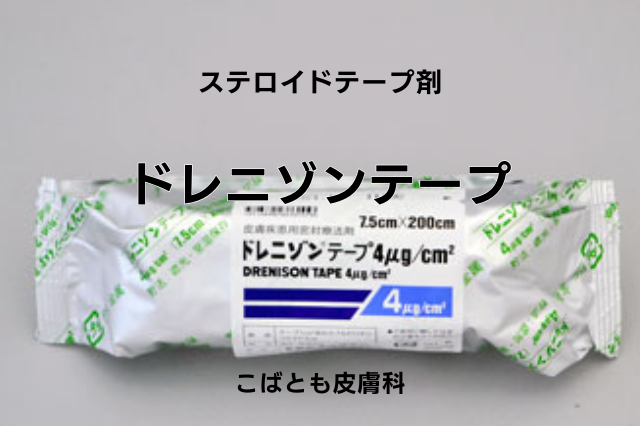フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)とは、主に皮膚科で使うステロイド外用薬で、テープ形状という特徴を持ちます。
皮膚に貼付することで有効成分が持続的に患部へ働きかけ、炎症やかゆみを和らげる目的で処方するケースが多いです。
局所に直接作用するため、内服ステロイドよりも全身性の副作用を抑えつつ、効果を期待できる点が大きなメリットになります。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
有効成分と効果、作用機序
フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)は、炎症を抑えるステロイドがテープに含まれた製剤です。ステロイド外用剤の中でも独自の形状を持ち、さまざまな皮膚症状に対して使われます。
有効成分の特徴
フルドロキシコルチドは、グルココルチコイド系のステロイド成分で、強力な抗炎症作用を持ち、アレルギー性の皮膚炎や湿疹、かゆみなどを抑制する役割を担います。
テープ製剤として加工されていることにより、以下のような特徴を持ちます。
- 患部に貼付するため、薬剤が局所で持続的に作用する
- 単純な外用薬に比べて密封効果を得やすい
- 汗や摩擦などに強く、一定時間患部を保護する
これらの特徴により、外用ステロイドを継続的に皮膚へ届けることが可能です。
作用機序の概要
ステロイドは、体内の免疫細胞が放出する炎症性物質の産生を抑える働きを持ち、フルドロキシコルチドテープも同様に、皮膚の炎症を引き起こすサイトカインの生成や好中球の過剰な活動を抑えます。
テープは皮膚表面を覆うため、蒸散を抑制し、皮膚温や湿度をある程度保ち、密封効果がステロイドの吸収を促進し、通常の軟膏よりも効率的に有効成分を届けられることが特徴です。
フルドロキシコルチドテープの主な特性
| 特性 | 内容 |
|---|---|
| 抗炎症作用 | サイトカインの産生を抑制し、炎症や発赤をコントロール |
| 抗アレルギー作用 | かゆみや腫れなど、アレルギー反応を和らげる |
| 密封効果(テープ形状の特性) | 薬剤の吸収を高め、長時間にわたる安定した効果を期待できる |
| 全身への影響 | 局所にとどまるため、内服ステロイドに比べれば低減されやすい |
炎症性皮膚疾患への効果
アトピー性皮膚炎や湿疹など、慢性化しやすい炎症性の皮膚疾患では、外用ステロイドの効果が重要で、フルドロキシコルチドテープは、局所に十分な濃度でステロイドを保つため、しつこいかゆみや赤みを抑える作用を期待できます。
特に、掻き壊しや寝ている間の擦れが原因で悪化する部位では、テープで患部を覆うことによる保護も役立ちます。
テープ製剤のメリット
通常の軟膏やクリームタイプの外用薬と比べて、テープ形状は次のようなことが利点があります。
- 薬剤が落ちにくい
- 就寝中にもはがれにくい
- 1日1回などの貼り替え指示を守りやすい
一方で、汗をかきやすい部位や関節の動きが大きい部位では、はがれるリスクや刺激感が増すことがあるため、貼る場所や方法に注意が必要です。
フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)の使用方法と注意点
フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)は、テープタイプならではの扱い方があり、貼り方や注意点を理解して、効率良く安全に治療を進めることが大切です。
テープの基本的な貼り方
テープを貼る時のステップ
- 患部を清潔にする
- 必要ならば水分や汚れを拭き取り、乾かす
- テープを指示どおりの大きさに切る(既定のサイズを使う場合は不要)
- 患部を覆うように丁寧に貼る
テープを無理に引っ張りながら貼ると、皮膚が引きつれて痛みが生じることがあります。密着性を高めるために、空気が入らないようにゆっくり貼るとことがポイントです。
テープを貼る際の注意点
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 患部の洗浄と乾燥 | 雑菌や皮脂を取り除くことで、薬の効果を安定して発揮 |
| テープの準備 | 必要な大きさにカットし、粘着面に触れすぎないよう注意 |
| テープの貼り付け | 空気が入り込まないようにゆっくり貼り、シワを作らない |
| 貼った後のチェック | かゆみや痛みが出ていないか、皮膚が突っ張っていないか確認 |
副作用を防ぐためのケア
ステロイドテープは密封効果があるため、皮膚がふやけたり細菌感染を起こしやすくなったりするリスクもあります。貼付部位が赤く腫れる、湿疹がかえって悪化するなどの兆候を見た場合、使用を一時的に中止し、医師に相談してください。
また、長時間貼り続けたままにするとかぶれの原因になる可能性があるので、医師や薬剤師から指示された貼付時間を守り、必要に応じて貼り替えを行うことが大切です。
テープ使用中に気をつけたいこと
- 1日1回など、決められた回数・時間で貼り替える
- 入浴後や汗をかいた後は、患部をよく乾かしてから再度テープを貼る
- 強いかゆみや湿疹が増したら、医療機関に連絡する
- 使用部位を必要以上にこすらない
テープをはがすときは、急に引っ張らず、皮膚を押さえながらゆっくりはがすと刺激が少なくなります。
用量と貼付時間
テープは1日1回の貼り替えが多いですが、症状や医師の方針によって異なり、長時間貼るほど効果が上がるわけではなく、指示を守ることが大切です。
一般的には24時間程度の貼り替えサイクルが多いため、貼付時間を管理しやすくなっています。
テープの貼付時間や頻度の目安
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 貼付頻度 | 1日1回が標準的 |
| 貼付時間 | 24時間程度(医師の指示に従う) |
| 貼り替えタイミング | 朝または就寝前が多い |
| 長期間使用の場合 | 定期的な経過観察が必要 |
注意すべき部位や状況
フルドロキシコルチドテープを貼ることが適さない部位や状況もあります。
化膿している部位や水疱がある場合、患部の状態を悪化させる可能性があり、また、すでに皮膚が薄くなっている箇所へテープを貼ると、強い刺激や皮膚障害の原因になるため、医師に相談したうえで適切な部位に使用することが重要です。
適応対象となる患者さん
フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)は、皮膚科領域で幅広く使われるステロイド製剤です。ただし、すべての皮膚トラブルに対して万能というわけではありません。
主な適応疾患
テープタイプのステロイド薬を使う場面は、主に以下のような皮膚症状です。
- アトピー性皮膚炎
- 湿疹(手湿疹や外的刺激による接触皮膚炎など)
- 乾癬の局所病変
- 掻破(ひっかき)による皮膚の炎症
- 慢性蕁麻疹による局所の皮膚炎
一時的に強い炎症が起きている部位をテープでカバーし、密封効果と抗炎症作用を得る目的があります。
代表的な疾患とテープ使用の目安
| 疾患名 | テープ使用の目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| アトピー性皮膚炎 | かゆみ・湿疹の緩和、掻破防止 | 長期使用時は皮膚の萎縮に注意 |
| 接触皮膚炎 | 原因物質除去後の急性炎症の緩和 | 感染兆候がある場合は医師の診断が必要 |
| 手湿疹 | 水仕事で悪化した箇所の集中的ケア | 指先など動きの多い部位でははがれやすい |
| 乾癬 | ステロイド効果による局所炎症の抑制 | 広範囲の場合は全身治療との併用が望ましい |
| 慢性蕁麻疹 | 繰り返し現れるかゆみの部分的コントロール | 原因究明や生活習慣改善も重要 |
小児や高齢者の場合
小児では皮膚が薄く、テープを剥がす際に刺激が強くなる可能性があり、また、高齢者も皮膚が薄い場合が多く、テープの粘着力によるトラブルを起こしやすいです。
しかし、テープの利点を活かしてうまく治療できるケースもあるため、医師と相談のうえ、テープのサイズや貼付時間を調整するなど工夫して使いましょう。
小児や高齢者で気をつけたい点
- テープをはがすときは皮膚を押さえながらゆっくり剥がす
- かぶれやすい体質の場合は短時間で様子を見る
- 薄い皮膚が傷つきやすい部位への貼付は最小限にする
- 定期的に皮膚の状態を観察し、異変があれば医師に相談する
生活習慣や職業との関係
水仕事やスポーツなどで汗をかきやすい環境にいる方は、テープがはがれやすかったり、湿気によって皮膚トラブルが発生しやすくなったりする場合があります。
テープを頻繁に貼り替える必要が出ることもあるため、職業やライフスタイルを考慮しながら使い方を調整することが必要です。
生活習慣や職業ごとの注意点
| 生活・職業パターン | 注意点 |
|---|---|
| 水仕事(調理、洗い物など) | テープが濡れてはがれやすくなる。貼り替え頻度を増やす |
| スポーツやジム通い | 汗で湿度がこもりやすい。こまめに状態をチェック |
| 屋外作業 | 直射日光や砂埃などの刺激が強い場合がある |
| 接客業やデスクワーク | 貼る部位や目立ち方に配慮が必要な場合がある |
併用療法の一環としてのテープ
ステロイドテープ単独で全ての皮膚症状をコントロールできるわけではありません。場合によっては、保湿剤や抗ヒスタミン薬などと併用することで相乗効果を期待することもあります。
医師が患者さんの症状や希望を総合的に判断し、テープによる治療を含めた最適なプランを提示する流れです。
フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)の治療期間
フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)は強力な抗炎症作用を持っていますが、長く貼り続けすぎると副作用が増える一方、十分な治療期間を確保しないと再発リスクが高まる場合もあります。
急性期の集中治療
湿疹や皮膚炎が急性期に入り、赤みや腫れ、かゆみなどが強い場合には、テープを使って集中的に炎症を抑える方針を取ることがあります。
数日から1週間ほど集中的に使用して、症状が緩和したら貼付時間や回数を減らしたり、通常の外用薬や保湿剤へ移行することが多いです。
急性期集中治療の例
- 1日1回、24時間貼付で1週間
- 症状が軽くなったら週末だけ貼るなどの段階的な減量
- 急性期に完治を目指すよりは、強い症状を抑えて日常生活を取り戻すのが目的
集中治療の期間は、症状の程度や回復の速さによって変動します。
慢性期の維持療法
アトピー性皮膚炎など、慢性的に皮膚の炎症が続く疾患では、長期的な視点での管理が必要です。
テープを長期間連続して使用すると、皮膚萎縮などの副作用リスクが高まるため、症状が落ち着いている期間は使用を控える、または使用頻度を大幅に下げるなどの工夫を行います。
慢性期の治療期間管理と方法
| 治療ステップ | 方法 | 目的 |
|---|---|---|
| 症状安定期 | テープの使用を減らし、保湿剤や軽めの外用ステロイドへ切り替え | 副作用リスクの抑制 |
| 軽度再燃時 | 痒みや赤みが出始めた段階でテープを短期間再開 | 症状の重症化を防ぐ |
| 完全寛解に近い状態 | テープを使わず、保湿ケアや生活習慣改善中心に管理 | ステロイド依存を避ける |
長期連用のリスク
ステロイドの長期使用は、皮膚が薄くなる(萎縮)、毛細血管拡張、色素沈着などの局所的な副作用や、まれに全身的な影響を及ぼす場合があります。
テープ製剤は密封効果によって皮膚への浸透量が多くなる傾向があるため、症状が落ち着いてきたら使用を減らし、長期連用の基準を医師と共有し、定期的な診察で副作用の有無をチェックします。
治療終了の判断
症状が改善し、皮膚が元の状態に近づいた場合、テープによる治療を終了するかどうかを判断し、医師によっては、完治を目指してしばらく経過観察をしながら、徐々にテープ使用の頻度を落としていくことを提案する場合があります。
急に使用をやめるとリバウンド現象で再発しやすいケースもあるため、段階的な減量が大切です。
フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)の副作用やデメリット
ステロイド薬の使用には、必ず副作用やデメリットの可能性が伴います。フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)は局所作用が中心ですが、長期または広範囲で使うと皮膚障害のリスクが増大します。
皮膚に現れる副作用
ステロイドを局所的に使うことで起こりうる皮膚の変化には以下のようなものがあります。
- 皮膚萎縮(薄くなる)
- 毛細血管拡張
- 色素沈着(色むらが生じる)
- 皮膚の感染症(細菌・真菌など)を起こしやすくなる
テープ形状は密閉力が高いため、軟膏やクリームよりも皮膚がふやけたり、感染リスクが増す場合があり、気になる症状が出たら、使用を一時中止して医師の診察を受けてください。
テープ使用時に注意が必要な皮膚症状と対策
| 症状 | 対策 |
|---|---|
| 皮膚萎縮 | 長期連用を避け、症状が軽くなったら使用頻度を下げる |
| 毛細血管拡張 | 強力なステロイドの連用を控える |
| 色素沈着 | こまめに皮膚状態を確認し、異常があれば医師に相談 |
| 感染症(細菌・真菌) | 発赤や痛み、膿などの兆候があれば速やかに医師へ報告 |
全身性の副作用
テープ製剤は一般的に全身への吸収量が内服薬ほど多くはありません。
しかし、広範囲に長期間使用した場合や肌のバリア機能が低下している場合、ステロイドが血中に吸収されやすくなり、むくみや血糖値の上昇など、全身的な副作用が起こる可能性も否定できません。
全身性の副作用例
- むくみや体重増加
- 血糖値上昇(糖尿病が悪化するリスク)
- 免疫抑制による感染症リスク増大
- 胃腸障害
ただし、外用テープのみの使用でこのような症状が顕著に出るケースは多くありません。
粘着性によるトラブル
テープを貼るときの粘着力が強いため、肌が弱い方や小児、高齢者では皮膚がかぶれたり剥がすときに強い痛みを感じる場合があります。
また、関節部位や曲げ伸ばしの多い場所では、動きに伴ってテープが剥がれやすくなり、皮膚トラブルが生じやすいです。
医療費や手間の面
テープタイプは1枚ごとのコストが軟膏やクリームに比べて高い傾向があり、使用範囲が大きい方は、多くの枚数を必要とする場合もあり、医療費負担が気になるかもしれません。
また、貼付や剥がす際に時間や手間がかかるなど、使用面でのデメリットを感じる方もいます。
効果がなかった場合
フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)は多くの皮膚疾患に対して有効ですが、必ずしもすべての人に十分な効果を発揮するわけではありません。
効果が不十分な場合や、まったく改善を感じない場合は、原因の分析と別の治療法の検討が必要です。
効果が出ない原因
効果が出ない一因として、貼り方や使用方法の誤りが考えられます。テープのサイズが合っていない、こまめな貼り替えが行われていない、患部が十分に清潔でないなど、基本的な使用方法を改めてチェックしてみることが大切です。
よくある使用方法の不備と改善策
| 不備の例 | 改善策 |
|---|---|
| 患部を清潔にせず貼る | 入浴後や洗浄後、よく乾かしてから貼り付ける |
| 長時間放置しすぎ | 指示された時間どおりに貼り替えて、皮膚の状態を確認する |
| サイズが小さく一部しか覆えていない | 十分に患部を覆える大きさのテープを使う、または複数枚を適切に貼り合わせる |
他のステロイド外用薬や治療法の検討
フルドロキシコルチドテープは確かに便利ですが、症状や部位によっては他のステロイド外用剤が向いている可能性があります。
強度の違うステロイド軟膏やクリーム、あるいは免疫調整剤や生物学的製剤など、別の治療法を試すことで改善が見込める場合があるので、医師との相談を通じて、最適な治療プランを再構築することが重要です。
原因疾患の再評価
皮膚症状の奥に別の疾患が隠れているケースも考えられ、例えば、アレルギー検査をしていない場合、真のアレルゲンを除去できていないのかもしれません。
また、内臓疾患やホルモンバランスの乱れなどが皮膚トラブルを引き起こす場合もあり、効果が乏しいと感じたら、皮膚科の範囲を越えた原因検索が必要になる可能性もあります。
再評価を考える際のチェックポイント
- 食生活やストレス、睡眠不足など生活習慣はどうか
- 職場や家庭環境で皮膚に負荷をかける要因があるか
- 糖尿病や甲状腺疾患など、既往症の影響はないか
- 症状が悪化する特定の季節や環境があるか
他の治療薬との併用禁忌
フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)は多くの状況で併用が可能ですが、特定の薬剤や成分との組み合わせで注意が必要な場合があります。
ステロイドの重複使用
ステロイド薬を複数組み合わせると、皮膚や全身への影響が強くなる可能性があります。
内服ステロイドや他の強い外用ステロイドをすでに使用している場合、フルドロキシコルチドテープを追加することで、ステロイド過剰による副作用が増えるリスクがあり、医師に現在使用中の薬剤を正確に伝えておくことが必要です。
ステロイド重複使用のリスク
| リスク項目 | 具体例 |
|---|---|
| 皮膚の副作用増加 | 皮膚萎縮、毛細血管拡張、感染リスクの上昇など |
| 全身性の副作用の拡大 | 高血糖、むくみ、免疫力低下など |
| 離脱症状やリバウンド | 急に減量すると症状のぶり返しやホルモンバランス異常 |
感染症治療薬との併用
フルドロキシコルチドテープは免疫反応を抑える可能性があるため、皮膚が感染しやすい状態になり、抗生物質や抗真菌薬を使う場合には、どちらの治療を優先すべきか、医師の判断が必要です。
感染症が進行している部位にステロイドを使うと治りにくくなる恐れがあるため、細心の注意を払います。
他の外用薬との重ね塗りや重ね貼り
保湿剤や他の外用ステロイドと一緒に使う場合、重ねて塗ることで皮膚の吸収率が変化し、過剰な刺激や逆に吸収不足が起こる場合があるので、テープの上から別の外用薬を塗るのは基本的に推奨されません。
併用が必要なら、医師や薬剤師に適切な塗布手順を確認するのが安全です。
外用薬を併用する際の注意点
- テープを貼る部位には他の薬を重ね塗りしない
- どうしても併用が必要な場合は時間差をつける
- テープを剥がしてしばらくしてから別の薬を塗る方法を検討する
- 接触皮膚炎が起きていないか定期的に確認する
サプリメントや市販薬との組み合わせ
市販薬の中には、皮膚のターンオーバーに影響を与える成分やホルモンバランスに影響する成分を含むものがあります。
フルドロキシコルチドテープとの組み合わせによる重大な相互作用はあまり報告されていませんが、念のために現在摂取しているサプリメントや市販薬の情報を医師へ伝えると安心です。
フルドロキシコルチドテープ(ドレニゾンテープ)の保険適用と薬価について
以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
保険適用の範囲
通常の皮膚科診療で処方される範囲内であれば、多くの場合保険が適用になります。ただし、美容目的や適応外使用での処方の場合、保険の対象外になる可能性があるため、診察時に医師に確認すると安心です。
保険適用に関する主なポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険診療の前提 | 医師の診察や処方があること |
| 適応疾患の範囲 | アトピー性皮膚炎、湿疹など多くの皮膚炎症に対応 |
| 自己負担割合 | 年齢や収入により1割~3割が基本的 |
| 適応外使用の扱い | 保険適用外となり全額自己負担となる場合がある |
薬価の目安
フルドロキシコルチドテープには複数の規格やサイズがあります。サイズが大きいテープほど薬価が高くなります。
- テープのサイズや枚数によって変動する
- 他のステロイド外用薬と比較するとやや高めの傾向
- 1枚あたりのコストは数十円〜数百円程度(保険点数などで異なる)
- 定期的に薬価改定が行われるため、最新情報は薬局や医師に確認する
以上
参考文献
Burr S. FLUDROXYCORTIDE TAPE: A VERSATILE, WELL-TOLERATED TREATMENT OPTION. Dermatological Nursing. 2021 Jun 1;20(2).
Goutos I, Ogawa R. Steroid tape: a promising adjunct to scar management. Scars, burns & healing. 2017 Feb 28;3:2059513117690937.
Ogawa R. Effectiveness of corticosteroid tapes and plasters for keloids and hypertrophic scars. Textbook on scar management: state of the art management and emerging technologies. 2020:491-6.
Aslam N. IMPACT OF ECZEMA AND OTHER DERMATOSES ON MENTAL AND EMOTIONAL HEALTH: THE ROLE OF STEROID TAPE IN ECZEMA MANAGEMENT. Dermatological Nursing. 2023 Sep 1;22(3).
Brown A. Managing hypergranulation in wounds. Journal of Community Nursing. 2024 Feb 1;38(1).
Sheng M, Chen Y, Li H, Zhang Y, Zhang Z. The application of corticosteroids for pathological scar prevention and treatment: current review and update. Burns & Trauma. 2023;11:tkad009.
Ogawa R, Akita S, Akaishi S, Aramaki-Hattori N, Dohi T, Hayashi T, Kishi K, Kono T, Matsumura H, Muneuchi G, Murao N. Diagnosis and treatment of keloids and hypertrophic scars—Japan scar workshop consensus document 2018. Burns & trauma. 2019 Dec 1;7.
Ogawa R, Quong WL. Effective treatment of an aggressive chest wall keloid in a woman using deprodone propionate plaster without surgery, radiotherapy, or injection. Plastic and Reconstructive Surgery–Global Open. 2024 Sep 1;12(9):e6117.
Sugaya M, Nagashima A, Nakamura R, Yano M, Morita T, Niijima Y, Takekoshi T, Kanda N, Tanaka M. Treatment of facial reactive B‐cell rich lymphoid proliferation with dapsone. The Journal of Dermatology.
Ogawa R, Akaishi S, Kuribayashi S, Miyashita T. Keloids and hypertrophic scars can now be cured completely: recent progress in our understanding of the pathogenesis of keloids and hypertrophic scars and the most promising current therapeutic strategy. Journal of Nippon Medical School. 2016 Apr 15;83(2):46-53.