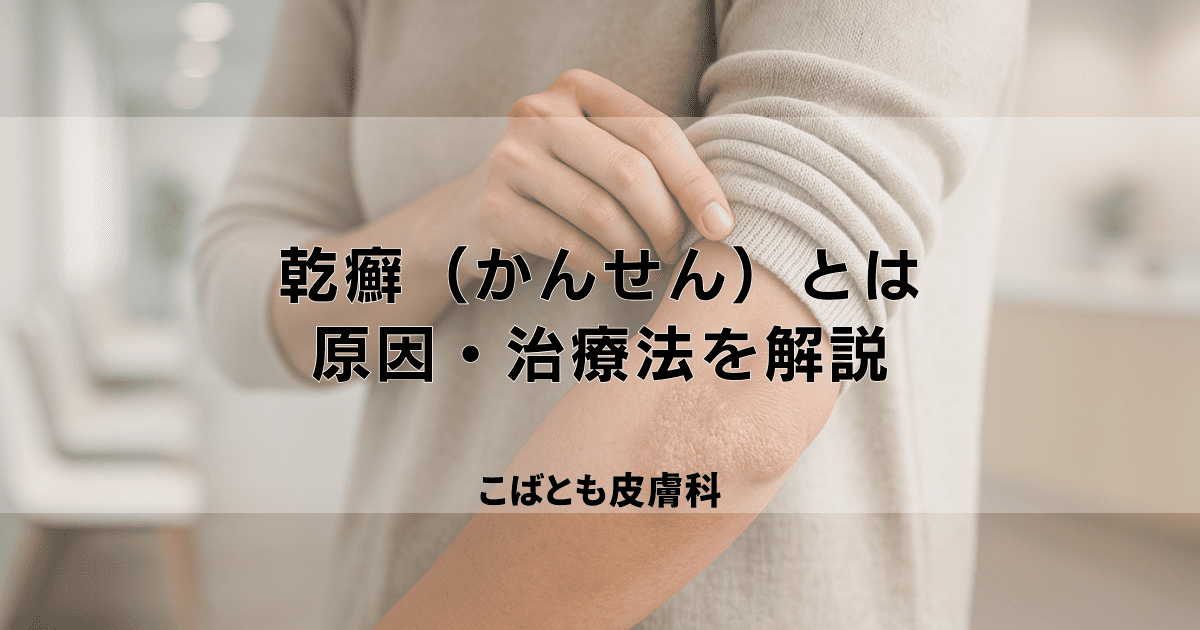皮膚が赤くなって盛り上がり、フケのようなものがポロポロと剥がれ落ちる。もし、このような症状にお悩みでしたら、それは乾癬(かんせん)かもしれません。乾癬は、単なる肌荒れや湿疹とは異なる、皮膚の病気です。
見た目の症状から誤解されることもありますが、人にうつることはありません。
この記事では、乾癬とはどのような病気なのか、原因から症状、誤解されがちな感染の有無、そして皮膚科で行う治療法まで、分かりやすく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
乾癬の基本的な知識
乾癬という病名を聞いたことはあっても、どのような病気なのか、詳しくは知らない方が多いかもしれません。まずは、乾癬の最も基本的な情報と、多くの方が抱く疑問について見ていきましょう。
乾癬とはどのような皮膚の病気か
乾癬は、皮膚の炎症と、それに伴う角質細胞の異常な増殖が特徴の、慢性の皮膚疾患です。
私たちの皮膚は、通常約1ヶ月の周期で新しい細胞に生まれ変わり、これをターンオーバーと呼びます。しかし、乾癬の皮膚では、このターンオーバーが異常に速まり、わずか4〜5日で新しい細胞が作られてしまいます。
未熟なままの皮膚細胞が次々と押し上げられることで、皮膚が厚く盛り上がり、赤みを帯び、表面に銀白色の鱗屑(りんせつ)が付着するのです。
症状は、良くなったり悪くなったりを繰り返すことが多く、長い付き合いになることも少なくありません。
皮膚の赤みや盛り上がり、フケのような鱗屑(りんせつ)
乾癬の代表的な症状は、皮膚に現れる「紅斑(こうはん)」「浸潤・肥厚(しんじゅん・ひこう)」「鱗屑(りんせつ)」の3つです。
紅斑は皮膚が赤くなること、浸潤・肥厚は皮膚が盛り上がって厚くなること、そして鱗屑は表面を覆う銀白色のフケのようなもので、ポロポロと剥がれ落ちます。
症状がはっきりと現れるのが乾癬の特徴で、湿疹など他の皮膚疾患との見分ける重要なポイントです。痒みを伴うこともありますが、全く痒みを感じない方や、強い痒みに悩まされる方など、程度には個人差があります。
乾癬の主な皮膚症状
| 症状 | 特徴 | 補足 |
|---|---|---|
| 紅斑 | 皮膚が赤みを帯びる | 炎症による血管の拡張が原因 |
| 浸潤・肥厚 | 皮膚が厚く盛り上がる | 皮膚細胞の異常な増殖によるもの |
| 鱗屑 | 銀白色のフケのようなもの | 剥がれやすい角質。掻くと剥がれ落ちる |
乾癬はうつらないことを正しく理解する
乾癬という名前や見た目の症状から、「他の人にうつるのではないか」と心配される方が非常に多くいらっしゃいますが、これは大きな誤解です。
乾癬は、細菌やウイルスが原因の感染症ではなく、皮膚が直接触れ合ったり温泉やプールに一緒に入ったり、タオルを共有したりしても、他の人にうつることはありません。
日本における乾癬の患者数と発症年齢
以前は欧米に多い病気とされていましたが、近年、日本でも患者数が増加傾向にあります。現在、日本の乾癬患者数は推定で50〜60万人にのぼるとみられています。
発症年齢は、20代から40代の比較的若い世代に多い傾向がありますが、子供から高齢者まで、どの年代でも発症する可能性があります。男女比では、男性の方が女性よりもやや多いです。
乾癬の主な種類とその特徴
乾癬と一括りにいっても、いくつかの種類(病型)に分類されます。症状の現れ方や合併症の有無によって分けられ、それぞれ治療方針も異なります。
最も多い尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)
尋常性乾癬は、乾癬患者さんの約90%を占める最も一般的なタイプです。頭部、肘、膝、腰回りなど、外部からの刺激を受けやすい部位に、境界がはっきりとした赤い発疹(紅斑)が現れ、その上に銀白色の鱗屑が付着します。
一つ一つの発疹が大きくなったり、複数の発疹がくっついて大きな病変になったりすることもあります。爪が変形したり、厚くなったりする爪乾癬を合併することも少なくありません。
関節の痛みを伴う関節症性乾癬(かんせつしょうせいかんせん)
皮膚の症状に加えて、関節リウマチのように関節の腫れや痛みが現れるのが、関節症性乾癬です。乾癬患者さんの10〜15%程度に見られます。指や足の関節、アキレス腱、背骨など、様々な関節に症状が出ます。
皮膚症状が先に出ることが多いですが、関節の症状が先に出る場合や、同時に現れることもあります。関節の変形につながることもあるため、早期の診断と治療が大切です。
発熱や倦怠感を伴う膿疱性乾癬(のうほうせいかんせん)
急な発熱や全身の倦怠感とともに、皮膚が広範囲に赤くなり、その上に膿を持った小さな水ぶくれ(膿疱)がたくさん現れる特殊なタイプの乾癬で、膿疱の中には細菌はおらず、無菌性です。
症状が急激に悪化することがあり、入院治療が必要になる場合もあり、国の指定難病にも定められています。
全身の皮膚が赤くなる乾癬性紅皮症(かんせんせいこうひしょう)
尋常性乾癬が全身に広がり、皮膚の90%以上が赤くなってしまう状態です。全身の皮膚が真っ赤になり、大量の鱗屑が剥がれ落ち、皮膚のバリア機能が損なわれるため、体温調節が難しくなったり、水分が失われやすくなったりします。
入院治療が必要になることが多く、速やかな対応が必要です。
乾癬の主な種類と特徴
| 種類(病型) | 主な特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 尋常性乾癬 | 最も多く、典型的な皮膚症状 | 爪の変形を伴うことがある |
| 関節症性乾癬 | 皮膚症状に加え、関節の痛みや腫れ | 関節の変形を防ぐ早期治療が重要 |
| 膿疱性乾癬 | 発熱と膿疱(うみを持った水ぶくれ) | 急激に悪化することがあり入院治療が必要 |
| 乾癬性紅皮症 | 全身の皮膚が赤くなる | 体温調節異常などを起こしやすく入院治療が必要 |
乾癬が発症する原因
なぜ乾癬が発症するのか、はっきりとした原因はまだ完全には解明されていませんが、近年の研究により、いくつかの要因が複雑に絡み合って発症に関わっていることが分かってきました。
遺伝的な要因と乾癬の関係
乾癬は、特定の遺伝子が一つあるだけで発症するような単純な遺伝病ではありません。しかし、乾癬になりやすい体質(遺伝的素因)があることは分かっています。
血縁者に乾癬の方がいる場合、いない場合に比べて発症する可能性が少し高くなるというデータがあります。ただし、これはあくまで「なりやすさ」を受け継ぐということであり、必ずしも発症するわけではありません。
乾癬発症に関わる遺伝的要因
- 特定の遺伝子による単純な遺伝病ではない
- 乾癬になりやすい体質(遺伝的素因)の存在
- 家族内での発症例は発症リスクを高める可能性
免疫システムの異常な働き
乾癬の発症には、免疫システムの異常が深く関わっていて、本来、免疫は細菌やウイルスなどの外敵から体を守るための大切な仕組みです。
しかし、何らかのきっかけでこの免疫システムに異常が生じ、自分自身の正常な皮膚細胞を攻撃してしまうことがあります。
この攻撃により皮膚に炎症が起こり、ターンオーバーが異常に速まることで、乾癬の症状が現れます。このため、乾癬は自己免疫疾患の一つとして捉えられています。
発症や悪化を招く環境的な要因
遺伝的な素因を持つ人が、様々な外的・内的な刺激(環境要因)を受けることで、乾癬が発症したり、症状が悪化したりすることが知られています。要因は人によって様々で、一つだけでなく複数が関係していることもあります。
日常生活の中で、要因をできるだけ避けることが、症状をコントロールする上で大切です。
乾癬の症状を悪化させる可能性のある要因
| 分類 | 具体的な要因の例 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| 物理的刺激 | 怪我、衣類の摩擦、掻きむしり | 健康な皮膚に刺激が加わると、そこに新たな発疹が出ることがある(ケブネル現象) |
| 感染症 | 風邪(特に溶連菌感染症)、扁桃腺炎 | 感染症をきっかけに免疫系が活性化し、乾癬が悪化することがある |
| 生活習慣 | 不規則な生活、睡眠不足、喫煙、過度の飲酒 | 体のバランスを崩し、免疫機能に影響を与える可能性がある |
| 精神的ストレス | 仕事や人間関係の悩み | ストレスは免疫系のバランスを乱し、症状を悪化させる一因となる |
| 薬剤 | 一部の降圧薬、痛み止めなど | 特定の薬の内服が、乾癬の発症や悪化のきっかけになることがある |
乾癬の症状が現れやすい部位
乾癬の皮疹は、体のどこにでも現れる可能性がありますが、特に刺激を受けやすい場所や、特徴的な部位に出やすい傾向があります。好発部位を知っておくことは、早期発見や、他の皮膚疾患との区別に役立ちます。
頭皮や髪の生え際
頭皮は乾癬が非常によく見られる部位の一つで、フケが大量に出る、かさぶたのようなものができる、といった症状で気づかれることが多いです。
脂漏性皮膚炎と間違われることもありますが、乾癬の場合は赤みのある部分の境界が比較的はっきりしています。髪の生え際にも症状が出やすく、見た目に影響するため悩まれる方が多い部位です。
肘や膝などの刺激を受けやすい部分
肘や膝は、衣服で擦れたり、机についたり、曲げ伸ばしをしたりと、日常的に物理的な刺激を受けやすい部位です。このような慢性的な刺激は、乾癬の症状を誘発しやすいと考えられています。
乾癬の初期症状として、肘や膝に小さな発疹が現れることも少なくありません。
刺激を避けるための工夫
- 締め付けの少ない、柔らかい素材の衣類を選ぶ
- 入浴時にナイロンタオルなどでゴシゴシ洗わない
- 皮膚を掻きむしらないように爪を短く切る
腰回りやおしり
ベルトによる締め付けや、長時間座っていることによる圧迫など、腰回りやおしりも刺激を受けやすい部位です。特にデスクワークが多い方などは、症状が悪化しやすい傾向が見られます。
下着のゴムによる摩擦も、症状を悪化させる要因になり得ます。
爪の変化にも注意が必要
乾癬は皮膚だけでなく、爪にも症状が現れることがあり、爪乾癬と呼びます。爪に小さな凹みができる(爪甲点状陥凹)、爪が厚くなる、変色する、先端が剥がれてくる(爪甲剥離)などの変化が見られます。
爪の症状は、関節症性乾癬を合併している患者さんでよく見られる兆候の一つでもあり、注意が必要です。水虫(爪白癬)と見た目が似ているため、自己判断せずに専門医の診断を受けることが大切です。
爪乾癬の主な症状
| 爪の症状 | 見た目の特徴 |
|---|---|
| 爪甲点状陥凹(そうこうてんじょうかんおう) | 爪の表面に針で刺したような小さな凹みができる |
| 爪甲剥離症(そうこうはくりしょう) | 爪の先端が爪床から剥がれて白く見える |
| 爪甲下角質増殖(そうこうかかくしつぞうしょく) | 爪の下に角質が厚くたまり、爪が盛り上がって見える |
皮膚科での乾癬の診断方法
乾癬の症状は、他の皮膚疾患と似ている場合があるため、正確な診断を下すには皮膚科専門医による診察が重要です。クリニックでは、いくつかの方法を組み合わせて総合的に判断します。
専門医による視診と問診
診断の基本は、医師が皮膚の状態を直接目で見て確認する視診です。乾癬に特徴的な、境界がはっきりした紅斑、銀白色の鱗屑、皮膚の盛り上がりなどを詳しく観察します。
また、問診では、いつから症状があるか、どのような経過をたどっているか、家族に乾癬の人はいるか、関節の痛みはないか、生活習慣などについて詳しくお話を伺います。
ダーモスコピーを用いた詳細な観察
ダーモスコピーは、ダーモスコープという特殊な拡大鏡を使って、皮膚の表面を詳しく観察する検査です。光の乱反射を抑えることで、皮膚の内部の色素の分布や血管の状態などをより詳細に見ることができます。
乾癬の病変部では、特徴的な点状の血管のパターンが観察されることが多く、この所見は湿疹など他の疾患との鑑別に役立ちます。
必要に応じて行う皮膚生検
視診やダーモスコピーでも診断が難しい場合や、他の病気の可能性を否定するために、皮膚生検を行うことがあります。これは、局所麻酔をした上で、病変部のごく一部(米粒大程度)を採取し、顕微鏡で組織の状態を詳しく調べる検査です。
乾癬に特徴的な皮膚の構造の変化(角層の異常、表皮の肥厚、真皮の炎症細胞など)を確認することで、確定診断に至ります。
診断の流れの概要
| 検査段階 | 主な内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 問診 | 症状の経過、家族歴、生活習慣などの聴取 | 診断の手がかりを得る |
| 視診 | 皮疹の形、色、分布などを直接観察 | 乾癬に特徴的な所見を確認する |
| 皮膚生検(必要時) | 皮膚組織を採取し、顕微鏡で調べる | 確定診断や他の疾患との鑑別 |
乾癬の治療法
乾癬の治療目標は、症状をコントロールし、QOL(生活の質)を高く維持することです。
現在のところ乾癬を完全に消し去る治療法はありませんが、治療法の進歩は目覚ましく、治療を継続することで、症状がほとんどない状態を長期間保つことも可能になってきました。
塗り薬(外用療法)による治療
外用療法は、乾癬治療の基本となる方法で、軽症から中等症の患者さんに主に行います。患部に直接薬を塗ることで、皮膚の炎症や異常な細胞増殖を抑え、主に使われるのはステロイド外用薬とビタミンD3外用薬です。
それぞれ作用の仕方が異なるため、単独で使ったり、2種類を組み合わせて使ったりし、最近では、この2つの成分を配合した合剤も広く使われています。
主な外用薬の種類
| 薬剤の種類 | 主な作用 | 剤形 |
|---|---|---|
| ステロイド外用薬 | 強い抗炎症作用で皮膚の赤みや腫れを抑える | 軟膏、クリーム、ローション、シャンプーなど |
| ビタミンD3外用薬 | 皮膚細胞の異常な増殖を抑制し、正常な状態に導く | 軟膏、クリーム、ローションなど |
| 配合剤 | ステロイドとビタミンD3の両方の作用を持つ | 軟膏、フォーム、ゲルなど |
飲み薬(内服療法)による治療
外用療法だけでは効果が不十分な場合や、皮疹の範囲が広い中等症から重症の患者さん、または関節症状を伴う場合に内服療法を検討します。
免疫の働きを調整する薬(シクロスポリン、メトトレキサートなど)や、炎症に関わる物質の働きを抑える薬(アプレミラスト)などがあります。
薬は全身に作用するため、定期的な検査で副作用をチェックしながら慎重に使用することが重要です。
内服療法のポイント
- 中等症から重症の患者さんが対象
- 全身の免疫や炎症に作用する
- 定期的な血液検査などによる副作用の確認が必要
紫外線を利用した光線療法(紫外線療法)
光線療法は、乾癬の症状を改善する効果のある特殊な波長の紫外線を、患部に照射する治療法です。皮膚の過剰な免疫反応を抑えることで効果を発揮し、主に、中波紫外線(UVB)や、長波紫外線(UVA)が用いられます。
週に1〜3回程度の通院が必要になりますが、内服薬のような全身性の副作用が少ないという利点があり、広範囲の皮疹に有効です。
生物学的製剤による治療
生物学的製剤は、乾癬の炎症を引き起こしている特定の物質(サイトカイン)の働きをピンポイントでブロックする注射薬です。
これまでの治療で効果が不十分だった重症の患者さんや、関節症性乾癬の患者さんにとって、大きな希望となる治療法です。非常に高い効果が期待できる一方で、免疫の働きを抑えるため感染症のリスク管理が大切になります。
日常生活で心がけたいこと
乾癬の症状を良好な状態でコントロールしていくためには、皮膚科での治療と並行して、日々の生活習慣を見直すことも非常に大切です。
皮膚への刺激を避ける工夫
乾癬の皮膚は非常にデリケートです。衣類の摩擦や掻きむしりなどの物理的な刺激は、症状を悪化させたり新たな皮疹を作ったりするケブネル現象の引き金になります。
肌触りの良い木綿素材の衣類を選んだり、体を洗うときは石鹸をよく泡立てて手で優しく洗ったりするなど、皮膚への刺激を最小限に抑える工夫を心がけましょう。保湿剤をこまめに塗って皮膚の乾燥を防ぐことも、バリア機能を保つ上で重要です。
バランスの取れた食事と栄養
特定の食べ物が乾癬を良くしたり悪くしたりするという科学的な根拠は、現在のところ明確ではありません。しかし、健康な体を作る基本として、バランスの取れた食事は非常に大切です。
脂肪分の多い食事や香辛料の強い食事は、炎症を助長する可能性があるため、摂りすぎには注意が必要で、野菜や魚などを中心とした、栄養バランスの良い食生活を意識しましょう。
食事で意識したいこと
- 脂肪の多い肉類や揚げ物は控えめにする
- 青魚(サバ、イワシなど)に含まれる油は炎症を抑える助けになる可能性がある
- 野菜や果物からビタミンやミネラルを十分に摂る
- 暴飲暴食を避け、腹八分目を心がける
ストレス管理と十分な休養
精神的なストレスは、免疫のバランスを乱し、乾癬を悪化させる大きな要因の一つです。ストレスを完全になくすことは難しいですが、自分なりの解消法を見つけて、上手に付き合っていくことが大切です。
趣味に没頭する時間を作ったり、軽い運動をしたり、ゆっくりと入浴したりするのも良いでしょう。また、睡眠不足も体の抵抗力を下げてしまうため、質の良い睡眠を十分にとることを心がけてください。
喫煙や過度な飲酒の影響
喫煙は、乾癬の発症リスクを高め、症状を悪化させることが多くの研究で報告されています。また、治療効果を弱めてしまう可能性も指摘されています。禁煙は、乾癬のコントロールだけでなく、全身の健康にとっても非常に有益です。
過度の飲酒も、症状を悪化させる要因となり得るため、控えることが望ましく、特に、内服薬で治療している場合は、肝臓への負担を増大させる可能性があるため、医師の指示に従う必要があります。
生活習慣の見直しポイント
| 項目 | 推奨される行動 | 避けるべき行動 |
|---|---|---|
| 皮膚ケア | 保湿、優しい洗浄 | 掻きむしり、強い摩擦 |
| 食事 | バランスの良い食事 | 高脂肪食、過度の飲酒 |
| 生活全般 | 十分な睡眠、禁煙、ストレス管理 | 不規則な生活、喫煙 |
よくある質問
最後に、乾癬の患者さんから特によく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 乾癬は完治しますか?
-
現在の医療では、残念ながら乾癬を完全に消し去り、再発しない状態にする完治は難しいとされ、良くなったり悪くなったりを繰り返す慢性の病気です。
しかし、治療法の進歩は目覚ましく、治療を継続することで、症状がほとんどない、あるいは全くない状態(寛解)を長期間維持することは十分にできます。
- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?
-
治療期間は、患者さん一人ひとりの症状の重症度や種類、治療法への反応によって大きく異なりため、一概にこのくらいの期間で良くなると断言することはできません。
乾癬は慢性的な経過をたどる病気であるため、症状が良くなったからといって自己判断で治療を中断してしまうと、再び悪化(再燃)することがあります。
根気強く治療を続け、医師と相談しながら症状をコントロールしていくことが大切です。
- 民間療法やサプリメントは効果がありますか?
-
乾癬に対して効果があると謳う様々な民間療法やサプリメントがありますが、多くは科学的な根拠が乏しいのが現状です。中には、症状を悪化させたり、標準的な治療の妨げになったりするものもあります。
健康食品やサプリメントを試したい場合は、必ず事前にかかりつけの皮膚科専門医に相談してください。
以上
参考文献
Fujita H, Terui T, Hayama K, Akiyama M, Ikeda S, Mabuchi T, Ozawa A, Kanekura T, Kurosawa M, Komine M, Nakajima K. Japanese guidelines for the management and treatment of generalized pustular psoriasis: the new pathogenesis and treatment of GPP. The Journal of dermatology. 2018 Nov;45(11):1235-70.
Kamiya K, Oiso N, Kawada A, Ohtsuki M. Epidemiological survey of the psoriasis patients in the Japanese Society for Psoriasis Research from 2013 to 2018. The Journal of Dermatology. 2021 Jun;48(6):864-75.
Komine M, Morita A. Generalized pustular psoriasis: current management status and unmet medical needs in Japan. Expert Review of Clinical Immunology. 2021 Sep 2;17(9):1015-27.
Hajime Iizuka MD. Management of Patients with Psoriasis in Japan. Advances in Psoriasis and Inflammatory Skin Diseases. 2011 Apr 1;2(4):126.
Saeki H, Nakagawa H, Nakajo K, Ishii T, Morisaki Y, Aoki T, Cameron GS, Osuntokun OO, Japanese Ixekizumab Study Group, Akasaka T, Asano Y. Efficacy and safety of ixekizumab treatment for Japanese patients with moderate to severe plaque psoriasis, erythrodermic psoriasis and generalized pustular psoriasis: results from a 52‐week, open‐label, phase 3 study (UNCOVER‐J). The Journal of dermatology. 2017 Apr;44(4):355-62.
Ohata C, Ohyama B, Kuwahara F, Katayama E, Nakama T. Real-world data on the efficacy and safety of apremilast in Japanese patients with plaque psoriasis. Journal of Dermatological Treatment. 2019 May 19;30(4):383-6.
Raharja A, Mahil SK, Barker JN. Psoriasis: a brief overview. Clinical Medicine. 2021 May 1;21(3):170-3.
Kimmel GW, Lebwohl M. Psoriasis: overview and diagnosis. Evidence-Based Psoriasis: Diagnosis and Treatment. 2018 Jul 1:1-6.
De Rie MA, Goedkoop AY, Bos JD. Overview of psoriasis. Dermatologic therapy. 2004 Oct;17(5):341-9.
Limaye K. Psoriasis: an overview and update. The Nurse Practitioner. 2015 Mar 12;40(3):23-6.