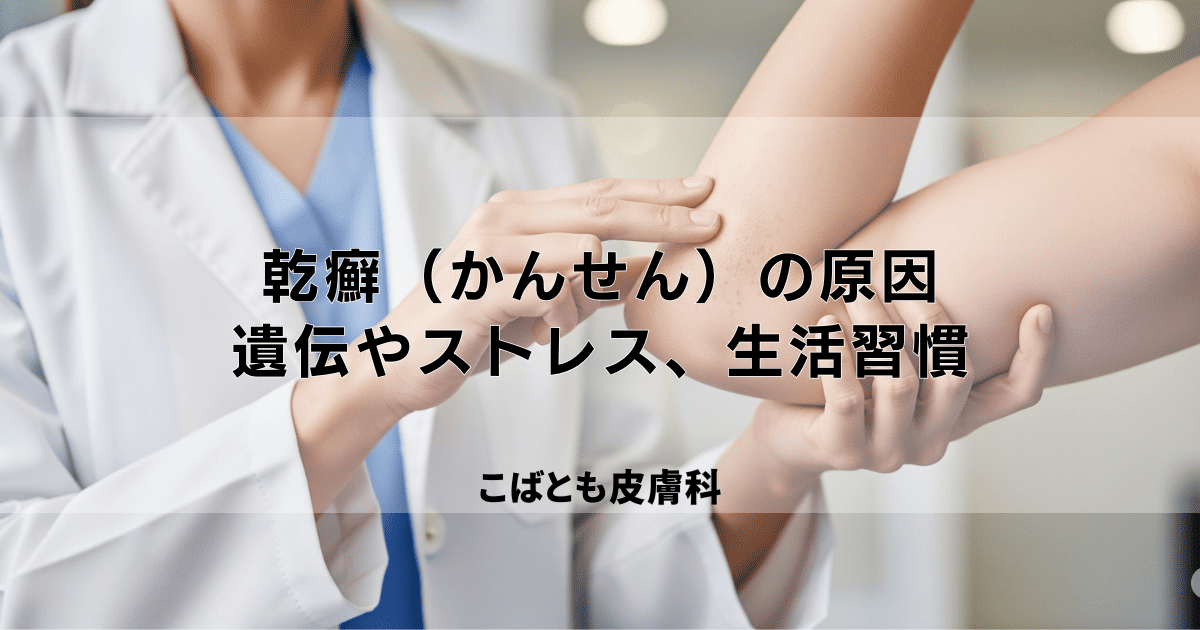皮膚に赤い発疹が現れ、その上に銀白色のフケのようなものが付着し、ポロポロと剥がれ落ちる乾癬。単なる肌荒れや湿疹とは異なり、原因が複雑で根気強い付き合い方が求められる皮膚の疾患です。
なぜ自分の皮膚にこのような症状が現れるのか、遺伝や日々のストレスが関係しているのではないかと、多くの方が不安に感じています。
この記事では、乾癬がなぜ発症するのか、原因として考えられる遺伝的要因、免疫システムの働き、ストレスや食生活、喫煙といった生活習慣との深い関わりについて、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
乾癬とはどのような病気か?
乾癬という名前を聞いたことがあっても、どのような病気なのか、正確に理解している方は少ないかもしれません。まずは、乾癬の基本的な特徴や症状について知り、理解を深めていきましょう。
単なる皮膚の病気ではない乾癬
乾癬は、皮膚の症状が目立つため、単に皮膚だけの病気だと思われがちです。しかし、その本質は、体の内部にある免疫システムの異常が関係している全身性の炎症性疾患と考えられています。
免疫システムが、誤って自身の正常な皮膚細胞を攻撃してしまうことで、皮膚のターンオーバーが異常に速まり、特徴的な症状が現れます。
見た目の問題だけでなく、関節の痛みや腫れを伴う乾癬性関節炎を合併することもあり、全身の状態に目を向けることが大事です。決して他人にうつる病気ではありませんが、見た目から誤解され、精神的な苦痛を感じる方も少なくありません。
典型的な症状と特徴
乾癬の最も代表的な症状は、皮膚に現れる赤い発疹、いわゆる紅斑(こうはん)で、周囲の健康な皮膚との境界がはっきりしているのが特徴です。
そして、その表面は銀白色の鱗屑(りんせつ)と呼ばれる、細かいフケのようなもので覆われていて、無理に剥がそうとすると点状に出血することがあります。
かゆみを伴うことも多く程度は個人差がありますが、強いかゆみによって日常生活に支障をきたすケースも見られます。症状は、良くなったり悪くなったりを繰り返す、慢性的な経過をたどることが一般的です。
乾癬の主な症状
- 境界明瞭な紅斑
- 銀白色の鱗屑
- 皮膚の肥厚
- かゆみ
- 爪の変形
乾癬が発症しやすい体の部位
乾癬の症状は、体のどこにでも現れる可能性がありますが、特に刺激を受けやすい部位に好発する傾向があります。
頭皮、肘、膝、お尻、腰回りなどは、衣服による摩擦や、日常生活での圧迫などがかかりやすいため、症状が出やすい代表的な場所です。頭皮に発症した場合は、フケと間違われることもあります。
また、爪に症状が現れることもあり、爪が厚くなったり、変形したり、小さな凹みが見られたりします。症状の現れる範囲や部位は人それぞれで、体のわずかな部分にだけ見られる軽症の方から、広範囲に広がる重症の方まで様々です。
症状が出やすい部位とその特徴
| 好発部位 | 特徴 | 日常生活での注意点 |
|---|---|---|
| 頭皮 | フケのような鱗屑が目立つ。かゆみを伴いやすい。 | 爪を立てて洗髪しない。刺激の少ないシャンプーを選ぶ。 |
| 肘・膝 | 衣服との摩擦や圧迫で厚くなりやすい。 | 机に肘をつかない。膝を締め付ける衣類を避ける。 |
| 腰・お尻 | 座っている時の圧迫や下着の摩擦で悪化しやすい。 | 柔らかいクッションを使う。通気性の良い下着を選ぶ。 |
乾癬の種類とそれぞれの違い
乾癬にはいくつかの種類(病型)があり、最も一般的なのが尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)です。これは乾癬患者さんの約9割を占めるといわれ、これまで説明してきた典型的な皮膚症状が現れます。
その他にも、水滴のような小さな発疹が全身に広がる滴状乾癬(てきじょうかんせん)、皮膚の深い部分に膿がたまる膿疱性乾癬(のうほうせいかんせん)、皮膚の広い範囲が真っ赤になる乾癬性紅皮症(かんせんせいこうひしょう)などがあります。
また、関節に炎症が起こる乾癬性関節炎も、乾癬の一種です。どの種類の乾癬かによって治療方針が異なる場合があるため、専門医による正確な診断が重要です。
乾癬の主な原因と考えられる要因
乾癬がなぜ発症するのか、そのはっきりとした原因はまだ完全には解明されていませんが、近年の研究により、いくつかの要因が複雑に絡み合って発症に至ると考えられています。
ここでは、現在、乾癬の主な原因として考えられている3つの大きな柱について見ていきましょう。
免疫システムの異常な働き
体を細菌やウイルスなどの外敵から守ってくれる免疫システムに、何らかの異常が生じ、自身の体を攻撃してしまうのが自己免疫疾患です。乾癬も、免疫システムの異常が深く関わっていると考えられています。
免疫細胞から放出される特定の情報伝達物質(サイトカイン)が過剰に作られることで、皮膚の細胞に炎症を起こし、異常な速さでの増殖を促してしまいます。
通常、皮膚の細胞は約4週間のサイクルで生まれ変わりますが、乾癬の皮膚ではこのサイクルがわずか数日間に短縮されてしまい、未熟な皮膚細胞が積み重なり、厚い鱗屑となって剥がれ落ちていきます。
遺伝的な素因の影響
乾癬は、遺伝的な要因が発症に関係していることが知られています。これは、血縁者に乾癬の方がいると、いない場合に比べて発症しやすい傾向があるからです。ただし、誤解してはいけないのは、乾癬が必ず遺伝する病気ではないという点です。
あくまで、乾癬になりやすい体質、つまり遺伝的な素因が受け継がれる可能性があるということで、特定の遺伝子を持っているからといって、誰もが乾癬を発症するわけではありません。
環境要因と遺伝的素因が組み合わさることで、発症のスイッチが入ると考えられています。
環境要因が引き金になることも
遺伝的な素因を持っているだけでは、乾癬は発症しません。そこに、さまざまな外的・内的な環境要因が加わることで、発症の引き金が引かれると考えられています。要因は、人によって異なり、また複数重なることもあります。
日常生活の中に潜む、乾癬発症のきっかけとなりうる要因を理解しておくことは、症状の管理において非常に大切です。
乾癬の悪化に関わる環境要因
| 要因の分類 | 具体的な例 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| 身体的要因 | 怪我、手術、日焼け、皮膚の摩擦 | 皮膚への物理的な刺激が炎症を誘発することがある。 |
| 精神的要因 | ストレス、不規則な生活、睡眠不足 | 心身のバランスの乱れが免疫系に影響を与える。 |
| 感染症 | 扁桃炎などの細菌・ウイルス感染 | 感染症に対する免疫反応が、乾癬を誘発・悪化させることがある。 |
遺伝は乾癬の発症に関係するのか
家族に乾癬の人がいると、自分もいつか発症するのではないかと心配になるかもしれません。遺伝と乾癬の関係は、多くの患者さんが気にする点です。
ここでは、遺伝がどの程度発症に関与するのか、そして遺伝だけが原因ではないことについて、さらに詳しく掘り下げていきます。
家族内での発症率
さまざまな調査から、乾癬患者さんの家族や親族には、同じく乾癬を発症している人が多いことが報告されています。欧米のデータでは、患者さんの約3分の1に家族内発症が見られるとされています。
日本での調査でも、家族に乾癬患者さんがいる場合の発症率は、いない場合と比較して高くなる傾向が示されています。
片方の親が乾癬の場合、子供が発症する確率は数パーセント程度、両親ともに乾癬の場合はさらにその確率が上がると考えられています。
しかし、この数字を見ても分かるように、確率が100%になることはなく、遺伝的素因を持っていても発症しない人の方が圧倒的に多いのです。
乾癬に関連する遺伝子
近年のゲノム研究の進歩により、乾癬の発症しやすさに関連する遺伝子が複数見つかっています。
遺伝子は、主に免疫システムの働きを調節したり、皮膚のバリア機能に関わったりするものです。特定の遺伝子(感受性遺伝子と呼ばれます)を持っていると、持っていない人に比べて乾癬を発症するリスクが少し高まります。
しかし、そのような遺伝子は一つではなく、多数の遺伝子が複雑に関与していると考えられています。
また、遺伝子は乾癬患者さんだけに特有のものではなく、健康な人でも持っていることがあるため、遺伝子検査だけで将来の発症を予測することは現在のところ困難です。
遺伝だけでは決まらない発症
ここで強調したいのは、乾癬は遺伝的素因と環境要因の両方がそろって初めて発症する多因子疾患であるという点です。
一卵性双生児(遺伝情報が全く同じ)の研究では、片方が乾癬の場合、もう片方も発症する確率は100%ではなく、70%程度という報告があります。
このことは、遺伝情報が同じでも発症しないケースがあることを示しており、遺伝以外の要因、つまり生活習慣やストレス、感染症といった環境要因がいかに重要であるかを物語っています。
遺伝的な素因は変えることができませんが、環境要因は自分自身の工夫や努力でコントロールできる部分があります。
ストレスが乾癬を悪化させる理由
仕事や人間関係など、現代社会でストレスを完全に避けることは難しいものです。多くの乾癬患者さんが、強いストレスを感じた後に症状が悪化したという経験をしています。
心と皮膚の密接なつながり
心と体は密接につながっており、特に皮膚は心の状態を映し出す鏡ともいわれます。緊張すると手に汗をかいたり、恥ずかしいと顔が赤くなったりする経験は誰にでもあるでしょう。
これは、自律神経系やホルモンなどを介して、脳が受け取った情報が皮膚に伝わるためです。
ストレスを感じると、脳からはさまざまな神経伝達物質やホルモンが分泌され、免疫システムや皮膚の細胞に直接的、あるいは間接的に作用し、乾癬の炎症を悪化させる一因となります。
また、乾癬の症状自体が新たなストレスとなり、さらに症状を悪化させるという悪循環に陥ってしまうことも少なくありません。
ストレスが引き起こす身体反応の例
| 反応の種類 | 具体的な変化 | 乾癬への影響 |
|---|---|---|
| 自律神経系の反応 | 交感神経が優位になる | 血管の収縮、かゆみを増強させる物質の放出 |
| 内分泌系の反応 | コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌 | 長期的には免疫バランスを乱し、炎症を促進する |
| 免疫系の反応 | 炎症性サイトカインの産生増加 | 皮膚の炎症を直接的に悪化させる |
ストレスによる免疫系への影響
ストレスは、乾癬の根本原因である免疫システムの異常に直接的な影響を与えます。人がストレスを感じると、体は危機的な状況に対応しようとして、特定の免疫細胞を活性化させたり、炎症を起こすサイトカインの産生を促したりします。
乾癬の素因を持っている人の場合、この反応が過剰に起こりやすく、皮膚の炎症が急激に悪化するきっかけとなります。
また、慢性的なストレスは、免疫全体のバランスを崩し、体を守るための正常な働きを低下させる一方で、乾癬のような自己免疫的な反応を助長してしまう可能性があります。
ストレスとどう向き合うか
ストレスをゼロにすることは不可能ですが、その影響を最小限に抑えるために、自分なりの対処法を見つけることが大切です。まずは、何が自分にとってストレスになっているのかを把握することから始めてください。
その上で、リラックスできる時間を作ることが重要で、趣味に没頭する、軽い運動をする、友人と話す、自然の中で過ごすなど、自分に合った方法で心と体を休ませてあげましょう。
十分な睡眠をとることも、ストレスへの抵抗力を高める上で欠かせません。
ストレス対処法の例
- 深呼吸や瞑想
- ヨガやストレッチ
- 音楽鑑賞
- 入浴
- アロマテラピー
生活習慣と乾癬の深い関わり
日々の何気ない生活習慣が、乾癬の症状に良くも悪くも影響を与えることがあります。食事や運動、睡眠といった基本的な生活リズムから、喫煙や飲酒などの嗜好品まで、さまざまな要素が乾癬と関連しています。
食生活が皮膚に与える影響
乾癬の症状を直接的に改善する特定の食品というものは、現在のところ科学的に証明されていませんが、食生活の乱れが体全体の炎症を起こし、乾癬を悪化させる可能性は指摘されています。
特に、高脂肪・高カロリーな食事は、肥満につながりやすく、炎症を促進する物質を体内で増やす原因となります。一方で、バランスの取れた食事は、免疫機能を正常に保ち、健康な皮膚を作るために必要です。
野菜や果物、青魚などに含まれる抗酸化物質や良質な脂質を積極的に摂り、加工食品や糖分の多い食品は控えめにすることを心がけましょう。
食事で意識したい栄養素と食品
| 栄養素 | 期待される働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| オメガ3系脂肪酸 | 炎症を抑える働き | サバ、イワシ、サンマなどの青魚、亜麻仁油 |
| ビタミン類 | 皮膚の健康維持、抗酸化作用 | 緑黄色野菜、果物、ナッツ類 |
| 食物繊維 | 腸内環境を整える | 野菜、きのこ、海藻、玄米 |
肥満と乾癬の悪循環
肥満は、乾癬の発症リスクを高め、症状を悪化させる重要な要因の一つであることが多くの研究で示されています。
脂肪細胞、特に内臓脂肪からは、炎症を引き起こすサイトカインが分泌されるため、肥満の状態は体全体が慢性的な炎症状態にあり、乾癬の病態をさらに悪化させるのです。
また、体重が増加すると、膝などの関節への負担が大きくなり、乾癬性関節炎のリスクも高まります。
さらに、肥満の方は皮膚がこすれやすく、摩擦による症状の悪化も起こりやすくなるので、適正体重を維持することは、乾癬のコントロールにおいて非常に重要な目標です。
喫煙と飲酒のリスク
喫煙と過度な飲酒は、乾癬にとって百害あって一利なしです。タバコに含まれる多くの化学物質は、血管を収縮させて皮膚の血流を悪化させるだけでなく、免疫システムに異常をきたし、体内の炎症を促進します。
喫煙者は非喫煙者に比べて乾癬の発症リスクが高く、また治療効果も出にくいことが報告されています。アルコールも同様に、体内の炎症を悪化させる可能性があります。
膿疱性乾癬などの特定の病型では、飲酒が症状の引き金になることも知られています。症状の改善を目指すのであれば、禁煙し、飲酒は適量を守るか、できるだけ控えることが必要です。
喫煙・飲酒がもたらすリスク
- 免疫系の機能異常
- 全身性の炎症促進
- 皮膚の血行不良
- 治療効果の減弱
- 特定の病型の誘発
睡眠不足がもたらす問題
質の良い睡眠は、心身の健康を維持するために不可欠です。
睡眠中には、体の修復や免疫システムの調整が行われます。睡眠不足が続くと、自律神経やホルモンのバランスが乱れ、免疫機能が低下したり、逆に過剰な炎症反応を起こしたりします。
また、夜間のかゆみで眠りが妨げられ、それがさらなる睡眠不足とストレスにつながるという悪循環に陥ることもあります。毎日決まった時間に就寝・起床するなど、規則正しい睡眠習慣を確立し、心と体を十分に休ませることが大切です。
乾癬と間違えやすい他の皮膚疾患
皮膚に赤い発疹やかゆみが出ると、誰もがまず湿疹や皮膚炎を疑うかもしれません。乾癬は、他のいくつかの皮膚疾患と症状が似ているため、自己判断は禁物です。
湿疹や皮膚炎との見分け方
湿疹や皮膚炎は、皮膚の病気の中で最も一般的なものの一つで、乾癬との大きな違いは、発疹の境界です。
乾癬の紅斑は、周囲の正常な皮膚との境目が比較的はっきりしているのに対し、湿疹・皮膚炎では境界が不明瞭で、じくじくとした浸出液を伴うことも多いです。また、乾癬に特徴的な厚い銀白色の鱗屑は、通常の湿疹ではあまり見られません。
ただし、慢性化した湿疹では皮膚が厚くなることもあり、見た目だけでの判断が難しい場合もあります。
乾癬と湿疹・皮膚炎の主な違い
| 項目 | 乾癬 | 湿疹・皮膚炎 |
|---|---|---|
| 発疹の境界 | 明瞭 | 不明瞭 |
| 鱗屑(フケ) | 厚く、銀白色 | 細かい、または見られない |
| 好発部位 | 肘、膝、頭皮など刺激を受けやすい部位 | 原因により様々 |
脂漏性皮膚炎との違い
頭皮や顔、胸、脇の下など、皮脂の分泌が盛んな部位に症状が出る場合、脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)との鑑別が必要になります。
脂漏性皮膚炎も、赤みとフケのような鱗屑を伴いますが、乾癬の鱗屑が銀白色で乾燥しているのに対し、脂漏性皮膚炎の鱗屑は黄色っぽく、やや湿り気や脂っぽさがあるのが特徴です。
しかし、両者の症状が合併しているケース(脂漏性乾癬)もあり、専門医でも判断に迷うことがあります。
爪の症状から考えるべきこと
爪の変形は、乾癬の患者さんの約半数に見られる症状です。爪に小さな凹み(点状陥凹)ができたり、爪が厚く濁ったり、先端が剥がれたりし、症状は、爪白癬(爪水虫)と非常によく似ています。
爪白癬はカビの一種である白癬菌の感染が原因であり、抗真菌薬による治療が必要です。
乾癬の爪症状と爪白癬とでは治療法が全く異なるため、顕微鏡検査などで菌の有無を確認し、正確に診断することが極めて重要で、自己判断で市販の水虫薬を使用すると、かえって症状を悪化させることもあります。
乾癬の症状を悪化させないための注意点
乾癬と診断されたら、専門医による治療を受けることが基本です。それに加えて、日常生活の中でいくつかの点に気をつけることで、症状の悪化を防ぎ、良い状態を長く維持することが期待できます。
皮膚への刺激を避ける工夫
乾癬の皮膚は非常にデリケートで、わずかな物理的刺激でも新たな発疹が出たり、既存の症状が悪化したりすることがあり、これをケブネル現象と呼びます。
衣類による摩擦、きついベルトや下着による締め付け、アクセサリーによる刺激、かきむしりなどは、症状を悪化させる代表的な要因です。
肌に触れる衣類は、木綿などの柔らかく通気性の良い素材を選び、ゆったりとしたデザインのものを着用しましょう。入浴時には、ナイロンタオルなどでゴシゴシこすらず、石鹸をよく泡立てて手で優しく洗うことが大切です。
日常生活における皮膚への刺激対策
| 場面 | 注意点 | 具体的な工夫 |
|---|---|---|
| 衣類 | 摩擦と締め付けを避ける | 綿素材、ゆったりしたデザイン、タグの除去 |
| 入浴 | こすりすぎない | 手で優しく洗う、熱いお湯を避ける、保湿成分のある入浴剤 |
| かゆみ | かきむしらない | 冷やす、保湿する、処方されたかゆみ止めを使用する |
感染症の予防と対策
風邪や扁桃炎、虫歯などの感染症は、免疫システムを活性化させ、乾癬の症状を急激に悪化させる引き金になることがあります。特に、溶連菌感染症の後に滴状乾癬が発症することはよく知られています。
日頃から、うがいや手洗いを習慣づけ、人混みを避けるなど、感染症にかからないための対策を心がけることが重要です。また、体の抵抗力を落とさないために、十分な休養と栄養バランスの取れた食事も大事です。
もし、のどの痛みや発熱などの症状が現れた場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
感染症予防の基本
- 手洗い・うがいの徹底
- 十分な睡眠と休養
- バランスの取れた食事
- 人混みを避ける
- 予防接種の検討
薬の使用に関する注意
乾癬の治療薬はもちろんですが、他の病気で服用している薬が、乾癬の症状に影響を与えることがあります。一部の降圧薬(血圧の薬)や精神疾患の治療薬、痛み止めなどが、乾癬を悪化させる可能性があると報告されています。
ただし、自己判断で薬を中止するのは大変危険です。他の医療機関で薬を処方してもらう際には、必ず乾癬であることと、現在使用している薬を医師に伝えてください。
お薬手帳を活用し、皮膚科医と他の診療科の医師との間で情報を共有することが、安全な治療につながります。
乾癬の原因に関するよくある質問
最後に、患者さんから特によく寄せられる質問と、回答をまとめました。
- 乾癬は他の人にうつりますか?
-
乾癬は、細菌やウイルスによる感染症ではなく、体内の免疫システムの異常によって起こる病気です。
そのため、皮膚の症状に直接触れたり、温泉やプールに一緒に入ったり、タオルを共用したりしても、感染する心配は全くありません。
この点は非常に重要なことで、患者さんご自身だけでなく、周りの方々にも正しく理解していただくことが、患者さんの精神的な負担を軽減することにつながります。
- 乾癬は完治しますか?
-
現在の医療では、残念ながら乾癬を完全に治し、再発しない状態にすることは難しいのが現状です。
乾癬は、良くなったり悪くなったりを繰り返す慢性的な病気であり、高血圧や糖尿病のように、長く付き合っていく必要があります。
しかし、近年、治療法は目覚ましく進歩しており、適切な治療を継続することで、症状がほとんどない、あるいは全くない状態を長期間維持することが可能になっています。
治療の目標は、完治ではなく、症状を上手にコントロールし、健やかな日常生活を送れるようにすることです。
- 食事で気をつけることは何ですか?
-
乾癬に直接効く特別な食べ物や、絶対に食べてはいけない食べ物というものはありません。基本は、栄養バランスの取れた食事を規則正しく摂ることです。
ただし、一般的に炎症を促進するといわれる高脂肪食や、香辛料などの刺激物は、症状を悪化させる可能性があるため、摂りすぎには注意が必要です。
また、唐辛子に含まれるカプサイシンや、一部の健康食品が症状を悪化させたという報告もあります。何か特定のものを食べて症状が悪化するようであれば、それを避けるようにしましょう。
特定の食品を極端に制限するのではなく、全体的な食生活のバランスを見直すことが大切です。
以上
参考文献
Ogawa K, Okada Y. The current landscape of psoriasis genetics in 2020. Journal of dermatological science. 2020 Jul 1;99(1):2-8.
Kamiya K, Kishimoto M, Sugai J, Komine M, Ohtsuki M. Risk factors for the development of psoriasis. International journal of molecular sciences. 2019 Jan;20(18):4347.
Oka A, Mabuchi T, Ozawa A, Inoko H. Current understanding of human genetics and genetic analysis of psoriasis. The Journal of dermatology. 2012 Mar;39(3):231-41.
Goto H, Nakatani E, Yagi H, Moriki M, Sano Y, Miyachi Y. Late-onset development of psoriasis in Japan: a population-based cohort study. JAAD international. 2021 Mar 1;2:51-61.
Sawada Y, Saito-Sasaki N, Mashima E, Nakamura M. Daily lifestyle and inflammatory skin diseases. International journal of molecular sciences. 2021 May 14;22(10):5204.
Bayaraa B, Imafuku S. Relationship between environmental factors, age of onset and familial history in Japanese patients with psoriasis. The Journal of Dermatology. 2018 Jun;45(6):715-8.
Kamiya K, Oiso N, Kawada A, Ohtsuki M. Epidemiological survey of the psoriasis patients in the Japanese Society for Psoriasis Research from 2013 to 2018. The Journal of Dermatology. 2021 Jun;48(6):864-75.
Yamashita H, Morita T, Ito M, Okazaki S, Koto M, Ichikawa Y, Takayama R, Hoashi T, Saeki H, Kanda N. Dietary habits in Japanese patients with psoriasis and psoriatic arthritis: Low intake of meat in psoriasis and high intake of vitamin A in psoriatic arthritis. The Journal of dermatology. 2019 Sep;46(9):759-69.
Xie W, Huang H, Deng X, Gao D, Zhang Z. Modifiable lifestyle and environmental factors associated with onset of psoriatic arthritis in patients with psoriasis: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Journal of the American Academy of Dermatology. 2021 Mar 1;84(3):701-11.
Chandran V, Raychaudhuri SP. Geoepidemiology and environmental factors of psoriasis and psoriatic arthritis. Journal of autoimmunity. 2010 May 1;34(3):J314-21.