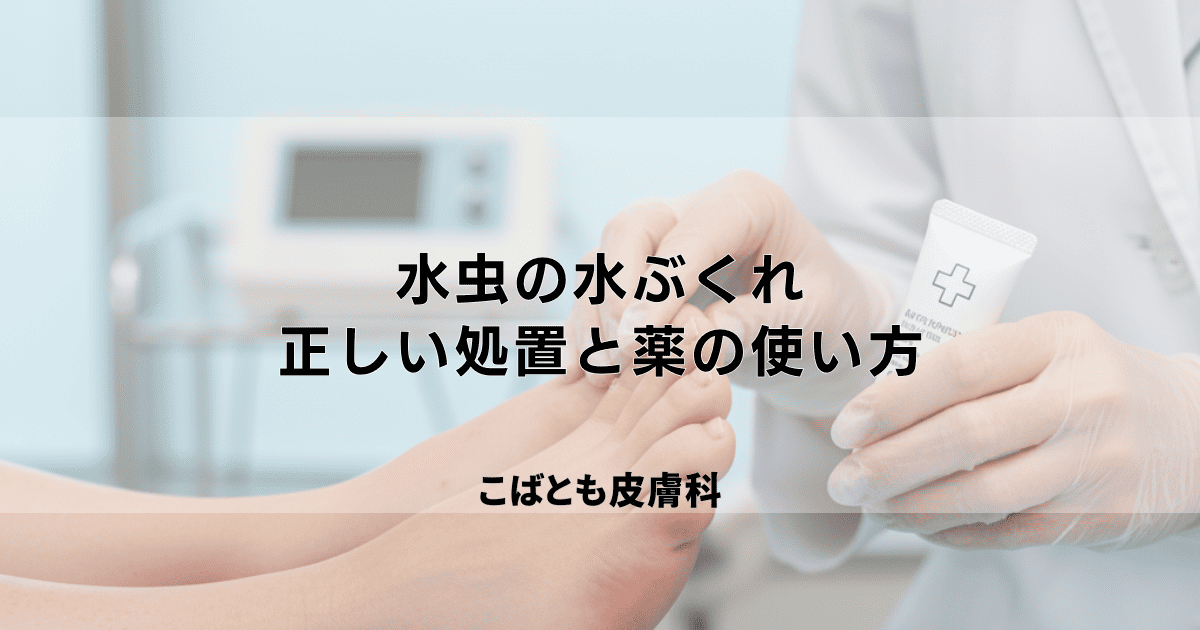足の指の間や土踏まずにできた、かゆみを伴う小さな水ぶくれ。水虫はジメジメとした季節になると症状が悪化し、強いかゆみで思わず掻き壊したり、水ぶくれを潰してしまいたくなったりする方も多いのではないでしょうか。
しかし、水ぶくれを、自己判断で潰してしまうのは大変危険な行為です。間違った処置は症状を悪化させるだけでなく、感染を広げてしまう原因にもなりかねません。
この記事では、水虫による水ぶくれがなぜできるのか、潰すことのリスク、かゆい水疱ができてしまった際の正しい処置と治療薬の使い方について、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
まず知っておきたい水虫と水ぶくれの基本
水虫の症状として多くの人が思い浮かべるのが、強いかゆみや皮むけで、中でも気になるのが、水ぶくれではないでしょうか。この水ぶくれの正体と、水虫がどのようにして発生するのか、基本的な知識を深めていきましょう。
水虫はなぜできるのか
水虫の正体は、白癬菌(はくせんきん)というカビ(真菌)の一種です。
白癬菌は、皮膚の最も外側にある角質層を栄養源にして増殖し、足に感染し、寄生することで水虫、足白癬(あしはくせん)と呼ばれる状態になります。
白癬菌は、高温多湿な環境を非常に好む性質を持っているため、靴や靴下で長時間蒸れた状態になりやすい足は、白癬菌にとって格好の住処となるのです。
多くの人が利用する公衆浴場やスポーツジムの足ふきマット、スリッパなどを介して、菌が付着した皮膚のかけらが他人の足に付着することで感染が広がります。
ただし、菌が付着しただけですぐに感染するわけではなく、付着した菌が角質層に侵入し、増殖を始めるまでには一定の時間が必要です。通常、24時間以内に足をきちんと洗浄すれば、感染のリスクは大幅に減少すると考えられています。
水ぶくれができる水虫の種類
水虫は、症状の現れ方によっていくつかのタイプに分類されます。水ぶくれ、つまり小さな水疱(すいほう)が特徴的なのは、小水疱型(しょうすいほうがた)水虫です。
このタイプは、主に足の裏、特に土踏まずや足の側面に発生しやすく、最初は小さな水疱がポツポツとでき、次第に数が増えたり、複数の水疱がくっついて大きくなったりします。
強いかゆみを伴うことが多く、水疱が破れると液体が出て、その後乾燥して皮がむけていき、液体自体に大量の菌がいるわけではありませんが、破れた箇所から細菌が侵入する危険性があります。
主な水虫のタイプ
| タイプ名 | 主な症状 | 発生しやすい場所 |
|---|---|---|
| 趾間型(しかんがた) | 皮がむける、白くふやける、じゅくじゅくする、かゆみ | 足の指の間(特に薬指と小指の間) |
| 小水疱型(しょうすいほうがた) | 小さな水ぶくれ、強いかゆみ、赤み | 土踏まず、足の側面 |
| 角質増殖型(かくしつぞうしょくがた) | 足の裏全体の皮膚が厚く硬くなる、ひび割れ、かゆみは少ない | かかと、足の裏全体 |
かゆみや痛みの原因は白癬菌
水虫による強いかゆみや、時に感じる痛みは、白癬菌そのものが直接引き起こしているわけではなく、白癬菌が角質層で増殖する際に排出する物質に対して、体がアレルギー反応を起こすことによって生じます。
体を守るための免疫反応が、かゆみや炎症といった不快な症状として現れるのです。小水疱型水虫では、アレルギー反応が強く出やすいため、激しいかゆみを伴うことが多いとされています。
掻き壊してしまうと、皮膚のバリア機能が破壊され、そこから細菌が侵入して二次感染を起こし、痛みや腫れ、膿みといったさらに深刻な症状につながることもあり、かゆくても掻かない、潰さないという意識が大切です。
なぜ足にできやすいのか
白癬菌は体のどこにでも感染する可能性がありますが、圧倒的に足に多いのはなぜでしょうか。それは、足が白癬菌の増殖にとって理想的な条件を備えているからです。
革靴やブーツ、ストッキングなどは通気性が悪く、足は一日中汗で蒸れた状態になり、高温多湿な環境が、白癬菌の増殖を後押しします。また、足の裏の角質層は体の他の部分に比べて厚く、白癬菌にとって豊富な栄養源となります。
さらに、歩行による刺激でできた小さな傷から菌が侵入しやすいという側面もあり、いろいろな条件が重なることで、足は水虫の温床となりやすいのです。
絶対にダメ!水ぶくれを潰すことの危険性
かゆくてたまらない水虫の水ぶくれを、針で刺したり、爪で潰したりすれば、一時的にかゆみが和らぐように感じるかもしれません。しかし、水ぶくれを自分で潰すことには、さまざまなリスクが伴います。
細菌感染のリスクが高まる
水ぶくれを潰すと、皮膚の表面に傷ができます。皮膚は、外部の刺激や病原体から体を守るバリアの役割を果たしているので、水ぶくれを潰すという行為は、自らそのバリアを破壊するのと同じことです。
できた傷口から、黄色ブドウ球菌などの細菌が侵入し、二次的な細菌感染症(二次感染)を起こす可能性があり、二次感染を起こすと、患部が赤く腫れあがり、熱を持ったり、痛みが強くなったりします。
ひどい場合には、膿が出てきたり、リンパ管に沿って炎症が広がる丹毒(たんどく)や、皮下組織の深い部分で炎症が起こる蜂窩織炎(ほうかしきえん)といった重篤な状態に発展することもあります。
水ぶくれを潰した場合に起こりうる二次感染
| 感染症名 | 主な症状 | 注意点 |
|---|---|---|
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 水ぶくれ、膿、かさぶたが広がる | 非常に感染力が強く、体の他の部位にも広がりやすい |
| 丹毒・蜂窩織炎 | 皮膚の赤み、腫れ、熱感、強い痛み、発熱 | 急速に悪化することがあり、入院治療が必要な場合もある |
水虫が他の部位に広がる可能性
水ぶくれを潰した際に出る液体に直接触れたり、掻き壊した手で体の他の部分を触ったりすることで、白癬菌が他の部位に感染する可能性があります。
手で患部を触った後に頭を掻くと、頭部に白癬菌が感染して「しらくも(頭部白癬)」になることがあり、同様に、股間に感染すれば「いんきんたむし(股部白癬)」、体幹部に感染すれば「ぜにたむし(体部白癬)」と呼ばれます。
また、爪に菌が侵入すると、爪が白く濁ったり、厚く変形したりする「爪水虫(爪白癬)」を引き起こします。爪水虫は治療が難しく、飲み薬が必要になることが多い厄介な病気です。
症状の悪化と治癒の遅れ
水ぶくれを潰して皮膚にダメージを与えると、炎症がさらにひどくなり、かゆみや赤みが強まることがあり、また、傷の修復に体のエネルギーが使われるため、本来の水虫自体の治癒が遅れてしまいます。
皮膚科では、水虫の診断のために皮膚の一部を採取して顕微鏡で菌の有無を確認する検査(鏡検)を行いますが、自己判断で水ぶくれを潰したり、市販薬を塗ったりした後では、正確な診断が難しくなることもあります。
治療を開始するためにも、患部はなるべくそのままの状態で専門医の診察を受けることが重要です。
水虫の水ぶくれができてしまった時の応急処置
強いかゆみを伴う水ぶくれができてしまった場合、皮膚科を受診するまでの間、どのように対処すればよいのでしょうか。症状を悪化させず、かゆみを少しでも和らげるための応急処置について解説します。
清潔に保つことが第一歩
水虫のケアで最も基本的なことは、患部を清潔に保つことです。白癬菌の増殖を抑え、二次感染を防ぐためにも、毎日の入浴やシャワーは欠かさず行いましょう。
洗う際は、薬用石鹸や殺菌成分の入ったボディソープをよく泡立て、手で優しく洗うのがポイントです。ナイロンタオルなどでゴシゴシこすると、皮膚が傷つき、かえって症状を悪化させてしまいます。
指の間まで丁寧に洗い、洗浄成分が残らないようにしっかりとすすぎ、洗い終わった後は、清潔なタオルで水分を優しく押さえるように拭き取ります。特に指の間は水分が残りやすいので、念入りに乾燥させることが大切です。
- 低刺激の石鹸をよく泡立てる
- 指の間まで丁寧に洗う
- ゴシゴシこすらない
- しっかりとすすぐ
- 優しく拭いて完全に乾燥させる
冷やすことでかゆみを和らげる
かゆみが我慢できないときは、患部を冷やすのが効果的で、冷たい刺激によって、かゆみを感じる神経の働きが一時的に鈍くなるため、症状が和らぎます。清潔なタオルやガーゼで保冷剤を包み、患部に優しく当てましょう。
直接保冷剤を当てると凍傷になる恐れがあるので注意が必要です。時間は5分から10分程度を目安にし、長時間冷やしすぎないようにしてください。入浴などで体が温まると血行が良くなり、かゆみが増すことがあります。
かゆみが強いときは、熱いシャワーを浴びたり、長風呂をしたりするのは避けた方が良いでしょう。かゆみ止め成分の入った市販薬もありますが、まずは冷やすというシンプルな方法を試してみてください。
かゆみ対策のポイント
| 対策 | 方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 冷やす | 保冷剤などをタオルで包み、患部に当てる | 直接当てない、長時間冷やしすぎない |
| 温めない | 長時間の入浴や熱いシャワーを避ける | 血行が良くなるとかゆみが増すことがある |
| 刺激を避ける | アルコールや香辛料の多い食事を控える | 体が温まり、かゆみを誘発することがある |
市販薬を使う前の注意点
ドラッグストアでは、さまざまな種類の水虫薬が販売されていますが、自己判断で市販薬を使用する前には、いくつか注意すべき点があります。まず、その症状が本当に水虫であるかどうかの確証はありません。
水虫とよく似た症状の皮膚疾患は他にもあり、もし違う病気だった場合、水虫薬を使っても効果がないばかりか、成分によるかぶれなどで症状を悪化させる可能性もあります。
また、水虫であったとしても、症状のタイプや進行度によって適した薬が異なります。水ぶくれがじゅくじゅくしている状態では、刺激の強い薬は避けるべきです。
やむを得ず破れてしまった場合の対処法
歩いているうちに擦れたり、寝ている間に無意識に掻いてしまい、意図せず水ぶくれが破れてしまうこともあります。もし破れてしまったら、まずは患部を清潔な水で優しく洗い流し、余分な水分を清潔なガーゼでそっと拭き取ります。
消毒液は刺激が強く、皮膚の正常な細胞まで傷つけてしまうことがあるため、基本的には不要です。その後、患部を保護するために通気性の良いガーゼを当て、テープで軽く固定します。
絆創膏などで密閉すると、内部が蒸れて菌が増殖しやすくなるため避けましょう。
皮膚科での水虫治療
市販薬で改善しない場合や、症状が広範囲に及ぶ場合、そして何よりも正確な診断と確実な治療を望む場合は、皮膚科への相談が最も良い方法です。ここでは、皮膚科を受診するメリットや治療の流れについて詳しく見ていきます。
専門医に相談するメリット
皮膚科を受診する最大のメリットは、症状が本当に水虫なのかを正確に診断してもらえる点で、専門医は、顕微鏡検査によって白癬菌の有無を直接確認するため、確実な診断が可能です。
検査により、水虫ではない他の病気である可能性もはっきりし、また、診断が確定すれば、症状やライフスタイルに合わせて最も効果的な治療薬を処方してもらえます。
市販薬には含まれていない強力な成分の薬や、爪水虫に有効な内服薬(飲み薬)も、医師の処方がなければ使用できません。治療中の経過観察や、生活習慣に関するアドバイスを受けられるのも、大きなメリットです。
皮膚科受診を特に推奨するケース
| 症状・状況 | 理由 |
|---|---|
| 初めて水虫が疑われる症状が出た | 正確な診断が必要なため |
| 市販薬を1〜2週間使っても改善しない | 薬が合っていないか、水虫ではない可能性があるため |
| かゆみや痛みが強い、患部が腫れている | 二次感染を起こしている可能性があるため |
| 爪の変色や変形がある | 爪水虫の可能性が高く、専門的な治療が必要なため |
診断の流れ
皮膚科での水虫診断は、通常、問診と視診、顕微鏡検査によって行われます。まず問診で、いつからどのような症状があるか、過去の治療歴、生活習慣などについて詳しく話を聞きます。
次に視診で、患部の状態を直接観察し、水虫の典型的な症状が出ているかを確認し、そして、診断を確定させるために顕微鏡検査を行います。
検査は、患部の皮膚(水疱の膜や鱗屑と呼ばれるカサカサした皮膚)をピンセットなどで少量採取し、水酸化カリウム(KOH)溶液で溶かして、顕微鏡で白癬菌がいるかどうかを探すものです。痛みはほとんどなく、数分で結果が分かります。
処方される主な治療薬
水虫の治療には、主に抗真菌薬が用いられ、軽症から中等症の足水虫であれば、外用薬(塗り薬)による治療が基本です。外用薬には、クリーム、軟膏、液体、スプレーなど、さまざまな剤形があります。
患部の状態によって使い分けられ、乾燥している部分には保湿効果のあるクリームや軟膏、じゅくじゅくしている部分には刺激の少ない軟膏が選択肢です。
外用薬だけでは効果が得られにくい角質増殖型の水虫や、爪水虫の場合には、内服薬(飲み薬)が処方されることがあります。
内服薬は体の中から菌に作用するため高い効果が期待できますが、副作用のリスクも考慮し、定期的な血液検査などを行いながら慎重に治療を進めます。
- クリーム剤
- 軟膏剤
- 液剤
- スプレー剤
- 内服薬
水虫治療薬の正しい使い方とポイント
皮膚科で処方された薬も、市販薬も、正しく使わなければ十分な効果は得られません。水虫をしっかりと治しきるために、薬の使い方に関する重要なポイントを理解しておきましょう。
薬を塗る範囲と量
水虫薬を塗る際、多くの人がやりがちな間違いが、かゆみや水ぶくれがある部分にしか塗らないことです。
白癬菌は、症状が出ていないように見える広範囲に潜んでいる可能性があるため、薬は症状のある部分だけでなく、その周囲も含めて広めに塗ることが大切になります。
足の指の間から足の裏全体、そしてかかとやアキレス腱の周り、足の側面まで、足全体に塗るのが理想的で、塗る量は、ティッシュペーパーが軽く付着するくらいが目安です。量が少なすぎると十分な効果が得られません。
人差し指の第一関節の長さ分(約0.5g)の量をチューブから出すと、片方の足裏全体を塗るのに適した量になります。
薬を塗る範囲の目安
| 塗るべき場所 | ポイント |
|---|---|
| 症状のある部分 | 中心的に、少し厚めに塗る |
| 症状のない周囲 | 最低でも指2〜3本分は広げて塗る |
| 足全体 | 特に指の間や足の裏は念入りに塗ることが再発予防につながる |
薬を塗るタイミング
薬を塗るのに最も適したタイミングは、入浴後です。入浴によって足の汚れや古い角質が洗い流され、皮膚が清潔で柔らかくなっているため、薬の成分が浸透しやすくなります。
入浴後は、タオルで水分をしっかりと拭き取り、皮膚が完全に乾いてから薬を塗りましょう。水分が残っていると、薬が薄まったり、効果が十分に発揮されなかったりします。
通常は1日1回の塗布で十分な効果が得られる薬がほとんどですが、症状によっては1日2回塗るように指示されることもあります。
治療期間の目安
水虫治療で最も重要なことの一つが、根気強く治療を続けることです。
多くの場合、薬を塗り始めて1〜2週間もすると、かゆみや水ぶくれといった自覚症状はかなり改善しますが、この時点で治ったと自己判断し、薬の使用をやめてしまう人が非常に多いのですが、これは再発の大きな原因です。
症状がなくなったように見えても、角質層の奥深くには白癬菌がまだ生き残っているので、菌を完全に死滅させるためには、症状が消えてからも最低1ヶ月以上は薬を塗り続ける必要があります。
皮膚のターンオーバー(新陳代謝)によって、菌に感染した古い角質がすべて新しい角質に入れ替わるまで、治療を続けることが大切です。
症状が改善しても油断は禁物
治療によって見た目がきれいになっても、完治を意味するわけではありません。白癬菌は非常にしぶとく、少しでも残っていると、再び増殖を始め、特に、梅雨時や夏場など、高温多湿になる季節は再発しやすい時期です。
医師から治療終了の指示があるまでは、自己判断で薬をやめないでください。治療の終わりは、医師が皮膚の状態を診察し、必要であれば再度顕微鏡検査を行って菌がいないことを確認した上で判断します。
水虫の再発を防ぐための生活習慣
水虫治療を成功させるには、薬物療法と並行して、白癬菌が増殖しにくい環境を作るための生活習慣の見直しがとても大事です。せっかく薬で菌を退治しても、菌が好む環境をそのままにしておくと、すぐに再発してしまいます。
足を清潔で乾燥した状態に保つ
水虫予防の基本は、足を常に清潔で乾燥した状態に保つことで、治療中の再発予防においても同様に重要です。毎日足を丁寧に洗い、乾燥させる習慣を徹底しましょう。
日中、仕事などで長時間靴を履きっぱなしの人は、足が蒸れやすいので、可能であれば、職場で通気性の良いサンダルなどに履き替えたり、休憩時間に靴を脱いで足を乾燥させたりする工夫も効果的です。
汗をかきやすい人は、替えの靴下を持ち歩き、こまめに履き替えるのも良い方法です。帰宅後すぐに足を洗う習慣をつけることも、菌の増殖時間を短くする上で役立ちます。
- 通気性の良い履物を選ぶ
- 同じ靴を毎日履かない
- 吸湿性の高い靴下を選ぶ
- こまめに靴下を履き替える
- 帰宅後すぐに足を洗う
靴や靴下の選び方とケア
日常的に履く靴や靴下も、水虫の再発に大きく関わっています。靴は、なるべく通気性の良い素材(天然皮革やメッシュ素材など)のものを選びましょう。合成皮革やゴム製の靴は内部が蒸れやすいので、長時間の使用は避けた方が賢明です。
また、同じ靴を毎日履き続けると、靴の中に湿気がこもり、菌の温床になってしまいます。複数の靴をローテーションで履き、履かない靴は風通しの良い場所でしっかりと乾燥させることが大切です。
靴の中に乾燥剤や抗菌スプレーを使用するのも良いでしょう。
靴下は、汗をよく吸い取る綿や麻、ウールなどの天然素材のものや、速乾性のある化学繊維のものがおすすめで、5本指ソックスは指の間の汗を吸収してくれるため、特に趾間型水虫の予防に効果的です。
靴のケア方法
| 方法 | 目的 | ポイント |
|---|---|---|
| ローテーション | 靴を完全に乾燥させる | 最低でも2〜3足を履き回す |
| 乾燥・換気 | 湿気を取り除き、菌の増殖を防ぐ | 風通しの良い場所で陰干しする |
| インソールの交換 | 清潔を保ち、湿気を吸収する | 定期的に洗うか、新しいものに交換する |
家族への感染を防ぐために
水虫は家族内で感染しやすい病気の一つです。家庭内に水虫の人がいる場合、床やバスマットなどに剥がれ落ちた皮膚(鱗屑)が付着し、そこに含まれる白癬菌が他の家族にうつってしまうことがあります。
家族への感染を防ぐためには、いくつかの点に注意が必要で、まず、足ふきマットやスリッパ、爪切りなどを共用しないようにします。バスマットはこまめに洗濯し、よく乾燥させましょう。
毎日掃除機をかけることも、床に落ちた鱗屑を取り除くのに有効です。水虫の治療を始めたら、そのことを家族にも伝え、協力して感染予防に努めることが、家庭内での感染拡大を防ぐ上で非常に重要になります。
水虫と間違えやすい他の皮膚疾患
足に水ぶくれやかゆみ、皮むけなどの症状が出た場合、多くの人はまず水虫を疑いますが、似たような症状を起こす皮膚疾患は他にもあります。自己判断で水虫薬を使い続けると、本来の病気が悪化してしまうこともあります。
汗疱(異汗性湿疹)
汗疱(かんぽう)は、手のひらや足の裏に、かゆみを伴う小さな水ぶくれがたくさんできる皮膚疾患です。特に、汗をかきやすい季節の変わり目などに発症しやすい傾向があります。
水虫の小水疱型と症状が非常によく似ているため、間違えられやすい病気の代表格で、汗疱の原因ははっきりとわかっていませんが、汗や金属アレルギー、ストレスなどが関与していると考えられています。
水虫との大きな違いは、汗疱はカビが原因ではないため、抗真菌薬は効果がなく、他人にうつることもありません。治療には、主にステロイド外用薬が用いられます。
水虫(小水疱型)と汗疱の比較
| 項目 | 水虫(小水疱型) | 汗疱(異汗性湿疹) |
|---|---|---|
| 原因 | 白癬菌(カビ) | 汗、アレルギー、ストレスなど |
| 感染の有無 | うつる | うつらない |
| 主な治療薬 | 抗真菌薬 | ステロイド外用薬 |
接触皮膚炎(かぶれ)
接触皮膚炎は、一般的に「かぶれ」として知られています。特定の物質が皮膚に触れることで、赤み、かゆみ、水ぶくれなどの炎症反応が起こる病気です。
原因となる物質は、植物(ウルシなど)、金属、化学物質、化粧品、薬など多岐にわたり、靴の素材や染料、靴下に使われているゴムなどが原因で足にかぶれが起こることもあります。
水虫薬の成分にかぶれてしまい、症状が悪化するケースも少なくありません。原因物質との接触を避けることが最も重要で、治療にはステロイド外用薬や抗ヒスタミン薬の内服などが用いられます。
掌蹠膿疱症
掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)は、手のひらや足の裏に、膿が入った小さな水ぶくれ(膿疱)がたくさんできる病気です。周期的に良くなったり悪くなったりを繰り返すのが特徴で、かゆみを伴うこともあります。
水虫と異なり、膿疱の中は無菌で、他人に感染することはありません。原因はまだ完全には解明されていませんが、喫煙や、虫歯や扁桃炎などの病巣感染が関与していると考えられています。
治療はステロイド外用薬やビタミンD3外用薬などが中心となりますが、難治性の場合もあります。
水虫の水ぶくれに関するよくある質問
ここでは、患者さんからよく寄せられる水虫の水ぶくれに関する質問と回答をまとめました。
- 水ぶくれの中の液体に触るとうつりますか?
-
水ぶくれの中の液体自体には、白癬菌はほとんど含まれていないため、液体に触ったからといって、すぐに水虫がうつるわけではありませんが、水ぶくれの周りの皮膚や、破れた後の皮には白癬菌がたくさん潜んでいます。
このような部分に触れた手で他の場所を触ると感染が広がる可能性があるため、患部に触れた後は必ず手をよく洗うようにしてください。
- 薬を塗るとかえってかゆくなるのはなぜですか?
-
薬を塗った後にかゆみが増す場合、いくつかの原因が考えられます。一つは、薬の成分そのものに対するアレルギー反応や刺激による接触皮膚炎(かぶれ)で、赤みや腫れがひどくなることが多いです。
もう一つは、薬が効いて白癬菌が死滅する際に、菌の成分が放出され、それに対して一時的にアレルギー反応が強く出ることによるものです。かぶれが疑われる場合は、すぐに薬の使用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。
- 治療中に運動や入浴はできますか?
-
治療中であっても日常生活に特別な制限はなく、運動や入浴も通常通り行って問題ありません。ただし、運動で汗をかいた後は、できるだけ早くシャワーを浴びるか、足を洗って清潔にし、よく乾燥させることが大切です。
汗で蒸れたまま放置すると、白癬菌が増殖しやすくなります。入浴の際は、患部をゴシゴシこすらず優しく洗うことを心がけてください。
家族と一緒に入浴する場合、最後の人がお風呂から出た後に、床や浴槽をシャワーで軽く洗い流しておくと、より安心です。
以上
参考文献
Ogawa T, Matsuda A, Ogawa Y, Tanaka R. Risk factors for the development of tinea pedis and onychomycosis: real‐world evidence from a single‐podiatry center, large‐scale database in Japan. The Journal of dermatology. 2024 Jan;51(1):30-9.
Takehara K, Oe M, Tsunemi Y, Ohashi Y, Kadowaki T, Sanada H. Association between tinea pedis and foot care factors in patients with diabetes. Journal of wound care. 2025 Apr 1;34(Sup4):S26-30.
Ishijima SA, Hiruma M, Sekimizu K, Abe S. Detection of Trichophyton spp. from footwear of patients with tinea pedis. Drug Discoveries & Therapeutics. 2019 Aug 31;13(4):207-11.
Tsunemi Y, Takehara K, Miura Y, Nakagami G, Sanada H, Kawashima M. Diagnosis of tinea pedis by the Dermatophyte Test Strip. British Journal of Dermatology. 2015 Nov 1;173(5):1323-4.
Leung AK, Barankin B, Lam JM, Leong KF, Hon KL. Tinea pedis: an updated review. Drugs in context. 2023 Jun 29;12.
Hiruma J, Kitagawa H, Noguchi H, Kano R, Hiruma M, Kamata H, Harada K. Terbinafine‐resistant strain of Trichophyton interdigitale strain isolated from a tinea pedis patient. The Journal of Dermatology. 2019 Apr;46(4):351-3.
Takehara K, Amemiya A, Mugita Y, Tsunemi Y, Seko Y, Ohashi Y, Ueki K, Kadowaki T, Oe M, Nagase T, Ikeda M. The association between tinea pedis and feet-washing behavior in patients with diabetes: A cross-sectional study. Advances in Skin & Wound Care. 2017 Nov 1;30(11):510-6.
Ogasawara Y. Prevalence and patient’s consciousness of tinea pedis and onychomycosis. Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi. 2003 Oct 30;44(4):253-60.
Watanabe S, Takahashi H, Nishikawa T, Takiuchi I, Higashi N, Nishimoto K, Kagawa S, Yamaguchi H, Ogawa H. Dose‐finding comparative study of 2 weeks of luliconazole cream treatment for tinea pedis–comparison between three groups (1%, 0.5%, 0.1%) by a multi‐center randomised double‐blind study. Mycoses. 2007 Jan;50(1):35-40.
Tanuma H. Current topics in diagnosis and treatment of tinea unguium in Japan. The Journal of Dermatology. 1999 Feb;26(2):87-97.