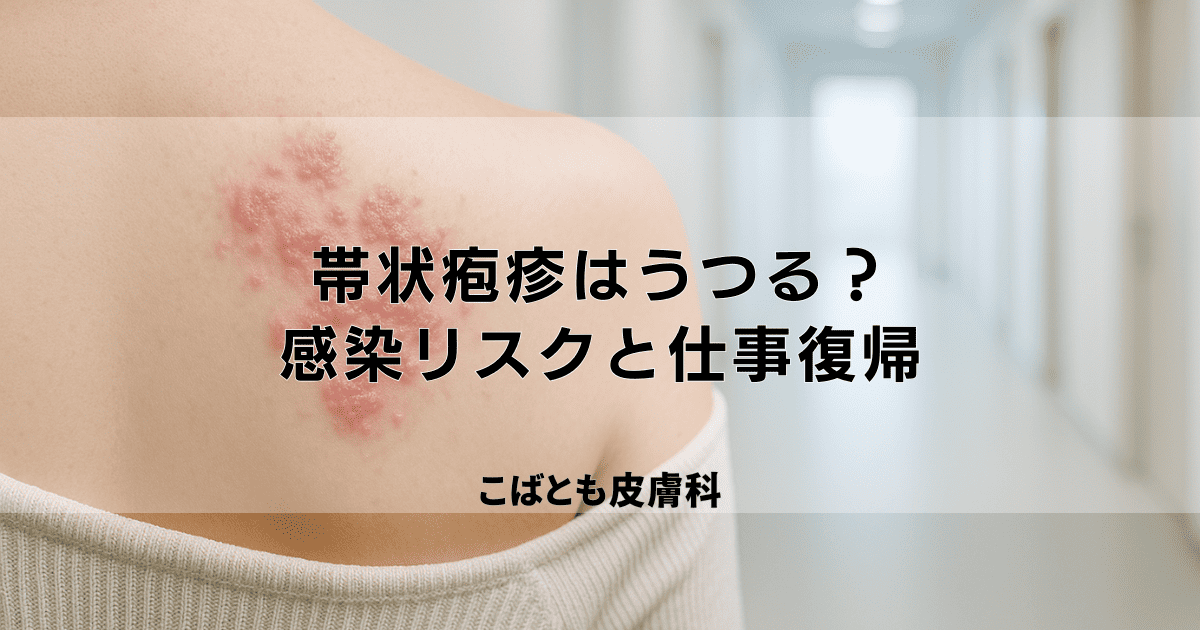「帯状疱疹になったけど、家族や同僚にうつるの?」「いつから仕事に行けるのだろう?」そんな疑問や不安を抱えていませんか。
帯状疱疹は、多くの人が子供の頃にかかる水ぼうそうと同じウイルスが原因で起こる病気です。体の片側にピリピリとした痛みが現れ、続いて赤い発疹や水ぶくれが出現し、つらい症状は、時に後遺症として長引くこともあります。
この記事では、帯状疱疹の感染経路や周りの人への影響、そして安心して仕事や日常生活に戻るための目安について、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
帯状疱疹の基本と感染のウワサの真相
帯状疱疹という病名を聞いたことはあっても、その正体や感染性については誤解も少なくありません。多くの人が経験する水ぼうそうとの関係性を理解することから始めましょう。
帯状疱疹とはどんな病気か
帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)によって起こる、痛みを伴う皮膚の病気で、ウイルスは、多くの人が幼少期に感染する水ぼうそうの原因ウイルスと同一です。
水ぼうそうが治癒した後、ウイルスは体内から消え去るわけではなく、背骨の近くにある神経の根元(後根神経節)などに潜伏し、活動を休止します。
数十年後、加齢、ストレス、過労、他の病気などによって体の免疫力が低下した際に、潜んでいたウイルスが再び目を覚まし、神経を伝って皮膚に到達し症状を引き起こします。これが帯状疱疹です。
症状は、まず皮膚に前駆痛と呼ばれる痛みや違和感、かゆみなどから始まることが多く、「刺すような」「焼けるような」と表現されることもあります。痛みが数日から1週間ほど続いた後、痛みのあった場所に赤い発疹(丘疹)が現れます。
発疹は胸から背中、腹部にかけての胴体部分に最も多く見られますが、顔や首、手足など、神経が通っている場所ならどこにでも現れる可能性があります。
その後、発疹は小さな水ぶくれ(水疱)に変化し、内部に膿が溜まる(膿疱)こともあり、最終的にこれらが破れてかさぶた(痂皮)となり、通常は2〜4週間で治癒します。
水ぼうそうとの関係性
帯状疱疹と水ぼうそうの関係は、同じウイルスが異なるタイミングで起こすものです。初めて水痘・帯状疱疹ウイルスに感染した場合は、全身に発疹と水ぶくれができる水ぼうそうとして発症します。
一方、体内に潜伏していたウイルスが再活性化して発症するのが帯状疱疹です。このため、水ぼうそうにかかったことがない人が、いきなり帯状疱疹になることはありません。
帯状疱疹は、あくまで水ぼうそうの既往がある人のみ発症する病気です。
帯状疱疹と水ぼうそうの比較
| 項目 | 帯状疱疹 | 水ぼうそう |
|---|---|---|
| 原因ウイルス | 水痘・帯状疱疹ウイルス(再活性化) | 水痘・帯状疱疹ウイルス(初感染) |
| 主な発症年齢 | 50代以降に多いが、若年層でも発症 | 主に9歳以下の小児期 |
| 発疹の範囲 | 体の片側の神経に沿って帯状に出る | 全身に散在して広がる |
「帯状疱疹はうつる」は本当か
「帯状疱疹がうつる」という言葉は、しばしば誤解を生みます。帯状疱疹という病気自体が、患者さんから他の人へそのまま伝染することはありません。
帯状疱疹の患者さんと話しただけで相手も帯状疱疹になる、ということはないのですが、全く感染のリスクがないわけではありません。問題となるのは、帯状疱疹の水ぶくれです。
水ぶくれの中には、原因である水痘・帯状疱疹ウイルスが大量に含まれていて、ウイルスが、免疫のない人に接触することで感染を起こす可能性があります。
感染のリスクがあるのはどんな人か
帯状疱疹の患者さんからウイルスが感染し、水ぼうそうを発症する可能性があるのは、水痘・帯状疱疹ウイルスに対する免疫を持っていない人です。
該当する人
- 過去に水ぼうそうにかかったことがない人
- 水ぼうそうのワクチンを接種したことがない人
- ワクチンを1回しか接種しておらず、十分な免疫がついていない人
上記に該当する人が帯状疱疹の水ぶくれの内容物に直接的、または間接的に触れると、ウイルスに初めて感染することになり、数週間後に水ぼうそうを発症します。
抵抗力の弱い乳幼児や、抗がん剤治療中の方、ステロイドを内服している方など、免疫機能が低下している人が水ぼうそうにかかると重症化しやすいため、より一層の注意が必要です。
帯状疱疹の感染経路
帯状疱疹のウイルスがどのようにして人にうつる可能性があるのか、経路を正しく理解することは、周囲への感染を防ぐうえで非常に大切です。空気感染の心配はほとんどありませんが、特定の状況下では注意を要します。
主な感染経路は接触感染
帯状疱疹の感染経路は、ほぼ接触感染に限られます。患者さんの水ぶくれが破れて中の液体(滲出液)が漏れ出た場合、液体には生きたウイルスが大量に含まれています。
液体に直接触れる直接接触はもちろんのこと、液体が付着したタオル、衣類、寝具、ドアノブ、おもちゃなどを介してウイルスに触れる間接接触によっても感染は成立します。
ウイルスが付着した手で、目、鼻、口の粘膜に触れることで、ウイルスが体内に侵入するので、感染予防の基本は、患部に触れないこと、そしてこまめな手洗いです。
空気感染や飛沫感染はするのか
通常の帯状疱疹であれば、空気感染や飛沫感染のリスクは極めて低いと考えられています。咳やくしゃみなどの飛沫にウイルスが含まれることは基本的にありません。
ただし、免疫機能が著しく低下している患者さん(臓器移植後や血液のがんを患っている方など)では、ウイルスが血液に乗って全身に広がり、水ぼうそうのように発疹が全身に出現する「汎発性帯状疱疹」という状態になることがあります。
この特殊な状態では、呼吸器からもウイルスが排出され、空気感染する可能性が指摘されていて、入院管理と厳重な感染対策が必要です。
感染経路の比較
| 感染経路 | 帯状疱疹における可能性 | 主な対策 |
|---|---|---|
| 接触感染 | あり(水ぶくれの内容物から) | 手洗い、患部の保護(ガーゼなど) |
| 飛沫感染 | 基本的にない | 特別な対策は不要 |
| 空気感染 | 汎発性など特殊な場合を除き、ない | 通常の帯状疱疹では不要 |
ウイルスが最も多い時期
ウイルスが体外に排出され、感染力が最も高まるのは、赤い発疹が水ぶくれ(水疱)に変化してから、破れてかさぶたになるまでの期間です。
水ぶくれがパンパンに張っている時期や、破れてじゅくじゅくしているびらん面には、ウイルスの数がピークに達し、この時期に患部に触れることは感染のリスクを著しく高めます。
発疹がまだ赤みだけの段階や、すべての水ぶくれが完全に乾いて黒っぽいかさぶたになった後では、感染力はほぼ消失したと考えてよいでしょう。
感染期間の目安
他者へ感染させる可能性がある期間は、一般的に、最初の水ぶくれが出現してから、すべての発疹がかさぶたで覆われるまでとされていて、おおよそ7日から10日程度です。
この間は、水ぼうそうの免疫がない人との接触は、できる限り避けましょう。特に免疫力が低下している方では、ウイルスの排出期間が長引くこともあるため、医師の指示に従うことが重要です。
家庭内で気をつけるべきこと
家族の中に帯状疱疹を発症した人がいる場合、家庭内での感染を防ぐための配慮が大切です。水ぼうそうにかかったことのない小さなお子さんや、免疫力が低下しているご家族、妊娠中の女性がいる場合は、対策を講じましょう。
患者本人ができる対策
まず、患者さん自身ができる最も重要な対策は、患部を管理することです。
水ぶくれは、ウイルスがたくさん詰まった袋です。これを掻きむしったり、故意に潰したりすると、ウイルスを周囲にまき散らすだけでなく、傷口から細菌が入って二次感染を起こす原因にもなります。
患部は清潔なガーゼや包帯で覆い、滲出液が外部に漏れないように保護してください。他者への感染を防ぐと同時に、衣類との摩擦による痛みを軽減する効果もあります。
さらに、患部に触れた後は、必ず石鹸と流水で丁寧に手を洗う習慣をつけ、衣類は、肌触りの良い、ゆったりとしたものを着用しましょう。
患者本人の感染対策リスト
- 患部を清潔に保ち、乾燥を心がける
- 水ぶくれを絶対に掻いたり潰したりしない
- 患部をガーゼなどで覆い、物理的に保護する
- 患部に触れた後や、着替えの後は必ず手洗いをする
同居家族が注意すべき点
同居している家族は、患者さんが使用した物品の取り扱いに少し注意を払うことで、感染リスクを大幅に減らすことができます。水ぶくれがじゅくじゅくしている時期は、タオルやバスタオルの共用は厳禁です。
洗濯については、患者さんの衣類やシーツを他の家族のものと分けて洗う必要まではありませんが、洗濯前の衣類を扱う際や、洗濯物を干した後は念のため手を洗いましょう。食器の共用や、同じ食卓で食事をすることは問題ありません。
家庭内での注意点
| 対象物 | 注意点 | 推奨される対応 |
|---|---|---|
| タオル・バスタオル | 共用は絶対に避ける | 患者さん専用のものを用意し、毎日交換する |
| 衣類・寝具 | 患部に直接触れたものは速やかに交換 | こまめに洗濯し、日光でよく乾かす |
| 入浴 | 湯船のお湯を介した感染は稀 | 患者さんが最後に入浴し、浴槽は軽く流す |
乳幼児や妊婦への配慮
家庭内に水ぼうそうの免疫がない乳幼児や妊婦さんがいる場合は、最大限の注意が必要です。乳幼児がウイルスに初感染すると水ぼうそうを発症し、時に重症化することがあります。
また、妊娠20週頃までの妊婦さんが水ぼうそうにかかると、胎児に影響が及ぶ「先天性水痘症候群(手足の形成不全、小頭症、目の異常など)」のリスクがあります。
患者さんとの不必要な接触は、すべての水ぶくれがかさぶたになるまで極力避け、生活空間を分けるなどの配慮も検討しましょう。もし接触してしまった場合は、速やかにかかりつけの産婦人科医や小児科医に相談してください。
職場での感染リスクと仕事復帰の判断
帯状疱疹と診断されたとき、多くの方が悩むのが仕事のことです。「同僚にうつしてしまわないか」「いつから出勤できるのか」「痛みが続くけど休んでいいのか」といった不安は当然のことです。
ここでは、職場での対応と仕事復帰の目安について、解説します。
仕事復帰はいつから可能か
仕事復帰のタイミングを判断する上で考慮すべき点は、「感染のリスク」と「本人の体調」の2つの側面です。
感染リスクの観点からは、すべての水ぶくれが完全に乾いてかさぶたになれば、他者への感染の心配はほぼなくなり、通常、発疹が出現してから7日から10日程度でこの状態になります。
しかし、もう一つの重要な側面が本人の体調です。帯状疱疹は強い痛みを伴うことが多く、皮膚症状が治まっても痛みが続くことがあります。
痛みのために集中力が低下したり、十分な休息がとれず疲労が蓄積したりしている状態では、業務の遂行が困難な場合があります。
仕事復帰の判断基準
| 判断基準 | 目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 感染リスクの消失 | 全ての発疹がかさぶた化する | 他者への感染力がなくなる医学的基準 |
| 本人の体調回復 | 痛みが業務に支障ないレベルまで軽快 | 鎮痛薬でコントロールでき、集中力が保てるか |
| 医師の総合的判断 | 治癒証明書や診断書の発行 | 職場規定に応じて必要となる場合がある |
出勤停止は法律で定められているか
帯状疱疹は、インフルエンザや麻疹(はしか)、新型コロナウイルス感染症のように、感染症法や学校保健安全法で出勤停止(あるいは出席停止)が厳密に義務付けられている感染症には分類されていません。
しかし、これは「出勤しても良い」という意味ではありません。職場には、妊婦さんや持病を持つ方など、様々な健康状態の人が働いています。
水ぼうそうの免疫がない同僚に感染させてしまうリスクを考慮し、感染の可能性がある期間は自宅療養することが強く推奨されます。
職種別の注意点
職種によっては慎重な復帰判断が求められ、一般の事務職などと比べて、より厳しい基準が適用されることがあります。
特に注意が必要な職種
| 職種 | 注意すべき理由 |
|---|---|
| 医療・介護従事者 | 免疫不全の患者や高齢者への感染リスクが非常に高い |
| 保育士・教員 | 水ぼうそう未罹患の小児への集団感染を引き起こすリスク |
| 調理師・食品加工業 | 食品衛生の観点と、他者への接触機会が多いこと |
上記の職種に従事する方は、職場の感染管理マニュアルなどを確認し、産業医や主治医と緊密に連携して復帰のタイミングを決める必要があります。
帯状疱疹の治療と痛みの管理
帯状疱疹の治療は、ウイルスの増殖を抑える原因療法と、つらい痛みを和らげる対症療法の二本柱で行います。早期に適切な治療を開始することが、回復を早め、帯状疱疹後神経痛(PHN)という後遺症を防ぐために極めて重要です。
主な治療法は抗ウイルス薬
帯状疱疹治療の根幹をなすのが、抗ウイルス薬の内服です。アシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルといった薬が、ウイルスのDNA複製を阻害し、増殖を強力に抑制します。
発疹が出現してから72時間(3日)以内に服用を開始することが最も効果的です。
この期間はウイルスが最も活発に増殖しているため、早期に叩くことで、神経へのダメージを最小限に食い止め、症状の重症化やPHNへの移行リスクを大幅に低減できます。
たとえ72時間を過ぎてしまっても、治療効果が全くないわけではないので、諦めずに受診してください。通常、7日間しっかりと服用を続けます。
痛みを和らげるための対症療法
帯状疱疹の痛みは急性痛と呼ばれ、神経が炎症を起こすことで生じる非常に強い痛みです。この痛みに対しては、抗ウイルス薬と並行して、鎮痛薬を積極的に使用します。
痛みを我慢することは体力を消耗させるだけでなく、痛みの記憶が脳に刻み込まれ、PHNに移行しやすくなる一因です。痛みの強さに応じて、様々な種類の薬を使い分け、あるいは組み合わせて対応します。
痛みの強さに応じた鎮痛薬
| 痛みのレベル | 使用される薬剤の例 |
|---|---|
| 軽度〜中等度 | アセトアミノフェン、NSAIDs(ロキソプロフェン、ジクロフェナクなど) |
| 中等度〜重度 | 神経障害性疼痛治療薬(プレガバリン、ミロガバリン)、トラマドール |
| 激しい痛み | 神経ブロック注射(局所麻酔薬)、医療用麻薬(オピオイド) |
皮膚症状に対する塗り薬
発疹や水ぶくれといった皮膚症状に対しては、細菌による二次感染を防ぎ、炎症を鎮め、皮膚の回復を助けるために塗り薬(外用薬)が処方されます。
水ぶくれの段階では、びらん面を保護し乾燥を促す軟膏、細菌感染を合併した場合は抗菌薬含有の軟膏が用いられます。自己判断で市販のステロイド軟膏などを塗ると、かえって症状を悪化させる危険性があるため、絶対にやめましょう。
必ず医師から処方された薬を指示通りに使用してください。
帯状疱疹後神経痛(PHN)とは
帯状疱疹後神経痛(PHN: Postherpetic Neuralgia)は、帯状疱疹の最もつらく頻度の高い合併症で、皮膚の発疹がすっかり治った後にもかかわらず、3ヶ月以上にわたって痛みが持続する状態を指します。
原因は、帯状疱疹ウイルスによって神経線維が深く損傷され、異常な痛みの信号が脳に送られ続けるためです。
痛みは「焼けるような」「締め付けられるような」「電気が走るような」などと表現され、衣類が触れるといった軽い刺激でも激痛が走る「アロディニア」という現象を伴うこともあります。
50歳以上の患者さんの約2割がPHNに移行するともいわれ、高齢であるほど、また初期の痛みが激しいほどリスクが高まります。
帯状疱疹を予防するためにできること
帯状疱疹は、一度かかるとつらい症状に悩まされる病気です。しかし、日々の心がけや医学的なアプローチによって、発症そのものを防いだり、もし発症しても軽症で済ませたりすることが可能です。
免疫力を維持する生活習慣
帯状疱疹の最大の引き金は、潜伏しているウイルスを抑え込む免疫力の低下で、日頃から免疫機能を正常に保つ生活を心がけることが、最も基本的かつ重要な予防策です。特定の食品だけで免疫力が劇的に上がるわけではありません。
主食・主菜・副菜のそろったバランスの良い食事を基本とし、十分な睡眠時間を確保して体を休ませ、ウォーキングなどの適度な運動を習慣づけることが大切です。また、過度な精神的ストレスは免疫系に悪影響を及ぼすことが知られています。
自分なりのリラックス法を見つけ、上手にストレスと付き合っていくことも、ウイルスに負けない体づくりにつながります。
免疫力維持のポイント
- バランスの取れた食事(ビタミン、ミネラル、タンパク質)
- 質の良い睡眠(6〜8時間を目安に)
- 適度な運動習慣(週に2〜3回、30分程度の有酸素運動)
- ストレス管理(趣味、入浴、瞑想など)
帯状疱疹ワクチンという選択肢
50歳以上の方は、帯状疱疹ワクチンを接種することで、発症リスクを大幅に下げることができます。ワクチンは、加齢とともに低下する水痘・帯状疱疹ウイルスに対する免疫を再強化する働きをします。
万が一発症した場合でも、症状が軽く済んだり、PHNへの移行を防いだりする効果も報告されています。現在、日本で接種できるワクチンには2種類あり、それぞれ特徴が異なります。
帯状疱疹ワクチンの種類と特徴
| 種類 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン |
|---|---|---|
| 分類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン(サブユニットワクチン) |
| 接種回数 | 1回 | 2回(2ヶ月間隔) |
| 予防効果 | 約50-60% | 約90%以上 |
| PHN予防効果 | 約67% | 約88%以上(70歳以上) |
どちらのワクチンが自分に適しているか、費用や副反応、持病などを考慮し、医師とよく相談して決めることが重要です。
過去に帯状疱疹にかかった人もワクチンは有効か
帯状疱疹は一度かかれば二度とからない、というわけではありません。数パーセントの確率で再発することが知られています。特に、初回の発症時に免疫力が著しく低下していた方などは、再発のリスクが比較的高くなります。
過去に帯状疱疹にかかったことがある人でも、ワクチンを接種することは可能です。ワクチン接種により、ウイルスに対する免疫力を再度高め、再発を予防する効果が期待できます。
接種のタイミングは、帯状疱疹の急性期の症状が治まってからとなりますので、主治医と相談してください。
水ぼうそうの既往歴が不明な場合
「自分が子供の頃に水ぼうそうにかかったか覚えていない」という方は少なくありません。しかし、現在の日本の成人(特に50歳以上)の9割以上は、自覚がない場合でも水痘・帯状疱疹ウイルスに対する免疫を持っています。
心配な方は、採血による抗体検査で免疫の有無を確認することもできますが、検査をせずにワクチンを接種しても医学的な安全性に問題はありません。
よくある質問
最後に、帯状疱疹に関して患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- お風呂に入っても大丈夫ですか?
-
シャワー浴や入浴は問題ありません。体を清潔に保つことは、細菌による二次感染の予防に重要です。また、体を温めることで血行が促進され、痛みが一時的に和らぐこともあります。
ただし、熱すぎるお湯や長時間の入浴は体力を消耗させるため避けましょう。患部は石鹸をよく泡立てて、手で優しく洗い流す程度にし、ゴシゴシこすらないでください。水ぶくれを破らないように細心の注意が必要です。
入浴後は清潔なタオルで軽く押さえるように水分を拭き取ります。感染リスクを考慮し、同居家族がいる場合は最後に入浴するのが望ましいです。
- 痛みはいつまで続きますか?
-
一般的には皮膚の症状が改善するにつれて、2〜4週間ほどで徐々に和らいでいきます。
しかし、一部の人は皮膚症状が治った後も痛みが続く帯状疱疹後神経痛(PHN)に移行することがあり、この場合は数ヶ月から数年にわたって痛みに悩まされることもあります。
痛みがなかなか改善しない、あるいは一度治まった痛みがぶり返すような場合は、我慢せずに主治医に相談し、ペインクリニックの受診も視野に入れながら、痛み治療を継続することが重要です。
- 食事で気をつけることはありますか?
-
帯状疱疹を直接治す特定の食べ物やサプリメントはありません。ダメージを受けた皮膚や神経の修復を助け、免疫力をサポートするために、栄養バランスの取れた食事を心がけることが非常に大切です。
特に、皮膚や粘膜の健康を保つビタミンA(緑黄色野菜)、ビタミンC(果物、野菜)、ビタミンB群(豚肉、玄米)、体の材料となる良質なタンパク質(肉、魚、大豆製品)を意識して摂取しましょう。
唐辛子などの刺激の強い香辛料や、多量のアルコールは、血管を拡張させたり神経を興奮させたりして、痛みを増強させることがあるため、症状が強い時期は控えてください。
- 運動はしてもいいですか?
-
発熱や強い痛みを伴う急性期は、安静が第一です。体力を消耗するような運動は避け、十分な休息と睡眠をとることに専念してください。症状が回復してきたら、散歩などの軽い運動から少しずつ再開するのは問題ありません。
ただし、痛みが残っている場合は無理をせず、どの程度の運動が可能か主治医に相談してから行ってください。
以上
参考文献
Kohanna FH. Ten common infectious diseases that affect health & safety in the workplace. InASSE Professional Development Conference and Exposition 2015 Jun 7 (pp. ASSE-15). ASSE.
Panlilio AL, Gerberding JL. Occupational infectious diseases. Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine. 2009 May 15:469.
Reddy V, Kollhoff AL, Murase JE, Martires K. Management guidelines for pregnant health care workers exposed to infectious dermatoses. International Journal of Women’s Dermatology. 2020 Jun 1;6(3):142-51.
Cheng VC, Chan JF, Hung IF, Yuen KY. Viral infections, an overview with a focus on prevention of transmission. International encyclopedia of public health. 2016 Oct 24:368.
Panlilio AL, Gerberding JL. Occupational infectious diseases. Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine. 2009 May 15:469.
Macher JM, Gold D, Cruz P, Kyle JL, Durrani TS, Shusterman D. Evaluation and management of exposure to infectious agents. Handbook of Occupational Safety and Health. 2019 Apr 10:147-97.
Rosamilia LL. Herpes zoster presentation, management, and prevention: a modern case-based review. American Journal of Clinical Dermatology. 2020 Feb;21(1):97-107.
Rafferty E, McDonald W, Qian W, Osgood ND, Doroshenko A. Evaluation of the effect of chickenpox vaccination on shingles epidemiology using agent-based modeling. PeerJ. 2018 Jun 20;6:e5012.
Madison LK. Shingles update: common questions in caring for a patient with shingles. Dermatology Nursing. 2001 Feb 1;13(1):51-.
MR MR, Haribabu Y, Velayudhankutty S, Eapen SC, Sujitha M. Review on: shingles, its complications & management. The Pharma Innovation. 2013 Jun 1;2(4).