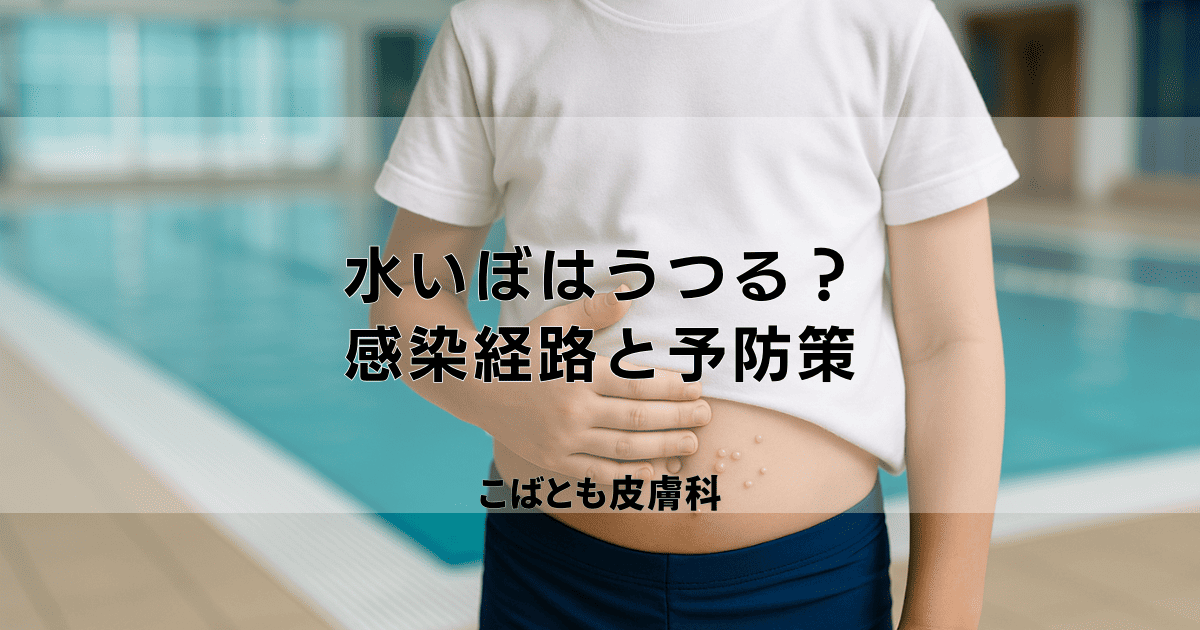お子さんの体に、ある日突然現れる光沢のある小さなブツブツ。それは、子どもたちの間でよく見られる皮膚の感染症、水いぼ(伝染性軟属腫)かもしれません。
水いぼはうつるのか、プールには入れるのか、兄弟にうつさないためにはどうすれば良いのか、多くの保護者の方が疑問や不安を抱えています。
この記事では、水いぼの正体から、気になる感染経路、プールやご家庭で今日から実践できる予防策まで、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
まず知っておきたい水いぼの基本
水いぼの見た目の特徴や原因、かかりやすい年齢など、基本的な知識を押さえておきましょう。一見するとただの湿疹やニキビのようにも見えますが、正体はウイルスであり特有の性質を持っています。
水いぼ(伝染性軟属腫)とは何か
水いぼの正式な病名は、伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ)です。伝染性、つまり人から人へとうつる性質を持っています。大きさは直径1mmから5mm程度で、表面はツルツルとしていて、真珠のような独特の光沢があるのが大きな特徴です。
色は肌色か少しピンク色で、半球状に盛り上がり、よく見ると中央にへそ(臍窩)のようなくぼみが見られます。くぼみは、水いぼを見分ける上で非常に重要なポイントです。
通常、痛みやかゆみはほとんどありませんが、体がウイルスを異物と認識して免疫反応を起こし始めると、水いぼの周りが赤く腫れてかゆみを伴うことがあります。これは治る前の兆候であることも多いです。
原因はウイルス感染
水いぼの原因は、伝染性軟属腫ウイルスというポックスウイルス科に属するウイルスです。
ウイルスが皮膚のバリア機能が低下した部分や、目に見えないほどの小さな傷から侵入し、皮膚の最も外側にある表皮の細胞内で増殖することで、特徴的なブツブツが作られます。
水いぼの中にはウイルスそのものと、ウイルスに感染して変性した細胞からなる、白い粥状の塊(軟属腫小体)が詰まっています。そして、軟属腫小体が、水いぼが潰れたり掻き壊されたりすることで外に飛び出し、新たな感染源となります。
原因はウイルスであるため、細菌感染に用いる抗生物質の飲み薬や塗り薬は全く効果がありません。
水いぼの主な特徴
| 項目 | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| 大きさ・形 | 直径1~5mm、半球状の盛り上がり | 中央にくぼみ(臍窩)が見られることが多い。 |
| 色・表面 | 肌色~淡いピンク色、なめらかで光沢がある | 「真珠様」と表現されることもある。 |
| 症状 | 通常は無症状(痛み・かゆみなし) | 掻き壊したり、治り際に炎症を起こしてかゆみが出ることがある。 |
好発年齢とできやすい部位
水いぼは、皮膚のバリア機能がまだ十分に発達しておらず、免疫機能も未熟な幼児から小学校低学年の子ども(おおむね10歳以下)に最も多いです。
もともと肌が乾燥しがちな子どもや、アトピー性皮膚炎のある子どもは、皮膚の表面に細かい傷ができやすく、バリア機能が低下しているためウイルスが侵入しやすく、感染しやすい傾向があります。
できやすい部位は、皮膚が薄く柔らかい場所や、衣類でこすれやすい場所で、胸、お腹、背中といった体幹部や、わきの下、ひじや膝の内側、首周りなどです。
大人は多くの場合、幼少期に感染して免疫を獲得しているため、感染することはまれですが、免疫力が著しく低下している状態では発症することもあります。
水いぼの主な感染経路
水いぼがうつる病気であることはわかりましたが、どのようにして感染は広がるのでしょうか。感染経路は、大きく分けて、人から直接うつる場合と、物を介して間接的にうつる場合があります。
皮膚と皮膚の直接的な接触
最も一般的で主要な感染経路は、水いぼのある人の皮膚と、他の人の皮膚が直接触れ合うことです。
子ども同士が保育園や公園で遊ぶ中で、肌がこすれ合ったり、おにごっこやレスリングごっこのような遊びで密着したりすることでウイルスが移動します。
水いぼを掻き壊して、ウイルスを含んだ内容物(軟属腫小体)が出てしまっている状態では、感染のリスクが格段に高いです。家庭内でも、兄弟げんかなどで肌を引っ掻き合ったり、親子でくっついて寝たりすることも、感染の機会となり得ます。
物を介した間接的な接触
ウイルスが付着した物を介して感染することも重要な経路で、間接接触感染と呼びます。水いぼのある人が使ったタオルや衣類、寝具、おもちゃなどには、目に見えないウイルスが付着している可能性があります。
ウイルスが付着した物を他の人が使うことで、皮膚に付着しそこから感染が成立します。特に、湿ったタオルやバスマット、プールで使うビート板や浮き輪などは、ウイルスが生存しやすい環境であるため注意が必要です。
乾燥した場所ではウイルスは比較的早く感染力を失いますが、湿った環境では長く生き残ることがあります。
主な感染経路のまとめ
| 感染経路 | 具体的な状況 | 主な感染の場 |
|---|---|---|
| 直接接触感染 | 肌が触れ合う遊び、兄弟げんか、親子での添い寝 | 家庭、保育園、幼稚園、学校、公園 |
| 間接接触感染 | タオル、ビート板、浮き輪、おもちゃ、体操マットの共有 | 家庭、プール、公衆浴場、ジム |
自分の体で広がる自家接種
水いぼは、他の人にうつるだけでなく、自分の体の中でどんどん増えていくことがあります。これが自家接種で、水いぼが広がる上で非常に重要な経路です。水いぼのある部分を掻いた手には、目に見えないウイルスが付着します。
その手で、体の他の部分、例えばお腹や腕などを無意識に触ることで、ウイルスが新たな場所に運ばれ、そこに新しい水いぼができてしまうのです。
乾燥肌やアトピー性皮膚炎でかゆみが強いお子さんは、広範囲を掻いてしまうため、あっという間に数十個、時には百個以上に増えてしまうこともあります。
プールでの感染は心配?水いぼとプールの関係
夏になると、保護者の方から最も多く寄せられる質問が、水いぼとプールの問題です。プールで水いぼがうつるのか、自分の子どもが他の子にうつしてしまわないか、心配は尽きません。
水そのものでの感染リスクは低い
多くの人が心配するのは、プールの水を介して感染するのではないか、という点です。
日本のプールの水は水道法に基づいて塩素濃度が厳しく管理されており、塩素によって伝染性軟属腫ウイルスは速やかに感染性を失う(不活化される)ため、水を介して水いぼに感染するリスクは極めて低いとされています。
水いぼがあるからといって、プールに入ること自体を禁止する必要はない、というのが日本臨床皮膚科医会や日本小児皮膚科学会の統一見解です。
ビート板やタオルの共有が主なリスク
プールで注意すべきなのは、水そのものよりも、皮膚が直接触れる物を介した間接接触感染です。ビート板やアームヘルパー、浮き輪、タオルなどを友達と貸し借りすることは、感染の大きなリスクとなります。
水いぼがこすれてウイルスが付着したビート板を、次に別の子供が胸やお腹に当てて使うことで、ウイルスがうつる可能性があり、また、プールサイドで子ども同士がじゃれ合って肌が触れ合うことも、直接接触による感染の原因です。
プール利用時の注意点
- ビート板や浮き輪、タオルの共有は絶対に避ける。
- プールサイドで走り回ったり、肌が激しく触れ合う遊びは控えるように話す。
- プール後はシャワーで体をよく洗い流し、塩素や汚れを落とす。
- ラッシュガードの着用で、物理的に水いぼを覆い、接触を防ぐ。
ラッシュガードの着用は有効か
水いぼができてしまった場合、他の子どもへの感染を広げない配慮として、また自分の水いぼを掻き壊しから守るためにも、ラッシュガードを着用することは非常に有効です。
ラッシュガードで水いぼのある部分を物理的に覆うことで、他の子どもとの直接的な肌の接触を防ぎ、ビート板などにウイルスが付着するリスクを大幅に減らすことができます。
園や学校によっては、ラッシュガードの着用を推奨、あるいはルール化しているところもあります。
保育園や幼稚園でのプールの方針
医学的にはプールに入ることが問題ないとされていても、保育園や幼稚園、スイミングスクールによっては、集団感染への懸念から、独自のルールで水いぼがある子どものプール参加を制限している場合があります。
これは、万が一の事態を避けたいという施設側の配慮によるものです。トラブルを避けるためにも、まずはかかりつけの医師に相談し、現状の医学的見解について確認した上で、園や施設の方針を確認し、従いましょう。
家庭内や集団生活での感染予防策
水いぼの感染は、プールだけでなく、日常の様々な場面で起こり得ます。肌が触れ合う機会の多い家庭内や、保育園・幼稚園などの集団生活の場では、感染を広げないための工夫が重要です。
タオルや衣類の共有を避ける
家庭内での感染予防の基本中の基本は、タオルやバスタオルの共有を徹底してやめることです。水いぼのある子もない子も、それぞれ自分専用のタオルを使い、色や柄で区別できるようにすると良いでしょう。
体を洗うスポンジやボディタオルも同様です。衣類やパジャマも、直接肌に触れるものなので、こまめに洗濯し、兄弟間での貸し借りはしないようにします。
洗濯は他の家族のものと一緒で構いませんが、洗濯後はしっかりと乾燥させることが大切です。
家庭内で注意すべき共有物
| 共有を避けるべき物 | 理由 | 対策 |
|---|---|---|
| タオル・バスタオル | 湿っていてウイルスが生存しやすい。 | 個人専用にする。こまめに洗濯・乾燥させる。 |
| 衣類・パジャマ | 直接肌に触れ、ウイルスが付着しやすい。 | 毎日着替え、洗濯する。兄弟での貸し借りをしない。 |
| 爪切り | 皮膚や爪の間にウイルスが付着する可能性がある。 | 個人専用にするか、使用後にアルコールで拭くなど消毒する。 |
お風呂での注意点
兄弟で一緒にお風呂に入ることは、感染のリスクも伴います。水いぼのある子どもは、湯船につかる前にシャワーで体をきれいに洗い、一番最後に入浴するように心がけましょう。
また、お風呂で使うおもちゃの共有も感染源となりうるため、使用後はよく洗って乾かしてください。体を洗う際は、水いぼを潰さないように、石鹸をよく泡立てて手で優しく洗うのがポイントです。
掻き壊しを防ぐためのスキンケア
水いぼの自家接種(自分の体で広がること)を防ぐためには、掻き壊さないことが何よりも重要です。乾燥肌やアトピー性皮膚炎があると、皮膚全体がかゆくなり、水いぼの周りも掻いてしまいがちです。
日頃から、入浴後や朝の着替えの際などに保湿剤をたっぷりと塗り、皮膚のバリア機能を正常に保つことが、水いぼの悪化や拡大を防ぐことにつながります。
爪は常に短く丸く切っておき、万が一掻いてしまっても皮膚を傷つけにくいようにしておきましょう。かゆみが強い場合は、皮膚科でかゆみ止めの薬を処方してもらうこともできます。
保育園・幼稚園への登園について
水いぼは、インフルエンザやおたふくかぜのように、学校保健安全法において「出席停止が必要な感染症」には指定されておらず、水いぼがあるという理由だけで、登園・登校を禁止されることはありません。
ただし、プール活動に関しては園や学校の方針を確認する必要があります。集団生活の場では、他の子どもへの配慮として、患部を衣服で覆ったり、数が少ない場合は絆創膏や包帯で保護しましょう。
水いぼの治療法と皮膚科での対応
水いぼは、基本的には自然に治る良性の病気です。しかし、数が多い場合や、掻き壊してどんどん広がってしまう場合、美容的な問題で気になる場合などには、皮膚科で治療を行うこともできます。
自然治癒を待つという選択肢
水いぼは、ウイルスに対する体の免疫が獲得されれば、何もしなくても半年から2、3年で自然に消えていきます。
数が少なく、本人も気にしていないようであれば、特別な治療をせずに経過観察をするというのも、選択肢の一つです。
痛みを伴う治療を怖がったり、嫌がったりする小さなお子さんの場合は、無理に治療せず、保湿などのスキンケアを徹底しながら自然に治るのを待つことも多いです。
治療法の比較
| 治療法 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| 自然治癒(経過観察) | 痛みがなく、子どもへの負担が少ない。傷跡の心配がない。 | 治るまでに時間がかかる。その間に増えたりうつしたりする可能性がある。 |
| ピンセットによる摘除 | 確実性が高く、すぐに取り除ける。治癒までの期間が短い。 | 痛みを伴う。出血や小さな傷跡のリスクがある。子どもの恐怖心が強い。 |
| 液体窒素による凍結療法 | ピンセットより痛みが少ない場合がある。出血が少ない。 | 数回の治療が必要。水ぶくれや色素沈着のリスクがある。 |
ピンセットによる物理的な摘除
最も確実で昔行われている治療法が、専用のリング状のピンセット(トラコーマ鑷子)で水いぼを一つひとつつまみ、中にあるウイルス塊(軟属腫小体)を圧出する方法です。
確実性が高く、治療期間を短縮できるのが最大のメリットですが、痛みを伴います。痛みを和らげるために、処置の1時間ほど前に、麻酔成分の入ったテープ(ペンレステープなど)を水いぼに貼ってから処置を行うことが一般的です。
数が少ない場合や、プールなどの行事のために早期に治したい場合に選択されます。
液体窒素による凍結療法
マイナス196℃の超低温の液体窒素を染み込ませた綿棒を水いぼに数秒間当て、ウイルスに感染した細胞を凍結させて壊死させる方法です。いぼ(尋常性疣贅)の治療でよく用いられる方法ですが、水いぼにも応用されることがあります。
ピンセットでの摘除よりは痛みが少ないとされますが、それでもピリッとした冷たい痛みを伴います。一度では取りきれず、1~2週間おきに数回の通院が必要になることが多いです。
治療後に水ぶくれや血豆ができたり、一時的に色素沈着が起こったりする可能性もあります。
その他の治療法
上記以外にも、いくつかの治療法が試みられることがあります。角質を柔らかくする作用のあるサリチル酸絆創膏を小さく切って貼る方法や、免疫力を高める効果が期待される漢方薬のヨクイニン(ハトムギのエキス)を内服する方法などです。
また、特殊な化学薬品(フェノールや硝酸銀など)を塗布する方法もありますが、実施している医療機関が限られます。
いずれの方法も効果には個人差があり、医学的な有効性が確立されているとは言えないため、あくまで補助的な治療と位置づけられています。
水いぼと間違えやすい他の皮膚疾患
子どもの体にできるブツブツは、水いぼだけではありません。中には、異なる治療が必要な病気もあります。自己判断は禁物ですが、参考として、水いぼと似た症状を示す他の皮膚疾患について知っておきましょう。
いぼ(尋常性疣贅)
一般的にいぼと呼ばれる尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)も、ウイルス(ヒトパピローマウイルス)による感染症で、子どもによく見られます。水いぼと異なり、表面がザラザラとしていて硬いのが特徴です。
ドーム状に盛り上がり、よく見ると黒い点々(血栓ができた毛細血管)が見えることがあり、足の裏にできると、体重で圧迫されて平らになり、魚の目と間違われることもあります。
自然に治ることは少なく、液体窒素による凍結療法などで積極的に治療を行います。
あせも(汗疹)
あせもは、汗の管が詰まることで起こる皮膚の炎症です。夏場に、汗をかきやすい首やひじ・膝の裏、おむつで蒸れるお尻などに、赤い小さなブツブツ(紅色汗疹)や、透明な小さな水ぶくれ(水晶様汗疹)が多発します。
強いかゆみを伴うことが多く、掻き壊すととびひ(伝染性膿痂疹)になることもあり、涼しい環境を保ち、こまめに汗を拭き、皮膚を清潔に保つことで改善します。
水いぼと似た疾患の見分け方
| 疾患名 | 見た目の特徴 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 水いぼ | 光沢があり、中央にくぼみがある半球状のいぼ | 通常は無症状 |
| いぼ(尋常性疣贅) | 表面がザラザラして硬い。黒い点々が見えることも。 | 通常は無症状 |
| あせも(汗疹) | 赤い小さなブツブツ、小さな水ぶくれが多発 | かゆみ |
| とびひ(伝染性膿痂疹) | 水ぶくれができ、破れてじゅくじゅくする。黄色いかさぶた。 | かゆみ、ヒリヒリ感 |
とびひ(伝染性膿痂疹)
とびひは、主に黄色ブドウ球菌やレンサ球菌による細菌感染症です。
虫刺されやあせも、湿疹を掻き壊した傷に細菌が感染して始まります。最初に水ぶくれ(水疱)ができ、すぐに破れて皮膚がめくれ(びらん)、じゅくじゅくした液体が出てきて、液体が乾くと、蜂蜜色のかさぶたができます。
水ぶくれの中の液体や、びらん面からの浸出液には細菌が大量に含まれており、これを触った手で他の場所を触ると、火事の飛び火のようにあっという間に広がります。抗生物質の飲み薬や塗り薬による治療が必須です。
よくある質問
最後に、水いぼに関して保護者の方からよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 水いぼは取った方がいいですか?
-
積極的に取るべきという考え方と、自然に治るのを待つべきという考え方があり、どちらも間違いではありません。取るメリットは、治癒までの期間を短縮できること、自家接種による拡大や他人への感染を防げることです。
一方、取らないメリットは、子どもに痛い思いをさせずに済むこと、処置による傷跡のリスクがないことです。
最終的には、水いぼの数(少数か多数か)、場所(目立つ場所か)、本人の年齢、アトピー性皮膚炎の有無(広がりやすいか)、生活環境(下に小さい兄弟がいるか)、そして保護者の方の考えなどを総合的に判断します。
どちらが正解ということはなく、医師とよく相談して、ご家庭に合った方針を決めるのが一番です。
- 水いぼの跡は残りますか?
-
水いぼそのものは、炎症を起こさずに自然に治れば、跡を残すことはほとんどありません。
しかし、強く掻き壊してしまったり、細菌による二次感染を起こして炎症がひどくなってしまったりすると、炎症後色素沈着として茶色っぽいシミが数ヶ月残ったり、小さなへこみが残ったりすることがあります。
ピンセットで取った場合も、処置後に炎症が起きれば同様のリスクがあります。跡を残さないためには、掻き壊さないように保湿などのスキンケアを徹底し、二次感染を防ぐことが重要です。
- 大人が水いぼになることはありますか?
-
大人が水いぼになることは非常にまれです。ほとんどの大人は、子どもの頃に知らないうちに感染して免疫を獲得しているか、ウイルスに接する機会があっても免疫力で発症を防いでいると考えられています。
ただし、アトピー性皮膚炎などで皮膚のバリア機能が低下していたり、ステロイドや免疫抑制剤の使用、HIV感染症、臓器移植後などで免疫力が低下している状態では、大人でも感染し、治りにくくなることがあります。
お子さんの水いぼの処置をする際は、念のため、処置後に流水と石鹸でしっかりと手洗いしましょう。
- 水いぼに効く市販薬はありますか?
-
現在、水いぼの原因である伝染性軟属腫ウイルスそのものに直接効く、と国から承認された市販の塗り薬や飲み薬はありません。
いぼ(尋常性疣贅)に使う市販薬(サリチル酸など)を自己判断で水いぼに使うと、正常な皮膚を傷つけてしまい、かえってウイルスを広げてしまう危険性があるので、絶対にやめましょう。
また、ハトムギエキス(ヨクイニン)を含む健康食品やサプリメントもありますが、効果は非常に緩やかで、医学的に確実性が証明されているわけではありません。
以上
参考文献
Robinson G, Townsend S, Jahnke MN. Molluscum contagiosum: review and update on clinical presentation, diagnosis, risk, prevention, and treatment. Current Dermatology Reports. 2020 Mar;9(1):83-92.
Leung AK, Barankin B, Hon KL. Molluscum contagiosum: an update. Recent patents on inflammation & allergy drug discovery. 2017 May 1;11(1):22-31.
Watanabe T, Nakamura K, Wakugawa M, Kato A, Nagai Y, Shioda T, Iwamoto A, Tamaki K. Antibodies to molluscum contagiosum virus in the general population and susceptible patients. Archives of dermatology. 2000 Dec 1;136(12):1518-22.
Chen X, Anstey AV, Bugert JJ. Molluscum contagiosum virus infection. The lancet infectious diseases. 2013 Oct 1;13(10):877-88.
Keyes A. MOLLUSCUM CONTAGIOSUM. Moschella and Hurley’s Dermatology. 2019 Jun 30;1:1165.
Silverberg NB. Pediatric molluscum contagiosum: optimal treatment strategies. Pediatric Drugs. 2003 Aug;5(8):505-11.
Skerlev M, Husar K, Sirotković-Skerlev M. Molluscum contagiosum. Der Hautarzt. 2009 Jun;60(6):472-6.
Montyn Lücher NE, Okoh UJ, Silverberg NB. Systematic Review of the Epidemiology and Risk Factors for Nonsexual Transmission of Warts and Molluscum in Children. Pediatric Dermatology. 2025.
Watanabe T, Morikawa S, Suzuki K, Miyamura T, Tamaki K, Ueda Y. Two major antigenic polypeptides of molluscum contagiosum virus. Journal of Infectious Diseases. 1998 Feb 1;177(2):284-92.
Takci Z, Karatas A, Bas Y, Tekin O, KALKAN G, Seckin H, Akbayrak A, Sezgin S, Demir O, Takci S. Demographic and clinic characteristics and risk factors of molluscum contagiosum in children. Journal of the Pakistan Medical Association. 2022;72(12).