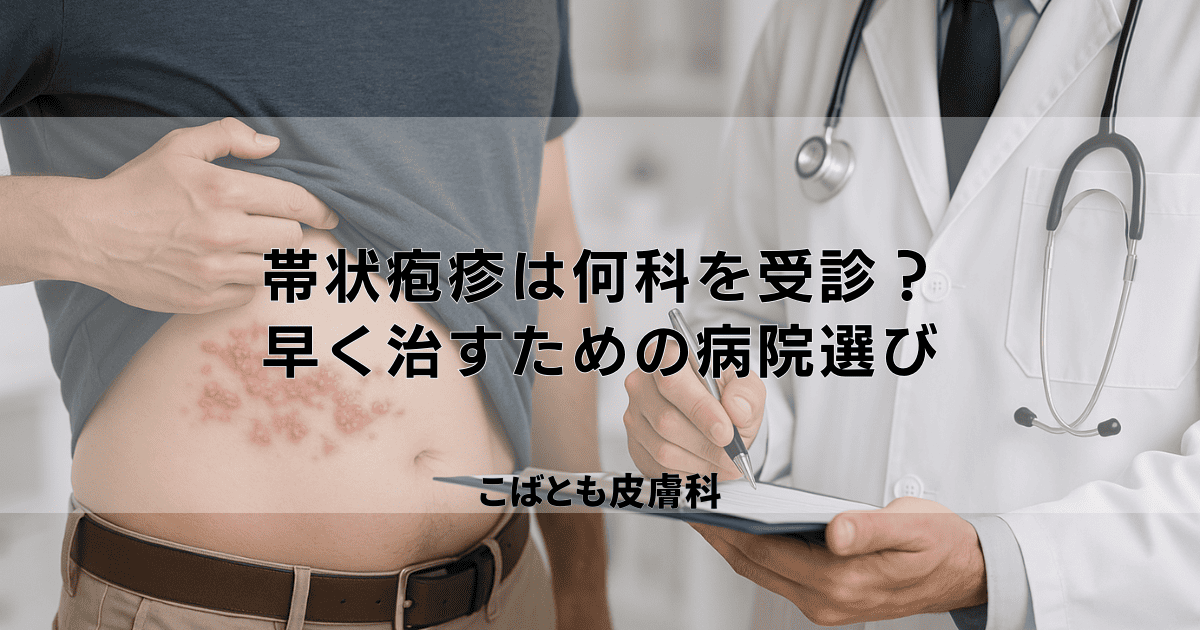体の片側にピリピリとした痛みを感じ、しばらくして赤い発疹や水ぶくれが現れたら、それは帯状疱疹かもしれません。
帯状疱疹は、治療の開始が遅れると、つらい痛みが長く続く帯状疱疹後神経痛という後遺症を残すことがあるので、症状に気づいたら一日でも早く適切な医療機関を受診することが重要です。
しかし、いざという時、皮膚の症状だから皮膚科なのか、体の痛みだから内科なのか、何科に行けば良いのか迷う方も少なくありません。
この記事では、帯状疱疹の基本的な知識から、なぜ早期受診が大切なのか、そして何科を選ぶべきかという疑問に、分かりやすくお答えします。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
まず知っておきたい帯状疱疹の基本
何科を受診するかを考える前に、まずは帯状疱疹がどのような病気なのかを正しく理解することが大切です。原因や特徴的な症状を知ることで、自身の状態を把握し、迅速な行動につなげることができます。
帯状疱疹とはどんな病気か
帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルスというウイルスによって引き起こされる皮膚の病気で、多くの人が子供の頃にかかる水ぼうそう(水痘)と同じウイルスが原因です。
水ぼうそうが治った後も、このウイルスは体内の神経節という場所に静かに潜伏しています。
そして、加齢や疲労、ストレスなどによって体の免疫力が低下したときに、ウイルスが再び活性化して神経を伝って皮膚に到達し、帯状疱疹として発症します。
特徴的なのは、体の左右どちらか一方の神経に沿って、帯状に痛みや皮膚症状が現れることです。
体の中心線を越えて症状が広がることはほとんどなく、胸から背中、腹部、顔、腕、足など、神経が通っている場所ならどこにでも発症する可能性があります。
帯状疱疹の典型的な症状
帯状疱疹の症状は、時間とともに変化していくのが一般的で、まず最初に現れるのは、皮膚の痛みです。
チクチク、ピリピリ、ズキズキといった、神経痛のような痛みが体の片側に生じますが、この段階ではまだ発疹がないため、筋肉痛や内臓の病気などと間違われることもあります。
痛みが出てから数日経つと、同じ場所に赤い発疹が現れ、その後、発疹は小さな水ぶくれに変化し、中央にくぼみが見られるようになります。
水ぶくれは数日間で膿を持つようになり、やがて破れてただれた状態(びらん)になった後、かさぶたとなって治癒していきます。
皮膚症状が治るまでには、通常3週間から1ヶ月程度かかり、発熱や頭痛、リンパ節の腫れなどを伴うこともあります。
症状の経過
| 時期 | 主な症状 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 初期 | 体の片側の痛み、違和感、かゆみ | 発疹出現の数日前~1週間前 |
| 中期 | 帯状の赤い発疹、小さな水ぶくれ | 発症後~約1週間 |
| 後期 | 水ぶくれが膿疱化、びらん、かさぶた | 発症後1~3週間 |
水ぼうそうとの関係
前述の通り、帯状疱疹と水ぼうそうは、同じ水痘・帯状疱疹ウイルスが原因です。初めてこのウイルスに感染したときには水ぼうそうとして発症し、水ぼうそうが治癒した後、ウイルスは体から消えるわけではなく、神経節に潜伏し続けます。
そして、何十年も経ってから、免疫力が低下したタイミングで潜伏していたウイルスが再活性化するのが帯状疱疹です。つまり、過去に水ぼうそうにかかったことがある人なら、誰でも帯状疱疹になる可能性があります。
日本人成人の90%以上がこのウイルスを体内に持っているとされ、80歳までに約3人に1人が発症するといわれています。一度帯状疱疹になっても、免疫力が低下すれば再発することもあります。
帯状疱疹の受診は何科が適切か
帯状疱疹を疑ったとき、最も重要なのは迅速に医療機関を受診することです。しかし、皮膚科、内科、ペインクリニックなど、いくつかの選択肢があり、どこへ行けば良いのか迷うかもしれません。
それぞれの診療科の役割と、なぜ皮膚科が第一選択となるのかを解説します。
第一選択は皮膚科
帯状疱疹の診断と治療において、最も中心的な役割を担うのは皮膚科です。帯状疱疹の診断は、特徴的な皮膚症状、体の片側に帯状に広がる赤い発疹や水ぶくれを見て判断することが基本となります。
皮膚科医は、このような皮膚症状を診る専門家であり、帯状疱疹と似た症状を示す他の皮膚疾患(単純ヘルペス、接触皮膚炎、虫刺されなど)との鑑別を正確に行うことができます。
また、治療の主体となる抗ウイルス薬の処方に加え、水ぶくれやびらんに対する外用薬の処置、かゆみ止めの処方など、皮膚症状全般に対する専門的なケアが可能です。
痛みと皮膚症状の両方を総合的に診察し、適切な初期治療を開始できるため、帯状疱疹を疑ったら、まずは皮膚科を受診してください。
皮膚科を受診するメリット
- 正確な診断
- 他の皮膚疾患との鑑別
- 適切な初期治療の開始
- 皮膚症状への専門的処置
内科でも受診は可能か
もちろん、内科でも帯状疱疹の診断と治療は可能です。特に、発疹が現れる前の痛みだけの時期や、発熱や頭痛などの全身症状が強い場合には、かかりつけの内科を受診する方も多いでしょう。
内科医も帯状疱疹に関する知識を持っており、抗ウイルス薬の処方など、基本的な治療を行うことができます。
ただし、皮膚症状が非典型的であったり、診断に迷うようなケースでは、最終的に皮膚科への紹介となることもあります。また、水ぶくれが破れた後の皮膚の処置など、専門的なスキンケアについては皮膚科の方がより手厚い対応を期待できます。
近くに皮膚科がない場合や、まずはかかりつけ医に相談したいという場合には、内科を受診するのも一つの選択肢です。
診療科別の主な役割
| 診療科 | 主な役割と特徴 |
|---|---|
| 皮膚科 | 皮膚症状の正確な診断と治療が中心。第一選択。 |
| 内科 | 全身症状を含めた診断と初期治療。かかりつけ医として相談しやすい。 |
| ペインクリニック | 痛みの管理に特化。特に帯状疱疹後神経痛の治療で重要。 |
痛みが強い場合はペインクリニックも選択肢に
帯状疱疹の治療で特に問題となるのが痛みです。急性期の激しい痛みや、皮膚症状が治った後も続く帯状疱疹後神経痛に悩まされるケースは少なくありません。このような痛みの管理を専門に行うのがペインクリニック(麻酔科)です。
ペインクリニックでは、内服薬の調整だけでなく、神経ブロック注射という専門的な治療法を用いて、痛みを効果的に和らげることができます。
神経ブロック注射は、痛みの原因となっている神経の近くに局所麻酔薬などを注射することで、痛みの伝達を遮断する治療法です。急性期の強い痛みを抑えることは、帯状疱疹後神経痛への移行を防ぐ上でも重要と考えられています。
皮膚科や内科での治療と並行して、痛みのコントロールのためにペインクリニックを受診することも有効な選択肢です。
なぜ早期受診が重要なのか
帯状疱疹の治療において、専門家が口を揃えて強調するのが早期発見・早期治療です。なぜそれほどまでに早く病院へ行くことが大切なのでしょうか。
抗ウイルス薬の効果を最大化するため
帯状疱疹の治療の中心となるのは、ウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬です。この薬は、体内でウイルスが増えるのを防ぐことで、皮膚症状の悪化を食い止め、治癒までの期間を短縮し、痛みを軽減する効果があります。
しかし、この抗ウイルス薬の効果が最も高いのは、ウイルスが活発に増殖している発症初期です。
皮膚に発疹が現れてから72時間(3日)以内に内服を開始することが最も効果的とされ、この時間を過ぎてしまうと、薬の効果が十分に得られにくくなり、症状が重症化したり、治るまでに時間がかかったりする可能性が高まります。
受診のタイミングと治療効果
| 受診タイミング | 期待される効果 |
|---|---|
| 発疹出現後72時間以内 | 抗ウイルス薬の効果が最大化され、重症化や後遺症のリスクを低減 |
| 発疹出現後72時間以降 | 効果は低下するが、治療しないよりは重症化を防ぐ効果が期待できる |
帯状疱疹後神経痛(PHN)のリスクを減らす
帯状疱疹で最も避けたい合併症が、帯状疱疹後神経痛(PHN: Postherpetic Neuralgia)で、これは、皮膚の症状が治った後も、焼けるような、あるいは電気が走るような、つらい痛みが数ヶ月から数年にわたって続く状態です。
PHNは、帯状疱疹の急性期にウイルスによって神経が深く傷つけられることが原因で起こります。治療の開始が遅れてウイルスの増殖を許してしまうと、神経へのダメージが大きくなり、PHNへ移行するリスクが高まります。
特に高齢者や、初期の痛みが激しかった人、皮膚症状が重かった人はPHNになりやすいとされています。
早期に抗ウイルス薬でウイルスの活動を抑え、神経へのダメージを最小限に食い止めることが、つらい後遺症を防ぐための最も重要な鍵です。
合併症の予防
帯状疱疹は、発症する部位によっては重い合併症を起こすことがあり、特に注意が必要なのが、顔面に発症した場合です。
三叉神経の第一枝である眼神経領域(額から目にかけて)に発症すると、ウイルスが目にも影響を及ぼし、結膜炎や角膜炎、ぶどう膜炎などを起こし、視力低下や失明に至る危険性もあります。
また、顔面神経や聴神経の領域に発症した場合は、顔面神経麻痺(ラムゼイ・ハント症候群)や、めまい、難聴、耳鳴りなどの症状が現れることがあります。合併症は、いずれも早期の適切な治療が予後を改善するために重要です。
顔に症状が出た場合は、ためらわずに直ちに皮膚科や眼科、耳鼻咽喉科などの専門医を受診してください。
注意すべき合併症
- 帯状疱疹後神経痛 (PHN)
- 眼合併症(角膜炎、ぶどう膜炎など)
- ラムゼイ・ハント症候群(顔面神経麻痺、難聴、めまい)
- 運動麻痺
病院を受診する前の準備
いざ病院へ行くと、緊張してしまい、聞きたいことや伝えたいことを忘れてしまうことがあります。限られた診察時間の中で、医師に正確な情報を伝え、的確な診断と治療を受けるために、事前にいくつかの点を整理しておくとスムーズです。
症状の経過をメモしておく
医師が診断を下す上で、症状がどのように始まったか、どのように変化したかという情報は非常に重要です。以下の項目について、簡単なメモを作成しておくと、正確に伝えることができます。
- いつから痛みや違和感があるか
- どの部位に最初に症状が出たか
- 痛みはどのような性質か(ピリピリ、ズキズキなど)
- いつから発疹が出たか
- 発疹はどのように変化したか(赤み→水ぶくれなど)
- 他に気になる症状(発熱、頭痛、だるさなど)はあるか
スマートフォンで症状が出ている部分の写真を撮っておくのも良い方法です。受診するまでに症状が変化した場合、初期の状態を医師に見せることで診断の助けになります。
服用中の薬や持病を伝える
帯状疱疹の治療薬と、普段服用している薬との飲み合わせ(相互作用)が問題になることがあり、また、持病によっては、使用できる薬に制限がある場合もあります。
特に、腎臓の機能が低下している方では、抗ウイルス薬の量を調整する必要があります。
現在服用しているすべての薬(処方薬、市販薬、サプリメントを含む)がわかるように、お薬手帳を持参するか、薬そのものを持っていくようにしましょう。
また、過去にかかった大きな病気や、現在治療中の持病(高血圧、糖尿病、腎臓病、膠原病など)についても、正確に医師に伝えてください。
医師に伝えるべき情報
| 項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 症状の経過 | いつから、どこに、どのような症状が、どう変化したか |
| 既往歴 | 過去にかかった水ぼうそうの時期、大きな病気、手術歴など |
| 服用中の薬 | 処方薬、市販薬、サプリメントなど(お薬手帳の持参が望ましい) |
| アレルギー歴 | 薬や食べ物のアレルギーの有無 |
質問したいことをまとめておく
診察後になって、あれを聞いておけばよかったと後悔しないように、事前に質問したいことをリストアップしておきましょう。病気に対する不安や、治療、日常生活での注意点など、疑問に思うことは遠慮なく質問することが大切です。
治療期間の目安、薬の副作用、仕事や学校を休む必要性、入浴の可否、他の人にうつす可能性、食事で気をつけることなど、具体的に聞いておきたいことをメモしておくと、聞き忘れを防ぐことができます。
医師との良好な関係は、安心して治療を進める上で大事な要素です。
帯状疱疹の治療法
医療機関では、診断が確定すると速やかに治療が開始されます。治療の三本柱は、ウイルスの増殖を抑えること、炎症や痛みを和らげること、そして皮膚症状を適切に処置することです。
抗ウイルス薬による治療
帯状疱疹治療の根幹をなすのが抗ウイルス薬です。この薬は、水痘・帯状疱疹ウイルスのDNA複製を阻害することで、ウイルスの増殖を抑えます。
新たな発疹の出現を防ぎ、皮膚症状の治癒を早め、急性期の痛みを軽減し、最も重要な目的である帯状疱疹後神経痛への移行リスクを低減させます。
アシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルといった内服薬が主に用いられ、通常の服用期間は7日間です。腎機能が低下している方や高齢者では、薬の種類や量を調整する必要があります。
症状が非常に重い場合や、免疫力が著しく低下している場合、合併症のリスクが高い場合には、入院して抗ウイルス薬の点滴治療を行うこともあります。
主な抗ウイルス内服薬
| 薬剤名(一般名) | 特徴 |
|---|---|
| アシクロビル | 古くから使用されている標準的な薬剤。1日5回の服用が必要。 |
| バラシクロビル | 体内でアシクロビルに変化。吸収が良く、1日3回の服用で済む。 |
| ファムシクロビル | 体内でペンシクロビルに変化。1日3回の服用で済む。 |
痛みに対する治療(鎮痛薬)
帯状疱疹の痛みは非常に強く、日常生活に大きな支障をきたすことがあるため、抗ウイルス薬による根本的な治療と並行して、痛みそのものをコントロールする治療も重要です。
痛みの強さに応じて、様々な種類の鎮痛薬を使い分けます。比較的軽い痛みには、アセトアミノフェンや、ロキソプロフェンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が用いられます。
これらの薬で効果が不十分な場合には、神経の興奮を鎮める作用のあるプレガバリンやミロガバリン、あるいはうつ病の治療にも使われる神経障害性疼痛治療薬などが処方されます。
痛みのコントロールは、急性期のQOL(生活の質)を保つだけでなく、帯状疱疹後神経痛への移行を防ぐ上でも大切です。
皮膚症状に対する外用薬
水ぶくれやびらんといった皮膚症状に対しては、状態に応じた外用薬(塗り薬)が処方されます。これは、患部の保護、細菌による二次感染の予防、そして治癒の促進が目的です。
初期の赤い発疹や小さな水ぶくれの段階では、炎症を抑える目的で非ステロイド系の抗炎症薬や、亜鉛華軟膏などが用いられます。水ぶくれが破れてびらんになったり、細菌感染が疑われたりする場合には、抗生物質を含んだ軟膏が処方されます。
自己判断で市販の薬を塗ると、かえって症状を悪化させることがあるため、必ず医師から処方された薬を指示通りに使用してください。
治療中の日常生活の注意点
薬による治療と合わせて、日常生活での過ごし方も症状の回復を大きく左右します。体を休め、適切なセルフケアを行うことで、治癒を早め、合併症のリスクを減らすことができます。
安静と休養を第一に
帯状疱疹は、体の免疫力が低下しているサインです。治療中は無理をせず、十分な休息と睡眠をとることが何よりも大切です。仕事や家事、学業なども、可能な範囲で休みをとるか、負担を減らすように調整しましょう。
疲労やストレスは免疫力をさらに低下させ、症状の悪化や治癒の遅れにつながります。心身ともにリラックスできる環境を整え、体の回復に専念することが、結果的に早く社会復帰できます。
患部のケアと入浴
患部は清潔に保つことが基本ですが、水ぶくれはなるべく破らないように注意が必要です。水ぶくれが破れると、細菌感染のリスクが高まります。医師の指示がない限り、水ぶくれを自分で潰したり、かさぶたを無理に剥がしたりしないでください。
入浴については、症状が軽い場合はシャワーを浴びても構いません。ただし、熱いお湯は避け、患部を石鹸でゴシゴシこすらないでください。優しく洗い流した後は、清潔なタオルで軽く押さえるように水分を拭き取ります。
痛みが強い場合や、全身状態が良くない場合は、無理に入浴せず、体を拭く程度に留めておきましょう。
患部のケアのポイント
| 項目 | 注意点 |
|---|---|
| 保護 | 水ぶくれを破らない。かさぶたを剥がさない。 |
| 清潔 | 優しく洗い、清潔に保つ。 |
| 衣類 | ゆったりとした、肌触りの良い素材を選ぶ。 |
他の人への感染について
帯状疱疹として、他の人にうつることはありません。
ただし、帯状疱疹の原因である水痘・帯状疱疹ウイルスは、水ぶくれの中に大量に含まれているため、まだ水ぼうそうにかかったことのない人(特に乳幼児や妊婦)が、水ぶくれの内容物に触れると、水ぼうそうとして感染する可能性があります。
水ぶくれがすべてかさぶたになるまでは、水ぼうそうにかかったことのない人との接触は避けましょう。患者本人が使ったタオルや衣類を分けたり、こまめに手洗いをしたりすることも大切です。
感染対策のまとめ
- 水ぼうそう未罹患の人との接触を避ける
- 患部をガーゼなどで覆う
- タオルや衣類の共用を避ける
- こまめな手洗い
食事と栄養
特定の食べ物が帯状疱疹を治すわけではありませんが、免疫力をサポートし、体の回復を助けるために、栄養バランスの取れた食事を心がけることは重要です。
特に、皮膚や粘膜の健康を保つビタミンA、C、Eや、エネルギー代謝を助けるビタミンB群、そして体の組織を作るもとになるタンパク質を積極的に摂取しましょう。
口の中に症状が出ている場合は、おかゆやスープなど、刺激が少なく、のどごしの良いものが食べやすいです。食欲がない時でも、水分だけはこまめに補給してください。
免疫力アップに役立つ栄養素
| 栄養素 | 多く含まれる食品 |
|---|---|
| タンパク質 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| ビタミンA/C/E | 緑黄色野菜、果物、ナッツ類 |
| ビタミンB群 | 豚肉、レバー、うなぎ、玄米 |
よくある質問 (Q&A)
最後に、帯状疱疹の受診や治療に関して、患者さんからよくいただく質問と回答をまとめました。
- 夜間や休日に発症したらどうすれば良いですか?
-
帯状疱疹は一刻も早い治療開始が望ましい病気です。もし夜間や休日に症状に気づき、痛みが強い場合や、顔に症状が出ている場合は、地域の救急外来や休日夜間診療所を受診することを検討してください。
そこで初期対応をしてもらい、翌日以降、改めて皮膚科を受診するのが良いでしょう。
痛みがそれほど強くなく、全身状態も良好であれば、翌日の診療時間まで待って皮膚科を受診しても問題ない場合が多いですが、迷った場合は電話で相談できる救急相談窓口などを利用するのも一つの方法です。
- 診断のために血液検査は必要ですか?
-
ほとんどの帯状疱疹は、特徴的な皮膚症状から視診だけで診断が可能ですが、発疹が非典型的であったり、診断に迷ったりする場合には、診断を確定させるために血液検査を行うことがあります。
血液検査では、水痘・帯状疱疹ウイルスに対する抗体の量を調べることで、最近ウイルスが再活性化したかどうかを確認することが可能です。
ただし、結果が出るまでに数日かかるため、多くの場合は検査結果を待たずに、臨床症状から判断して治療を開始します。
- 帯状疱疹は予防できますか?
-
帯状疱疹は、日頃からバランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけ、免疫力を落とさない生活を送ることが基本的な予防策となります。
それに加えて、より積極的な予防法として、50歳以上の方を対象とした帯状疱疹ワクチンがあります。
ワクチンを接種することで、帯状疱疹の発症を完全に防ぐことはできませんが、発症率を大幅に下げ、もし発症しても症状が軽く済んだり、帯状疱疹後神経痛への移行を予防したりする効果が期待できます。
ワクチンには2種類あり、それぞれ特徴が異なるため、接種を希望する場合は医師に相談してください。
帯状疱疹ワクチンの種類
種類 接種回数 特徴 生ワクチン 1回 従来からあるワクチン。費用が比較的安い。 不活化ワクチン 2回 予防効果が高い。免疫力が低下した人にも接種可能。
以上
参考文献
Takanashi S, Ohmura K, Misaki K, Ihata A, Matsui T, Tohma S, Saegusa J, Sato S, Matsubara T, Yamaoka K, Amano K. Optimal timing of recombinant herpes zoster virus vaccination for a JAK inhibitor treatment in rheumatoid arthritis: a multicentre, open-label, randomised comparative study (STOP-HZ study): study protocol. BMJ open. 2024 Nov 1;14(11):e090668.
Ishikawa Y, Nakano K, Tokutsu K, Nakayamada S, Matsuda S, Fushimi K, Tanaka Y. Short-term prognostic factors in hospitalized herpes zoster patients and its associated cerebro-cardiovascular events: a nationwide retrospective cohort in Japan. Frontiers in Medicine. 2022 Mar 4;9:843809.
Watanabe D, Mizukami A, Holl K, Curran D, Van Oorschot D, Varghese L, Shiragami M. The potential public health impact of herpes zoster vaccination of people aged≥ 50 years in Japan: results of a Markov model analysis. Dermatology and Therapy. 2018 Jun;8(2):269-84.
Hashizume H, Nakatani E, Sato Y, Goto H, Yagi H, Miyachi Y. A new susceptibility index to predict the risk of severe herpes zoster-associated pain: a Japanese regional population-based cohort study, the Shizuoka study. Journal of Dermatological Science. 2022 Mar 1;105(3):170-5.
Hoshi SL, Seposo X, Shono A, Okubo I, Kondo M. Cost-effectiveness of Recombinant Zoster Vaccine (RZV) and Varicella Vaccine Live (VVL) against herpes zoster and post-herpetic neuralgia among adults aged 65 and over in Japan. Vaccine. 2019 Jun 12;37(27):3588-97.
Asada H. Recent topics in the management of herpes zoster. The Journal of dermatology. 2023 Mar;50(3):305-10.
Shiraki K, Toyama N, Daikoku T, Yajima M, Miyazaki Dermatologist Society. Herpes zoster and recurrent herpes zoster. InOpen Forum Infectious Diseases 2017 (Vol. 4, No. 1, p. ofx007). US: Oxford University Press.
Kawaguchi K, Inamura H, Abe Y, Koshu H, Takashita E, Muraki Y, Matsuzaki Y, Nishimura H, Ishikawa H, Fukao A, Hongo S. Reactivation of herpes simplex virus type 1 and varicella‐zoster virus and therapeutic effects of combination therapy with prednisolone and valacyclovir in patients with Bell’s palsy. The Laryngoscope. 2007 Jan;117(1):147-56.
Kawai K, Gebremeskel BG, Acosta CJ. Systematic review of incidence and complications of herpes zoster: towards a global perspective. BMJ open. 2014 Jun 1;4(6):e004833.
Koshy E, Mengting L, Kumar H, Jianbo W. Epidemiology, treatment and prevention of herpes zoster: a comprehensive review. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology. 2018 May 1;84:251.