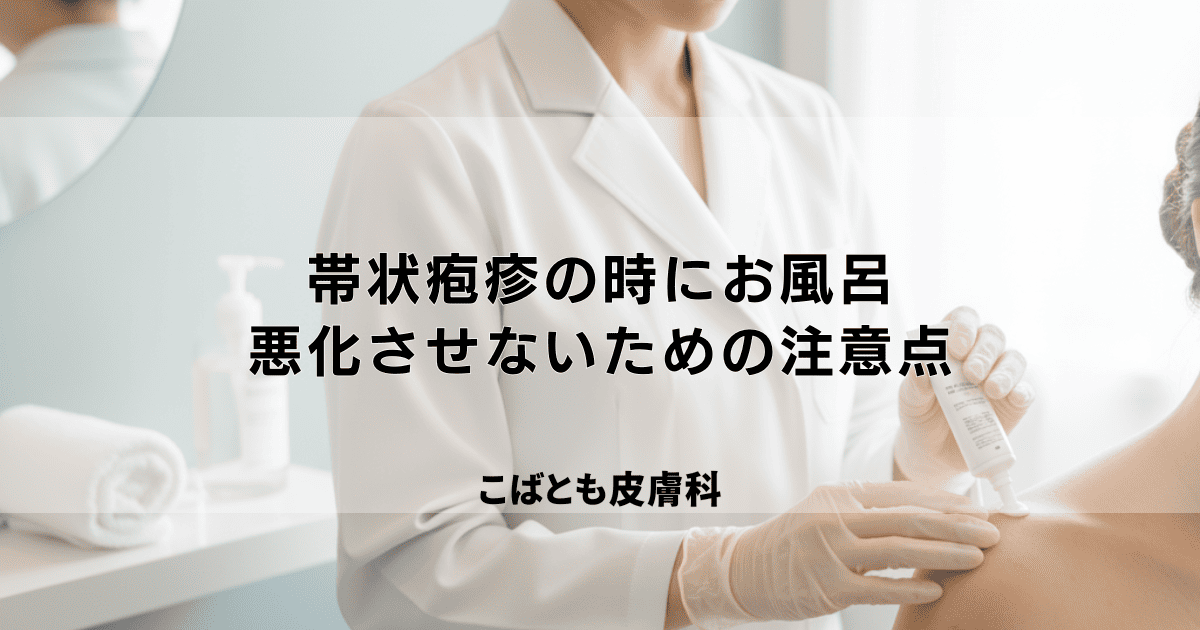ある日突然、体の片側にピリピリとした痛みを感じ、しばらくすると赤い発疹や水ぶくれが現れる症状は、帯状疱疹のサインかもしれません。
診断を受けた後、治療とともに気になるのが日々の生活習慣、特に毎日のお風呂ではないでしょうか。
汗を流してさっぱりしたいけれど、症状を悪化させてしまわないか、水ぶくれが破れたらどうしよう、家族にうつしてしまわないか、といった不安が頭をよぎるかもしれません。
この記事では、帯状疱疹と診断された方が抱える入浴に関する疑問や不安を解消し、安心して体を清潔に保つための方法と注意点を詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
そもそも帯状疱疹とはどんな病気?
帯状疱疹の症状に悩まされ、入浴について考える前に、まずはこの病気について正しく理解することが大切です。どのような原因で発症し、どのような症状が現れるのかを知ることが、適切な対処法の第一歩となります。
原因は水ぼうそうのウイルス
帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルスというウイルスが原因で起こり、多くの方が子どもの頃にかかる水ぼうそうも、同じウイルスが原因です。水ぼうそうが治った後も、このウイルスは体内の神経節と呼ばれる場所に静かに潜伏し続けます。
そして、加齢やストレス、過労、病気などが引き金となり、体の免疫力が低下した時に、潜んでいたウイルスが再び活動を始めます。再活性化したウイルスは、神経を伝って皮膚に到達し、そこで炎症を起こして帯状疱疹として発症します。
過去に水ぼうそうにかかったことがある人なら、誰でも帯状疱疹になる可能性があり、日本人では50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症するといわれています。
体の片側に現れる痛みを伴う発疹
帯状疱疹の症状は特徴的で、多くの場合、まず皮膚にピリピリ、チクチク、ズキズキといった神経痛のような痛みが現れます。
痛みは、発疹が出る数日前から1週間ほど前から感じることがあり、初期段階では原因が分からず、筋肉痛や内臓の病気と勘違いすることもあり、その後、痛みのあった場所に帯状のように赤い発疹が現れ、次第に小さな水ぶくれに変化します。
発疹や水ぶくれは、体の左右どちらか片側の神経の支配領域に沿って現れるのが大きな特徴です。
胸から背中、腹部、顔、腕、足など、体のどこにでも発症する可能性があり、発疹は通常、2週間から4週間ほどでかさぶたになり、自然に治癒していきます。
帯状疱疹の主な症状の経過
| 時期 | 主な症状 | 注意点 |
|---|---|---|
| 初期(発疹前) | 皮膚の違和感、ピリピリ・チクチクする痛み、かゆみ | 原因が分かりにくく、他の病気と間違えやすい |
| 急性期(発疹・水ぶくれ) | 体の片側に帯状の赤い発疹、痛みを伴う水ぶくれ | 水ぶくれを破らないように注意が必要 |
| 回復期(かさぶた) | 水ぶくれが乾燥し、かさぶたになる | 無理に剥がさず、自然に取れるのを待つ |
帯状疱疹がうつる可能性について
帯状疱疹そのものが、空気感染などで他の人にうつることはありませんが、注意が必要です。帯状疱疹の原因である水痘・帯状疱疹ウイルスは、水ぶくれの中に大量に含まれています。
このため、まだ水ぼうそうにかかったことがない人や、水ぼうそうの予防接種を受けていない人が、水ぶくれに直接触れると、水ぼうそうとして感染する可能性があります。
特に、免疫力が未熟な赤ちゃんや、妊婦さん、免疫力が低下している方が周りにいる場合は、慎重な対応が必要です。水ぶくれがすべてかさぶたになれば、ウイルスの排出はなくなり、感染の心配はなくなります。
家族にうつさないためにも、正しい知識を持つことが重要で、入浴時だけでなく、普段の生活でも患部をガーゼなどで保護し、タオルの共用を避けるなどの配慮をしましょう。
帯状疱疹の時にお風呂に入っても大丈夫?
体の清潔を保つことは、皮膚の感染症を防ぐ上でとても重要ですが、帯状疱疹の時にむやみに入浴すると、かえって症状を悪化させる危険性もあります。ここでは、入浴の可否を判断する基準や、どのような場合に注意が必要かについて解説します。
基本的には入浴可能
帯状疱疹の症状が比較的軽く、全身の状態が良い場合は、お風呂に入っても問題ありません。入浴によって皮膚を清潔に保つことは、水ぶくれが破れた後の細菌による二次感染を防ぐために推奨されます。
また、体を温めることで血行が良くなり、痛みが一時的に和らぐと感じる方もいます。ただし、これはあくまでも一般的な話であり、症状の程度や体の状態によって判断は異なり、大切なのは、自分の体調をよく観察し、無理をしないことです。
入浴を避けるべきタイミング
症状によっては、一時的に入浴を控えた方が良い場合があり、体を清潔に保つことよりも、症状の悪化を防ぐことを優先すべき状況を理解しておきましょう。
発熱や頭痛、倦怠感など、全身に症状が出ている時は、体力を消耗させる入浴は避けるべきで、この時期は安静が第一です。
また、水ぶくれが広範囲に広がっている、あるいは痛みが非常に強い場合も、入浴による刺激が症状を悪化させる可能性があります。
水ぶくれが破れて、じゅくじゅくした状態(びらん)になっている時も、細菌感染のリスクが高まるため、シャワーで優しく洗い流す程度にとどめるか、医師の指示に従うのが賢明です。
入浴を控えるべき症状のチェック
| チェック項目 | 該当する場合の対応 | 理由 |
|---|---|---|
| 37.5度以上の発熱がある | 入浴を中止し、安静にする | 体力の消耗を避け、回復に専念するため |
| 強い倦怠感や頭痛がある | 入浴を中止し、安静にする | 全身症状が悪化する可能性があるため |
| 痛みが非常に強く、動くのがつらい | 無理に入浴せず、医師に相談する | 入浴による刺激で痛みが増すことがあるため |
医師に相談が必要なケース
自己判断で入浴を続けてよいか不安な場合は、ためらわずに専門医に相談してください。特に、顔や頭部に帯状疱疹ができた場合は注意が必要です。
目の角膜や聴神経にウイルスが影響を及ぼし、視力障害や顔面神経麻痺、難聴といった重篤な合併症を起こすことがあるので、入浴に関しても医師の専門的な指示を仰ぐことが大切です。
また、糖尿病などの持病がある方や、免疫を抑制する薬を服用している方も、感染症のリスクが高いため、入浴方法について医師や看護師に確認してください。
自己判断が症状の悪化や合併症につながることもあるため、少しでもおかしいと感じたら、かかりつけの皮膚科医に相談しましょう。
医師への相談が特に推奨される兆候
- 発疹が顔、目、耳の周りにできた
- 発疹が広範囲に広がってきた
- 痛みが我慢できないほど強い
- 発熱や頭痛が続く
- 水ぶくれが破れて化膿した
症状を悪化させないための正しい入浴法
帯状疱疹の時に安心して入浴するためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。お湯の温度から体の洗い方、入浴後のケアまで、患部に負担をかけず、かつ清潔を保つための方法を見ていきましょう。
お湯の温度と長湯は避ける
帯状疱疹の患部にとって熱いお湯や長時間の入浴は強い刺激となり、熱すぎるお湯は血行を促進しすぎ、かゆみや痛みを増強させることがあります。
また、長湯は体力を消耗させるだけでなく、皮膚の乾燥を招き、バリア機能の低下につながる可能性もあります。お湯の温度は、38〜40度程度のぬるめに設定するのがおすすめです。
ぬるめのお湯に短時間浸かることで、心身ともにリラックスでき、血行も穏やかに促進されます。入浴時間は10分程度を目安にし、体が温まりすぎないように注意しましょう。
あくまでも体を清潔にすることが目的であり、リラックスのための長湯は症状が落ち着いてからにしてください。
適切な入浴温度と時間の目安
| 項目 | 推奨 | 避けるべきこと |
|---|---|---|
| お湯の温度 | 38〜40度のぬるま湯 | 41度以上の熱いお湯 |
| 入浴時間 | 10分程度の短時間 | 20分以上の長湯 |
| 入浴の目的 | 皮膚の清浄、血行促進 | 過度な発汗、体力の消耗 |
体の洗い方のポイント
入浴時に最も注意したいのが、体の洗い方で、水ぶくれを破らないように、患部を優しく扱うことが何よりも重要です。体を洗う際は、ナイロンタオルやスポンジでゴシゴシこするのは絶対にやめてください。
摩擦によって水ぶくれが破れると、細菌感染のリスクが高まるだけでなく、治りが遅くなったり、跡が残りやすくなったりします。石鹸やボディソープは、低刺激性のものを選び、手でよく泡立ててから、泡でなでるように優しく洗いましょう。
泡がクッションとなり、皮膚への直接的な刺激を和らげ、患部は特に慎重に、泡を乗せる程度で十分です。洗い流す時も、シャワーの水圧を弱めに設定し、直接患部に当てないように注意しながら、ぬるま湯でそっと流してください。
体の洗い方のOK例とNG例
| 項目 | OK例 | NG例 |
|---|---|---|
| 洗浄料 | 低刺激性の石鹸やボディソープをよく泡立てる | 洗浄力の強い石鹸、スクラブ入り製品 |
| 洗い方 | 手のひらや指の腹で、泡でなでるように優しく洗う | ナイロンタオルやブラシでゴシゴシこする |
| すすぎ方 | 弱めの水圧のシャワーで、そっと洗い流す | 強い水圧のシャワーを患部に直接当てる |
入浴剤の使用について
リラックス効果を期待して入浴剤を使いたい方もいるかもしれませんが、帯状疱疹の症状が出ている間は、使用を控えるのが無難です。
入浴剤に含まれる香料や色素、その他の化学成分が、敏感になっている患部を刺激し、かゆみや炎症を悪化させる可能性があります。
硫黄成分が含まれる温泉系の入浴剤や、メントールなどの清涼成分が入ったものは、強い刺激となることがあるため避けるべきです。
どうしても何か入れたい場合は、成分がシンプルなものや、保湿効果のある低刺激性のものを選ぶべきですが、基本的には何も入れない更湯(さらゆ)での入浴が最も安全です。
症状が完全に治癒し、皮膚の状態が安定してから、お気に入りの入浴剤を楽しみましょう。
入浴前後の準備とケア
入浴の効果を最大限に引き出し、トラブルを防ぐためには、入浴前後のケアも大切です。入浴前には、脱衣所を暖めておき、浴室との温度差を少なくしておきましょう。急激な温度変化は体に負担をかけ、痛みを誘発することがあります。
また、入浴後に使用するタオルや着替えも事前に準備しておくとスムーズです。入浴後は、体を拭く際にも注意が必要で、ゴシゴシこすらず、清潔で柔らかいタオルを肌に優しく押し当てるようにして水分を吸い取ります。
患部は慎重に、タオルで軽く押さえる程度にし、水分を拭き取った後は、皮膚が乾燥しないうちに、医師から処方された塗り薬を塗布します。その後、通気性の良い、ゆったりとした衣類を身につけて、皮膚への刺激を最小限に抑えましょう。
入浴後のケア用品
- 吸水性の高い柔らかいタオル
- 医師から処方された塗り薬
- 締め付けの少ないゆったりした衣類
- 保湿剤(医師の許可がある場合)
入浴時に注意すべきポイント
正しい入浴法を理解した上で、さらに注意すべき点がいくつかあり、ご自身の症状悪化を防ぐだけでなく、同居する家族への配慮にもつながる重要な事柄です。
水ぶくれを破らないようにする
繰り返しになりますが、水ぶくれを故意に破ったり、潰したりしないことが最も重要です。水ぶくれの中にはウイルスが大量に含まれており、破れるとそのウイルスが周囲の皮膚に広がり、症状を悪化させる原因となります。
また、水ぶくれが破れた箇所から細菌が侵入し、二次感染(化膿)を起こすリスクも高まり、二次感染を起こすと、痛みがさらに強くなるだけでなく、治癒が遅れ、皮膚に跡が残りやすくなることもあります。
入浴中はもちろん、着替えや就寝時など、日常生活のあらゆる場面で、患部を引っ掻いたり、強くこすったりしないように意識することが大切です。
かゆみが強い場合は、冷たいタオルで軽く冷やすと和らぐことがありますが、それでも我慢できない場合は医師に相談し、かゆみ止めの薬を処方してもらいましょう。
タオルの選び方と拭き方
入浴後に使用するタオルは、清潔で肌触りの良いものを選びましょう。新品のゴワゴワしたタオルよりも、使い慣れた柔らかい綿素材のものがおすすめです。
体を拭く際はタオルで皮膚をこするのではなく、優しく押し当てるようにして水分を吸収させます。この方法は「押さえ拭き」とも呼ばれ、皮膚への摩擦を最小限に抑えることができます。
患部とそれ以外の部分でタオルを使い分けるか、患部を最後に拭くようにすると、より衛生的です。使用後のタオルは、他の家族のものとは分けて洗濯してください。
同居家族への配慮
帯状疱疹は、水ぼうそうにかかったことのない人にウイルスをうつし、水ぼうそうを発症させる可能性があるため、同居している家族がいる場合は、いくつかの配慮が必要です。
まず、入浴の順番は最後にすることで、浴槽のお湯を介してウイルスが広がるリスクを減らすことができます。また、使用したタオルは共用せず、すぐに洗濯するように心掛けましょう。
患部に触れた手で、家のあちこちを触らないように注意することも大切です。水ぶくれがすべてかさぶたになれば、感染の心配はなくなりますが、それまではこうした細やかな配慮が家族を守ることにつながります。
家族への感染対策まとめ
| 対策 | 具体的な行動 | 目的 |
|---|---|---|
| 入浴の順番 | 家族の中で最後に入る | 浴槽のお湯を介した感染リスクの低減 |
| タオルの管理 | タオルの共用を避け、使用後はすぐに洗濯する | タオルを介した接触感染の防止 |
| 患部の保護 | 日中はガーゼなどで患部を覆っておく | 意図せず水ぶくれに触れる機会を減らす |
入浴以外の日常生活での注意点
帯状疱疹の根本的な原因は免疫力の低下なので、治療と並行して、免疫力を回復させるための生活習慣を心掛けることが、早期回復への鍵となります。入浴だけでなく、食事や睡眠、ストレス管理にも目を向けてみましょう。
安静と十分な睡眠
帯状疱疹の治療において、最も重要なことの一つが安静で、ウイルスと戦っている体は、普段以上にエネルギーを消耗しています。仕事や家事で無理をせず、できるだけ体を休める時間を作りましょう。
質の良い睡眠を十分にとることは、免疫細胞の働きを活発にし、体の回復力を高める上で欠かせません。痛みが強くて眠れない場合は、我慢せずに医師に相談し、適切な鎮痛薬を処方してもらうことが大切です。
眠る前はスマートフォンやテレビの使用を控え、部屋を暗くしてリラックスできる環境を整えるなど、安眠のための工夫を試してみるのも良いでしょう。
バランスの取れた食事
免疫力を高めるためには、栄養バランスの取れた食事が基本で、特定の食品だけを食べるのではなく、主食、主菜、副菜をそろえ、様々な食材から栄養を摂ることを意識しましょう。
皮膚や粘膜の健康を保つビタミンA、ビタミンB群、ビタミンCや、免疫細胞の材料となるタンパク質を積極的に摂取してください。
食事だけで十分な栄養を摂るのが難しい場合は、医師や管理栄養士に相談の上で、サプリメントなどを補助的に利用するのも一つの方法です。
ただし、刺激の強い香辛料やアルコール、過剰な糖分は、炎症を悪化させる可能性があるため、症状が落ち着くまでは控えることをおすすめします。
帯状疱疹の回復を助ける栄養素と食材例
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食材の例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 免疫細胞や皮膚の材料となる | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| ビタミンB群 | 神経の機能を正常に保つ | 豚肉、レバー、うなぎ、玄米 |
| ビタミンC | 抗酸化作用、皮膚の再生を助ける | ピーマン、ブロッコリー、キウイ、柑橘類 |
ストレスを溜めない工夫
精神的なストレスは、免疫力を低下させる大きな要因の一つで、帯状疱疹の発症自体がストレスになることもありますが、できるだけ心穏やかに過ごす工夫が大切です。
痛みがつらいと気分も落ち込みがちですが、一人で抱え込まずに家族や友人に話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。
また、体調が良い日には、軽い散歩をしたり、好きな音楽を聴いたり、読書をしたりと、自分がリラックスできることを見つけて時間を作りましょう。深い呼吸や瞑想なども、心を落ち着かせるのに役立ちます。
ストレス軽減のための方法
- 趣味の時間を楽しむ(読書、音楽鑑賞など)
- 軽い運動(散歩、ストレッチなど)
- 信頼できる人との会話
- 腹式呼吸や瞑想
- 十分な休息
帯状疱疹の治療と回復過程
帯状疱疹は、適切な治療を早期に開始することが、症状の悪化や後遺症を防ぐ上で非常に重要です。皮膚科での治療の流れや、回復までの道のりについて理解を深めておきましょう。
皮膚科での早期治療の重要性
体の片側に痛みや発疹が現れたら、できるだけ早く皮膚科を受診してください。帯状疱疹の治療は、ウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬が中心となりますが、薬は発症してから72時間以内に服用を開始するのが最も効果的です。
治療の開始が早いほど、皮膚症状や痛みが軽く済み、治癒までの期間も短くなり、また、早期治療は、後遺症として最も問題となる帯状疱疹後神経痛のリスクを減らすことにもつながります。
自己判断で様子を見たり、市販薬で済ませたりせず、疑わしい症状があればすぐに専門医の診察を受けることが、何よりも大切です。
主な治療薬の種類
帯状疱疹の治療の基本は、原因である水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖を抑えることで、抗ウイルス薬の内服が処方されます。症状が重い場合や、合併症のリスクが高い場合は、入院して点滴で投与することもあります。
並行して、つらい痛みを和らげるための鎮痛薬も使用しますが、痛みには個人差が大きいため、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)から、より作用の強い神経障害性疼痛治療薬など、症状に合わせて様々な薬が選択されます。
また、皮膚の症状に対しては、細菌の二次感染を防いだり、炎症を抑えたりするための塗り薬が処方されることもあります。
帯状疱疹の主な治療薬
| 薬の種類 | 主な目的 | 具体例 |
|---|---|---|
| 抗ウイルス薬 | ウイルスの増殖を抑える | 内服薬、点滴薬 |
| 鎮痛薬 | 痛みを和らげる | 非ステロイド性抗炎症薬、神経障害性疼痛治療薬 |
| 外用薬(塗り薬) | 二次感染の予防、炎症を抑える | 抗生物質含有軟膏、非ステロイド性抗炎症薬含有軟膏 |
帯状疱疹後神経痛について
帯状疱疹の皮膚症状が治った後も、3ヶ月以上にわたって痛みが続く状態を帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼び、これは、ウイルスによって神経が損傷を受けたことが原因で起こる、最もつらい後遺症の一つです。
焼けるような痛み、締め付けられるような痛み、電気が走るような痛みなど、その性質は様々で、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。高齢者や、帯状疱疹の初期症状が重かった人ほど、帯状疱疹後神経痛に移行しやすい傾向があります。
痛みの治療は簡単ではありませんが、ペインクリニックでの神経ブロック注射や、専門的な内服薬による治療など、様々な選択肢があります。
皮膚の症状が治まっても痛みが続く場合は、我慢せずに主治医に相談し、専門的な治療を受けることが大切です。
帯状疱疹後神経痛のリスク因子
- 高齢(特に60歳以上)
- 発症時の皮膚症状が重症
- 発症時の痛みが激しい
- 顔面に帯状疱疹ができた
- 治療開始が遅れた
帯状疱疹の入浴に関するよくある質問
最後に、患者様から特によく寄せられる、帯状疱疹の時の入浴に関する質問と回答をまとめました。
- シャワーだけでも大丈夫ですか
-
問題ありません。湯船に浸かることによる体力消耗や、患部への刺激が心配な場合は、シャワー浴の方が推奨され、シャワーであれば、毎日体を清潔に保つことができます。
その際も、お湯の温度はぬるめに設定し、水圧は弱くしてください。患部にはシャワーを直接当てず、手でお湯をすくって優しくかけるようにすると、刺激を最小限に抑えられます。
体の洗い方や拭き方に関する注意点は、湯船に浸かる場合と同様です。
- 温泉や公衆浴場は利用できますか
-
症状が出ている間の温泉や公衆浴場の利用は避けるべきです。水ぶくれがある状態では、他の方にウイルスをうつしてしまう可能性があります。
特に、水ぼうそうにかかったことのない子どもや、免疫力の低下した方が利用する施設では、感染を広げてしまうリスクを考慮しなくてはなりません。また、不特定多数の人が利用するお湯は、細菌感染のリスクも高まります。
すべての水ぶくれがかさぶたになり、完全に乾いて感染の心配がなくなってから、温泉や公衆浴場を利用してください。
- 患部を温めると痛みは和らぎますか
-
一般的に、体を温めて血行を良くすると痛みが和らぐことが多いですが、帯状疱疹の急性期には、温めることで逆に炎症が強まり、痛みやかゆみが増すこともあります。
入浴中に痛みが強くなるようであれば、長湯は避けてください。冷やしすぎも血行を悪くし、回復を遅らせる可能性があり、もし痛みがつらい場合は、入浴とは別に、濡らしたタオルを軽く当てる程度に冷やすのが良いでしょう。
温めるか冷やすかについては個人差が大きいため、自分が心地よいと感じる方法を試すか、医師に相談してください。
- 入浴後に薬を塗るタイミングはいつが良いですか
-
入浴後、皮膚を清潔にした直後が最も適したタイミングです。入浴後の皮膚は柔らかくなっており、余分な皮脂や汚れも落ちているため、薬の成分が浸透しやすくなっています。
体をタオルで優しく拭いて水分を取り除いた後、できるだけ速やかに、医師の指示に従って処方された塗り薬を塗布してください。
薬を塗る際は、清潔な綿棒を使うか、よく洗った手で優しく塗り広げ、患部をこすらないように注意しましょう。入浴後の清潔な状態での塗布を習慣にすることで、治療効果を高めることが期待できます。
以上
参考文献
Toyama N, Shiraki K, Members of the Society of the Miyazaki Prefecture Dermatologists. Epidemiology of herpes zoster and its relationship to varicella in Japan: a 10‐year survey of 48,388 herpes zoster cases in Miyazaki prefecture. Journal of medical virology. 2009 Dec;81(12):2053-8.
Asada H. Recent topics in the management of herpes zoster. The Journal of dermatology. 2023 Mar;50(3):305-10.
Shiraki K, Toyama N, Daikoku T, Yajima M, Miyazaki Dermatologist Society. Herpes zoster and recurrent herpes zoster. InOpen Forum Infectious Diseases 2017 (Vol. 4, No. 1, p. ofx007). US: Oxford University Press.
Sato K, Adachi K, Nakamura H, Asano K, Watanabe A, Adachi R, Kiuchi M, Kobayashi K, Matsuki T, Kaise T, Gopala K. Burden of herpes zoster and postherpetic neuralgia in Japanese adults 60 years of age or older: Results from an observational, prospective, physician practice‐based cohort study. The Journal of Dermatology. 2017 Apr;44(4):414-22.
Matsuoka K, Togo K, Yoshii N, Hoshi M, Arai S. Incidence rates for hospitalized infections, herpes zoster, and malignancies in patients with ulcerative colitis in Japan: an administrative health claims database analysis. Intestinal research. 2023 Jan 1;21(1):88-99.
Takao Y, Miyazaki Y, Okeda M, Onishi F, Yano S, Gomi Y, Ishikawa T, Okuno Y, Mori Y, Asada H, Yamanishi K. Incidences of herpes zoster and postherpetic neuralgia in Japanese adults aged 50 years and older from a community-based prospective cohort study: the SHEZ study. Journal of Epidemiology. 2015 Nov 5;25(10):617-25.
Patil A, Goldust M, Wollina U. Herpes zoster: a review of clinical manifestations and management. Viruses. 2022 Jan 19;14(2):192.
Dworkin RH, Johnson RW, Breuer J, Gnann JW, Levin MJ, Backonja M, Betts RF, Gershon AA, Haanpää ML, McKendrick MW, Nurmikko TJ. Recommendations for the management of herpes zoster. Clinical infectious diseases. 2007 Jan 1;44(Supplement_1):S1-26.
Donahue JG, Choo PW, Manson JE, Platt R. The incidence of herpes zoster. Archives of internal medicine. 1995 Aug 7;155(15):1605-9.
Weinberg JM. Herpes zoster: epidemiology, natural history, and common complications. Journal of the American academy of dermatology. 2007 Dec 1;57(6):S130-5.