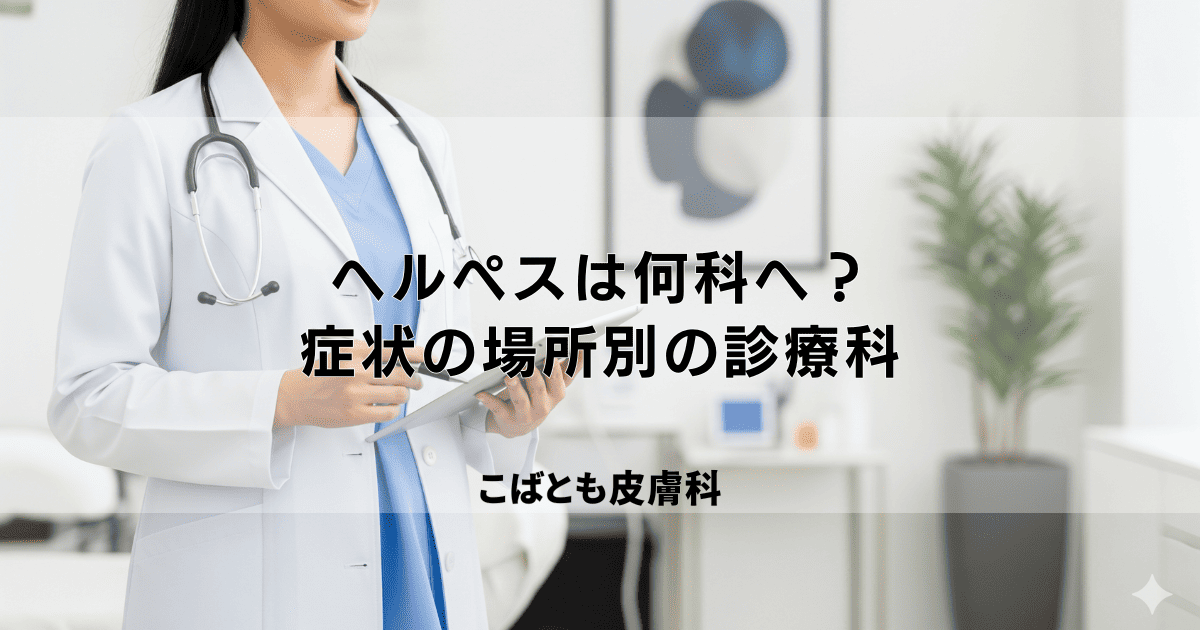ある日突然、唇や体にピリピリとした痛みを感じ、しばらくすると赤く腫れて水ぶくれができるヘルペスは、多くの方が経験する皮膚疾患ですが、いざ症状が出ると、どの病院の何科へ行けば良いのか迷ってしまう方も少なくないでしょう。
症状が出ている場所によっては、皮膚科以外の診療科が適している場合もあります。治療を早期に開始することは、症状の悪化を防ぎ、回復を早めるためにとても重要です。
この記事では、ヘルペスの基本的な知識から、症状が現れた場所ごとにどの診療科を受診すべきか、治療法や日常生活での注意点まで、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
ヘルペスとは?ウイルスの種類と主な症状
ヘルペスは、ヘルペスウイルス科に属するウイルスへの感染によって生じる疾患の総称です。一度感染すると、ウイルスは体内の神経節に潜伏し続け、体の抵抗力が落ちたときなどに再び活動を始めて症状を起こします。
単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)とは
単純ヘルペスウイルス1型、通称HSV-1は、主に上半身、特に口の周りや唇に症状を起こすことが多いウイルスで、一般的に口唇ヘルペスとして知られています。
子どもの頃に、ウイルス保持者である家族とのキスや食器の共有などを通じて感染することが多いです。初感染時には症状が出ないこともありますが、発熱や歯肉の腫れなどを伴う歯肉口内炎として現れることもあります。
その後、ウイルスは顔の感覚を支配する三叉神経節に潜伏します。
風邪、疲労、ス、トレス、強い紫外線を浴びることなどが引き金となり、ウイルスが再活性化すると、唇の周りにピリピリとした違和感やかゆみが生じ、その後に小さな水ぶくれができます。
水ぶくれは数日でかさぶたになり、1週間から2週間ほどで治癒するのが一般的です。
単純ヘルペスウイルス2型(HSV-2)とは
単純ヘルペスウイルス2型、通称HSV-2は、主に下半身、特に性器やその周辺に症状を起こすウイルスで、性器ヘルペスの主な原因です。
主に性的な接触によって感染が広がり、初感染の場合、性器周辺に多くの水ぶくれや潰瘍ができ、強い痛みや排尿困難、発熱などを伴うことがあります。女性の方が男性よりも症状が重くなる傾向が見られます。
治療後、ウイルスは腰や仙骨部の神経節に潜伏し、HSV-1と同様に、体の免疫力が低下した際に再発を繰り返すことがあります。
再発時の症状は初感染時よりも軽いことが多いですが、それでも痛みや不快感を伴うため、多くの患者さんを悩ませます。性器ヘルペスは、症状がないときでもパートナーに感染させる可能性があるため、正しい知識を持つことが大事です。
ヘルペスウイルスの種類と特徴
| ウイルスの種類 | 主な症状が現れる場所 | 主な感染経路 |
|---|---|---|
| 単純ヘルペスウイルス1型 (HSV-1) | 口唇、顔、上半身 | 接触感染(キス、タオルの共有など) |
| 単純ヘルペスウイルス2型 (HSV-2) | 性器、臀部、下半身 | 性的接触 |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス (VZV) | 全身(水ぼうそう)、体の片側(帯状疱疹) | 空気感染、接触感染 |
水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)とは
水痘・帯状疱疹ウイルス、VZVもヘルペスウイルスの一種です。多くの方が子どもの頃にかかる水ぼうそう(水痘)の原因となるウイルスがこれにあたります。
水ぼうそうが治った後も、VZVは体内の神経節に潜伏し続け、加齢や過労、ストレスなどによって免疫力が低下すると、ウイルスが再活性化して帯状疱疹を発症します。
帯状疱疹は、神経の走行に沿って、体の左右どちらか片側に帯状に赤い発疹と水ぶくれが現れるのが特徴で、多くの場合、ピリピリ、チクチクとした強い痛みを伴います。
症状は胸から背中、腹部によく見られますが、顔や手足に現れることもあり、特に顔面に発症した場合は、顔面神経麻痺や難聴、角膜炎などの合併症を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
症状が出たときの初期対応
ヘルペスを疑う症状、例えば皮膚のピリピリ感や小さな水ぶくれに気づいたら、できるだけ早く医療機関を受診することが重要です。
抗ウイルス薬はウイルスの増殖を抑える薬であるため、症状が出始めてから48時間以内、遅くとも72時間以内に服用を開始することが、症状の悪化を防ぎ、治療期間を短縮する上で効果的です。
患部を清潔に保つことは大切ですが、水ぶくれを自分で潰すのは絶対にやめましょう。水ぶくれの中にはウイルスが大量に含まれており、潰すことで他の部位に感染を広げたり、細菌による二次感染を引き起こしたりするリスクがあります。
また、患部に触れた手で目や口、性器などを触らないように注意し、手洗いを徹底しタオルや食器、の共有も避けてください。
ヘルペスの診療科選びガイド
ヘルペスの症状は体のさまざまな場所に現れる可能性があり、場所によって相談すべき専門の診療科が異なります。ここでは、症状が現れた場所別に、どの診療科を受診すれば良いのかを具体的に解説します。
口唇や顔に症状が出た場合
唇の周りや鼻の下、頬などにピリピリとした痛みや水ぶくれができた場合、口唇ヘルペスや顔面ヘルペスの可能性が高いです。このような皮膚症状に対する診断と治療は、皮膚科が最も専門としています。
皮膚科では症状を直接観察し、必要に応じて検査を行うことで、ヘルペスかどうかを正確に診断し、抗ウイルス薬の飲み薬や塗り薬を処方し、症状を和らげるための指導を行います。
また、口唇ヘルペスは風邪の初期症状と似ていることから、風邪をひいたときに内科を受診し、そこでヘルペスと診断されることもあります。かかりつけの内科がある場合は、まずそこで相談してみるのも一つの方法です。
性器周辺に症状が出た場合
性器やお尻の周りに痛みやかゆみ、水ぶくれができた場合は、性器ヘルペスが疑われます。この場合、男性は泌尿器科または皮膚科、女性は産婦人科または皮膚科の受診が一般的です。
性器ヘルペスは性感染症(STD)の一つであり、他の性感染症を合併している可能性も考慮する必要があります。産婦人科や泌尿器科では、ヘルペスの治療と同時に、他の性感染症の検査も実施できます。
特に女性の場合、妊娠中の初感染は胎児に影響を及ぼす可能性があるため、産婦人科での管理が重要です。
身体の片側に帯状に症状が出た場合
胸や背中、腹部など、体の左右どちらか片側の神経に沿って帯状に痛みや発疹、水ぶくれが出た場合、帯状疱疹の可能性が非常に高いです。帯状疱疹の治療は、皮膚科が中心で、皮膚症状の管理と抗ウイルス薬による治療を行います。
帯状疱疹の最もつらい症状の一つは痛みで、皮膚の症状が治った後も痛みが長期間続く帯状疱疹後神経痛(PHN)は、生活の質を大きく低下させることがあります。
痛みが非常に強い場合や、痛みが長引く場合には、痛みの治療を専門とするペインクリニック科の受診を検討すると良いでしょう。ペインクリニック科では、神経ブロック注射などの専門的な治療で痛みを和らげることができます。
症状の場所と推奨される診療科
| 症状の場所 | 主な疾患 | 推奨される診療科 |
|---|---|---|
| 口唇、頬、鼻の周り | 口唇ヘルペス | 皮膚科、内科 |
| 性器、臀部 | 性器ヘルペス | 皮膚科、産婦人科(女性)、泌尿器科(男性) |
| 体の片側(胸、背中、腹部、顔など) | 帯状疱疹 | 皮膚科、ペインクリニック科(痛みが強い場合) |
| 目、まぶた | 角膜ヘルペス | 眼科 |
目やその周辺に症状が出た場合
まぶたや目の周りにヘルペスの症状が出た場合、あるいは目に充血や痛み、視力低下などを感じた場合は、ウイルスが角膜に感染している角膜ヘルペスの可能性があります。この場合は、ためらわずに直ちに眼科を受診してください。
角膜ヘルペスは、治療が遅れると角膜に濁りを残し、視力に恒久的な障害を及ぼす危険性がある緊急性の高い疾患です。
皮膚科で処方される抗ウイルス薬の飲み薬だけでは不十分な場合が多く、眼科専門医による抗ウイルス薬の点眼薬や眼軟膏を用いた専門的な治療が必要です。
皮膚科でのヘルペス治療の流れ
ヘルペスの症状で最も多くの患者さんが訪れるのが皮膚科です。一般的な問診から診断、そして治療法に至るまでの流れを解説します。
問診と視診による診断
まず、医師は患者さんから症状について詳しく話を聞き、いつから、どこに、どのような症状が出ているのか、痛みやかゆみの程度、過去に同じような症状を経験したことがあるか、などを伝えてください。
問診の後は、患部の状態を直接目で見て確認する視診を行います。ヘルペスの水ぶくれは非常に特徴的な形をしているため、多くの場合、経験豊富な皮膚科医であれば問診と視診だけで診断が可能です。
口唇ヘルペスや典型的な帯状疱疹では、この段階で診断が確定し、治療が開始されることがほとんどです。
必要に応じて行う検査
診断が難しい非典型的な症状の場合や、確定診断が必要な場合には、追加で検査を行うことがあります。最も一般的なのは、患部の水ぶくれやびらんから綿棒で細胞をこすり取り、ウイルス抗原を検出する迅速検査です。
検査は15分程度で結果が分かり、その日のうちに診断を確定でき、その他にも、血液検査でヘルペスウイルスに対する抗体の有無や量を調べることもあります。
抗体検査は、過去に感染したことがあるかどうかを確認したり、初感染か再発かを判断したりするのに役立ちます。
皮膚科で行う主な検査
| 検査方法 | 検査内容 | 検査で分かること |
|---|---|---|
| ウイルス抗原迅速検査 | 患部の細胞を採取し、ウイルス抗原の有無を調べる | 現在、ヘルペスウイルスに感染しているか |
| 血液検査(抗体検査) | 採血し、血液中のウイルスに対する抗体を測定する | 過去の感染歴、初感染か再発かの推定 |
| PCR検査 | 患部の細胞や体液からウイルス遺伝子を検出する | ウイルスの有無をより高感度に検出 |
主な治療法である抗ウイルス薬
ヘルペス治療の中心となるのは、ウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬です。アシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルといった成分の薬が用いられ、飲み薬と塗り薬、重症の場合には点滴で投与します。
- 飲み薬
- 塗り薬
- 点滴
飲み薬は体の中からウイルスに作用するため、最も効果が高い治療法です。通常、5日間から10日間程度服用を続け、塗り薬は、飲み薬と併用したり、ごく軽症の場合に単独で用いたりします。症状が出始めた初期段階で使用すると効果的です。
入院が必要なほど重症な帯状疱疹や、ヘルペス脳炎などでは、点滴による強力な治療を行います。
症状を和らげる対症療法
抗ウイルス薬と並行して、つらい症状を和らげるための対症療法も行い、痛みに対しては、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などの鎮痛剤を処方します。帯状疱疹の痛みは強いことが多いため、痛みのコントロールは非常に重要です。
また、水ぶくれが破れてびらんになった部分からの細菌感染を防ぐために、抗生物質入りの軟膏を処方することもあります。かゆみが強い場合には、抗ヒスタミン薬の飲み薬が処方されることもあります。
性器ヘルペスかも?産婦人科・泌尿器科との連携
性器周辺の症状は非常にデリケートな問題であり、受診をためらってしまう方もいるかもしれませんが、性器ヘルペスは放置するとパートナーへの感染や、特に女性の場合は出産時に深刻な問題を引き起こす可能性があります。
性器ヘルペスの特徴と感染経路
性器ヘルペスは、主に単純ヘルペスウイルス2型(HSV-2)によって起きますが、近年ではオーラルセックスの普及により、1型(HSV-1)による性器ヘルペスも増えています。主な感染経路は、ウイルスが活発な時期の性的な接触です。
コンドームの使用はある程度の予防効果がありますが、コンドームで覆われていない部分の皮膚や粘膜からもうつる可能性があるため、完全ではありません。症状としては、性器やその周辺に水ぶくれや潰瘍ができ、強い痛みを伴います。
初感染では、発熱や足の付け根のリンパ節の腫れなど、全身症状が現れることもあります。
性器ヘルペスの感染経路と潜伏期間
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主な原因ウイルス | 単純ヘルペスウイルス2型 (HSV-2)、1型 (HSV-1) |
| 主な感染経路 | 性的接触(性交、オーラルセックス、アナルセックス) |
| 潜伏期間 | 感染から2日~10日程度 |
産婦人科での検査と治療
女性が性器ヘルペスを疑う場合、産婦人科は非常に重要な役割を果たし、産婦人科では、内診によって外陰部だけでなく、膣や子宮頸部の状態も確認できます。
ヘルペスの診断と治療はもちろんのこと、クラミジアや淋菌など、他の性感染症の検査も同時に行うことが可能です。
特に重要なのが、妊娠との関わりで、妊娠中に性器ヘルペスに初感染すると、ウイルスが胎盤を通じて胎児に感染し、流産や早産のリスクを高めることがあります。
また、出産時に産道でウイルスが排出されていると、赤ちゃんに感染し、重篤な新生児ヘルペスを起こす可能性があるため、妊婦さんや妊娠を希望する方の性器ヘルペスは、産婦人科での専門的な管理が必要です。
泌尿器科が専門となるケース
男性の場合、性器ヘルペスは泌尿器科の専門領域の一つで、泌尿器科では、陰茎や亀頭、陰嚢などの症状を診察します。また、ヘルペスによって尿道炎が引き起こされ、排尿時に痛みを感じることもあります。
排尿に関するトラブルは、泌尿器科医が専門的に対応します。性器ヘルペスは、時に前立腺炎などの合併症を引き起こす可能性も指摘されており、泌尿器科での診察は重要です。
皮膚科と同様に、視診やウイルス検査によって診断し、抗ウイルス薬による治療を行います。
パートナーへの配慮と対応
性器ヘルペスと診断された場合、パートナーへの配慮が大切です。症状が出ている期間はもちろん、症状が治まっていてもウイルスが排出される可能性があるため、性的な接触は控える必要があります。
いつから性交渉を再開できるかについては、医師とよく相談してください。また、ご自身の感染が分かったら、勇気を持ってパートナーに伝え、検査を勧めることが重要です。
- 症状がある時は性交渉を避ける
- 症状がなくても感染リスクがあることを理解する
- コンドームを正しく使用する
注意が必要な特殊なケースと専門診療科
ヘルペスは多くの場合、皮膚や粘膜の症状で済みますが、まれに重篤な合併症を起こすことがあります。特定の場所に症状が出た場合や、特定の人が感染した場合には、専門的な診療科での迅速な対応が必要です。
角膜ヘルペスと眼科の重要性
単純ヘルペスウイルスが目の角膜に感染すると、角膜ヘルペスを発症し、目の充血、痛み、異物感、まぶしさ、涙が増える、視力が低下するなどの症状を起こします。帯状疱疹が顔面にできた場合にも、ウイルスが目に影響を及ぼすことがあります。
角膜ヘルペスは、日本の失明原因の上位に挙げられる疾患であり、治療が遅れたり、再発を繰り返したりすると、角膜が白く濁って視力が著しく低下する可能性があります。
目の症状に気づいたら、絶対に自己判断せず、すぐに眼科を受診してください。眼科では、専用の顕微鏡で目の状態を詳しく観察し、抗ウイルス薬の点眼や軟膏、場合によっては内服薬を組み合わせて治療を行います。
ヘルペス脳炎の疑いと神経内科
ヘルペス脳炎は、単純ヘルペスウイルスが脳に感染して炎症を起こす、非常に重篤な病気です。発熱、頭痛、嘔吐といった風邪のような症状から始まり、急に意識障害やけいれん、異常な言動などが現れます。
死亡率が高く、救命できても記憶障害や言語障害などの重い後遺症が残ることが少なくありません。ヘルペス脳炎が疑われる場合は、一刻も早く、脳神経内科や神経内科、救急科のある総合病院を受診する必要があります。
診断には、髄液検査や頭部MRI、脳波検査などが行われ、治療は、抗ウイルス薬の大量点滴を緊急で行うことが必須です。疑わしい症状があれば、ためらわずに救急車を呼ぶことも検討してください。
新生児ヘルペスと小児科
新生児ヘルペスは、母親が性器ヘルペスに感染している場合に、主に出産時に産道で赤ちゃんが感染することによって起こります。
生後数日から数週間で発症し、皮膚や目、口だけに症状が出る軽症型から、脳に感染する脳炎型、全身の臓器に感染が広がる全身型まで様々です。脳炎型や全身型は極めて重篤で、命に関わる危険性が高い病気です。
赤ちゃんの元気がない、母乳やミルクの飲みが悪い、発熱、黄疸、けいれん、特徴的な水ぶくれなどの症状が見られたら、すぐに小児科、特に新生児集中治療室(NICU)のある総合病院を受診する必要があります。
ヘルペスの再発を防ぐために日常生活でできること
ヘルペスは一度感染するとウイルスが体内に潜伏し続けるため、根本的に治癒させることは難しいのが現状ですが、ウイルスの再活性化を減らすことで、症状が出る頻度をコントロールすることは可能です。
免疫力を維持する生活習慣
ヘルペスウイルスが再活性化する最大のきっかけは、免疫力の低下なので、日頃から免疫力を高く維持する生活を心がけることが、最も効果的な再発予防策です。
- バランスの取れた食事
- 十分な睡眠
- 適度な運動
特定の食品だけを食べるのではなく、主食、主菜、副菜をそろえ、ビタミンやミネラルを豊富に含む野菜や果物を積極的に摂りましょう。睡眠不足は免疫力を低下させる大きな要因です。
毎晩決まった時間に就寝し、質の良い睡眠を確保するよう努めてください。また、ウォーキングやジョギングなどの適度な運動は、血行を促進し、体力を向上させ、免疫機能の維持に役立ちます。
免疫力維持に役立つ生活習慣
| 項目 | 具体的な内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 食事 | 多様な食材をバランス良く摂取する。特にビタミンA,C,Eを意識する。 | 体の抵抗力を高める |
| 睡眠 | 1日6~8時間の質の良い睡眠を確保する。 | 疲労回復、免疫細胞の活性化 |
| 運動 | 週に数回、30分程度の有酸素運動を行う。 | 体力向上、ストレス軽減 |
ストレス管理の重要性
精神的なストレスも、免疫力を低下させ、ヘルペスの再発を起こす大きな要因です。現代社会でストレスを完全になくすことは難しいですが、自分なりの方法でストレスを上手に発散し、溜め込まないようにすることが大切です。
趣味に没頭する時間を作ったり、友人と話したり、ゆっくりと入浴したりするのも良いでしょう。ヨガや瞑想、深呼吸などは、心身をリラックスさせるのに効果的です。
ストレス対処法の例
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| リラクゼーション | 深呼吸、瞑想、ヨガ、アロマテラピー、音楽鑑賞 |
| 気分転換 | 趣味への没頭、散歩、友人との会話、旅行 |
| 運動 | ウォーキング、ジョギング、ストレッチ、スポーツ |
紫外線対策と皮膚の保護
強い紫外線は、皮膚の免疫機能を低下させ、特に口唇ヘルペスの再発の引き金になることが知られています。スキーや海水浴など、紫外線を強く浴びるレジャーの後に口唇ヘルペスが再発するのはこのためです。
外出時には、日焼け止めクリームを塗る、帽子や日傘を利用するなどの紫外線対策を忘れずに行いましょう。唇専用のUVカット機能のあるリップクリームも有効です。
また、皮膚が乾燥したり、傷ついたりすると、そこからヘルペスが再発しやすくなることもあるので、日頃から保湿を心がけ、皮膚のバリア機能を健康に保つことも大切です。
再発抑制療法という選択肢
性器ヘルペスなど、再発を頻繁に(例えば年6回以上)繰り返す方には、再発抑制療法という治療の選択肢があります。
これは、症状がないときでも毎日少量の抗ウイルス薬を服用し続けることで、ウイルスの再活性化を抑え、再発の頻度を減らす、あるいは症状を非常に軽くするための治療法です。パートナーへの感染リスクを低減させる効果もあります。
再発頻度が高く、お悩みの方は、一度皮膚科や産婦人科の医師に相談してみると良いでしょう。
医療機関を受診する前に準備しておきたいこと
いざ病院に行くと、緊張してしまって言いたいことの半分も言えなかった、という経験はありませんか。限られた診察時間の中で、医師に的確な情報を伝え、自分も納得のいく説明を受けるためには、事前の準備がとても役立ちます。
症状の経緯をメモする
医師が診断する上で最も重要な情報の一つが、症状の詳しい経緯です。受診前に、以下の点について簡単なメモを作成しておくと、正確に情報を伝えることができます。
- いつから症状が始まったか(○日前、○月○日頃など)
- 最初に気づいた症状は何か(痛み、かゆみ、赤みなど)
- 症状はどのように変化したか(水ぶくれができた、範囲が広がったなど)
- 痛みの程度(10段階でどのくらいか、ズキズキ、ピリピリなど)
- 過去に同じような症状を経験したことがあるか
情報を整理しておくだけで、医師は診断の助けとなる多くの手がかりを得られます。
服用中の薬や持病を伝える準備
現在服用している薬や、治療中の病気(持病)、アレルギーの有無なども、医師にとって重要な情報です。ヘルペスの治療薬と飲み合わせが良くない薬があるかもしれませんし、持病によっては薬の選択に注意が必要な場合もあります。
お薬手帳を持参するのが最も確実です。サプリメントや漢方薬を飲んでいる場合も、忘れずに伝えましょう。
免疫を抑制する薬を使用している方や、糖尿病、腎臓病などの持病がある方は、ヘルペスが重症化しやすい傾向があるため、必ず申告してください。
質問したいことをリストアップする
診察が終わってから、あれも聞けばよかったと後悔しないように、事前に質問したいことをリストアップしておくことをお勧めします。例えば、以下のような点です。
- 病名とその原因について
- 処方される薬の効果と副作用
- 治療にかかる期間の目安
- 日常生活での注意点(仕事、入浴、食事など)
- 人にうつす可能性と、その予防法
ヘルペスに関するよくある質問
最後に、ヘルペスに関して患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- ヘルペスは他人にうつりますか?
-
ヘルペスウイルスは、症状が出ているときの水ぶくれやびらん部分に多く含まれており、その部分に直接触れること(接触感染)で感染します。
口唇ヘルペスの場合は、キスやグラス、タオルの共有などでも感染する可能性があり、性器ヘルペスは、主に性的な接触によって感染します。
症状が出ていないときでも、皮膚や粘膜からウイルスが排出されていることがあるため、感染のリスクはゼロではありません。
患部には触らない、触った後はよく手を洗う、タオルなどを共有しない、といった基本的な対策が重要です。
- 市販薬で治療できますか?
-
口唇ヘルペスの再発に限り、薬剤師の指導のもとで購入できる市販薬(第1類医薬品)があり、過去に医師から口唇ヘルペスの診断を受け、治療経験がある人が対象です。
初めて症状が出た場合や、症状の範囲が広い場合、症状が重い場合には使用できません。自己判断で市販薬を使用すると、症状が悪化したり、診断が遅れたりする可能性があります。
基本的には、ヘルペスを疑う症状が出たら、まずは医療機関を受診して正確な診断を受けることが原則です。
- 治療期間はどのくらいですか?
-
一般的な口唇ヘルペスや性器ヘルペスの初感染・再発の場合、抗ウイルス薬を5日間から10日間服用し、皮膚の症状は1週間から2週間程度で治まることが多いです。
帯状疱疹の場合は、通常7日間の抗ウイルス薬の服用が必要で、皮膚症状が完全に治るまでには3週間程度かかることもあります。
痛みが長引く帯状疱疹後神経痛に移行した場合は、数ヶ月から数年にわたり治療が必要になることもあります。いずれの場合も、早期に治療を開始するほど、回復は早くなる傾向にあります。
- 完治はしますか?
-
現在の医療では、一度体内に侵入し、神経節に潜伏したヘルペスウイルスを完全に排除する方法はなく、完治するというよりは、症状を抑え、コントロールしていく病気と考えるのが適切です。
抗ウイルス薬は、ウイルスの増殖を抑えて症状を改善させ、回復を早めるための薬であり、ウイルスを体内から消し去るものではありません。
しかし、生活習慣の改善やストレス管理によって、再発の頻度を大幅に減らすことは可能で、ヘルペスと上手く付き合っていくという視点が大切です。
以上
参考文献
Imafuku S. Recent advance in management of herpes simplex in Japan. The Journal of Dermatology. 2023 Mar;50(3):299-304.
Hashido M, Lee FK, Nahmias AJ, Tsugami H, Isomura S, Nagata Y, Sonoda S, Kawana T. An epidemiologic study of herpes simplex virus type 1 and 2 infection in Japan based on type-specific serological assays. Epidemiology & Infection. 1998 Mar;120(2):179-86.
Uchio E, Takeuchi S, Itoh N, Matsuura N, Ohno S, Aoki K. Clinical and epidemiological features of acute follicular conjunctivitis with special reference to that caused by herpes simplex virus type 1. British journal of ophthalmology. 2000 Sep 1;84(9):968-72.
Itoh N, Matsumura N, Ogi A, Nishide T, Imai Y, Kanai H, Ohno S. High prevalence of herpes simplex virus type 2 in acute retinal necrosis syndrome associated with herpes simplex virus in Japan. American journal of ophthalmology. 2000 Mar 1;129(3):404-5.
Asada H. Recent topics in the management of herpes zoster. The Journal of dermatology. 2023 Mar;50(3):305-10.
Takase H, Kubono R, Terada Y, Imai A, Fukuda S, Tomita M, Miyanaga M, Kamoi K, Sugita S, Miyata K, Mochizuki M. Comparison of the ocular characteristics of anterior uveitis caused by herpes simplex virus, varicella-zoster virus, and cytomegalovirus. Japanese journal of ophthalmology. 2014 Nov;58(6):473-82.
Doi Y, Ninomiya T, Hata J, Yonemoto K, Tanizaki Y, Arima H, Liu Y, Rahman M, Iida M, Kiyohara Y. Seroprevalence of herpes simplex virus 1 and 2 in a population-based cohort in Japan. Journal of epidemiology. 2009 Mar 5;19(2):56-62.
Shiraki K, Toyama N, Daikoku T, Yajima M, Miyazaki Dermatologist Society. Herpes zoster and recurrent herpes zoster. InOpen Forum Infectious Diseases 2017 (Vol. 4, No. 1, p. ofx007). US: Oxford University Press.
Shoji H, Wakasugi K, Miura Y, Imaizumi T, Kazuyama Y. Herpesvirus infections of the central nervous system. Japanese journal of infectious diseases. 2002 Apr 30;55(1):6-13.
Kojima J, Suzuki S, Hoshi SI, Sekizawa A, Sagara Y, Matsuda H, Ishiwata I, Kitamura T. Challenges for early diagnosis of neonatal herpes infection in Japan. Frontiers in Reproductive Health. 2024 Aug 8;6:1393509.