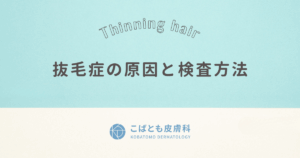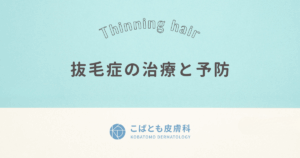抜毛症(トリコチロマニア)は、自分の毛髪を繰り返し引き抜いてしまう衝動制御障害の一つです。この行動は、頭皮だけでなく、眉毛やまゆ毛、まつ毛など、体のあらゆる部位の毛が対象となることがあります。
多くの場合、ストレスや不安が引き金となり、行為後に一時的な解放感や満足感を得るものの、結果として薄毛や皮膚のトラブル、さらには自己嫌悪感に繋がることも少なくありません。
 Dr.小林智子
Dr.小林智子この記事では、抜毛症の具体的な症状や、皮膚科や精神科と連携した治療法、日常生活での対策について詳しく解説します。
治療の第一歩 – 専門医と相談して決める治療方針の選択

抜毛症の治療を始めるにあたり、まずは専門医に相談することが重要です。皮膚科医は頭皮の状態を診断し、精神科医や心理士は抜毛行動の背景にある心理的な原因を探ります。
これらの情報を総合的に判断し、患者さん一人ひとりに合った治療方針を決定します。早期の相談が、症状改善への近道となります。
皮膚科での初期対応と診断
皮膚科では、まず抜毛による頭皮のダメージや炎症の有無、脱毛の範囲やパターンを確認します。他の脱毛症との鑑別診断も行い、抜毛症であると特定することが最初のステップです。
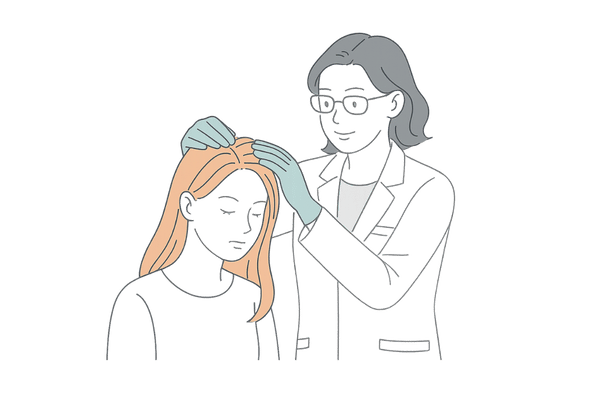
頭皮の環境を整えるためのアドバイスや、必要に応じて外用薬の処方も検討します。
頭皮の状態セルフチェックポイント
| チェック項目 | 状態 | 考えられること |
|---|---|---|
| 脱毛斑の形状 | 不規則、毛が途中で切れている | 抜毛の可能性 |
| 頭皮の色 | 赤み、炎症 | 物理的刺激による皮膚炎 |
| かゆみや痛み | ある、またはない | 炎症のサイン、または無自覚 |
精神科や心療内科との連携
抜毛行為の背景には、ストレス、不安、抑うつなどの精神的な要因が関わっていることが多いため、精神科医や心療内科医との連携が治療効果を高めます。
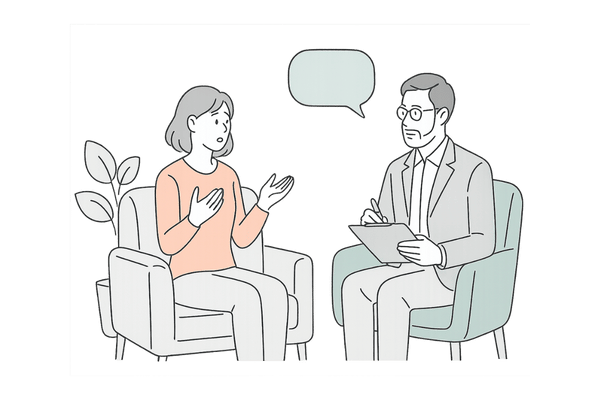
心理的なアセスメントを通じて、抜毛に至るまでの感情や思考のパターンを把握し、適切な心理療法の導入を検討します。
認知行動療法による治療 – 行動の改善と習慣の変化を目指して
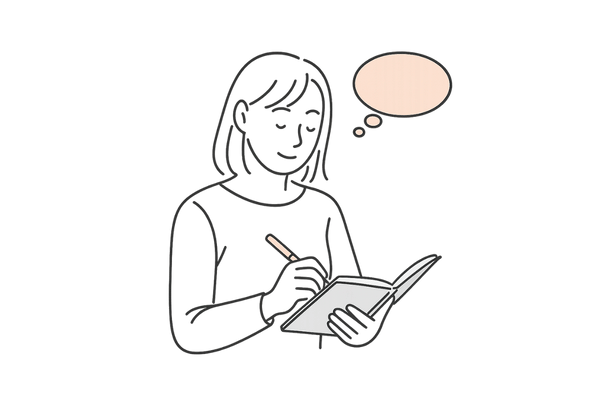
認知行動療法(CBT)は、抜毛症の治療において有効性が示されている心理療法の一つです。この療法では、抜毛行動に繋がる思考(認知)のパターンを特定し、それをより現実的で健康的なものに変えることを目指します。
また、抜毛という行動そのものを、別のより害の少ない行動に置き換える練習(習慣逆転法など)も行います。
ハビットリバーサル訓練(HRT)の導入
ハビットリバーサル訓練は、抜毛行動に気づき(アウェアネス・トレーニング)、その衝動を感じたときに拮抗反応(例:手を握る、気を紛らわせる行動をとる)を行うことで、抜毛を防ぐ訓練です。
これにより、無意識的な抜毛行動を減らし、セルフコントロール能力を高めます。
HRTの主な構成要素
| 要素 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 自己認識訓練 | 抜毛行動やその前兆を詳細に記録 | 行動パターンとトリガーの特定 |
| 拮抗反応訓練 | 抜毛衝動時に代替行動を行う | 抜毛の物理的阻止 |
| 動機づけと般化 | 治療への意欲維持、日常生活への応用 | 治療効果の持続と拡大 |
アクセプタンス&コミットメントセラピー(ACT)
アクセプタンス&コミットメントセラピーは、抜毛したいという衝動やそれに伴う不快な感情を無理に消そうとせず、あるがままに受け入れる(アクセプタンス)練習をします。
その上で、自分にとって価値のある目標(コミットメント)に向かって行動することを重視します。これにより、衝動に振り回されず、より充実した生活を送ることを目指します。
内服薬による治療アプローチ – 精神科薬物療法の役割と効果
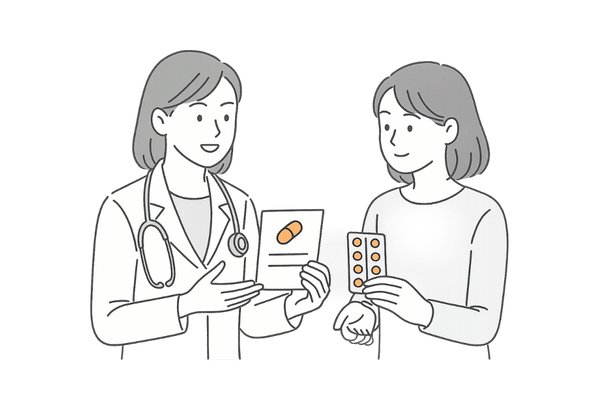
抜毛症の治療において、薬物療法は主に併存する精神症状の緩和や、抜毛衝動の軽減を目的として用いられます。特に、うつ病や不安障害が背景にある場合、それらの治療薬が抜毛行動の改善に間接的に寄与することがあります。
薬物療法は、必ず精神科医の診断と指導のもとで行います。
選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)の利用
SSRIはうつ病や不安障害の治療に広く用いられる薬剤ですが、強迫的な症状を持つ抜毛症に対しても効果が期待されることがあります。
セロトニンという脳内の神経伝達物質のバランスを整えることで、衝動性や不安感を和らげる効果が報告されています。ただし、効果や副作用には個人差があるため、医師との十分な相談が必要です。
その他の薬物療法の選択肢
N-アセチルシステインのような抗酸化作用を持つサプリメントが、一部の研究で抜毛衝動を軽減する可能性が示唆されています。
また、非定型抗精神病薬が重度の抜毛症に対して用いられることもありますが、これは他の治療法で効果が見られない場合の選択肢となります。いずれの薬剤も、その効果とリスクを医師とよく話し合い、慎重に検討します。
薬物療法で考慮する点
| 薬剤の種類(例) | 期待される効果 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| SSRI | 不安・抑うつ・衝動性の軽減 | 効果発現までの時間、副作用(吐き気など) |
| N-アセチルシステイン | 衝動性の軽減 | エビデンスは限定的、消化器症状 |
| 非定型抗精神病薬 | 重度の衝動性の抑制 | 副作用(眠気、体重増加など)、定期的な検査 |
外用薬を用いた治療方法 – 頭皮ケアと毛髪再生のサポート
抜毛症によってダメージを受けた頭皮のケアや、毛髪の再生をサポートするために、皮膚科では外用薬を用いることがあります。

抜毛行為そのものを止めるものではありませんが、頭皮環境を改善し、発毛を促すことで心理的な負担を軽減する一助となります。
ミノキシジル外用薬の適用
ミノキシジルは、血管を拡張し毛根への血流を増加させることで発毛を促進する効果が知られています。抜毛によって薄毛が気になる部位に使用することで、毛髪の再生をサポートします。
ただし、抜毛行為が続いている間は効果が十分に得られないこともあります。皮膚科医の指導のもと、適切な濃度と使用方法を守ることが大切です。
頭皮の炎症を抑えるステロイド外用薬
繰り返される抜毛によって頭皮に炎症や湿疹が生じている場合、ステロイド外用薬を使用して炎症を鎮めることがあります。これにより、かゆみや痛みを軽減し、頭皮環境の悪化を防ぎます。
ただし、長期的な使用や自己判断での使用は避け、必ず医師の指示に従ってください。
頭皮ケア外用薬の比較
| 薬剤の種類 | 主な目的 | 使用上のポイント |
|---|---|---|
| ミノキシジル外用薬 | 発毛促進、毛髪再生サポート | 継続使用が必要、効果には個人差 |
| ステロイド外用薬 | 頭皮の炎症抑制、かゆみ軽減 | 医師の指示通り短期間使用が原則 |
| 保湿剤 | 頭皮の乾燥予防、バリア機能保護 | 刺激の少ない製品を選択 |
代替療法と補完的アプローチ – リラクゼーション技法の活用
抜毛症の治療においては、標準的な治療法に加えて、代替療法や補完的なアプローチが役立つことがあります。
特に、ストレスや不安が抜毛のトリガーとなる場合、リラクゼーション技法を取り入れることで心身の緊張を和らげ、衝動をコントロールしやすくする効果が期待できます。
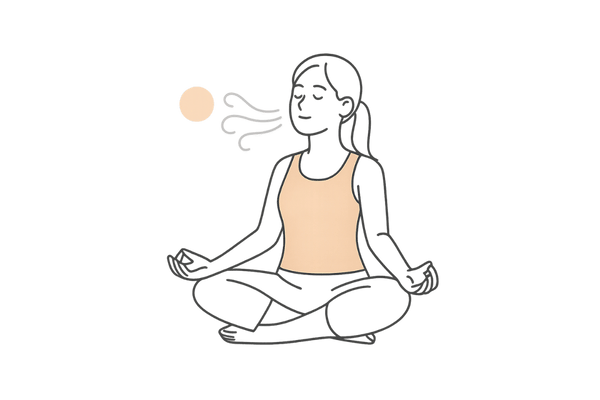
マインドフルネス瞑想とリラクゼーション
マインドフルネス瞑想は、「今、ここ」の瞬間に意識を集中させ、自分の思考や感情、身体感覚を判断せずに観察する練習です。抜毛したいという衝動に気づきやすくなり、衝動に自動的に反応するのではなく、一歩引いて対処するスペースを作ることができます。
深呼吸や漸進的筋弛緩法などのリラクゼーション技法も、心身の緊張を解きほぐし、不安を軽減するのに役立ちます。
ヨガやアロマセラピーの可能性
ヨガは身体的なポーズ、呼吸法、瞑想を組み合わせたもので、心身のバランスを整え、ストレス軽減に効果があるとされています。
アロマセラピーでは特定の植物から抽出したエッセンシャルオイルの香りを利用して、リラックス効果や気分の改善を図ります。ラベンダーやカモミールなどの香りは、鎮静作用があるとされ、不安感の緩和に繋がる可能性があります。
ただし、これらの効果には個人差があり、専門家のアドバイスのもとで行うことが望ましいです。
日常生活でできる予防策 – トリガーを避ける環境作り
抜毛症の症状をコントロールし、再発を防ぐためには、日常生活の中で抜毛のトリガー(引き金)となる状況や感情を特定し、それらをできるだけ避けるような環境を整えることが重要です。
自己観察を通じて、どのような時に抜毛しやすいかを把握しましょう。
抜毛しやすい状況の特定と回避
多くの人にとって、一人でいる時、退屈している時、テレビを見ている時、読書中、あるいは勉強や仕事で集中している時に無意識に毛を抜いてしまうことがあります。また、鏡を見ることで抜毛衝動が誘発されることもあります。
これらの状況を意識し、可能な範囲で環境を調整します。例えば、手に何か持つ、手袋をする、鏡を覆うなどの対策が考えられます。

一般的な抜毛トリガーと対策例
| トリガーとなる状況・感情 | 具体的な対策例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 退屈、手持ち無沙汰 | 手を使う趣味(編み物、パズル)、フィジェットトイ | 手を別の活動で忙しくする |
| ストレス、不安 | リラクゼーション技法の実践、相談 | 感情の波を穏やかにする |
| 鏡を見る | 鏡を見る時間を制限、鏡を一部覆う | 視覚的刺激の低減 |
物理的なバリアの設置
抜毛行動を物理的に困難にする工夫も有効です。例えば、家でリラックスしている時には帽子やスカーフを着用する、指先に絆創膏を貼る、手袋をするなどが挙げられます。
これにより、無意識に髪や眉毛、まつ毛に手が伸びるのを防ぎ、抜毛衝動に気づくきっかけにもなります。
ストレス管理の重要性 – 健康的な対処法を身につける

抜毛症の多くのケースで、ストレスが症状の悪化や再発の大きな原因となります。そのため、日常生活においてストレスを効果的に管理し、健康的な対処法を身につけることが、治療と予防の両面で非常に重要です。
自分に合ったストレス対処法を見つけ、実践することが求められます。
ストレス源の認識と対処
まず、何が自分にとってストレスの原因となっているのかを具体的に認識することが第一歩です。仕事、人間関係、経済的な問題など、ストレス源は人それぞれです。
原因が特定できれば、それに対して直接的な解決策を講じるか、あるいは受け止め方を変えることで、ストレスの影響を軽減することができます。
- 定期的な運動
- 十分な睡眠
- バランスの取れた食事
- 趣味やリフレッシュの時間
専門家による心理的サポートの活用
ストレス対処法を一人で見つけるのが難しい場合や、ストレスが慢性化している場合には、心理カウンセラーや精神科医などの専門家のサポートを受けることが有効です。
専門家は、個々の状況に合わせた具体的なアドバイスや、ストレス耐性を高めるためのトレーニングを提供してくれます。これにより、より効果的にストレスと向き合い、抜毛行動の改善に繋げることができます。
習慣置換法の実践 – 髪を抜く行動を別の行動に変える

習慣置換法は、抜毛という望ましくない習慣をより建設的、あるいは無害な別の行動に置き換えることを目指す行動療法の一技法です。
抜毛したいという衝動を感じた際に意識的に別の行動をとることで、徐々に抜毛の頻度を減らしていくことを目標とします。この方法は、認知行動療法の一部として取り入れられることが多いです。
代替行動の選択とトレーニング
代替行動は抜毛衝動を感じたときにすぐに行える、自分にとって実行しやすいものであることが重要です。例えば、手を強く握りしめる、ストレスボールを握る、指を組む、腕を組む、趣味の道具に触れるなどが挙げられます。
これらの行動を抜毛衝動のサイン(例:手が頭や顔に近づく、特定の場所を触る)に気づいた直後に行うように練習します。
代替行動の具体例
| 衝動を感じる部位 | 代替行動の例 | ポイント |
|---|---|---|
| 頭髪 | こぶしを握る、頭皮マッサージ器を使う(優しく) | 手を髪から遠ざける |
| 眉毛・まつ毛 | 顔に触れないように腕を組む、アイマスクを短時間つける | 顔への接触を避ける |
| 全般 | 深呼吸をする、好きな音楽を聴く、場所を変える | 気分転換を図る |
自己報酬システムの導入
習慣置換法を継続し、抜毛を我慢できた際には、自分自身にご褒美を与えることも有効な動機づけになります。
ご褒美は物質的なものに限らず、好きなことをする時間を作る、自分を褒めるなど、達成感を感じられるものであれば何でも構いません。これにより、新しい習慣の定着を促し、治療へのモチベーションを維持します。
再発防止のためのセルフモニタリング – 継続的な自己観察
抜毛症の治療がある程度進み、症状が改善してきた後も、再発を防止するためにはセルフモニタリング(自己観察)を継続することが非常に大切です。
どのような状況で再び抜毛しそうになるか、その時の感情や思考はどうだったかを記録し続けることで、再発の兆候を早期に察知し、適切な対策を講じることができます。
抜毛日記の活用
抜毛した日時、場所、状況、その時の気分、抜く前に何をしていたか、抜いた後の気持ちなどを記録する「抜毛日記」は、自己理解を深め、再発防止に役立つツールです。
記録を振り返ることで自分の抜毛パターンやトリガーを客観的に把握し、予防策を立てやすくなります。スマートフォンアプリなどを活用するのも良いでしょう。
セルフモニタリングで記録する項目
| 記録項目 | 具体的内容 | 分析の視点 |
|---|---|---|
| 日時・場所 | いつ、どこで抜毛したか | 特定の時間帯や場所との関連性 |
| 状況・活動 | 抜毛前に何をしていたか(例:テレビ視聴、勉強) | 特定の活動がトリガーになっていないか |
| 感情・思考 | 抜毛時の気分(例:不安、退屈、緊張) | 感情と抜毛行動の結びつき |
早期警戒サインへの対応
セルフモニタリングを通じて、自分なりの「早期警戒サイン」を認識することが重要です。
例えば、「最近ストレスが溜まっているな」「無意識に髪を触る回数が増えてきたな」といったサインに気づいたら、意識的にリラクゼーションを取り入れたり、代替行動を強化したり、必要であれば再度専門医に相談するなど、早めに対処することで本格的な再発を防ぐことができます。
サポートグループと家族の理解 – 回復を支える環境づくり
抜毛症からの回復には、本人の努力だけでなく、周囲の理解とサポートが大きな力となります。
特に、同じ悩みを抱える人々と繋がるサポートグループへの参加や、家族の正しい理解と協力は、孤独感を和らげ、治療へのモチベーションを維持する上で非常に重要です。
サポートグループ参加のメリット
サポートグループでは、同じ抜毛症の悩みを抱える仲間と体験や情報を共有し、共感し合うことができます。「自分だけではない」という安心感は、心理的な負担を大きく軽減します。
また、他の人の対処法や成功体験を聞くことで、新たな気づきや治療へのヒントを得られることもあります。
- 孤独感の軽減
- 情報交換と共感
- 新たな対処法の発見
- 治療継続の動機づけ
家族や近しい人々の関わり方
家族やパートナーなど、身近な人々が抜毛症について正しく理解し、本人の気持ちに寄り添ったサポートをすることが大切です。
抜毛行為を単に「悪い癖」として非難したり、無理にやめさせようとしたりするのではなく、本人が抱えるストレスや不安に耳を傾け、治療を温かく見守る姿勢が求められます。
皮膚科や精神科の医師から、家族向けのガイダンスを受けることも有効です。
家族ができるサポート
| サポートの種類 | 具体的な行動 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 理解と共感 | 病気について学び、本人の気持ちを受け止める | 本人の安心感、信頼関係の構築 |
| 治療への協力 | 通院の付き添い、治療法の情報を共有する | 治療の継続と効果向上 |
| 安心できる環境作り | 過度な注目を避け、リラックスできる雰囲気を作る | ストレスの軽減、抜毛衝動の抑制 |
よくある質問
- 抜毛症は意志の弱さが原因ですか
-
いいえ、抜毛症は意志の弱さや単なる癖ではなく、精神医学的な診断がつくこともある衝動制御の問題です。ストレスや不安、遺伝的要因、脳機能の偏りなどが複雑に関与していると考えられています。
自己嫌悪に陥る必要はなく、専門的な治療やサポートによって改善を目指せるものです。
- 抜毛症で髪の毛や眉毛が薄くなったら、もう生えてきませんか
-
毛を抜く行為が長期間続くと、毛根がダメージを受け、永久に毛が生えてこなくなる可能性もあります。しかし、早期に抜毛行動を止め、頭皮や毛根のケアを行えば、多くの場合、毛髪は再生します。
皮膚科医に相談し、頭皮の状態を診断してもらい、適切なアドバイスや治療(ミノキシジル外用など)を受けることが重要です。
- 子供が髪を抜いているようなのですが、どう対応すれば良いですか
-
まず、お子さんの行動を叱ったり、無理にやめさせようとしたりするのは避けましょう。背景にストレスや不安があるかもしれません。優しく話を聞き、安心できる環境を作ることが大切です。
症状が続くようであれば、小児科医や児童精神科医、皮膚科医などの専門医に相談することを検討してください。早期の対応が症状の改善に繋がります。
- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか
-
治療期間は、症状の重さ、併存する精神的な問題の有無、治療法の種類、本人の取り組み方などによって大きく異なります。数ヶ月で改善が見られる場合もあれば、年単位でのケアが必要な場合もあります。
焦らず、専門医と相談しながら、一歩ずつ治療を進めていくことが大切です。セルフモニタリングを続け、再発防止に努めることも長期的な視点では重要になります。
抜毛症のより詳しい原因や、病院で行われる検査方法については、「抜毛症(トリコチロマニア)の原因と検査法」で解説しています。
当記事と合わせてお読みいただくことで、抜毛症への理解をさらに深めることができます。
参考文献
FRANÇA, Katlein, et al. Trichotillomania (hair pulling disorder): clinical characteristics, psychosocial aspects, treatment approaches, and ethical considerations. Dermatologic therapy, 2019, 32.4: e12622.
JONES, Grant; KEUTHEN, Nancy; GREENBERG, Erica. Assessment and treatment of trichotillomania (hair pulling disorder) and excoriation (skin picking) disorder. Clinics in dermatology, 2018, 36.6: 728-736.
SNORRASON, Ivar; BERLIN, Gregory S.; LEE, Han-Joo. Optimizing psychological interventions for trichotillomania (hair-pulling disorder): an update on current empirical status. Psychology Research and Behavior Management, 2015, 105-113.
JAFFERANY, Mohammad, et al. Nonpharmacological treatment approach in trichotillomania (hair‐pulling disorder). Dermatologic Therapy, 2020, 33.4: e13622.
EVERETT, Gregory J.; JAFFERANY, Mohammad; SKURYA, Jonathon. Recent advances in the treatment of trichotillomania (hair‐pulling disorder). Dermatologic therapy, 2020, 33.6: e13818.
TORALES, Julio, et al. Hair‐pulling disorder (Trichotillomania): Etiopathogenesis, diagnosis and treatment in a nutshell. Dermatologic therapy, 2021, 34.1: e13466.
STEIN, Dan J., et al. Trichotillomania (hair pulling disorder), skin picking disorder, and stereotypic movement disorder: Toward DSM‐V. Depression and anxiety, 2010, 27.6: 611-626.
WALSH, Kelda H.; MCDOUGLE, Christopher J. Trichotillomania: Presentation, etiology, diagnosis and therapy. American journal of clinical dermatology, 2001, 2: 327-333.
PENZEL, Fred. The hair-pulling problem: A complete guide to trichotillomania. Oxford University Press, 2003.
ROMANOV, Dmitry V., et al. Trichotillomania (hair pulling disorder). In: Psychodermatology in clinical practice. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 197-213.
抜毛症(トリコチロマニア)の関連記事