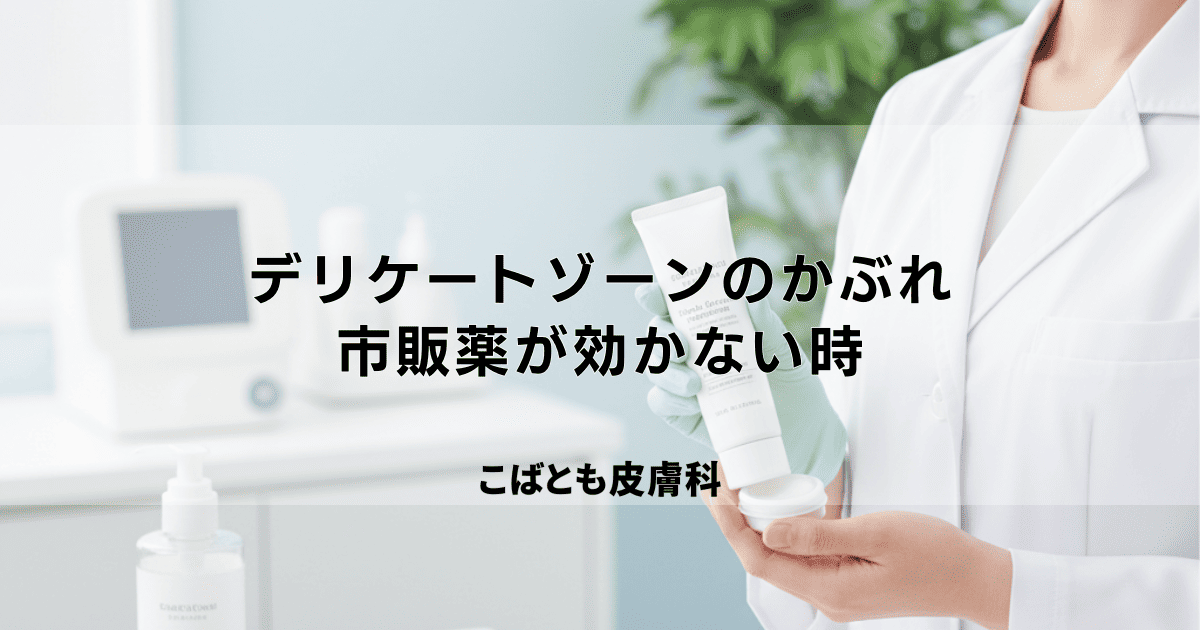デリケートゾーンのかゆみや赤みが誰にも相談できず、市販薬で対処しようと考える人も多いでしょう。
しかし、市販薬を使っても一向に良くならない、あるいは悪化してしまう場合、そこには単なるかぶれとは異なる原因が隠れているかもしれません。
この記事では、デリケートゾーンのかぶれがなぜ起こるのか、市販薬が効かない場合の理由、皮膚科での専門的な対処法について、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
デリケートゾーンのかぶれとは?
デリケートゾーンのかぶれ、医学的には接触皮膚炎と呼ばれるこの症状は、多くの女性が一度は経験する身近なトラブルです。
かゆみや赤み 初期症状の見分け方
デリケートゾーンのかぶれの最も一般的で初期的なサインは、かゆみと赤みで、下着やナプキンが触れる部分がムズムズとかゆくなったり、鏡で見ると皮膚が赤くなっていたりします。
この段階では、単なる刺激による一時的な炎症であることが多いですが、かゆみは非常に強く、我慢できないことも少なくありません。
かゆみの程度や赤みの範囲、特定の物を着用した時だけ症状が出るのか、それとも持続するのか、といった点を初期段階で観察することが大切です。
悪化するとどうなる? 浸出液やただれ
初期のかゆみや赤みを放置したり、かゆいからといって掻きむしってしまったりすると、症状は悪化し、皮膚のバリア機能が破壊され、炎症が強くなると、皮膚がジクジクとした浸出液で湿っぽくなることがあります。
さらに進行すると、皮膚の表面が剥がれてただれた状態(びらん)になることもあり、この段階になると、強い痛みを伴うようになり、排尿時や歩行時にもしみるような痛みを感じます。
かぶれと他の皮膚トラブル(性感染症など)との違い
デリケートゾーンの症状は、すべてがかぶれ(接触皮膚炎)とは限りません。性感染症(ヘルペス、クラミジアなど)や、カンジダなどの真菌感染症、硬化性萎縮性苔癬のような特殊な皮膚疾患も、かゆみやただれを起こすことがあります。
かぶれは通常、原因となる物質が触れた範囲に症状が出ることが多いですが、感染症の場合はおりものの変化(量、色、匂い)を伴ったり、水疱(すいほう)や潰瘍ができたりするなど、特有の症状を示します。
かぶれと感染症の主な違い(目安)
| 症状の特徴 | かぶれ(接触皮膚炎) | 真菌(カンジダ) |
|---|---|---|
| かゆみ | 強い | 非常に強い |
| おりもの | 変化は少ない | 白くカッテージチーズ状 |
| 外陰部の状態 | 赤み、ただれ(原因物質接触部) | 赤み、白い苔状のもの |
放置するリスクと早期対応の重要性
デリケートゾーンのかぶれを「恥ずかしいから」「そのうち治るだろう」と放置することは、多くのリスクを伴います。炎症が慢性化すると、皮膚が厚くゴワゴワしたり、色素沈着を起こして黒ずんだりすることがあります。
これは美容的な問題だけでなく、皮膚が本来持つバリア機能を低下させ、さらに刺激に弱い状態になるという悪循環を生み、また、掻き壊した傷口から細菌が侵入し、二次感染を起こす可能性もあります。
初期の段階で適切に対応すれば、多くのかぶれは比較的短期間で改善するので、症状が軽いうちに原因を見つけ、ケアを始めることが、重症化を防ぐ鍵です。
なぜデリケートゾーンはかぶれやすいのか?
デリケートゾーンは、体の他の部分と比べて非常にトラブルが起きやすい場所です。なぜ外部からの刺激に弱く、かぶれやすいのか、背景にある要因を理解しましょう。
皮膚の薄さと構造的特徴
デリケートゾーン、特に外陰部の皮膚は、腕や脚の皮膚と比べて非常に薄くデリケートです。角質層が薄いため、外部からの刺激物質が侵入しやすく、また皮膚の水分が蒸発しやすい(経皮水分蒸発量が多い)という特徴があります。
粘膜に近い部分もあり、感受性は非常に高いため、少しの摩擦や化学物質の接触でも炎症反応が起こりやすいです。
ムレやすい環境と湿度
デリケートゾーンは、下着や衣類に常に覆われており、解剖学的な構造からも通気性が悪くなりがちな場所です。汗や皮脂、おりもの、尿などが付着しやすく、湿度と温度が高い状態が保たれやすい環境にあります。
高温多湿の環境は、皮膚のバリア機能を低下させる一因となり、皮膚がふやけた状態になると、摩擦によるダメージを受けやすくなり、また細菌や真菌(カビ)が繁殖しやすい絶好の温床ともなります。
摩擦や刺激の影響
日常生活の中で、デリケートゾーンはさまざまな物理的刺激にさらされていて、歩行や運動による衣類との摩擦、タイトなジーンズやガードルなどによる圧迫、自転車や長時間の座位による影響などです。
また、トイレットペーパーでの拭きすぎや、ゴシゴシと強く洗う行為も、皮膚の表面を傷つける原因となります。皮膚が薄く敏感なため、繰り返しの摩擦や圧迫が蓄積することで、微細な傷から炎症が起き、かぶれへと発展しやすいです。
デリケートゾーンへの主な物理的刺激
| 刺激の種類 | 具体例 | 対策のヒント |
|---|---|---|
| 摩擦 | 歩行、タイトな下着、洗いすぎ | 綿素材、ゆったりした衣類、優しく洗う |
| 圧迫 | スキニージーンズ、ガードル | 締め付けの少ない服装を選ぶ |
| ムレ | ナプキン、通気性の悪い下着 | こまめな交換、通気性の良い素材 |
女性ホルモンと皮膚バリア機能の関係
女性の皮膚の状態は、月経周期に伴う女性ホルモン(エストロゲンとプロゲステロン)の変動に大きく影響されます。特に、月経前はプロゲステロン(黄体ホルモン)の影響で皮脂分泌が活発になり、皮膚がやや不安定になりがちです。
また、閉経後はエストロゲンの分泌が急激に減少し、皮膚全体の乾燥が進み、デリケートゾーンも例外ではありません。皮膚が乾燥するとバリア機能が低下し、萎縮(いしゅく)も伴うため、わずかな刺激でもかゆみや炎症を感じやすくなります。
デリケートゾーンかぶれの主な原因
デリケートゾーンにかぶれを起こす原因は、一つではなく、多くの場合いくつかの要因が組み合わさっています。
下着や衣類による刺激(素材、締め付け)
毎日身につける下着や衣類が、かぶれの原因となることがあり、特に化学繊維(ポリエステル、ナイロンなど)は、吸湿性が低くムレやすいため、デリケートゾーンの環境を悪化させる可能性があります。
人によっては素材自体がアレルギーの原因(アレルギー性接触皮膚炎)となり、また、レースや縫い目などの硬い部分が擦れて物理的な刺激となることも少なくありません。
さらに、体を締め付けるタイトな下着や、スキニージーンズ、ガードルなどは、血流を妨げ、摩擦や圧迫を強めるため、かぶれのリスクを高めます。
ナプキンやおりものシートによる接触皮膚炎
生理用ナプキンやおりものシートは、デリケートゾーンの皮膚に長時間密着するものです。含まれる素材(高分子吸収剤、香料、接着剤など)が肌に合わず、刺激性またはアレルギー性の接触皮膚炎を起こすことがあります。
また、吸収された経血やおりものが皮膚に触れ続けること自体が刺激となり、ムレと相まって炎症を悪化させ、長時間交換しないで使用を続けると、雑菌が繁殖しやすくなり、かぶれだけでなく感染症のリスクも高まります。
汗や皮脂、尿やおりものによる刺激
デリケートゾーンは汗腺や皮脂腺が多く分布しており、汗や皮脂の分泌が活発な場所で、皮膚の表面に留まることで、かゆみや炎症を起こすことがあります。
また、尿やおりもの、便などが微量に皮膚に付着することも、アルカリ性や酵素による刺激となり、皮膚のバリア機能を低下させる原因です。
誤った洗い方や石鹸の使いすぎ
デリケートゾーンを清潔に保とうとするあまり、洗いすぎているケースも多く見られます。
ナイロンタオルなどでゴシゴシこすったり、殺菌作用の強い石鹸やボディソープで何度も洗ったりすると、皮膚の表面を保護している必要な皮脂膜や常在菌まで洗い流してしまうので注意が必要です。
皮膚のバリア機能が損なわれると乾燥しやすくなり、外部からの刺激に非常に弱くなり、また、膣内まで石鹸で洗うことは、膣内の酸性度(pH)バランスを崩し自浄作用を低下させ、かえって感染症を招きやすくします。
清潔ケアの注意点
- 洗浄力の強すぎる石鹸、ボディソープは避ける
- デリケートゾーン専用の弱酸性ソープを検討する
- ナイロンタオルなどでこすらない
- お湯の温度はぬるめ(38~40度程度)にする
- 膣の中までは洗わない
市販薬が効かないのはなぜ?
デリケートゾーンのかぶれで市販薬を試してみたものの、一向に良くならない、あるいはかえって悪化してしまった、という経験はありませんか。自己判断での対処には限界があることを理解しましょう。
原因と薬のミスマッチ
市販薬が効かない最大の理由の一つに、症状の原因と使用した薬の成分が合っていないミスマッチが挙げられます。
デリケートゾーンのかゆみの原因がカンジダという真菌(カビ)であった場合、通常のかぶれ(炎症)を抑えるステロイド外用薬を使用すると、かえってカンジダ菌の増殖を助けてしまい、症状を悪化させることがあります。
細菌感染を疑って抗生剤入りの軟膏を使用しても、原因が化学物質によるかぶれであれば効果は期待できません。
症状と市販薬のミスマッチ例
| 症状の原因(推測) | 間違った市販薬の選択 | 起こりうる結果 |
|---|---|---|
| 真菌(カンジダ) | ステロイド(抗炎症) | 症状の悪化(菌の増殖) |
| かぶれ(炎症) | 抗真菌薬 | 効果なし、刺激の可能性 |
| 細菌感染 | ステロイドのみ | 感染の拡大 |
市販薬の成分による新たな刺激
市販薬に含まれている成分自体が、デリケートゾーンの敏感な皮膚にとって新たな刺激となり、かぶれを起こす可能性があります。
薬の有効成分だけでなく、基剤(軟膏やクリームのベースとなる物質)や、防腐剤、香料などが肌に合わないケースです。良かれと思って塗った薬で、かゆみや赤みがさらに強くなった場合は、すぐに使用を中止する必要があります。
症状が進行しすぎているケース
市販薬で対応できるのは比較的軽度の炎症に限られ、すでに症状が悪化し、皮膚がただれたり浸出液が出たりしている状態、あるいは掻き壊しによって二次感染を起こしている可能性がある場合、市販薬の弱い作用では炎症を抑えきれません。
重症化した状態では、より強力な抗炎症作用を持つ医療用の薬剤や、感染を抑えるための抗生剤・抗真菌薬の使用が必要です。
市販薬を数日間(例えば3~5日)使用しても改善が見られない、あるいは悪化するようであれば、セルフケアの限界を超えています。
かぶれではなく別の病気の可能性
市販薬がまったく効かない場合、症状がそもそもかぶれ(接触皮膚炎)ではない可能性を考える必要があります。
デリケートゾーンには性感染症(ヘルペス、尖圭コンジローマなど)や、自己免疫が関わる特殊な皮膚疾患(硬化性萎縮性苔癬、扁平苔癬など)、皮膚がん(パジェット病など)といった、診断と治療を要する病気が隠れていることもあります。
しこりがある、皮膚が白く変色している、ただれが長期間治らないといった場合は、自己判断を続けず、必ず皮膚科専門医の診察を受けてください。
かぶれと間違いやすいデリケートゾーンの病気
デリケートゾーンのかゆみやただれは、すべてがかぶれによるものとは限らず、市販薬で改善しない場合、かぶれ以外の病気が潜んでいる可能性を疑うことが重要です。
カンジダ(真菌)性皮膚炎
カンジダは、もともと皮膚や膣内に存在する常在菌(真菌の一種、カビの仲間)ですが、疲労、ストレス、抗生剤の使用、妊娠などで体の抵抗力が落ちたり、ムレなどで環境が悪化したりすると、異常増殖して症状を起こします。
外陰部が赤くなり、非常に強いかゆみを伴い、特徴的なのは、ポロポロとした白いカッテージチーズ状のおりものが増えることです(膣炎を併発した場合)。
皮膚だけの場合は、赤みと強いかゆみに加え、皮膚の表面に小さな水疱や膿疱(うみを持ったブツブツ)ができ、その周りがふやけて白っぽくなることもあります。
かぶれと間違えてステロイド外用薬を使用すると、劇的に悪化するため注意が必要です。
細菌性膣症や他の感染症
細菌性膣症は、膣内の常在菌のバランスが崩れ、特定の細菌が増殖することで起こります。主な症状は、魚が腐ったような生臭い匂い(アミン臭)のある、水っぽく灰色がかったおりものが増えることです。
かゆみは軽度か、ない場合も多いですが、この異常なおりものが外陰部を刺激し、かぶれ(刺激性皮膚炎)を起こすことがあります。
他にも、トリコモナス膣炎(強いかゆみと泡立ったおりもの)や、性感染症であるクラミジア、淋菌、ヘルペスなども、デリケートゾーンの不快な症状の原因です。
感染症による主な症状
- 細菌性膣症: 魚臭い匂い、灰色のおりもの
- トリコモナス: 強いかゆみ、泡立ったおりもの
- ヘルペス: 強い痛みを伴う水疱
硬化性萎縮性苔癬などの皮膚疾患
硬化性萎縮性苔癬は、デリケートゾーン(外陰部や肛門周囲)の皮膚が白っぽく変色し、硬くなり、萎縮していく原因不明の皮膚疾患です。
中年以降の女性に多く見られ、初期症状は強いかゆみやヒリヒリ感であることが多く、かぶれやカンジダと間違われやすく、進行すると皮膚が薄く傷つきやすくなり、ただれたり、性交痛が出たり、外陰部の形が変形したりすることもあります。
長期化すると皮膚がんを発生するリスクもわずかに上がると言われており、専門医による長期的な管理が必要で、市販薬では改善しません。
かぶれと硬化性萎縮性苔癬の比較
| 項目 | かぶれ(接触皮膚炎) | 硬化性萎縮性苔癬 |
|---|---|---|
| 主な症状 | かゆみ、赤み、ただれ | 強いかゆみ、ヒリヒリ感、皮膚の白色化 |
| 皮膚の状態 | ジクジクまたはカサカサ | 白く硬くなる、薄くシワが寄る |
| 進行 | 原因除去で改善 | 慢性、進行性(形態変化も) |
アレルギー性接触皮膚炎
刺激性接触皮膚炎(かぶれ)とは別に、特定の物質に対してアレルギー反応(IV型アレルギー)を起こし、炎症が生じるのがアレルギー性接触皮膚炎です。
原因となる物質(アレルゲン)に触れてから1~2日経ってから、強いかゆみと赤み、時には水疱を伴う湿疹が現れます。
デリケートゾーンでは、ナプキンやおりものシートの素材、消毒薬、外用薬の成分、下着の染料、ラテックス(コンドーム)などが原因となり得ます。
一度感作(アレルギーが成立)してしまうと、ごく微量の接触でも症状を繰り返すようになるので、原因物質を特定し、徹底的に避けることが唯一の対策です。
市販薬が効かない時のセルフケア見直し
市販薬を試してもデリケートゾーンのかぶれが改善しない場合、薬だけに頼るのではなく、日常生活の習慣(セルフケア)を見直すことが非常に重要です。
デリケートゾーンの正しい洗い方
清潔を保つことは大切ですが、洗いすぎは逆効果で、デリケートゾーンを洗う際のポイントは優しく、洗いすぎないことです。
ゴシゴシこするのは厳禁で、ナイロンタオルやスポンジは使わず、デリケートゾーン専用の低刺激性(弱酸性)のソープ、またはお湯のみで洗います。
ソープを使う場合は、手でよく泡立て、その泡で外陰部のヒダやシワの間をなでるように優しく洗い、洗い残しがないよう、ぬるま湯(38~40度程度)で十分にすすぎます。熱すぎるお湯は、皮膚の乾燥を招くため避けてください。
また、膣の中まで洗う(ビデの使いすぎも含む)必要はありません。膣には自浄作用があり、洗いすぎるとバランスを崩してしまいます。
洗い方の「優しく」のポイント
| 項目 | 推奨される方法 | 避けるべき方法 |
|---|---|---|
| 洗浄剤 | 低刺激性ソープまたはお湯のみ | 殺菌性の強い石鹸、ボディソープ |
| 洗い方 | 手のひらや指の腹で優しく | ナイロンタオル、スポンジでこする |
| お湯の温度 | ぬるま湯(38~40度) | 熱いお湯 |
下着や衣類の選び方(素材、通気性)
デリケートゾーンのムレと摩擦は、かぶれを悪化させる大きな要因です。下着は、吸湿性と通気性に優れた綿(コットン)100%のものが最も推奨され、化学繊維のものは避けましょう。
デザインも、レースや装飾が多いものより、縫い目が少なくシンプルなものが肌への刺激を減らします。
サイズ感も重要で、体を締め付けるきつい下着や、ガードル、スキニージーンズは、摩擦と圧迫、ムレの原因となるため、症状が落ち着くまでは避け、ゆったりとした通気性の良い服装を心がけてください。
下着選びのポイント
- 素材は「綿(コットン)」を選ぶ
- 通気性と吸湿性が良いもの
- 締め付けないサイズ感
- レースや縫い目が少ないデザイン
生活習慣の改善(食生活、睡眠、ストレス)
皮膚の健康は、体全体の健康状態と密接に関連していて、デリケートゾーンのかぶれが長引く背景に、生活習慣の乱れが隠れていることもあります。 まず、十分な睡眠と休息を取り、疲労をためないことが大切です。
体の免疫力が低下すると、皮膚のバリア機能も弱まり、炎症が治りにくくなり、 ストレスも、かゆみを強く感じさせたり、ホルモンバランスを乱したりすることで、症状を悪化させる一因となります。
リラックスできる時間を作り、上手にストレスを発散させる工夫をしましょう。
食生活においては、極端なダイエットや偏った食事は避け、栄養バランスの取れた食事を心がけ、皮膚の再生に必要なビタミンB群や、抗酸化作用のあるビタミンC、Eなどを意識して摂ることが大切です。
刺激物やアルコールの過剰摂取は、かゆみを増強させることがあるため、症状が強い時は控えてください。
生理用品の見直しと交換頻度
生理用ナプキンやおりものシートが原因で、かぶれている可能性は非常に高いです。
ナプキンには、表面の素材(メッシュ、コットンなど)や、吸収剤の種類によって多くの製品があり、特定の製品でかゆみが出るなら、別の素材(特に肌に優しいとされるコットン素材)のものに変えてみましょう。
最も重要なのは、交換頻度です。経血やおりものを吸収したナプキンは、ムレと雑菌の温床なので、症状がある時は特に、こまめに(少なくとも2~3時間ごと)交換することを徹底してください。
ナプキンではなく、タンポンや月経カップなど、外陰部に触れないタイプの生理用品に一時的に変えてみるのも、皮膚を休ませる良い方法です。
生理用品の選択肢
| 種類 | 特徴 | かぶれ対策 |
|---|---|---|
| ナプキン(コットン) | 肌当たりが優しい | 肌に合うものを選び、こまめに交換 |
| ナプキン(メッシュ) | サラサラ感が続くが、肌に合わない人も | かゆみが出たらコットン素材に変更 |
| タンポン・月経カップ | 外陰部に触れない | ムレ・かぶれ対策に有効な選択肢 |
皮膚科での診断と治療
市販薬を5~7日程度使用しても改善しない、症状が悪化する、あるいは何度も繰り返す場合は、自己判断でのケアを中止し、速やかに皮膚科または婦人科を受診してください。
皮膚科を受診するタイミング
以下のような症状が見られたら、市販薬での対処をやめ、皮膚科を受診することが大切です。
受診を推奨するタイミング
- 市販薬を5日以上使っても良くならない
- 市販薬を使ったら、かえって症状が悪化した
- かゆみが非常に強く、日常生活や睡眠に支障が出ている
- 皮膚がただれて浸出液が出ている、または出血している
- おりものの色、量、匂いに明らかな異常がある
どのような検査を行うか
皮膚科では、まず問診(いつから、どのような症状か、市販薬の使用歴、生理用品など)と、視診(患部の状態を直接見る)を行います。
かぶれ以外の病気、特に感染症が疑われる場合は、追加の検査を行い、カンジダや細菌を調べるために、患部やおりものを綿棒でこすって採取し、顕微鏡で観察したり、培養検査に出したりすることがあります。
主な治療薬(外用薬、内服薬)
診断に基づいて治療薬が処方され、原因がかぶれ(接触皮膚炎)であれば、炎症を抑えるためのステロイド外用薬が処方されるのが一般的です。
ステロイドと聞くと不安に思うかもしれませんが、デリケートゾーンは薬剤の吸収が良い反面、副作用も出やすいため、医師は症状と部位に合わせて適切な強さのステロイドを選択します。
カンジダが原因であれば、抗真菌薬(ステロイドは含まない、またはごく弱いステロイドとの合剤)が処方され、 細菌感染が疑われる場合は、抗生剤の外用薬や内服薬が使われます。
また、かゆみが非常に強い場合は、抗ヒスタミン薬の内服薬が併用されることもあります。
主な治療薬の例
| 原因 | 主な治療薬 | 目的 |
|---|---|---|
| かぶれ(炎症) | ステロイド外用薬 | 炎症を抑える |
| カンジダ(真菌) | 抗真菌薬 外用・内服 | 菌を殺す・抑える |
| 細菌感染 | 抗生剤 外用・内服 | 細菌を殺す・抑える |
治療期間の目安と再発予防
単純なかぶれであれば、ステロイド外用薬を数日~1週間程度使用すれば、かゆみや赤みは急速に改善することが多いです。しかし、カンジダや慢性化した湿疹の場合は、症状が消えてからも一定期間、治療の継続が必要な場合があります。
自己判断で「良くなった」と薬をやめてしまうと、すぐに再発することがあるため、必ず医師の指示に従ってください。 治療と並行して、原因となった生活習慣(洗い方、下着、生理用品など)の改善を指導されます。
デリケートゾーンのかぶれに関するよくある質問
治らないデリケートゾーンのかぶれについて、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
- どのくらい市販薬を試して効かなかったら病院に行くべきですか?
-
市販薬を使用して5日から1週間程度経っても、症状が全く改善しない、あるいは悪化する場合は、使用を中止して皮膚科を受診してください。
また、期間に関わらず、市販薬を使用してかゆみや痛みが強くなった場合や、水疱、ただれなど、明らかに症状が悪化した場合は、すぐに使用をやめて受診しましょう。市販薬で対応できるのは軽症の場合のみです。
- 病院ではどのような服装で行けばよいですか?
-
デリケートゾーン(外陰部)の診察では、下着とズボンやスカートを脱いでいただく必要があります。
タイトなジーンズや重ね着など、着脱に時間がかかる服装よりは、ゆったりとしたスカートや、すぐに着脱できるパンツスタイルが便利です。
診察室ではタオルやシーツで体を覆うなどの配慮がありますので、服装について過度に心配する必要はありません。
- 完治後、再発しないために最も気をつけることは何ですか?
-
デリケートゾーンのかぶれは一度治っても再発しやすいので、原因となった刺激や環境を日常生活から取り除くことが重要です。
通気性の良い綿素材の下着を選び、締め付ける服装を避けてム」と摩擦を軽減し、清潔にしたいあまり洗いすぎないことを日頃から意識することが、健康な皮膚状態を保つための鍵となります。
以上
参考文献
Mikamo H, Matsumizu M, Nakazuru Y, Okayama A, Nagashima M. Efficacy and safety of a single oral 150 mg dose of fluconazole for the treatment of vulvovaginal candidiasis in Japan. Journal of Infection and Chemotherapy. 2015 Jul 1;21(7):520-6.
Mikamo H, Kawazoe K, Izumi K, Watanabe K, Ueno K, Tamaya T. Comparative study on vaginal or oral treatment of bacterial vaginosis. Chemotherapy. 1997 Sep 11;43(1):60-8.
Mikamo H, Izumi K, Ito K, Tamaya T. Comparative study of the effectiveness of oral fluconazole and intravaginal clotrimazole in the treatment of vaginal candidiasis. Infectious diseases in obstetrics and gynecology. 1995;3(1):7-11.
Kobayashi T, Amenomori Y. Results of a Clinical Investigation of Clotrimazole (Canesten), A New Anti-Mycotic Substance, in the Therapy of Vaginal Fungal Infections. Journal of International Medical Research. 1974 Sep;2(5):366-9.
Arpa MD, Yoltaş A, Onay Tarlan E, Şenyüz CŞ, Sipahi H, Aydın A, Üstündağ Okur N. New therapeutic system based on hydrogels for vaginal candidiasis management: formulation–characterization and in vitro evaluation based on vaginal irritation and direct contact test. Pharmaceutical Development and Technology. 2020 Nov 25;25(10):1238-48.
Mizuno S, Cho N. Clinical evaluation of three-day treatment of vaginal mycosis with clotrimazole vaginal tablets. Journal of International Medical Research. 1983 May;11(3):179-85.
Hainer BL, Gibson MV. Vaginitis: diagnosis and treatment. American family physician. 2011 Apr 1;83(7):807-15.
Ayehunie S, Cannon C, LaRosa K, Pudney J, Anderson DJ, Klausner M. Development of an in vitro alternative assay method for vaginal irritation. Toxicology. 2011 Jan 11;279(1-3):130-8.
Gupta M. Assessment of oral toxicity and vaginal irritation test of novel antimicrobial mucoadhesive herbal vaginal tablet for the treatment of vaginitis. International Journal of Green Pharmacy (IJGP). 2018 Mar 5;12(01).
Ries AJ. Treatment of vaginal infections: candidiasis, bacterial vaginosis, and trichomoniasis. Journal of the American Pharmaceutical Association (1996). 1997 Sep 1;37(5):563-9.