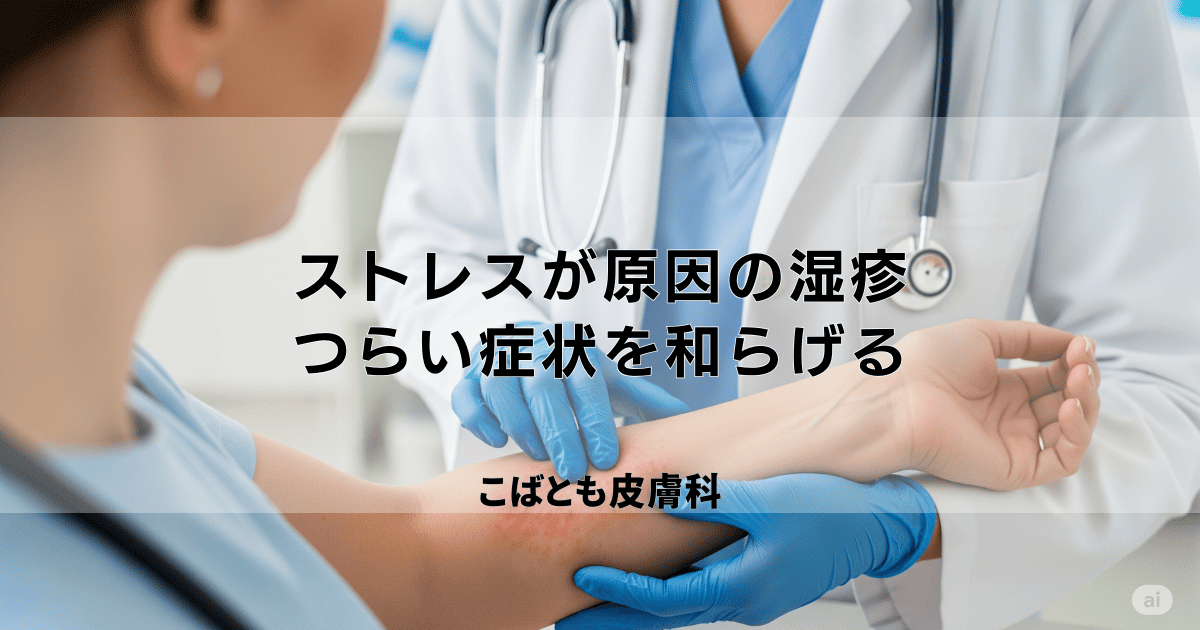強いストレスを感じると、肌にかゆみや湿疹が出ることがありませんか。実は、心と皮膚は深くつながっており、ストレスが引き金となってさまざまな皮膚トラブルが現れることは珍しくありません。
仕事や人間関係の悩み、環境の変化などが、知らず知らずのうちに肌への負担となっているのです。
この記事では、ストレスが原因で起こるかゆみ、湿疹、痒疹の症状と、そのつらい症状を和らげるためのセルフケア方法を詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
ストレスと皮膚の密接な関係
心の問題が体に影響を及ぼすことは広く知られていますが、特に皮膚は心の状態を映し出す鏡とも言えるほど、密接な関係を持っています。背景には、自律神経やホルモン、免疫といった体の基本的な仕組みが複雑に関わり合っています。
心と皮膚のつながり
皮膚と脳は、受精卵が細胞分裂していく初期段階で、同じ外胚葉という組織から分かれて作られていて、起源を同じくするため、両者は生涯を通じて互いに情報をやり取りし、影響を与え合う関係にあります。
緊張すると手汗をかいたり、恥ずかしいと顔が赤くなったりするのも、このつながりを示す身近な例です。精神的な緊張や不安が皮膚の知覚神経を過敏にし、わずかな刺激でもかゆみとして感じさせてしまうことがあります。
長引く皮膚の不快な症状が、気分の落ち込みやいらだちを引き起こし、精神的な健康を損なうことも少なくありません。
ストレスが自律神経に与える影響
ストレスは、体のアクセル役である交感神経と、ブレーキ役である副交感神経からなる自律神経のバランスを大きく乱す原因です。
通常、日中の活動時には交感神経が、休息時や夜間には副交感神経が優位に働き、体の状態を適切に調整していますが、慢性的なストレスにさらされると、交感神経が過剰に働き続ける状態に陥ります。
交感神経の過緊張は、血管を収縮させて全身の血行を悪化させ、皮膚への血流が滞ると、細胞の隅々まで十分な酸素や栄養素が供給されなくなり、老廃物の排出も遅れます。
このことにより、皮膚の再生能力(ターンオーバー)が乱れ、健康な状態を保つ力が全体的に弱まってしまうのです。さらに、皮脂や汗の分泌バランスも崩れ、肌が乾燥したり脂っぽくなったりと、不安定な状態に傾きます。
免疫機能の低下と皮膚バリア機能
皮膚の最も外側にある角層には、外部の刺激(紫外線、乾燥、アレルゲン、細菌など)から体を守り、内部の水分蒸発を防ぐための精巧なバリア機能が備わっています。
しかし、長引くストレスは、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を促し、体の免疫機能を低下させます。皮膚においては、外部からの異物を監視するランゲルハンス細胞などの免疫細胞の働きを抑制してしまいます。
バリア機能が弱まると、これまで問題にならなかったような、ほこりや花粉、化粧品などのわずかな刺激にも皮膚が過敏に反応し、乾燥やかゆみ、炎症を起こしやすくなるのです。
ストレスが起こす体の変化
| 影響を受ける部分 | ストレスによる変化 | 皮膚への影響 |
|---|---|---|
| 自律神経 | 交感神経が優位になり続ける | 血行不良、皮脂・汗の分泌異常、ターンオーバーの乱れ |
| 免疫系 | 免疫バランスが乱れ、機能が低下する | バリア機能の低下、外部刺激への過敏反応、炎症の悪化 |
| ホルモンバランス | コルチゾール(ストレスホルモン)の増加 | 皮膚の再生能力低下、皮脂の過剰分泌、コラーゲン破壊 |
ストレスによって現れる皮膚症状の種類と特徴
ストレスが原因で現れる皮膚症状は、一つではありません。じんましんのように数時間で消える急性のものから、湿疹や痒疹のように数週間から数ヶ月続く慢性のものまで、現れ方はさまざまです。
突然のかゆみと蕁麻疹(じんましん)
強いプレッシャーや緊張を感じた直後などに、突然、皮膚の一部が蚊に刺されたように赤く盛り上がり、激しいかゆみを伴うことがあります。
これは蕁麻疹(じんましん)と呼ばれ、個々の発疹(膨疹)は数十分から数時間で跡形もなく消えるのが大きな特徴です。ストレスによって自律神経が乱れ、皮膚にある肥満細胞が刺激されると、かゆみの原因物質であるヒスタミンなどが放出されます。
ヒスタミンが皮膚の血管に作用して血液成分を漏れ出させ、赤みや盛り上がり、かゆみを引き起こし、特定の食べ物や薬のアレルギーがなくても、精神的な要因だけで発症する心因性蕁麻疹は珍しくありません。
繰り返す湿疹と皮膚炎
湿疹は、皮膚の表面に起こる炎症の総称で、赤み、細かいぶつぶつ(丘疹)、小さな水ぶくれ(小水疱)、じゅくじゅくした状態(びらん)、かさぶた(痂皮)など、多彩な症状が混在して現れます。
ストレスは、アトピー性皮膚炎や、皮脂の分泌が多い部位にできる脂漏性皮膚炎などを悪化させる明確な要因です。
また、はっきりとした外的要因がないにもかかわらず、首筋や目の周り、肘や膝の内側など、特定の場所に湿疹が繰り返し現れる場合、ストレスが関与している可能性を考えます。
硬くなる痒疹(ようしん)
痒疹は、強いかゆみを伴う、ドーム状に硬く盛り上がった発疹(丘疹や結節)です。掻き壊しを執拗に繰り返すことで、皮膚がだんだんと厚く、ゴワゴワした象の皮膚のような状態(苔癬化:たいせんか)になります。
腕や脚に多発する結節性痒疹は、虫刺されと間違われることもありますが、かゆみは非常に激しく夜も眠れないほどで、生活の質を大きく損なうことがあります。
耐えがたいかゆみ自体がさらなるストレスとなり、症状を悪化させる悪循環に陥りやすい、非常に厄介な皮膚疾患の一つです。
主なストレス性皮膚症状の比較
| 症状名 | 主な特徴 | かゆみの強さ |
|---|---|---|
| 蕁麻疹 | 赤く盛り上がる発疹(膨疹)、数時間で消退と出現を繰り返す | 強い |
| 湿疹・皮膚炎 | 赤み、ぶつぶつ、じゅくじゅくなど多彩な症状が混在、持続する | 中程度~強い |
| 痒疹 | 硬い盛り上がり(結節)、掻き壊しで悪化し苔癬化する | 非常に強い |
なぜストレスでかゆみや湿疹が悪化するのか
ストレスが皮膚症状の引き金になるだけでなく、一度現れた症状を長引かせ、悪化させる大きな要因にもなります。かゆみを感じて掻いてしまう行動や、治らないことへの不安感が、さらなる悪化を招く負の連鎖を生み出してしまうのです。
かゆみの悪循環(イッチ・スクラッチサイクル)
かゆみを感じると、私たちは反射的に皮膚を掻いてしまいます。
掻くという行為は、一時的にかゆみの感覚を痛みの感覚で上書きし、紛らわせることができますが、代償は大きく、爪で皮膚のバリア機能を物理的に破壊し、外部からの刺激が侵入しやすい無防備な状態にしてしまいます。
ダメージがさらなる炎症を起こし、炎症細胞から新たなかゆみ誘発物質が放出され、皮膚の知覚神経を刺激し、もっと強いかゆみ信号を脳に送る、という最悪の悪循環に陥ります。
これが、イッチ・スクラッチサイクルと呼ばれるものです。
睡眠不足がもたらす肌へのダメージ
ストレスや、特に夜間に強くなるかゆみは、質の良い睡眠を妨げる大きな要因ですが、私たちの皮膚細胞がダメージを修復し、新しく生まれ変わる(ターンオーバー)のは、主に成長ホルモンが分泌される深い睡眠中です。
睡眠不足が続くと、この貴重な修復時間が奪われ、皮膚のターンオーバーが著しく乱れ、バリア機能の回復が遅れ、皮膚はますます乾燥して敏感になり、外部からの刺激に対して脆弱になります。
無意識の掻き壊しとそのリスク
仕事に集中している時やテレビを見ている時、就寝中など、自分でも気づかないうちに皮膚をポリポリと掻きむしっていることはありませんか。無意識の掻き壊しは、症状をじわじわと悪化させる大きな原因です。
さらに深刻なのは、掻き傷からの二次感染のリスクです。
爪の間には黄色ブドウ球菌などの細菌が常にあり、掻き壊した傷からこれらの細菌が侵入すると、とびひ(伝染性膿痂疹)や、皮膚の深い部分まで炎症が及ぶ蜂窩織炎(ほうかしきえん)といった、より深刻な皮膚感染症につながる危険性があります。
かゆみの悪循環を断ち切るための初期対応
| 行動 | 目的 | 具体的な方法 |
|---|---|---|
| 冷やす | かゆみの神経活動を一時的に鎮める | 清潔なタオルで包んだ保冷剤を数分間当てる |
| 保湿する | 乾燥を防ぎ、バリア機能を物理的に補う | 低刺激性の保湿剤をこすらず優しく塗布する |
| 掻く以外の行動 | かゆみから意識をそらし、掻破行動を置き換える | 軽くたたく、つねる、趣味や作業に没頭する |
日常生活で実践できるストレス対策
皮膚症状の根本的な改善を目指すには、かゆみや湿疹に対する直接的なケアと並行して、原因であるストレス自体を上手に管理し、軽減することが重要です。
自分に合ったリラックス方法を見つける
人によって心からリラックスできる方法は異なります。大切なのは、これをやらなければと義務感でやるのではなく、自分が本当に心地よいと感じ、楽しめる時間を持つことです。
好きなアーティストの音楽をじっくり聴く、ぬるめのお湯に好きな香りの入浴剤を入れてゆっくり浸かる、アロマディフューザーでラベンダーやカモミールの香りを漂わせるなど、五感に働きかける方法は効果的です。
また、数分間目を閉じて自分の呼吸に意識を向ける深呼吸や瞑想も、場所を選ばず手軽にできる優れたリラックス法で、短時間でも良いので、意識的に仕事や悩みを忘れてスイッチをオフにする時間を作りましょう。
- 深呼吸や瞑想
- 軽いストレッチやヨガ
- ハーブティーを飲む
- 自然の中で過ごす
- 親しい友人や家族と話す
質の良い睡眠を確保する工夫
健やかな肌を育むためには、量だけでなく質の良い睡眠が欠かせません。毎日できるだけ同じ時間に寝て同じ時間に起きる、規則正しい生活リズムを心がけることが体内時計を整える基本です。
特に寝る前の1〜2時間は、心と体をリラックスモードに切り替えるための大切な時間です。スマートフォンやパソコンの画面が発するブルーライトは、脳を覚醒させて眠りを妨げるため、使用は控えましょう。
その代わりに、穏やかな音楽を聴いたり、難しい内容ではない本を読んだりするのも良い方法です。寝室を快適な温度・湿度に保ち、遮光カーテンなどで光を遮断し、静かで暗い環境を整えることも、深い眠りへとつながります。
睡眠の質を高めるための環境づくり
| 要素 | ポイント | 具体的な工夫 |
|---|---|---|
| 光 | 寝室をできるだけ暗くする | 遮光カーテンを利用する、電子機器の光を消す |
| 音 | 静かな環境を保つ | 耳栓やホワイトノイズマシンを活用する |
| 温度・湿度 | 快適と感じる範囲に調整する | 夏は25-26℃、冬は22-23℃、湿度は50-60%が目安 |
適度な運動が心身にもたらす効果
ウォーキングやジョギング、水泳、サイクリングなどのリズミカルな有酸素運動は、ストレス解消に非常に有効です。運動をすると、幸福感をもたらし気分を高揚させるセロトニンやエンドルフィンといった脳内物質が分泌されます。
また、体を動かすことで心地よい疲労感が得られ、寝つきが良くなる効果も期待でき、さらに、定期的な運動はストレスホルモンであるコルチゾールのレベルを正常に保つ助けにもなります。
かゆみを和らげるためのスキンケア
ストレスによってバリア機能が低下した皮膚をサポートし、かゆみの悪循環を断ち切るためには、毎日の丁寧で正しいスキンケアが何よりも大事です。
保湿の重要性と正しい保湿剤の選び方
スキンケアの基本であり、最も重要なのが保湿です。
皮膚が乾燥すると、角層がめくれあがって隙間ができ、外部からの刺激が侵入しやすくなるだけでなく、かゆみを感じる神経線維が皮膚の表面近くまで伸びてきて、かゆみに過敏な状態になります。
入浴後や洗顔後は、肌の水分が急速に蒸発していくため、タオルで優しく水分を押さえたら5分以内を目安に、できるだけ早く保湿剤を塗りましょう。
保湿剤は、肌のバリア機能を補うセラミドや、水分を抱え込むヒアルロン酸、水分蒸発を防ぐワセリンなどが含まれた、刺激の少ない製品を選びます。
べたつきが苦手な方はローションタイプ、乾燥が強い方はクリームや軟膏タイプと、使用感や季節に合わせて使い分けるのがおすすめです。
肌の状態に合わせた保湿剤のタイプ
| タイプ | 特徴 | おすすめの肌状態 |
|---|---|---|
| ローション(化粧水) | 水分が多く、さっぱりした使用感。広範囲に塗りやすい | 軽い乾燥、脂性肌、夏場 |
| クリーム | 水分と油分がバランス良く配合され、保湿力が高い | 普通の乾燥~強い乾燥、季節の変わり目、冬場 |
| 軟膏 | 油分が主成分で、皮膚を保護する膜を作る力が最も強い | 特に乾燥がひどい部分、ひび割れ、水仕事の後 |
肌に優しい衣類や寝具の選択
直接長時間肌に触れる衣類や寝具の素材選びも、かゆみを悪化させないために非常に重要です。チクチクとした感触のウールや、ごわごわした化学繊維は物理的な刺激となり、かゆみを誘発します。
吸湿性・通気性に優れ、肌触りの柔らかい綿(コットン)やシルクなどの天然素材を選びましょう。衣類は体を締め付けない、ゆったりとしたデザインがおすすめです。
また、洗濯洗剤や柔軟剤に含まれる香料や界面活性剤が肌への刺激になることもあるため、なるべくシンプルな成分のものを選び、すすぎは十分に行い、洗剤が衣類に残らないように注意しましょう。
- 合成界面活性剤
- アルコール(エタノール)
- 香料・着色料
- 防腐剤(パラベンなど)
入浴時に気をつけたいポイント
体を清潔に保つことは大切ですが、間違った入浴方法はかえって肌の乾燥を悪化させ、バリア機能を低下させます。
熱すぎるお湯(42℃以上)は、皮膚を守るために必要な皮脂まで奪いすぎてしまうため、お風呂の温度は38〜40℃程度のぬるめに設定しましょう。
体を洗う際は、石鹸やボディソープをよく泡立て、ナイロンタオルなどでゴシゴシこすらず、きめ細かい泡で包み込むように手で優しくなでるように洗います。
石鹸成分が肌に残ると刺激になるため、シャワーで時間をかけて丁寧に洗い流すことも忘れないでください。
食事と栄養で内側からケアする方法
健やかで美しい皮膚は、一朝一夕に作られるものではなく、日々の食事が大きく影響します。外側からのスキンケアだけでなく、バランスの取れた食事で体の中から皮膚の健康を支えることも、症状の根本的な改善には必要です。
皮膚の健康を支える栄養素
皮膚の細胞を作る基本となるのは、良質なタンパク質なので、肉や魚、卵、大豆製品などを毎日の食事にしっかり取り入れましょう。
また、皮膚の新陳代謝を正常に保ち、粘膜を健康にするビタミンB群、コラーゲンの生成を助け抗酸化作用を持つビタミンC、血行を促進し皮膚の老化を防ぐビタミンE、皮膚のターンオーバーを助ける亜鉛も、積極的に摂取したい栄養素です。
肌の健康をサポートするビタミンとミネラル
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| ビタミンB群 | 皮膚や粘膜の健康維持、エネルギー代謝を助ける | 豚肉、レバー、うなぎ、納豆、卵 |
| ビタミンC | コラーゲンの生成促進、メラニン生成抑制、抗酸化作用 | ピーマン、ブロッコリー、キウイ、柑橘類 |
| 亜鉛 | タンパク質の合成を助け、皮膚の新陳代謝を促す | 牡蠣、牛肉(赤身)、レバー、チーズ |
腸内環境と皮膚コンディション
腸は第二の脳とも呼ばれ、体内の免疫細胞の約7割が集中する、最大の免疫器官です。腸内環境が乱れて悪玉菌が増えると、有害物質が作られて腸のバリア機能が低下し、全身に軽度の炎症が広がることがあります。
炎症が皮膚に現れることで、湿疹やアトピー性皮膚炎が悪化すると考えられています(腸-皮膚相関)。
善玉菌を含むヨーグルトや納豆などの発酵食品(プロバイオティクス)と、そのエサとなる食物繊維やオリゴ糖を多く含む野菜や果物、海藻類(プレバイオティクス)を一緒に摂り、腸内環境を整えることが、巡り巡って皮膚の健康につながります。
腸内環境を整える食品群
| 種類 | 働き | 代表的な食品 |
|---|---|---|
| プロバイオティクス | 体に良い働きをする生きた善玉菌を直接補給する | ヨーグルト、納豆、味噌、キムチ、チーズ |
| プレバイオティクス | 腸内にもともといる善玉菌のエサとなり、その増殖を助ける | 野菜(ごぼう、玉ねぎ)、果物(バナナ)、豆類、海藻類 |
刺激物やアレルギーを考慮した食事
唐辛子などの香辛料を多く使った食事や、アルコール、カフェインを多く含む飲み物は、血管を拡張させたり、交感神経を刺激したりして、体温を上昇させ、かゆみを増強させることがあります。
症状が強く出ている時期は、刺激物を控えるように心がけましょう。また、遅延型フードアレルギーのように、食べてから時間が経ってから皮膚症状として現れるものもあります。
もし特定の食べ物を食べた後に症状が悪化するようなら、食事日記をつけてみるのも一つの方法です。
皮膚科での相談と治療の選択肢
さまざまなセルフケアを試みても症状が改善しない場合や、かゆみが強くて仕事や勉強に集中できない、夜眠れないなど、日常生活に支障が出ている場合は、ためらわずに皮膚科を受診してください。
専門医による的確な診断と治療は、つらい症状から早く解放されるための最も確実な方法です。
専門医に相談するタイミング
「これくらいで病院に行くのは大げさかもしれない」と考える必要はありません。
かゆみで夜中に目が覚める、掻き壊して血が出たり、じゅくじゅくしたりしている、市販薬を1週間使っても良くならない、発疹がどんどん広がっていく、といった場合は、受診をおすすめします。
また、症状の原因が本当にストレスだけなのか、あるいは他の内科的な病気や感染症が隠れていないかを確認するためにも、一度専門医の診察を受けることは非常に有益です。
受診の際は、いつから、どこに、どんな症状があるか、どんな時に悪化するかなどをメモしておくと、診察がスムーズに進みます。
- いつから症状があるか
- どんな時に症状が悪化するか
- 現在使用している薬(市販薬含む)
- 最近の生活での変化やストレス要因
- アレルギー歴
主な治療法(外用薬・内服薬)
皮膚科での治療の中心は、炎症を効果的に抑えるステロイド外用薬や、かゆみの原因となるヒスタミンの働きをブロックする抗ヒスタミン薬の内服です。
ステロイド外用薬は、炎症の強さや体の部位に合わせて適切なランク(強さ)の薬を処方します。医師の指示通りに、適切な量を適切な期間使用すれば、非常に効果的で安全性の高い薬です。
内服の抗ヒスタミン薬は、かゆみを内側から抑えることで、掻き壊しの悪循環を断ち切り、皮膚が良い状態に戻るのを力強くサポートします。その他、症状に応じて、保湿薬や、細菌感染を合併している場合には抗菌薬などが処方されます。
代表的な外用薬の種類と働き
| 薬剤の種類 | 主な働き | 使用目的 |
|---|---|---|
| ステロイド外用薬 | 強力な抗炎症作用で、湿疹・皮膚炎の根本的な原因を抑える | 湿疹、皮膚炎、痒疹の赤み、腫れ、かゆみを鎮める |
| 非ステロイド性抗炎症薬 | 比較的穏やかな抗炎症作用を持つ | 軽度の湿疹、顔などデリケートな部位の長期管理に |
| 保湿薬 | 皮膚の水分を保ち、低下したバリア機能を補い、保護する | 乾燥の予防、全ての湿疹・皮膚炎治療の基本 |
心理的なアプローチの必要性
皮膚症状の背景に、自分でも気づいている、あるいは無自覚の強いストレスや心理的な問題がある場合は、皮膚の治療だけでは根本的な解決に至らず、症状を繰り返してしまうことがあります。
そのような場合には、カウンセリングや、ストレス関連の疾患を専門とする心療内科との連携を検討することもあります。
ストレスの原因と向き合い、物事の捉え方を変えたり、適切な対処法を身につけたりすることが、心の負担を軽くし、結果として皮膚症状の長期的な安定と再発予防につながるからです。
よくある質問
ストレスによる皮膚症状について、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- ストレスによるかゆみは自然に治りますか?
-
ストレスの原因が一時的なもので、原因が取り除かれれば、症状が自然に軽快することもあります。特に一過性の蕁麻疹などは、ストレスフルな状況が過ぎ去ると同時に消えることも少なくありません。
しかし、湿疹や痒疹のように炎症が定着してしまった場合や、かゆみと掻き壊しの悪循環に陥っている場合は、ストレスがなくなっても皮膚の炎症は続いてしまうため、自然治癒は難しく、適切な治療が必要です。
放置すると、掻き壊した跡がシミ(炎症後色素沈着)になったり、皮膚が硬く盛り上がったままになったりする可能性もあるため、長引く場合は自己判断せず、専門医に相談しましょう。
- 子供でもストレスで湿疹ができますか?
-
子供でもストレスが原因で皮膚症状が現れたり、悪化したりすることがあります。進学や転校といった環境の変化、友人関係の悩み、習い事のプレッシャー、家庭環境の変化などが、子供にとって大きなストレスとなり得ます。
子供は自分のストレスをうまく言葉で表現できないことが多いため、お腹が痛くなるのと同じように、皮膚症状が心のサインとして現れることもあります。
アトピー性皮膚炎を持つお子さんの場合、ストレスが悪化の引き金になることは非常によく見られます。
お子さんの皮膚の状態に変化が見られたら、最近何か変わったことがなかったか、生活の様子を注意深く見守り、話を聞いてあげることが大切です。
- 市販薬を使っても良いですか?
-
ごく軽度の湿疹やかゆみで、原因がはっきりしている場合(例えば、一時的なストレスで少し湿疹が出たなど)であれば、市販薬で対応できることもあります。ただし、市販薬を選ぶ際には注意が必要です。
症状に合わない薬を使うとかえって悪化させたり、実はカビ(真菌)が原因の皮膚炎にステロイド薬を塗ってしまい症状を悪化させたりする危険性があります。
特に、顔などのデリケートな部位や、症状の範囲が広い場合、じゅくじゅくして感染が疑われる場合は、自己判断で市販薬を使わず、まず皮膚科を受診してください。
市販薬を5〜6日使用しても改善しない、あるいは悪化する場合は、すぐに使用を中止して専門医に相談することが重要です。
以上
参考文献
Kodama A, Horikawa T, Suzuki T, Ajiki W, Takashima T, Harada S, Ichihashi M. Effect of stress on atopic dermatitis: investigation in patients after the great hanshin earthquake. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 1999 Jul 1;104(1):173-6.
Yamamoto Y, Yamazaki S, Hayashino Y, Takahashi O, Tokuda Y, Shimbo T, Fukui T, Hinohara S, Miyachi Y, Fukuhara S. Association between frequency of pruritic symptoms and perceived psychological stress: a Japanese population-based study. Archives of dermatology. 2009 Dec 1;145(12):1384-8.
Amano H, Negishi I, Akiyama H, Ishikawa O. Psychological stress can trigger atopic dermatitis in NC/Nga mice: an inhibitory effect of corticotropin-releasing factor. Neuropsychopharmacology. 2008 Feb;33(3):566-73.
Furue M, Chiba T, Takeuchi S. Current status of atopic dermatitis in Japan. Asia Pacific Allergy. 2011 Jul 1;1(2):64-72.
Tokura Y, Yunoki M, Kondo S, Otsuka M. What is “eczema”?. The Journal of Dermatology. 2025 Feb;52(2):192-203.
Omata N, Tsukahara H, Ito S, Ohshima Y, Yasutomi M, Yamada A, Jiang M, Hiraoka M, Nambu M, Deguchi Y, Mayumi M. Increased oxidative stress in childhood atopic dermatitis. Life sciences. 2001 Jun 1;69(2):223-8.
Murota H, Koike Y, Morisaki H, Matsumoto M, Takenaka M. Exacerbating factors and disease burden in patients with atopic dermatitis. Allergology International. 2022;71(1):25-30.
Mochizuki H, Lavery MJ, Nattkemper LA, Albornoz C, Valdes Rodriguez R, Stull C, Weaver L, Hamsher J, Sanders KM, Chan YH, Yosipovitch G. Impact of acute stress on itch sensation and scratching behaviour in patients with atopic dermatitis and healthy controls. British Journal of Dermatology. 2019 Apr 1;180(4):821-7.
Rupprecht M, Salzer B, Raum B, Hornstein OP, Koch HU, Riederer P, Sofic E, Rupprecht R. Physical stress-induced secretion of adrenal and pituitary hormones in patients with atopic eczema compared with normal controls. Experimental and clinical endocrinology & diabetes. 1997;105(01):39-45.
Kupfer J, Gieler U, Braun A, Niemeier V, Huzler C, Renz H. Stress and atopic eczema. International archives of allergy and immunology. 2001;124(1-3):353.