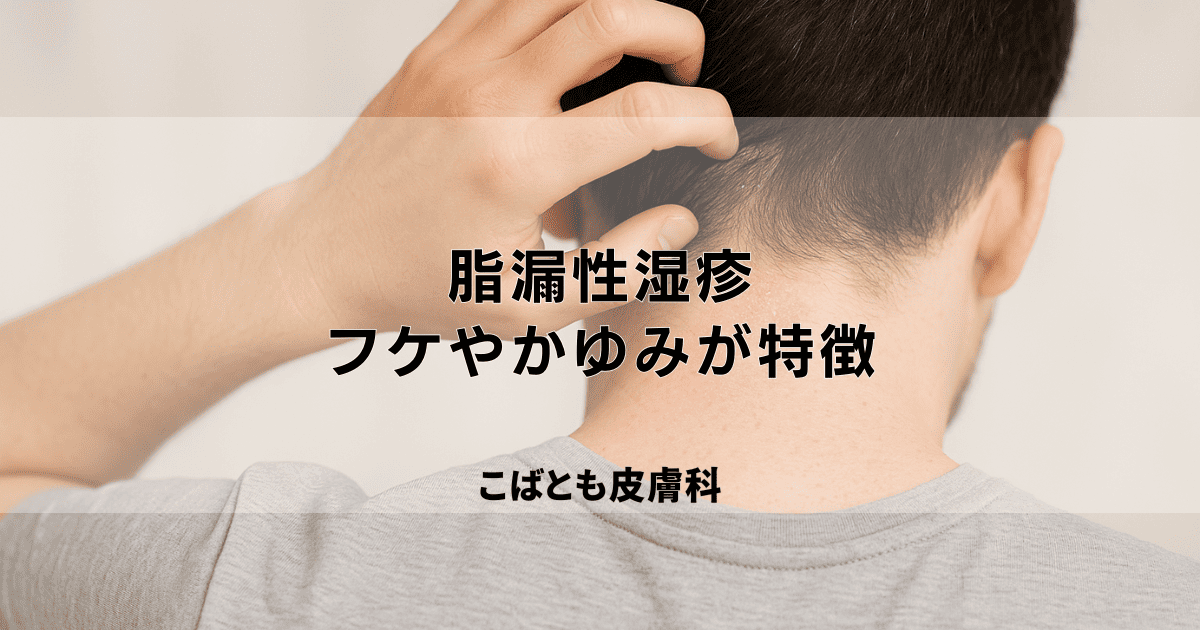頭皮のフケがなかなか治まらない、顔の小鼻の周りや髪の生え際が赤くなり、カサカサと皮膚がむけるような症状に心当たりはありませんか。単なる乾燥や肌荒れではなく、脂漏性湿疹という皮膚炎のサインかもしれません。
脂漏性湿疹は、皮脂の分泌が盛んな部位に発症しやすい、皮膚の病気です。
この記事では、脂漏性湿疹の詳しい症状から原因、ご自身でできる日常のケア、皮膚科で行う治療法まで、分かりやすく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
脂漏性湿疹の基本的な知識
脂漏性湿疹という言葉を初めて聞く方もいるかもしれません。まずは、この皮膚炎がどのようなもので、なぜそう呼ばれるのか、そして似たような症状を持つ他の皮膚炎とどう違うのか、基本的な事柄から見ていきましょう。
脂漏性湿疹とはどのような皮膚炎か
脂漏性湿疹は、湿疹性疾患の一種です。湿疹とは、皮膚の表面に起こる炎症の総称で、赤み、ぶつぶつ、かゆみなどの症状を伴います。
その中でも脂漏性湿疹は、特に皮脂腺が多く、皮脂の分泌が活発な場所に好発し、主に頭皮、髪の生え際、眉毛、鼻の周り、耳の後ろ、胸の中央、脇の下、股間などです。
症状の現れ方は人それぞれですが、一般的には皮膚の赤みと、黄色みを帯びた湿り気のあるフケや、乾燥したうろこ状のフケ(鱗屑 りんせつ)がみられます。
かゆみを伴うことも多く、軽度の場合から、日常生活に支障をきたすほど強い場合まで様々です。この皮膚炎は、乳児期と思春期以降の成人に発症のピークが二つあるという特徴も持っています。
乳児の場合は、生後数週間から数ヶ月で自然に良くなることがほとんどですが、成人の場合は再発を繰り返し、慢性的な経過をたどることが少なくありません。
なぜ脂漏性という名前がついているのか
脂漏性湿疹の脂漏(しろう)とは、文字通り皮脂が脂のように漏れ出るという意味合いを持っています。
皮脂腺から分泌される皮脂は、本来、皮膚の表面に膜を張り、水分の蒸発を防いだり、外部の刺激から皮膚を守ったりする大切な役割を担っています。
しかし、何らかの理由で皮脂の分泌が過剰になったり、皮脂の成分バランスが崩れたりすると、皮膚の常在菌であるマラセチア菌というカビ(真菌)の一種が異常に増殖することがあります。
このマラセチア菌が皮脂を分解する際に生み出す遊離脂肪酸が、皮膚に刺激を与えて炎症を起こします。皮脂が豊富な環境が、炎症の引き金となるため、脂漏性湿疹という名前が付けられているのです。
ただし、必ずしも皮脂の量が多い人だけが発症するわけではなく、皮脂の質や、体の免疫反応なども複雑に関係していることが分かっています。
他の皮膚炎との違い
フケやかゆみ、赤みといった症状は、他の皮膚炎でも見られるため、自己判断は難しい場合があります。アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)、接触皮膚炎(かぶれ)などとの見極めが重要です。
アトピー性皮膚炎は、強いかゆみを伴う湿疹が良くなったり悪くなったりを繰り返す病気で、肘や膝のくぼみなど、乾燥しやすい部位に症状が出やすい傾向があります。一方、脂漏性湿疹は皮脂の多い部位が中心です。
尋常性乾癬は、皮膚が赤く盛り上がり、その上に銀白色のフケのようなものが厚く付着するのが特徴で、境界がはっきりしています。脂漏性湿疹のフケは、より黄色っぽく、湿り気があることが多いです。
接触皮膚炎は、特定の物質が触れた場所に限定して症状が現れるため、原因物質との接触がなければ症状は改善します。
他の皮膚炎との主な違い
| 皮膚炎の種類 | 主な症状 | 好発部位 |
|---|---|---|
| 脂漏性湿疹 | 赤み、黄色っぽい湿ったフケ、かゆみ | 頭皮、顔(鼻周り、眉)、胸、脇 |
| アトピー性皮膚炎 | 強いかゆみ、乾燥、ジュクジュクした湿疹 | 肘や膝のくぼみ、首、顔 |
| 尋常性乾癬 | 境界明瞭な赤い盛り上がり、銀白色の鱗屑 | 頭皮、肘、膝、腰 |
脂漏性湿疹の主な症状と特徴
脂漏性湿疹の症状は、体のどの部分に現れるかによって少しずつ見た目や特徴が異なります。また、乳児と成人では症状の出方が違う点も特徴の一つです。
頭皮にあらわれる症状
成人の脂漏性湿疹で最も多く見られるのが、頭皮の症状です。初期段階では、フケが増えたと感じる程度かもしれません。フケは、パラパラとした乾いたタイプのものから、少し大きめで黄色っぽく、湿り気やべたつきのあるタイプまで様々です。
症状が進行すると、頭皮全体が赤みを帯びてきます。
かゆみを伴うことが多く、無意識にかきむしってしまうと、頭皮が傷つき、そこから液体(浸出液)が出てきたり、かさぶたができたりすることもあります。
ひどい場合には、フケとかさぶたが混じり合って、厚い塊となって頭皮にこびりつくこともあります。髪の生え際、特に額や耳の周りにも症状が広がりやすいのが特徴です。
顔にあらわれる症状
顔も皮脂の分泌が多い場所であるため、脂漏性湿疹が好発する部位です。特に、鼻の両脇から口角にかけての溝(鼻唇溝 びしんこう)、眉毛とその周辺、眉間、額、下あごなどは症状が出やすい場所です。
顔の症状も、基本的には皮膚の赤みと、細かくカサカサとした皮膚のはがれ(落屑 らくせつ)が中心です。鼻の周りでは、赤みとともに少しべたついた感じのフケが見られることがあります。
眉毛の中にフケが絡みついたり、皮膚がむけたりすることもあり、かゆみの程度は様々です。男性の場合、ひげが生えている部分に症状が出ることもあります。
体にあらわれる症状
脂漏性湿疹は、頭や顔だけでなく、体の脂漏部位にも発症します。
胸骨部(胸の中央)、肩甲骨の間、脇の下、足の付け根(股部)などは、衣類で蒸れやすく、症状が出やすい場所で、比較的境界がはっきりした、淡い赤色から黄紅色をした円形や楕円形の斑点が現れることが多いです。
表面には、フケのような細かい鱗屑が付着しています。また、脇の下や股間など、皮膚がこすれやすい場所では、赤みが強くなり、ジュクジュクとした状態になることもあります。
かゆみは必ずしも強いわけではありませんが、汗をかくと悪化する傾向があります。
症状が出やすい体の部位
- 頭皮・髪の生え際
- 眉毛・眉間
- 鼻の周り(鼻翼部、鼻唇溝)
- 耳の中や後ろ
- 胸の中央部、脇の下
乳児と思春期以降で異なる症状
脂漏性湿疹は、発症する年齢によって症状の現れ方が大きく異なります。
乳児の場合、生後2~4週頃から見られ始め、頭やおでこ、眉毛に黄色っぽい厚いかさぶたのようなものが付着するのが特徴的です。
これは乳痂(にゅうか)と呼ばれ、かゆみはあまり強くないことが多く、通常は生後8ヶ月から1年以内には自然に軽快していきます。
一方、思春期以降に発症する成人の脂漏性湿疹は、フケや赤み、かゆみが主な症状です。
乳児期のものとは異なり、一度発症すると良くなったり悪くなったりを繰り返し、慢性的な経過をたどり、ストレスや生活習慣の乱れなど、様々な要因で悪化することが知られています。
年齢別の症状の特徴
| 年齢層 | 主な症状 | 経過 |
|---|---|---|
| 乳児期(生後数週~) | 黄色い厚いかさぶた(乳痂)、赤み | 多くは生後1年以内に自然軽快する |
| 成人期(思春期以降) | フケ、赤み、かゆみ | 慢性化しやすく、再発を繰り返す |
脂漏性湿疹の原因と考えられる要因
脂漏性湿疹がなぜ起こるのか、はっきりとした原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
皮脂の過剰な分泌
脂漏性湿疹の発症における中心的な役割を担っているのが皮脂です。
皮脂腺から分泌される皮脂は、トリグリセリド、ワックスエステル、スクアレンなど様々な脂質から構成されていて、皮膚の潤いを保ち、バリア機能として働く重要な役割を持っています。
しかし、ホルモンバランスの影響や体質などによって皮脂の分泌が過剰になると、皮膚表面の環境が変化します。特に、皮脂に含まれるトリグリセリドが、マラセチア菌によって分解されると、皮膚に刺激を与える遊離脂肪酸が生成されます。
この遊離脂肪酸が炎症を引き起こし、皮膚の赤みやかゆみ、フケといった脂漏性湿疹の症状につながるのです。
マラセチア菌の増殖
私たちの皮膚には、多種多様な細菌や真菌が常に存在しており、これが皮膚常在菌と呼ばれるものです。
マラセチア菌もその一種で、健康な皮膚にも存在するごくありふれたカビ(真菌)で、普段は特に害を及ぼすことはありませんが、皮脂を栄養源として増殖するという性質を持っています。
皮脂の分泌が盛んになったり、汗をかいて湿度が高くなったり、あるいは体の免疫力が低下したりすると、マラセチア菌が異常に増殖することがあります。
増えすぎたマラセチア菌が、その代謝物である遊離脂肪酸を大量に産生し、皮膚の角質層にダメージを与え、炎症反応を誘発します。
脂漏性湿疹の患者さんの皮膚では、健康な人と比べてマラセチア菌の数が多いことが確認されており、この菌の増殖が発症の重要な引き金です。
脂漏性湿疹の主な要因
| 要因 | 内容 | 脂漏性湿疹への関与 |
|---|---|---|
| 皮脂 | 皮膚を保護する脂質 | 過剰になるとマラセチア菌の栄養源となる |
| マラセチア菌 | 皮膚の常在菌(カビ) | 増殖すると皮脂を分解し、刺激物質を生成する |
| 個人の体質 | 免疫反応やホルモンバランス | 炎症の起こりやすさや皮脂分泌に影響する |
生活習慣の乱れ
不規則な生活や偏った食事、睡眠不足などは、体の様々な機能に影響を及ぼし、脂漏性湿疹の発症や悪化に関与します。
特に、ビタミンB群の不足は皮膚の健康と密接な関係があり、ビタミンB2やB6は、皮脂の分泌をコントロールする働きや、皮膚の新陳代謝(ターンオーバー)を正常に保つ働きを担っています。
ビタミンが不足すると、皮脂の分泌が過剰になったり、皮膚のバリア機能が低下したりして、脂漏性湿疹を発症しやすい状態になります。脂肪分や糖分の多い食事に偏ると、皮脂の分泌を促進してしまう可能性があります。
また、睡眠不足はホルモンバランスの乱れや免疫力の低下を招き、皮膚の炎症を悪化させる一因です。
その他の関連要因
上記以外にも、いくつかの要因が脂漏性湿疹に関わっていると考えられています。過度のストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、免疫機能を低下させることで、皮膚の炎症を悪化させる原因です。
また、遺伝的な素因が関係している可能性も指摘されています。
パーキンソン病などの神経系の病気を持つ患者さんや、HIV感染症などで免疫機能が低下している方では、脂漏性湿疹の発症率が高いことも報告されており、体の免疫システムの状態が皮膚の健康に大きく影響することを示しています。
生活習慣で気をつけたいこと
- 睡眠時間を確保する
- バランスの良い食事を心がける
- 適度な運動を取り入れる
- ストレスを溜め込まない
脂漏性湿疹が悪化するきっかけ
脂漏性湿疹は、一度症状が落ち着いても、些細なきっかけで再発したり悪化したりすることがあります。日常生活に潜む悪化要因について見ていきましょう。
ストレスと疲労の蓄積
精神的なストレスや身体的な疲労は、脂漏性湿疹の代表的な悪化要因です。仕事や人間関係の悩み、環境の変化などによるストレスは、自律神経のバランスを崩します。
自律神経は、血管の収縮や拡張、ホルモンの分泌などをコントロールしており、その乱れは皮膚の状態に直接影響します。
また、ストレスを感じると、体内でコルチゾールというホルモンが分泌されます。
コルチゾールは、短期的には炎症を抑える働きがありますが、慢性的なストレスによって分泌が続くと、免疫機能のバランスが崩れ、かえって皮膚の炎症を助長してしまうことがあります。
同様に、過労や睡眠不足も体の免疫力を低下させ、皮膚のバリア機能を弱めるため、外部からの刺激に敏感になり、湿疹が悪化しやすくなります。
症状がなかなか改善しない時は、心と体の疲れが溜まっていないか、自身の生活を振り返ってみることが大切です。
不適切なスキンケア
良かれと思って行っているスキンケアが、実は症状を悪化させているケースも少なくありません。フケやべたつきが気になるからといって、洗浄力の強すぎるシャンプーや洗顔料で一日に何度も洗うのは逆効果です。
必要な皮脂まで奪ってしまい皮膚の乾燥を招き、かえって皮脂の分泌が過剰になったり、バリア機能が低下して炎症が悪化したりすることがあります。
また、ゴシゴシと強くこすって洗うことも、皮膚を傷つけ、炎症をひどくする原因です。逆に、洗顔や洗髪が不十分で、皮脂や汚れが皮膚に残っていると、マラセチア菌の増殖を促してしまいます。
自分に合った洗浄剤を使い、優しく丁寧に洗い、十分にすすぐことが基本です。洗った後の保湿ケアも重要ですが、油分の多いクリームなどは毛穴を詰まらせ、症状を悪化させる可能性があるため、製品選びには注意が必要です。
悪化要因のセルフチェック
| 項目 | 内容 | はい / いいえ |
|---|---|---|
| ストレス | 最近、強いストレスを感じている | |
| 睡眠 | 睡眠時間が6時間未満の日が多い | |
| 洗浄 | 一日に何度も洗顔やシャンプーをする | |
| 食事 | 脂っこいものや甘いものをよく食べる |
季節や環境の変化
季節の変わり目や、特定の環境下で症状が悪化することもよくあります。一般的に、空気が乾燥する秋から冬にかけては、皮膚のバリア機能が低下しやすいため、症状が悪化する傾向があり、汗をかきやすい夏も注意が必要です。
汗に含まれる塩分やアンモニアなどが皮膚への刺激となるほか、高温多湿の環境はマラセチア菌が増殖しやすいため、症状が悪化することがあります。
また、エアコンの効いた室内は空気が乾燥しているため、冬場だけでなく夏場も皮膚の乾燥を招き、バリア機能の低下につながります。
紫外線も、適度であれば殺菌作用などが期待できますが、浴びすぎると皮膚にダメージを与え、炎症を悪化させる要因となり得ます。
食生活の偏り
日々の食事が皮膚の状態に与える影響は決して小さくありません。特に、脂漏性湿疹の悪化に関与すると考えられているのが、脂肪分や糖分の多い食事です。
揚げ物やスナック菓子、ケーキなどの洋菓子を過剰に摂取すると、皮脂の分泌を促進し、症状を悪化させる可能性があります。
香辛料などの刺激物やアルコールの過剰な摂取も、血管を拡張させて皮膚の赤みやかゆみを増強させることがあるため、症状が強い時は控えた方が良いでしょう。
皮膚の新陳代謝を助け、皮脂の分泌を正常に保つ働きのあるビタミンB群(B2, B6)や、抗酸化作用のあるビタミンC、Eなどを積極的に摂取することは、皮膚の健康維持に役立ちます。
食事で意識したい栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
|---|---|---|
| ビタミンB2 | 皮脂の分泌調整、皮膚の再生 | レバー、うなぎ、卵、納豆 |
| ビタミンB6 | タンパク質の代謝、皮膚の健康維持 | かつお、まぐろ、バナナ、ささみ |
| ビタミンC/E | 抗酸化作用、皮膚のバリア機能サポート | 野菜、果物、ナッツ類 |
自宅でできるセルフケアと予防法
脂漏性湿疹の治療は皮膚科で行うのが基本ですが、症状をコントロールし、再発を防ぐためには日々のセルフケアが非常に重要です。毎日の洗髪や洗顔、保湿、そして生活習慣全体を見直すことで、皮膚の状態を健やかに保つことができます。
正しい洗髪と洗顔の方法
毎日の洗浄は、余分な皮脂や汚れ、増えすぎたマラセチア菌を洗い流し、皮膚を清潔に保つための基本ですが、洗いすぎやこすりすぎは禁物です。
洗髪の際は、まずぬるま湯で頭皮と髪を十分に予洗いします。シャンプーは直接頭皮につけず、手のひらでよく泡立ててから、指の腹を使って頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。
爪を立ててゴシゴシこするのは、頭皮を傷つける原因になるので絶対に避けてください。すすぎは特に丁寧に行い、シャンプー成分が残らないように時間をかけて洗い流します。
洗顔も同様に、洗顔料をよく泡立て、泡で顔を包み込むように優しく洗います。特に鼻の周りや眉間など、症状が出やすい部分はきちんと洗いましょう。
すすぎ残しは肌トラブルの原因になるため、髪の生え際やフェイスラインまでしっかりとぬるま湯で洗い流してください。
正しいシャンプーの手順
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. 予洗い | ぬるま湯で頭皮と髪の汚れをしっかり流す |
| 2. 泡立て・洗浄 | シャンプーをよく泡立て、指の腹で優しく洗う |
| 3. すすぎ | 時間をかけて、すすぎ残しがないように洗い流す |
保湿ケアの重要性
脂漏性湿疹は皮脂が多い部位にできるため、保湿は不要だと思われがちですが、これは大きな誤解です。洗浄によって皮脂が洗い流された後の皮膚は、乾燥しやすく、バリア機能が低下した状態にあります。
この状態を放置すると、外部からの刺激を受けやすくなったり、皮膚が潤いを補おうとしてかえって皮脂を過剰に分泌したりすることがあります。
洗顔や入浴後は、できるだけ速やかに保湿ケアを行いましょう。化粧水で水分を補給し、その後、乳液やジェルなどで水分が逃げないように蓋をします。
この時、油分の多いクリームやオイルは、毛穴を詰まらせて症状を悪化させる可能性があるため、オイルフリーやノンコメドジェニック(ニキビができにくい処方)と表示された、さっぱりとした使用感のものを選ぶのがおすすめです。
頭皮用の保湿ローションなどもあるので、頭皮の乾燥が気になる場合は活用すると良いでしょう。
スキンケア製品選びのポイント
- 低刺激性・無香料・無着色
- アレルギーテスト済み
- ノンコメドジェニックテスト済み
- 抗真菌成分(ミコナゾールなど)配合のもの
生活習慣の見直し
皮膚は体の状態を映す鏡とも言われます。健やかな皮膚を保つためには、体の中からコンディションを整えることが大切です。まずは、十分な睡眠を確保しましょう。
睡眠中には成長ホルモンが分泌され、皮膚の修復や再生が促され、質の良い睡眠を心がけることが、皮膚のターンオーバーを正常化し、バリア機能を高めることにつながります。
食事面では、脂肪分や糖分の多い食事は控えめにし、ビタミンB群やビタミンC、食物繊維などを豊富に含む、バランスの取れた食事を心がけてください。緑黄色野菜や果物、きのこ類、海藻類は積極的に取り入れたい食品です。
また、適度な運動は血行を促進し、ストレス解消にも役立ちます。
刺激の少ない衣類の選択
衣類による摩擦や蒸れも、体の脂漏性湿疹を悪化させる要因になります。肌に直接触れる下着や衣類は、吸湿性や通気性に優れた綿やシルクなどの天然素材を選ぶと良いでしょう。
化学繊維、特にナイロンやポリエステルなどは、汗を吸いにくく蒸れやすいため、症状がある場合は避けた方が無難で、体を締め付けるようなタイトなデザインの服も、皮膚との摩擦が生じやすく、通気性を妨げます。
洗濯の際に、洗剤や柔軟剤が衣類に残留しないよう、すすぎを十分に行うことも大切です。
皮膚科での診断と治療法
セルフケアを続けても症状が改善しない場合や、かゆみが強い場合、症状の範囲が広い場合は、自己判断で悩まずに皮膚科を受診することが重要です。
診断の流れ
皮膚科では、まず問診と視診によって診断を行います。問診では、いつからどのような症状があるのか、かゆみの有無や程度、症状が良くなったり悪くなったりするきっかけ、現在使用している薬、生活習慣などについて詳しく尋ねます。
次に、視診で皮膚の状態を詳しく観察し、皮疹の分布(どこにできているか)、色や形、フケの状態(乾いているか、湿っているか)などを見ることで、多くの場合、脂漏性湿疹の診断がつきます。
ただし、症状が非典型的で、アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬など他の病気との区別が難しい場合には、皮膚の一部を採取して顕微鏡で調べる真菌検査や、皮膚生検(皮膚の一部を切り取って病理組織を調べる検査)を行うこともあります。
主な治療薬の種類と役割
脂漏性湿疹の治療の基本は、炎症を抑えることと、原因の一つであるマラセチア菌の増殖を抑えることで、主に用いられるのは、ステロイド外用薬と抗真菌外用薬です。
ステロイド外用薬は、皮膚の炎症を強力に抑える作用があり、赤みやかゆみを迅速に改善し、症状の強さや部位に応じて、様々な強さのランクの薬を使い分けます。
顔や首などの皮膚の薄い部分にはマイルドなものを、頭皮などには比較的強めのものが処方されることが一般的です。
抗真菌外用薬は、マラセチア菌の増殖を抑える薬です。炎症を直接抑える作用はありませんが、原因菌を減らすことで、症状の根本的な改善と再発予防につながります。
ステロイドでまず炎症を抑え、症状が落ち着いてきたら抗真菌薬に切り替えたり、両者を併用したりするなど、症状に合わせて治療法を調整します。
かゆみが強い場合には、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬の内服薬が、皮脂の分泌を整える目的でビタミンB2やB6の内服薬が処方されることもあります。
皮膚科で処方される主な薬剤
| 薬剤の種類 | 主な役割 | 代表的な薬剤(成分名) |
|---|---|---|
| ステロイド外用薬 | 皮膚の炎症(赤み、かゆみ)を抑える | ヒドロコルチゾン、プレドニゾロンなど |
| 抗真菌外用薬 | 原因菌(マラセチア菌)の増殖を抑える | ケトコナゾール、ミコナゾールなど |
| 内服薬 | かゆみを抑える、ビタミンを補う | 抗ヒスタミン薬、ビタミンB群など |
治療期間の目安と注意点
外用薬を使い始めると、通常は1~2週間程度で赤みやかゆみなどの症状は改善してきますが、症状が良くなったからといって自己判断で薬をやめてしまうと、すぐに再発してしまうことが少なくありません。
脂漏性湿疹は慢性化しやすく、再発を繰り返す性質があるため、症状がなくなった後も、再発予防のために抗真菌薬の塗布を継続したり、スキンケアを続けたりすることが大切です。
医師の指示に従って、薬の量や回数を徐々に減らしていくことが重要です。また、ステロイド外用薬を長期間、不適切に使用すると、皮膚が薄くなったり、血管が浮き出たりといった副作用のリスクもあります。
必ず医師の指導のもとで正しく使用してください。
治療中の注意点
- 医師の指示通りに薬を使用する
- 自己判断で薬を中断しない
- 症状が改善してもセルフケアを続ける
- 気になることがあればすぐに相談する
よくある質問 (Q&A)
最後に、脂漏性湿疹に関して患者さんからよく寄せられる質問と答えをまとめました。
- 脂漏性湿疹は他の人にうつりますか?
-
脂漏性湿疹の原因の一つであるマラセチア菌は、誰もが皮膚に持っている常在菌です。脂漏性湿疹は、常在菌のバランスが崩れることなどによって発症するものであり、感染症ではなく、他の人にうつる心配はありません。
タオルや寝具を共用しても問題ありませんが、衛生面を考慮し、清潔に保つことは大切です。
- 自然に治ることはありますか?
-
乳児の脂漏性湿疹は、多くの場合、特別な治療をしなくても生後1年くらいまでには自然に良くなります。しかし、成人の脂漏性湿疹は、残念ながら自然に完治することは稀で、慢性的な経過をたどることがほとんどです。
生活習慣の改善やセルフケアで症状が軽くなることはありますが、放置すると悪化したり、症状が長引いたりすることが多いため、皮膚科で相談することをお勧めします。
- 市販薬を使っても良いですか?
-
軽症の場合、抗真菌成分や弱いステロイドが配合された市販薬で症状が和らぐこともありますが、症状の原因が本当に脂漏性湿疹なのか、自己判断は難しい場合があります。
もし別の皮膚炎だった場合、市販薬を使うことでかえって症状が悪化する可能性もあります。まずは皮膚科を受診し、正確な診断を受けてから、ご自身の症状に合った薬を処方してもらうのが最も安全で確実な方法です。
- 完治はしますか?
-
成人の脂漏性湿疹は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のように、体質的な要因が関わっているため、薬で症状を完全に消し去り、二度と再発しないようにする完治は難しいのが現状です。
しかし、適切な治療とセルフケアを継続することで、症状がほとんどない、あるいは全くない良好な状態を長期間維持することは十分に可能です。
参考文献
Sugita T, Tajima M, Takashima M, Amaya M, Saito M, Tsuboi R, Nishikawa A. A new yeast, Malassezia yamatoensis, isolated from a patient with seborrheic dermatitis, and its distribution in patients and healthy subjects. Microbiology and immunology. 2004 Aug;48(8):579-83.
Polaskey MT, Chang CH, Daftary K, Fakhraie S, Miller CH, Chovatiya R. The global prevalence of seborrheic dermatitis: a systematic review and meta-analysis. JAMA dermatology. 2024 Aug 1;160(8):846-55.
Tanaka A, Cho O, Saito C, Saito M, Tsuboi R, Sugita T. Comprehensive pyrosequencing analysis of the bacterial microbiota of the skin of patients with seborrheic dermatitis. Microbiology and immunology. 2016 Aug;60(8):521-6.
Tajima M, Sugita T, Nishikawa A, Tsuboi R. Molecular analysis of Malassezia microflora in seborrheic dermatitis patients: comparison with other diseases and healthy subjects. Journal of investigative dermatology. 2008 Feb 1;128(2):345-51.
Sei Y. Seborrheic Dermatitis Clinical Diagnosis and Therapeutic Value of Different Drugs. Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi. 2003 Apr 30;44(2):77-80.
Okiyama N, Kohsaka H, Ueda N, Satoh T, Katayama I, Nishioka K, Yokozeki H. Seborrheic area erythema as a common skin manifestation in Japanese patients with dermatomyositis. Dermatology. 2008 Nov 1;217(4):374-7.
Hiruma J, Nojo H, Hiruma M, Sugita T, Makimura K, Harada K, Kano R. Malassezia polysorbatinonusus sp. nov., a Novel Isolate from a Japanese Patient with Seborrheic Dermatitis. Mycopathologia. 2025 Feb;190(1):15.
Tajima M. Malassezia species in patients with seborrheic dermatitis and atopic dermatitis. Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi. 2005 Jul 30;46(3):163-7.
Yamamoto M, Umeda Y, Yo A, Yamaura M, Makimura K. Utilization of matrix‐assisted laser desorption and ionization time‐of‐flight mass spectrometry for identification of infantile seborrheic dermatitis‐causing M alassezia and incidence of culture‐based cutaneous M alassezia microbiota of 1‐month‐old infants. The Journal of Dermatology. 2014 Feb;41(2):117-23.
Nakabayashi A, Sei Y, Guillot J. Identification of Malassezia species isolated from patients with seborrhoeic dermatitis, atopic dermatitis, pityriasis versicolor and normal subjects. Medical mycology. 2000 Jan 1;38(5):337-41.