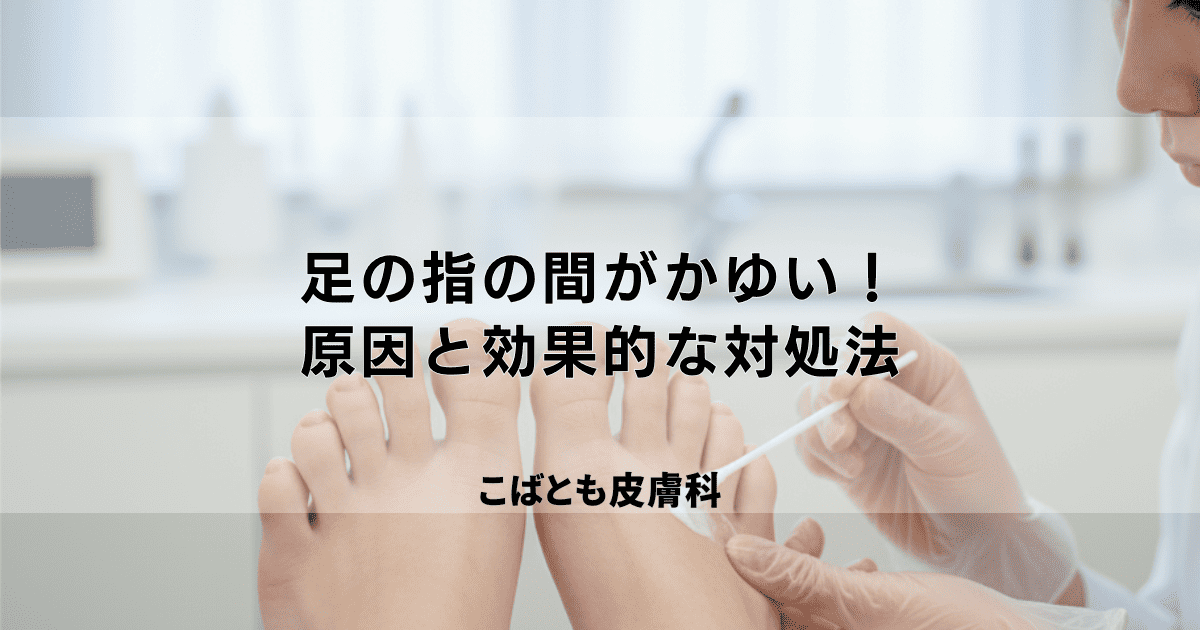足の指の間に、むずむずとしたしつこいかゆみ。多くの方がまず水虫を疑い、市販薬を試してみるのではないでしょうか。しかし、薬を使っても一向に良くならない、あるいは水虫の検査では陰性だったという経験はありませんか。
足の指の間に限らず、足にかゆみを起こす皮膚のトラブルは水虫だけではなく、かぶれや汗、細菌など、さまざまな原因が考えられます。
この記事では、水虫以外で足の指の間にかゆみが起こる主な原因を掘り下げ、それぞれの特徴やご自宅でできるセルフケア、そして専門的な治療について詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
水虫じゃないのに足の指の間がかゆいのはなぜ?
足の指の間のかゆみの代表格として水虫(足白癬)がよく知られているため、多くの方が自己判断で市販薬を使い始めることがありますが、症状が改善しない場合、かゆみは水虫ではない他の皮膚疾患が原因である可能性が高いです。
自己判断の危険性
水虫だと思い込んで市販の水虫薬を塗り続けると、症状が改善しないばかりか、薬の成分によるかぶれ(接触皮膚炎)を起こし、かゆみがさらに悪化することがあります。
また、本来必要な治療が遅れることで、症状が慢性化したり、色素沈着などの跡が残ったりするリスクも高まります。
水虫薬に含まれる抗真菌成分は、水虫の原因である白癬菌には効果を発揮しますが、他の原因による湿疹やかぶれには効果がなく、刺激となって症状を悪化させることさえあるのです。
水虫との見分け方
水虫と他の皮膚疾患を完全に見分けることは専門家でも難しい場合がありますが、いくつかの特徴からある程度の推測は可能です。
水虫は、足の指の間が白くふやけて皮がむけたり、じゅくじゅくしたりする趾間型、足の裏に小さな水ぶくれができる小水疱型、かかとなどが硬くガサガサになる角質増殖型など、いくつかのタイプに分かれます。
かゆみの程度も人それぞれで、全くかゆみを感じない人もいます。水虫以外の疾患では、赤みや腫れが強かったり、かゆみが非常に強かったり、特定の状況で症状が悪化したりするなど、それぞれに特徴的な症状が現れます。
症状から見る鑑別のポイント
| 症状 | 水虫(足白癬)の傾向 | その他の皮膚疾患の傾向 |
|---|---|---|
| 皮むけ | 指の間が白くふやけ、薄い皮がむける | 赤みや水ぶくれを伴い、厚めに皮がむけることがある |
| 水ぶくれ | 足の裏や側面に小さな水ぶくれができることがある | 指の間に集中して小さな水ぶくれが多発することがある(汗疱など) |
| かゆみの強さ | 強い場合もあれば、全くない場合もある | 非常に強いかゆみを伴うことが多い(接触皮膚炎、汗疱など) |
かゆみ以外の症状にも注目
かゆみだけでなく、同時に現れている他の症状にも目を向けることが、原因を特定する上で重要な手がかりになります。水ぶくれの有無やその見た目、皮むけの状態、赤みや腫れの範囲、痛みや熱感を伴うかなど、細かく観察してみましょう。
また、足の指の間だけでなく、手の指や体の他の部分にも似たような症状が出ていないか確認することも大切です。
- 赤みや腫れの強さ
- 水ぶくれの有無と大きさ
- じゅくじゅくしているか、乾燥しているか
- 痛みや熱っぽさ
- 他の部位の症状
接触皮膚炎(かぶれ)
水虫以外で足の指の間がかゆくなる原因として、非常に多いのが接触皮膚炎、いわゆるかぶれです。特定の物質が皮膚に接触することで炎症が起こるもので、原因物質によって刺激性のものとアレルギー性のものに大別されます。
刺激性接触皮膚炎とは
刺激性接触皮膚炎は、原因となる物質そのものが持つ刺激によって、誰にでも起こりうる皮膚炎です。
強力な化学薬品でなくても、身の回りにあるさまざまなものが原因となり得、靴の中の汗や蒸れ、洗剤や石鹸のすすぎ残し、あるいは不適切な濃度の消毒液などが挙げられます。
足の指の間は汗がたまりやすく、皮膚がふやけてバリア機能が低下しやすいため、弱い刺激でも炎症を起こしやすい環境にあります。原因物質に触れてから比較的短い時間で赤みやかゆみ、ひりひりとした痛みが出ることが特徴です。
刺激性接触皮膚炎の原因となりうるもの
| 分類 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 化学的刺激 | 洗剤、石鹸、アルコール消毒液、水虫薬 | すすぎ残しや、必要以上の使用に注意が必要です。 |
| 物理的刺激 | 汗、蒸れ、靴や靴下の摩擦 | 通気性の悪い靴を長時間履くことでリスクが高まります。 |
| 植物など | 植物の汁、虫の毒 | 素足での活動時に接触する可能性があります。 |
アレルギー性接触皮膚炎とは
アレルギー性接触皮膚炎は、特定のアレルゲン(アレルギーの原因物質)に対してアレルギー反応を起こす体質の人にのみ発症します。
原因物質に触れてすぐに症状が出るわけではなく、何度か接触を繰り返すうちに体がその物質を異物と認識し、次に触れたときに強い炎症反応を起こすようになります。
足の指の間で原因となりやすいものには、靴や靴下に使われる化学繊維、染料、皮革をなめす際に使う化学薬品、ゴム製品に含まれる加硫促進剤、あるいは外用薬に含まれる成分などです。
原因物質に触れてから半日~2日ほど経ってから、強いかゆみや赤み、小さな水ぶくれなどが現れます。
アレルギー性接触皮膚炎の原因となりうるもの
| 分類 | 具体例 | 含まれる製品の例 |
|---|---|---|
| 金属 | ニッケル、クロム、コバルト | 靴の金具、皮革なめし剤 |
| 化学物質 | 染料、ゴムの硬化剤、接着剤 | 靴下、靴の中敷き、サンダル |
| 薬剤 | 抗生物質、抗真菌薬、消毒薬 | 塗り薬、絆創膏 |
原因物質の特定方法
接触皮膚炎の治療で最も重要なのは、原因となっている物質を特定し、触れないようにすることです。新しい靴を履き始めてから症状が出た、特定の靴下を履いた日にかゆくなるなど、症状が出る直前の行動を振り返ることが手がかりになります。
原因が疑われるものを一時的に使用中止し、症状が改善するかどうかを見るのも一つの方法です。
皮膚科では、アレルギーが疑われる場合にパッチテストを行います。これは、原因として疑われる物質を背中などに貼り、皮膚の反応を見ることでアレルゲンを特定する検査です。
汗疱(かんぽう)・異汗性湿疹
特に春から夏にかけて、足の指の間や側面に強いかゆみを伴う小さな水ぶくれが突然現れた場合、汗疱(かんぽう)または異汗性湿疹(いかんせいしっしん)の可能性があります。
汗疱の特徴的な症状
汗疱の最も特徴的な症状は、1~2mm程度の小さな水ぶくれ(小水疱)が、手のひらや指の側面、足の裏や指の間に突然多発することです。水ぶくれは透明で、非常に強いかゆみや、時に痛みを伴うこともあります。
水ぶくれは互いにくっついて大きくなることもありますが、数週間すると自然に乾燥し、その後、薄い皮がむけて治っていくのが一般的で、水虫と異なり、他の人にうつることはありません。
ただし、かゆみが強いため、掻き壊してしまうと細菌感染を併発して症状が悪化することがあるため注意が必要です。
汗疱が悪化する要因
汗疱のはっきりとした原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が症状の悪化に関わっていると考えられ、日常生活で避けるように心がけることが症状のコントロールに繋がります。
汗疱を悪化させる可能性のある要因
| 要因 | 解説 | 対策 |
|---|---|---|
| 多汗症 | 汗の量が多いと、汗の出口が詰まりやすくなります。 | 通気性の良い靴下や靴を選び、足を清潔に保ちます。 |
| 金属アレルギー | ニッケル、クロム、コバルトなどの金属アレルギーが関与することがあります。 | 金属を多く含む食品(チョコレート、豆類など)を控えることで改善する場合もあります。 |
| ストレス | 精神的なストレスは自律神経のバランスを乱し、発汗に影響を与えることがあります。 | 十分な休息や睡眠、リラックスできる時間を作ることが大切です。 |
汗とのかかわり
病名に汗という文字が含まれている通り、汗疱は汗と深いかかわりがあります。足の裏は体の他の部分に比べて汗腺が密集しており、一日にかく汗の量も非常に多い場所です。
夏場や運動時、緊張した時などにかく多量の汗が、皮膚の表面にある汗管(汗の通り道)を詰まらせ、炎症を起こすきっかけになると考えられています。
ただし、汗をかくこと自体が悪いわけではなく、汗をかいた後に放置し、皮膚が蒸れた状態が続くことが問題です。こまめに汗を拭き取ったり、通気性の良い環境を保ったりすることが予防に繋がります。
汗疱のケア方法
汗疱の症状が出た場合、まずは掻かないことが重要です。水ぶくれを無理に潰すと、細菌が入って二次感染を起こす原因になります。かゆみが強い場合は、冷たいタオルなどで冷やすと一時的に和らぐことがあります。
基本的なケアとしては、足を清潔に保ち、しっかりと乾燥させることが大切です。症状が軽い場合はセルフケアで改善することもありますが、かゆみが強い場合や範囲が広い場合、何度も繰り返す場合は皮膚科を受診してください。
皮膚科では、炎症を抑えるステロイド外用薬やかゆみを抑える抗ヒスタミン薬の飲み薬などを処方し、症状をコントロールします。
- 患部を掻かない、水ぶくれを潰さない
- 足を清潔に保ち、優しく洗う
- 通気性の良い靴や靴下を選ぶ
- 強いかゆみは冷やしてしのぐ
細菌感染
足の指の間は、高温多湿で細菌が繁殖しやすい絶好の環境です。水虫や他の湿疹によって皮膚のバリア機能が低下していると、そこから細菌が侵入し、二次的な細菌感染を起こすことがあります。
細菌が繁殖しやすい環境
足、特に指の間は、解剖学的に指同士が密着しているため、通気性が悪くなりがちです。靴や靴下を履いている時間が長い現代人の足は、常に汗で湿っており、皮膚の表面温度も高めに保たれています。
このような高温多湿の環境は、黄色ブドウ球菌や溶連菌といった常在菌を含むさまざまな細菌にとって、非常に増殖しやすい条件です。
加えて、歩行による摩擦で小さな傷ができやすかったり、既存の皮膚炎を掻き壊してしまったりすると、細菌が皮膚の内部に侵入する入り口を与えてしまいます。
足の清潔を保つためのポイント
| 項目 | 具体的な方法 | 目的 |
|---|---|---|
| 洗浄 | 石鹸をよく泡立て、指の間まで丁寧に洗う。 | 余分な皮脂や汚れ、細菌を取り除く。 |
| すすぎ | 石鹸成分が残らないよう、十分に洗い流す。 | 洗浄剤による刺激を防ぐ。 |
| 乾燥 | タオルで優しく押さえるように水分を拭き取る。 | 湿った環境を作らないようにする。 |
細菌感染による症状
細菌感染を併発すると、元々のかゆみに加えて、痛みや腫れ、熱感といった症状が強く現れるようになり、患部が赤く腫れあがり、時には膿を持った水ぶくれ(膿疱)ができたり、黄色いかさぶたが付着したりすることもあります。
症状がひどくなると、足の甲まで腫れが広がったり、近くのリンパ節(足の付け根など)が腫れて痛んだり、発熱したりすることもあり、この状態が蜂窩織炎(ほうかしきえん)です。
このような症状が見られた場合は、セルフケアで対応できる範囲を超えているため、速やかに医療機関を受診する必要があります。
水虫との違い
水虫は真菌(カビ)の一種である白癬菌が原因であるのに対し、ここで言う細菌感染は、主に黄色ブドウ球菌などの細菌が原因です。
水虫はじんわりとしたかゆみが主体であることが多いですが、細菌感染ではズキズキとした痛みや熱感を伴うことが大きな違いです。
また、水虫の治療に用いる抗真菌薬は細菌には全く効果がなく、逆に細菌感染の治療に用いる抗菌薬(抗生物質)は水虫には効きません。
両者を合併している場合もあるため、正確な診断に基づいて、両方の治療を同時に行うことが必要になるケースもあります。
適切な治療の重要性
細菌感染が疑われる場合、治療の基本は原因となっている細菌を抑えることで、皮膚科では、抗菌薬の塗り薬や飲み薬を処方します。特に、腫れや痛みが強い場合や、発熱を伴う蜂窩織炎の状態では、飲み薬による治療が重要です。
自己判断で市販の湿疹薬などを使用すると、原因菌を増殖させてしまい、かえって症状を悪化させる危険性があります。細菌感染は急速に進行することがあるため、疑わしい症状に気づいたら、できるだけ早く専門医に相談することが大切です。
- 足を清潔に保つ
- 小さな傷でも放置しない
- 掻き壊さない
- 通気性の良い履物を心がける
見過ごしがちなその他の原因
これまで紹介した代表的な原因の他にも、足の指の間のかゆみを起こす可能性のある、いくつかの状態があり、比較的稀ですが、症状が長引く場合には考慮に入れる必要があります。
乾燥による皮膚のバリア機能低下
足は汗をかきやすい一方で、冬場など空気が乾燥する季節には、皮膚の水分が失われて乾燥しやすくなり、皮膚が乾燥すると、表面の角層が剥がれやすくなり、外部からの刺激を守るバリア機能が低下します。
この状態になると、普段なら何でもないような靴下の繊維の摩擦や、わずかな汚れなどにも敏感に反応し、かゆみや湿疹を起こすことがあります。足の指の間はもともと皮膚が薄いため、乾燥の影響を受けやすい部分です。
保湿クリームなどで日頃からケアを行い、皮膚の潤いを保つことが予防に繋がります。
趾間(しかん)びらん症
趾間びらん症は、主に足の第4趾(薬指)と第5趾(小指)の間に見られる皮膚のトラブルで、この部分は指の間隔が狭く、蒸れやすいため、皮膚が白くふやけて、じゅくじゅくとした状態(びらん)になりやすいです。
多くはカンジダというカビの一種や細菌の増殖が関与していると考えられていて、強いかゆみや、時には亀裂が入って痛みを伴うこともあります。水虫の趾間型と見た目が非常に似ているため、鑑別には皮膚科での検査が必要です。
治療には、原因となっている微生物に応じた抗真菌薬や抗菌薬の塗り薬を用います。
水虫・趾間びらん症・汗疱の比較
| 疾患名 | 主な症状 | 特徴的な部位 |
|---|---|---|
| 水虫(趾間型) | 皮膚が白くふやける、皮がむける、じゅくじゅくする | どの指の間にも起こりうる |
| 趾間びらん症 | 白くふやける、じゅくじゅくする、亀裂、痛み | 主に薬指と小指の間 |
| 汗疱 | 小さな水ぶくれ、強いかゆみ | 指の間、側面、足の裏 |
内科的な病気が隠れている可能性
非常に稀ではありますが、全身のかゆみの一症状として、足の指の間にかゆみが現れることもあります。
糖尿病では、血行不良や免疫力の低下、皮膚の乾燥などが原因で、皮膚のトラブルが起こりやすくなり、血糖値が高い状態が続くと、末梢神経に障害が出て、かゆみを感じやすくなることも知られています。
また、肝臓や腎臓の機能が低下している場合も、体内に老廃物やかゆみの原因物質がたまり、全身にかゆみが生じることがあります。
足のかゆみがなかなか治らず、他に気になる症状(のどの渇き、体重減少、だるさなど)がある場合は、一度内科的な観点からのチェックも必要です。
自宅でできるセルフケアと予防法
足の指の間のかゆみを防ぎ、症状を悪化させないためには、日々のセルフケアが非常に重要で、原因が何であれ、足の環境を清潔で快適に保つことが基本となります。
正しい足の洗い方
毎日の入浴時に、足を正しく洗う習慣をつけましょう。大切なのは、ゴシゴシと強くこすりすぎないことです。ナイロンタオルなどで強くこすると、皮膚の表面を傷つけ、バリア機能を損なう原因になります。
石鹸やボディソープをよく泡立て、その泡で指の間や爪の周りまで優しく丁寧に洗いましょう。そして、それ以上に重要なのがすすぎです。石鹸成分が残っていると、それが刺激となってかぶれの原因になることがあります。
シャワーで時間をかけて、指の間までしっかりと洗い流してください。洗い終わった後は、清潔なタオルで水分を完全に拭き取り、特に指の間は水分が残りやすいので、タオルの角などを使って優しく押さえるように拭き取りましょう。
靴や靴下の選び方と管理
一日の中で長時間履いている靴や靴下は、足の環境に大きな影響を与えます。選び方や管理方法を工夫することで、かゆみのリスクを大幅に減らすことが可能です。
靴・靴下の選び方と管理のポイント
| 項目 | ポイント | 理由 |
|---|---|---|
| 靴下の素材 | 綿やシルクなど、吸湿性・通気性の良い天然素材を選ぶ。 | 汗をしっかり吸収し、蒸れを防ぎます。 |
| 靴の選び方 | 通気性の良い素材(メッシュ、天然皮革など)で、つま先にゆとりのあるデザインを選ぶ。 | 空気の通り道を確保し、指への圧迫を減らします。 |
| 靴の管理 | 毎日同じ靴を履かず、2~3足をローテーションさせる。履いた後は乾燥させる。 | 靴の中に湿気がこもるのを防ぎ、細菌やカビの繁殖を抑えます。 |
足の環境を快適に保つ工夫
靴や靴下以外にも、日常生活の中でできる工夫があります。
職場では可能であれば通気性の良いサンダルなどに履き替える、汗をかいたらこまめに靴下を履き替える、帰宅後はすぐに靴下を脱いで足を解放してあげる、といった小さな習慣が大切です。
また、5本指ソックスは、指同士の密着を防ぎ、汗を吸収してくれるため、指の間の蒸れ対策として有効です。市販の制汗スプレーや足用のパウダーなども、上手に活用すると快適に過ごす助けになります。
- 5本指ソックスの活用
- オフィスでの履き替え
- 汗をかいた後の靴下の交換
- 制汗剤・パウダーの使用
市販薬を使う際の注意点
症状が軽い場合、市販薬を試してみる人もいますが、原因がはっきりしない段階での使用には注意が必要です。水虫を疑って抗真菌薬を使っても、原因がかぶれや汗疱であれば効果はありません。
逆に、湿疹やかぶれに使うステロイド系の薬を、水虫に使ってしまうと、白癬菌を増殖させて症状を悪化させる危険性があります。
市販薬を1週間程度使用しても症状が改善しない、あるいは悪化するような場合は、使用を中止し、必ず皮膚科を受診してください。
市販薬の主な成分と注意点
| 成分の種類 | 主な用途 | 使用上の注意 |
|---|---|---|
| 抗真菌成分 | 水虫、カンジダ症 | 水虫以外の湿疹には効果がなく、悪化させる可能性がある。 |
| ステロイド成分 | 湿疹、皮膚炎、かぶれ | 細菌や真菌による感染症を悪化させる可能性がある。 |
| 鎮痒成分 | かゆみ止め | 根本的な原因治療にはならず、一時的な対症療法。 |
かゆみが続く場合に皮膚科を受診すべき理由
セルフケアを続けてもかゆみが治まらない、あるいは悪化していく場合は、ためらわずに皮膚科専門医に相談することが重要です。専門家による的確な診断と治療が、つらい症状からの早期回復に繋がります。
正確な診断の重要性
足の指の間のかゆみの原因は多岐にわたり、それぞれの原因によって治療法は全く異なります。皮膚科では、まず視診で皮膚の状態を詳しく観察し、必要に応じて顕微鏡検査(真菌検査)やパッチテストなどを行います。
真菌検査は、患部の皮膚を少しこすり取って顕微鏡で見ることで、水虫の原因である白癬菌がいるかどうかをその場で確認できる簡単な検査です。
専門的な治療の選択肢
皮膚科では、診断に基づいて、一人ひとりの症状に合った治療を提供します。接触皮膚炎や汗疱など、炎症が主な原因である場合は、炎症を強力に抑えるステロイド外用薬を処方します。
かゆみが非常に強い場合には、かゆみを和らげる抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬の飲み薬を併用することもあり、細菌感染を伴う場合は、抗菌薬の塗り薬や飲み薬が必要です。
処方薬は、市販薬に比べて効果が高く、医師の指導のもとで使うことで、安全かつ効果的に症状を改善させることが期待できます。
皮膚科で相談できること
| 相談内容 | 対応 |
|---|---|
| 原因の特定 | 視診、真菌検査、パッチテストなどによる正確な診断 |
| 症状の治療 | 塗り薬(ステロイド、抗菌薬など)や飲み薬(抗ヒスタミン薬など)の処方 |
| スキンケア指導 | 日常生活での注意点や、正しい足の洗い方などのアドバイス |
症状の悪化を防ぐために
かゆみを我慢して掻き続けていると、皮膚のバリア機能がさらに破壊され、湿疹が慢性化したり、細菌感染を併発したりして、治療がより複雑で長期間にわたるものになってしまいます。
また、掻き壊した跡が黒ずんで残る(炎症後色素沈着)ことも少なくありません。早期に適切な治療を開始することは、こうした症状の悪化や合併症を防ぎ、皮膚をきれいな状態に戻すために非常に重要です。
足の指の間のかゆみに関するよくある質問
- かゆいとき、冷やすのは効果がありますか?
-
一時的にかゆみを和らげる効果が期待できます。冷やすことで、かゆみを感じる神経の働きが鈍くなり、また血管が収縮して炎症による腫れや赤みが少し引くためです。
清潔なタオルで包んだ保冷剤などを短時間あてるのが良いでしょう。ただし、これはあくまで対症療法ですので、根本的な解決にはなりません。また、冷やしすぎると凍傷のリスクもあるため注意してください。
- 子供の足の指の間にも同じような症状は出ますか?
-
子供は新陳代謝が活発で汗をかきやすいため、汗疱やあせも、細菌感染などを起こしやすい傾向があり、また、大人に比べて皮膚のバリア機能が未熟なため、ちょっとした刺激でかぶれやすいことも特徴です。
水虫(足白癬)は大人に多い病気ですが、家族内に水虫の人がいると感染する可能性はあります。症状に気づいたら、早めに小児科か皮膚科に相談することをお勧めします。
- どんな靴下を選べばよいですか?
-
吸湿性と通気性に優れた素材の靴下を選ぶことが基本で、綿(コットン)や絹(シルク)、麻(リネン)などの天然繊維がお勧めです。化学繊維は汗を吸いにくいものが多く、蒸れの原因になりやすいです。
また、指の間の汗対策として、5本指ソックスは非常に有効です。締め付けの強すぎる靴下は血行を妨げる可能性があるので避け、自分の足に合ったサイズのものを選びましょう。
- 市販薬を1週間使っても治らない場合はどうすればいいですか?
-
市販薬を1週間使用しても症状の改善が見られない、またはかえって悪化した場合は、薬の使用を直ちに中止し、皮膚科を受診してください。原因と薬の種類が合っていない可能性が高いです。
自己判断で薬を使い続けると、症状が悪化したり、本来の症状がわからなくなって診断がつきにくくなったりすることがあります。専門医による正確な診断を受け、適切な治療を開始することが早期回復への一番の近道です。
以上
参考文献
Watanabe S, Harada T, Hiruma M, Iozumi K, Katoh T, Mochizuki T, Naka W, Japan Foot Week Group. Epidemiological survey of foot diseases in Japan: Results of 30 000 foot checks by dermatologists. The Journal of Dermatology. 2010 May;37(5):397-406.
Katsuta M, Ishiuji Y, Ogawa‐Tominaga M, Chiba K, Dekio I, Nobeyama Y, Asahina A. Number of itchy sites is important in evaluation for atopic dermatitis. Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology. 2024 Jun 1;38(6).
Torisu-Itakura H, Anderson P, Piercy J, Pike J, Sakamoto A, Kabashima K. Impact of itch and skin pain on quality of life in adult patients with atopic dermatitis in Japan: results from a real-world, point-in-time, survey of physicians and patients. Current Medical Research and Opinion. 2022 Aug 3;38(8):1401-10.
Takehara K, Oe M, Tsunemi Y, Ohashi Y, Kadowaki T, Sanada H. Association between tinea pedis and foot care factors in patients with diabetes. Journal of wound care. 2025 Apr 1;34(Sup4):S26-30.
Nakagami G, Takehara K, Kanazawa T, Miura Y, Nakamura T, Kawashima M, Tsunemi Y, Sanada H. The prevalence of skin eruptions and mycoses of the buttocks and feet in aged care facility residents: a cross-sectional study. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2014 Mar 1;58(2):201-4.
Chand M. The dangers of itchy feet: Parasitic infections imported by returning travellers. The Biochemist. 2009 Aug 1;31(4):4-7.
Deguchi T, Takatsuna H, Yokoyama M, Shiosakai K, Inoue T, Seki H, Uetake Y. A cross-sectional web survey of satisfaction with treatment for pain in participants with suspected diabetic peripheral neuropathic pain in both feet. Advances in Therapy. 2021 Aug;38(8):4304-20.
Furue M, Yamazaki S, Jimbow K, Tsuchida T, Amagai M, Tanaka T, Matsunaga K, Muto M, Morita E, Akiyama M, Soma Y. Prevalence of dermatological disorders in Japan: a nationwide, cross‐sectional, seasonal, multicenter, hospital‐based study. The Journal of dermatology. 2011 Apr;38(4):310-20.
Lee HJ, Ha SJ, Ahn WK, Kim D, Park YM, Byun DG, Kim JW. Clinical Evaluation of Atopic Hand‐Foot Dermatitis. Pediatric dermatology. 2001 Mar;18(2):102-6.
Nazarko L. Care of the feet: common problems and how to treat them. British Journal of Healthcare Assistants. 2007 Apr 12;1(1):27-30.