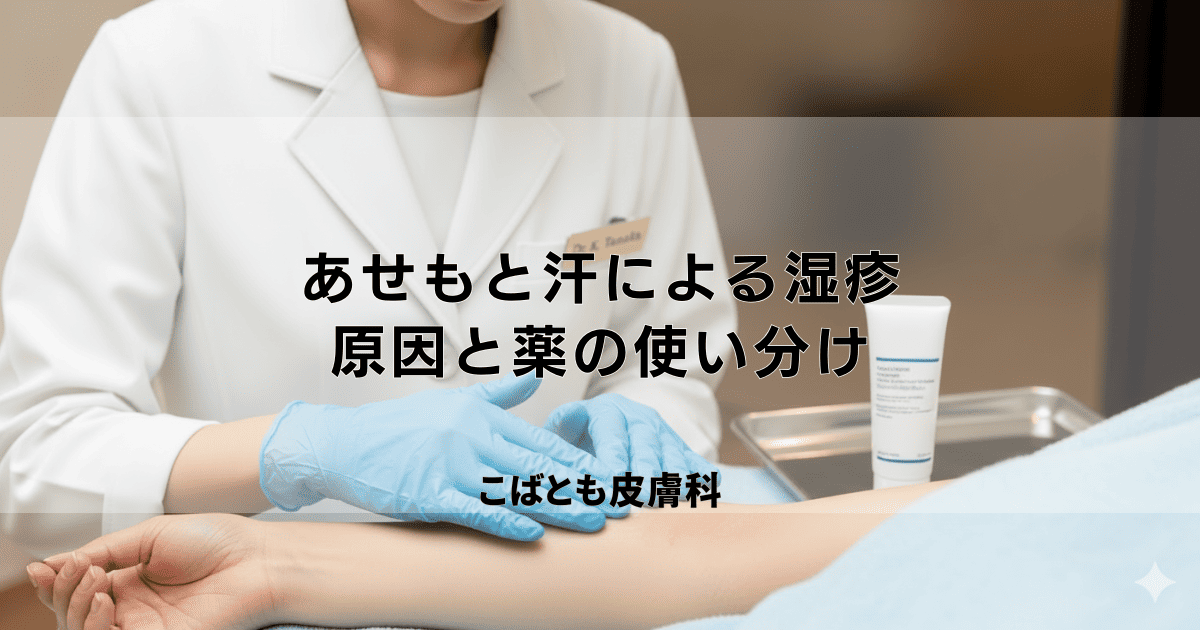汗ばむ季節になると、多くの人が皮膚のトラブルに悩みます。あせもや汗による湿疹は、見た目が似ていることもあり、どちらなのか判断に迷うことが多いのではないでしょうか。
しかし、この二つは原因が異なり、対処法や適切な薬も変わってきます。間違ったケアは症状を悪化させることにもつながりかねません。
この記事では、あせもと汗による湿疹の根本的な違いから、それぞれの原因、そしてご自身でできるセルフケア、市販薬の正しい選び方、皮膚科を受診する目安まで、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
「あせも」と「汗による湿疹」の基本的な違い
汗をかいた後に出てくる赤いブツブツ。多くの人は単純にあせもだと考えがちですが、実は汗による湿疹(汗あれ)の可能性もあります。
見た目の特徴やかゆみの性質、症状が現れやすい場所などを知ることで、ご自身の状態をより正確に把握できます。
見た目でわかる症状の違い
あせもと汗による湿疹は、見た目にいくつかの違いがあります。
あせもは、汗の出口である汗管が詰まることで発生し、小さく透明な水ぶくれ(水晶様汗疹)や、かゆみを伴う赤いブツブツ(紅色汗疹)として現れ、一つひとつの発疹が比較的はっきりしているのが特徴です。
汗による湿疹は、汗の成分が皮膚を刺激し、バリア機能が低下することで炎症が起きた状態のため、あせものようなはっきりとした個々の発疹というよりは、広範囲にわたって赤みやかさつき、細かいブツブツがまだらに広がる傾向があります。
時には、皮膚がじゅくじゅくしたり、ごわごわと厚くなったりすることもあります。
症状の見た目による比較
| 項目 | あせも(紅色汗疹) | 汗による湿疹(汗あれ) |
|---|---|---|
| 発疹の様子 | 小さく赤いブツブツが中心 | 赤み、細かいブツブツ、かさつきが混在 |
| 広がり方 | 個々の発疹が多発する | まだらに広がる傾向がある |
| 境界 | 比較的はっきりしている | 境界が不明瞭なことが多い |
かゆみや痛みの感じ方の違い
かゆみの質にも違いが見られます。あせも、特に紅色汗疹では、チクチク、ピリピリとした刺激的なかゆみを感じることが多く、汗をかいた時に、かゆみが強くなるのが典型的な症状です。
汗による湿疹のかゆみは、むずむずするような持続的なかゆみが特徴で、我慢できずについ掻き壊してしまい、さらに症状を悪化させる悪循環に陥りやすいのも、汗による湿疹のほうが多いです。
痛みに関しては、あせもでは通常、強い痛みを感じることはありませんが、汗による湿疹では、掻き壊して皮膚が傷つくと、ひりひりとした痛みを感じることがあります。
症状が出やすい体の部位
症状が現れる部位も、見分けるための重要なヒントになります。あせもは、汗をたくさんかき、汗がたまりやすい場所にできやすく、首の周り、ひじや膝の裏、脇の下、おむつで蒸れやすい赤ちゃんの臀部などが挙げられます。
衣類で擦れたり、締め付けられたりする部分も注意が必要です。それに対して汗による湿疹は、汗が皮膚表面にとどまりやすい場所であればどこにでも起こる可能性があります。
もともと皮膚のバリア機能が弱い乾燥肌の人や、アトピー性皮膚炎の素因がある人は、顔や首、腕や足など、比較的広い範囲に症状が出やすいです。
症状が出やすい部位のまとめ
| 症状 | 主な好発部位 | 特徴 |
|---|---|---|
| あせも | 首、ひじ・膝の裏、脇の下 | 汗がたまりやすく蒸れやすい部位 |
| 汗による湿疹 | 顔、首、腕、足など広範囲 | 皮膚のバリア機能が低下している部位 |
なぜ起こる?汗が引き起こす皮膚トラブルの原因
汗は体温調節に欠かせない重要な役割を担っていますが、時として皮膚トラブルの原因になります。なぜ同じ汗が、あせもや湿疹といった異なる症状を起こすのでしょうか。
背景には、汗の成分そのものの影響や、汗が排出される汗管の状態、そして皮膚の健康状態が深く関わっています。
汗の成分と皮膚への影響
汗の約99%は水分ですが、残りの1%には塩分(ナトリウム)、尿素、アンモニア、乳酸などが含まれていて、成分は、皮膚の表面にもともとある常在菌によって分解されると、皮膚への刺激物質に変わることがあります。
また、汗が蒸発して水分だけがなくなると、残された塩分や尿素などの濃度が高まり、健康な皮膚にとっては天然の保湿成分として働く一方で、皮膚のバリア機能が低下している状態では、成分が刺激となって炎症やかゆみを起こす原因になります。
この状態が、いわゆる汗による湿疹、汗あれです。
汗に含まれる主な成分
| 成分 | 皮膚への影響(バリア機能低下時) |
|---|---|
| 塩分(ナトリウム) | 刺激、かゆみの誘発 |
| 尿素・アンモニア | 刺激、pHバランスの乱れ |
| 乳酸 | 刺激、かゆみの誘発 |
汗管の詰まりが原因のあせも
あせもは、汗の通り道である汗管が詰まることで発症し、大量に汗をかくと、汗をスムーズに排出しきれなくなります。この時、皮膚の表面にある垢やほこりなどが汗管の出口を塞いでしまうと、汗が皮膚の中に閉じ込められてしまいます。
閉じ込められた汗が周囲の組織を刺激し、炎症を起こした状態が、一般的にあせもと呼ばれる紅色汗疹です。皮膚の浅い部分で詰まった場合は、かゆみのない小さな水ぶくれである水晶様汗疹となります。
高温多湿の環境や、通気性の悪い衣類の着用、急な発熱などで一気に汗をかいた時に起こりやすいです。
あせもの主な種類
- 水晶様汗疹
- 紅色汗疹
- 深在性汗疹
バリア機能の低下と汗による湿疹(汗あれ)
汗による湿疹は、汗管の詰まりではなく、皮膚のバリア機能の低下が大きく関与しています。
皮膚の表面は、角層と皮脂膜によって外部の刺激から守られていますが、紫外線、乾燥、間違ったスキンケア、体調不良などによってこのバリア機能が低下すると、皮膚は非常に敏感な状態になります。
このような状態で汗をかくと、汗の成分が刺激となり、皮膚の内部で炎症反応が起きてしまい、これが汗による湿疹の正体です。
もともとアトピー性皮膚炎や乾燥肌の人は皮膚のバリア機能が弱い傾向にあるため、汗による湿疹を起こしやすいです。
症状を悪化させないためのセルフケアと応急処置
あせもや汗による湿疹の症状が出てしまった場合、それ以上悪化させないためには、迅速で適切なセルフケアが重要です。かゆいからといって掻き壊してしまうと、そこから細菌が入り込んで二次感染を起こす(とびひなど)危険性もあります。
汗をかいた後の正しい対処法
最も基本的な対策は、汗をかいたらできるだけ速やかに洗い流すか、優しく拭き取ることで、シャワーを浴びるのが理想的ですが、難しい場合は濡れたタオルや汗拭きシートを使いましょう。その際、ゴシゴシと強くこするのは禁物です。
皮膚のバリア機能をさらに傷つけてしまうため、押さえるようにして優しく汗を吸い取ります。
石鹸やボディソープを使う場合は、洗浄力が強すぎない低刺激性のものを選び、よく泡立ててから手で優しく洗い、すすぎ残しがないように十分に洗い流してください。
シャワーや汗を拭いた後は、必ず保湿ケアを行い、皮膚の潤いを保つことが大切です。
冷やすことの効果と注意点
強いかゆみがある場合、患部を冷やすと一時的にかゆみが和らぎ、冷たいおしぼりや、タオルで包んだ保冷剤などを当てるのが効果的です。冷やすことで、かゆみを感じる神経の働きが鈍くなり、炎症による熱感も抑えることができます。
ただし、保冷剤を直接長時間当て続けると凍傷のリスクがあるため、必ず布などで包んで使用し、一箇所に当てる時間は数分程度にしましょう。
この方法は、あくまで一時的なかゆみ対策であり、根本的な治療ではないことを理解しておく必要があります。
かゆみ対策のポイント
- 汗をすぐに洗い流す、または拭き取る
- 濡れタオルや保冷剤で冷やす
- 掻かないように爪を短く切る
- 保湿を徹底する
かきむしりを防ぐための工夫
強いかゆみがあると、無意識のうちに掻いてしまうことがあります。掻き壊しは症状を悪化させる最大の原因で、防ぐためには、まず爪を短く切り、やすりで滑らかにしておきましょう。
就寝中にかきむしってしまう場合は、肌触りの良い綿の手袋を着用するのも一つの方法です。日中は、かゆみを感じたらすぐに冷やす、保湿するなどの対処を心がけ、掻く以外の方法でかゆみを紛らわしましょう。
かゆみを我慢できないほどの症状であれば、早めに皮膚科を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
衣類や寝具の選び方
肌に直接触れる衣類や寝具の素材選びも、症状の悪化を防ぐ上で非常に大切です。吸湿性や通気性に優れた綿(コットン)や絹(シルク)などの天然素材を選びましょう。汗を素早く吸い取り、発散させてくれるため、皮膚が蒸れにくくなります。
化学繊維であるポリエステルやナイロンは、汗を吸いにくく、蒸れやすいため、症状がある時は避けた方が無難です。また、体を締め付けるようなデザインの服も、摩擦や蒸れの原因になるため避け、ゆったりとした服装を心がけましょう。
寝具も同様に、シーツやパジャマは吸湿性の良い素材を選び、こまめに洗濯して清潔に保つことが大事です。
おすすめの衣類素材
| 素材 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 綿(コットン) | 吸湿性・通気性が良い、肌触りが良い | 乾きにくい場合がある |
| 絹(シルク) | 吸湿性・放湿性に優れる、肌への刺激が少ない | 高価、手入れに注意が必要 |
| 麻(リネン) | 通気性が非常に良い、速乾性がある | シワになりやすい、肌触りが硬め |
市販薬の選び方と正しい使い方
ドラッグストアには、あせもや湿疹向けの様々な市販薬が並んでいますが、症状によって適した成分は異なります。自分の症状が「あせも」なのか「汗による湿疹」なのかをある程度見極めた上で、適切な薬を選ぶことが早期改善への鍵です。
ここでは、市販薬を選ぶ際のポイントと、安全に使うための注意点を解説します。
あせもに適した市販薬の成分
汗管の詰まりと軽い炎症が主な原因であるあせもには、炎症を抑える成分や、かゆみを鎮める成分、殺菌成分が配合された薬が適しています。
非ステロイド性の抗炎症成分であるグリチルリチン酸や、酸化亜鉛などが含まれているものは、比較的軽度のあせもに使いやすいでしょう。かゆみが気になる場合は、ジフェンヒドラミンなどのかゆみ止め成分が入っているものが効果的です。
また、掻き壊しによる細菌感染を防ぐために、イソプロピルメチルフェノールなどの殺菌成分が配合されている製品もあります。
パウダータイプのものは、皮膚をさらさらに保つ効果がありますが、汗管を詰まらせる可能性も指摘されているため、汗を拭き取った清潔な肌に薄くつけましょう。
汗による湿疹向けの市販薬
皮膚のバリア機能低下と、炎症が主な原因である汗による湿疹には、あせもよりも少ししっかりと炎症を抑える必要があります。赤みやかゆみが強く、症状が長引いている場合は、ステロイド外用薬の使用を検討します。
市販のステロイド外用薬には強さにランクがありますが、まずは最も弱いランク(ウィーク)や、その次に弱いランク(ミディアム)のものから試すのがよいでしょう。顔や首などの皮膚の薄い部位には、弱いランクのものが適しています。
また、尿素が配合された保湿剤は、角質を柔らかくする効果がありますが、炎症がある部位に塗ると刺激を感じることがあるため、湿疹が治まってからの使用が推奨されます。
市販薬の主な有効成分
| 成分の種類 | 主な成分名 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 抗炎症成分 | グリチルリチン酸、ウフェナマート | 炎症を和らげる |
| かゆみ止め成分 | ジフェンヒドラミン、クロタミトン | かゆみを鎮める |
| ステロイド成分 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | 強い炎症を抑える |
ステロイド外用薬を使う際の注意点
ステロイド外用薬は、炎症を抑える効果が高い一方で、副作用を心配する人も少なくありませんが、医師や薬剤師の指示に従い、適切な期間、適切な量を守って使えば、非常に有効で安全な薬です。
市販薬を使用する際は、まず5〜6日程度を目安に使い、症状が改善するかどうかを見ます。もし改善しない、あるいは悪化するようであれば、使用を中止して皮膚科を受診してください。
また、症状が良くなったからといって、すぐに使用を中止すると再発することがあります。赤みが引いても、皮膚の下ではまだ炎症がくすぶっていることがあるため、医師の指示がある場合は、徐々に薬の量を減らしていくなどの対応が必要です。
自己判断で長期間、広範囲に使い続けることは避けてください。
皮膚科を受診するべき症状の目安
セルフケアや市販薬を試しても症状が改善しない場合や、症状が重い場合は、専門家である皮膚科医の診察を受けることが重要です。自己判断でケアを続けることが、かえって症状をこじらせ、跡を残す原因にもなりかねません。
市販薬を1週間使っても改善しない場合
市販薬を5〜6日、長くとも1週間程度使用しても、症状が全く良くならない、あるいはかえって悪化しているように感じる場合は、受診のタイミングです。
選んだ薬が症状に合っていない可能性や、あせもや汗湿疹ではなく、別の皮膚疾患(例えば、カビの一種である真菌感染症や、アレルギー性接触皮膚炎など)の可能性があります。
皮膚科では、医師が症状を正確に診断し、原因に合った適切な薬を処方します。
かゆみが強く眠れない、日常生活に支障がある
かゆみの感じ方には個人差がありますが、夜も眠れないほどのかゆみや、仕事や勉強に集中できないなど、日常生活に支障をきたしている場合は、我慢せずに受診しましょう。
強いかゆみは大きなストレスになりますし、無意識に掻き壊すことで症状はどんどん悪化します。
皮膚科では、炎症を強力に抑える外用薬に加え、かゆみを和らげるための抗ヒスタミン薬などの内服薬を処方することもあり、つらいかゆみを効果的にコントロールし、掻き壊しの悪循環を断ち切ることが可能です。
受診を推奨する症状リスト
- 市販薬で改善が見られない
- 強いかゆみで眠れない
- じゅくじゅくして浸出液が出ている
- 黄色いかさぶたができている
- 症状が全身に広がっている
じゅくじゅくしたり、化膿したりしている
患部を掻き壊した傷口から細菌が侵入し、二次感染を起こすと、皮膚がじゅくじゅくして浸出液が出たり、黄色い膿をもった発疹(膿疱)や黄色いかさぶたができたりすることがあります。
これは伝染性膿痂疹(とびひ)と呼ばれる状態で、抗菌薬による治療が必要です。放置すると、体の他の部位にも症状が広がってしまう可能性があるので、化膿のサインが見られたら、すぐに皮膚科を受診してください。
症状が広範囲に広がっている
症状が体の一部だけでなく、腕全体や背中全体など、広範囲に及んでいる場合も、専門的な治療が必要です。広範囲の炎症を市販薬だけでコントロールするのは難しく、また、内臓の疾患など、他の病気が隠れている可能性もゼロではありません。
特に、急激に全身に発疹が広がった場合や、発熱や倦怠感など、皮膚以外の症状を伴う場合は、速やかに医療機関を受診することが大事です。
皮膚科で行う専門的な治療法
皮膚科では、まず医師が患者の症状を詳しく診察し、あせもなのか、汗による湿疹なのか、あるいは他の皮膚疾患なのかを正確に診断し、診断に基づいて、一人ひとりの症状の重症度や部位、年齢などに合わせた治療法を提案します。
主な治療は薬物療法ですが、生活指導なども含めて総合的にアプローチします。
処方される外用薬の種類
治療の基本は、炎症を抑えるためのステロイド外用薬です。市販薬よりも種類が豊富で、症状の強さや部位(顔、体、手足など)に応じて、適切な強さのステロイドを使い分けます。
皮膚が薄くデリケートな顔には弱いランクのものを、皮膚が厚い手足には強いランクのものを使用し、また、ステロイド以外にも、非ステロイド性の抗炎症薬や、かゆみを抑える成分を配合した保湿剤などが処方されることもあります。
細菌感染を伴う場合には、抗菌薬の入った外用薬が必要です。
処方される外用薬の例
| 薬の種類 | 主な目的 | 使用される状況 |
|---|---|---|
| ステロイド外用薬 | 炎症を抑える | 赤み、かゆみ、腫れが強い場合 |
| 保湿剤 | 皮膚のバリア機能を整える | 乾燥、かさつきがある場合、症状改善後 |
| 抗菌薬含有外用薬 | 細菌の増殖を抑える | 化膿している場合(二次感染) |
かゆみを抑えるための内服薬
外用薬だけではコントロールできないほどの強いかゆみがある場合には、内服薬を併用し、主に使用するのは、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬です。
内服薬は、かゆみの原因となるヒスタミンという物質の働きをブロックすることで、つらいかゆみを内側から和らげます。
夜間のかゆみが強い人にとっては、睡眠の質を改善する助けにもなります。眠気が出やすいタイプと出にくいタイプがあるので、ライフスタイルに合わせて医師と相談しながら薬を選択します。
悪化因子を特定するアレルギー検査
汗による湿疹が繰り返し起こる場合や、アトピー性皮膚炎が背景にあると考えられる場合、汗以外の悪化因子が関わっている可能性を探るためにアレルギー検査を実施することがあります。
血液検査で特定のアレルゲン(ダニ、ハウスダスト、食物など)に対するIgE抗体の量を調べたり、皮膚に直接アレルゲンを貼って反応を見るパッチテストを行ったりします。
原因となるアレルゲンが特定できれば、それを避けることで症状の改善や再発予防につながります。
汗とうまく付き合うための予防策
あせもや汗による湿疹は、一度治っても、汗をかく季節になると繰り返しやすい皮膚トラブルです。
だからこそ、症状が出てから対処するだけでなく、日頃から汗と上手につきあい、トラブルを未然に防ぐための予防策を生活に取り入れることが非常に重要になります。少しの心がけで、夏の皮膚トラブルを大きく減らすことができます。
日常生活で心がけたい汗対策
根本的な予防は、汗をかいたまま放置しないことです。外出時にはこまめに汗を拭けるよう、清潔なタオルやハンカチ、あるいは低刺激の汗拭きシートを携帯しましょう。
運動などで大量の汗をかいた後は、できるだけ早くシャワーを浴びるのが理想です。室内では、エアコンや除湿機を適切に使い、高温多湿の環境を避ける工夫も効果的です。
また、通気性の良い、ゆったりとした服装を心がけ、肌への刺激を減らすことも忘れないようにしましょう。
汗対策グッズの活用
- 吸湿速乾性のインナー
- 携帯用ミニ扇風機
- 冷却スプレー
- 汗拭きシート(アルコールフリー推奨)
スキンケアの基本と保湿の重要性
汗による皮膚トラブルの予防には、日々のスキンケアで皮膚のバリア機能を健康に保つことが欠かせません。洗浄と保湿が二本柱です。
体を洗う際は、洗浄力の強すぎる石鹸は避け、弱酸性・低刺激性の製品を選び、よく泡立てて優しく洗いましょう。ナイロンタオルなどでゴシゴシこするのは厳禁です。
そして、お風呂上がりやシャワーの後は、皮膚が乾燥する前に、すぐに保湿剤を全身に塗布します。
汗による湿疹を起こしやすい人は、夏場でもさっぱりとした使用感のローションやジェルタイプの保湿剤で、しっかりと保湿ケアを続けることが再発予防につながります。
スキンケアの基本手順
| 手順 | ポイント | 目的 |
|---|---|---|
| 洗浄 | 低刺激性の洗浄料で優しく洗う | 汗や汚れを落とし、皮膚を清潔に保つ |
| 保湿 | 入浴後すぐに保湿剤を塗る | 皮膚の水分を補い、バリア機能を維持する |
食生活で意識したいポイント
健康な皮膚を維持するためには、体の内側からのケア、つまりバランスの取れた食生活も重要です。
特に、皮膚のターンオーバーを正常に保つビタミンA、皮膚や粘膜の健康を助けるビタミンB群、抗酸化作用があり炎症を抑える助けとなるビタミンCやビタミンEなどを積極的に摂取しましょう。
また、香辛料の多い刺激的な食べ物や、アルコールは、血管を拡張させてかゆみを増強させることがあるため、症状が出ている時は控えるのが賢明です。
規則正しい生活とバランスの良い食事で、皮膚の抵抗力を高めていくことが、根本的な予防策です。
よくある質問
ここでは、あせもや汗による湿疹に関して、患者さんから特によく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 赤ちゃんや子どものあせも・汗湿疹で気をつけることは?
-
赤ちゃんや子どもは、大人に比べて汗をかく機能が未熟で、単位面積あたりの汗腺の密度が高いため、あせもができやすいです。ケアの基本は大人と同じで、こまめに汗を拭き取り、着替えさせ、シャワーで清潔にすることです。
衣類は通気性の良い綿素材を選びましょう。市販薬を使う場合は、子どもに使用できるかどうかを必ず確認し、デリケートな肌に使える低刺激性のものを選んでください。
ただし、症状が改善しない場合や、機嫌が悪くぐずるほどかゆみが強い場合は、自己判断せず小児科や皮膚科を受診することをおすすめします。
- 汗をかくこと自体は悪いことではない?
-
汗をかくこと自体は、体温を調節し、体内の老廃物を排出するための非常に重要な生理現象です。汗をかくことを恐れて、過度に運動を避けたり、エアコンの効いた部屋に閉じこもったりするのは健康によくありません。
問題なのは、かいた汗をそのまま放置してしまうことです。汗をかく習慣がないと、いざという時にうまく汗をかけなくなったり、ベタベタした質の悪い汗になったりすることもあります。
適度な運動で良い汗をかく習慣をつけ、その後のケアをしっかり行うことが大切です。
- 治った後も跡が残ることはありますか?
-
通常、適切に治療されたあせもや軽い汗による湿疹であれば、跡を残さずにきれいに治ることがほとんどです。
しかし、かゆみが強いからといって激しく掻き壊してしまったり、炎症が皮膚の深い部分(真皮層)にまで及んでしまったりすると、炎症後色素沈着と呼ばれるシミのような跡が残ることがあります。
色素沈着は、数ヶ月から1年ほどで自然に薄くなることが多いですが、完全に消えない場合もあります。また、二次感染を起こして化膿した場合も、跡が残りやすくなります。
跡を残さないためには、症状が軽いうちに治療を開始し、掻かないようにすることが最も重要です。
以上
参考文献
Kaneko S, Murota H, Murata S, Katayama I, Morita E. Usefulness of sweat management for patients with adult atopic dermatitis, regardless of sweat allergy: a pilot study. BioMed research international. 2017;2017(1):8746745.
Murota H, Yamaga K, Ono E, Murayama N, Yokozeki H, Katayama I. Why does sweat lead to the development of itch in atopic dermatitis?. Experimental dermatology. 2019 Dec;28(12):1416-21.
Murota H, Yamaga K, Ono E, Katayama I. Sweat in the pathogenesis of atopic dermatitis. Allergology International. 2018;67(4):455-9.
Katayama I, Kohno Y, Akiyama K, Ikezawa Z, Kondo N, Tamaki K, Kouro O. Japanese guideline for atopic dermatitis. Allergology International. 2011;60(2):205-20.
Murota H, Katayama I. Exacerbating factors of itch in atopic dermatitis. Allergology International. 2017 Jan 1;66(1):8-13.
Suzuki T, Tajima H, Migita M, Pawankar R, Yanagihara T, Fujita A, Shima Y, Yanai E, Katsube Y. A case of anhidrotic ectodermal dysplasia presenting with pyrexia, atopic eczema, and food allergy. Asia Pacific Allergy. 2019 Jan 1;9(1):e3.
Miyano K, Tsunemi Y. Current treatments for atopic dermatitis in Japan. The Journal of Dermatology. 2021 Feb;48(2):140-51.
Soni R, Lokhande AJ, D’souza P. Atypical presentation of sweat dermatitis with review of literature. Indian dermatology online journal. 2019 Nov 1;10(6):698-703.
SPERLING L. Skin diseases associated with excessive heat, humidity, and sunlight. MILITARY DERMATOLOGY. 1917;41(2):39.
Flores S, Davis MD, Pittelkow MR, Sandroni P, Weaver AL, Fealey RD. Abnormal sweating patterns associated with itching, burning and tingling of the skin indicate possible underlying small‐fibre neuropathy. British Journal of Dermatology. 2015 Feb 1;172(2):412-8.