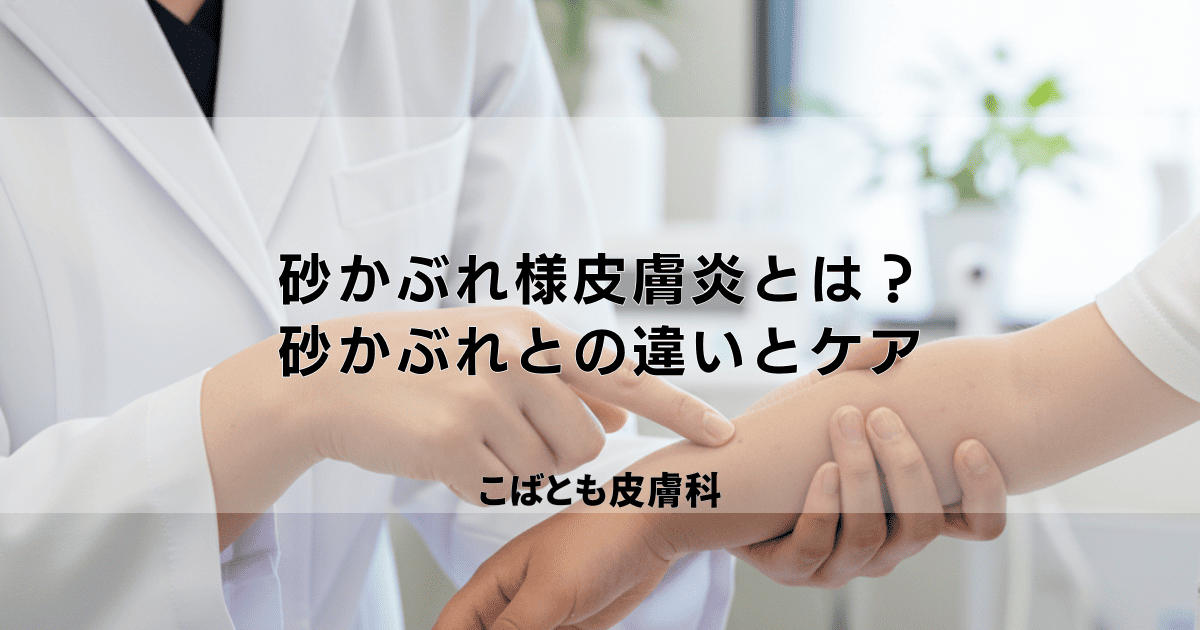お子さんが公園の砂場や海辺で元気に遊ぶ姿は微笑ましいものですが、楽しかった砂遊びの後に、手足に赤いブツブツができて、かゆがっていることはありませんか。
多くの保護者の方が、それは単なる砂かぶれだと考えがちですが、普通の砂かぶれとは異なる、砂かぶれ様皮膚炎(小児掌蹠丘疹性紅斑性皮膚炎)かもしれません。
この記事では、砂かぶれ様皮膚炎とは何か、普通の砂かぶれとの見分け方、家庭でできる適切なケア、そして皮膚科を受診するタイミングについて、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
砂かぶれ様皮膚炎とは?
お子さんの手足に見慣れない発疹を見つけると、誰しも心配になるものです。砂遊びの後に現れる症状は、見た目が似ていることもあり、どれも同じに見えてしまうかもしれません。
砂かぶれ様皮膚炎とはどんな病気か
砂かぶれ様皮膚炎は、正式名称を小児掌蹠丘疹性紅斑性皮膚炎(しょうにしょうせききゅうしんせいこうはんせいひふえん)と言います。
主に子供の(小児)、手のひら(手掌)や足の裏(足蹠)に、赤い盛り上がりのあるブツブツ(丘疹)や赤いシミ(紅斑)が現れる皮膚の病気です。
時に小さな水ぶくれ(小水疱)を伴うこともあり、子供にとっては耐え難いほどの強いかゆみや、時にはチクチクとした軽い痛みを伴うのが特徴です。
多くの場合、数週間で自然に治癒に向かいますが、症状が強かったり長引いたりする場合には、皮膚の炎症を抑えるため治療を必要とします。
何らかのウイルス感染が引き金になるという説が有力ですが、特定のウイルスが原因だと断定はされておらず、まだはっきりとした原因はわかっていません。
主にどの部位に症状が現れるか
この皮膚炎の症状は、特定の部位に集中して現れるという顕著な傾向があり、最も典型的な発症部位は、手のひらと足の裏です。
指の腹や側面、足の裏では土踏まずを避けた体重がかかる部分など、外部の物と接触しやすく、刺激を受けやすい場所に強く症状が出ることがあります。
症状の範囲は個人差が大きく、進行すると手の甲や足の甲、さらには手首や足首の周辺まで発疹が広がっていくことも珍しくありません。
稀なケースではありますが、膝やお尻に似たような症状が見られることも報告されていますが、基本的には手足が中心に左右対称性に現れるのが一つの目印です。
症状が現れやすい体の部位
| 主な部位 | 具体的な場所 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|
| 手 | 手のひら、指の腹、指の側面 | 数ミリ程度の小さな赤い丘疹が多発する。少し硬く触れることがある。 |
| 足 | 足の裏(特に体重がかかる部分)、足の側面 | 硬い丘疹や少しむくんだような紅斑が見られる。歩行時に違和感を訴える子もいる。 |
| その他 | 手の甲、足の甲、手首、足首 | 症状が強い場合に、中心部から外側へ広がるように発疹が見られることがある。 |
発症しやすい年齢と季節
砂かぶれ様皮膚炎は、乳幼児期から学童期の子供、特に活発に動き始める1歳から6歳くらいの子供に多く見られます。この年齢層の子供は、皮膚の構造自体が大人と比べて未熟であり、角層が薄く皮脂膜も不十分です。
皮膚のバリア機能がまだ十分に発達しておらず、外部からの様々な刺激に対して非常に敏感な状態にあり、また、公園の砂場や泥遊びなど、手足が直接刺激物に触れる機会が多いことも発症の一因です。
発症には明確な季節性があり、主に春から初夏にかけて、気温が上昇し戸外での活動が増える時期に多く報告されます。汗をかきやすくなることも、皮膚が蒸れてバリア機能が低下するため、症状の誘発や悪化に深く関係している可能性があります。
普通の砂かぶれと砂かぶれ様皮膚炎 症状の決定的な違い
砂かぶれと砂かぶれ様皮膚炎は、どちらも砂遊びをきっかけに症状が出ることが多いため、保護者の方々が混同しやすい皮膚トラブルの代表格ですが、この二つは原因の成り立ちも症状の経過も全く異なります。
症状の見た目の違い
普通の砂かぶれは、砂の粒子が皮膚を物理的に摩擦することで起こる、刺激性接触皮膚炎の一種です。症状は皮膚表面のざらつきや軽い赤み、カサつきが主で、一つ一つの発疹の境界はあまりはっきりしません。
一方、砂かぶれ様皮膚炎では、境界が比較的はっきりとした鮮やかな赤い丘疹や、少し盛り上がった紅斑が多発し、丘疹はドーム状に少し盛り上がっており、時には小さな水ぶくれや膿疱を伴うこともあります。
多くの場合で症状が手足の左右対称に現れやすいのも、普通の砂かぶれには見られない、砂かぶれ様皮膚炎の重要な特徴の一つです。
見た目の特徴比較
| 項目 | 普通の砂かぶれ(刺激性接触皮膚炎) | 砂かぶれ様皮膚炎 |
|---|---|---|
| 発疹の状態 | 境界が不明瞭な赤み、カサつきが中心 | 境界が比較的はっきりした赤い丘疹、紅斑 |
| 盛り上がり | ほとんどないか、ごくわずか | ドーム状に少し盛り上がっていることが多い |
| 水ぶくれ | 通常伴わない | 伴うことがある(小水疱) |
かゆみの強さと持続性
かゆみの程度とその性質も、両者を見分ける重要な判断材料です。
普通の砂かぶれのかゆみは、比較的軽度で一過性のものがほとんどで、原因となった砂をしっかりと洗い流し、皮膚を清潔にすれば、数時間から1日程度で自然と落ち着くことが多いでしょう。
砂かぶれ様皮膚炎のかゆみは非常に強く、執拗で持続的な傾向があり、かゆみは子供の日常生活に大きな影響を及ぼし、夜も眠れないほどかきむしってしまったり、日中もかゆみのために不機嫌になったり集中力がなくなったりするほどです。
強いかゆみは、単なる物理的刺激だけでなく、体の中での何らかの免疫学的な反応が関与していることを示唆しており、砂かぶれ様皮膚炎を強く疑うサインです。
治るまでの期間の比較
普通の砂かぶれは原因である砂の刺激がなくなれば、皮膚の自己修復能力によって速やかに改善し、通常は特別な治療をしなくても1日から2日程度で気にならなくなります。
しかし、砂かぶれ様皮膚炎は、一度発症するとなかなか治りにくいのが特徴で、皮膚科で治療を受け、家庭でのケアを丁寧に行っても、症状が完全に消えるまでには2週間から4週間、時にはそれ以上かかることも珍しくありません。
また、急性期の赤い発疹が治まった後も、しばらくは皮膚がカサカサと乾燥したり、薄皮がむけたり、炎症後の色素沈着によって茶色っぽいシミが残ったりすることがあります。
再発のしやすさ
普通の砂かぶれは、原因が明確な外的刺激なので、砂に触れるたびに誰にでも起こりうる一過性の皮膚トラブルです。
砂かぶれ様皮膚炎は、特定の素因を持つ子供が、ウイルス感染や物理的刺激といった何らかのきっかけで発症する内因性の疾患と考えられているため、一度治癒しても、同じような季節になると再び同じような症状を繰り返すことがあります。
毎年春から夏にかけて手足に原因不明の発疹が出る、というお子さんは、砂かぶれ様皮膚炎の可能性が高いです。
なぜ子供に多い?砂かぶれ様皮膚炎の原因を探る
なぜこの皮膚炎は、皮膚が丈夫な大人ではほとんど見られず、特定の年齢の子供に集中して発症するのでしょうか。背景には、子供特有の未熟な皮膚の状態や、活発な生活習慣が深く関わっています。
単なる砂の刺激だけではない
砂かぶれ様皮膚炎は、砂が直接的な原因物質だと思われがちですが、実際には砂の物理的な刺激だけが原因で発症するのではありません。
もし砂だけが原因なのであれば、砂遊びをするすべての子供が同じように発症するはずですが、実際には同じ環境で遊んでいても発症する子としない子がいます。
この事実は、子供自身の内的要因、すなわち個々の体質が発症に大きく関わっていることを物語っています。
発症に関わる要因の分類
| 外的要因(きっかけ・誘因) | 内的要因(素因・体質) |
|---|---|
| 砂や土との物理的接触 | アレルギーを起こしやすい素因(アトピー素因) |
| 汗による蒸れや化学的刺激 | 構造的に未熟な皮膚バリア機能 |
| 紫外線による皮膚へのダメージ | ウイルス感染などを契機とする免疫反応の特性 |
アレルギー素因との関連性
砂かぶれ様皮膚炎を発症する子供の背景を調べると、アトピー性皮膚炎や気管支喘息、アレルギー性鼻炎など、何らかのアレルギー疾患(アトピー疾患)を持っている、あるいは血縁家族にアレルギー体質の人がいることが多いと報告されています。
これは、アレルギー反応を起こしやすい体質、いわゆるアトピー素因が、この皮膚炎の発症しやすさに深く関係している可能性を示唆しています。
ただし、これは特定の物質に対するアレルギーというわけではなく、様々な刺激に対して皮膚が過敏に反応し、炎症を起こしやすい状態にある、と理解するのが適切です。
汗や紫外線が与える影響
この皮膚炎が春から夏にかけて多発することからも分かるように、汗や紫外線も重要な悪化要因として挙げられます。子供は新陳代謝が活発で、体に占める水分の割合も多いため、大人に比べて非常に汗をかきやすいです。
汗に含まれる塩分や尿素、アンモニアといった成分が、バリア機能の低下した皮膚には強い刺激となり、また、汗で皮膚が長時間湿った状態(蒸れ)が続くと、角層がふやけてバリア機能がさらに低下し、外部からの刺激を受けやすくなります。
さらに、春から夏にかけて強くなる紫外線は、それ自体が皮膚にダメージを与え、炎症を起こすきっかけになります。砂遊びで紫外線をたくさん浴び、いっぱい汗をかくという状況は、砂かぶれ様皮膚炎を発症しやすい環境です。
皮膚への影響要因
- 物理的刺激(砂、土、衣類の摩擦)
- 化学的刺激(汗、洗浄剤のすすぎ残し、消毒薬)
- 環境因子(紫外線、急激な温度・湿度の変化)
- 生物学的因子(ウイルス感染、細菌の付着)
皮膚のバリア機能の未熟さ
子供の皮膚は、見た目はすべすべで綺麗に見えますが、機能的には非常に未熟でデリケートです。皮膚の最も外側にあって体を守っている角層が、大人の半分から3分の2程度の厚さしかありません。
さらに、角層細胞の間を埋めて水分を保ち、外部からの異物の侵入を防ぐセラミドなどの細胞間脂質や、皮脂の分泌量も少ないため、外部の刺激から肌を守るための総合的なバリア機能がまだ十分に発達していません。
大人なら何ともないようなわずかな刺激(例えば、服のこすれや少しの乾燥)でも、容易に炎症を起こしてしまい、バリア機能が未熟な肌は、内部の水分が蒸発しやすく常に乾燥しがちです。
乾燥した肌はさらに刺激に敏感になるという「乾燥と炎症の悪循環」に陥りやすく、砂かぶれ様皮膚炎のような皮膚トラブルを起こす大きな土台となっています。
砂かぶれ様皮膚炎の診断
お子さんの症状が砂かぶれ様皮膚炎かもしれないと思ったら、自己判断で市販薬を使い続けるのではなく、一度は皮膚科専門医の診察を受けましょう。
問診で確認すること
診察室では、まず保護者の方から詳しくお話を聞くことから始まります。
問診では、いつから症状が始まったか、最初にどこにできたか、どのように広がったか、かゆみの程度はどれくらいか、夜は眠れているか、砂遊びや潮干狩りなど何かきっかけになった出来事はあるか、などを聞き取ります。
また、お子さん自身やご家族にアトピー性皮膚炎などのアレルギー歴があるかどうかも、体質を把握する上で大切な情報です。
問診での主な確認項目
| 確認項目のカテゴリー | 医師が知りたい具体的な情報 |
|---|---|
| 症状の経過 | 発症時期、初発部位、拡大の様子、症状の変動(日内・日間) |
| 自覚症状 | かゆみの強さ(睡眠への影響)、痛みの有無、熱感 |
| 既往歴・家族歴 | アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎・結膜炎の有無 |
| 生活歴 | 最近の戸外活動(砂遊びなど)、発疹前の風邪症状の有無 |
視診による症状の評価
次に行うのが視診で、発疹の色、形、大きさ、表面の状態(カサカサか、ジクジクか)、分布範囲などを詳しく見て、砂かぶれ様皮膚炎に特徴的な所見があるかを確認します。
手のひらや足の裏に、赤い盛り上がった丘疹が左右対称に見られるか、一つ一つの発疹が融合していないか、水ぶくれを伴っていないか、などを注意深くチェックします。
また、掻き壊した傷(搔破痕)や、そこから細菌が二次感染を起こしていないかも、治療方針を決める上で重要な観察ポイントです。
必要に応じて行う検査
通常、典型的な砂かぶれ様皮膚炎の診断に、特別な検査は必要ありませんが、症状が非典型的であったり、手足口病やジアノッティ・クロスティ症候群、汗疱状湿疹などとの区別が難しい場合には、診断を補助する追加の検査を行うことがあります。
水ぶくれの内容物や皮膚の表面をこすって顕微鏡で観察し、特定のウイルスや真菌(カビ)、細菌がいないかを確認することがあります。
また、アレルギーの関与をより詳しく調べるために血液検査(特異的IgE抗体検査など)を行うこともあります。
これは、診断を確定させるためではなく、お子さんのアレルギー体質を把握し、今後のスキンケア指導などに役立てる目的で行うことが多いです。
家庭でできる砂かぶれ様皮膚炎の正しいケア方法
砂かぶれ様皮膚炎の治療は、皮膚科で処方されるステロイド外用薬などの薬物療法が中心となりますが、それ以上に大切なのが、毎日の家庭でのスキンケアです。
基本は洗浄と保湿
すべてのスキンケアの基本は、皮膚を清潔に保ち、十分なうるおいを与えることです。砂遊びなどから帰宅したら、まず手足を優しく洗い、付着した砂や汗、その他の汚れをしっかりと落としましょう。
このとき、ナイロンタオルなどでゴシゴシこするのは絶対に禁物です。皮膚のバリアをさらに傷つけてしまうので、刺激の少ない弱酸性の石鹸やボディソープをよく泡立て、たっぷりの泡でなでるように優しく洗うのがコツです。
洗浄後は、すすぎ残しがないようにぬるま湯で洗い流し、清潔で柔らかいタオルで水分をそっと押さえるように拭き取ります。そして、皮膚が完全に乾ききる前の、まだ少し湿り気があるうちに、すぐに保湿剤をたっぷりと塗りましょう。
正しい洗浄の手順
- 38〜40℃のぬるま湯で予洗いする
- 洗浄剤を泡立てネットなどで十分に泡立てる
- 泡をクッションにして、手で優しくなでるように洗う
- 洗浄成分が皮膚に残らないようしっかりすすぐ
- 柔らかいタオルでこすらずに押さえ拭きする
かゆみを和らげるための工夫
強いかゆみは、子供にとって非常につらいものです。我慢できずにかきむしってしまうと、皮膚のバリア機能がさらに破壊され、炎症が悪化する「イッチ・スクラッチサイクル」という悪循環に陥ります。
それだけでなく、掻き傷から細菌が侵入して二次感染(とびひなど)を起こす危険もあるので、かゆみを少しでも和らげるために、患部を冷たいおしぼりや、タオルで包んだ保冷剤などで短時間冷やすのが効果的です。
冷やすことで、かゆみを感じる神経の働きが一時的に鈍くなりますが、冷やしすぎによる凍傷には注意してください。また、爪は常に短く丸く切っておき、もし掻いてしまっても皮膚へのダメージが最小限になるようにしましょう。
市販薬を使用する際の注意点
ドラッグストアには様々な皮膚用の市販薬が並んでおり、手軽に購入できますが、砂かぶれ様皮膚炎に自己判断で使用するのは注意が必要です。
特に、ステロイド外用薬は炎症を抑える効果が高い反面、強さのランクが様々であり、症状や部位、年齢に合わないものを使用すると、皮膚が薄くなるなどの副作用のリスクがあります。
また、かゆみ止めとして販売されている抗ヒスタミン成分の塗り薬や、局所麻酔成分を含む薬は、それ自体が接触皮膚炎(かぶれ)の原因となることがあるため、漫然と長期間使用するのは避けるべきです。
症状がごく軽い場合は市販の保湿剤でのケアを基本とし、改善しない場合や赤みやかゆみが強い場合は、必ず皮膚科医の診察を受けて、症状に合った適切な薬を処方してもらうことが、最も安全で早い回復への近道です。
保湿剤の主な種類と特徴
| 種類 | 主な成分の例 | 特徴・使用感 |
|---|---|---|
| ヘパリン類似物質製剤 | ヘパリン類似物質 | 高い保湿力に加え、血行促進作用、抗炎症作用を併せ持つ。クリーム、ローション、フォームなど剤形が豊富で使いやすい。 |
| 尿素系製剤 | 尿素 | 角層に水分を取り込み、硬くなった皮膚を柔らかくする作用がある。ただし、傷や炎症が強い部分にしみることがあるので注意が必要。 |
| ワセリン基剤 | 白色ワセリン | 皮膚表面に油性の膜を作り水分の蒸発を防ぐ(エモリエント効果)。刺激は極めて少ないが、べたつきやすいのが難点。 |
正しい保湿剤の選び方と塗り方
保湿剤は、お子さんの肌質や季節、使用感の好みに合った、刺激の少ないものを選ぶことが継続の鍵です。一般的には、夏場はさっぱりとしたローションタイプ、冬場はしっとりとしたクリームタイプなどと使い分けるのも良いでしょう。
塗る量の目安として、人差し指の第一関節の先までチューブから出した量(約0.5g、これを1フィンガーチップユニットと言います)で、大人の手のひら2枚分の面積に塗るのが適量とされています。
たっぷり塗るのがポイントで、塗った後に皮膚が少し光り、ティッシュペーパーが貼りつくくらいが目安です。皮膚のシワに沿って、手のひらで優しくなでるように塗り広げましょう。
お風呂上がり直後はもちろん、朝の着替えの時や、日中乾燥が気になった時など、1日に数回こまめに塗ることで、皮膚のうるおいを効果的に保つことができます。
悪化させないために 日常生活で注意すべきポイント
皮膚科での治療や日々のスキンケアと並行して、日常生活の中に潜む症状の悪化要因を一つずつ減らしていくことも、健やかな肌を取り戻すためには非常に大切です。
掻き壊しを防ぐ対策
強いかゆみから皮膚を掻き壊してしまうことは、症状を悪化させ、治療を長引かせる最大の要因です。
冷却法や爪を短く切っておくといった基本的な対策に加え、子供が患部を掻いているのに気づいたら、「かゆいね、冷やそうか」と声をかけたり、好きなおもちゃや絵本で気を紛らわせたりするなどして、対応しましょう。
夜間に無意識に掻いてしまう場合には、柔らかい綿素材の手袋をさせたり、通気性の良い長袖長ズボンを着用させたりするのも一つの方法です。
どうしてもかゆみがコントロールできない場合は、かゆみを抑える抗ヒスタミン薬の飲み薬を皮膚科で処方してもらうこともできますので、我慢せずに相談しましょう。
掻き壊し対策のポイント
- 爪を常に短く丸く切っておく
- 冷たいおしぼりなどで局所を冷やす
- 保湿を徹底し、皮膚の乾燥を防ぐ
- 就寝時にミトンや肌触りの良い衣類を着用させる
- かゆみ止めの内服薬について医師に相談する
衣服や靴の選び方
肌に直接触れる衣類は、皮膚への刺激ができるだけ少ないものを選ぶことが大事で、素材は、吸湿性と通気性が良く、肌触りの柔らかい綿(コットン)100%のものが最もおすすめです。
ゴワゴワした素材や、チクチク感のあるウール、汗を吸いにくい化学繊維は、かゆみを誘発することがあるので避けましょう。縫い目やタグが肌に当たって刺激にならないように、裏返して着せたり、タグを外したりするのも良い工夫です。
靴や靴下も同様に、通気性の良い素材のものを選び、足が汗で蒸れないように注意します。特に夏場は、裸足でサンダルを履く機会が増えますが、靴ずれなどが新たな刺激にならないよう、必ず足のサイズに合った靴を選んであげてください。
衣類選びのチェックリスト
| ポイント | 推奨されるもの | 避けるべきもの |
|---|---|---|
| 素材 | 綿(コットン)、シルク | ウール、化学繊維(ナイロン、アクリルなど) |
| デザイン | ゆったりとしたサイズ、縫い目が少ない、タグが外側にある | 身体にぴったりと密着するデザイン、レースなどの装飾が多い |
| 洗濯 | 低刺激性の液体洗剤を使用し、すすぎを十分に行う | 香料や蛍光増白剤の強い粉末洗剤、柔軟剤の過度な使用 |
砂場遊びでの注意点
急性期で症状が強く出ている間は、さらなる悪化を防ぐためにも、基本的に砂場遊びは控えてください。
症状が落ち着いてきて、お子さんがどうしても遊びたがる場合は、時間を30分以内など短く区切る、遊んだ後はすぐに手足をきれいに洗うなどの対策を徹底することが前提です。
一般的に、乾いたサラサラの砂よりも、湿った砂の方が皮膚に付着しやすく、摩擦による刺激が強くなる傾向があると言われています。
また、公園の砂場は動物のフンなどが混入している可能性もあり、衛生状態が必ずしも良いとは限らないため、掻き壊した傷があると細菌感染のリスクも高まります。
食生活で気をつけたいこと
現在のところ、特定の食べ物が砂かぶれ様皮膚炎を直接起こしたり、悪化させたりするという医学的な証拠はないので、自己判断で極端な食事制限を行う必要は全くありません。
皮膚の材料となる良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)、皮膚の新陳代謝を助けるビタミンB群(豚肉、レバーなど)、抗酸化作用があり炎症を抑える働きも期待されるビタミンCやビタミンE(緑黄色野菜、果物など)を意識して摂りましょう。
香辛料を多く使った刺激的な食べ物や、チョコレートなどのお菓子類は、血行を促進して体がかゆみを感じやすくさせることがあるため、症状が特に強い時期は少し控えてください。
皮膚の健康に役立つ栄養素
| 栄養素 | 期待される働き | 多く含まれる食品の例 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 皮膚細胞の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| ビタミンB群 | 皮膚のターンオーバーを助ける | 豚肉、レバー、うなぎ、納豆、玄米 |
| ビタミンC/E/A | 抗酸化作用、皮膚の健康維持 | 緑黄色野菜、果物、ナッツ類、かぼちゃ |
砂かぶれ様皮膚炎に関するよくある質問(Q&A)
最後に、実際の診察の場で保護者の方からよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 砂かぶれ様皮膚炎は他の子供にうつりますか?
-
砂かぶれ様皮膚炎は、ウイルスや細菌が直接の原因となる感染症ではないため、人から人へとうつることはありません。
発疹が出ているお子さんと一緒に遊んだり、プールやお風呂に一緒に入ったりしても問題ありませんのでご安心ください。
ただし、掻き壊した傷口に黄色ブドウ球菌などが感染して二次感染(伝染性膿痂疹、とびひ)を起こした場合は、とびひが他の人にうつる可能性はあるので、皮膚を清潔に保ち、掻き壊さないようにケアすることが大切です。
- 症状が治まれば砂場で遊ばせても良いですか?
-
遊ばせても大丈夫ですが、再発しやすいので、いくつかの注意が必要です。赤みやブツブツが完全に消え、皮膚の状態が落ち着いたのを確認してからにしましょう。
遊ぶ前には、刺激から肌を守るためにワセリンや保湿剤を少し厚めに塗り、保護膜を作ってあげ、遊ぶ時間は短めに設定し、遊んだ後はできるだけ早く手足を優しく洗い、再び保湿ケアを徹底してください。
このような対策を行うことで、再発のリスクを減らすことができます。
- プールやお風呂には入れますか?
-
どちらも入れますが、いくつか注意点があります。お風呂は皮膚の汗や汚れを落とし清潔にするために、毎日入るのが基本です。
熱いお湯は血行を良くしてかゆみを増すことがあるので、38〜40度くらいのぬるめのお湯にしましょう。石鹸のすすぎ残しにも注意してください。
プールに関しては、消毒に使われる塩素が敏感な肌の刺激になることがあるため、ジュクジュクしているなど症状がひどい時は避けた方が無難です。
症状が落ち着いている時に入る場合でも、プールから上がったらすぐにシャワーで塩素をよく洗い流し、忘れずに保湿剤を塗るようにしてください。
- この病気は大きくなれば治りますか?
-
ほとんどの場合は成長とともに自然に発症しなくなります。砂かぶれ様皮膚炎は、皮膚のバリア機能が未熟な幼児期に特有の疾患です。
年齢が上がり、小学校高学年から中学生くらいになると、皮膚の構造や機能が大人に近づいて丈夫になるため、同じような刺激を受けても発症することはほとんどなくなります。
再発を繰り返すお子さんでも、成長とともに軽快していくことがほとんどですので、あまり心配しすぎず、その時々の症状に対してスキンケアを続けてあげることが大切です。
以上
参考文献
Higashi N, Fukai K, Tsuruta D, Nagao J, Ohira H, Ishii M. Papular‐purpuric gloves‐and‐socks syndrome with bloody bullae. The Journal of Dermatology. 2002 Jun;29(6):371-5.
Chuh A, Zawar V, Sciallis GF, Kempf W, Lee A. Pityriasis rosea, Gianotti-Crosti syndrome, asymmetric periflexural exanthem, papular-purpuric gloves and socks syndrome, eruptive pseudoangiomatosis, and eruptive hypomelanosis: do their epidemiological data substantiate infectious etiologies?. Infectious disease reports. 2016 Mar 21;8(1):6418.
Seguí N, Zayas A, Fuertes A, Marquina A. Papular-purpuric’gloves-and-socks’ syndrome related to rubella virus infection. Dermatology. 2000;200(1):89.
Scaparrotta A, Rossi N, Attanasi M, Petrosino MI, Di Pillo S, Chiarelli F. A strange rash with “gloves and socks” distribution. Archives of Medical Science. 2015 Aug 11;11(4):908-10.
Smitha SB, Libowa LF, Elstona DM, Bernerta RA, Warschaw KE. Gloves and socks syndrome: early and late histopathologic features. Journal of the American Academy of Dermatology. 2002 Nov 1;47(5):749-54.
Hsieh MY, Huang PH. The juvenile variant of papular–purpuric gloves and socks syndrome and its association with viral infections. British Journal of Dermatology. 2004 Jul 1;151(1):201-6.
Gutermuth J, Nadas K, Zirbs M, Seifert F, Hein R, Ring J, Brockow K. Papular-purpuric gloves and socks syndrome. The Lancet. 2011 Jul 9;378(9786):198.
Harms M, Feldmann R, Saurat JH. Papular-purpuric “gloves and socks” syndrome. Journal of the American Academy of Dermatology. 1990 Nov 1;23(5):850-4.
VARGAS‐DÍEZ ER, Buezo GF, Aragües M, Dauden E, De Ory F. Papular‐purpuric gloves‐and‐socks syndrome. International journal of dermatology. 1996 Sep;35(9):626-32.
Zelman B, Muhlbauer A, Kim W, Speiser J. A rare case of papular‐purpuric “gloves and socks” syndrome associated with influenza. Journal of Cutaneous Pathology. 2022 Jul;49(7):632-7.