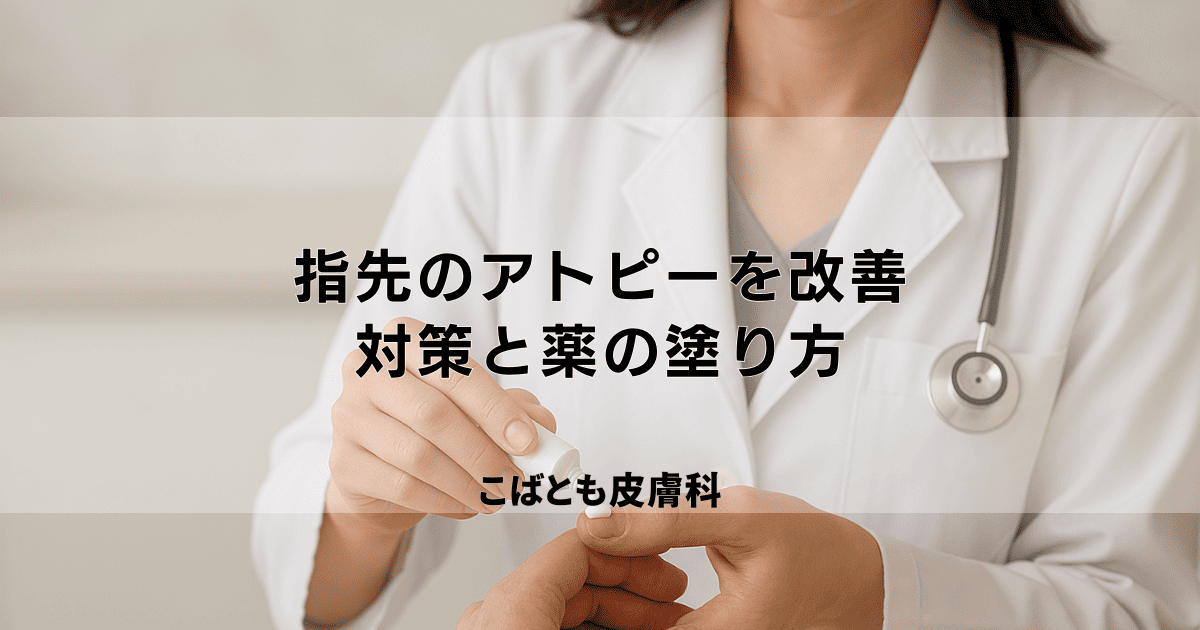指先のひび割れ、かゆみ、そしてジンジンとした痛みに、長年悩まされていませんか。一度悪化すると、日常生活のあらゆる場面でつらさを感じ、なかなか治らない指先のアトピー性皮膚炎は、多くの方にとって深刻な問題です。
水仕事が多い方にとっては、改善を諦めかけているかもしれませんが、対策をすれば症状をコントロールし、健やかな指先を取り戻すことはできます。
この記事では、なぜ指先のアトピーが治りにくいのか、根本的な原因から、日々の水仕事の対策、皮膚科で処方される薬の正しい塗り方、ご自身でできるセルフケアまで、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
なぜ指先のアトピーは一度なると治りにくいのか?
指先は、体の他の部分とは少し違う特徴を持っていて、皮膚の構造や、日常的に置かれている環境が、アトピー性皮膚炎を一度発症するとなかなか治りにくく、再発を繰り返す要因になっています。
指先の皮膚は薄くバリア機能が弱い
皮膚は、外部の刺激や乾燥から体を守るバリア機能を持っていますが、指先の皮膚、特に指の腹の部分は、手のひらや足の裏と同じように角層が厚い一方で、他の部位に比べて皮膚全体としては薄いことが特徴です。
さらに、物を掴んだり触ったりすることで常に摩擦を受けるため、角層が傷つきやすく、バリア機能が低下しやすい状態にあり、バリア機能が弱まると、アレルゲンや刺激物質が皮膚の内部に侵入しやすくなり、炎症やかゆみを起こします。
炎症が繰り返されることで、皮膚はさらに薄く、敏感になり、アトピーの症状が慢性化してしまうのです。
絶えず外部からの刺激にさらされる部位
手、特に指先は、一日の中で最も多く外部の物と接触する部位です。仕事でパソコンのキーボードを打つ、書類をめくる、料理をする、掃除をするといった日常の何気ない動作すべてが、指先にとっては刺激となります。
洗剤、シャンプー、石鹸、アルコール消毒液などの化学物質に触れる機会も頻繁にあり、また、紙や段ボールなどを扱うと、指先の水分や油分が奪われ、乾燥が進みます。
指先は常に物理的・化学的な刺激にさらされているため、炎症が治まる暇がなく、症状が長引きやすい環境にある部位です。
指先の皮膚と他の部位の皮膚の比較
| 比較項目 | 指先の皮膚 | 腕の皮膚 |
|---|---|---|
| 皮脂腺の量 | 非常に少ない | 比較的多い |
| 汗腺の密度 | 非常に高い | 普通 |
| 受ける刺激 | 物理的・化学的刺激が常に多い | 衣類による摩擦が主 |
皮脂腺が少なく極度に乾燥しやすい
皮膚の潤いを保ち、バリア機能を維持するためには、皮脂腺から分泌される皮脂が作る天然の保湿膜が重要ですが、手のひらや指先には、皮脂腺がほとんどありません。そのため、指先はもともと非常に乾燥しやすい部位です。
水仕事や手洗いによって必要な皮脂膜が洗い流されると、水分がどんどん蒸発してしまい、深刻な乾燥状態に陥ります。
乾燥した皮膚は、ひび割れやあかぎれを起こしやすく、そこからさらに刺激物質が侵入して炎症が悪化するという負の連鎖につながります。
治りかけてもすぐに悪化を繰り返す悪循環
指先のアトピーは、少し良くなったかと思うと、またすぐに悪化することを繰り返しやすく、これは、バリア機能の低下、絶え間ない外部刺激、そして乾燥しやすい性質という3つの要因が複雑に絡み合っているためです。
薬を塗って一時的に炎症が治まっても、水仕事や作業ですぐに皮膚が傷つき、再び炎症がぶり返してしまいます。また、かゆみを感じて無意識にかきむしってしまうことも、バリア機能をさらに破壊し、症状を悪化させる大きな原因です。
指先のアトピーを悪化させる日常生活の落とし穴
毎日当たり前のように行っている習慣が、知らず知らずのうちに指先のアトピーを悪化させていることがあります。症状を改善するためには、治療と同時に、生活の中に潜む悪化要因を見つけ出し、一つひとつ丁寧に取り除いていくことが大切です。
洗剤やシャンプーの使いすぎ
食器用洗剤や洗濯洗剤、シャンプー、ボディソープなどに含まれる界面活性剤は、油汚れを落とす強力な洗浄力を持っていますが、汚れだけでなく、皮膚を守るために必要な皮脂まで根こそぎ奪ってしまいます。
洗浄力の強い製品を素手で長時間使用することは、皮膚のバリア機能を著しく低下させ、アトピーを悪化させる直接的な原因となります。
また、製品に残っている香料や防腐剤などの化学物質がアレルゲンとなり、接触皮膚炎(かぶれ)を併発することもあり、できるだけ素手で洗剤類に触れる機会を減らす工夫が必要です。
日常生活で注意したい化学物質
| 種類 | 含まれる製品の例 | 指先への影響 |
|---|---|---|
| 界面活性剤 | 食器用洗剤、シャンプー、石鹸 | 皮脂を奪い、乾燥を促進する |
| アルコール類 | 手指消毒液、ウェットティッシュ | 水分を蒸発させ、乾燥や刺激の原因になる |
| 香料・防腐剤 | 化粧品、ハンドソープ、洗剤 | アレルギー反応を引き起こすことがある |
手を洗いすぎる習慣と熱いお湯の使用
清潔を保つために手洗いは重要ですが、過度な手洗いは逆効果で、一日に何度も石鹸を使って手を洗うと、そのたびに皮脂膜が失われ、皮膚は無防備な状態になります。特に、殺菌効果を謳う薬用石鹸は、刺激が強い場合があるため注意が必要です。
また、熱いお湯は皮脂を溶かし出しやすく、乾燥を助長するので、手洗いや水仕事の際には、少しぬるいと感じるくらいの温度の水かお湯を使うように心がけましょう。
手を洗った後は、必ず清潔なタオルで優しく水分を拭き取り、すぐに保湿剤を塗る習慣をつけることが大切です。ゴシゴシと強くこするように拭くのは、摩擦による刺激となるため避けてください。
素手での作業や摩擦による刺激
日常生活には、指先に物理的な刺激を与える作業が多く潜んでいます。ガーデニングでの土いじり、段ボールの開梱、新聞紙や雑誌をめくる行為なども、指先の水分と油分を奪い、細かい傷をつける原因です。
また、指輪や腕時計などのアクセサリーがこすれることや、きつい手袋による摩擦も刺激になります。細かい作業をするときでも、できるだけ薄手の手袋を着用するなど、指先を保護する意識を持つことが症状の改善につながります。
かゆいときに爪を立ててかく行為は最も避けなければなりません。かくことで皮膚が傷つき、炎症がさらに広がるだけでなく、雑菌が侵入して感染症を引き起こすリスクもあります。
- 段ボールの開梱・片付け
- 新聞紙や雑誌を読む
- 土いじりや園芸作業
- 指先の乾燥した状態で布製品に触れる
- 爪でシールなどを剥がす行為
ストレスや睡眠不足による免疫力の低下
皮膚の状態は、心身の健康状態を映し出す鏡ともいわれています。
精神的なストレスや過労、睡眠不足が続くと、自律神経のバランスが乱れ、免疫機能が正常に働かなくなり、皮膚の炎症を抑える力が弱まり、アトピーの症状が悪化しやすくなります。
かゆみで夜眠れなくなり、それがまたストレスになるという悪循環に陥ることも少なくありません。
十分な睡眠時間を確保し、リラックスできる時間を作る、適度な運動を取り入れるなど、ストレスを上手に管理することも、指先のアトピーを改善するための重要な要素です。
毎日の水仕事とうまく付き合うための工夫
水仕事は、指先のアトピーにとって最大の悪化要因の一つですが、生活する上で完全に避けることはできません。大切なのは、水仕事によるダメージを最小限に抑えるための正しい知識と工夫です。
水仕事の基本は手袋の着用
食器洗いや掃除、洗濯物を干すときなど、洗剤や水に触れる作業をする際には、必ず手袋を着用することを徹底しましょう。
これが最も効果的で基本的な対策です。素手で作業するのと手袋を着けるのとでは、指先への負担が全く異なります。
短時間の作業だからと油断せず、コップ一杯を洗うだけでも手袋を着ける習慣をつけ、小さな積み重ねが、バリア機能の回復につながります。
手袋の選び方と正しい使い方
手袋には様々な種類がありますが、アトピーの症状がある場合は、素材の選び方が重要です。
ゴム手袋はアレルギー(ラテックスアレルギー)を起こす可能性があるため、ビニール製やニトリルゴム製のものを選ぶと良いでしょう。
また、ゴム手袋を直接つけると、手袋の中で汗をかいて蒸れてしまい、かえって症状を悪化させることがあります。これを防ぐために、まず肌触りの良い綿の手袋をはめ、その上からビニール手袋などを重ねて着用する二重手袋がおすすめです。
綿の手袋が汗を吸収し、指先を快適な状態に保ちます。使用後の手袋は、内側をよく乾かして清潔に保つことも忘れないでください。
手袋の種類と特徴
| 手袋の種類 | 特徴 | おすすめの使い方 |
|---|---|---|
| 綿手袋 | 吸湿性が高く、肌に優しい | ゴム手袋の下ばき用、就寝時の保護用 |
| ビニール手袋 | ラテックスアレルギーの心配がない | 食器洗いや掃除などの水仕事全般 |
| ニトリル手袋 | 強度があり、油にも強い | 料理の下ごしらえ、長時間の作業 |
水仕事の前後に欠かせない保湿ケア
手袋を使うことに加えて、水仕事の前後のケアも大切です。作業を始める前に、指先にワセリンなどの撥水性の高い保湿剤を塗っておくと、皮膚の保護膜となり、万が一水が侵入した際のダメージを軽減できます。
水仕事が終わった後はすぐに手袋を外し、手を洗って清潔にした後、できるだけ早く保湿剤を塗りましょう。水分が蒸発して乾燥が進む前にケアをすることが重要です。
- 水仕事の前には撥水性の高い保湿剤を塗る
- 水仕事中は必ず手袋(二重が望ましい)を着用する
- 水仕事後はすぐに手を拭き、保湿剤をたっぷり塗る
塗り薬の効果を最大限に引き出す正しい使い方
皮膚科で処方されるステロイド外用薬や保湿剤は、指先のアトピー治療の主役ですが、ただ何となく塗っているだけでは、薬が持つ本来の効果を十分に引き出すことはできません。
薬を塗る前の準備とタイミング
薬を塗る前にはまず手を洗い、清潔な状態にすることが基本です。汚れた手で薬を塗ると、雑菌が一緒に塗り込まれてしまい、症状を悪化させる原因になりかねません。
手を洗った後は、清潔なタオルで優しく押さえるようにして水分を拭き取り、皮膚がまだ少し湿っているうちに塗ると、薬の伸びが良くなり、浸透しやすくなります。薬を塗る最も効果的なタイミングは、入浴後です。
入浴後の皮膚は水分を含んで柔らかくなっており、薬の吸収が格段に高まります。その他、手洗い後や水仕事の後など、こまめに塗り直すことも大切です。
ステロイド外用薬の適切な量と塗り方
ステロイド外用薬は、炎症を強力に抑える効果がありますが、使用量が少なすぎると十分な効果が得られません。
適切な量の目安として、フィンガーチップユニット(FTU)という考え方があり、これは、大人の人差し指の第一関節までチューブから薬を絞り出した量(約0.5g)で、大人の手のひら2枚分の面積に塗るのが適量とされています。
指先のような細かい部分に塗る場合は、患部がテカっと光り、ティッシュペーパーが貼りつくくらいが目安です。薬をすり込むのではなく、患部に優しく置き、指の腹で広げるように塗りましょう。
ひび割れがある場合は、割れ目にも薬がしっかり入るように丁寧に塗ります。
ステロイド外用薬の強さの目安
| ランク | 強さ | 主な使われ方 |
|---|---|---|
| I群 | 最も強い(Strongest) | 非常に症状が重い場合(顔や陰部には通常使わない) |
| II群 | かなり強い(Very Strong) | 症状が重い場合(体幹や四肢など) |
| III群 | 強い(Strong) | 顔や子どもの体などデリケートな部位にも使われる |
保湿剤との併用で効果アップ
多くの場合、皮膚科ではステロイド外用薬と保湿剤が一緒に処方され、併用することで、治療効果を大きく高めることができます。
塗る順番については、医師の指示に従うのが基本ですが、特に指示がない場合は、まず保湿剤を指全体、あるいは手全体に広く塗り、皮膚に潤いを与えてから、ステロイド外用薬を炎症が起きている患部にのみ重ねて塗るのが一般的です。
保湿剤で皮膚のバリア機能を補い、ステロイドで炎症を抑えるという、二つのアプローチを組み合わせることで、より早く症状を改善し、再発しにくい状態を作ることができます。
症状が良くなった後の塗り薬のやめ方
ステロイド外用薬を自己判断で急にやめてしまうと、抑えられていた炎症が再びぶり返すリバウンドが起こることがあります。
症状が良くなってきたら、塗る回数を1日2回から1回へ、そして2日に1回へと徐々に減らしていくのが一般的な方法です。
見た目には綺麗になっても、皮膚の内部ではまだ弱い炎症がくすぶっていることがあるため、医師の指示なく中断しないことが重要です。
最終的にステロイド外用薬が不要になった後も、保湿剤によるスキンケアは毎日継続し、良好な皮膚状態を維持するよう努めましょう。
- 医師の指示なく急に中断しない
- 塗る回数や頻度を徐々に減らしていく
- 見た目がきれいになってもすぐにはやめない
- 症状が落ち着いた後も保湿ケアは続ける
薬だけに頼らないセルフケアのすすめ
薬による治療は炎症を抑えるために非常に重要ですが、同時に、自分自身の皮膚を健やかに保つためのセルフケアを習慣にすることが、根本的な改善と再発予防につながります。
保湿の徹底がバリア機能回復の鍵
指先のアトピーケアの基本であり、最も重要なのが保湿です。皮膚のバリア機能が低下している状態では、いくら良い薬を使っても外からの刺激が入り込みやすく、なかなか改善しません。
保湿剤をこまめに塗ることで、失われた皮脂膜の代わりとなり、水分の蒸発を防ぎ、外部の刺激から皮膚を守り、手を洗った後、入浴後、水仕事の後、就寝前は必ず保湿剤を塗ってください。
日中も、乾燥を感じる前に予防的に塗るのが理想です。ベタつきが気になる場合は、日中はさらっとしたローションやクリームタイプ、夜はしっかり保護できる軟膏やワセリンタイプと使い分けるのも良いでしょう。
保湿剤の種類と選び方
| 種類 | 特徴 | おすすめのシーン |
|---|---|---|
| ローション | 水分が多く、さっぱりした使用感 | 日中の塗り直し、広範囲への使用 |
| クリーム | 油分と水分のバランスが良い | 日常的な保湿、入浴後など |
| 軟膏・ワセリン | 油分が多く、保護力が非常に高い | 就寝前、特に乾燥がひどい部位 |
爪を短く切り清潔に保つ
かゆみを感じたとき、無意識のうちにかきむしってしまうことは誰にでもあります。
しかし、爪が長いと、皮膚を深く傷つけてしまい、症状を悪化させるだけでなく、爪の間にいる細菌が傷口から侵入し、二次感染(とびひなど)を起こす原因になります。
これを防ぐためにも、爪は常に短く切り、角が滑らかになるようにやすりで整えておき、爪と指の間の汚れもこまめに取り除き、清潔な状態を保つことが大切です。
かゆみが我慢できないときは、冷たいタオルや保冷剤を当てるなどして、かきむしる以外の方法でかゆみを鎮める工夫をしましょう。
血行を促進して皮膚の再生を助ける
指先のような末端の部位は、血行が悪くなりがちです。血行が悪いと、皮膚の細胞に必要な栄養や酸素が十分に行き渡らず、皮膚の再生(ターンオーバー)が遅れてしまい、傷や炎症が治りにくくなります。
適度な運動や入浴で全身の血行を良くすることに加え、指先そのものの血行を促進する簡単なマッサージやストレッチを取り入れるのも効果的です。
ただし、炎症が強いときや傷があるときは、マッサージによる刺激が逆効果になることもあるため、症状が落ち着いているときに行いましょう。指先を温めることも血行改善に役立ちます。
- 指を一本ずつゆっくり反らすストレッチ
- 指の付け根から指先に向かって優しく揉む
- 指先でグー、パーを繰り返す運動
指先のアトピー治療における注意点と皮膚科受診の目安
指先のアトピーはセルフケアも重要ですが、自己判断だけで対処しようとすると、かえって症状をこじらせてしまう危険性もあります。正しい知識を持ち、必要なときには専門家である皮膚科医の診断を受けることが、快方への一番の近道です。
民間療法や自己判断のリスク
インターネットや口コミで広まる様々な民間療法の中には、医学的な根拠が乏しいものや、アトピーの肌には刺激が強すぎるものも少なくありません。
特定の食品を極端に制限したり、効果が証明されていないオイルやクリームを塗ったりすることで、栄養バランスが崩れたり、かぶれ(接触皮膚炎)を起こしたりする可能性があります。
また、ステロイド外用薬に対する誤った情報から使用をためらい、適切な治療の機会を逃してしまうケースも見られます。自己判断で治療を進める前に、まずは皮膚科で正確な診断を受けることが重要です。
市販薬で改善しない場合は早めに受診を
市販薬にもアトピー性皮膚炎に効果のある薬はありますが、多くは比較的症状が軽い場合を想定しています。
市販薬を1週間程度使用しても症状が全く改善しない、あるいはかえって悪化するような場合は、使用を中止して速やかに皮膚科を受診してください。
症状に合わない薬を使い続けると、治療が長引くだけでなく、色素沈着などの跡が残ってしまうこともあります。専門医は、症状の重さや部位、年齢などを総合的に判断し、最も適した強さの薬を処方します。
皮膚科を受診すべき症状の例
| 症状 | 考えられる状態 | 対応 |
|---|---|---|
| 強いかゆみで眠れない | 炎症がコントロールできていない | 早めの受診が必要 |
| ひび割れが深く、出血する | 皮膚の損傷が激しい | 適切な処置と薬が必要 |
| じゅくじゅくして黄色い汁が出る | 細菌感染の可能性 | 抗生物質の投与が必要な場合がある |
皮膚科で行う専門的な治療法
皮膚科での治療は、ステロイド外用薬や保湿剤の処方が基本となりますが、それだけではありません。かゆみが非常に強い場合には、抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬の内服薬を併用して、かゆみを内側から抑えます。
症状が重度で、外用薬だけではコントロールが難しい場合には、免疫抑制薬の外用薬や内服薬、紫外線療法(光線療法)、さらには注射薬(生物学的製剤)など、より専門的な治療法も選択肢です。
指先のアトピーに関するよくある質問
ここでは、指先のアトピー性皮膚炎について、患者さんからよくいただく質問と回答をまとめました。
- 食べ物で気をつけることはありますか?
-
アトピー性皮膚炎と食物アレルギーは関連がある場合もありますが、成人において特定の食べ物が直接指先の症状を悪化させるケースは比較的少ないと考えられています。
ただし、一般的に、香辛料の多い刺激物や、ヒスタミンを多く含む食品(アクの強い野菜、一部の青魚、加工食品など)は、かゆみを増強させることがあります。
バランスの取れた食事を基本とし、もし特定の食べ物を食べた後に決まって症状が悪化するようであれば、一度食べるのをやめてみて、皮膚科医に相談してみるのが良いでしょう。
自己判断で極端な食事制限を行うことは避けてください。
- 絆創膏や保護テープは使ってもいいですか?
-
ひび割れが深く、水仕事などでしみる場合には、一時的に絆創膏や保護フィルムで保護することは有効です。外部の刺激から傷口を守り、痛みを和らげる助けになります。
ただし、長時間貼りっぱなしにすると、蒸れてかぶれたり、剥がすときに皮膚を傷つけたりすることがあるので、粘着力の弱い製品を選び、こまめに取り替えましょう。
また、薬を塗った上からラップを巻く密封療法(ODT)という方法もありますが、薬の吸収を高めすぎて副作用のリスクもあるため、必ず医師の指導のもとで行ってください。
- 症状が良くなったり悪くなったりを繰り返します。どうすればいいですか?
-
アトピー性皮膚炎は、残念ながらすぐに完治する病気ではなく、良くなったり悪くなったり(寛解と増悪)を繰り返しながら、長期的に付き合っていくことが多い皮膚疾患です。
大切なのは、症状が良い時でも油断せず、保湿などの基本的なスキンケアを毎日続けることです。良い状態を維持するプロアクティブ療法(症状が出る前に定期的に薬を塗る治療法)が有効な場合もあります。
また、症状が悪化したときには、何がきっかけになったのか(季節の変わり目、忙しさ、特定の作業など)を振り返り、悪化要因を突き止めて対策を立てることも重要です。
- 綿の手袋をつけて寝るのは効果がありますか?
-
夜、就寝中に無意識にかきむしってしまうのを防ぐために、綿の手袋を着用することは非常に有効です。
また、就寝前に保湿剤や薬をたっぷり塗った後、手袋をすることで、薬が寝具についてしまうのを防ぎ、皮膚への浸透を高める効果もあります。
手袋は、通気性と吸湿性の良い綿100%のものを選び、毎日清潔なものに交換してください。きつすぎるものは血行を妨げる可能性があるので、少しゆとりのあるサイズが良いでしょう。
以上
参考文献
Katoh N, Ohya Y, Ikeda M, Ebihara T, Katayama I, Saeki H, Shimojo N, Tanaka A, Nakahara T, Nagao M, Hide M. Japanese guidelines for atopic dermatitis 2020. Allergology International. 2020;69(3):356-69.
Saeki H. Management of atopic dermatitis in Japan. Journal of Nippon Medical School. 2017 Jan 15;84(1):2-11.
Minamoto K, Watanabe T, Diepgen TL. Self‐reported hand eczema among dental workers in Japan–a cross‐sectional study. Contact Dermatitis. 2016 Oct;75(4):230-9.
Muto T, Hsieh SD, Sakurai Y, Yoshinaga H, Suto H, Okumura K, Ogawa H. Prevalence of atopic dermatitis in Japanese adults. British Journal of Dermatology. 2003 Jan 1;148(1):117-21.
Saeki H, Furue M, Furukawa F, Hide M, Ohtsuki M, Katayama I, Sasaki R, Suto H, Takehara K, Committee for Guidelines for the Management of Atopic Dermatitis of Japanese Dermatological Association. Guidelines for management of atopic dermatitis. The Journal of dermatology. 2009 Oct;36(10):563-77.
Takeuchi S, Esaki H, Furue M. Epidemiology of atopic dermatitis in Japan. The Journal of dermatology. 2014 Mar;41(3):200-4.
Ruff SM, Engebretsen KA, Zachariae C, Johansen JD, Silverberg JI, Egeberg A, Thyssen JP. The association between atopic dermatitis and hand eczema: a systematic review and meta‐analysis. British Journal of Dermatology. 2018 Apr 1;178(4):879-88.
Mortz CG, Lauritsen JM, Bindslev‐Jensen C, Andersen KE. Prevalence of atopic dermatitis, asthma, allergic rhinitis, and hand and contact dermatitis in adolescents. The Odense Adolescence Cohort Study on Atopic Diseases and Dermatitis. British Journal of Dermatology. 2001 Mar 1;144(3):523-32.
Coenraads PJ, Diepgen TL. Risk for hand eczema in employees with past or present atopic dermatitis. International archives of occupational and environmental health. 1998 Feb;71(1):7-13.
Rystedt I. Hand eczema and long-term prognosis in atopic dermatitis. Acta dermato-venereologica. Supplementum. 1985 Jan 1;117:1-59.