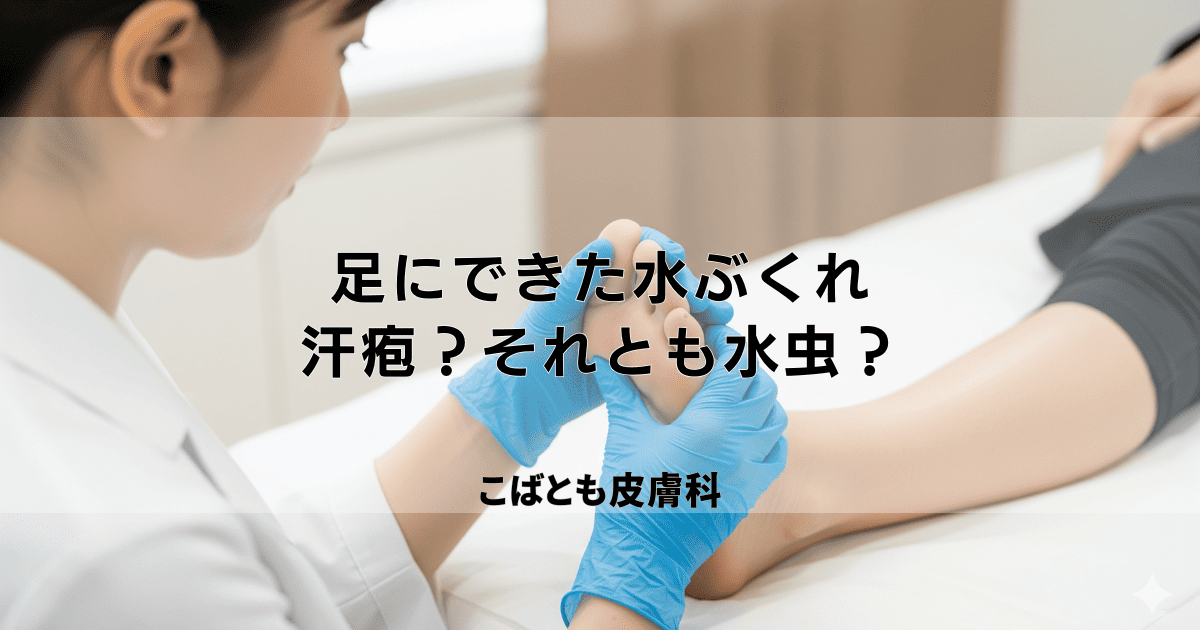足の裏や指に突然現れる小さな水ぶくれ。強いかゆみを伴うことも多く、汗疱なのか、それとも水虫なのかと不安に思う方は少なくありません。見た目が似ているため自己判断は非常に難しく、誤ったケアは症状を悪化させる原因にもなります。
この二つの皮膚疾患は、水ぶくれという症状は共通していても、原因も治療法も全く異なります。
この記事では、皮膚科専門医の視点から、汗疱と水虫のそれぞれの特徴、症状から見分けるためのポイント、対処法までを詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
足にできる水ぶくれの正体とは?
足に水ぶくれができると、多くの方がまず水虫を疑うかもしれませんが、原因は一つとは限りません。まずは水ぶくれがどのような状態なのか、なぜできるのかを皮膚の構造から説明します。
そもそも水ぶくれとは何か
水ぶくれは、医学用語で水疱(すいほう)と呼ばれ、皮膚の最も外側にある表皮、またはその下の真皮との間に、体液の一種である血清や血漿などの透明な液体(漿液性滲出液)が溜まった状態です。
皮膚が、外部からの物理的な刺激や、体内で起こる炎症反応によってダメージを受けると、体を守るための防御反応として液体が溜まり、クッションのように組織を守るために水ぶくれを形成します。
大きさは様々で、直径数ミリの小さなものから、数センチに及ぶ大きなものまであり、液体は、単なる水ではなく、傷ついた皮膚を潤った状態に保ち、外部の細菌などから保護し、皮膚の再生を助ける重要な役割を担っています。
日常で起こりやすい水ぶくれの原因
何らかの病気が原因でなくても、日常生活の中には水ぶくれを起こす要因がいくつもあります。特に足は、一日中体重を支え、靴による圧迫や摩擦、長時間の歩行など、日常的に大きな負担がかかる部位です。
新しい靴や慣れない靴を履いた時に起こる靴擦れは、最も身近な例でしょう。これは、皮膚の同じ場所が繰り返しこすれることで摩擦熱が生じ、表皮が下の組織から剥がれて隙間ができ、そこに液体が溜まることで発生します。
また、熱いお湯や油、調理器具などに触れてしまう熱傷(やけど)も、水ぶくれの一般的な原因です。やけどの深さがII度に達すると、真皮が傷つき、強い炎症反応によって水ぶくれができます。
物理的刺激による主な水ぶくれの原因
- 靴擦れ(摩擦)
- 長時間の歩行や運動
- 熱傷(やけど)
- 凍傷
- 虫刺され
注意が必要な水ぶくれのサイン
ほとんどの物理的刺激による水ぶくれは、原因がはっきりしており、皮膚を保護していれば時間の経過とともに自然に液体が吸収され、治癒します。
しかし、中には単なる物理刺激では説明がつかない、皮膚疾患のサインとして現れる水ぶくれもあります。
思い当たる原因がないのに水ぶくれが繰り返しできる、耐え難いほどの強いかゆみや痛みを伴う、水ぶくれの周りが赤く腫れて熱を持つ、水ぶくれが破れてじゅくじゅくした状態が続くなどの場合は、単なる靴擦れなどではない可能性が高いです。
発熱や倦怠感など、全身の症状を伴う場合も注意が必要で、症状に気づいたら、自己判断で放置したり市販薬で済ませたりせず、皮膚科専門医に相談してください。
汗疱(かんぽう)の症状と特徴を徹底解説
足の水ぶくれの原因として、水虫と非常によく混同されるのが汗疱です。名前から汗が直接的な原因と思われがちですが、実態はまだ完全には解明されていません。
汗疱とはどんな皮膚疾患か
汗疱は、手のひらや足の裏に、強いかゆみを伴う小さな水ぶくれ(小水疱)が突然多数現れる皮膚疾患です。異汗性湿疹(いかんせいしっしん)という別名もあります。
かつては汗の出口が詰まることで発症すると考えられていましたが、現在では汗の管とは直接的な関係はないことがわかっています。
ただし、汗をかきやすい人に多く見られることや、夏場に悪化することから、汗が症状を悪化させる一因である可能性は指摘されています。明確な原因は不明ですが、いくつかの要因が関与していると考えられています。
代表的なものは、ニッケル、コバルト、クロムといった金属に対するアレルギー反応です。アクセサリーだけでなく、歯科金属や食品にも含まれているため、体の中からアレルギー反応を起こすことがあります。
その他、アトピー性皮膚炎などのアレルギー体質(アトピー素因)、精神的なストレス、喫煙習慣などが複雑に関わり合って発症すると考えられています。
汗疱の発生に関与すると考えられる要因
| 要因の種類 | 具体的な内容 | 関連性 |
|---|---|---|
| アレルギー | 金属(ニッケル、クロム等)、薬剤 | 特定の物質への体の過敏反応として発症 |
| 内的要因 | アトピー素因、ストレス、多汗症 | 個人の体質や精神状態が影響する可能性 |
| 外的要因 | 喫煙、洗剤などの化学物質 | 生活習慣や日常的に接触する物質が誘因 |
汗疱ができやすい場所と時期
汗疱は、主に手のひら、指の側面、足の裏、足指の側面など、特定の場所に好発します。
これらの部位には、角層が厚く、エクリン汗腺という汗の腺が密集しているという共通点があり、指の付け根や側面、土踏まずのあたりに集中して現れることが多いです。
季節的には、気温と湿度が上昇し、汗をかきやすくなる春から夏にかけて症状が現れたり、悪化したりする傾向が強く見られます。逆に、空気が乾燥する秋から冬にかけては自然と症状が落ち着くことが多いのも、大きな特徴の一つです。
汗疱の主な症状とかゆみの特徴
汗疱の最も特徴的な症状は、1~2mm程度の小さな水ぶくれが、皮膚のやや深い部分に多発することです。水ぶくれは透明で、互いにくっつき合って融合し、大きな水ぶくれになることもあります。
症状の出始めに、むずむずとした何とも言えない強いかゆみや、人によってはチクチク、ピリピリとした痛みを感じることが多いです。
かゆみは非常に強く、夜も眠れなくなるほどになることもあります。通常、水ぶくれは数週間で新たなものはできなくなり、自然に乾燥して吸収され、その後、水ぶくれがあった部分の皮膚が剥がれて(落屑)、カサカサした状態になります。
水ぶくれの出現から落屑までの一連のサイクルを数週間から数ヶ月の間に繰り返すことが多く、慢性化するケースも少なくありません。
汗疱が悪化する要因
汗疱の症状は、特定の要因によって悪化することがあります。精神的なストレスや身体的な疲労が溜まると、自律神経やホルモンバランスが乱れ、体の免疫機能に影響を与えて症状が出やすくなることがあります。
また、水仕事や、洗剤、シャンプー、アルコール消毒液などの化学物質に頻繁に触れることも、皮膚のバリア機能を低下させ、外部からの刺激に敏感になり症状を悪化させる一因です。
金属アレルギーがある方は、身につけるアクセサリーだけでなく、チョコレートやナッツ、豆類など特定の金属を多く含む食品を摂取することで、全身的なアレルギー反応として汗疱の症状が誘発されることも報告されています。
水虫(足白癬)の症状と見分け方
足のかゆみや水ぶくれと聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべるのが水虫でしょう。水虫は感染症であり、汗疱のような体質的な湿疹とは根本的に異なります。
水虫の正体は白癬菌(はくせんきん)
水虫の正式名称は足白癬(あしはくせん)といい、白癬菌というカビ(真菌)の一種が、足の皮膚の最も外側にある角質層に寄生することで発症する感染症です。
白癬菌は皮膚糸状菌とも呼ばれ、皮膚の角質層を構成するケラチンというタンパク質を栄養源として生きていて、高温多湿な環境を非常に好み、増殖します。
靴や靴下で長時間覆われ、汗で蒸れやすい人間の足は、白癬菌にとってまさに絶好の繁殖場所となるのです。
白癬菌は、感染している人の足から剥がれ落ちた皮膚(鱗屑)などに潜んでおり、それを他の人が素足で踏むなどして皮膚に付着することで感染します。
ただし、菌が付着してすぐに感染するわけではなく、洗い流されずに長時間とどまり、角質層の内部に入り込むことで感染が成立します。
白癬菌の主な感染経路
- 家族が使用するスリッパやバスマット
- 温泉やスポーツジムなどの脱衣所
- 感染者との皮膚の直接的な接触
- 自身の爪水虫からの再感染
水虫の代表的な3つのタイプ
水虫は、症状の現れ方によって主に3つのタイプに分類され、人によっては複数のタイプを合併することもあります。
足白癬の臨床病型
| タイプ名 | 主な症状 | 好発部位 |
|---|---|---|
| 趾間型(しかんがた) | 指の間が白くふやける、皮がむける、じゅくじゅくする、かゆみ | 特に薬指と小指の間 |
| 小水疱型(しょうすいほうがた) | 小さな水ぶくれ、強いかゆみ、赤み、水ぶくれが破れて皮がむける | 土踏まずや足の側面、指の付け根 |
| 角質増殖型(かくしつぞうしょくがた) | 足裏全体、特にかかとが硬く厚くなる、乾燥、ひび割れ、粉を吹く | かかとを中心に足の裏全体 |
最も多く見られるのが趾間型で、構造的に指同士が密着して蒸れやすい薬指と小指の間に好発し、夏場に悪化します。
小水疱型は、土踏まずや足の側面に赤い小さな水ぶくれが多発し、汗疱と見た目が非常に似ているため、専門家による検査なしでの鑑別は困難です。
角質増殖型は、かゆみがほとんどないか、あっても軽度なため、水虫と気づかずに単なる乾燥や加齢による角化だと思い込んでいるケースが非常に多く、治療が遅ることもあります。
このタイプは感染力が強く、家族への感染源になりやすいので注意が必要です。
水虫特有の症状とは?
水虫の症状はタイプによって様々ですが、いくつかの共通する特徴もあります。水虫は多くの場合、片足から発症し、時間をかけてもう片方の足へ、あるいは手の皮膚(手白癬)へと広がっていきます。
また、足の指の間や爪に症状が出やすいのも大きな特徴で、足の爪が白や黄色に濁って厚く変形したり、もろくなってボロボロと崩れたりしている場合は、爪水虫(爪白癬)を併発している可能性が極めて高いです。
爪の中に白癬菌が侵入すると、爪が菌の貯蔵庫のようになってしまい、この状態を放置すると、いくら足の皮膚の水虫を塗り薬で治療しても、爪から菌が供給され続けて再発を繰り返す、という悪循環に陥ります。
他の疾患との見分けが難しい理由
水虫、特に小水疱型の症状は非常に多彩で、汗疱だけでなく、接触皮膚炎(かぶれ)、掌蹠膿疱症、細菌感染症など、他の様々な皮膚疾患と症状が似ています。
水ぶくれ、皮むけ、かゆみといった症状は多くの皮膚疾患に共通して見られるため、見た目だけで正確に診断することは専門医でも困難な場合があります。
よくあるのが、水虫ではない湿疹に市販の水虫薬を塗り続けてしまい、薬の刺激で接触皮膚炎を起こして症状を悪化させてしまうケースです。
その逆もまた然りで、水虫をただの湿疹だと思ってステロイド薬を塗ると、一時的にかゆみは治まりますが、白癬菌の増殖を助けてしまい、かえって症状を悪化させることになります。
汗疱と水虫、症状から見分ける5つのポイント
原因も治療法も全く異なる汗疱と水虫。ここでは、両者を見分けるための参考となる具体的なポイントを5つに絞って解説します。
汗疱と水虫の比較まとめ
| 比較ポイント | 汗疱(異汗性湿疹) | 水虫(足白癬) |
|---|---|---|
| 水ぶくれの見た目 | 小さく透明な水疱が皮膚の深い部分に多発。赤みは少ない。 | 赤みを伴うことが多く、比較的破れやすい。水疱の周りの皮がむける。 |
| 発生部位 | 足の裏、指の側面。左右対称に出やすい傾向。指の間には少ない。 | 指の間、土踏まず。片足から始まることが多く、左右非対称。 |
| 感染性 | なし(他人にうつらない) | あり(他人にうつる) |
ポイント1 水ぶくれの見た目と分布
汗疱の水ぶくれは、直径1~2mm程度の小さくて透明なものが多く、角層の厚い足の裏の、やや深いところにできるため、プツプツとした硬いドーム状の見た目が特徴です。
赤みはあまり伴いません。一方、水虫(小水疱型)の水ぶくれは、もう少し大きく、炎症を伴って周囲が赤くなることが多く、比較的皮膚の浅いところにできるため破れやすい傾向があります。
また、汗疱はアレルギー反応など内的な要因で起こるため、両足の同じような場所に、左右対称に症状が出ることが多いのに対し、水虫は外部からの感染で起こるため、片足の指の間や土踏まずから始まり、徐々に広がる非対称性の特徴が見られます。
ポイント2 かゆみの質とタイミング
かゆみはどちらの疾患でも見られますが、質やタイミングに違いが出ることがあります。汗疱のかゆみは、水ぶくれが出現する時期にピークを迎え、むずむず、チクチクするような非常に強いかゆみとして感じられることが多いです。
水ぶくれが乾燥してくると、かゆみも次第に落ち着いてきます。一方、水虫のかゆみは、じゅくじゅくした趾間型で特に強く、持続的なかゆみであることが多いです。
ただし、角質増殖型のようにかゆみがほとんどない水虫もあり、かゆみの感じ方には個人差が大きいため、これだけで判断するのは難しいでしょう。
ポイント3 発生しやすい季節
汗疱は、汗をかく量と症状の悪化に明らかな関連が見られることが多く、汗ばむ春から夏にかけて発症・悪化し、空気が乾燥する冬には自然と軽快する、というはっきりとした季節性を示すのが大きな特徴です。
水虫も、白癬菌が高温多湿を好むため、夏に症状が悪化する傾向はありますが、冬に完全に症状がなくなることは少なく、一年を通してくすぶり続けることが一般的です。
冬場にかかとがガサガサしているのは、乾燥ではなく角質増殖型の水虫かもしれません。
ポイント4 感染性の有無
汗疱はアレルギーや体質などが関与する内因性の湿疹であり、感染症ではないので、どれだけ症状がひどくても、他の人にうつることは絶対になく、温泉やプールに入ることも問題ありません。
水虫は白癬菌というカビによる明らかな感染症なので、家族内や共同生活の場などで、人と人との間で感染する可能性があります。もし、同居しているご家族にも足の皮むけやかゆみなどの症状がある場合は、水虫の可能性がより高まります。
ポイント5 指の間や爪の状態
症状が出ている部位をよく観察することも診断の大きなヒントになり、汗疱は足の裏や指の側面にはできますが、指の間にできることは比較的少ないです。
もし、足の指の間、特に最も蒸れやすい薬指と小指の間が白くふやけたり、皮がむけてじゅくじゅくしたりしている場合は、水虫(趾間型)の可能性が非常に高いと考えられます。
また、足の爪が白や黄色に濁る、厚くなる、もろくなって崩れるといった変化が見られる場合は、爪水虫のサインです。爪に菌がいるということは、皮膚にも菌がいる可能性が極めて高く、皮膚の症状も水虫である可能性を強く裏付けます。
爪水虫のセルフチェック
- 爪が白や黄色に濁っている
- 爪が厚くなって切りにくい
- 爪の表面に筋が入ったり、もろくなったりしている
- 爪が変形している
汗疱と水虫以外の足の水ぶくれの原因疾患
足に水ぶくれができる原因は、汗疱や水虫だけではありません。ここでは、鑑別が必要となる他の代表的な皮膚疾患をいくつか紹介します。
接触皮膚炎(かぶれ)
接触皮膚炎は、特定の物質が皮膚に触れることでアレルギー反応や刺激反応が起こり、赤み、かゆみ、水ぶくれなどを起こす疾患で、原因物質が触れた部分に境界がはっきりとした湿疹ができるのが特徴です。
足の場合は、靴の素材(皮革のなめし剤、ゴムに含まれる化学物質、接着剤、金属の飾りなど)、靴下に使われる染料、あるいは自分で塗った外用薬の成分などが原因となることがあり、水虫薬にかぶれて悪化するケースも少なくありません。
掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)
手のひらや足の裏に、かゆみを伴う小さな膿(うみ)がたまった水ぶくれ(膿疱)が、多数くり返し出現する難治性の皮膚疾患です。水ぶくれの中に黄色い膿が見えるのが特徴ですが、この膿は無菌性で、他人に感染することはありません。
症状が良くなったり悪くなったりを繰り返し、慢性的に経過します。喫煙や、のどの扁桃腺炎、虫歯などの病巣感染、歯科金属アレルギーなどが発症や悪化に関与していると考えられています。
足の水ぶくれを伴う主な皮膚疾患
| 疾患名 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 接触皮膚炎 | 赤み、かゆみ、水ぶくれ | 原因物質に触れた部位に限定して発症。境界が明瞭。 |
| 掌蹠膿疱症 | 膿を持った小さな水ぶくれ(膿疱)、赤み、皮むけ | 良くなったり悪くなったりを繰り返す。喫煙との関連が強い。 |
| 細菌感染症 | 強い痛み、赤み、腫れ、熱感、膿 | 傷口などから細菌が侵入して急激に発症。 |
細菌感染症
水ぶくれが破れたり、皮膚に傷があったりすると、そこから細菌(主に黄色ブドウ球菌やレンサ球菌)が侵入し、二次的な感染症を引き起こすことがあります。
これを伝染性膿痂疹(とびひ)や、さらに深い組織まで炎症が及んだものを蜂窩織炎(ほうかしきえん)と呼び、水ぶくれの周りが赤く大きく腫れあがり、熱っぽさやズキズキとした強い痛みを伴います。
急速に症状が広がり、発熱など全身症状を伴うこともあるため、抗菌薬による早期の治療が必要です。
足の水ぶくれ、自分でできる対処法と注意点
足に水ぶくれができたとき、すぐに病院に行けない場合もあるでしょう。症状を悪化させないために、自宅でできる応急処置や日常の注意点について解説します。
水ぶくれは潰すべき?潰さないべき?
基本的に、水ぶくれは自分で潰さないのが原則です。水ぶくれの中の液体には、傷ついた皮膚を保護し、治癒を促す成分が含まれていて、また、水ぶくれを覆っている皮は、外部の細菌から傷口を守る天然の絆創膏の役割を果たしています。
無理に潰してしまうと、治りが遅くなるだけでなく、そこから細菌が侵入して二次感染を起こすリスクが格段に高まります。
靴擦れなどで水ぶくれが大きく、パンパンに張って痛みが強く、歩くのに支障が出るような場合に限り、清潔な針で小さな穴を開けて液体をそっと抜き、皮は剥がさずに上から保護材を貼る方法もあります。
しかし、感染のリスクを考えると、できるだけ皮膚科で清潔な器具を用いて処置してもらうのが最も安全です。
自宅でできる応急処置
かゆみが強い場合は、患部を掻きむしらないことが最も大切です。掻くことで皮膚のバリア機能がさらに壊れて症状が悪化するだけでなく、掻き傷から細菌が侵入して二次感染を引き起こすことがあります。
冷たい水で濡らしたタオルや、タオルで包んだ保冷剤などを当てることで、炎症が鎮まり、一時的にかゆみを和らげることができます。
水ぶくれが自然に破れてしまった場合は、水道水で優しく洗い流して清潔にし、患部を保護するために絆創膏やガーゼを当てておきましょう。
かゆみを悪化させないための工夫
- 患部を冷やす(温めるとかゆみが増す)
- 爪を短く切り、やすりで滑らかにしておく
- 就寝時に掻いてしまう場合は綿の手袋を着用する
- 刺激の少ない石鹸をよく泡立て、優しく洗う
市販薬を使う前に知っておきたいこと
ドラッグストアには、水虫薬やかゆみ止めの塗り薬など、様々な市販薬が並んでおり、手軽に入手できますが、自己判断で薬を選ぶことには大きなリスクが伴います。
汗疱と水虫は見た目が似ていても原因が全く違うため、使用する薬も異なります。もし汗疱や湿疹に、水虫薬(抗真菌薬)を使ってしまうと、薬の成分による刺激でかぶれ(接触皮膚炎)を起こし、症状がさらに悪化することが頻繁にあります。
水虫に湿疹用のステロイド外用薬だけを使うと、一時的に炎症が抑えられてかゆみは収まりますが、原因である白癬菌を殺す力はないため、菌を増殖させてしまい、かえって水虫を広範囲に悪化させることになります。
市販薬を1~2週間使用しても症状が全く改善しない、あるいは悪化するようであれば、その薬は症状に合っていない可能性が高いです。すぐに使用を中止して速やかに皮膚科を受診してください。
市販薬使用時の注意点
| 薬の種類 | 対象疾患 | 誤用した場合のリスク |
|---|---|---|
| 抗真菌薬(水虫薬) | 水虫(足白癬) | 汗疱や湿疹に使用すると、刺激でかぶれて悪化することがある。 |
| ステロイド外用薬 | 汗疱、湿疹、かぶれ | 水虫に使用すると、白癬菌が増殖し症状を悪化・長期化させる。 |
| かゆみ止め(抗ヒスタミン薬) | 湿疹などに伴うかゆみ | 根本的な治療にはならず、原因疾患は治らない。 |
悪化させないための生活習慣
症状の悪化を防ぎ、再発を予防するためには、日々の生活習慣を見直すことも非常に大切です。特に足は蒸れやすいため、常に清潔と乾燥を保つことを意識しましょう。
革靴やブーツなど通気性の悪い靴を長時間履くことは避け、できれば複数の靴をローテーションして、靴を十分に乾燥させる時間を作ってください。
靴下は、吸湿性・速乾性に優れた綿やシルク、機能性素材のものを選び、汗をかいたらこまめに履き替えるのが理想で、帰宅後はすぐに足を洗い、特に指の間は水分が残りやすいので、タオルで優しく、しかし確実に拭き取ることが重要です。
汗疱の場合は、ストレスや疲労を溜めないように、十分な睡眠とバランスの取れた食事を心がけることも、症状の安定につながります。
皮膚科での診断と治療法
正確な診断と、それに基づいた適切な治療を受けることが、足の悩みを解消するための最も確実で安全な方法です。
正確な診断のために行う検査
汗疱と水虫の鑑別のために、皮膚科で最も一般的に行われるのが顕微鏡検査(直接鏡検)です。
症状が出ている部分の皮膚(水ぶくれの皮や、カサカサしている部分の角質)を、ピンセットやハサミでごく少量、痛みを感じない範囲で採取し、水酸化カリウム(KOH)溶液で溶かして顕微鏡で観察します。
検査で、白癬菌の菌糸や胞子が見つかれば水虫と確定診断されます。痛みは全くなく、数分で結果が分かる非常に有用な検査です。もしこの検査で白癬菌が見つからなければ、汗疱やその他の皮膚疾患の可能性を考えていきます。
必要に応じて、アレルギーの原因を調べるパッチテストや血液検査を行うこともあります。
皮膚科で行う主な検査
| 検査名 | 検査内容 | 何がわかるか |
|---|---|---|
| 顕微鏡検査(直接鏡検) | 患部の皮膚や爪を採取し顕微鏡で観察 | 白癬菌の有無(水虫の確定診断) |
| パッチテスト | 原因と思われる物質を背中などに貼り反応を見る | アレルギー性接触皮膚炎の原因特定 |
| 血液検査 | 採血によりアレルギー反応などを調べる | 金属アレルギーの有無など |
汗疱の主な治療法
汗疱の治療は、主に皮膚の炎症やかゆみを抑えるための対症療法が中心となり、炎症を抑えるために最も効果的なのがステロイド外用薬です。
足の裏は皮膚が厚いため、比較的強めのステロイド薬が必要となることが多いですが、症状の強さに応じて適切な強さの薬を処方します。医師の指示通りに使用すれば、副作用の心配はほとんどありません。
かゆみが非常に強い場合には、かゆみを抑える抗ヒスタミン薬や抗アレルギー薬の内服薬を併用することもあります。水ぶくれが破れてじゅくじゅくしている場合は、亜鉛華軟膏などで患部を保護し、皮膚の乾燥を促します。
また、金属アレルギーが疑われる場合には、原因金属を避ける食事指導や生活指導を行います。
水虫の主な治療法
水虫の治療の基本は、原因である白癬菌を殺す、あるいは増殖を抑える作用のある抗真菌薬を使用することです。基本的には塗り薬(外用薬)で治療します。
クリーム、軟膏、液体、スプレーなど様々な剤形があり、患部の状態(乾燥しているか、じゅくじゅくしているかなど)に合わせて使い分けます。
外用薬を塗る際の重要なポイントは、症状が出ている部分だけでなく、かゆみや皮むけがない部分も含めて、足の裏全体と指の間に広く塗ることです。
爪水虫を合併している場合や、角質増殖型で薬が浸透しにくい場合、症状が広範囲に及ぶ場合には、飲み薬(内服薬)による治療が必要となることもあります。
治療期間と再発予防の重要性
汗疱は体質的な要因も大きいため、一度症状が治まっても、ストレスや季節の変化などをきっかけに再発を繰り返すことがあります。
根治が難しい場合もありますが、日頃から皮膚の保湿やストレス管理、悪化要因を避ける生活を心がけることで、症状をコントロールし、良い状態を保つことは可能です。
一方、水虫の治療で最も重要なのは、症状がなくなったからといって自己判断で薬をやめないことです。かゆみや水ぶくれが消えて見た目がきれいになっても、角質層の中には白癬菌がまだしぶとく生き残っています。
ここで治療をやめてしまうと、生き残った菌が再び増殖し、すぐに再発してしまいます。皮膚科医の指示に従い、皮膚がきれいになってからもしばらく(最低1ヶ月以上)、根気強く治療を続けることが、完治のために絶対に必要です。
よくある質問
最後に、足の水ぶくれに関して患者さんからよく寄せられる質問と答えをまとめました。
- 汗疱と水虫は併発しますか?
-
もともと汗疱の症状がある足に、皮膚のバリア機能が低下したところへ白癬菌が感染して水虫を発症するケースや、その逆のケースも考えられ、両者が併発すると、診断や治療がより複雑になります。
水虫の治療で抗真菌薬を塗っている部分が、汗疱や薬のかぶれによって悪化することもあります。
症状が混在している場合は特に、自己判断はせずに専門医に相談し、それぞれの疾患に対して適切な治療を同時に行うことが大事です。
- 子供の足にも水ぶくれができますか?
-
汗疱は、お子さんにも比較的よく見られる疾患で、新陳代謝が活発で汗をかきやすいため、特に夏場に症状が出やすい傾向があります。
一方、お子さんの水虫は、以前は少ないとされていましたが、生活様式の変化(ペットとの接触、スイミングスクールなど)により、近年では珍しくなくなりました。
家族に水虫の人がいる場合は、家庭内での感染のリスクが高まります。
- 病院に行くタイミングはいつですか?
-
足に原因不明の水ぶくれができて、数日経っても改善しない場合は、一度皮膚科を受診することをお勧めします。特に、強い症状がある場合や、市販薬を試しても一向に改善しない場合は、できるだけ早く受診してください。
早期に正しい診断を受け、適切な治療を開始することが、症状の悪化を防ぎ、つらい症状から早く解放されるための最も重要なポイントです。
以上
参考文献
Gonçalo M, Santiago L. Dermatological Injuries. InThe Sports Medicine Physician 2019 Apr 13 (pp. 447-458). Cham: Springer International Publishing.
Maruyama R, Hiruma M, Yamauchi K, Teraguchi S, Yamaguchi H. An epidemiological and clinical study of untreated patients with tinea pedis within a company in Japan. Mycoses. 2003 Jun;46(5‐6):208-12.
de Berker D. Tinea pedis and onychomycosis. Onychomycosis: Diagnosis and Effective Management. 2018 Jun 22:21-30.
Tsunemi Y, Naka W. Exploratory study on short‐term administration of oral fosravuconazole for tinea pedis. The Journal of Dermatology. 2025 Jan;52(1):79-86.
Nowicka D, Nawrot U. Tinea pedis—An embarrassing problem for health and beauty—A narrative review. Mycoses. 2021 Oct;64(10):1140-50.
Watanabe S, Harada T, Hiruma M, Iozumi K, Katoh T, Mochizuki T, Naka W, Japan Foot Week Group. Epidemiological survey of foot diseases in Japan: Results of 30 000 foot checks by dermatologists. The Journal of Dermatology. 2010 May;37(5):397-406.
Ochiai T, Morishima T, Hao T, Takayama A. Bullous amyloidosis: the mechanism of blister formation revealed by electron microscopy. Journal of cutaneous pathology. 2001 Sep;28(8):407-11.
Hsu CY, Wang YC, Kao CH. Dyshidrosis is a risk factor for herpes zoster. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2015 Nov;29(11):2177-83.
Lofgren SM, Warshaw EM. Dyshidrosis: epidemiology, clinical characteristics, and therapy. DERM. 2006 Dec 1;17(4):165-81.
Chang YY, Van der Velden J, Van der Wier G, Kramer D, Diercks GF, van Geel M, Coenraads PJ, Zeeuwen PL, Jonkman MF. Keratolysis exfoliativa (dyshidrosis lamellosa sicca): a distinct peeling entity. British Journal of Dermatology. 2012 Nov 1;167(5):1076-84.