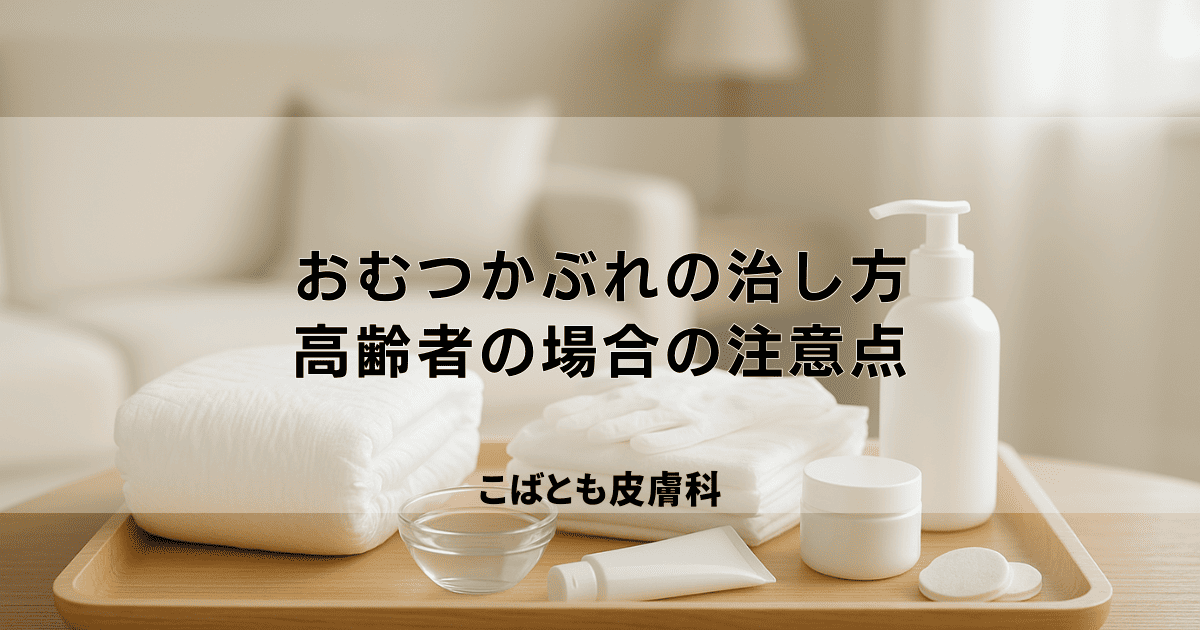おむつかぶれは、赤ちゃんだけでなく介護を必要とする高齢者にも起こりうる、つらい皮膚トラブルです。はじめは軽い赤みでも、放置すると悪化し、強い痛みやただれを起こすことがあります。
特に、皮膚がデリケートな高齢者の場合、重症化しやすいため注意が必要です。
この記事では、おむつかぶれの基本的な知識から、症状を悪化させないための正しいケア方法、部位別の対策、高齢者特有の注意点まで、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
おむつかぶれとは?
おむつかぶれ、医学的にはおむつ皮膚炎と呼ばれるこの症状は、多くの人が経験する身近な皮膚トラブルですが、原因や症状の現れ方は一つではありません。
蒸れと摩擦が主な原因
おむつの中は、尿や汗によって常に湿度が高い状態にあり、高い湿度は、皮膚の最も外側にある角層をふやけさせ、外部からの刺激に対するバリア機能を低下させます。バリア機能が弱まった皮膚は、非常に傷つきやすくなります。
そこにおむつが擦れる物理的な摩擦が加わることで、炎症が起きます。寝返りをうつ高齢者の場合、足の付け根やお尻のふくらんだ部分など、摩擦が起きやすい場所にかぶれが発生しやすいです。
尿や便そのものも、皮膚にとって大きな刺激となります。尿に含まれるアンモニアは、長時間皮膚に触れることでアルカリ性に傾き、皮膚を刺激して炎症を起こしやすいです。
また、便、特に下痢便には、消化酵素が多く含まれ、皮膚のタンパク質を分解し、強い炎症を起こすことがあります。おむつ交換が遅れると、これらの刺激物質が皮膚に接触する時間が長くなり、おむつかぶれのリスクは格段に高まります。
おむつかぶれの主な原因物質
| 原因物質 | 含まれる場所 | 皮膚への影響 |
|---|---|---|
| アンモニア | 尿 | 皮膚をアルカリ性に傾け、刺激を与える |
| 消化酵素 | 便(特に下痢便) | 皮膚のタンパク質を分解し、強い炎症を引き起こす |
| 水分 | 尿・汗 | 皮膚をふやかし、バリア機能を低下させる |
カンジダ菌による感染症との違い
おむつかぶれとよく似た症状に、カンジダ皮膚炎があり、カンジダという真菌(カビの一種)が増殖して起こる感染症です。通常のおむつかぶれと異なり、カンジダ皮膚炎には抗真菌薬による治療が必要になります。
見分けるポイントは、症状の現れ方です。
通常のおむつかぶれは、おむつが直接当たるお尻のふくらんだ部分に赤みが広がることが多いのに対し、カンジダ皮膚炎は、皮膚のしわの奥まで赤くなり、小さな膿疱や、赤いブツブツが広範囲に散らばるように現れる特徴があります。
自己判断で市販薬を使い続けると、かえって症状を悪化させることもあるため、見分けが難しい場合は早めに皮膚科を受診することが大切です。
初期症状から見られる皮膚の変化
おむつかぶれの初期症状は、おむつが当たっている部分の皮膚がほんのり赤くなることから始まり、この段階では、かゆみや痛みはほとんど感じないかもしれませんが、ケアを怠ると症状は進行します。
赤みが強くなり、ポツポツとした赤い発疹が現れ、次第に皮膚が少し盛り上がってくることもあり、この段階になると、軽いヒリヒリ感やかゆみを感じるようになります。早期に気づき、適切なケアを開始することが、重症化を防ぐ鍵です。
おむつかぶれのサインと見分け方
単なる赤みだと軽く考えていると、おむつかぶれは予想以上に悪化することがあります。重症化すると、治療に時間がかかり、本人にとっても介護者にとっても大きな負担です。
皮膚の状態を注意深く観察し、悪化の兆候を見逃さないようにしましょう。
赤みやブツブツだけではない重症化のサイン
おむつかぶれが重症化すると、皮膚の赤みはより一層強くなり、鮮やかな紅色になります。皮膚全体が腫れぼったくなり、熱を持つこともあります。
また、赤いブツブツ(丘疹)だけでなく、液体を含んだ小さな水ぶくれ(小水疱)や、膿を持ったブツブツ(膿疱)が見られるようになり、症状は、炎症が皮膚の深い部分にまで及んでいるサインです。
この状態になると、強いかゆみや痛みを伴うことが多く、不快感を訴えることがあります。
おむつかぶれの進行度と症状
| 進行度 | 主な症状 | 本人の感覚 |
|---|---|---|
| 軽症 | 部分的な赤み、軽い発疹 | ほとんど無症状か、軽い違和感 |
| 中等症 | 強い赤み、腫れ、赤いブツブツ | かゆみ、ヒリヒリ感 |
| 重症 | 鮮やかな赤み、びらん、潰瘍、膿疱 | 強い痛み、灼熱感 |
皮膚がむけるびらんや潰瘍の状態
さらに症状が進行すると、皮膚の表面がむけて、ジクジクとした液体(滲出液)が出てくる状態、いわゆるびらんになります。びらんがさらに深くなると、皮膚がえぐれたような潰瘍を形成することもあります。
ここまで進行すると、皮膚のバリア機能は完全に失われ、細菌感染を起こすリスクが非常に高いです。強い痛みを伴うため、おむつ交換やお風呂の際に、激しく泣いたり痛がったりするようになります。
重症のおむつかぶれは、家庭でのケアだけで治すことは困難であり、速やかに皮膚科での専門的な治療が必要です。
痛みを伴う場合の注意点
おむつかぶれで痛みを伴う場合、炎症が強い証拠です。特に排尿や排便時、おしりを拭くときにしみるような痛みを感じ、痛みから、おむつ交換を嫌がるようになることも少なくありません。
痛みが強い場合は、無理にこすって拭き取ることは避け、ぬるま湯で優しく洗い流すなどの工夫が必要です。また、痛みのために十分な睡眠がとれなくなるなど、生活の質にも影響を及ぼすことがあります。
痛みを我慢させず、早めに医療機関に相談しましょう。
重症化しやすい人の特徴
誰もがおむつかぶれになる可能性がありますが、特に重症化しやすい人がいます。もともとアトピー性皮膚炎などで皮膚のバリア機能が低下している人は、わずかな刺激でも炎症を起こしやすく、重症化しやすい傾向があります。
また、下痢が続いている場合も、刺激の強い便が頻繁に皮膚に接触するため、リスクが高まります。高齢者の場合は、皮膚の乾燥や菲薄化(皮膚が薄くなること)、免疫力の低下などが重症化の要因です。
おむつかぶれの基本的な治し方と自宅でのセルフケア
おむつかぶれの治療と予防の基本は、皮膚を清潔に保ち、刺激から守ることです。軽症であれば、日々のセルフケアを見直すだけで改善することも少なくありません。
清潔と乾燥を保つおむつ交換の基本
おむつかぶれのケアで最も重要なのは、おむつの中を清潔で乾いた状態に保つことです。尿や便をしたら、できるだけ早くおむつを交換しましょう。特に便をした後は、すぐに交換することが大切です。
おむつ交換の際には、しばらくお尻を空気に触れさせて乾燥させる時間を作ると効果的で、おむつを外した状態で5分から10分程度、タオルなどの上で過ごさせるだけでも、皮膚の湿度は大きく改善します。
おむつは通気性の良い製品を選び、サイズが合っているかどうかも確認しましょう。きつすぎると摩擦の原因になり、緩すぎると漏れにつながります。
おむつ交換時のチェックリスト
- すぐに交換する
- お尻を乾燥させる時間を作る
- 通気性の良いおむつを選ぶ
- 正しいサイズのおむつを使用する
正しい洗い方と拭き方のコツ
お尻を清潔にする際の洗い方と拭き方にもコツがあります。便をしたときは、おしりふきでゴシゴシこするのではなく、ぬるま湯で優しく洗い流すのが最も理想的です。シャワーボトルや霧吹きなどを使うと、手軽に洗い流せます。
洗い流した後は、乾いた柔らかい布やタオルで、押さえるようにして水分を拭き取ります。このときも、こすらないように注意しましょう。
外出先など、洗い流すのが難しい場合は、水分を多く含んだ厚手のおしりふきを使い、優しく汚れを拭き取ってください。アルコールや香料が含まれていない、肌に優しい製品を選ぶことがポイントです。
市販薬の選び方と注意点
軽度のおむつかぶれであれば、市販の薬で対応することも可能です。薬を選ぶ際は、炎症を抑える成分だけでなく、皮膚を保護する成分が含まれているものを選ぶとよいでしょう。
酸化亜鉛を含む軟膏は、皮膚の表面に保護膜を作り、尿や便などの刺激から皮膚を守る働きがあります。ただし、ステロイドを含む薬の使用には注意が必要です。
ステロイドは炎症を抑える効果が高い一方で、カンジダ皮膚炎などの感染症を悪化させる可能性があります。症状が改善しない、または悪化する場合は、自己判断で薬を使い続けず、皮膚科を受診してください。
市販薬の主な成分と働き
| 成分の種類 | 主な働き | 使用上の注意点 |
|---|---|---|
| 酸化亜鉛 | 皮膚の保護、弱い消炎作用 | 比較的安全に使えるが、症状が強い場合は効果が限定的 |
| 非ステロイド性抗炎症薬 | 炎症を和らげる | ステロイドより作用は穏やか |
| ステロイド外用薬 | 強い抗炎症作用 | 感染症を悪化させるリスクあり。長期使用は避ける |
皮膚のバリア機能を高める保湿ケア
皮膚の乾燥はバリア機能の低下に直結し、おむつかぶれを悪化させる要因になるので、尻を清潔にした後は、保湿剤で皮膚の潤いを保つことが大切です。ワセリンや低刺激性の保湿クリームなどを、お尻全体に優しく塗り広げましょう。
保湿剤を塗ることで、皮膚の水分が逃げるのを防ぐだけでなく、尿や便などの刺激物が直接皮膚に触れるのを防ぐ物理的なバリアとしても機能します。おむつ交換のたびに、毎回保湿ケアを行うことを習慣にしましょう。
足の付け根など特定部位のおむつかぶれ対策
おむつかぶれは、お尻全体に均一にできるわけではありません。体の構造や動きによって、特にトラブルが起きやすい部位があり、代表的なのが、足の付け根やお尻、性器周辺です。
部位の特性を理解しそれに合わせたケアを行うことで、より効果的に症状を改善、予防することができます。
動きが多く蒸れやすい足の付け根のケア
足の付け根は、歩いたり足を動かしたりすることで常に皮膚がこすれ合い、摩擦が起きやすい部位です。また、しわが深いため汗や汚れが溜まりやすく、湿度が高くなりがちで、おむつかぶれが非常に発生しやすい場所になります。
足の付け根のケアでは、特に清潔を保つことが重要です。おむつ交換の際には、しわを丁寧に広げて、ぬるま湯で優しく洗い流し、汚れが残らないようにしましょう。
水分を拭き取った後は、この部分にもしっかりと保湿剤や保護クリームを塗り、摩擦による刺激を軽減させることが大切で、おむつのギャザーが食い込みすぎないよう、おむつの当て方やサイズを見直すことも有効です。
足の付け根ケアのポイント
- しわを広げて丁寧に洗う
- 水分をしっかり拭き取る
- 保湿剤・保護クリームを塗る
- おむつのサイズや当て方を見直す
お尻全体に広がるかぶれの対処法
お尻の、特に体重がかかる部分に広がるかぶれは、圧迫と蒸れが大きな原因です。長時間同じ姿勢でいる寝たきりの高齢者によく見られ、対処法としては、こまめな体位変換が有効です。
定期的に体の向きを変えることで、同じ場所に圧力がかかり続けるのを防ぎ、血行を促進し、また、通気性の高いおむつや尿とりパッドを使用したり、エアマットを導入したりすることも、お尻の蒸れを軽減するのに役立ちます。
性器周辺のデリケートな部分の注意点
性器周辺は皮膚が非常に薄くデリケートなため、特に優しいケアが求められます。尿や便が直接触れやすく、炎症を起こしやすい部位でもあります。
清潔にする際は、前から後ろに向かって優しく拭き、雑菌が尿道に入るのを防ぎましょう。女性の場合は、この拭き方が重要です。男性の場合は、包皮の先に汚れが溜まりやすいので、注意して洗う必要があります。
薬を塗る際は、粘膜に付着しないように気をつけ、薄く塗り広げるようにしましょう。強い赤みや腫れ、排尿時の痛みなどが見られる場合は、他の病気の可能性も考えられるため、早めに医師に相談してください。
デリケートゾーンのケア方法
| 性別 | 洗浄・清拭のポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 女性 | 前から後ろへ一方向に拭く | 膣内に雑菌が入らないようにする |
| 男性 | 包皮の先の汚れを優しく洗う | 無理に包皮をむかない |
高齢者特有のおむつかぶれ 原因と予防・ケアのポイント
高齢者のおむつかぶれは、赤ちゃんのケースとは異なる、特有の難しさがあります。加齢に伴う皮膚の変化や、さまざまな健康上の問題が複雑に絡み合い、一度発症すると治りにくく、重症化しやすい傾向にあります。
高齢者の皮膚の特徴とリスク
加齢とともに、皮膚は大きく変化し、皮脂や汗の分泌が減少し、皮膚は乾燥しやすくなります。
また、皮膚のハリを保つコラーゲンやエラスチンが減少し、皮膚が薄く(菲薄化)、弱くなるため、わずかな摩擦や刺激でも傷つきやすいです。
さらに、皮膚の細胞が新しく生まれ変わるターンオーバーの周期も長くなるため、一度できた傷や炎症が治りにくくなります。このような加齢による変化が、高齢者のおむつかぶれを重症化させる大きなリスク要因です。
加齢による皮膚の変化
| 変化する項目 | 具体的な変化 | おむつかぶれへの影響 |
|---|---|---|
| 皮脂・汗の分泌 | 減少する | 乾燥し、バリア機能が低下する |
| 皮膚の厚み | 薄くなる(菲薄化) | 刺激に弱く、傷つきやすくなる |
| ターンオーバー | 遅くなる | 傷や炎症が治りにくくなる |
基礎疾患や服用薬が与える影響
高齢者は、糖尿病や心疾患、腎疾患といった基礎疾患を抱えていることが少なくありません。疾患は、血行不良や免疫力の低下を引き起こし、皮膚トラブルのリスクを高め、例えば、糖尿病では末梢の血流が悪化し、皮膚の治癒力が低下します。
また、治療のために服用している薬の副作用として、皮膚が乾燥したり、免疫力が抑制されたりすることもあります。
利尿薬を服用している場合は尿の回数や量が増え、おむつ内が蒸れやすくなるなど、治療内容がおむつかぶれに影響を与えることも考慮に入れることが必要です。
高齢者向けのおむつの選び方
高齢者のおむつ選びは、吸収力だけでなく、通気性や肌触りも重視することが大切です。長時間使用することが多いため、湿気を外に逃がす機能が高い製品を選ぶと、蒸れを軽減できます。
また、肌に直接触れる素材が柔らかく、刺激の少ないものを選びましょう。体型に合っているかどうかも重要なポイントです。サイズが合わないと、漏れや摩擦の原因になります。
本人の活動量や尿量、皮膚の状態に合わせて、パンツタイプやテープタイプ、尿とりパッドなどを適切に組み合わせることが、快適さを保ち、皮膚トラブルを防ぐことにつながります。
高齢者のおむつ選びのポイント
- 通気性の良さ
- 肌触りの柔らかさ
- 体型に合ったサイズ
- 吸収量と活動量に合わせた組み合わせ
介護者が知っておくべきケアの重要性
高齢者のおむつケアは、単なる排泄物の処理ではありません。本人の尊厳を守り、快適な生活を支えるための重要なケアの一つです。おむつ交換の際には、プライバシーに配慮し、丁寧な声かけを心がけましょう。
皮膚の状態を毎回観察し、赤みや傷などの小さな変化を見逃さないことが、重症化を防ぐために大事です。もし本人が不快感を訴えたり、痛みを訴えたりした場合は、原因を考え、ケアの方法を見直す必要があります。
介護者だけで抱え込まず、必要であれば訪問看護師や医師など、専門家の助言を求めることも大切です。
皮膚科を受診するタイミング
自宅でのケアを続けていても、なかなか症状が良くならない、あるいは悪化してしまうこともあります。そのようなときは、専門家である医師の診察を受けることが最善の解決策です。
セルフケアで改善しないときは迷わず受診を
市販薬を使ったり、おむつ交換の頻度を増やしたりと、セルフケアを1週間程度続けても症状が改善しない、または赤みが広がったり、ジクジクしてきたりした場合は、医療機関を受診するタイミングです。
特に、以下のような症状が見られる場合は、早めに受診を検討してください。
受診をおすすめする症状
- 皮膚がむけている(びらん)
- 水ぶくれや膿疱がある
- 出血している
- 強い痛みを伴う
- 発熱がある
このような症状は、重症化しているか、細菌や真菌による二次感染を起こしている可能性があります。放置するとさらに悪化する恐れがあるため、自己判断を続けずに専門医に相談しましょう。
皮膚科で行う専門的な診断と治療
おむつかぶれの診療は、主に皮膚科が専門で、まず視診で皮膚の状態を詳しく観察します。通常のおむつかぶれか、カンジダ皮膚炎などの感染症が疑われるかなどを判断します。
必要に応じて、皮膚の表面をこすって検体を採取し、顕微鏡で真菌の有無を調べる検査(直接鏡検)を行うこともあります。何科にかかればよいか迷った場合は、まず皮膚科を受診してください。
皮膚科での主な検査と診断
| 検査・診断方法 | 目的 | 内容 |
|---|---|---|
| 視診 | 皮膚の状態を評価する | 発疹の性状、範囲、分布などを詳しく観察する |
| 直接鏡検(KOH法) | 真菌(カビ)の有無を確認する | 皮膚の角層を採取し、顕微鏡でカンジダ菌などを探す |
医師に伝えるべき症状のポイント
診察を受ける際には、医師に正確な情報を伝えることが、適切な診断につながります。以下の点を整理しておくと、スムーズに診察が進みます。
- いつから症状が始まったか
- どのような症状があるか(赤み、ブツブツ、ジクジクなど)
- 症状は良くなっているか、悪化しているか
- 痛みやかゆみの有無
- これまでに行ったケア(使用した市販薬など)
- 下痢の有無や、全身の健康状態
特に、使用した市販薬の名前がわかるように、パッケージやお薬手帳を持参するとよいでしょう。
治療薬の種類と正しい使い方
皮膚科で処方される薬は、症状や原因によって異なります。通常のおむつかぶれで炎症が強い場合は、ステロイド外用薬が処方され、カンジダ皮膚炎と診断された場合は、抗真菌薬の塗り薬が処方されます。
細菌感染を併発している場合は、抗生物質の塗り薬や飲み薬が必要になることもあります。薬は、医師の指示通りに、正しい回数と量を守って使用することが重要です。
症状が良くなったからといって自己判断で中断すると、再発することがあるので、必ず指示された期間、治療を続けてください。
処方される主な治療薬
| 薬の種類 | 主な目的 | 代表的な薬 |
|---|---|---|
| ステロイド外用薬 | 炎症を抑える | 症状の強さに応じてランクを使い分ける |
| 抗真菌外用薬 | カンジダ菌を殺菌する | カンジダ皮膚炎の場合に用いる |
| 亜鉛華軟膏 | 皮膚を保護する | 炎症が軽度の場合や、保護目的に用いる |
おむつかぶれに関するよくある質問(FAQ)
ここでは、おむつかぶれのケアに関して、患者さんやご家族からよく寄せられる質問にお答えします。日々のケアの参考にしてください。
- 赤ちゃん用の薬を大人が使っても大丈夫?
-
赤ちゃん用に販売されているおむつかぶれの市販薬は、作用が穏やかなものがほとんどです。
高齢者が使用しても大きな問題が起こることは少ないですが、高齢者の皮膚は赤ちゃんとは異なり、乾燥が進んでいたり、薄くなっていたりします。
また、症状の原因が単純なかぶれではない可能性も考慮しなくてはなりません。市販薬で改善が見られない場合は、やはり皮膚科を受診し、高齢者の皮膚の状態に合った薬を処方してもらうのが最も安全で確実です。
- おむつかぶれはどのくらいで治りますか?
-
軽症であれば、こまめなおむつ交換や洗浄などのセルフケアを徹底することで、2〜3日から1週間程度で改善することが多いです。
しかし、皮膚がむけたりジクジクしたりしている重症の場合は、皮膚科で適切な治療を受けても、完全にきれいな状態に戻るまでには数週間以上かかることもあります。大切なのは、焦らずに根気よくケアを続けることです。
- 予防のためにベビーパウダーは有効ですか?
-
かつては、ベビーパウダー(天花粉)がおむつかぶれの予防によく使われていました。パウダーが皮膚の湿気を吸い取り、サラサラに保つ効果を期待してのことですが、最近では積極的には推奨されていません。
パウダーが汗や尿を吸って固まり、それがかえって皮膚への刺激になったり、毛穴を塞いでしまったりする可能性があるためです。また、カンジダ菌は湿った環境を好むため、パウダーが菌の温床になることも指摘されています。
予防の基本は、洗浄と乾燥、そして保湿による保護です。
- 食事はおむつかぶれに関係しますか?
-
直接的な原因ではありませんが、食事の内容が便の性状に影響を与え、間接的におむつかぶれに関係することがあります。
香辛料の多い食事や、酸味の強い果物などを多く摂取すると、便が刺激性になり、おむつかぶれを悪化させることがあります。
また、食物アレルギーによって下痢が引き起こされ、それが原因でおむつかぶれがひどくなるケースもあります。
下痢が続くときや、特定の食べ物を食べた後に症状が悪化するような場合は、食事内容を見直してみるのも一つの方法です。
以上
参考文献
Boiko S. Treatment of diaper dermatitis. Dermatologic clinics. 1999 Jan 1;17(1):235-40.
Sharifi-Heris Z, Amiri Farahani L, Hasanpoor-Azghadi SB. A review study of diaper rash dermatitis treatments. Journal of Client-Centered Nursing Care. 2018 Feb 10;4(1):1-2.
Takahashi H, Oyama N, Tanaka I, Hasegawa M, Hirano K, Shimada C, Hasegawa M. Preventive effects of topical washing with miconazole nitrate‐containing soap to diaper candidiasis in hospitalized elderly patients: A prospective, double‐blind, placebo‐controlled study. The Journal of Dermatology. 2017 Jul;44(7):760-6.
Kitagaki H. Skin Health of the Elderly and People in Long-term Care. Current Cosmetic Science. 2023 Jan;2(1):E200323214765.
Takahashi H, Oyama N, Amamoto M, Torii T, Matsuo T, Hasegawa M. Prospective trial for the clinical efficacy of anogenital skin care with miconazole nitrate‐containing soap for diaper candidiasis. The Journal of Dermatology. 2020 Apr;47(4):385-9.
Isogai R, Yamada H. Factors involved in the development of diaper‐area granuloma of the aged. The Journal of Dermatology. 2013 Dec;40(12):1038-41.
Foureur N, Vanzo B, Meaume S, Senet P. Prospective aetiological study of diaper dermatitis in the elderly. British Journal of Dermatology. 2006 Nov 1;155(5):941-6.
Dall’Oglio F, Musumeci ML, Puglisi DF, Micali G. A novel treatment of diaper dermatitis in children and adults. Journal of Cosmetic Dermatology. 2021 Apr;20:1-4.
Bitencourt GR, Alves LD, Santana RF. Practice of use of diapers in hospitalized adults and elderly: cross-sectional study. Revista brasileira de enfermagem. 2018;71(2):343-9.
Marsman DS, Rai P, Felter SP. Dermal safety evaluation: use of disposable diaper products in the elderly. InTextbook of aging skin 2017 (pp. 1457-1471). Springer, Berlin, Heidelberg.