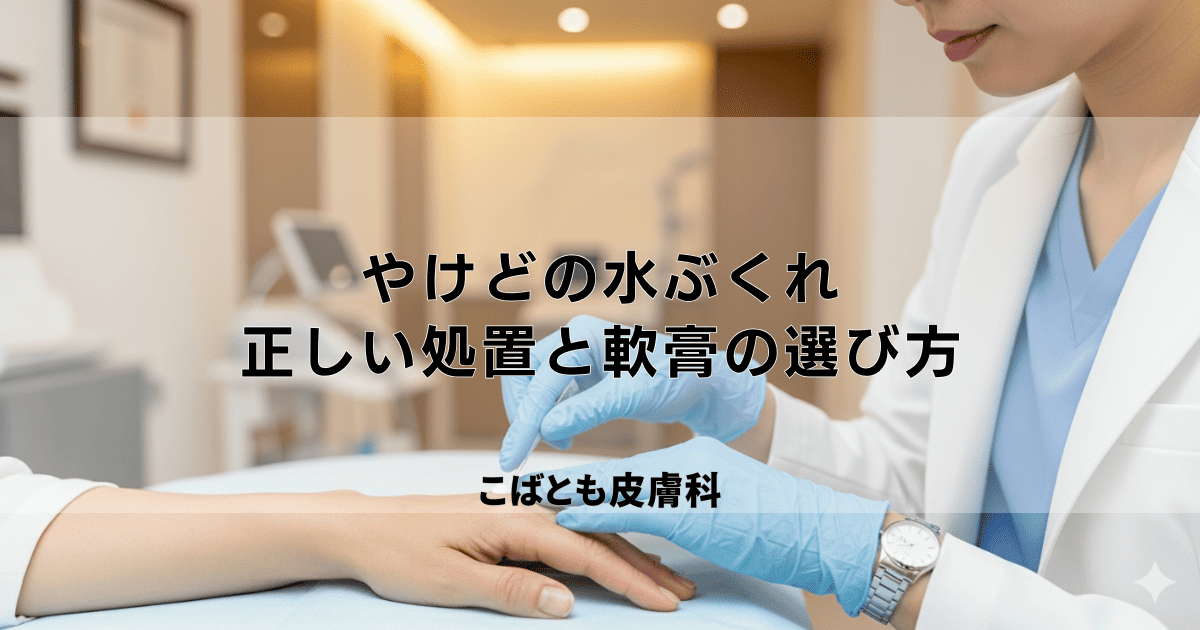やけどをして水ぶくれができてしまい、うっかり破れてしまったら、どうすればいいか不安になりますよね。ジンジンとした痛みに加え、傷口が化膿しないか、跡が残らないかと心配になる方も多いでしょう。
水ぶくれが破れた後の処置は、感染を防ぎ、きれいに治すために非常に重要です。自己判断で間違った手当てをすると、かえって治りを遅らせたり、深刻なトラブルにつながることもあります。
この記事では、ご家庭でできる正しい応急処置の方法、感染させないためのポイント、市販の軟膏を選ぶ際の注意点まで、解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
まずは落ち着いて確認 やけどの深さと水ぶくれの状態
やけどで水ぶくれが破れてしまうと、慌ててしまいがちですが、まずは落ち着いて傷の状態を観察することが、適切な処置への第一歩です。
やけどの重症度を判断する3つのレベル
やけどは、皮膚の損傷がどの深さまで達しているかによって、重症度が分類され、一般的に、Ⅰ度からⅢ度の3段階に分けられ、それぞれ症状と必要な対処が異なります。
Ⅰ度は最も軽いやけどで、皮膚の表面(表皮)のみが損傷している状態です。日焼けのように皮膚が赤くなり、ヒリヒリとした痛みを伴いますが、水ぶくれはできず、通常、数日で跡を残さずに治ります。
Ⅱ度は、表皮とその下の真皮まで損傷が及んでいる状態で、強い痛みと赤み、そして水ぶくれ(水疱)ができるのが特徴です。Ⅱ度はさらに、浅いもの(浅達性Ⅱ度熱傷)と深いもの(深達性Ⅱ度熱傷)に分けられます。
Ⅲ度は最も重いやけどで、皮膚の全層、場合によっては皮下組織まで損傷が及んでいます。皮膚は白や黒っぽく変色し、神経も破壊されるため痛みを感じないこともあります。このレベルのやけどは、必ず医療機関での専門的な治療が必要です。
やけどの重症度レベル
| 重症度 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| Ⅰ度熱傷 | 皮膚の赤み、ヒリヒリした痛み | 水ぶくれはできない。通常、跡は残らない。 |
| Ⅱ度熱傷 | 強い痛み、赤み、水ぶくれ | 跡が残る可能性がある。感染に注意が必要。 |
| Ⅲ度熱傷 | 皮膚が白または黒くなる、痛みを感じない | 皮膚移植が必要になることが多い。必ず受診が必要。 |
水ぶくれができるのはどのレベルのやけどか
やけどの症状として特徴的な水ぶくれは、Ⅱ度熱傷で見られ、熱によって損傷した血管から、血漿(けっしょう)と呼ばれる液体成分が漏れ出し、表皮と真皮の間にたまることで形成されます。
水ぶくれの中の液体には、皮膚の再生を助ける成分が含まれており、また外部の細菌や刺激から傷口を守るクッションのような役割も果たしているため、水ぶくれはむやみに破らない方が良いとされています。
水ぶくれの大きさが非常に大きい場合や、関節など動きの多い場所にできて破れそうな場合は、医療機関で適切に処置してもらうのが安全です。
もし水ぶくれが自然に破れてしまった場合は、感染を起こさないよう、正しい処置を行うことが大切になります。
破れた水ぶくれの皮はどうするべきか
水ぶくれが破れてしまった後、めくれた皮膚(びらん)をどう扱うかは多くの人が悩む点ですが、基本的には、無理に剥がさないことが原則です。
残った皮は、たとえ破れていても、その下にある新しい皮膚が再生するまでの間、天然の絆創膏のように傷口を保護する役割を持っています。
無理に剥がしてしまうと、再生中のデリケートな皮膚を傷つけ、強い痛みを起こしたり、感染のリスクを高めたりする可能性があり、また、治癒が遅れたり、傷跡が残りやすくなったりする原因にもなります。
もし、皮が土や砂などで明らかに汚れてしまっている場合は、そのままの状態で医療機関を受診してください。
すぐに病院へ行くべき危険なサイン
ほとんどの軽いやけどは家庭での処置が可能ですが、中には専門的な治療を緊急に必要とするケースもあります。
自己判断で様子を見ているうちに状態が悪化し、重篤な結果につながることを防ぐため、危険なサインを知っておくことは非常に重要です。
以下の表に示すような症状が見られる場合は、応急処置をしながらも、速やかに皮膚科や救急外来を受診してください。
医療機関の受診を強く推奨するケース
| サイン | 具体的な状況 | 考えられるリスク |
|---|---|---|
| 広範囲のやけど | 手のひら以上の大きさのⅡ度熱傷、またはそれより小さいⅢ度熱傷 | 体液の喪失、感染、ショック状態 |
| 特定の部位のやけど | 顔、首、関節部、陰部など | 機能障害や引きつれ(拘縮)が残りやすい |
| 感染の兆候 | 傷の周りの強い赤み、腫れ、熱感、膿、悪臭 | 全身への感染拡大(敗血症)の可能性 |
| 特殊な原因によるやけど | 化学薬品、感電、深い低温やけど | 見た目以上に内部の損傷が深いことがある |
感染リスクを最小限に 家庭でできる応急処置
水ぶくれが破れた傷口は、皮膚のバリア機能が失われ、細菌が侵入しやすい無防備な状態です。ここでの初期対応が、後の治り具合を大きく左右します。
処置の前に 必ず手を清潔にする
やけどの処置を始める前に、最も重要で基本的なことは、処置をする人の手を清潔にすることです。手には、目には見えないたくさんの細菌が付着していて、汚れた手で傷口に触れると、そこから細菌が侵入し、感染を起こす原因となります。
感染を起こすと、治癒が遅れるだけでなく、傷跡がひどくなる可能性も高まります。処置の前には、必ず石鹸と流水で指の間や爪の先まで丁寧に手を洗いましょう。もし可能であれば、使い捨ての清潔な手袋を着用すると、さらに安全です。
これは、自分自身の傷を手当てする場合も、他の人の手当てをする場合も同様です。
傷口を優しく洗浄する方法
手がきれいになったら、次に傷口を洗浄します。洗浄の目的は、傷口についた汚れや細菌、古い軟膏などを洗い流し、清潔な状態にすることです。このとき、決してゴシゴシと強くこすらないでください。
再生しようとしているデリケートな皮膚組織を傷つけてしまいます。洗浄には、刺激の少ない石鹸をよく泡立てて使い、泡を傷口に乗せ、優しく撫でるように汚れを浮き上がらせるのがポイントです。
その後、十分な量の流水(水道水で構いません)を使い、泡が完全になくなるまで丁寧にすすぎ、洗い終わったら、清潔なタオルやガーゼをそっと押し当てるようにして、水分を優しく拭き取ります。
応急処置の基本的な流れ
- 手洗い
- 傷口の洗浄
- 水分除去
- 軟膏塗布
- ドレッシング材での保護
消毒液は本当に必要か
やけどの傷には消毒液、と考える方は多いかもしれませんが、日常的なやけどの処置に消毒液は必ずしも推奨されていません。
多くの消毒液(ポビドンヨードや消毒用エタノールなど)は、細菌を殺すだけでなく、皮膚の再生に必要な細胞まで傷つけてしまう可能性があるからです。
人間の体には、本来、傷を自分で治そうとする力(自然治癒力)が備わっていて、消毒液によって正常な細胞がダメージを受けると、治癒の妨げになることがあります。
基本的には、前述した石鹸と流水による十分な洗浄で、感染予防としては十分と考えられています。ただし、傷が土やサビなどでひどく汚れている場合や、医師の指示があった場合は例外です。
水道水での洗浄は問題ないのか
傷口を洗う際に、水道水を使っても大丈夫かと心配される方がいますが、日本の水道水は非常に清潔に管理されているため、やけどの洗浄に使用しても全く問題ありません。
生理食塩水などをわざわざ準備するよりも、すぐに利用できる流水でためらわずに、十分な量の水で洗い流すことの方が重要です。
やけどをしたら、まずは衣類の上からでも構わないので、すぐに流水で15分から20分程度、痛みが和らぐまで冷やし続けることが応急処置の基本です。
冷却によって、やけどが深くなるのを防ぎ、痛みを軽減する効果があります。水ぶくれが破れた後の洗浄においても、清潔な水道水が最も手軽で効果的な洗浄液です。
傷口を保護する軟膏の役割と選び方
洗浄後の傷口をそのままにしておくと、乾燥してしまい、痛みが増したり治りが遅くなったりする原因になります。適切な軟膏を使って傷口の潤いを保ち、外部の刺激から保護することがきれいに治すための鍵です。
なぜ軟膏を塗る必要があるのか
やけどの傷をきれいに、早く治すためには、傷口を適度に潤った状態(湿潤環境)に保つことが大切です。
かつては傷を乾かすのが良いとされていましたが、現在では、湿潤環境の方が皮膚の細胞が活発に働き、再生が促されることがわかっています。
軟膏には、主に2つの重要な役割があります。一つは、傷口の乾燥を防ぎ、湿潤環境を維持することで、痛みが和らぎ、かさぶたができにくくなるため、跡が残りにくくなります。
もう一つの役割は、外部からの細菌の侵入や物理的な刺激を防ぐバリア機能です。軟膏の油分が膜を作り、傷口を保護し、また、ガーゼなどのドレッシング材が傷口に直接貼り付いてしまうのを防ぐ効果もあります。
市販薬に含まれる成分に注目する
ドラッグストアには多くの種類のやけど治療薬が並んでいますが、製品を選ぶ際には、パッケージの宣伝文句だけでなく、どのような有効成分が含まれているかを確認することが重要なります。
炎症を抑える成分、細菌の増殖を抑える成分、皮膚の組織修復を助ける成分などがあり、自分のやけどの状態に合わせて、適切な成分が含まれた軟膏を選ぶことが、効果的な治療への近道です。
市販軟膏に含まれる主な有効成分
| 成分の種類 | 代表的な成分名 | 期待される役割 |
|---|---|---|
| 殺菌・消毒成分 | クロルヘキシジン、ベンザルコニウム塩化物 | 細菌の増殖を抑え、感染を防ぐ。 |
| 抗炎症成分 | プレドニゾロン(ステロイド)、グリチルリチン酸 | やけどによる赤みや腫れなどの炎症を鎮める。 |
| 組織修復促進成分 | アラントイン、ビタミンA | 皮膚の細胞の再生を助け、治癒を促す。 |
| 局所麻酔成分 | リドカイン、ジブカイン | やけどによる痛みを一時的に和らげる。 |
抗生物質入り軟膏を選ぶべきケース
市販薬の中には、抗生物質(化膿止め)を含む軟膏もありますが、すべてのやけどに抗生物質が必要なわけではありません。抗生物質は細菌を殺す強力な薬であり、予防的に使いすぎると、薬が効かない耐性菌を生み出す原因にもなり得ます。
明らかに感染を起こしている、あるいは感染のリスクが非常に高いと考えられる場合に、使用が推奨されます。
抗生物質入り軟膏の使用を検討する状況
| 状況 | 具体的な例 |
|---|---|
| 明らかに感染の兆候がある | 傷口から膿が出ている、悪臭がする、周囲の腫れや痛みが強くなっている。 |
| 傷が汚れている | 土やホコリ、動物の唾液などが付着した可能性がある。 |
| 免疫力が低下している | 糖尿病などの持病がある、高齢者、ステロイド薬を内服中など。 |
ワセリンだけでも代用は可能か
ワセリンは、石油から精製された保湿剤で、皮膚の表面に油分の膜を作ることで水分の蒸発を防ぎ、外部の刺激から皮膚を保護する効果があります。
ワセリン自体には、殺菌成分や組織修復を促進する成分は含まれていませんが、優れた保護・保湿効果により、軽度のやけどであれば、清潔にした傷口にワセリンを塗って保護するだけでも十分な場合があります。
特に、他に適切な軟膏が手元にない場合の応急処置としては非常に有効です。傷口を洗浄した後、ワセリンを塗り、ガーゼで保護することで、湿潤環境を保ち、治癒を助けることができます。
ただし、ワセリンはあくまで保護が目的で、感染の兆候がある場合や、治りが悪い場合には、医療機関での診察が必要です。
軟膏の正しい塗り方とドレッシング材(被覆材)の使い方
効果的な軟膏を選んでも、塗り方やその後の保護方法が間違っていると、十分な効果を発揮できません。薬を塗る量や頻度、そして傷口を覆うドレッシング材の選び方と使い方には、いくつかのポイントがあります。
軟膏を塗る適切な量と頻度
軟膏を塗る際のポイントは、少し多いかなと感じるくらいたっぷりと塗ることです。量が少ないと、すぐに乾燥してしまったり、ガーゼに吸収されてしまったりして、十分な効果が得られません。
目安としては、ティッシュペーパーが軽く貼り付くくらいの量が適量です。塗る際は、清潔な綿棒を使うか、手をよく洗ってから指で優しく乗せるように塗り、傷口に擦り込む必要はありません。
塗る頻度は、1日に1〜2回が目安で、入浴後など、傷口を洗浄した後に塗り直すのが最も効果的です。傷の状態によっては、医師から特別な指示がある場合もありますので、その際は指示に従ってください。
軟膏を塗る前の準備
- 石鹸での丁寧な手洗い
- 清潔な綿棒の用意
- ドレッシング材(ガーゼなど)の準備
傷口を保護するドレッシング材とは
ドレッシング材とは、軟膏を塗った傷口を覆い、保護するための医療材料の総称です。一般的にはガーゼや絆創膏などがこれにあたります。
ドレッシング材の主な目的は、傷口を外部の汚染や衝撃から守ること、滲出液(傷口から出る液体)を吸収すること、そして傷口の湿潤環境を維持することです。
最近では、様々な機能を持つ高機能なドレッシング材も開発されており、傷の状態に合わせて適切なものを選択することが、治癒を促進する上で重要になります。
ドレッシング材の種類と特徴
| 種類 | 特徴 | 適した用途 |
|---|---|---|
| ガーゼ | 安価で入手しやすい。滲出液の吸収性に優れる。 | 滲出液が多い初期の傷。軟膏と併用する。 |
| フィルム材 | 透明で薄いフィルム。防水性があり、傷の観察が容易。 | 滲出液が少ない傷の保護。シャワー時に便利。 |
| ハイドロコロイド材 | 滲出液を吸収してゲル化し、湿潤環境を維持する。 | 感染のない、滲出液が少ない〜中等量の傷。 |
ガーゼと絆創膏の使い分け
家庭で最も一般的に使われるドレッシング材は、ガーゼと絆創膏でしょう。この二つは、やけどの大きさや場所によって使い分けます。比較的小さな、指先などのやけどには、軟膏を塗った上から絆創膏で保護するのが手軽です。
最近では、パッド部分が大きいものや防水タイプのものなど、様々な種類があります。一方、手のひらや腕、足など、ある程度の広さがあるやけどには、ガーゼが適しています。傷の大きさに合わせてカットでき、滲出液もしっかり吸収します。
ガーゼを当てる際は、軟膏をたっぷり塗った後、傷より一回り大きくガーゼを当て、医療用テープや包帯で固定します。ガーゼ交換の際に傷にくっついて痛い場合は、無理に剥がさず、ぬるま湯で湿らせてからゆっくり剥がすと良いでしょう。
ハイドロコロイド材は使っても良いか
ハイドロコロイド材は、貼るだけで傷口を密閉し、湿潤環境を保つことができる非常に便利なドレッシング材で、キズパワーパッドなどの商品名で知られていますが、水ぶくれが破れたやけどへの使用には注意が必要です。
ハイドロコロイド材は、感染のないきれいな傷に使うことが前提で、水ぶくれが破れた直後の傷は、感染のリスクがゼロではありません。
もし細菌が残ったままハイドロコロイド材で密閉してしまうと、内部で細菌が増殖し、感染を悪化させる危険性があります。
自己判断での使用は慎重に行うべきで、傷の周りに赤みや腫れがある場合、膿が出ている場合、糖尿病などの持病がある方は絶対に使用しないでください。
やけどの治癒を妨げる やってはいけない行動
良かれと思ってやったことが、実はやけどの治りを遅らせ、傷跡を悪化させる原因になることがあります。昔ながらの民間療法や誤った思い込みは、時として危険な結果を招きます。
むやみに傷口を触る・こする
治りかけの傷はかゆみを伴うことが多く、気になってつい触ったり、掻いてしまったりしがちですが、絶対にやめてください。手についた細菌を傷口に運び、感染の原因になるだけでなく、再生しかけている新しい皮膚を傷つけてしまいます。
物理的な刺激が、治癒を遅らせ、色素沈着やケロイドといった目立つ傷跡につながることもあります。かゆみが我慢できない場合は、傷の周りを冷やしたり、医師に相談してかゆみ止めの薬を処方してもらったりするなどの対策をとりましょう。
アロエや味噌などの民間療法
昔から、やけどにはアロエ、味噌、醤油、油などを塗ると良いという民間療法が伝えられていますが、科学的根拠がなく、非常に危険な行為です。
このような食品や植物には、様々な細菌が含まれている可能性があり、傷口に塗ることで感染のリスクを著しく高めます。また、傷口への刺激となり、炎症を悪化させることもあります。
やけどの応急処置は、まず冷やすこと、清潔に保つことが基本です。根拠のない民間療法に頼るのは絶対にやめ、医学的に正しい処置を行ってください。
避けるべき主なNG行動
- 傷を不潔な手で触る
- 水ぶくれを故意に潰す
- アロエなどを塗る民間療法
- 傷を乾かそうとする
- 感染のサインを放置する
傷口を乾燥させようとする行為
傷は乾かした方が早く治る、という考えは過去のもので、現在では、傷を適度な潤いのある環境(湿潤環境)に保つ「湿潤療法」が主流です。
傷口を乾燥させると、かさぶたができ、かさぶたは傷を守っているように見えますが、その下では皮膚の再生が妨げられ、治癒が遅くなることがわかっています。
また、かさぶたが剥がれるときに、新しくできた皮膚も一緒に剥がしてしまい、傷跡が残りやすくなります。軟膏やドレッシング材を使って、傷が乾かないように保護することが、きれいに治すための重要なポイントです。
喫煙や過度な飲酒
喫煙や飲酒といった生活習慣も、やけどの治りに影響を与えます。タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させる作用があり、傷を治すために必要な酸素や栄養素を運ぶ血流が悪化し、皮膚の再生が遅れてしまいます。
また、過度な飲酒は、体の免疫機能を低下させ、感染症にかかりやすくなる可能性があります。やけどが治るまでは、できるだけ禁煙し、飲酒も控えてください。
治療中の生活で気をつけるべきこと
やけどの治療は、傷口の処置だけではなく、日常生活の中での少しの心がけが、回復を早め、合併症を防ぐことにつながります。食事や入浴、紫外線対策など、治療中に注意すべき点をいくつかご紹介します。
栄養バランスの取れた食事の重要性
皮膚が再生するためには、材料となる栄養素が必要です。特に、新しい皮膚の主成分であるタンパク質や、合成を助けるビタミンC、亜鉛などを意識的に摂取することが、治癒を促進します。
偏った食事ではなく、肉、魚、卵、大豆製品、緑黄色野菜、果物などをバランス良く取り入れた食事を心がけましょう。十分な栄養を摂ることは、体の内側から傷の治りをサポートし、免疫力を高めて感染を防ぐ上でも大切です。
皮膚の再生を助ける栄養素
| 栄養素 | 役割 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 皮膚や血管の主成分となる。 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |
| ビタミンC | コラーゲンの生成に必要。抗酸化作用。 | ピーマン、ブロッコリー、キウイ、柑橘類 |
| 亜鉛 | 細胞の分裂や再生を助ける。 | 牡蠣、レバー、牛肉、チーズ |
入浴時の注意点と傷の保護
やけどをしていても、体を清潔に保つためにシャワーや入浴は必要ですが、いくつか注意点があります。まず、お湯の温度はぬるめに設定し、長時間の入浴は避けましょう。
熱いお湯は血行を促進しすぎて、痛みやかゆみを増強させることがあります。傷口は、石鹸をよく泡立てて優しく洗います。シャワーの水圧が直接傷口に当たらないように注意してください。
入浴後は、清潔なタオルで優しく水分を拭き取り、すぐに軟膏を塗って新しいドレッシング材で保護します。防水性のフィルム材などを貼ってシャワーを浴びるのも一つの方法です。
入浴・シャワー時のポイント
- ぬるめのお湯にする
- 傷口を強くこすらない
- シャワー圧を直接当てない
- 入浴後はすぐに処置する
紫外線が傷跡に与える影響
やけどの跡が治りかけている、あるいは治ったばかりの皮膚は、非常にデリケートで紫外線に弱い状態です。この時期に紫外線を浴びると、メラニン色素が過剰に生成され、色素沈着、シミのような跡が残りやすくなります。
色素沈着は、一度できてしまうと消えるまでに長い時間がかかったり、完全には消えなかったりすることもあります。傷が治ってからも、少なくとも3ヶ月から半年程度は、その部位の紫外線対策を徹底することが重要です。
外出時には、衣類や帽子で覆ったり、日焼け止めを塗ったりして、皮膚を紫外線から守りましょう。
痛みが続く場合の対処法
やけどによる痛みは、受傷直後が最も強く、通常は時間の経過とともに和らいでいきますが、処置をしていても痛みが続く、あるいは一度和らいだ痛みが再び強くなるような場合は注意が必要です。
痛みの増強は、感染のサインである可能性があります。傷の周りが赤く腫れて熱を持っている、膿が出ているなどの症状が伴う場合は、すぐに医療機関を受診してください。
また、感染がなくても、神経が過敏になって痛みが続くこともあり、痛みが日常生活に支障をきたすほどつらい場合は、我慢せずに医師に相談し、鎮痛薬を処方してもらうことも検討しましょう。
皮膚科受診のタイミングと治療内容
家庭での応急処置はあくまで一時的なものです。特に水ぶくれが破れたやけどは、専門医による診断と治療が望ましい場合が多くあります。
この症状が出たら迷わず受診を
応急処置をしても、症状が改善しない、あるいは悪化しているように感じる場合は、専門家である皮膚科医の診察を受けるべきサインです。特に感染を疑う症状は、放置すると重症化する危険があるため、早期の対応が大事です。
皮膚科受診を強く推奨する症状
- 数日経っても痛みが改善しない、または悪化する
- 傷の周りの赤み、腫れ、熱感が広がっている
- 傷から黄色や緑色の膿が出ている、または悪臭がする
- 発熱や体のだるさなど、全身の症状が出てきた
- 自分で処置をしても、傷が全く治る気配がない
皮膚科で行う専門的な処置
皮膚科では、まずやけどの深さと範囲を正確に診断し、その上で、感染の有無を確認し、適切な処置を行います。家庭での処置と大きく異なるのは、専門的な器具や薬剤を使用できる点です。
感染や壊死(組織が死んでしまうこと)の原因となる不要な組織を、清潔な環境下で安全に除去することがあります。
また、滲出液の量や感染の状態に合わせて、様々な種類の軟膏や高機能なドレッシング材を使い分け、最適な湿潤環境を作り出します。痛みが強い場合には内服の鎮痛薬、感染が確認された場合には内服の抗生物質を処方することもあります。
傷跡を残さないための治療の選択肢
やけどの治療において、多くの人が心配するのが傷跡です。特に深達性Ⅱ度熱傷やⅢ度熱傷では、傷跡が残りやすくなります。皮膚科では、傷を治すだけでなく、できるだけ跡が目立たないようにするための治療も行います。
治癒の過程で皮膚が盛り上がって硬くなる肥厚性瘢痕(ひこうせいはんこん)やケロイドを予防・治療するために、ステロイドのテープ剤や注射、シリコンジェルシート、内服薬などを用いることがあります。
また、色素沈着に対しては、ハイドロキノンなどの美白外用薬やビタミンCなどの内服薬、レーザー治療などが選択肢となる場合もあります。
医療機関で処方される軟膏の種類
皮膚科で処方される軟膏は、市販薬よりも有効成分の濃度が高かったり、特定の目的に特化した薬剤であったりします。やけどの治療では、傷の状態に応じて様々な軟膏が使い分けられます。
処方される主な外用薬(軟膏)
| 薬剤の種類 | 主な薬剤名 | 主な目的 |
|---|---|---|
| ステロイド外用薬 | リンデロン-VG、ロコイド | 強い抗炎症作用で、初期の炎症を抑える。 |
| 抗菌薬外用薬 | ゲンタシン軟膏、アクアチム軟膏 | 細菌感染の治療・予防。 |
| 皮膚潰瘍治療薬 | プロスタンディン軟膏、フィブラストスプレー | 血流を改善し、肉芽形成や表皮再生を促進する。 |
| その他 | アズノール軟膏、亜鉛華軟膏 | 消炎作用、皮膚の保護。 |
よくある質問
最後に、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 破れた水ぶくれの皮は、いつ自然に剥がれますか
-
破れた水ぶくれの皮が自然に剥がれるまでの期間は、一般的には1週間から2週間程度が目安です。下の皮膚が十分に再生してくると、古くなった皮は乾燥して自然にポロポロと剥がれ落ちていきます。
この間、無理に剥がそうとすると、新しい皮膚を傷つけてしまうので、自然に剥がれるのを待つのが基本です。毎日の洗浄や軟膏を塗る処置を続けているうちに、徐々にきれいに取れていきます。
もし、いつまでも皮が残っていたり、その下がジクジクして治る気配がなかったりする場合は、何か問題がある可能性も考えられるため、皮膚科に相談してください。
- 処置をしているのに、かゆみが出てきました。どうすれば良いですか
-
傷が治る過程でかゆみが生じるのは、非常によくあることで、傷の修復のために様々な化学物質が放出されたり、新しい皮膚や神経が再生されたりする際に起こる、ある意味で「治ってきているサイン」とも言えます。
かゆいからといって掻いてしまうのは禁物です。掻くことで傷が悪化したり、感染を起こしたりする危険があります。かゆみがつらい場合は、まず冷たいタオルなどで傷の周りを優しく冷やしてみてください。
血行が抑えられ、かゆみが少し和らぐことがあります。それでも我慢できない場合は、皮膚科で相談すれば、かゆみを抑える抗ヒスタミン薬の内服薬や、非ステロイド系の鎮痒外用薬などを処方してもらうことができます。
- 子どもがやけどをしてしまいました。大人と同じ処置で大丈夫ですか
-
基本的な処置の流れ(冷やす、洗う、保護する)は大人と同じです。ただし、子どもの皮膚は大人に比べて薄くデリケートなため、同じ温度でも大人より深いやけどになりやすい傾向があります。
また、体に対するやけどの面積の割合が大きくなりやすく、重症化しやすいという特徴もあります。大人が見てたいしたことがないと思っても、小児科や皮膚科を受診することを強くお勧めします。
特に、乳幼児の場合は自分の症状をうまく伝えられないため、注意深い観察が必要です。
以上
参考文献
Uchinuma E, Koganei Y, Shioya N, Yoshizato K. Biological evaluation of burn blister fluid. Annals of plastic surgery. 1988 Mar 1;20(3):225-30.
Ono I, Gunji H, Zhang JZ, Maruyama K, Kaneko F. A study of cytokines in burn blister fluid related to wound healing. Burns. 1995 Aug 1;21(5):352-5.
Fujimoto M, Asai J, Asano Y, Ishii T, Iwata Y, Kawakami T, Kodera M, Abe M, Amano M, Ikegami R, Isei T. Wound, pressure ulcer and burn guidelines–4: Guidelines for the management of connective tissue disease/vasculitis‐associated skin ulcers. The Journal of dermatology. 2020 Oct;47(10):1071-109.
Morita S, Higami S, Yamagiwa T, Iizuka S, Nakagawa Y, Yamamoto I, Inokuchi S. Characteristics of elderly Japanese patients with severe burns. Burns. 2010 Nov 1;36(7):1116-21.
Wakisaka N, Kubota T, Ando K, Aihara M, Inoue H, Ishida H. Endothelin-1 kinetics in plasma, urine, and blister fluid in burn patients. Annals of plastic surgery. 1996 Sep 1;37(3):305-9.
NISHIZAKI A, Okuda J, AOYAMA H, IZAWA Y, MIZUTA E. Studies on transfer of injected cefmenoxime to exudates (blister) of wounds of burn patients. Chemotherapy. 1985 Dec;33:1069-74.
Pan SC, Wu LW, Chen CL, Shieh SJ, Chiu HY. Deep partial thickness burn blister fluid promotes neovascularization in the early stage of burn wound healing. Wound repair and regeneration. 2010 May;18(3):311-8.
Inoue M, Zhou LJ, Gunji H, Ono I, Kaneko F. Effects of cytokines in burn blister fluids on fibroblast proliferation and their inhibition with the use of neutralizing antibodies. Wound repair and regeneration. 1996 Oct;4(4):426-32.
Sargent RL. Management of blisters in the partial-thickness burn: an integrative research review. Journal of burn care & research. 2006 Jan 1;27(1):66-81.
Murphy F, Amblum J. Treatment for burn blisters: debride or leave intact?. Emergency Nurse. 2014 Apr 30;22(2).