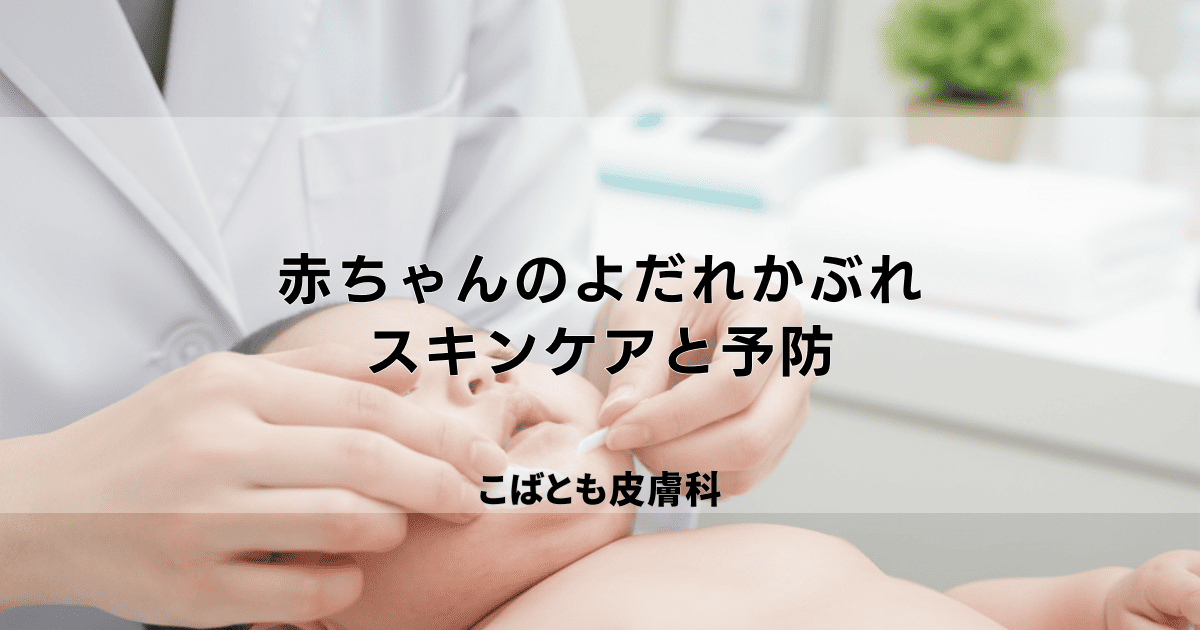赤ちゃんのぷにぷにした頬や口周りが赤くなっているのを見ると、とても心配になりますよね。特によだれの量が増えてくる生後3ヶ月頃から、多くの赤ちゃんがよだれかぶれを経験します。
これは、赤ちゃんの成長過程で自然なことですが、かゆみや痛みを伴うこともあり、見ている親御さんもつらいものです。
この記事では、よだれかぶれがなぜ起こるのか、原因から、ご家庭でできる正しいスキンケア方法、症状を悪化させないための生活習慣、そして皮膚科での治療法まで解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
そもそも赤ちゃんのよだれかぶれとは?原因と症状を解説
赤ちゃんの肌トラブルの中でも、特によく見られるよだれかぶれは、医学的には接触皮膚炎の一種です。まずは、なぜよだれが原因で皮膚炎が起きてしまうのか、根本的な理由と症状について見ていきましょう。
なぜ赤ちゃんはよだれが多いのか
赤ちゃんのよだれが多いのは、いくつかの理由が関係しています。生後2〜3ヶ月頃から唾液腺の発達が活発になりますが、赤ちゃんはまだ唾液を飲み込む機能が未熟なため、作られた唾液が口からあふれ出てしまいます。
また、歯が生え始める時期には、歯茎が刺激されて唾液の分泌量がさらに増加し、食べ物に興味を持ち始め、口をもぐもぐ動かすようになることも、よだれが増える一因です。
すべて赤ちゃんの健やかな成長の証であり、よだれの量が多いこと自体は心配する必要はありません。
よだれが肌の刺激になる理由
よだれ、つまり唾液には、食べ物の消化を助けるための消化酵素が含まれています。
アミラーゼやリパーゼといった酵素は、口の中では重要な役割を果たしますが、長時間肌に付着すると、皮膚の表面にある角質層を分解し、肌のバリア機能を低下させます。
バリア機能が弱まった肌は、外部からのわずかな刺激にも敏感になり、炎症を起こしやすくなります。
さらに、よだれが蒸発する際に肌の水分も一緒に奪ってしまうため、乾燥が進み、さらに肌トラブルを悪化させるという悪循環に陥ることがあるのです。
よだれに含まれる主な刺激物
| 成分名 | 役割 | 肌への影響 |
|---|---|---|
| 消化酵素(アミラーゼなど) | 食べ物の消化を助ける | タンパク質を分解し、皮膚のバリア機能を傷つける |
| 水分 | 口内を潤す | 蒸発時に肌の水分を奪い、乾燥を招く |
| 食べかす | 食事の残り | 雑菌の温床となり、炎症を悪化させる可能性がある |
よだれかぶれの主な症状
よだれかぶれの初期症状は、肌の赤みです。よだれがよく付着する口の周りやあご、頬などがうっすらと赤くなり、症状が進行すると、赤みが増し、ブツブツとした小さな湿疹やかゆみを伴うようになります。
さらに悪化すると、皮膚がじゅくじゅくしたり、かさぶたができたりすることもあり、赤ちゃんがかゆみから患部を掻きむしってしまうと、そこから細菌が入り込み、二次感染を引き起こす可能性もあるため注意が大切です。
症状が出やすい体の部位
よだれかぶれの症状は、よだれが付着しやすい場所に現れ、最も多いのは口の周りで、上唇と鼻の間、下唇の下、口角はよだれがたまりやすい部分です。あごや頬にもよく見られます。
また、うつ伏せで寝る赤ちゃんや、寝返りをする赤ちゃんは、よだれが首に流れ落ちて、首のしわの間にたまり、かぶれを起こすこともあります。
指しゃぶりの癖がある場合は、よだれが付いた手で顔や体を触ることで、予期せぬ場所に症状が広がることも考えられます。
よだれかぶれと間違いやすい赤ちゃんの皮膚トラブル
赤ちゃんの顔に赤い湿疹ができると、すべてよだれかぶれと考えがちですが、似たような症状を示す皮膚トラブルは他にもいくつかあり、原因が異なれば、対処法も変わってきます。
ここでは、よだれかぶれと見分けるのが難しい代表的な皮膚疾患について解説し、それぞれの特徴と見分け方のポイントを整理します。
あせもとの見分け方
あせもは、汗をたくさんかいたときに、汗の出口である汗管が詰まって炎症を起こすものです。赤い小さなブツブツができ、かゆみを伴います。
よだれかぶれが口周りを中心にできるのに対し、あせもは汗をかきやすいおでこ、首、背中、肘や膝の裏側など、全身どこにでもできる可能性があります。
特に夏場や厚着をさせているときに見られ、口周りだけでなく、首やおでこにも同じような湿疹が広がっている場合は、あせもの可能性も考えましょう。
よだれかぶれとあせもの比較
| 項目 | よだれかぶれ | あせも |
|---|---|---|
| 主な原因 | よだれ(唾液)の刺激 | 汗による汗管の詰まり |
| できやすい場所 | 口周り、あご、頬、首 | おでこ、首、背中、関節の内側など汗をかきやすい場所 |
| できやすい季節 | 通年(特によだれが増える時期) | 夏場や厚着の時期 |
乳児湿疹との違い
乳児湿疹は、生後2週間頃から数ヶ月の間に見られる、原因がはっきりしない湿疹の総称です。
皮脂の分泌が盛んなおでこや眉毛、頭皮に黄色いかさぶたやフケのようなものができたり、頬や体にかさかさした赤い湿疹ができたりと、症状は多彩です。
よだれかぶれのように口周りだけに限定されず、広範囲に症状が出ることが多く、皮脂の分泌が原因の一つと考えられており、よだれの刺激とは直接の関係はありません。
ただし、乳児湿疹で肌のバリア機能が低下していると、よだれかぶれを併発しやすくなることがあります。
食物アレルギーによるかぶれ
離乳食が始まると、特定の食べ物が原因でアレルギー反応を起こし、口の周りにかぶれのような症状が出ることがあります。食べた直後から口の周りが赤くなったり、じんましんが出たりするのが特徴です。
よだれかぶれとの大きな違いは、原因となる食べ物を食べたときにだけ症状が現れる点で、初めての食材を試した後に症状が出た場合は、食物アレルギーを疑う必要があります。
全身にじんましんが広がったり、咳や呼吸困難などの症状が見られたりする場合は、すぐに医療機関を受診してください。
アレルギーが疑われる場合のチェック項目
- 特定の食べ物を食べた後に症状が出るか
- 口の周りだけでなく、全身に湿疹やじんましんは出ていないか
- 嘔吐、下痢、咳などの他の症状はないか
- 機嫌が悪くなったり、ぐったりしたりしていないか
カンジダ皮膚炎の可能性
カンジダは、もともと皮膚に存在する常在菌(カビの一種)ですが、肌が湿った状態が続くと異常に増殖し、皮膚炎を起こすことがあります。よだれで常に湿っている口角や、おむつで蒸れやすい股などは、カンジダ皮膚炎が起こりやすい場所です。
よだれかぶれと似た赤みに加え、皮膚の表面が少し白っぽくなったり、ただれたり、小さな膿疱が見られたりし、通常の保湿ケアやステロイド外用薬では改善しにくく、抗真菌薬による治療が必要になります。
家庭でできるよだれかぶれの正しいスキンケア方法
よだれかぶれのケアの基本は、肌を清潔に保ち、しっかりと保湿することです。特別なことではありませんが、日々の積み重ねが赤ちゃんの肌を守ります。
よだれの拭き方とタイミング
よだれが出たら、こまめに拭き取ることが基本ですが、ゴシゴシと強くこするのは禁物です。乾いたティッシュやガーゼで強くこすると、摩擦で肌を傷つけてしまいます。
大切なのは、濡らしたガーゼやコットンを使い、肌を優しく押さえるようにしてよだれを吸い取ることです。外出先などで水が使えない場合は、ノンアルコールの赤ちゃん用おしりふきなどを活用するのも良いでしょう。
拭くタイミングは、よだれが出ているのに気づいた時、授乳や食事の後、寝る前など、こまめに行うのが理想です。
ぬるま湯での洗浄と洗い方のコツ
食事の後など、汚れがひどいときには、拭くだけでなく洗い流すのが効果的です。洗面器にぬるま湯(38〜39度程度)をため、ガーゼなどを使って優しく洗いましょう。
石鹸を使う場合は、赤ちゃん用の低刺激性のものをよく泡立て、泡でなでるように洗います。石鹸成分が肌に残らないよう、十分にすすぐことが大切です。
洗った後は、清潔で柔らかいタオルを使い、ここでもこすらずに、押さえるようにして水分を拭き取ります。お風呂の時も同様に、顔は最後に優しく洗いましょう。
洗浄時のポイント
- お湯の温度は38〜39度のぬるま湯に設定する
- 低刺激性のベビーソープを十分に泡立てて使う
- 指の腹を使って優しくなでるように洗う
- すすぎ残しがないように丁寧に洗い流す
保湿剤の選び方と塗り方
肌を清潔にした後は、すぐに保湿をし、水分を拭き取ってから5分以内が目安です。保湿剤は、赤ちゃんのデリケートな肌に合う、無香料・無着色・低刺激性のものを選びましょう。
ローション、クリーム、軟膏など様々なタイプがあり、肌の状態や季節に合わせて使い分けるのがおすすめです。
塗るときは、保湿剤をたっぷりと手に取り、肌に優しく乗せるように広げ、すり込むのではなく、皮膚のしわに沿って一定方向に伸ばすと、肌への負担が少なくなります。
保湿剤のタイプと特徴
| タイプ | 特徴 | おすすめの季節・肌状態 |
|---|---|---|
| ローション | 水分が多く、さっぱりとした使用感。伸びが良い。 | 夏場や広範囲への塗布、軽度の乾燥 |
| クリーム | 油分と水分のバランスが良く、しっとり感が続く。 | 春・秋や中程度の乾燥、部分的なケア |
| 軟膏・バーム | 油分が主成分で、保護力が高い。べたつきがある。 | 冬場や特に乾燥がひどい部位、皮膚の保護 |
ワセリンの効果的な使い方
ワセリンは、皮膚の表面に油分の膜を作ることで、水分の蒸発を防ぎ、外部の刺激から肌を保護する役割を果たします。
よだれかぶれのケアでは、保湿剤で肌に潤いを与えた後、その上からワセリンを薄く重ね塗りするのが効果的で、よだれが直接肌に触れるのを防ぐバリアの役割を果たします。
食事の前や就寝前など、よだれが多くなるタイミングで塗っておくと、肌への刺激を軽減できます。ただし、ワセリン自体に肌に水分を与える効果はないため、必ず保湿剤とセットで使うようにしましょう。
よだれかぶれを悪化させないための生活習慣のポイント
スキンケアと並行して、日々の生活習慣を見直すことも、よだれかぶれの改善と予防にはとても大事です。赤ちゃんが快適に過ごせる環境を整え、肌への刺激をできるだけ減らしてあげましょう。
スタイの選び方から室内の環境設定まで、少しの工夫で大きな違いが生まれます。
スタイ(よだれかけ)の選び方と交換頻度
スタイは、よだれを吸収し、衣服や肌が濡れるのを防ぐ便利なアイテムですが、選び方と使い方には注意が必要です。
素材は、肌に優しく、吸水性の高い綿100%のものがおすすめで、化学繊維は通気性が悪く、蒸れてかぶれの原因になることがあります。また、濡れたスタイを長時間着けていると、かえって肌への刺激になります。
スタイが湿ったら、こまめに取り替えるようにしましょう。1日に何枚も取り替えることになりますが、赤ちゃんの肌のためにはとても重要なことです。
スタイの素材別メリット・デメリット
| 素材 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 綿(コットン) | 吸水性・通気性が高い、肌触りが良い | 乾きにくい、濡れると冷たく感じることがある |
| ガーゼ | 通気性が非常に良い、乾きやすい、柔らかい | 吸水量が少ない、耐久性がやや低い |
| ポリエステル | 乾きやすい、デザインが豊富 | 吸水性が低い、蒸れやすい、肌への刺激になることがある |
衣服や寝具の素材選び
スタイと同様に、赤ちゃんの肌に直接触れる衣服や寝具の素材も、肌触りの良い綿100%のものを選びましょう。
首周りは、衣類のタグや縫い目が刺激になることがあるので、タグは外側に付いているものを選んだり、肌に当たらないように切ったりする工夫も有効です。
洗濯の際には、赤ちゃん用の無添加洗剤を使用し、すすぎを十分に行い、洗剤が衣類に残らないように注意しましょう。柔軟剤の香料などが刺激になることもあるため、使用は慎重に判断してください。
部屋の温度と湿度の管理
空気が乾燥していると肌の水分が奪われ、バリア機能が低下しやすくなり、冬場やエアコンを使用する時期は注意が大切です。加湿器などを利用して、部屋の湿度を50〜60%程度に保つように心がけましょう。
夏場に汗をたくさんかくと、あせもを併発し、よだれかぶれを悪化させる原因になります。室温は赤ちゃんが快適に過ごせる20〜25度程度を目安に、季節や服装に合わせて調整してあげてください。
爪を短く切る重要性
よだれかぶれにかゆみが出てくると、赤ちゃんは無意識に患部を掻いてしまいます。赤ちゃんの爪は薄くて鋭いため、少し引っ掻いただけでも肌が傷つき、症状が悪化したり、細菌が入って二次感染を起こす原因になったりします。
これを防ぐために、赤ちゃんの爪はこまめにチェックし、常に短く丸い状態に整えておきましょう。爪切りが苦手な場合は、赤ちゃんが寝ている間に行うのがおすすめで、ベビー用の爪切りハサミやヤスリを使うと安全です。
赤ちゃんの肌に優しい食事と離乳食の進め方
よだれかぶれは、離乳食が始まる時期と重なることが多いため、食事との関連を心配される方も少なくありません。食べこぼしによる刺激や、特定の食材が肌に影響を与えることもあります。
離乳食開始時期と肌への影響
一般的に、離乳食は生後5〜6ヶ月頃から始めるのが目安とされ、この時期は、よだれの量が増え、肌のバリア機能もまだ未熟なため、よだれかぶれが起こりやすいタイミングと重なります。
離乳食を始めること自体が、直接よだれかぶれの原因になるわけではありませんが、食べこぼしが口周りに付着し、よだれと混ざることで、肌への刺激が増す可能性があります。
離乳食を開始する際は、これまで以上に口周りの清潔と保湿を徹底することが大切です。
口周りの汚れを防ぐ工夫
食べこぼしを完全に防ぐことは難しいですが、少しの工夫で汚れを最小限に抑えることはでき、食事の前に、口周りにワセリンを塗っておくと、肌を保護し、汚れが直接付着するのを防げます。
食事用のエプロンは、ポケット付きのものを選ぶと、食べこぼしを受け止めてくれて便利です。食事が終わったら、すぐに口周りをきれいにしましょう。濡らしたガーゼで優しく拭き取るか、可能であれば洗い流し、その後必ず保湿をしてください。
離乳食の進め方と肌ケアのポイント
| 時期 | 食べ方の目安 | 肌ケアのポイント |
|---|---|---|
| 初期(ゴックン期) | スプーンから飲み込む練習 | 食事のたびに口周りを洗浄・保湿する |
| 中期(モグモグ期) | 舌と上あごでつぶして食べる | 食べこぼしが増えるため、こまめに拭き取る |
| 後期(カミカミ期) | 手づかみ食べが始まる | 食事前のワセリン保護が特に有効 |
アレルギーのリスクがある食材の注意点
食物アレルギーが心配で、離乳食の開始をためらう必要はありません。近年では、アレルギーが疑われる食材の開始をいたずらに遅らせることは、逆にアレルギー発症のリスクを高める可能性も指摘されています。
ただし、初めて与える食材、特に卵、乳製品、小麦などのアレルギーを起こしやすいものは、慎重に進める必要があります。平日の午前中など、万が一症状が出た場合にすぐに医療機関を受診できる時間帯に、ごく少量から試すようにしましょう。
口周りだけでなく、全身の皮膚の状態や機嫌なども注意深く観察してください。
初めての食材を試す際の注意点
- 一度に試すのは1種類だけにする
- ごく少量(スプーンの先に少し)から始める
- 医療機関の開いている平日の午前中に試す
- 食べた後、数時間は赤ちゃんの様子をよく観察する
皮膚科でのよだれかぶれの治療法
毎日のスキンケアを頑張っていても、なかなか症状が良くならなかったり、かえって悪化してしまったりすることもあり、自己判断で市販薬を試すのではなく、皮膚科医に相談することが大切です。
皮膚科を受診するタイミングの目安
家庭でのセルフケアを1週間ほど続けても改善が見られない場合や、症状が悪化している場合は、一度皮膚科を受診することをおすすめします。
赤みが強い、じゅくじゅくしている、黄色いかさぶたが付いている、かゆみが強くて赤ちゃんがよく掻いている、といった症状が見られる場合は、早めに相談しましょう。
また、よだれかぶれなのか、他の皮膚疾患なのか判断に迷う場合も、専門医の診察を受けることで、正しい診断と適切な治療に繋がります。
受診を検討すべき症状
| 症状のレベル | 具体的な状態 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 軽度 | うっすら赤みがある程度、かゆみは少ない | まず1週間、家庭でのスキンケアを徹底する |
| 中等度 | 赤みが強く、ブツブツしている、かゆみがある | セルフケアで改善がなければ受診を検討 |
| 重度 | じゅくじゅくしている、ただれている、掻き壊している | 早急に皮膚科を受診する |
主な塗り薬の種類と役割
皮膚科では、症状に応じて主に保湿剤やステロイド外用薬が処方されます。保湿剤は、ヘパリン類似物質や尿素などが配合された医療用のものが処方され、肌の水分保持能力を高めます。
炎症が強い場合には、ステロイド外用薬を使って、まず炎症をしっかりと抑える治療を行います。ステロイドと聞くと不安に思うかもしれませんが、医師の指導のもと、適切な強さの薬を適切な期間使用すれば、非常に効果的で安全な薬です。
じゅくじゅくして細菌感染が疑われる場合には、抗生物質入りの軟膏が処方されることもあります。
処方される主な塗り薬
- 保湿剤(ヒルドイド、ビーソフテンなど)
- 非ステロイド性抗炎症薬(アズノール軟膏など)
- ステロイド外用薬(ロコイド、キンダベートなど)
- 抗生物質含有軟膏(フシジンレオ軟膏など)
薬の正しい塗り方と注意点
処方された薬は、医師の指示通りの回数と量を守って塗ることが何よりも重要です。塗る前には、必ず手をきれいに洗いましょう。塗る順番は、一般的に保湿剤を先に塗り、肌が潤った上からステロイドなどの治療薬を重ねます。
ただし、医師から特別な指示があった場合はそれに従ってください。薬は患部より少し広めに、優しく伸ばします。自己判断で薬を中止したり、量を減らしたりすると、症状が再燃することがあるため、必ず医師の指示に従いましょう。
治療期間の目安
よだれかぶれの治療期間は、症状の重さや肌の状態によって異なりますが、軽い炎症であれば、数日から1週間程度で改善することが多いです。しかし、症状が重い場合や、掻き壊してしまっている場合は、治療に数週間かかることもあります。
大切なのは、症状が良くなったからといってすぐに薬をやめるのではなく、医師が指示した期間、きちんと治療を続けることで、炎症が治まった後も、再発を防ぐために保湿ケアは継続することが重要です。
よだれかぶれを繰り返さないための予防策
一度よだれかぶれが良くなっても、よだれの多い時期が続く限り、再発のリスクは常にあります。つらい症状を繰り返さないためには、治療だけでなく、日々の予防が何よりも大切です。
ここでは、赤ちゃんの肌を健やかに保ち、よだれかぶれを寄せ付けないための予防のポイントをいくつかご紹介します。
毎日のスキンケアの習慣化
よだれかぶれの予防の基本は、スキンケアを毎日続けることで、症状が出ていないときでも、朝起きた時、授乳や食事の後、お風呂上がり、寝る前など、1日複数回の保湿を習慣にしましょう。
肌が常に潤っている状態を保つことで、バリア機能が正常に働き、よだれなどの外部刺激に強い肌を育てることができます。大変ですが、この毎日の積み重ねが、赤ちゃんの肌を守る一番の力になります。
毎日のスキンケアチェックリスト
- よだれはこまめに優しく拭いているか
- 1日1回、泡で優しく洗浄しているか
- お風呂や洗浄後はすぐに保湿しているか
- 保湿剤は十分な量を塗れているか
- 食事前や寝る前にワセリンで保護しているか
肌のバリア機能を高める食事
肌は体の中から作られます。肌の健康を保つためには、バランスの取れた栄養が大切です。
離乳食が進んだら、皮膚の材料となるタンパク質(豆腐、魚、鶏ささみなど)、肌の新陳代謝を助けるビタミンB群(レバー、納豆、緑黄色野菜など)、肌の調子を整えるビタミンA・C・E(緑黄色野菜、果物など)を意識して取り入れましょう。
ただし、特定の栄養素だけをたくさん摂れば良いというわけではなく、様々な食材をバランスよく食べることが、丈夫な肌を作ります。
おもちゃや指しゃぶりの衛生管理
赤ちゃんは何でも口に入れて確認するので、おもちゃや自分の指をしゃぶることにより、よだれが顔以外にも付着し、かぶれの原因になることがあります。
赤ちゃんが口にする可能性のあるおもちゃは、こまめに洗浄したり、赤ちゃん用の除菌シートで拭いたりして、清潔に保ちましょう。
指しゃぶり自体を無理にやめさせる必要はありませんが、爪を短く切っておくこと、手を清潔に保つことを心がけてください。このひと手間が、肌トラブルの予防に繋がります。
衛生管理のポイント
| 対象 | 具体的な方法 | 頻度の目安 |
|---|---|---|
| おもちゃ | 水洗い、煮沸消毒、赤ちゃん用除菌グッズで拭く | 汚れたらその都度、定期的に |
| 手・指 | 濡れガーゼで拭く、手洗い | 食事の前、外から帰った時など |
| 寝具・タオル | こまめに洗濯する | 2〜3日に1回 |
よだれかぶれに関するよくある質問
最後に、よだれかぶれに関して保護者の方からよくいただく質問と回答をまとめました。
- よだれかぶれは自然に治りますか
-
ごく軽い赤み程度であれば、こまめなスキンケアを心がけることで自然に良くなることもありますが、赤ちゃんの肌はデリケートで、一度バリア機能が壊れると悪化しやすいです。
赤みが続いたり、ブツブツが出てきたりした場合は、自然治癒を期待して様子を見るよりも、適切なケアや治療を開始する方が、早くきれいに治ります。
- 市販の薬を使っても良いですか
-
自己判断での市販薬の使用はおすすめしません。市販薬の中には、赤ちゃんへの使用が推奨されていない成分が含まれているものや、症状に合っていないものもあります。
特にステロイド含有の薬は、強さや使用法を間違うと副作用のリスクもあります。よだれかぶれかどうかの診断も含め、まずは皮膚科で診察を受け、赤ちゃんの症状に合った薬を処方してもらうのが最も安全で確実です。
- スキンケアはいつまで続けるべきですか
-
よだれかぶれの症状が改善した後も、保湿を中心としたスキンケアは継続することをおすすめします。赤ちゃんの皮膚が大人と同じくらいの強さになるのは、3歳頃と言われています。
特によだれの多い時期や、空気が乾燥する季節は、肌トラブルを起こしやすい状態が続くので、肌のバリア機能を維持するために、日々の保湿を習慣として続けていきましょう。
- 歯が生え始めると悪化しますか
-
歯が生え始める時期(歯ぐずり期)は、歯茎のむずがゆさから、よだれの分泌量がさらに増える傾向があります。
また、機嫌が悪くなってぐずったり、おもちゃなどを頻繁に口に入れたりすることで、口周りへの刺激が増え、よだれかぶれが悪化したり、再発したりすることがあります。
この時期は、これまで以上にこまめによだれを拭き取り、清潔と保湿を徹底することが大切です。
以上
参考文献
Weber M. Child with Rash and Drooling. Cases in Pediatric Acute Care: Strengthening Clinical Decision Making. 2020 Apr 15:165-8.
Gagnon LR. Healthy Skin Care for Mother and Baby. Journal of Perinatal Education. 1992 Sep 1;1(3).
Munisamy M. Common skin conditions in older infants and toddlers. Indian Journal of Pediatrics. 2025 Aug 15:1-1.
Abu-Naser, S.S. and Hamed, M.A., 2016. An Expert System for Mouth Problems in Infants and Children.
Zamula E. Contact dermatitis: Solutions to rash mysteries. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Food and Drug Administration, Office of Public Affairs (5600 Fishers Lane, Rockville 20857); 1991.
Holzberger S. Primary care: Supporting parents in the management of minor conditions in infants. AJP: The Australian Journal of Pharmacy. 2022 Oct 1;103(1221):105-8.
Fleischer Jr AB. Diagnosis and management of common dermatoses in children: atopic, seborrheic, and contact dermatitis. Clinical pediatrics. 2008 May;47(4):332-46.
Fairhurst CB, Cockerill H. Management of drooling in children. Archives of Disease in Childhood-Education and Practice. 2011 Feb 1;96(1):25-30.
Zamula E. Contact dermatitis: Solutions to rash mysteries. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Food and Drug Administration, Office of Public Affairs (5600 Fishers Lane, Rockville 20857); 1991.
Eisenstadt M, Malkiel S, Pollak U. It’s Alright, Ma (I’m only Teething…) dispelling the Myth from the Teeth. Acad J Ped Neonatol. 2017;3(4):1-4.