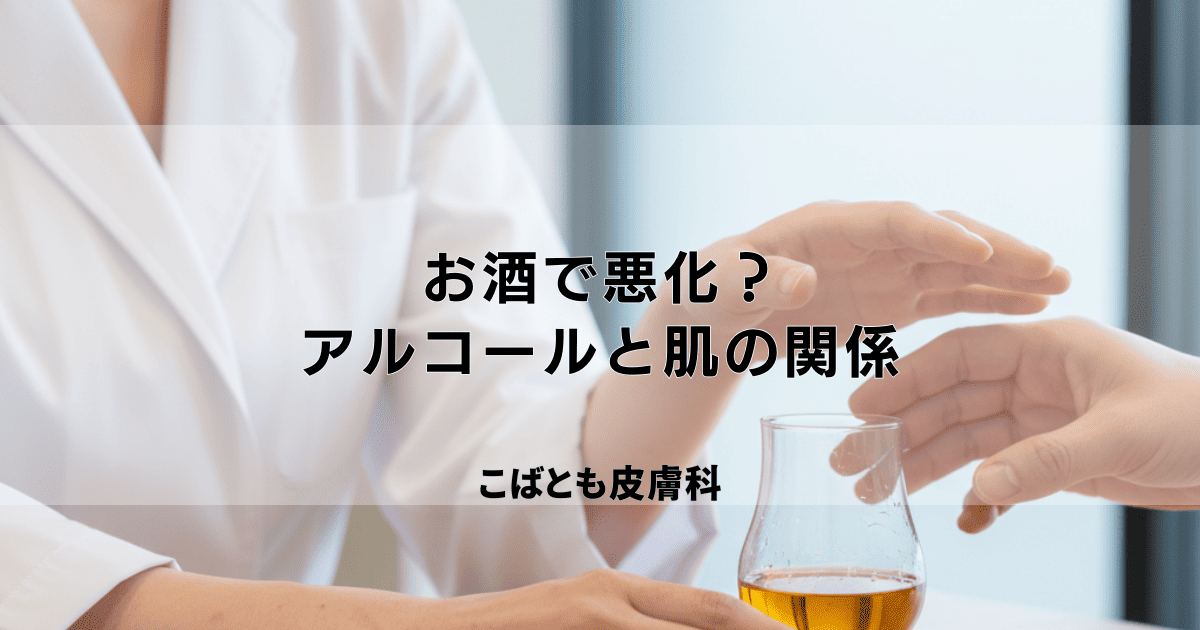日々の疲れを癒やすための一杯が、かえって肌のかゆみや赤みを起こすことはありませんか。お酒を飲むとアトピー性皮膚炎や蕁麻疹の症状が悪化すると感じる方は少なくありません。
アルコールが体内でどのように作用し、なぜ皮膚症状に影響を与えるのか、その関係は複雑です。
この記事では、アルコールとアトピー、蕁麻疹の関連性について、詳しく解説し、肌の健康を守りながらお酒と上手に付き合うための具体的な対処法や日常生活での注意点を紹介します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
なぜお酒でアトピーや蕁麻疹が悪化するのか
アルコールを摂取すると、体の中ではさまざまな反応が起こります。どのような変化が肌に影響を与えているのかを、見ていきましょう。
アルコール摂取と血流の変化
アルコールには血管を拡張させる作用があり、お酒を飲むと顔が赤くなったり、体がポカポカしたりするのは、血管拡張作用によるものです。
血流が増加すること自体は悪いことではありませんが、アトピー性皮膚炎や蕁麻疹のように、すでに皮膚で炎症が起きている場合、状況は異なり、炎症部位には、かゆみや赤みの原因となる物質が集まりやすいです。
血流が増えることで、炎症を起こす物質がさらに多く運ばれたり、炎症反応が活発になったりする可能性があります。
また、血管が拡張すると、血管の壁の透過性(物質が通り抜ける度合い)が高まり、血液中の水分や炎症に関わる細胞が血管の外に漏れ出しやすくなります。
これが皮膚の赤みや腫れ、蕁麻疹の場合は膨疹(みみず腫れ)の形成につながると考えられます。
皮膚のバリア機能が低下しているアトピー性皮膚炎の方では、わずかな刺激でも炎症が悪化しやすいため、血流の増加はかゆみを強く感じる要因です。
ヒスタミン放出の促進
アルコールが体内に入ると、かゆみの原因としてよく知られるヒスタミンが体内で放出されやすくなります。ヒスタミンは、アレルギー反応や炎症において中心的な役割を果たす化学伝達物質です。
ヒスタミンが放出されると、主に2つの作用が起こります。一つは、知覚神経を刺激して強いかゆみを起こすことで、もう一つは、血管の透過性を高めて血液中の成分を漏れ出させることで、蕁麻疹特有の膨疹や赤みを生じさせます。
アトピー性皮膚炎の方も、皮膚に存在する肥満細胞(マスト細胞)がさまざまな刺激によってヒスタミンを放出しやすい状態にあることが多いです。
アルコールの摂取がヒスタミンの放出をさらに促すことで、かゆみや赤みが一気に強まることがあります。
お酒に含まれるヒスタミン様物質
アルコール自体がヒスタミンの放出を促すだけでなく、お酒の種類によっては、ヒスタミンそのものや、ヒスタミンと似た作用を持つ物質(ヒスタミン様物質)が含まれていることがあります。
ヒスタミン様物質を摂取すると、体内で作られるヒスタミンと合わせて、アレルギー症状が悪化する原因となります。
| 酒類 | 含まれやすい物質 | 考えられる影響 |
|---|---|---|
| 赤ワイン | ヒスタミン、チラミン | 血管拡張、かゆみの誘発 |
| ビール | ヒスタミン(発酵過程で生成) | かゆみ、鼻づまりの誘発 |
| 日本酒 | ヒスタミン様物質 | 皮膚の赤み、かゆみ |
特に赤ワインはヒスタミン含有量が多いことで知られており、蕁麻疹や頭痛の原因となることがあります。醸造酒は、発酵の過程でこれらの物質が生成されやすいため、蒸留酒に比べて注意が必要です。
肝臓の解毒機能と肌への影響
肝臓は体内の毒素を解毒する重要な臓器で、アルコールの分解には多くの酵素やエネルギーが必要です。
日常的に飲酒量が多いと、肝臓はアルコールの分解作業に追われることになり、この状態が続くと、肝臓の機能が全般的に低下し、アルコール以外の有害物質や老廃物を解毒・排出する能力も落ちてしまいます。
体内に解毒されなかった有害物質が蓄積すると、血液に乗って全身を巡り、皮膚に到達します。皮膚は体内の状態を映す鏡とも言われ、肝機能の低下は肌荒れや皮膚の炎症として現れることがあります。
アルコールが肌のバリア機能に及ぼす影響
アトピー性皮膚炎の方にとって、皮膚のバリア機能は症状をコントロールする上で非常に重要ですが、アルコールは、皮膚のバリア機能にも直接的・間接的に悪影響を与えます。
皮膚の乾燥と脱水症状
アルコールには強い利尿作用があり、お酒を飲むとトイレが近くなるのはこのためです。体内の水分が尿として過剰に排出されると、体全体が脱水傾向になります。
皮膚の水分量が減少し皮膚が乾燥すると、表面の角質層がはがれやすくなり、外部からの刺激物(アレルゲン、細菌、化学物質など)が侵入しやすい状態になり、アトピー性皮膚炎をさらに悪化させます。
また、アルコールを分解する過程でも体内の水分が使用され、飲酒量が多いほど体はより多くの水分を失い、皮膚の乾燥は深刻です。
乾燥した皮膚はかゆみを感じやすくなるため、無意識に掻いてしまい、さらなるバリア機能の破壊と炎症の悪化という悪循環に陥りやすくなります。
炎症反応の増強
アルコールとその代謝物であるアセトアルデヒドは、体内で炎症反応を強める働きを持つことが知られています。アトピー性皮膚炎は慢性的な皮膚の炎症が本態ですが、アルコールは炎症をさらに煽る燃料のような役割を果たすことがあります。
アルコールが分解される過程で活性酸素が発生し、細胞を傷つけ酸化ストレスを起こし、炎症を引き起こすさまざまな物質の生成を促進すのです。
炎症を促進する主な物質
- プロスタグランジン
- ロイコトリエン
- サイトカイン(炎症性)
このような物質が増加すると、皮膚の赤み、腫れ、かゆみが強くなります。
免疫システムのバランスの乱れ
アトピー性皮膚炎や蕁麻疹は、免疫システムのバランスが崩れることと深く関連していて、アトピー性皮膚炎では、外部からの刺激に対して免疫が過剰に反応しやすい状態(Th2優位)です。
アルコールの摂取、特に慢性的な多量飲酒は、免疫システムのバランスをさらに乱し、腸内環境にも影響を与えます。
腸内細菌のバランスが崩れると、腸のバリア機能が低下し(リーキーガット症候群)、本来であれば体内に侵入しないはずの未消化物や毒素が血液中に入り込むことがあります。
未消化物や毒素が免疫システムを過剰に刺激し、アレルギー反応や炎症反応が全身で起こりやすくなるのです。
皮膚は免疫反応が現れやすい場所の一つであるため、腸内環境の悪化が巡り巡ってアトピー性皮膚炎や蕁麻疹の悪化につながることも考えられます。
アトピー性皮膚炎とアルコールの関係
アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う湿疹が良くなったり悪くなったりを繰り返す病気で、アルコールの摂取は、症状の波に直接的な影響を与え、かゆみを強くします。
かゆみの増強とその背景
アトピー性皮膚炎の方がアルコールを摂取した際に最も強く感じる変化は、かゆみの増強で、複数の理由が関わっています。
第一に、血流の増加で、皮膚の温度が上昇し、血流が良くなることで、かゆみを感じる神経(知覚神経)が刺激されやすくなります。また、ヒスタミンの放出が促進されることも、直接的なかゆみの原因です。
第二に、アルコールの利尿作用による皮膚の乾燥で、乾燥した肌は非常に敏感になっており、わずかな刺激でもかゆみを感じやすくなります。
さらに、飲酒によって判断力や自制心が低下することも見過ごせません。普段は我慢できていたかゆみも、お酒が入ると強く掻きむしってしまうことがあります。
掻破(そうは)行動が皮膚のバリアを物理的に破壊し、炎症をさらに悪化させ、かゆみがもっと強くなるという悪循環を生み出します。
アセトアルデヒドの刺激
アルコール(エタノール)は肝臓で分解されると、二日酔いの原因ともなる毒性の強いアセトアルデヒドという物質に変わります。
アセトアルデヒドは、体内のさまざまな細胞にとって刺激物となり、皮膚においても例外ではありません。アセトアルデヒドが血液中に増えると皮膚の細胞を刺激し、炎症反応を起こしたり、かゆみを誘発したりすることがあります。
アセトアルデヒドを分解する酵素(ALDH2)の働きが生まれつき弱い、あるいはない人(お酒に弱い体質の人)は、少量の飲酒でも体内に高濃度のアセトアルデヒドが長時間とどまります。
アセトアルデヒド分解能力の個人差
アセトアルデヒドの活性は遺伝的に決まっており、日本人を含むモンゴロイド系人種には活性が低いか欠損している人が多いです。
| 酵素のタイプ | 特徴(お酒の強さ) | アセトアルデヒドによる肌への影響リスク |
|---|---|---|
| 活性型(NN型) | お酒に強い | 中(飲酒量が増えがちなため) |
| 低活性型(ND型) | お酒に弱い(飲むと赤くなる) | 高(アセトアルデヒドが蓄積しやすいため) |
| 非活性型(DD型) | お酒が全く飲めない | 極めて高(少量のアルコールでも危険) |
お酒に弱い体質の人が無理して飲むと、アセトアルデヒドの影響を強く受け、アトピー性皮膚炎の症状が顕著に悪化することがあります。
睡眠の質低下による悪化
寝る前にお酒を飲むと寝付きが良くなると感じるかもしれませんが、一時的なもので、アルコールは睡眠の後半部分で眠りを浅くし、夜中に目が覚めやすくする(中途覚醒)作用があります。
睡眠の質が低下すると、体は十分に休息できず、ストレス状態になり、免疫系やホルモンバランスに影響を与え、アトピー性皮膚炎の炎症を悪化させることが知られています。
また、アトピー性皮膚炎のかゆみは、体が温まる夜間、就寝中に強くなる傾向があり、飲酒によって睡眠が浅くなると、かゆみをより意識しやすくなり、寝ている間に掻きむしってしまうことにもつながるのです。
蕁麻疹(じんましん)とアルコールの直接的な関連
蕁麻疹は、突然皮膚の一部が赤く盛り上がり(膨疹)、強いかゆみを伴う病気で、アルコールは、蕁麻疹を起こしたり、悪化させたりする直接的な原因となることがあります。
アルコール性蕁麻疹とは
飲酒後、数分から数時間以内に蕁麻疹が出現する場合、アルコール性蕁麻疹の可能性があり、アルコールそのもの、または代謝物であるアセトアルデヒドに対するアレルギー反応、あるいは非アレルギー性の反応によって起きます。
アセトアルデヒドを分解する酵素(ALDH2)の働きが弱い人は、アセトアルデヒドが体内に蓄積しやすく、直接的に皮膚の肥満細胞を刺激してヒスタミンを放出させ、蕁麻疹を起こすと考えられています。
このタイプの蕁麻疹は、お酒に弱い体質の人に多いです。
血管拡張による膨疹(ぼうしん)の出現
アルコールによる強い血管拡張作用も、蕁麻疹の症状を悪化させます。蕁麻疹の膨疹は、皮膚の浅い部分にある血管が拡張し、血管の透過性が高まることで血液中の水分(血漿)が周囲の組織に漏れ出すことによって形成されます。
アルコールはこの血管拡張と透過性の亢進を強力に促進し、すでに何らかの原因で蕁麻疹が出やすい状態にある人が飲酒すると、症状はより広範囲でより強いです。
また、物理性蕁麻疹の一つである温熱蕁麻疹(体温が上昇すると蕁麻疹が出る)を持つ人の場合、アルコール摂取による体温上昇が引き金となって症状が誘発されます。
食物アレルギーとの関連性
アルコールは、特定の食物アレルギーの症状を誘発または増強することがあり、これは食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA)の特殊なケースです。
特定の食物(例:小麦、甲殻類など)を食べただけでは症状が出ないのに、その食物を食べた後に運動をするとアナフィラキシー(重篤なアレルギー反応)が起こることがあります。
アルコールは胃腸の粘膜の透過性を高め、アレルゲン(アレルギーの原因物質)が体内に吸収されやすくする作用があります。
普段は問題ない量の食物アレルゲンでも、お酒と一緒に摂取することでアレルギー反応が起こりやすくなり、蕁麻疹として現れることがあります。
アルコールと関連しやすい食物
お酒のおつまみとして定番のものでも、アルコールと組み合わさることで蕁麻疹のリスクを高めます。
| 食物カテゴリ | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 甲殻類 | エビ、カニ | アルコールがアレルゲンの吸収を促進する可能性 |
| 小麦製品 | ピザ、パスタ、唐揚げの衣 | FDEIAの原因として知られる |
| サバ・マグロなど | ヒスタミンが多く含まれる | アルコールがヒスタミン分解を阻害する可能性 |
お酒の種類による肌への影響
アルコールである以上、どのお酒にも共通のリスク(血管拡張、利尿作用など)はありますが、お酒の製造方法や含まれる成分の違いによって、肌への影響の出方が異なる可能性はあります。
醸造酒(ビール、日本酒、ワイン)の特徴
醸造酒は、原料(麦、米、ブドウなど)を酵母によって発酵させて造るお酒で、アルコール以外にも、原料由来のタンパク質や糖質、発酵過程で生まれるさまざまな微量成分が含まれています。
アルコール以外の成分が、アレルギー反応や炎症を起こすことがあり、ビールやワインに含まれる亜硫酸塩(酸化防止剤)や、原料のタンパク質に対してアレルギー反応を起こす人もいます。
また、醸造酒、特に赤ワインや熟成したお酒には、ヒスタミンやヒスタミン様物質が多く含まれる傾向があり、このような物質も直接かゆみや蕁麻疹の原因です。
醸造酒の主な成分と肌への影響
醸造酒に含まれる多様な成分が、肌トラブルの原因となることがあります。
| 成分 | 含まれる主な酒 | 肌への潜在的影響 |
|---|---|---|
| ヒスタミン・チラミン | 赤ワイン、ビール、日本酒 | かゆみ、蕁麻疹、赤みの誘発 |
| 亜硫酸塩(添加物) | ワイン(特に白) | アレルギー様の反応、喘息の誘発 |
| 原料由来タンパク質 | ビール(大麦)、日本酒(米) | 食物アレルギーと同様の反応 |
蒸留酒(焼酎、ウイスキー、ウォッカ)の特徴
蒸留酒は、醸造酒をさらに蒸留して造るお酒で、蒸留の過程でアルコールと水以外の多くの成分(糖質、タンパク質、不純物など)が取り除かれます。
醸造酒に含まれるようなヒスタミン様物質や原料由来のアレルゲン、添加物などの影響は、一般的に蒸留酒の方が少ないです。
「蒸留酒ならアトピーや蕁麻疹が出にくい」と感じる人がいるとすれば、不純物の影響が少ないためかもしれませんが、あくまでアルコール以外の成分の話です。
アルコールそのものが持つ血管拡張作用、利尿作用、アセトアルデヒドの毒性による影響は、蒸留酒でも全く同じように起こります。
アルコール度数が高いものが多いため、純アルコール摂取量が多くなり、かえって症状が悪化する可能性も十分にあります。
糖質の多いお酒(カクテル、梅酒など)の注意点
カクテルやリキュール、梅酒、チューハイなどには、飲みやすくするために多くの糖質(砂糖や果糖ぶどう糖液糖)が加えられています。
糖質を一度に多く摂取すると、血糖値が急上昇し、血糖値を下げるためにインスリンというホルモンが大量に分泌されます。インスリンの分泌や血糖値の急激な変動は、体内の炎症を促進するので注意が必要です。
糖質が肌炎症に与える影響
- 血糖値の急激な上昇と下降
- インスリン様成長因子(IGF-1)の増加
- 皮脂分泌の促進
また、過剰な糖質は体内のタンパク質と結びつき、糖化反応を起こし、生成されるAGEs(最終糖化産物)は、体の老化や炎症を促進する物質です。
アトピー性皮膚炎や蕁麻疹の背景には慢性的な炎症があるため、糖質の多いお酒は、アルコールの影響に加えて、糖質による炎症促進という二重の負担を肌にかける可能性があります。
アトピーや蕁麻疹を持つ人のお酒との付き合い方
アトピー性皮膚炎や蕁麻疹の症状がある場合、最も安全なのはお酒を飲まないこと(禁酒・断酒)ですが、もし飲むのであれば、症状の悪化を最小限に抑えるための工夫が大切です。
まずは医師に相談する重要性
お酒と皮膚症状の関係は、個人の体質や症状の程度によって大きく異なります。自己判断でお酒の種類を変えたり、量を調整したりする前に、まずはかかりつけの皮膚科医に相談することが大事です。
現在使用している治療薬(内服薬や外用薬)とアルコールの相互作用が問題となる場合もあります。
抗ヒスタミン薬の中には、アルコールと一緒に飲むと眠気が非常に強く出ることがあるので、医師に自分の飲酒習慣を伝え、どの程度なら許容されるか、あるいは完全に避けるべきかのアドバイスを受けてください。
飲酒量を管理する
もし医師から飲酒の許可が出た場合でも、量は厳格に管理する必要があります。症状の悪化は、摂取した純アルコールの総量に比例する傾向があります。
自分がどれくらいの量を飲むと症状が悪化するかを正確に把握し、その手前で必ず止める意識が大切です。
適度な飲酒量の目安
厚生労働省が推進する「健康日本21」では、節度ある適度な飲酒量として、1日平均純アルコールで約20g程度としていますが、あくまで健康な成人の目安であり、皮膚に症状がある場合は、これより大幅に少ない量でも悪化する可能性があります。
| 純アルコール量(約20g)の目安 | 主な酒類 |
|---|---|
| ビール(中瓶1本) | 500mL |
| 日本酒(1合) | 180mL |
| ウイスキー(ダブル1杯) | 60mL |
飲む前・飲酒中・飲んだ後のセルフケア
飲酒による肌へのダメージを少しでも減らすために、飲む前から飲んだ後までの一連のケアが重要です。
飲む前には、空腹状態を避けましょう。胃が空っぽの状態でお酒を飲むと、アルコールの吸収が速まり、血中アルコール濃度が急激に上昇し、アセトアルデヒドの影響も強く受けます。食事と一緒、あるいは何か食べてから飲むようにしてください。
飲酒中は、アルコールの利尿作用による脱水を防ぐため、お酒と同量以上の水(チェイサー)を積極的に飲むことが大切です。
飲酒時のセルフケアポイント
- 空腹時の飲酒を避ける
- お酒と同量以上の水を飲む
- 飲酒後は入念に保湿する
飲んだ後は、寝る前にしっかりと保湿ケアを行います。アルコールで体が乾燥しているため、いつも以上に丁寧に保湿剤を塗ることが、夜間のかゆみを予防するために役立ちます。
飲酒以外でアトピー・蕁麻疹を管理する方法
お酒はアトピーや蕁麻疹の悪化因子の一つに過ぎません。症状を根本的にコントロールするためには、飲酒を控えることと同時に、日々の生活習慣全体を見直し、適切な治療を継続することが必要です。
スキンケアの基本
アトピー性皮膚炎の管理において、スキンケアは治療の土台となり、皮膚のバリア機能を正常に保つことが、あらゆる刺激から肌を守る鍵です。
基本は洗浄と保湿で、洗浄時は、低刺激性の洗浄剤をよく泡立て、手で優しく洗います。ゴシゴシこするとバリア機能が壊れてしまうため、絶対に避けてください。洗い流すお湯の温度も熱すぎず、ぬるま湯(38〜40度程度)が適しています。
入浴後は、皮膚が乾燥する前に、すぐに保湿剤を塗布します。タオルで水分を優しく押さえるように拭き、まだ皮膚が少し湿っているうちに塗るのが効果的です。
保湿剤の選び方
保湿剤にはさまざまな種類があり、肌の状態や季節によって使い分けることが望ましいです。
| 種類 | 特徴 | 適した肌状態・季節 |
|---|---|---|
| ローション(化粧水) | 水分が多く、さっぱりした使用感 | 比較的軽度の乾燥、夏場 |
| クリーム | 油分と水分のバランスが良い | 中等度の乾燥、春秋 |
| 軟膏(ワセリンなど) | 油分が主体で、皮膚を保護する力が強い | 乾燥が強い部位、冬場、バリア機能が低下した部位 |
どの保湿剤が自分に合うかわからない場合は、皮膚科で相談し、適切なものを処方してもらうか、アドバイスを受けるとよいでしょう。
食生活の見直し
特定の食べ物が直接アトピーや蕁麻疹の原因となる(食物アレルギー)場合を除いても、日々の食生活は肌の状態に大きく影響します。
腸内環境を整えることは、免疫バランスを整える上で重要で、発酵食品(ヨーグルト、納豆など)や食物繊維(野菜、海藻、きのこ類)を積極的に摂り、腸内細菌のバランスを良好に保つよう心がけることが大切です。
高脂肪食、加工食品、スナック菓子、糖質の多い食品は、体内の炎症を促進する可能性があるので、摂取が多いと感じる場合は、見直してみましょう。
肌の健康を支える栄養素
- ビタミンA(皮膚や粘膜の健康維持)
- ビタミンC(コラーゲン生成、抗酸化作用)
- 亜鉛(皮膚の新陳代謝)
- 良質な脂質(オメガ3脂肪酸など)
このような栄養素をバランス良く摂取することが、健康な皮膚を作るために役立ちます。
ストレス管理
精神的なストレスは、アトピー性皮膚炎や蕁麻疹の明確な悪化因子で、ストレスを感じると、体内でかゆみを起こす物質が放出されたり、免疫バランスが乱れたりします。
現代社会でストレスをゼロにすることは困難ですが、自分なりのストレス解消法を見つけ、上手に付き合っていくことが大切です。
日常でできるストレス対策
| 方法 | 具体例 | 期待できること |
|---|---|---|
| リラクゼーション | 深呼吸、瞑想、ヨガ、ぬるめのお風呂 | 自律神経のバランスを整える |
| 適度な運動 | ウォーキング、ストレッチ(汗をかいたらすぐケア) | 気分転換、睡眠の質の向上 |
| 趣味の時間 | 音楽鑑賞、読書、ガーデニング | 悩み事から意識をそらす |
適切な医療機関での治療
セルフケアだけで症状がコントロールできない場合は、皮膚科を受診してください。アトピー性皮膚炎や蕁麻疹の治療は、近年大きく進歩しています。
炎症を抑えるためのステロイド外用薬や免疫抑制外用薬、かゆみを抑えるための抗ヒスタミン薬の内服、重症の場合には生物学的製剤(注射薬)やJAK阻害薬(内服薬)といった新しい治療選択肢もあります。
アルコールと肌に関するよくある質問
最後に、患者さんからよく寄せられる質問について、いくつかお答えします。
- お酒に強い人(分解が早い人)はアトピーが悪化しにくいですか?
-
一概にそうとは言えません。
お酒に弱い人(アセトアルデヒドの分解が遅い人)は、アセトアルデヒドの毒性による皮膚症状の悪化が起こりやすいですが、お酒に強い人(分解が早い人)は、飲酒量が多くなりがちです。
摂取する純アルコールの総量が増えれば、アルコールそのものが持つ血管拡張作用、利尿作用による乾燥、炎症促進作用などの影響を強く受けることになります。
- ノンアルコールビールなら飲んでも大丈夫ですか?
-
日本の酒税法では、アルコール度数1%未満の飲料をノンアルコール飲料としていますが、実際には0.5%や0.8%といった微量のアルコールを含む商品も多くあります。
アルコールに非常に敏感な方や、アセトアルデヒド分解酵素がない方にとっては、微量なアルコールでも症状が出る可能性があります。
また、ノンアルコール飲料には、風味をビールに似せるためにさまざまな添加物や糖質が多く含まれている場合があり、肌への刺激となる可能性もゼロではありません。
- 飲酒後に肌がかゆくなった時の応急処置は?
-
まずは、それ以上お酒を飲むのを直ちに中止してください。そして、かゆい部分を冷やすことが有効です。冷水で濡らしたタオルや、タオルで包んだ保冷剤などを当てて、皮膚の温度を下げ、炎症と神経の興奮を鎮めます。
ただし、寒冷蕁麻疹(冷やすと蕁麻疹が出る)の方はこの方法は使えません。掻きむしるのは絶対に避け、処方されているかゆみ止めの外用薬(ステロイドなど)があれば、塗布します。
症状がひどい場合や、呼吸困難、気分の悪さなどを伴う場合は、すぐに医療機関を受診してください。
- 減感作療法(アレルゲン免疫療法)中に飲酒してもよいですか?
-
推奨されません。特にスギ花粉やダニに対する舌下免疫療法を行っている場合、治療薬を服用した当日の飲酒は避けましょう。
アルコールによる血管拡張作用で、アレルゲンが体内に急激に吸収されたり、副反応(口の中の腫れやアナフィラキシーなど)が出やすくなったりするリスクが考えられます。
以上
参考文献
Ophaswongse S, Maibach HI. Alcohol dermatitis: allergic contact dermatitis and contact urticaria syndrome: a review. Contact dermatitis. 1994 Jan;30(1):1-6.
Nakagawa Y, Sumikawa Y, Nakamura T, Itami S, Katayama I, Aoki T. Urticarial reaction caused by ethanol. Allergology International. 2006;55(4):411-4.
Matano Y, Morita T, Ito M, Okazaki S, Koto M, Ichikawa Y, Takayama R, Hoashi T, Saeki H, Kanda N. Dietary habits in Japanese patients with chronic spontaneous urticaria. Australasian Journal of Dermatology. 2020 Aug;61(3):e333-8.
Sticherling M, Brasch J. Alcohol: intolerance syndromes, urticarial and anaphylactoid reactions. Clinics in dermatology. 1999 Jul 1;17(4):417-22.
Wilkin JK, Fortner G. Ethnic contact urticaria to alcohol. Contact Dermatitis (01051873). 1985 Feb 1;12(2).
Sticherling M, Brasch J, Brüning H, Christophers E. Urticarial and anaphylactoid reactions following ethanol intake. British Journal of Dermatology. 1995 Mar;132(3):464-7.
Katoh N, Ohya Y, Ikeda M, Ebihara T, Katayama I, Saeki H, Shimojo N, Tanaka A, Nakahara T, Nagao M, Hide M. Japanese guidelines for atopic dermatitis 2020. Allergology International. 2020;69(3):356-69.
Ophaswongse S, Maibach HI. Alcohol dermatitis: allergic contact dermatitis and contact urticaria syndrome: a review. Contact dermatitis. 1994 Jan;30(1):1-6.
Warin RP. Acute urticaria due to alcohol. British Journal of Dermatology. 1983 Dec;109(6):723-.
Sticherling M, Brasch J. Alcohol: intolerance syndromes, urticarial and anaphylactoid reactions. Clinics in dermatology. 1999 Jul 1;17(4):417-22.