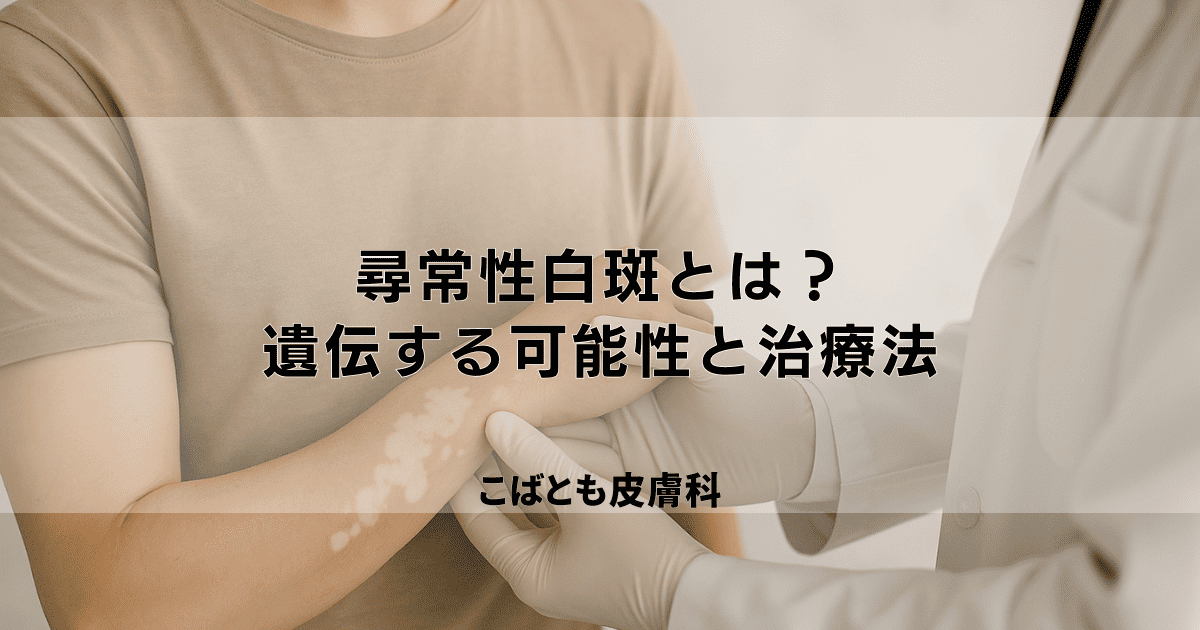ある日突然、肌の色が部分的に白く抜けてしまう尋常性白斑。痛みやかゆみといった自覚症状がないことが多いものの、見た目の変化から、大きな不安や悩みを抱える方も少なくありません。
この記事では、尋常性白斑の基本的な知識から、原因、遺伝との関係、そして皮膚科で行われる専門的な検査や治療法、日常生活での注意点まで、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
尋常性白斑の基本的な知識
尋常性白斑という病名を聞いたことがあっても、どのような状態を指すのか、詳しく知る機会は少ないかもしれません。まずは、この病気の最も基本的な部分から理解を深めていきましょう。
尋常性白斑とはどのような病気か
尋常性白斑は、皮膚の色素を作る細胞であるメラノサイトが何らかの理由で減少または消失することにより、皮膚の色が白く抜けてしまう後天性の病気です。
尋常性という言葉は一般的にみられる、ありふれたという意味で使われ、白斑は皮膚の色が白くなる状態を指します。つまり、特別な病気ではなく、誰にでも起こりうる皮膚疾患の一つです。
感染症ではないため、他の人にうつることはなく、また、白斑部分の皮膚機能が損なわれるわけではなく、痛みやかゆみなどの自覚症状も基本的には伴いません。
しかし、整容的な問題、つまり見た目の変化が患者さんの心に大きな負担を与えることがあり、生活の質(QOL)に影響を及ぼす疾患です。
皮膚の色が抜ける仕組み
私たちの肌の色は、主にメラニンという色素の量によって決まり、メラニンを産生しているのが、表皮の最も深い層である基底層に存在するメラノサイトという細胞です。
紫外線などの刺激を受けると、メラノサイトは活発にメラニンを作り出し、周囲の表皮細胞に受け渡し、メラニンが、紫外線から皮膚の細胞核を守る日傘のような役割を果たしています。
尋常性白斑では、メラノサイトが後天的にその部位でなくなってしまうか、あるいは機能しなくなってしまいます。
メラニンを産生する工場がなくなってしまうため、その部分の皮膚はメラニン色素を失い、本来の肌の色が抜けて白く見えるようになるのです。
尋常性白斑と他の脱色素斑との違い
| 種類 | 主な原因 | 特徴 |
|---|---|---|
| 尋常性白斑 | 自己免疫など複数の要因 | 境界明瞭な白い斑点。拡大・融合することがある。 |
| 老人性白斑 | 加齢によるメラノサイトの減少 | 数ミリ程度の小さな白い点状。主に手足や体幹に多発する。 |
| 脱色素性母斑 | 生まれつきのメラノサイト機能低下 | 出生時または幼少期から存在する。大きさはあまり変化しない。 |
発症しやすい部位と年齢
尋常性白斑は、体のどの部分にも発症する可能性がありますが、特に現れやすい部位がいくつかあり、手や足の甲、指先、肘、膝といった、日常的に摩擦や圧迫などの物理的な刺激を受けやすい部位です。
また、顔面では口の周りや目の周り、鼻、額などにも好発し、このほか、脇の下、へその周り、陰部などにも発症しやすいです。
特定の部位に発症しやすい傾向があるのは、ケブネル現象という、皮膚への刺激が発症の引き金になる現象と関連があると考えられています。
全年齢層で起こりえますが、特に10代から30代の若年層での発症が多いと報告されています。約半数の患者さんが20歳までに発症し、70〜80%が30歳までに発症するというデータもあり、比較的若い時期に始まることが多い病気です。
他の皮膚疾患との見分け方
皮膚が白くなる病気は尋常性白斑だけではありません。高齢者の腕や脚によく見られる数ミリ大の白い斑点は、老人性白斑(特発性滴状メラニン減少症)であることが多く、これは加齢に伴う生理的な変化と考えられています。
また、生まれつき、あるいは生後まもなくから存在する白いあざは、脱色素性母斑(はたけ)の可能性があります。
白斑の大きさが体の成長に伴って拡大することはあっても、尋常性白斑のように数が増えたり、範囲が大きく広がったりすることは稀です。
その他、癜風(でんぷう)という皮膚の真菌症や、炎症後色素脱失といって、湿疹や皮膚炎が治った後に一時的に色が抜ける状態などとも見分ける必要があります。
尋常性白斑の原因として考えられること
尋常性白斑がなぜ発症するのか、そのはっきりとした原因はまだ特定されていません。しかし、長年の研究からいくつかの説が有力視されており、多くの場合、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。
自己免疫疾患との関連性
現在、最も有力な原因と考えられているのが自己免疫説です。
体には、外部から侵入してきた細菌やウイルスなどを異物として認識し、攻撃して体を守る免疫というシステムが備わっていますが、免疫システムに異常が生じると、誤って自分自身の正常な細胞や組織を攻撃してしまうことがあります。
これが自己免疫疾患で、尋常性白斑の場合、免疫システムが自分のメラノサイトを異物と間違えて攻撃し、破壊してしまうことで発症するという考え方です。
この説を裏付けるように、尋常性白斑の患者さんでは、甲状腺疾患(橋本病やバセドウ病)、悪性貧血、1型糖尿病、円形脱毛症といった他の自己免疫疾患を合併する頻度が一般よりも高いことが知られています。
また、患者さんの血液中からメラノサイトを攻撃する自己抗体が見つかることもあります。
尋常性白斑に合併しやすい自己免疫関連疾患
- 甲状腺疾患(橋本病、バセドウ病)
- 円形脱毛症
- 1型糖尿病
- 悪性貧血
- アジソン病
ストレスや外的刺激の影響
精神的なストレスや肉体的な疲労が、尋常性白斑の発症や悪化の引き金になるのではないか、という説もあります。ストレスは自律神経やホルモンバランスの乱れを引き起こし、免疫機能にも影響を与えることが知られています。
また、物理的な刺激も重要な要因です。皮膚を強くこすったり、掻いたり、あるいは衣類で締め付けられたりする場所に白斑が生じることがあります。これをケブネル現象と呼び、尋常性白斑の特徴的な所見の一つです。
手術の傷跡や、日焼けによる炎症の後に白斑が現れることもあり、外的刺激がメラノサイトに何らかのダメージを与え、それをきっかけに免疫反応が引き起こされるのではないかと考えられています。
日常生活においては、肌に過度な刺激を与えないように心がけることが大切です。
神経系の異常との関係
尋常性白斑の中には、神経の走行に沿って白斑が分布する分節型と呼ばれるタイプがあり、体の片側のある神経が支配する領域に限って白斑が生じます。
このことから、神経系の異常がメラノサイトの機能に影響を与えているのではないかという説があります。
神経の末端から放出される特定の神経伝達物質が、メラノサイトに対して毒性を持つように作用したり、メラノサイトの自己破壊を誘導したりするという説です。
また、自律神経のバランスの乱れが、皮膚の血流や免疫応答に影響を与え、間接的に白斑の発症に関わっているという見方もあります。
考えられる発症要因のまとめ
| 要因説 | 概要 | 関連する現象 |
|---|---|---|
| 自己免疫説 | 免疫系がメラノサイトを攻撃する | 他の自己免疫疾患の合併 |
| ストレス・刺激説 | 精神的・物理的要因が引き金となる | ケブネル現象(摩擦部位の発症) |
| 神経説 | 神経系の異常がメラノサイトに影響する | 分節型白斑(神経支配領域に一致) |
原因不明の場合も多い現状
尋常性白斑の発症には自己免疫、遺伝的素因、ストレス、外的刺激、神経系の異常など、様々な要因が関わっていると考えられていますが、多くの患者さんにおいて、要因のどれか一つだけで発症を説明することは困難です。
多くの場合、遺伝的に尋常性白斑になりやすい体質を持つ人が、何らかの環境因子(ストレス、感染症、皮膚への刺激など)をきっかけとして免疫系に異常をきたし、発症に至るのではないか、という多因子的な発症モデルが想定されています。
尋常性白斑と遺伝の関係性
尋常性白斑と診断された方や、そのご家族が最も心配されることの一つに、遺伝の問題があります。
自分に白斑があることで、子供にも遺伝してしまうのではないか、あるいは家族に白斑の人がいるから自分も発症したのではないか、という不安は当然のことです。
尋常性白斑は遺伝するのか
結論から言うと、尋常性白斑は単純な遺伝病ではありませんが、全く遺伝が関係ないかというと、そうでもありません。研究により、尋常性白斑の発症には遺伝的な要因、いわゆる病気になりやすい体質が関わっていることがわかっています。
これは、特定の遺伝子一つで決まるメンデル遺伝(例えば血液型など)とは異なり、多数の遺伝子が少しずつ関与する多因子遺伝という形式をとると考えられています。
発症に関わる遺伝子は、主に免疫系の働きを調節するものが多いと報告されており、これが自己免疫説とも深く関連しています。
家族内発症の確率
尋常性白斑の患者さんのうち、家族(親子、兄弟姉妹、祖父母など)にも同じ病気の方がいる割合は、おおよそ20%前後です。この数字からも、遺伝的要因だけで発症するわけではないことがわかります。
もし尋常性白斑が強い遺伝性を持つ病気であれば、この割合はもっと高くなるはずです。
一方で、一般人口における尋常性白斑の発症率が約1%であることを考えると、家族に患者さんがいる場合に発症するリスクは、そうでない場合に比べてやや高くなっています。
遺伝的要因と環境要因の役割
| 要因 | 役割 | 具体例 |
|---|---|---|
| 遺伝的要因 | 発症しやすさ(素因)に関わる | 免疫機能を調節する遺伝子など |
| 環境要因 | 発症の引き金(誘因)となる | ストレス、外的刺激、感染症など |
遺伝的要因が関わる場合の特徴
家族歴、つまり家族に尋常性白斑の患者さんがいる場合、いない場合と比較していくつかの特徴が見られることがあります。
家族歴のある患者さんの方が、より若年で発症する傾向があるという報告があり、また、白斑の範囲がより広範囲に及ぶ非分節型(汎発型)になりやすい可能性も指摘されています。
さらに、甲状腺疾患などの自己免疫疾患を合併する頻度も、家族歴のある患者さんの方が高い傾向にあるようです。
このような特徴は、遺伝的素因が病気のなりやすさだけでなく、発症年齢や病気のタイプ、重症度にもある程度影響を与えていることを示唆しています。
遺伝以外の要因の重要性
尋常性白斑の発症において遺伝的素因は一つの要素に過ぎません。同じ遺伝情報を持つ一卵性双生児でさえ、一方が発症してももう一方は発症しないというケースも報告されており、このことは遺伝以外の要因の重要性を強く物語っています。
遺伝的素因という土台の上に、ストレス、皮膚への物理的刺激、特定の薬剤、ウイルス感染、あるいは日焼けといった様々な環境要因が引き金となって、初めて発症に至ると考えられています。
日常生活において、皮膚への過度な刺激を避けたり、心身のストレスを上手に管理したりするなど、環境要因に配慮することの方が、発症や悪化を防ぐ上で現実的かつ重要です。
尋常性白斑の分類と種類
尋常性白斑は、白斑の分布や広がり方によって、主に非分節型、分節型、そして分類不能なタイプに分けられます。
非分節型(汎発型)の特徴と進行
非分節型は尋常性白斑の中で最も多いタイプで、全体の約8割から9割を占めるといわれています。このタイプの特徴は、白斑が体の左右両側に対称性、あるいは非対称性に出現し、体の様々な部位に多発することです。
初期には小さな白斑が一つか二つ現れるだけですが、時間とともに数が増えたり、個々の白斑が拡大して融合したりして、広範囲に及ぶことがあり、汎発型とも呼ばれます。
進行のスピードには個人差が大きく、数ヶ月で急速に広がる場合もあれば、数年かけてゆっくりと進行する場合、あるいはある程度のところで進行が止まる場合もあります。
ケブネル現象(物理的刺激を受けた部位に白斑が生じる)が起こりやすいのも、非分節型の特徴で、また、甲状腺疾患などの自己免疫疾患を合併しやすいのもこちらのタイプです。
非分節型白斑の好発部位
- 手足の指先、甲
- 顔面(口囲、眼囲)
- 肘、膝などの関節部
- 体幹、脇の下
- 陰部
分節型の特徴と好発部位
分節型は、非分節型に次いで多いタイプで、全体の1〜2割程度を占めます。最大の特徴は、白斑が体の片側だけに、皮膚の神経支配領域(デルマトーム)に沿って出現することです。
顔の右側だけ、あるいは胸の左側だけといったように、体の正中線を越えずに帯状に分布するため、神経系の異常が発症に関与していると考えられています。非分節型に比べて若年、特に小児期に発症することが多い傾向があります。
多くの場合、発症から1〜2年以内に急速に拡大しますが、その後は進行が停止し、長期間にわたって状態が安定することが多いのも特徴です。
白斑部分の毛(髪の毛、眉毛、まつ毛など)も白くなることがよくありますが、非分節型とは異なり、ケブネル現象や自己免疫疾患の合併は比較的少ないとされています。
尋常性白斑の主な種類の比較
| 項目 | 非分節型(汎発型) | 分節型 |
|---|---|---|
| 分布 | 全身性、左右非対称または対称 | 片側性、神経支配領域に沿う |
| 進行 | 進行性、活動性が変動しやすい | 初期に拡大後、停止することが多い |
| 好発年齢 | 10〜30代が多い | 小児期に多い |
混合型や未分類型の存在
典型的な非分節型、分節型に分類されることが多い尋常性白斑ですが、中にはこれらの特徴を併せ持つ混合型のケースもあります。
最初は分節型として発症した白斑が、数年後に体の他の部位にも非分節型の白斑として出現するような場合です。このようなケースでは、分節型と非分節型の両方の発症要因が関わっている可能性が考えられます。
また、白斑が非常に限局しており、どちらのタイプにもはっきりと分類できない状態を未分類型とすることもあります。粘膜(唇や陰部など)だけに白斑が限局する粘膜型や、体の限られた一箇所だけに白斑が生じる限局型などがこれに含まれます。
これらのタイプは、その後の経過を慎重に観察し、白斑の広がり方によって最終的に非分節型などに移行するかどうかを判断していくことになります。
皮膚科で行う尋常性白斑の検査と診断
皮膚に白い斑点ができた場合、それが本当に尋常性白斑なのか、それとも他の病気なのかを正確に判断することが、治療への第一歩です。皮膚科では、専門的な知識といくつかの検査方法を用いて、的確な診断を行います。
視診と問診の重要性
診断の基本は、医師による丁寧な視診と問診です。
視診では、白斑の大きさ、形、境界の明瞭さ、色調(完全に色が抜けているか、少し色が残っているか)、分布(体のどの部分にあるか、左右対称か)、白斑部分の毛の色などを詳細に観察します。
問診では、いつ頃から白斑に気づいたか、最初の発生部位はどこか、その後どのように広がったか、といった白斑自体の経過を詳しく聞きます。
さらに、家族に同じ病気の人がいないか、甲状腺疾患や円形脱毛症など他の自己免疫疾患にかかっていないか、皮膚に傷や強い刺激を受けたことがなかったか、精神的なストレスはなかったかなど、発症の誘因となりうる事柄についても確認します。
ウッド灯検査による診断
ウッド灯(とう)検査は、尋常性白斑の診断において非常に有用な検査で、ウッド灯とは、特定の波長(約365nm)の紫外線を放出する特殊なブラックライトのことです。
この光を暗い部屋で皮膚に当てると、尋常性白斑のようにメラニン色素が完全に消失している部分は、青白く、あるいは真っ白に明るく光って見えます。
通常の照明下では分かりにくい境界が不明瞭な白斑や、まだ色が抜け始めたばかりの初期の白斑も、はっきりと捉えることができ、健常な皮膚との境界が明確になり、白斑の正確な範囲を把握するのに役立ちます。
また、炎症後色素脱失など、メラニンが完全には消失していない他の疾患との鑑別にも有用です。
診断時に確認する主な項目
- 白斑の発生時期と経過
- 分布(部位、対称性)
- 境界の明瞭さ
- 家族歴や既往歴
- ケブネル現象の有無
皮膚生検が必要なケース
ほとんどの尋常性白斑は、視診、問診、ウッド灯検査で診断が可能ですが、中には診断が難しいケースもあります。白斑の形状が非典型的であったり、他の皮膚疾患との鑑別が困難であったりする場合です。
そのような場合には、確定診断のために皮膚生検を行うことがあります。
尋常性白斑の病変部では、顕微鏡で観察すると、表皮基底層に存在するはずのメラノサイトが消失している所見や、真皮にリンパ球などの炎症細胞が集まっている所見が認められます。
血液検査で調べること
尋常性白斑そのものを診断するために、必須となる血液検査はありません。
しかし、尋常性白斑(特に非分節型)は、甲状腺疾患(橋本病、バセドウ病)や1型糖尿病、悪性貧血といった他の自己免疫疾患を合併することがあるため、合併症の有無をスクリーニングする目的で、血液検査を行うことが推奨されています。
甲状腺ホルモンや抗甲状腺抗体、血糖値やHbA1c、抗核抗体などを調べ、もし検査で異常が見つかった場合は、それぞれの専門科(内分泌内科など)と連携して、治療や管理を行っていくことが必要です。
皮膚科における尋常性白斑の主な治療法
尋常性白斑の治療目標は、白斑の拡大を止め、色素の再生を促すことです。現在のところ、誰にでも確実に効く特効薬というものはありませんが、皮膚科では様々な治療法を組み合わせることで、症状の改善を目指します。
外用薬(ステロイド・その他)による治療
治療の基本となるのが、塗り薬による治療(外用療法)です。主に、白斑部に起きている異常な免疫反応を抑える目的で、ステロイド外用薬が用いられます。
ステロイドには様々な強さのランクがあり、白斑の部位(顔面などの皮膚が薄い場所か、手足などの皮膚が厚い場所か)や年齢に応じて適切な強さのものが選択されます。
長期間使用する場合には、皮膚が薄くなる、毛細血管が拡張するといった副作用に注意が必要です。
また、ステロイド以外の選択肢として、タクロリムス軟膏やデルゴシチニブ軟膏といった、ステロイドとは異なる仕組みで免疫を調節する外用薬も用いられます。
顔面など、ステロイドの長期使用がはばかられる部位にも使いやすいのが利点です。外用療法は、範囲が狭い白斑や、発症して間もない白斑に対して有効性が期待できます。
主な外用薬の種類と特徴
| 薬剤の種類 | 主な作用 | 注意点 |
|---|---|---|
| ステロイド外用薬 | 抗炎症作用、免疫抑制作用 | 長期使用による皮膚萎縮などの副作用 |
| タクロリムス軟膏 | 免疫抑制作用(非ステロイド性) | 使用開始時の刺激感、日光への注意 |
| デルゴシチニブ軟膏 | JAK阻害による免疫調節作用 | 比較的新しい薬剤、長期的なデータは蓄積中 |
光線療法(ナローバンドUVB・エキシマライト)
外用療法と並行して、あるいは外用療法で効果が不十分な場合に積極的に行われるのが光線療法(紫外線療法)です。
治療に有効な特定の波長の紫外線を白斑部に照射することで、異常な免疫反応を抑え、残っているメラノサイトを刺激して色素の再生を促します。
現在主流となっているのは、ナローバンドUVB療法とエキシマライト(またはエキシマランプ)療法です。
ナローバンドUVBは、治療効果が高く有害な作用が少ないとされる中波長紫外線(UVB)の中の非常に狭い波長域(311nm)の光を、白斑が広範囲にある場合は全身に、あるいは部分的に照射します。
エキシマライトは、さらに波長の短い(308nm)紫外線を、より強力に、かつ病変部だけにピンポイントで照射できるのが特徴です。週に1〜2回の通院が必要ですが、非分節型に対して高い効果が期待できます。
外科的治療(皮膚移植)の選択肢
長期間、外用療法や光線療法を行っても色素の再生が見られない、活動性が停止した白斑に対しては、外科的治療が選択肢となることがあります。代表的なものに、吸引水疱蓋移植術やミニグラフト法などがあります。
正常な皮膚(主にお尻や太ももなど、目立たない部位)からごく薄く皮膚を採取し、白斑部分に移植することで、メラノサイトを補充する治療法です。特に、進行が停止している分節型の白斑が良い適応とされます。
ただし、移植した皮膚がうまく生着しない可能性や、採取した部位と移植した部位の色調が完全に一致しない可能性もあります。また、ケブネル現象が起きやすい活動性の白斑には適していません。
尋常性白斑との上手な付き合い方
尋常性白斑の治療は長期にわたることが多いため、皮膚科での治療と並行して、日常生活の中で病気と上手に付き合っていく工夫も大切です。日々の少しの心がけが、症状の安定や精神的な負担の軽減につながります。
日常生活で注意すべき点
最も重要な注意点の一つが、皮膚への物理的な刺激を避けることです。
ケブネル現象を誘発しないために、体を洗うときにごしごし擦らない、サイズのきつい衣類や下着の着用を避ける、ベルトやカバンの紐が常に同じ場所に当たらないようにするなど、日常的な摩擦や圧迫に気をつけましょう。
また、切り傷や擦り傷、虫刺されなども白斑のきっかけになりうるため、怪我をしないように注意することも大切です。精神的なストレスや過労も、白斑の活動性を高める要因となりえます。
日常生活での注意点リスト
- 皮膚を強く擦らない
- 締め付けの強い衣類を避ける
- 怪我をしないように注意する
- 十分な睡眠と休息をとる
- ストレスを溜めない工夫をする
紫外線対策の重要性
紫外線との付き合い方は、尋常性白斑において少し複雑な側面があります。治療法として紫外線を活用する光線療法があるように、適度な紫外線は色素再生に有益な場合がありますが、過度な紫外線は白斑の悪化要因となりえます。
特に注意したいのが、日焼けで、白斑部分はメラニン色素による防御機能がないため、日光に対して非常に敏感で、日焼けによる炎症(サンバーン)を起こしやすい状態です。日焼けはケブネル現象を誘発し、白斑を拡大させる可能性があります。
また、白斑の周りの正常な皮膚が日焼けすると、白斑との色のコントラストがより目立ってしまいます。日常生活においては、日焼け止めをこまめに塗る、帽子や日傘、長袖の衣類を活用するなどして、過度な紫外線を避ける対策が重要です。
紫外線対策のポイント
| 対策方法 | ポイント |
|---|---|
| 日焼け止め | SPF30/PA++以上を目安に、こまめに塗り直す |
| 衣類 | 長袖、長ズボン、UVカット機能のある素材を選ぶ |
| 小物 | 帽子、日傘、サングラスなどを活用する |
カバーメイクという選択肢
治療によって色素が回復するまでには、ある程度の時間が必要です。その間、白斑が気になって外出が億劫になったり、人と会うのがつらくなったりすることもあるかもしれません。そのような場合に非常に有効なのが、カバーメイクです。
カバーメイクとは、白斑やあざ、傷跡などを一時的に隠すための専用の化粧品のことで、通常のファンデーションよりもカバー力が高く、汗や水に強いのが特徴です。
白斑部分に塗ることで、周囲の肌の色と馴染ませ、目立たなくすることができます。
尋常性白斑に関するよくある質問
最後に、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 治療期間はどのくらいかかりますか
-
色素の再生には時間がかかり、数ヶ月から数年単位での治療が必要になることが多いです。光線療法などでは、効果を実感するまでに少なくとも3ヶ月から半年程度は継続することが推奨されます。
また、治療効果が見られ始めた後も、再発を防ぐために治療を続けることもあります。
- 治療費は保険適用されますか
-
尋常性白斑の治療は、ほとんどが健康保険の適用対象です。診察、検査(ウッド灯、皮膚生検など)、処方される外用薬、光線療法(ナローバンドUVB、エキシマライト)も保険が適用されます。
ただし、外科的治療(皮膚移植)や、審美的な目的で行われるカバーメイクの製品購入やカウンセリングなどは、自費診療となる場合があります。
- 食生活で気をつけることはありますか
-
現時点では、特定の食品が尋常性白斑を良くしたり、悪化させたりするという明確な科学的根拠はありません。最も大切なのは、様々な食品を偏りなく摂取し、栄養バランスの取れた食事を心がけることです。
特に、抗酸化作用のあるビタミン(ビタミンC、ビタミンEなど)やミネラルを多く含む野菜や果物を積極的に摂ることは、健康な皮膚を保つ上で良い影響を与える可能性があります。
- 子供でも発症しますか
-
お子さんでも尋常性白斑を発症することはあり、神経の走行に沿って白斑が現れる分節型は、小児期に発症することが多いです。
お子さんの場合は、まだ自分で症状をうまく説明できなかったり、治療への協力が難しかったりすることがあり、また、学校生活などで、お友達から見た目について指摘されるなど、心理的な影響も心配されます。
治療法については、年齢やライフスタイルを考慮し、負担の少ない方法から選択します。
以上
参考文献
Oiso N, Suzuki T, Wataya‐kaneda M, Tanemura A, Tanioka M, Fujimoto T, Fukai K, Kawakami T, Tsukamoto K, Yamaguchi Y, Sano S. Guidelines for the diagnosis and treatment of vitiligo in Japan. The Journal of dermatology. 2013 May;40(5):344-54.
Ohguchi R, Kato H, Furuhashi T, Nakamura M, Nishida E, Watanabe S, Shintani Y, Morita A. Risk factors and treatment responses in patients with vitiligo in Japan—A retrospective large‐scale study. The Kaohsiung Journal of Medical Sciences. 2015 May;31(5):260-4.
Narita T, Oiso N, Fukai K, Kabashima K, Kawada A, Suzuki T. Generalized vitiligo and associated autoimmune diseases in Japanese patients and their families. Allergology International. 2011;60(4):505-8.
Zhang XJ, Chen JJ, Liu JB. The genetic concept of vitiligo. Journal of Dermatological Science. 2005 Sep 1;39(3):137-46.
Inoue S, Suzuki T, Sano S, Katayama I. JAK inhibitors for the treatment of vitiligo. Journal of Dermatological Science. 2024 Mar 1;113(3):86-92.
Okamura K, Suzuki T. Genetics and epigenetics in vitiligo. Journal of Dermatological Science. 2025 Mar 1;117(3):45-51.
Spritz RA, Andersen GH. Genetics of vitiligo. Dermatologic clinics. 2017 Apr 1;35(2):245-55.
Muramatsu S, Suga Y, Mizuno Y, Hasegawa T, Komuro Y, Kubo Y, Imakado S, Ogawa H. A Japanese case of naevoid basal cell carcinoma syndrome associated with segmental vitiligo. British Journal of Dermatology. 2005 Apr 1;152(4):812-4.
Spritz RA, Santorico SA. The genetic basis of vitiligo. Journal of Investigative Dermatology. 2021 Feb 1;141(2):265-73.
Hayashi M, Jin Y, Yorgov D, Santorico SA, Hagman J, Ferrara TM, Jones KL, Cavalli G, Dinarello CA, Spritz RA. Autoimmune vitiligo is associated with gain-of-function by a transcriptional regulator that elevates expression of HLA-A* 02: 01 in vivo. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2016 Feb 2;113(5):1357-62.