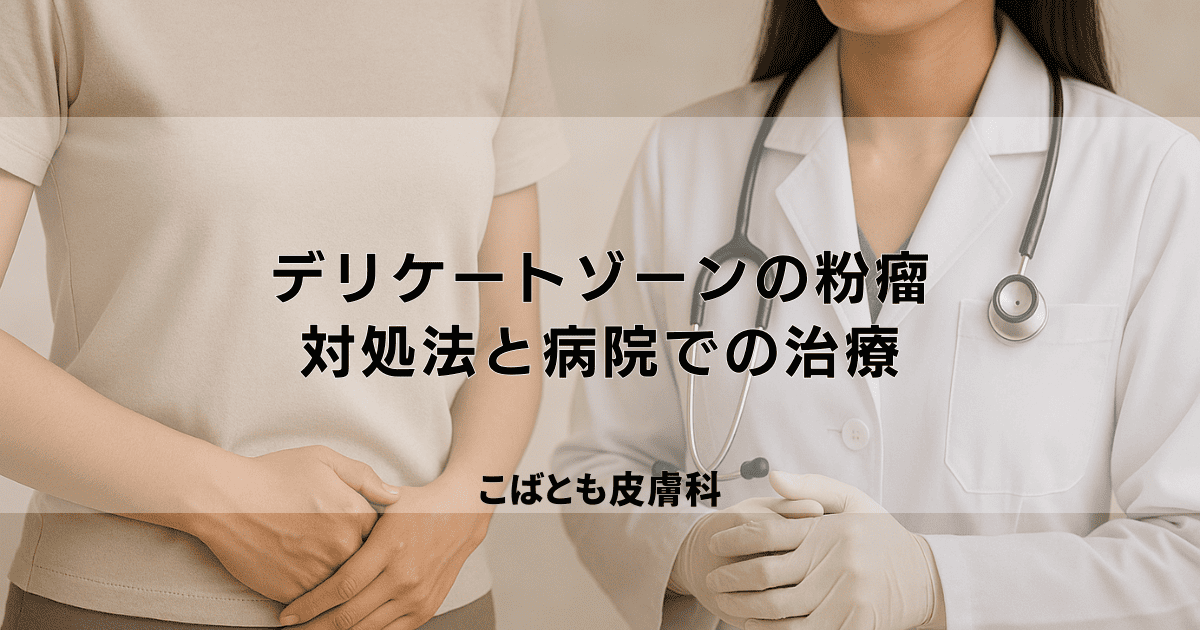デリケートゾーンにできる、しこりのようなもの。触るとコリコリしていて、時には痛みも伴うこの症状に、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
それは粉瘤(ふんりゅう)、またはアテロームと呼ばれる良性の皮膚腫瘍かもしれません。ニキビと間違えやすいですが、原因も対処法も全く異なります。
この記事では、デリケートゾーンの粉瘤の原因から、自然治癒の可能性、痛みがある場合の対処法、皮膚科で行う専門的な治療まで、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
デリケートゾーンのしこり、それは粉瘤かもしれません
ある日突然、デリケートゾーンにこれまでなかったしこりを見つけると、誰でも驚き、心配になるもので、その正体は、皮膚のできものの中でも比較的多く見られる粉瘤である可能性が高いです。
ただし、見た目だけでは他の皮膚疾患との区別がつきにくいため、まずは粉瘤がどのようなものなのかを正しく知ることが重要です。
粉瘤とはどのようなものか
粉瘤は、皮膚の下に袋状の構造物ができ、その中に本来は皮膚から剥がれ落ちるはずの垢(あか)や皮脂などの老廃物が溜まってしまうことで形成される、ドーム状のしこりです。
皮膚の内側に袋ができてしまうことが根本的な成り立ちで、袋がある限り老廃物は溜まり続けます。最初は小さな点程度の大きさですが、時間とともに少しずつ大きくなる傾向があります。
中央部分に黒い点(開口部)が見えることがあり、強く押すと臭いを伴うドロドロとした内容物が出てくることもありますが、自分で無理やり押し出すのは避けるべきです。
粉瘤の主な症状
- 半球状の盛り上がり
- 中央の黒い点
- 特有の臭い
- 炎症時の痛みや腫れ
ニキビやおできとの見分け方
デリケートゾーンはニキビやおでき(毛嚢炎)もできやすい場所のため、粉瘤と混同されがちですが、成り立ちが全く異なります。
ニキビは毛穴の詰まりとアクネ菌の増殖による炎症が主な原因であり、おできは毛穴の奥の毛根を包む部分に細菌が感染して起こります。粉瘤との大きな違いは、皮膚の下に老廃物を溜め込む袋状の構造があるかどうかです。
この袋を取り除かない限り、粉瘤は完治しません。
粉瘤・ニキビ・おできの比較
| 種類 | 主な原因 | 特徴 |
|---|---|---|
| 粉瘤(アテローム) | 皮膚の下にできた袋に老廃物が溜まる | 中央に黒い点、袋状の構造物、特有の臭い |
| ニキビ | 毛穴の詰まり、アクネ菌の増殖 | 芯がある、炎症性の赤み |
| おでき(毛嚢炎) | 毛穴への細菌感染 | 毛穴を中心に赤く腫れる、膿を持つ |
粉瘤ができやすい体の部位
粉瘤は皮脂の分泌が多い場所や、毛穴がある場所ならどこにでもできる可能性があります。
特に顔、首、背中、耳の後ろなどは好発部位として知られていて、自分でも鏡で確認しやすい場所ですが、デリケートゾーンのように普段あまり目にしない場所にもできることを知っておく必要があります。
体のどこにできても、基本的な性質は同じです。
粉瘤の好発部位
| 部位 | できやすさの理由 |
|---|---|
| 顔・首 | 皮脂腺が多く、毛穴が密集している |
| 背中 | 自分では見えにくく、皮脂が溜まりやすい |
| デリケートゾーン | 蒸れやすく、下着による摩擦が起こりやすい |
デリケートゾーンにできる粉瘤の特徴
VIOラインなどのデリケートゾーンは、他の部位と比較していくつかの特徴があります。まず、下着による締め付けや摩擦、座ることによる圧迫など、日常的に物理的な刺激を受けやすい環境です。
また、通気性が悪く蒸れやすいため、細菌が増殖しやすい状況にもあり、要因が重なることで、デリケートゾーンの粉瘤は炎症を起こしやすく、痛みを伴う炎症性粉瘤に発展しやすい傾向があるため、特に注意が必要です。
デリケートゾーンに粉瘤ができる原因とは
なぜ、デリケートな場所に粉瘤ができてしまうのでしょうか。原因は一つではなく、皮膚の基本的な構造から、生活習慣、外部環境まで、さまざまな要因が複雑に関係しています。
皮膚の構造と粉瘤の成り立ち
皮膚は、外側から表皮、真皮、皮下組織という層で構成されていて、粉瘤は、何らかの理由で表皮の一部が皮膚の内側に入り込み、袋を形成してしまうことから始まります。
通常、表皮の細胞は新陳代謝によって垢として剥がれ落ちますが、袋の中では逃げ場がなく、袋の中に垢や皮脂がどんどん蓄積し、しこりとして触れるようになるのです。
毛穴の詰まりが引き金に
粉瘤ができる直接的な原因として最も多いと考えられているのが、毛穴の詰まりです。
毛穴の出口付近が何らかの理由で塞がってしまうと、皮膚のターンオーバーが正常に行われなくなり、表皮の成分が皮膚の内部にめり込むようにして袋を形成することがあります。
デリケートゾーンは毛が多い部位であり、自己処理による肌へのダメージや、皮脂、汗などが原因で毛穴が詰まりやすい環境にあるため、粉瘤の発生リスクが高い場所です。
デリケートゾーンの毛穴が詰まる要因
| 要因 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 不適切なムダ毛処理 | カミソリ負けや毛抜きによる毛穴へのダメージ |
| 皮脂や汚れの蓄積 | 洗浄が不十分で、古い角質や皮脂が残る |
| 下着による圧迫 | 締め付けの強い下着で毛穴の出口が塞がれる |
ホルモンバランスの乱れとの関連
ホルモンバランスの乱れも、粉瘤の発生や悪化に関与する可能性があり、男性ホルモンには皮脂の分泌を活発にする働きがあります。
ストレスや不規則な生活、睡眠不足などによってホルモンバランスが崩れると、皮脂が過剰に分泌され、毛穴が詰まりやすくなり、粉瘤ができやすい肌状態になることが考えられます。
ホルモンバランスが乱れる主な生活習慣
- 過度なストレス
- 睡眠不足
- 偏った食生活
- 疲労の蓄積
外部からの刺激や摩擦の影響
デリケートゾーンは、下着や衣類との摩擦、長時間の座位による圧迫など、物理的な刺激を常に受けやすい部位です。
このような慢性的な刺激は、皮膚の角質を厚くし、毛穴を塞ぐ原因となり、また、皮膚のバリア機能を低下させ、小さな傷から皮膚の成分が内部に入り込んでしまうことも考えられます。
タイトなジーンズやガードルなどを日常的に着用する習慣がある方は、注意が必要です。
デリケートゾーンの粉瘤は自然治癒するのか
できてしまった粉瘤が、薬を塗ったり、そのままにしておいたりすることで自然に消えてなくなることはあるのでしょうか。
デリケートゾーンの粉瘤は、病院に行くのをためらってしまう方も多く、自然治癒を期待したい気持ちはよく分かりますが、残念ながらその期待に反して、粉瘤の自然治癒は極めて難しいです。
粉瘤の袋状構造と自然治癒の難しさ
粉瘤が自然に治らない最大の理由は、成り立ちにあり、粉瘤は皮膚の下にできてしまった袋の中に老廃物が溜まることで形成されます。
たとえ内容物を一時的に排出できたとしても、原因である袋そのものが皮膚の内側に残っている限り、再び老廃物は溜まり始め、再発してしまいます。この袋状構造を取り除かない限り、根本的な解決には至りません。
自然治癒を期待して放置することは、問題の先延ばしにしかならないのです。
自然治癒が困難な理由
| 理由 | 詳細 |
|---|---|
| 袋の存在 | 老廃物を生み出す根源である袋が体内に残存する |
| 継続的な蓄積 | 袋がある限り、垢や皮脂は常に溜まり続ける |
| 体の異物反応 | 体は袋を異物と認識し、自然に分解・吸収できない |
なぜ放置は危険なのか
小さなうちは痛みもなく、特に気にならないかもしれませんが、粉瘤の放置にはいくつかのリスクが伴います。一つは、サイズが徐々に大きくなることで、大きくなればなるほど、治療の際の傷跡も大きくなる可能性があります。
また、デリケートゾーンという場所柄、大きくなることで座ったり歩いたりする際に違和感を覚え、日常生活に支障をきたすことも考えられます。そして、最大のリスクは次に説明する炎症です。
炎症性粉瘤へと悪化するリスク
粉瘤に細菌が感染したり、袋が破れて内容物が周辺組織に漏れ出したりすると、体は異物と認識し、強い炎症反応を起こし、これを炎症性粉瘤と呼びます。炎症を起こすと、粉瘤は急激に赤く腫れあがり、ズキズキとした強い痛みを伴います。
熱を持つこともあり、場合によっては膿が溜まってブヨブヨとした状態になります。デリケートゾーンは特に蒸れやすく細菌が繁殖しやすいため、炎症を起こすリスクが高い部位です。
自己判断で潰すことの危険性
気になってつい触ってしまったり、ニキビのように中身を押し出そうとしたりする方がいますが、絶対にやめてください。無理に潰そうとすると、皮膚の下で袋が破れてしまい、炎症を悪化させる原因になります。
内容物が周囲に散らばることで、痛みや腫れがさらに強くなり、治療がより複雑になる可能性があり、また、完全に内容物を排出しきれず、すぐに再発してしまいます。
自分で潰すことの主なリスク
- 炎症の悪化
- 細菌感染の拡大
- 瘢痕(はんこん)形成
- 不完全な排出による即時再発
炎症を起こした場合の応急処置
デリケートゾーンの粉瘤が急に痛み出し、赤く腫れてきたら、炎症性粉瘤のサインかもしれません。強い痛みを伴うため、すぐにでも何とかしたいと思うでしょう。
病院に行くまでの間、少しでも症状を和らげるために自宅でできることと、逆に症状を悪化させてしまうため絶対にやってはいけないことを知っておくことが大切です。
痛みや腫れがある時のサイン
炎症性粉瘤のサインは非常に分かりやすいです。昨日まで何ともなかったしこりが、急に大きくなったように感じ、赤みを帯びてきます。
触ると熱を持っており、何もしなくてもズキズキ、ジンジンとした拍動するような痛みを感じるようになります。
下着が擦れるだけで激痛が走ったり、座ることも困難になったりするなど、日常生活に大きな影響が出始め、これは体内で強い炎症が起きている証拠です。
医療機関を受診すべき炎症のサイン
- 急激なサイズの増大
- 皮膚の赤みと熱感
- 自発痛(何もしなくても痛い)
- 圧痛(押すと強く痛む)
自宅でできる応急的な対処法
強い痛みがある場合、まずは患部を清潔に保ち、安静にすることが第一です。シャワーなどで優しく洗い、清潔なタオルで水分を拭き取ります。
締め付けの強い下着は避け、通気性の良いゆったりとしたものを着用し、患部への刺激を最小限に抑えましょう。痛みが強い場合は、清潔なガーゼやタオルで包んだ保冷剤などで短時間冷やすと、一時的に楽になることがあります。
ただし、これらはあくまで症状を緩和するための応急処置であり、治療ではないことを理解してください。
炎症時のセルフケア可否
| 対処法 | 可否 | 注意点 |
|---|---|---|
| 患部を清潔に保つ | 可 | 石鹸でゴシゴシ擦らず、優しく洗い流す |
| 患部を冷やす | 可 | 冷やしすぎに注意し、短時間にとどめる |
| 市販の痛み止めを飲む | 可 | 用法用量を守る。あくまで一時的な対処 |
| 市販の化膿止めを塗る | 不可 | 症状を悪化させる可能性があるため自己判断は避ける |
やってはいけない行動
痛いからといって、患部を何度も触ったり、揉んだり、自分で潰そうとしたりするのは最も危険な行為で、炎症をさらに広げ、細菌感染を悪化させる原因になります。また、カイロなどで温める行為も炎症を助長するため避けるべきです。
自己判断で市販の軟膏、特にステロイド系の薬を塗ることも、免疫を抑制して感染を悪化させる可能性があるため危険で、基本的には、清潔と安静を保ち、できるだけ早く専門医の診察を受けることが重要です。
医療機関を受診するタイミング
デリケートゾーンの粉瘤に、痛み、赤み、腫れ、熱感といった炎症のサインが一つでも見られたら、すぐに皮膚科を受診すべきタイミングです。
放置しても良いことは一つもなく、時間が経つほど炎症は強くなり、治療後の傷跡にも影響する可能性があります。痛みが我慢できないほど強い場合や、膿が出てきている場合は、一刻も早く診察を受けましょう。
炎症がない小さな粉瘤の場合でも、大きくなる前や、気になる時点で一度相談することをお勧めします。
皮膚科で行う粉瘤の専門的な治療法
デリケートゾーンの粉瘤は、皮膚科での外科的な処置が唯一の根治治療です。診察の結果、粉瘤と診断された場合、大きさや炎症の有無によって治療法が選択されます。
ここでは、皮膚科で行われる代表的な治療法について、内容や特徴を詳しく解説します。手術と聞くと不安に感じるかもしれませんが、局所麻酔を用いた日帰り手術が基本です。
専門医による正確な診断
まずは、しこりが本当に粉瘤であるか、他の腫瘍の可能性はないかを正確に診断することが治療の第一歩です。
多くの場合は視診と触診で診断可能ですが、非常に大きい場合や深い場所にある場合など、必要に応じて超音波(エコー)検査を行い、しこりの大きさや深さ、内部の性状を確認します。
検査により、より安全で確実な手術計画を立てることができます。デリケートゾーンという部位だからこそ、経験豊富な専門医による的確な診断が大切です。
くりぬき法(へそ抜き法)の詳細
くりぬき法は、比較的小さな粉瘤や、炎症を起こしていない粉瘤に対して行われることが多い手術法です。局所麻酔の後、トレパンという特殊な円筒状のメスを使って、粉瘤の開口部を中心に小さな円形の穴を開けます。
その小さな穴から内容物を絞り出し、しぼんだ袋状の組織を抜き取る方法です。傷口が非常に小さく済むため、術後の回復が早く、傷跡も目立ちにくいという大きな利点があります。
切開法の詳細
切開法は、粉瘤が大きい場合や、過去に炎症を繰り返している場合、または袋が周囲の組織と癒着していることが疑われる場合などに選択される手術法です。
局所麻酔の後、粉瘤の大きさや部位に応じて皮膚を紡錘形に切開し、粉瘤の袋を周囲の組織から丁寧に剥がしながら、袋ごと丸ごと摘出します。袋が破れないように取り除くことで、再発のリスクを最小限に抑えることができます。
摘出後は、皮膚を縫い合わせ、約1週間後に抜糸を行います。
くりぬき法と切開法の比較
| 項目 | くりぬき法 | 切開法 |
|---|---|---|
| 対象 | 小さな粉瘤、炎症がないもの | 大きな粉瘤、炎症を繰り返したもの |
| 傷跡 | 小さい(数ミリ程度) | 切開の長さに応じる(線状の傷) |
| 手術時間 | 短い(5~15分程度) | くりぬき法よりは長い(15~30分程度) |
| 再発率 | 比較的低い | 最も低い |
手術の痛みと麻酔について
手術中の痛みを心配される方が多いですが、どの手術法を選択する場合でも、必ず局所麻酔を行います。注射の際にチクッとした痛みはありますが、麻酔が効いてしまえば手術中に痛みを感じることはほとんどありません。
麻酔の効果は1~2時間程度持続します。手術後は、麻酔が切れると多少の痛みが出ることがありますが、処方される痛み止めで十分にコントロール可能です。
治療後の注意点とセルフケア
手術が無事に終わっても、それで終わりではありません。傷跡をできるだけきれいに治し、再発を防ぐためには、術後のセルフケアが非常に重要です。
デリケートゾーンは、清潔を保ちにくいことや、動きによって傷に負担がかかりやすいことなど、注意すべき点があります。医師の指示をしっかりと守り、適切なケアを心がけましょう。
傷跡をきれいに治すためのポイント
手術後の傷跡は、誰でも気になるものです。傷跡を最小限にするためには、まず傷を濡らさない、汚さないことが基本です。
医師から指示された期間は、ガーゼや保護テープでしっかりと保護します。傷に過度な力がかかると傷口が広がり、跡に残りやすくなるので、デリケートゾーンの場合、足を大きく開く動作や、きつい下着の着用は避けるようにしましょう。
手術後のケアまとめ
| 期間 | 注意点 |
|---|---|
| 手術当日~翌日 | 安静にし、患部を濡らさないようにする |
| ~抜糸まで(約1週間) | 医師の指示に従い、シャワー浴。激しい運動は避ける |
| 抜糸後~ | 傷跡への過度な刺激や紫外線を避ける |
日常生活での注意すること
手術当日は、飲酒や激しい運動、長時間の入浴は避けてください。血行が良くなることで、出血や痛みの原因となります。シャワーは翌日から可能なことが多いですが、患部を強く擦らないように注意が必要です。
仕事や学業への復帰は、手術の内容や体の負担によりますが、デスクワークなどであれば翌日から可能な場合がほとんどです。ただし、体に大きな負担のかかる仕事や運動は、抜糸が済むまで控えてください。
再発を予防するためにできること
手術で粉瘤の袋を完全に取り除けば、同じ場所に再発することはほとんどありませんが、粉瘤ができやすい体質は変わらないため、別の場所に新たな粉瘤ができる可能性はあります。
再発を予防するためには、デリケートゾーンを常に清潔に保つことが基本です。通気性の良い綿素材の下着を選び、汗をかいたらこまめに拭き取るなど、蒸れない工夫をしましょう。
また、バランスの取れた食事や十分な睡眠を心がけ、皮膚のターンオーバーを正常に保つことも大切です。
再発予防のための生活習慣
- デリケートゾーンの清潔保持
- 通気性の良い下着の着用
- バランスの取れた食事
- 十分な睡眠時間の確保
- ストレス管理
デリケートゾーンの粉瘤に関するよくある質問
最後に、患者さんから特によくいただく質問と回答をまとめました。治療に関する不安や疑問の解消にお役立てください。
- 治療は保険適用になりますか?
-
はい、粉瘤の診断および手術は、健康保険が適用される治療です。炎症を起こしている場合の切開排膿処置も同様に保険適用となります。ただし、手術の方法や粉瘤の大きさ、部位によって費用は異なります。
保険適用と自費診療
治療内容 保険適用 備考 診察・検査 適用 初診料、再診料、超音波検査料など 炎症性粉瘤の切開排膿 適用 膿を出す応急処置。後日、袋の摘出が必要 粉瘤摘出手術(くりぬき法・切開法) 適用 露出部か非露出部か、大きさで費用が変動 - 手術後の痛みはどのくらい続きますか?
-
手術後の痛みには個人差がありますが、多くの場合、手術当日から翌日にかけてが痛みのピークです。この期間は処方された痛み止めを服用することで、十分に痛みをコントロールできます。
通常、2~3日もすれば、痛みはかなり和らいでいきます。もし痛みが長引いたり、日に日に強くなったりするような場合は、感染などの可能性も考えられるため、すぐにクリニックに連絡してください。
- 手術当日から入浴はできますか?
-
手術当日は、湯船に浸かる入浴は避けていただく必要があります。傷口が温まることで出血のリスクが高まるためです。
シャワーについては、患部を濡らさなければ当日から可能な場合もありますが、安全のため翌日からとするのが一般的で、湯船に浸かれるようになるのは、通常、抜糸が終わってからです。
- パートナーにうつることはありますか?
-
粉瘤は、皮膚の中に袋ができて老廃物が溜まるという、ご自身の体の内部の問題で発生するものです。ウイルスや細菌による感染症ではないため、人にうつることは一切ありません。
性的な接触を含め、他者へ感染する心配は全くないので、その点はご安心ください。
以上
参考文献
Ohta H, Hatta M, Ota K, Yoshikata R, Salvatore S. Online survey of genital and urinary symptoms among Japanese women aged between 40 and 90 years. Climacteric. 2020 Nov 1;23(6):603-7.
Ueda Y, Mandai M, Matsumura N, Baba T, Suzuki A, Yoshioka Y, Kosaka K, Konishi I. Adenoid cystic carcinoma of Skene glands: a rare origin in the female genital tract and the characteristic clinical course. International journal of gynecological pathology. 2012 Nov 1;31(6):596-600.
Suwa M, Takeda M, Bilim V, Takahashi K. Epidermoid cyst of the penis: a case report and review of the literature. International journal of urology. 2000 Nov;7(11):431-3.
Shibuki S, Saida T, Hoshiai S, Ishiguro T, Sakai M, Amano T, Abe T, Yoshida M, Mori K, Nakajima T. Imaging findings in inflammatory disease of the genital organs. Japanese journal of radiology. 2024 Apr;42(4):331-46.
Yoong WC, Shakya R, Sanders BT, Lind J. Clitoral inclusion cyst: a complication of type I female genital mutilation. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2004 Jan 1;24(1):98-9.
Shebel HM, Farg HM, Kolokythas O, El-Diasty T. Cysts of the lower male genitourinary tract: embryologic and anatomic considerations and differential diagnosis. Radiographics. 2013 Jul;33(4):1125-43.
Toy H. Female genıtal tract cysts. European Journal of General Medicine. 2012 Jan 10;9(12):21-6.
Aldrich ER, Pauls RN. Benign cysts of the vulva and vagina: a comprehensive review for the gynecologic surgeon. Obstetrical & Gynecological Survey. 2021 Feb 1;76(2):101-7.
Lund AJ, Cummings MM. Cyst of the accessory genital tract: a case report with a review of the literature. The Journal of Urology. 1946 Sep;56(3):383-6.
Costa C, Barba M, Cola A, Frigerio M. Paraclitoral Epidermal Cysts: A Literature Systematic Review. Medicina. 2025 Mar 17;61(3):520.