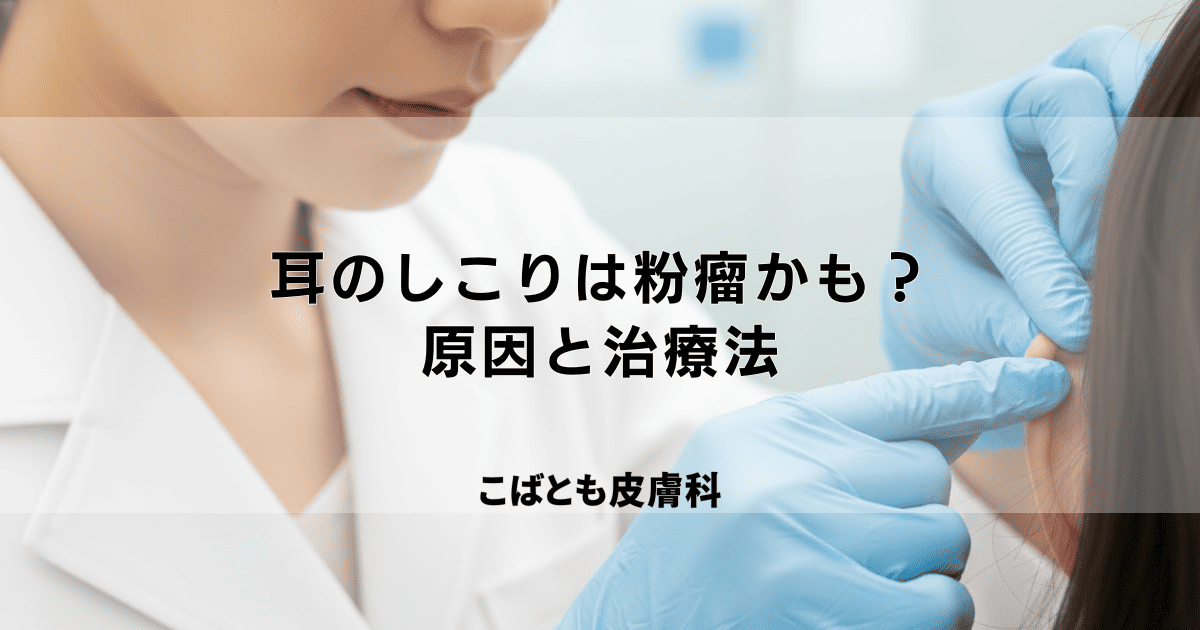ある日、ふと耳たぶや耳の後ろを触ったときに、コリっとした小さなしこりを見つけた経験はありませんか。
しこりの正体は、皮膚のできものの一種である粉瘤(ふんりゅう)、別名アテロームの可能性があります。粉瘤は良性の腫瘍ですが、放置すると徐々に大きくなったり、ある日突然、炎症を起こして痛みや腫れを起こします。
この記事では、耳にできるしこりの正体である粉瘤の基本的な知識から、原因、放置した場合のリスク、皮膚科で行う治療法について、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
耳のしこりの正体は?粉瘤(アテローム)の基礎知識
耳にできるしこりと聞くと、何か悪いものではないかと心配になるかもしれませんが、多くは粉瘤と呼ばれる良性の皮膚腫瘍です。粉瘤は決して珍しいものではなく、皮膚科の診療で日常的に目にする疾患の一つです。
粉瘤とは皮膚の下にできる袋状の構造物
粉瘤は、専門用語で類表皮嚢胞(るいひょうひのうほう)とも呼ばれ、皮膚の下に袋状の構造(嚢胞)ができてしまうことで発生し、皮膚の一番外側にある表皮とよく似た組織でできています。
通常、表皮の細胞は新陳代謝(ターンオーバー)によって、最終的に垢(角質)となって剥がれ落ちていきます。
しかし、粉瘤の袋の中でも同じように細胞が角質を作り続けるため、出口のない袋の中に角質や皮脂といった老廃物がどんどん溜まっていきます。この蓄積した内容物によって、皮膚がドーム状に盛り上がり、しこりとして触れるようになるのです。
大きさは数ミリの小さなものから、時には10センチを超えるほど巨大になることもあります。
体のどこにでもできる可能性がありますが、特に顔、首、背中、耳たぶや耳の後ろといった、皮脂を分泌する毛穴(皮脂腺)が多い場所にできやすい傾向があります。
袋が皮膚表面と細いトンネルで繋がっている場合、出口が中心部に小さな黒い点(開口部)として見えることがあります。これはコメド(面皰)とも呼ばれ、粉瘤を見分ける上での重要なサインの一つです。
開口部から細菌が侵入すると、炎症を起こす原因にもなります。
粉瘤の主な特徴
| 特徴 | 詳細 | 注意点 |
|---|---|---|
| 形状 | 皮膚がなだらかに盛り上がった半球状のしこり | 大きさは個人差が大きく、時間と共に増大する傾向がある |
| 感触 | 指で押すと少し硬いゴムのような弾力がある。皮膚と癒着している | 炎症を起こすと硬くなり、強い痛みを伴うようになる |
| 中央の開口部 | 「へそ」とも呼ばれる黒い点が見えることがある | 開口部がない、または非常に小さい粉瘤も多い |
内容物の正体と特有の臭い
粉瘤の袋の中に溜まっているのは、前述の通り、人間の垢(角質)と皮脂が混じり合ったものです。もし何かの拍子でしこりが強く圧迫されると、開口部からドロドロとした、お粥やチーズのような白から黄色の物質が出てくることがあります。
内容物は、時間の経過とともに袋の中で熟成・腐敗するため、独特の強い腐敗臭、酸っぱいような不快な臭いを放ちます。臭いが気になって、自分で無理やり内容物を押し出そうとする方がいますが、非常に危険な行為です。
袋が皮膚の下で破れて内容物が周囲に漏れ出すと、体が異物と認識し、激しい炎症を起こす原因になります。臭いが気になる場合でも、決して自分で潰したりせず、皮膚科を受診してください。
良性腫瘍であり、がん化することはまれ
粉瘤は良性の腫瘍であり、命に関わるような悪性のできものに変化(がん化)することは非常にまれなので、基本的には慌てる必要はありません。
しかし、頻度は極めて低いものの、長年放置された巨大な粉瘤や、炎症を何度も繰り返している粉瘤から、有棘細胞がん(ゆうきょくさいぼうがん)という皮膚がんが発生したという報告もあります。
もし、しこりが急激に大きくなってきた、表面がジュクジュクしてきて治らない、簡単に出血を繰り返すといった、通常とは異なる変化が見られる場合は、注意が必要です。
多くの場合、見た目の問題や炎症による痛み、日常生活での不便さなどが治療のきっかけとなります。しこりに気づいたら、まずは自己判断せずに皮膚科を受診し、正確な診断を受けることが何よりも大切です。
なぜ耳に粉瘤ができるのか?主な原因と発生しやすい場所
全身のどこにでもできる可能性がある粉瘤ですが、なぜ特に耳たぶや耳の後ろにできやすいのでしょうか。理由を理解するためには、皮膚の基本的な構造と、粉瘤が発生するに至るいくつかのきっかけを知ることが助けになります。
皮膚の生まれ変わりと粉瘤の成り立ち
皮膚は、絶えず新しい細胞が生まれ、古い細胞が剥がれ落ちるというサイクル(ターンオーバー)を繰り返すことで、健康を保っていますが、何らかの理由でこの正常な排出経路が妨げられると、粉瘤が形成されるきっかけとなります。
最も一般的な原因は、毛穴の出口付近が詰まることです。皮脂や汚れによって毛穴が塞がれると、奥で皮膚の一部が内側にめくれ込むようにして袋状の構造を形成してしまうことがあります。
また、ニキビ跡や、ピアスの穴を開けた際の小さな傷、手術の縫合跡など、皮膚への何らかの外傷が原因で、表皮の細胞が皮膚の深い部分(真皮)に入り込んでしまい、そこで増殖して袋を作ることもあります。
一度袋ができてしまうと、その中でターンオーバーは続くため、行き場を失った角質や皮脂が袋の中にどんどん蓄積し、時間とともに大きなしこり、つまり粉瘤へと成長していくのです。
粉瘤が発生する主なきっかけ
| きっかけ | 概要 | 関連部位 |
|---|---|---|
| 毛穴の詰まり | 過剰な皮脂分泌や古い角質によって毛穴の出口が塞がれる | 顔、背中、胸、耳など |
| 小さな外傷 | 切り傷、擦り傷、ニキビ跡、虫刺されの掻き壊しなど | 全身のあらゆる部位 |
| ピアスの穴 | ピアッシングの際に表皮細胞が真皮内に入り込むことが原因 | 耳たぶ、耳の軟骨部 |
耳たぶや耳の裏側にできやすい理由
耳、特に耳たぶや耳介後部(耳の後ろの付け根)は、皮脂を分泌する皮脂腺が比較的多く存在する部位で、他の部位に比べて毛穴が詰まりやすく、粉瘤の発生につながりやすい環境です。
また、ピアスの穴が粉瘤の直接的な原因となることもあり、ピアッシングによる刺激が、表皮の成分を皮膚の内部に迷入させ、粉瘤を形成します。
さらに、耳の後ろは自分では見えにくく、シャンプーのすすぎ残しや汗が溜まりやすいにもかかわらず、意識して丁寧に洗うことが少ない場所でもあり、不衛生な状態が毛穴の詰まりを助長し、粉瘤発生の一因となっている可能性も考えられます。
体質や生活習慣が関与することも
粉瘤の発生には明確な原因が特定できないことも多く、遺伝的な要因や体質的にできやすい人もいると考えられています。
また、不規則な生活や慢性的な睡眠不足、精神的なストレス、偏った食生活などは、ホルモンバランスの乱れや皮膚のターンオーバーサイクルの異常を招きます。
このような要因が、間接的に皮脂の過剰分泌や毛穴の詰まりやすい状態を作り出し、粉瘤の発生リスクを高める可能性も指摘されていますが、生活習慣と粉瘤発生の直接的な因果関係は、まだ完全には解明されていません。
粉瘤は年齢や性別を問わず、誰にでもできる可能性がある、ごくありふれた皮膚のできものです。
ターンオーバーに影響を与える可能性のあるもの
- 睡眠不足
- 栄養バランスの偏り(特に脂質や糖質の過剰摂取)
- 精神的なストレス
- 過度な紫外線
- 不適切なスキンケア(洗浄不足または過剰な洗浄)
粉瘤とニキビはどう違う?見分けるポイント
特に耳にできる小さなしこりは、ニキビと間違えられやすいものですが、粉瘤とニキビは発生の原因も構造も全く異なるため、対処法も変わってきます。
発生原因と構造の違い
ニキビは、毛穴に皮脂が詰まり、そこでアクネ菌が増殖して炎症を起こす疾患で、毛穴の病気であり、一時的なものです。一方、粉瘤は皮膚の下に袋状の構造物(嚢胞)ができてしまうことが原因です。
ニキビのように一時的な炎症ではなく、袋がある限り、自然に消えてなくなることはありません。「袋の有無」が両者を分ける根本的な違いです。
見た目や大きさの変化
ニキビは初期段階では白ニキビや黒ニキビとして現れ、炎症を起こすと赤ニキビ、化膿すると黄ニキビへと変化し、大きさは数ミリ程度がほとんどです。
対して粉瘤は、初期はニキビと見分けがつきにくいこともありますが、時間とともに数センチ、時にはそれ以上にまでゆっくりと大きくなる傾向があります。
また、粉瘤特有のサインとして、しこりの中央に黒い点(開口部)が見られることがあります。
粉瘤とニキビの主な違い
| 項目 | 粉瘤(アテローム) | ニキビ(尋常性ざ瘡) |
|---|---|---|
| 原因 | 皮膚の下にできた袋への老廃物の蓄積 | 毛穴の詰まりとアクネ菌の増殖 |
| 大きさ | 数ミリ~10cm以上になることも。徐々に増大する | 通常は数ミリ程度 |
| 臭い | 内容物が排出されると強い悪臭がある | 通常、強い臭いはない |
内容物と治り方
ニキビを潰すと、膿や皮脂の塊(コメド)が出てきます。適切なケアをすれば、多くは数日から数週間で治癒し、跡形もなく消えることもあります。
しかし粉瘤を潰すと、独特の悪臭を放つ粥状の物質が出てきて、内容物をすべて出したとしても、原因である袋が皮膚の下に残っているため、必ず再発します。
自分で潰すことで炎症を悪化させるリスクもあるため、ニキビか粉瘤か判断がつかない場合は、むやみに触らずに皮膚科を受診してください。
耳の粉瘤を放置する危険性 炎症や感染のリスク
痛みがなく、ただそこにあるだけの小さなしこりだと、「そのうち治るだろう」とつい放置してしまうこともあるでしょう。しかし、耳の粉瘤をそのままにしておくと、様々な厄介なトラブルを引き起こす可能性があります。
注意が必要なのは、粉瘤が細菌感染を起こして痛みや腫れを伴う状態、炎症性粉瘤です。
炎症性粉瘤とはどのような状態か
炎症性粉瘤とは、粉瘤の袋の中に細菌が侵入し、免疫反応によって急性の炎症が起こった状態です。
粉瘤の開口部から皮膚の常在菌であるブドウ球菌などが侵入したり、自分で潰そうとしたり、何かにぶつけたりする刺激で袋が破れたりすることがきっかけとなります。
炎症を起こすと、それまで痛みのなかったしこりが数日のうちに急激に赤く腫れ上がり、熱感を持ち、脈打つようなズキズキとした強い痛みを伴うようになります。
痛みで夜も眠れなくなったり、耳の違和感で日常生活に集中できなくなったりすることも珍しくありません。
炎症性粉瘤の主な症状
| 症状 | 状態 | 対処 |
|---|---|---|
| 発赤 | しこりを中心に周囲の皮膚が赤くなる | すぐに皮膚科を受診することが望ましい |
| 腫脹 | しこりが短期間で倍以上に大きく腫れあがる | 患部を冷やすことで一時的に症状が和らぐ場合がある |
| 疼痛 | 触れるだけでも痛い、あるいは何もしなくてもズキズキと痛む | 自己判断で潰さず、医師の診察を受ける |
巨大化して整容的な問題が生じることも
炎症を起こさなくても、粉瘤は袋の中に老廃物を溜め込み続けるため、放置すれば年月をかけて少しずつ大きくなります。耳たぶや耳の軟骨の近くにできた粉瘤が大きくなると、見た目がこぶのように目立ってしまい、整容的な問題となります。
また、イヤホンがしにくくなったり、睡眠時に枕に当たって気になったり、マスクの紐が擦れて痛んだりするなど、日常生活における物理的な支障が生じることがあります。
耳は人目につきやすい場所のため、しこりが小さいうちに治療する方が、手術の傷跡も小さく済み、身体的・精神的な負担も軽いです。
袋が破れると強い炎症や膿だまりに
炎症がさらに進行すると、パンパンに腫れ上がった粉瘤の袋が、皮膚の下でついに破裂することがあり、袋の内容物である大量の角質や皮脂が、異物として周囲の組織に一気に漏れ出します。
体はこれを敵とみなし、激しい異物反応性の炎症を起こし、皮膚の下に膿が大量に溜まり、表面がブヨブヨとした波動を触れる状態(膿瘍形成)になることもあります。
この状態になると、非常に強い痛みや高熱を伴うこともあり、一刻も早く皮膚を切開して膿を排出する処置が必要になります。ここまで悪化すると、治療期間が長引くだけでなく、最終的に残る傷跡も大きくなってしまう可能性が高いです。
炎症を悪化させる行為
- 自分で潰して内容物を無理やり押し出す
- 安全でない針などで穿刺する
- 気になって頻繁にしこりを触る、揉む
- 痛みや腫れがあるのに放置して様子を見る
粉瘤と間違えやすい他の耳のしこり
耳にできるしこりは、すべてが粉瘤というわけではなく、中には、異なる原因で発生する別の種類のしこりもあります。治療法が異なるため、正確に鑑別することが非常に重要です。
脂肪腫(リポーマ)
脂肪腫は、成熟した脂肪細胞が増殖してできる、最も一般的な良性の軟部組織腫瘍で、粉瘤としばしば混同されますが、いくつかの違いがあります。
脂肪腫は粉瘤よりも皮膚の深い部分(皮下組織)に発生し、触れると消しゴムのように非常に柔らかく、指で押すと皮膚の下で動く感じがするのが特徴です。粉瘤のような中心の開口部はなく、皮膚の表面の色も通常は変わりません。
ゆっくりと大きくなることがありますが、炎症を起こして痛むことはまれで、耳たぶよりも、耳の後ろの首に近い部分など、脂肪の多い部位にできやすい傾向があります。
石灰化上皮腫(毛母腫)
石灰化上皮腫は、毛を産生する細胞(毛母細胞)から発生する良性の皮膚腫瘍で、10代までの子供や若い人の顔、首、腕にできやすいとされ、最大の特徴は硬さです。
触れると石や骨片のようにゴツゴツと硬い塊として感じられ、粉瘤の弾力のある感触とは明らかに異なり、皮膚の上からしこりが青黒く透けて見えることもあります。
通常、痛みはありませんが、診断を確定するためには、摘出して病理組織検査を行うことが一般的です。
粉瘤と他のしこりの比較
| 種類 | 硬さ | 中心の開口部 | 炎症の起こしやすさ |
|---|---|---|---|
| 粉瘤(アテローム) | 弾力のある硬さ | あることが多い | 比較的高い |
| 脂肪腫 | 非常に柔らかい | ない | まれ |
| 石灰化上皮腫 | 石のように硬い | ない | まれ |
その他の腫瘍やリンパ節の腫れ
その他にも、耳の周囲には様々な腫瘍ができる可能性があります。耳の軟骨に傷ができた後などに発生する硬いしこりであるケロイド、ウイルス感染によるイボ(尋常性疣贅)、血管の増殖による血管腫などです。
また、耳の後ろや下のしこりが、風邪や中耳炎などの感染症に伴う反応性のリンパ節の腫れである場合もあります。この場合、通常は圧痛を伴い、原因となる感染症が治癒するとともにしこりも自然に小さくなっていきます。
皮膚科での粉瘤診断の流れ
耳にしこりを見つけたら、まずは自己判断で悩まずに皮膚科を受診しましょう。専門医は、しこりの状態を詳しく観察し、必要に応じて検査を行うことで、それが粉瘤なのか、それとも他の疾患なのかを正確に診断します。
問診で症状の経過などを確認
まず医師が患者さんから詳しい話を聞きます。
いつからしこりに気づいたか、それからの大きさや色に変化はあるか、痛みやかゆみ、熱感といった自覚症状はあるか、過去にその場所を怪我したり、ピアスを開けたりした経験はあるかなど、が正確な診断を下すための重要な手がかりとなります。
このとき、気になっていることや不安な点を遠慮なく医師に伝えることが、信頼関係を築き、安心して治療に進むために大切です。
医師に伝えると良い情報
- しこりに気づいた正確な時期
- 大きさや色の具体的な変化(例:1ヶ月で倍になった)
- 痛み、赤み、熱感の有無とその程度
- 過去のケガやピアスの経験の有無
- 現在治療中の病気や服用中の薬(特に血液をサラサラにする薬など)
視診と触診による診察
問診の後は、医師が実際にしこりを見て、触って状態を物理的に確認します。視診では、しこりの大きさ、形状、皮膚表面の色調の変化、粉瘤に特徴的な中心の開口部(へそ)の有無などを注意深く観察します。
次に触診で、しこりの硬さ(硬いか柔らかいか)、可動性(指で押したときに動くか、周囲の組織と固着しているか)、圧痛(押したときの痛みの有無)などを評価します。
超音波(エコー)検査で内部を詳しく調査
診断をより確実にするため、また、しこりの詳細な情報を得るために、超音波(エコー)検査を行うことが一般的です。
超音波検査により、皮膚の上からではわからない、しこりの正確な大きさや深さ、内部の性状(内容物がドロドロか、均一かなど)が明瞭にわかり、典型的な粉瘤は、境界がはっきりした袋状の構造物として黒く映し出されます。
超音波検査でわかること
| 項目 | 詳細 | 診断・治療への貢献 |
|---|---|---|
| 大きさ・深さ | しこりの正確な3次元的なサイズと皮膚表面からの深さを測定する | 手術方法の選択(くり抜き法か切開法か)や切開範囲の決定に役立つ |
| 内部の性状 | 内容物が液体か固体か、均一か不均一かなどを詳細に評価する | 粉瘤に特徴的な画像所見を確認し、診断の確度を高める |
| 周囲との関係 | 重要な血管や神経、耳の軟骨など、周囲の組織との位置関係を把握する | 手術をより安全かつ確実に行うための重要な情報となる |
耳の粉瘤に対する皮膚科での治療法
粉瘤の根本的な治療法は、原因となっている袋を完全に取り除く外科手術しかありません。薬で小さくしたり、消し去ったりすることは不可能です。
根本治療は袋ごと取り除く外科手術
粉瘤は、内容物を一時的に排出するだけでは、必ず再発します。原因である袋(嚢胞壁)が皮膚の下に残っている限り、その中で再び角質や皮脂が産生され、溜まり始めるからです。
イタチごっこを終わらせ、根本的に治すためには、局所麻酔を行った上で、この袋を残さずきれいに取り除く手術が必要です。
手術と聞くと大げさに感じ、不安になるかもしれませんが、ほとんどの場合は外来で、日帰りで行うことが可能な、比較的身体への負担が少ない処置で、通常10分から30分程度で終了します。
くり抜き法(へそ抜き法)による低侵襲手術
近年、多くの施設で積極的に行われているのが、くり抜き法(へそ抜き法)と呼ばれる低侵襲な手術方法です。
トレパンという特殊な円筒状のメス(パンチ)を使い、粉瘤の中心の開口部(へそ)を含むように、直径2~5ミリ程度の小さな円形の穴を開けます。
その小さな穴から、まず内容物を揉み出し、袋を空っぽにし、小さくしぼんだ袋そのものを、ピンセットなどで引き抜きます。
この方法の最大の利点は、皮膚の切開が最小限で済むため、傷跡が非常に小さく、丸いニキビ跡のようになることで、耳のような目立つ場所の粉瘤には特に適しています。手術時間が短く、術後の痛みや出血が少ないのもメリットです。
手術方法の比較
| 手術方法 | 傷跡の大きさ | 手術時間(目安) | メリット |
|---|---|---|---|
| くり抜き法 | 小さい(数ミリの円形) | 5分~15分程度 | 傷が小さく目立ちにくい、身体への負担が少ない |
| 切開法 | 粉瘤の大きさに応じた線状 | 15分~30分程度 | 大きな粉瘤や癒着が強い場合に確実に取り除ける |
炎症が強い場合の治療
すでに赤く腫れて強い痛みを伴う炎症性粉瘤の場合は、原則として、その日のうちに袋を取り除く根治手術は行えません。
なぜなら、炎症が強い組織は麻酔が効きにくく痛みを伴いやすい上に、袋自体がもろくなっていて、少し触るだけですぐに破れてしまうからです。
この状態で無理に手術をしても、袋を完全に取り除くことは難しく、かえって炎症を広げてしまうリスクがあるので、まず応急処置として皮膚を少しだけ切開し、中に溜まった膿を外に排出させる処置(切開排膿)を優先します。
処置により内圧が下がるため、痛みや腫れは劇的に改善します。抗生物質の内服などを併用しながら炎症が完全に治まるのを待ち、通常は1~3ヶ月後に、改めて袋を取り除くための根治手術を計画します。
治療後の注意点とセルフケア
手術が無事に終わっても、それで治療が完了したわけではありません。傷口が問題なくきれいに治癒するためには、術後の数週間、いくつかの注意点を守って生活することが大切です。
手術当日の過ごし方
手術当日は、局所麻酔の影響が数時間残っていますが、麻酔が切れると多少の痛みを感じることがあるため、痛み止めを処方します。痛みが強くなる前に服用するのが効果的です。
血行が良くなると、出血や痛みの原因になることがあるため、手術当日は飲酒、激しい運動、長時間の入浴は避けて、できるだけ安静に過ごしてください。
シャワーは、傷口を濡らさないように保護すれば、首から下であれば当日から可能な場合が多いですが、必ず医師の指示に従ってください。食事は通常通りで問題ありません。
傷口のケアと通院
通常、手術の翌日または数日後に、傷口の状態を確認するために再診が必要です。医師が感染の兆候などがないかを確認し、問題がなければ、自宅での処置方法について説明します。
シャワーを浴びる際に、石鹸をよく泡立てて傷口を優しく洗浄し、シャワーでしっかり洗い流し、その後、清潔なタオルで水分をそっと拭き取り、処方された軟膏を塗って新しいガーゼや絆創膏で保護します。
傷口を清潔に保つことが、感染を防ぐ上で最も重要で、皮膚を縫合した場合は、手術から約1週間後に抜糸のために再度通院が必要です。くり抜き法で縫合しなかった場合は、傷が自然に閉じるのを待ちます。
術後の一般的な経過
| 時期 | 状態 | 主なケア |
|---|---|---|
| 手術当日~翌日 | 麻酔が切れると多少の痛み。少量の出血が見られることも。 | 安静にし、処方された抗生剤・痛み止めを服用する。 |
| 術後2日~1週間 | 痛みは次第に和らぎ、傷口からの浸出液も減る。 | 医師の指示通りに、自宅で傷の洗浄・消毒・保護を行う。 |
| 術後1週間~ | 抜糸(必要な場合)。傷は上皮化し、徐々に安定してくる。 | 傷跡の保護(遮光テープなど)を継続することが推奨される。 |
再発の可能性と予防
手術で粉瘤の袋をきれいに完全に取り除くことができれば、同じ場所に粉瘤が再発することは基本的にありません。
しかし、非常にまれですが、炎症が強かった場合などに、目に見えないほど小さな袋の一部が残存し、数年後にそこから再発する可能性もあります。
また、粉瘤ができやすい体質の場合、耳の別の場所や他の部位に、新たな粉瘤ができることは十分にあり得ます。
日頃から皮膚を清潔に保つこと、バランスの取れた食事や十分な睡眠を心がけ、皮膚のターンオーバーを正常に保つことが、皮膚全体の健康を維持し、新たな粉瘤のリスクを減らす上でも大切です。
耳のしこりに関するよくある質問
最後に、患者さんからよく寄せられる耳の粉瘤に関する質問と回答をまとめました。
- 粉瘤は自分で潰してもいいですか?
-
自分で無理に潰すと、皮膚の下で袋が破裂し、内容物が周囲の組織に散らばって激しい異物反応性の炎症を起こす可能性が非常に高いです。
また、指や爪についた細菌が傷口から入り込み、感染を悪化させるリスクもあり、そのため治療がより複雑になり、痛みも長引き、最終的に残る傷跡も汚くなってしまうことにつながります。
しこりが気になっても決して触らず、まずは皮膚科専門医に相談してください。
- 手術は痛いですか?麻酔はしますか?
-
手術は必ず局所麻酔を行ってから開始します。麻酔の注射をする際に、細い針を使用しチクッとした痛みはありますが、一度麻酔がしっかりと効いてしまえば、手術中の痛みはほとんど感じることはありません。
もし手術中に痛みを感じるようなことがあれば、麻酔を追加しますので、遠慮なく医師に伝えてください。痛みに弱い方でも安心して治療を受けられるよう配慮します。
手術後に麻酔が切れると少しジンジンとした痛みが出ることがありますが、処方される痛み止めを服用すれば十分にコントロール可能です。
- 手術後の傷跡は目立ちますか?
-
傷跡の大きさや目立ちやすさは、元の粉瘤の大きさ、手術方法、個人の体質(ケロイド体質など)によって変わります。
一般的に、「くり抜き法」は、従来の切開法に比べて傷跡が小さく、ニキビ跡のように治ることが多いため、特に耳のような目立つ部位では良い適応です。
手術後の傷は、最初は赤みを帯びていますが、数ヶ月から1年ほどかけて徐々に白く、平坦になり、目立ちにくくなっていきます。
術後に紫外線対策や保湿、傷跡用の保護テープを使用するなど、適切なアフターケアを行うことで、よりきれいな傷跡を目指すことができます。
- 手術にかかる費用はどのくらいですか?
-
粉瘤(皮膚良性腫瘍)の摘出手術は、病気の治療と見なされるため、健康保険が適用されます。費用は、粉瘤の大きさ(長径)と、手術する場所(露出部か非露出部か)によって公的に定められています。
耳は衣服で隠れない「露出部」にあたり、3割負担の場合、手術費用自体はおおよそ5,000円から15,000円程度が目安です。
加えて、初診料や再診料、処方箋料、薬剤費、摘出した腫瘍を詳しく調べる病理組織検査を行う場合は、費用が別途必要になります。
以上
参考文献
Ueno T, Takayama R, Osada SI, Saeki H. Epidermoid cyst arising on the body of the tongue: case report and literature review. Journal of Nippon Medical School. 2018 Dec 10;85(6):343-6.
Egawa T, Morioka D, Zhang Z, Minohara S, Kadomatsu K. Association of congenital ear deformities with dermoid cysts of the auricle. European Journal of Plastic Surgery. 2020 Oct;43(5):557-62.
Kodama H, Maeda M, Hirokawa Y, Suzuki H, Hori K, Taki W, Takeda K. MRI findings of malignant transformation of epidermoid cyst: case report. Journal of neuro-oncology. 2007 Apr;82(2):171-4.
Dive AM, Khandekar S, Moharil R, Deshmukh S. Epidermoid cyst of the outer ear: A case report and review of literature. Indian Journal of Otology. 2012 Jan 1;18(1):34-7.
Cho Y, Lee DH. Clinical characteristics of idiopathic epidermoid and dermoid cysts of the ear. Journal of audiology & otology. 2017 Jul 5;21(2):77.
Trinh CT, Nguyen CH, Chansomphou V, Chansomphou V, Tran TT. Overview of epidermoid cyst. European journal of radiology open. 2019 Jan 1;6:291-301.
Kim GW, Park JH, Kwon OJ, Kim DH, Kim CW. Clinical characteristics of epidermoid cysts of the external auditory canal. Journal of Audiology & Otology. 2016 Apr 21;20(1):36.
Abdel-Aziz M. Epidermoid cyst of the external auditory canal in children: diagnosis and management. Journal of Craniofacial Surgery. 2011 Jul 1;22(4):1398-400.
Shabbir A, Loss L, Bogner P, Zeitouni NC. Squamous cell carcinoma developing from an epidermoid cyst of the ear. Dermatologic surgery. 2011 May 1;37(5):700-3.
Karmacharya S, Sah SK, Adhikari S. Epidermoid cyst of the ear lobule in adult. Kathmandu University Medical Journal. 2021 Dec 31;19(4):531-3.