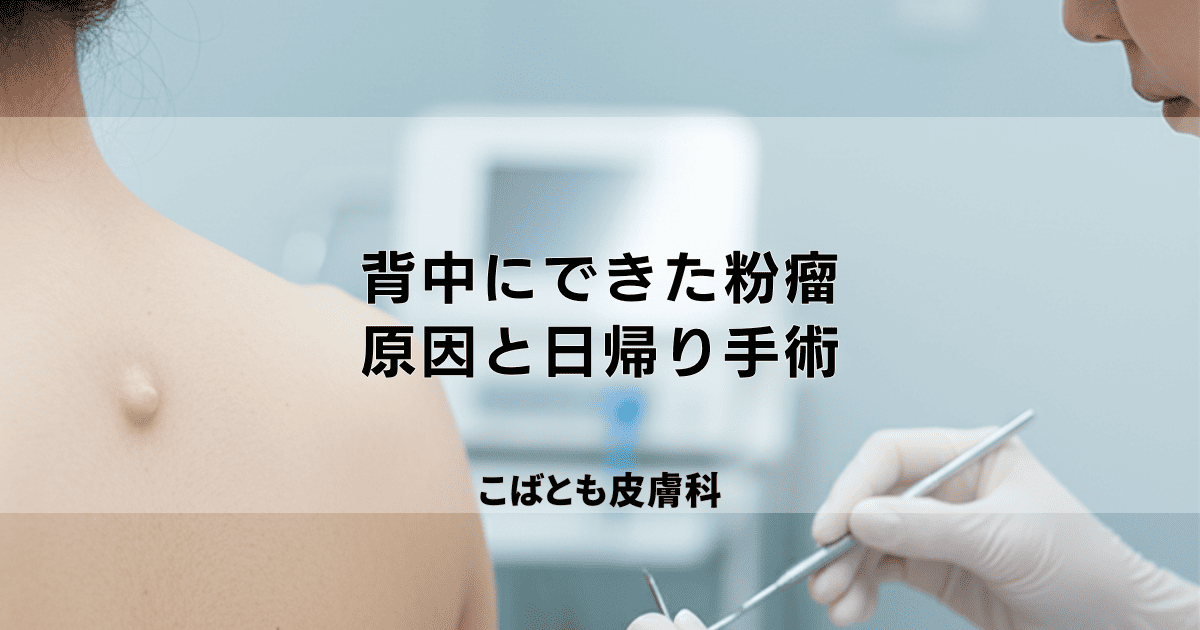背中に、いつの間にかポツンとできものができていることに気づいた経験はありませんか。最初は小さくて気にならなかったものが、少しずつ大きくなったり、ある日突然痛みだしたりすると、何か悪いものではないかと不安になるでしょう。
しこりの正体は、粉瘤(ふんりゅう)かもしれません。粉瘤はアテロームとも呼ばれる良性の皮膚腫瘍ですが、放置すると炎症を起こして生活に支障をきたすこともあります。
この記事では、背中にできるしこりの代表格である粉瘤とは何か、原因、症状、皮膚科で行われる手術について、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
背中のしこり、もしかして粉瘤かもしれません
ふと背中に触れた時に感じる小さな膨らみ。多くの人が一度は経験するかもしれないこの違和感の正体について、まずは基本的なところから見ていきましょう。
多くの人が経験する背中の異変
背中の皮膚の下にできるしこりは、決して珍しい症状ではなく、年齢や性別を問わず、誰にでもできる可能性があります。多くの場合、痛みやかゆみといった自覚症状がないまま、ある程度の大きさになるまで気づかれないことも少なくありません。
入浴中に体を洗っていて偶然発見したり、家族やパートナーに指摘されて初めて認識したりするケースがほとんどです。
最初はニキビのような小さなものだと考えていたものが、治らずに残り続け、徐々に大きくなることで、ようやく皮膚の異常として意識し始めます。
しこりの正体、粉瘤とは何か
粉瘤は、皮膚の下に袋状の構造物(嚢腫)ができ、その中に本来であれば皮膚から剥がれ落ちるはずの垢(角質)や皮脂が溜まっていくことで形成される、良性の腫瘍で、皮膚腫瘍の中では最も頻繁に見られるものの一つです。
袋の壁は表皮と同じ構造をしており、そこから毎日少しずつ垢が作られて袋の中に溜まっていくため、時間とともにゆっくりと大きくなる性質があります。体のどこにでもできる可能性がありますが、特に背中は好発部位です。
粉瘤のできやすい主な部位
| 部位 | 特徴 | できやすい理由 |
|---|---|---|
| 背中 | 皮脂腺が多く、自分での確認が難しい | 衣類との摩擦や蒸れが起きやすい |
| 顔・首 | 目立ちやすく、美容的な問題になりやすい | 毛穴が多く、皮脂の分泌が活発 |
| 耳の後ろ | 比較的小さなものができやすい | 皮脂が溜まりやすく、不衛生になりがち |
なぜ背中にできやすいのか
粉瘤が特に背中に多く見られるのには、いくつかの理由が考えられ、まず、背中は皮脂を分泌する皮脂腺が比較的多くある部位です。皮脂の分泌が活発であることは、毛穴の詰まりを起こしやすく、粉瘤の発生につながることがあります。
また、衣類との摩擦も一因です。常に衣服に覆われている背中は、摩擦による刺激を受けやすく、皮膚のターンオーバーが乱れたり、毛穴周辺の皮膚が傷ついたりすることが、粉瘤形成のきっかけとなり得ます。
さらに、汗をかきやすく蒸れやすい環境であることも、細菌の繁殖を促し、毛穴のトラブルを招きやすい状況を作ります。
粉瘤の正体と特徴を詳しく解説
背中にできたしこりが粉瘤かもしれない、と思っても、どのような特徴があるのか分からなければ判断がつきません。ここでは、粉瘤の構造から見た目、炎症を起こした際のサインまで、特徴を説明します。
皮膚の下にできる袋状の構造物
粉瘤の本質は、皮膚の内部にできてしまった袋、すなわち嚢腫(のうしゅ)です。本来、私たちの皮膚は、古くなった角質を垢として体外へ排出し、新しい細胞へと生まれ変わるターンオーバーを繰り返しています。
しかし、何らかの原因で皮膚の一部が内側に向かってめり込み、袋状の構造を形成してしまうことがあり、袋の内壁も皮膚の表面(表皮)と同じ性質を持っているため、内部に向かって角質や皮脂を排出し続けます。
出口のない袋の中に老廃物が溜まり続けることで、しこりとして皮膚の表面を盛り上げていく、これが粉瘤の成り立ちです。袋そのものを取り除かない限り、中身を一時的に排出しても再発するのは、このためです。
粉瘤の中身は何でできているのか
粉瘤の袋の中に溜まっているのは、ドロリとした粥状(おかゆのような状態)の物質で、袋の内壁から剥がれ落ちた角質(垢)と、皮脂が混ざり合ったものです。
独特の臭いを伴うことが多く、強く圧迫したり、袋が破れたりすると、その内容物が外に出てきて強い臭気を放ち、色は白から黄色がかった色をしています。
内容物は、細菌の栄養源になりやすく、細菌が侵入すると感染を起こし、炎症につながることがあります。
粉瘤の見た目と手触り
粉瘤は、皮膚がドーム状に盛り上がっているのが一般的で、大きさは数ミリの小さなものから、10センチを超える大きなものまで様々です。表面の皮膚の色は通常、周囲の肌と同じ色か、少し黒ずんでいることがあります。
しこりの中央部分をよく見ると、開口部と呼ばれる小さな黒い点が見えることがあり、これは、皮膚がめり込んで袋を形成した名残であり、毛穴の入り口にあたる部分です。
この黒い点を強く押すと、臭いのある内容物が出てくることもありますが、感染の原因となるため推奨しません。手で触れると、皮膚の下に弾力のある、やや硬い塊として感じられます。
皮膚の表面とは少し癒着していますが、その下の組織とは固定されておらず、指で押すと少し動く感じがするのも特徴です。
粉瘤の主な症状リスト
- 皮膚の盛り上がり
- 中央の黒い点(開口部)
- 弾力のある硬さ
- 押すと少し動く
- 独特の臭い
痛みの有無と炎症のサイン
通常、炎症を起こしていない状態の粉瘤には、痛みやかゆみといった自覚症状はほとんどなく、しこりがある、という感覚だけです。しかし、何らかのきっかけで細菌が侵入し、袋の中で繁殖すると、炎症を起こすことがあります(炎症性粉瘤)。
炎症が起こると、それまでとは全く違う症状が現れ、急に大きさが倍以上になったり、しこりのある部分が赤く腫れ上がったりし、また、ズキズキとした強い痛みを感じるようになり、熱を持つこともあります。
症状が進行すると、袋の中に膿が大量に溜まり、皮膚が破れて膿や血液混じりの内容物が排出されることもあります。
炎症を疑うべきサイン
| サイン | 具体的な症状 | 対処のポイント |
|---|---|---|
| 赤み | しこりの周囲の皮膚が赤くなる | 早めに皮膚科を受診する |
| 腫れ | しこりが急に大きくなる | 自分で圧迫したりしない |
| 痛み | 触れたり、何もしなくてもズキズキ痛む | 冷却よりも受診を優先する |
なぜ粉瘤はできるのか?主な原因
多くの人を悩ませる粉瘤ですが、なぜできてしまうのでしょうか。はっきりとした原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの有力な要因が考えられています。
毛穴の詰まりが始まり
粉瘤の最も一般的な原因として考えられているのが、毛穴の入り口部分の詰まりです。
毛穴の出口付近の皮膚のターンオーバーが乱れ、古い角質がうまく排出されずに詰まってしまうと、そこから皮膚が内側に入り込み、袋状の構造を形成することがあり、ニキビ跡が原因となることもあります。
ニキビによって毛穴の構造がダメージを受け、正常な角質の排出ができなくなることで、粉瘤の発生母地となるケースです。背中は皮脂の分泌が多い部位であり、ニキビもできやすいため、このタイプの粉瘤が発生しやすい環境になります。
外傷が引き金になることも
怪我によって粉瘤ができることもあり、背中をどこかに強くぶつけたり、切り傷や擦り傷を負ったりした際に、皮膚の表面の一部(表皮細胞)が皮膚の深い部分(真皮)に入り込んでしまうことがあります。
入り込んでしまった表皮細胞が増殖し、袋を形成することで粉瘤が発生します(外傷性表皮嚢腫)、この場合、毛穴とは無関係の場所にでき、手術の傷跡などに発生することもあります。
体質や生活習慣との関連性
明確な因果関係は証明されていませんが、粉瘤のできやすさには体質的な要因も関係していると考えられています。家族に粉瘤ができやすい人がいる場合、自分もできやすい傾向があるかもしれません。
また、生活習慣の乱れが間接的に影響する可能性も指摘されていて、不規則な食生活や睡眠不足、ストレスなどは、皮膚のターンオーバーを乱す原因です。
皮膚のターンオーバーが正常に機能しないと、毛穴が詰まりやすくなり、粉瘤の発生リスクを高める可能性があります。
背中のしこり、粉瘤と間違いやすい他の皮膚腫瘍
背中にできるしこりは、すべてが粉瘤というわけではなく、中には、見た目や感触が似ている他の皮膚腫瘍もあります。自己判断で放置してしまうと、適切な治療の機会を逃すことにもなりかねません。
脂肪腫との見分け方
粉瘤と最も間違いやすい皮膚腫瘍の一つが脂肪腫(しぼうしゅ)で、脂肪細胞が増殖してできた良性の腫瘍です。粉瘤と同様に、通常は痛みがなく、徐々に大きくなりますが、いくつか見分けるポイントがあります。
脂肪腫は粉瘤よりも皮膚の深い場所にできるため、境界がやや不明瞭で、触れるとゴムまりのように柔らかいのが特徴です。また、粉瘤に見られるような中央の黒い点(開口部)は脂肪腫にはありません。
大きさも粉瘤より大きくなる傾向があり、10センチを超える巨大なものもあります。
粉瘤と脂肪腫の主な違い
| 項目 | 粉瘤(アテローム) | 脂肪腫(リポーマ) |
|---|---|---|
| 硬さ | 弾力のある硬さ | ゴムまりのような柔らかさ |
| 中央の開口部 | あることが多い | ない |
| 炎症 | 起こすことがある(赤み、痛み) | ほとんど起こさない |
石灰化上皮腫との違い
石灰化上皮腫(せっかいかじょうひしゅ)は、毛母細胞(毛を作る細胞)を起源とする良性の皮膚腫瘍です。子供や若い人の顔、首、腕などによく見られますが、背中にできることもあります。
この腫瘍の特徴は、腫瘍の一部が石灰のように硬くなっていることで、触れると、皮膚の下に石や骨のような硬い塊として感じられ、表面の皮膚は青みがかって見えることもあります。
粉瘤と比べて明らかに硬いため、触診である程度の区別はつきますが、確定診断のためには詳しい検査が必要です。
自己判断は危険、専門医の診断が重要
ここまでいくつかの皮膚腫瘍を挙げましたが、他にも様々な種類の腫瘍があり、中にはごく稀ですが悪性のもの(がん)の可能性もあります。
特に、しこりが急激に大きくなっている、形がいびつである、表面が崩れて出血している、などの症状がある場合は注意が必要です。
最終的な診断は、医師が視診や触診、場合によっては超音波(エコー)検査や病理組織検査などを行った上で総合的に判断します。背中のしこりに気づいたら、自分で判断せずに、まずは皮膚科の専門医に相談することが何よりも大切です。
粉瘤を放置するとどうなる?考えられるリスク
痛みやかゆみがないと、つい受診を後回しにしてしまいがちな背中の粉瘤ですが、良性だからといって放置しておくことには、いくつかのリスクが伴います。
徐々に大きくなる可能性
粉瘤は、皮膚の下にある袋の中で常に新しい角質や皮脂が作られているため、基本的に自然に小さくなることはなく、時間とともに少しずつ大きくなっていく傾向があります。
成長のスピードには個人差があり、何年も大きさが変わらないこともあれば、数ヶ月で目に見えて大きくなることもあります。
最初は気にならない大きさでも、直径5センチ、10センチと大きくなると、見た目が気になるだけにとどまりません。
日常生活にも影響が出始め、仰向けに寝たときに当たって違和感があったり、椅子の背もたれに寄りかかると圧迫されたり、衣類と擦れて不快感を感じたりすることがあります。
また、大きくなってから手術を受けると、切開する範囲が広くなり、傷跡も大きくなる可能性があるので注意が必要です。
炎症と痛みを引き起こす炎症性粉瘤
粉瘤を放置する最大のリスクは、炎症を起こすことで、粉瘤の袋の中に細菌が侵入すると、免疫反応が起こり、赤く腫れ上がり、強い痛みを伴う炎症性粉瘤という状態になります。
背中は蒸れやすく、雑菌が繁殖しやすい環境のため、炎症を起こすリスクは他の部位より高くなります。炎症を起こすと、ズキズキとした痛みで夜も眠れなくなったり、熱が出たりすることもあり、すぐにでも医療機関での処置が必要です。
炎症が強い時期には、粉瘤の袋を完全に取り除く根治手術ができない場合が多く、まずは皮膚を切開して中の膿を出す応急処置(切開排膿)を行うことになります。
炎症性粉瘤の主な症状
- 急激な腫れ
- 皮膚の赤み
- 熱感
- 強い痛み(自発痛・圧痛)
細菌感染による化膿のリスク
炎症性粉瘤の状態がさらに進行すると、袋の中に大量の膿が溜まり、ひどく化膿し、こうなると皮膚が自然に破れて、臭いの強い膿や血液が混じった内容物が排出されることがあります。下着や衣服が汚れるだけでなく、衛生的にも問題があります。
また、一度切開排膿を行っても、原因である袋が残っている限り、炎症を繰り返したり、しこりが再発したりする可能性が高くなります。
炎症を繰り返すうちに周囲の皮膚との癒着がひどくなり、いざ根治手術を行う際に、きれいに袋を取り除くのが難しいです。
稀なケースとしての悪性化
粉瘤は良性腫瘍であり、基本的には悪性化(がん化)することはありません。
しかし、極めて稀なケースとして、長年放置された巨大な粉瘤や、炎症を何度も繰り返している粉瘤から、有棘細胞癌(ゆうきょくさいぼうがん)という皮膚がんが発生したという報告があります。
特に、高齢の方の粉瘤で、急激に大きくなったり、表面が崩れてきたりした場合には、注意深い観察と検査が必要です。稀なリスクを避けるという意味でも、粉瘤に気づいたら放置せず、専門医の診察を受けることが推奨されます。
皮膚科で行う粉瘤の日帰り手術
粉瘤の根本的な治療法は、原因となっている袋状の構造物を残さず取り除く外科手術で、多くの粉瘤は、クリニックでの日帰り手術で治療が可能です。ここでは、皮膚科で行われる代表的な手術方法や、手術当日の流れについて解説します。
手術が必要と判断される場合
すべての粉瘤にすぐに手術が必要というわけではありませんが、以下のような場合には、手術を検討することが勧められます。まず、粉瘤が徐々に大きくなっており、見た目が気になる、あるいは生活に不便を感じる場合です。
また、炎症を繰り返している粉瘤も、根本的な解決のために手術が必要です。炎症が起こる前に手術を行う方が、傷跡が小さく、きれいに治る可能性が高まります。
将来的な炎症のリスクを避けるために、自覚症状がなくても、ある程度の大きさになった時点で予防的に切除するという考え方もあります。最終的に手術を行うかどうかは、医師と相談の上、ご自身の希望を踏まえて決定します。
手術前に医師に伝えておきたいこと
- 現在治療中の病気
- 普段飲んでいる薬(特に血液をサラサラにする薬)
- 薬や麻酔でのアレルギー歴
- 妊娠中や授乳中であるか
くり抜き法(へそ抜き法)の概要
くり抜き法は、比較的小さな粉瘤や、炎症を起こしていない粉瘤に対して行われることが多い手術方法です。この方法では、ディスポーザブルパンチという円筒状のメスを使い、粉瘤の開口部を中心に直径4〜5ミリ程度の小さな穴を開けます。
小さな穴から、皮膚の下にある粉瘤の袋と内容物を揉み出すようにして摘出し、傷口が非常に小さく済むため、縫合しないか、しても1針程度で済むことが多く、体への負担が少なく、傷跡も目立ちにくいのが最大の利点です。
手術時間も短時間で終わりますが、粉瘤の袋が周囲の組織と癒着している場合や、大きな粉瘤の場合には、この方法が適用できないこともあります。
切開法の概要
切開法は、粉瘤の大きさや状態にかかわらず行える、最も標準的な手術方法です。
粉瘤の真上の皮膚を、腫瘍の大きさに合わせて紡錘形(ラグビーボールのような形)に切開し、粉瘤の袋を周囲の組織から剥がしながら、袋が破れないように慎重に丸ごと摘出します。
袋の内容物を残さずに完全に取り除くことができるため、再発のリスクが低い確実な方法です。過去に炎症を起こして周囲と癒着している粉瘤や、サイズの大きい粉瘤に適していて、摘出後は、切開した部分を縫い合わせます。
くり抜き法に比べると傷跡は長くなりますが、形成外科的な縫合技術を用いることで、できるだけ目立たないきれいな傷跡になるように配慮します。
主な手術方法の比較
| 項目 | くり抜き法 | 切開法 |
|---|---|---|
| 傷の大きさ | 小さい(数ミリ) | 粉瘤の大きさに応じる |
| 手術時間 | 短い(5〜10分程度) | やや長い(15〜30分程度) |
| 再発率 | 切開法よりやや高い傾向 | 低い |
手術時間と当日の流れ
粉瘤の日帰り手術は、クリニックに来院してから帰宅するまで、全体で1時間程度で終わることがほとんどです。
まず、医師による最終的な診察の後、手術内容の説明を受け、同意書にサインし、その後、手術室で患部を消毒し、局所麻酔の注射をします。麻酔が効けば、手術中に痛みを感じることはありません。
実際の手術時間は、粉瘤の大きさや手術方法にもよりますが、おおむね10分から30分程度です。手術が終わると、傷口に軟膏を塗ってガーゼやテープで保護します。
着替えを済ませた後、術後の注意点についての説明を受け、痛み止めや抗生剤などの薬を受け取って帰宅となります。
手術当日の一般的な流れ
| 順番 | 内容 | 所要時間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 受付・診察 | 体調の確認と手術部位の最終確認 | 約10分 |
| 2. 手術準備・麻酔 | 消毒と局所麻酔の注射 | 約10分 |
| 3. 手術(摘出・縫合) | 粉瘤の摘出と傷の縫合 | 約10〜30分 |
日帰り手術後の過ごし方とアフターケア
手術が無事に終わっても、傷が完全に治るまではご自身でのケアが大切です。手術後の過ごし方や注意点を守ることで、感染などのトラブルを防ぎ、傷跡をよりきれいに治すことにつながります。
手術当日の注意点
手術当日は、麻酔が切れると少し痛みが出てくることがありますので、処方された痛み止めを我慢せずに服用してください。傷口を濡らさないようにすれば、当日からシャワーを浴びることは可能です。
ただし、湯船に浸かる入浴は、感染のリスクがあるため、医師の許可が出るまでは控える必要があります。飲酒は血行を良くし、出血や痛みの原因となることがあるため、当日は控えてください。
激しい運動や力仕事も、傷口に負担がかかり、出血の原因となりうるため避けましょう。食事については特に制限はありません。
手術後の生活における注意点
- 飲酒
- 激しい運動
- 長時間の入浴
- 傷口への強い刺激
傷跡をきれいに治すためのケア
手術後の傷跡がどの程度目立つかは、体質だけでなく、アフターケアによっても大きく変わってきます。手術の翌日、あるいは医師の指示に従って、ご自身で傷の処置(消毒や軟膏の塗布、ガーゼ交換など)を行ってもらうことがあります。
処置の方法については、看護師から詳しく説明がありますので、指示通りに行ってください。傷口を清潔に保つことが感染予防の基本です。
また、傷が治る過程で、紫外線を浴びると色素沈着を起こし、傷跡が茶色く目立ってしまうことがあります。
背中は衣類で隠れることが多いですが、夏場などで露出する可能性がある場合は、傷が落ち着くまでテープで保護したり、日焼け止めを塗ったりするなどの紫外線対策が重要です。
傷跡ケアのポイント
| ケア項目 | 目的 | 具体的な方法 |
|---|---|---|
| 清潔保持 | 細菌感染の予防 | 医師の指示通りの洗浄・消毒 |
| 保湿 | 皮膚の乾燥を防ぎ、再生を助ける | ワセリンや専用の軟膏を塗布 |
| 紫外線対策 | 色素沈着の予防 | 遮光テープや日焼け止めの使用 |
抜糸までの期間と通院
手術で皮膚を縫合した場合、後日、抜糸のために通院が必要です。抜糸までの期間は、手術した部位や傷の大きさによって異なりますが、背中の場合は一般的に術後10日から14日後くらいが目安となります。
抜糸のタイミングが早すぎると傷が開いてしまうリスクがあり、遅すぎると糸の跡が残りやすくなるため、医師が指定した日に必ず受診してください。抜糸自体はほとんど痛みなく、数分で終わります。
抜糸後も、しばらくは傷跡を保護するテープを貼り続けるよう指示されることがあり、テープは、傷跡が横に広がるのを防ぎ、きれいな一本の線状の傷に治癒するのを助ける役割があります。
再発の可能性について
粉瘤の手術における再発とは、取り除いたはずの同じ場所に、再び粉瘤ができてしまうことを指します。再発の主な原因は、手術の際に粉瘤の袋の一部が取り切れずに残ってしまうことです。
炎症を強く起こした粉瘤の手術では、袋がもろくなっていて周囲の組織と癒着しているため、完全な摘出が難しくなり、再発のリスクがやや高まる傾向があります。目に見えないレベルで、袋の組織が残ってしまう可能性はゼロではありません。
もし、手術した場所が再び膨らんできた場合は、再発の可能性がありますので、早めに手術を受けたクリニックに相談してください。
背中の粉瘤に関するよくある質問
最後に、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。手術や症状に関する不安や疑問の解消にお役立てください。
- 粉瘤は自分で潰しても良いですか
-
粉瘤を自分で潰したり、針で刺したりすると、皮膚の下にある袋が破れてしまい、内容物が周囲に散らばり、細菌感染を起こしてひどい炎症を起こす危険性が非常に高いです。
強い痛みや腫れにつながるだけでなく、皮膚に瘢痕(はんこん)という硬いしこりが残ってしまうこともあります。また、袋の組織が残っている限り、根本的な解決にはならず、必ず再発します。
無理に内容物を出そうとせず、気になっても触らず、専門医に相談してください。
- 手術は痛いですか
-
手術は局所麻酔で行い、最初に麻酔の注射をする際に、チクッとした痛みを感じますが、採血や予防接種の注射と同じ程度の痛みです。麻酔がしっかりと効いてからは、手術が終わるまで痛みを感じることはありません。
もし手術中に何か感覚があれば、我慢せずにすぐに医師やスタッフに伝えてください。麻酔を追加することで対応できます。
手術後は、麻酔が切れると少しジンジンとした痛みが出ることがありますが、処方される痛み止めの薬で十分にコントロールできる範囲の痛みです。
- 手術後に運動はできますか
-
手術当日は運動を控えていただき、翌日以降は、散歩などの軽い運動であれば問題ありませんが、汗をかくような激しい運動や、背中に負担がかかる筋力トレーニングなどは、抜糸が終わるまで避けましょう。
背中の皮膚は体の動きによって伸び縮みするため、傷口に負担がかかりやすい部位です。激しい運動によって傷口が開いてしまったり、内出血を起こしたりする可能性があります。
どの程度の運動から再開できるかは、傷の大きさや場所によっても異なりますので、手術後の診察の際に医師に確認してください。
- 傷跡は残りますか
-
皮膚を切開する以上、残念ながら傷跡が全くゼロになることはありませんが、手術方法の工夫や、形成外科的な縫合技術を用いることで、傷跡をできるだけ目立たないようにすることは可能です。
くり抜き法は傷が非常に小さく、点状の跡になることが多く、切開法の場合は、皮膚のシワの方向に沿って切開し、丁寧に縫合することで、将来的には細い一本の白い線のような傷跡になることを目指します。
傷の最終的な仕上がりには、手術後のケアや個人の体質(ケロイド体質など)も影響します。傷跡について心配な点があれば、診察の際に遠慮なく医師にご相談ください。
以上
参考文献
Kasai M, Asakura Y, Taira Y. Surgical treatment of choledochal cyst. Annals of surgery. 1970 Nov;172(5):844.
Uchida K, Nakano K, Takada M, Sugino N, Hasegawa H, Michiko Y, Kagami H, Taguchi A. Characteristics of clinical and imaging findings of epidermoid cysts under the skin of the mental region. Journal of Hard Tissue Biology. 2017 Jul 1;26(3):305-8.
Sasaki A, Sugita S, Horimi K, Yasuda K, Inomata M, Kitano S. Retrorectal epidermoid cyst in an elderly woman: report of a case. Surgery today. 2008 Aug;38(8):761-4.
Yamamoto T, Nishikawa T, Fujii T, Mizuno K. A giant epidermoid cyst demonstrated by magnetic resonance imaging. British Journal of Dermatology. 2001 Jan 1;144(1):217-8.
Usui K, Yamashita R, Sakura Y, Nakamura M, Shinsaka H, Matsuzaki M, Niwakawa M. Epidermoid cyst of the testis: A report of three cases. Clinical Case Reports. 2024 Apr;12(4):e8577.
Trinh CT, Nguyen CH, Chansomphou V, Chansomphou V, Tran TT. Overview of epidermoid cyst. European journal of radiology open. 2019 Jan 1;6:291-301.
Kim CS, Na YC, Yun CS, Huh WH, Lim BR. Epidermoid cyst: a single-center review of 432 cases. Archives of Craniofacial Surgery. 2020 Jun 29;21(3):171.
Kandogan T, Koç M, Vardar E, Selek E, Sezgin Ö. Sublingual epidermoid cyst: a case report. Journal of medical case reports. 2007 Sep 17;1(1):87.
Ravindranath AP, Ramalingam K, Natesan A, Ramani P, Premkumar P, Thiruvengadam C. Epidermoid cysts: an exclusive palatal presentation and a case series. International journal of dermatology. 2009 Apr;48(4):412-5.
Apollos JR, Ekatah GE, Ng GS, McFadyen AK, Whitelaw SC. Routine histological examination of epidermoid cysts; to send or not to send?. Annals of Medicine and Surgery. 2017 Jan 1;13:24-8.