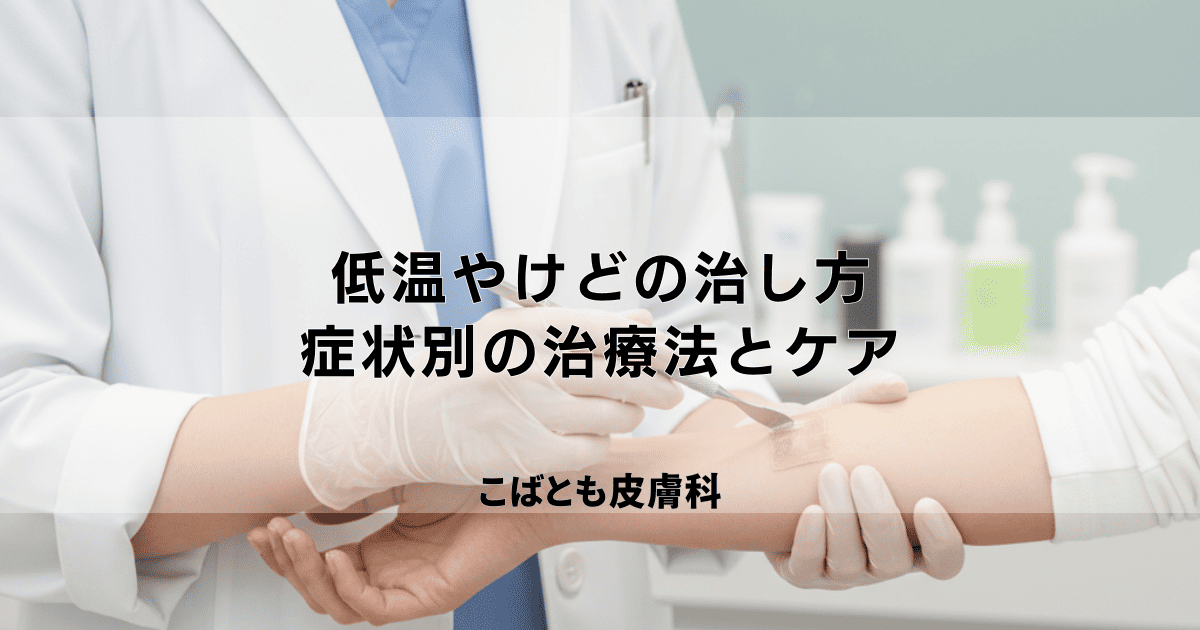冬場に活躍するカイロや湯たんぽなどは、心地よい温かさで私たちを癒してくれますが、使い方を誤ると低温やけどを起こす原因になります。
低温やけどは、熱いものに触れた瞬間に起こるやけどとは異なり、じんわりと時間をかけて皮膚の奥深くまでダメージが進行するため、気づいたときには重症化しているケースも少なくありません。
一見するとただの赤みでも、実は皮膚の内部では細胞がゆっくりと壊死していく深刻な事態が起きている可能性があり、変化はすぐには表面化せず、数日経ってから水ぶくれや色の変化として現れることもあります。
この記事では、低温やけどの基本的な知識から、症状レベルに応じた正しい治し方、ご家庭でできる応急手当、そして専門的な治療法までを詳しく解説します。
そもそも低温やけどとは?普通のやけどとの違い
低温やけどという言葉は聞いたことがあっても、どのような状態を指すのか、普通のやけどと何が違うのかを正確に理解している方は少ないかもしれません。正しい対処法を知るためには、まず低温やけどの性質をきちんと把握することが重要です。
低温やけどの定義
低温やけどは、体温より少し高い、触ってもすぐに熱いとは感じない程度の温度(一般的に44℃から50℃程度)のものに、長時間触れ続けることで発生するやけどを指します。
短時間であれば問題ない温度でも、皮膚の同じ部分が長時間接触し続けると、熱が皮膚の深い部分までじっくりと伝わり、細胞のタンパク質が変性して損傷してしまいます。
カイロを直接肌に貼り続けたり、湯たんぽを足元に置いたまま眠ってしまったりする状況が典型例です。
皮膚が損傷を受ける温度と時間の目安
| 温度 | やけどに至るまでの時間(目安) |
|---|---|
| 44℃ | 約3~4時間 |
| 46℃ | 約30分~1時間 |
| 50℃ | 約2~3分 |
普通のやけどとの主な違い
高温のものに触れて一瞬で起こるやけど(高温熱傷)と低温やけどは、発生する温度と接触時間に大きな違いがあります。
高温熱傷は皮膚の表面が主なダメージを受けるのに対し、低温やけどは時間をかけて熱が伝わるため、まるで弱火で肉を煮込むように、皮膚の深い組織、時には筋肉や骨にまでダメージが及ぶことがあります。
見た目の範囲は狭くても、損傷は深くなる傾向にあり、治癒に時間がかかることが多いのです。
主な相違点の比較
| 項目 | 低温やけど | 普通のやけど(高温熱傷) |
|---|---|---|
| 原因となる温度 | 44℃~50℃程度 | 100℃以上など高温 |
| 接触時間 | 長時間 | 一瞬~短時間 |
| 損傷の深さ | 深いことが多い(皮下組織、筋肉まで及ぶことも) | 浅いことが多い(主に表皮、真皮) |
なぜ気づきにくいのか
低温やけどの最も厄介な点は、痛みや熱さを感じにくく、自覚症状がないまま進行することで、44℃程度の温度では、触れていても心地よいと感じることが多く、危険を察知しにくいのです。
また、人の感覚は持続的な刺激に対して順応する性質があるため、最初は少し熱いと感じても、次第に慣れてしまい、危険信号として脳に伝わらなくなります。
睡眠中や、糖尿病などで末梢神経の感覚が鈍くなっている方は、長時間熱源に接触していても気づかず、重症化するリスクが非常に高まります。
皮膚が赤くなっている、ヒリヒリするといった症状に気づいたときには、すでに皮膚の奥深くで組織の壊死が始まっていることも珍しくありません。
低温やけどが起こりやすい状況
私たちの身の回りには、低温やけどを起こす可能性のあるものが数多くあります。特に冬場は暖房器具の使用が増えるため注意が必要です。日々の生活の中でどのような状況が危険なのかを認識し、予防に努めることが大事です。
低温やけどの原因として報告が多いもの
- 湯たんぽ・使い捨てカイロ
- 電気毛布・電気あんか・ホットカーペット
- ノートパソコン・スマートフォン(充電中)
- ファンヒーターの温風
- 車のシートヒーター
低温やけどの症状レベルと見分け方
低温やけどは、その深さによって症状が異なり、治療法も変わってきて、軽症だと思っていても、専門的な治療が必要なケースもあります。ここでは、症状のレベルごとの特徴と、医療機関を受診すべきサインについて解説します。
軽症(I度熱傷)のサイン
最も軽いやけどで、皮膚の一番外側にある表皮のみが損傷している状態で、主な症状は、皮膚が赤くなる(発赤)、ヒリヒリとした痛みを感じる、触れると少し熱を持っている、といったものです。
指で押すと一時的に白くなり、離すとまた赤くなります。この段階では水ぶくれは形成されません。通常、数日で皮膚の赤みは自然に引き、薄皮がむけることがありますが、傷跡も残らないことがほとんどです。
ただし、この状態でも熱源に触れ続ければ、さらに深いII度やIII度のやけどに進行する可能性があるため、すぐに熱源から離れて冷やすことが大切です。
中等症(II度熱傷)の特徴
表皮を越えて、その下の真皮まで損傷が及んだ状態です。II度のやけどは、さらに損傷の深さによって浅達性II度熱傷と深達性II度熱傷に分けられます。
浅達性の場合は、真皮の浅い層までの損傷で、毛細血管が傷つくため、強い痛みとともに水ぶくれ(水疱)ができるのが特徴です。水ぶくれの底は赤く、潤っています。
深達性になると真皮の深い部分まで損傷が及ぶため、神経の末端もダメージを受け、痛みが感じにくくなることがあり、水ぶくれの底は白っぽく見え、赤みがまだらに混在することもあります。
このレベルになると、治癒までに時間がかかり、傷跡が残る可能性も高いです。
症状レベルごとの主な特徴
| 症状レベル | 主な症状 | 痛み |
|---|---|---|
| I度(軽症) | 皮膚の赤み、ヒリヒリ感 | あり |
| 浅達性II度(中等症) | 赤みを伴う水ぶくれ(水疱)、強い痛み | 強い |
| 深達性II度(中等症) | 白っぽい水ぶくれ、痛みは軽度または鈍い | 軽度~鈍い |
重症(III度熱傷)の見極め
皮膚の全層(表皮、真皮)を越えて、皮下脂肪組織まで損傷が達した状態です。皮膚は血液循環が完全に失われるため、白や黄褐色、黒っぽく変色し、ロウのように硬くなり、神経も完全に破壊されてしまうため、痛みを感じません。
つねったり針で刺したりしても感覚がなく、皮膚は再生能力を失っているため、自然治癒は期待できないので、皮膚移植などの外科的な治療が必要になることがほとんどです。
見た目が派手でなくても、痛みがない場合は重症である可能性を疑う必要があります。
医療機関を受診すべき症状
低温やけどは見た目以上に深くまで損傷している可能性があります。自己判断で様子を見るのではなく、少しでも心配な点があれば専門医に相談することが重要です。特に以下のような症状が見られる場合は、速やかに皮膚科を受診してください。
- 水ぶくれができた(大きさにかかわらず)
- 皮膚の色が白、黄褐色、黒っぽく変化した
- やけどの部分の感覚がない、または鈍い
- やけどの範囲が手のひらよりも大きい
- 数日経っても赤みや痛みが引かない、むしろ悪化している
【症状別】低温やけどの正しい応急手当
低温やけどに気づいたら、その後の経過を左右する最初の対応、つまり応急手当が非常に重要ですが、良かれと思ってやったことが、かえって症状を悪化させてしまうこともあります。
症状のレベルに合わせて、どのような手当をすればよいのか、そして絶対にやってはいけないことは何かを学びましょう。
まずは冷やすことが基本
やけどに気づいたら、何よりもまず患部を冷やすことが最優先です。水道の流水など、清潔な水で15分から30分程度、ゆっくりと冷やし続け、皮膚の奥にこもった熱を取り除き、やけどがそれ以上深くなるのを防ぎます。
また、痛みを伝える神経の興奮を抑え、痛みを和らげる効果もあります。冷やしすぎると凍傷になったり、体温が下がりすぎたりする恐れがあるため、氷や保冷剤を直接当てるのは避け、タオルで包むなどして、冷たさを調節することが大切です。
服の上からやけどをした場合は、無理に脱がさず、服の上からそのまま冷やしましょう。
応急手当の基本的な流れ
| 手順 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 熱源から離れる | すぐにやけどの原因から離れる | 当然ですが最も重要です |
| 2. 冷やす | 清潔な流水で15~30分間冷却 | 氷を直接当てないこと、冷やしすぎないこと |
| 3. 保護する | 清潔なガーゼやラップで優しく覆う | 患部を清潔に保ち、乾燥と刺激を防ぎます |
赤みやヒリヒリ感のみの場合(軽症)
I度熱傷のように、赤みや痛みだけの軽症であれば、十分に冷やした後は患部を清潔に保ち、刺激を与えないようにして様子を見ます。乾燥すると痛みが出やすくなるため、非刺激性の保湿剤(ワセリンなど)を塗布して保護するのも良いでしょう。
ただし、自己判断で市販のステロイド軟膏などを使うのは、感染のリスクを高める可能性もあるため避けた方が無難です。もし数日経っても症状が改善しない、または悪化するようなら、皮膚科を受診してください。
水ぶくれができた場合(中等症)
水ぶくれができた場合は、II度熱傷の可能性が高いです。応急手当として十分に冷やした後、水ぶくれを絶対に破らないように注意してください。
水ぶくれの中の液体(滲出液)には、傷の治癒を促す成分が含まれており、また水ぶくれの膜は、外部の細菌から傷口を守る天然の絆創膏の役割を果たしています。破ってしまうと、そこから細菌が侵入し、感染症を起こすリスクが高まります。
清潔なガーゼで患部をそっと保護し、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。
やってはいけないNGな対処法
民間療法や誤った知識による対処は、症状を悪化させ、治りを遅らせる原因になります。低温やけどの際には、以下のような行為は絶対に行わないでください。
低温やけどの際の禁止事項
| NGな対処法 | 理由 |
|---|---|
| 水ぶくれを意図的に潰す | 感染のリスクが非常に高まるため |
| アロエ、味噌、油などを塗る | 不純物から細菌感染を起こす原因になるため |
| 粘着力の強い絆創膏を直接貼る | 剥がすときに水ぶくれや皮膚を傷つけるため |
皮膚科での専門的な治療法
応急手当を済ませた後、特に水ぶくれができたり、皮膚の色が変わったりしている場合は、皮膚科での専門的な治療が必要です。
低温やけどは見た目以上に深い損傷を受けていることが多く、医師による正確な診断と治療計画が、後の回復に大きく影響します。
診察の流れと診断方法
クリニックに来院すると、まずは医師による問診と視診が行われ、いつ、何が原因で、どのくらいの時間接触していたのか、どのような症状があるかなどを詳しく伝えてください。
医師は患部の色、深さ、大きさ、水ぶくれの有無などを観察し、やけどの重症度を診断します。低温やけどは受傷直後よりも数日後に症状が悪化することがあるため、初診時の見た目だけで判断せず、経過を注意深く観察することが重要です。
必要に応じて、超音波(エコー)検査などで皮膚の下の組織の損傷の深さを客観的に評価することもあります。
軽症から中等症に対する治療
I度から浅達性II度のやけどに対しては、主に外用薬による保存的治療が行われ、治療の目的は、感染を防ぎ、傷を湿潤な環境に保つことで、皮膚が本来持つ自己治癒力を最大限に引き出すことです。
まず、患部を生理食塩水などで十分に洗浄し、汚染や壊死した組織があれば除去し、その後、抗菌作用のある軟膏や、皮膚の再生を助ける創傷被覆材(ドレッシング材)を用いて患部を保護します。
通院の頻度は症状によりますが、数日から1週間ごとに創部の状態を観察し、処置を継続します。
治療で用いられる主な外用薬・被覆材
| 種類 | 主な働き・特徴 |
|---|---|
| 抗菌薬含有軟膏 | 細菌の増殖を抑え、感染を予防する(例:スルファジアジン銀) |
| 皮膚再生促進薬 | 皮膚細胞の増殖を促し、治癒を早める(例:フィブラストスプレー) |
| 創傷被覆材 | 傷を保護し、湿潤環境を保つ。様々な種類がある(ハイドロコロイド、フォーム材など) |
重症の場合の治療選択肢
深達性II度やIII度の重症なやけどでは、皮膚の深い部分が壊死しているため、自然治癒が困難です。この場合、壊死した組織を手術で取り除くデブリードマンという処置が必要になります。
壊死組織は細菌の温床となり、治癒を妨げるだけでなく、全身への感染症の原因にもなるため、取り除くことが治療の第一歩です。
デブリードマンを行った後、皮膚が大きく欠損した場合には、ご自身の他の部位(太ももやお尻など)から健康な皮膚を薄く採取して移植する植皮術(皮膚移植)が必要になることもあります。
重症の場合は、入院による治療や、形成外科との連携が必要になることも少なくありません。
低温やけどの治癒過程と期間
やけどが治るまでには、いくつかの段階を経る必要があります。この治癒の過程を理解することで、ご自身の症状が順調に回復しているのか、あるいは何か問題が起きているのかを判断する助けになります。
治癒の3つの段階
やけどの創傷治癒は、大きく分けて「炎症期」「増殖期」「成熟期」という3つの段階で進行、段階がスムーズに進むことで、傷はきれいに治っていきます。
創傷治癒の各段階の概要
| 段階 | 期間の目安 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 炎症期 | 受傷直後~約3日間 | 赤み、腫れ、痛み。止血と細菌排除が目的。 |
| 増殖期 | 約3日後~数週間 | 新しい血管や皮膚の元(肉芽組織)が作られる。 |
| 成熟期 | 数週間後~数ヶ月以上 | 傷が収縮し、色が薄くなり、瘢痕(傷跡)が完成する。 |
治癒を遅らせる要因
やけどの治りが悪い場合、何らかの要因が治癒を妨げている可能性があります。深い低温やけどで要因が重なると、治療が長期化しやすくなるので、治療とともに、治癒を妨げる要因を取り除くことも大切です。
- 創部の感染
- 血行不良(糖尿病、喫煙など)
- 栄養状態の低下(特にタンパク質やビタミンの不足)
- 患部への圧迫や摩擦などの物理的刺激
- 高齢であること
治療期間の目安
やけどの深さによって、治癒にかかる時間は大きく異なります。軽症であれば短期間で治りますが、重症の場合は手術を含め、数ヶ月にわたる治療が必要となることも覚悟しなくてはなりません。焦らず、根気強く治療を続けることが重要です。
治療後のセルフケアと注意点
皮膚科での治療と並行して、ご自宅でのセルフケアも傷をきれいに治すためには非常に重要で、医師の指示を守り、患部を清潔に保つことが基本です。
治療が終わった後も、デリケートな状態の皮膚をどのようにケアしていくかで、傷跡の残り方や再発防止に大きな差が出ます。
傷跡をきれいに治すためのケア
やけどの跡は、治癒の過程で皮膚が硬くなったり(瘢痕拘縮)、赤みが続いたり、色素沈着を起こしたりすることがあります。これを最小限に抑えるためには、保湿と紫外線対策、そして物理的な刺激を避けることが鍵です。
治りかけの皮膚は非常に乾燥しやすく、デリケートなので、保湿剤をこまめに塗って、皮膚のバリア機能をサポートしましょう。
また、新しい皮膚は紫外線に弱く、シミになりやすいため、外出時には日焼け止めを塗ったり、衣類やサポーターで覆ったりして、徹底した紫外線対策を少なくとも半年から1年は続けることが大切です。
傷跡ケアの重要ポイント
| ケアの種類 | 目的 | 具体的な方法 |
|---|---|---|
| 保湿 | 皮膚の乾燥を防ぎ、柔軟性を保つ | ヘパリン類似物質含有クリームなどを1日数回塗布する |
| 紫外線対策 | 色素沈着や皮膚の劣化を防ぐ | 日焼け止め(SPF30/PA++以上)、衣類などで保護 |
| マッサージ・ストレッチ | 皮膚のひきつれ(瘢痕拘縮)を予防 | 医師や理学療法士の指導のもとで行う |
感染症を防ぐためのポイント
やけどをした皮膚はバリア機能が低下しているため、細菌が侵入しやすく、感染症を起こすリスクがあります。感染を起こすと治癒が遅れるだけでなく、傷跡がひどくなる原因にもなります。患部を清潔に保つことが最も重要です。
医師の指示通りに洗浄や軟膏の塗布を行い、ガーゼ交換の際には事前に石鹸で手をきれいに洗いましょう。もし、感染の兆候が見られた場合は、自己判断せず、すぐに医師に相談してください。
日常生活で気をつけること
治療中は、患部に負担をかけない生活を心がけることが大切です。患部を圧迫したり、擦ったりするようなタイトな衣服は避け、綿素材などの柔らかく、ゆったりとした服装を選びましょう。
入浴については、医師の許可が出るまでは湯船に浸かるのは控え、シャワーで済ませるのが基本です。
血行が良くなりすぎると、痛みやかゆみが増すことがあるため、アルコールの摂取や香辛料の多い食事、激しい運動も症状が落ち着くまでは控えてください。
また、傷の治癒には十分な栄養が必要ですので、タンパク質やビタミンをバランス良く摂取するよう心がけましょう。
低温やけどを未然に防ぐ予防策
低温やけどの治療は時間もかかり、大変な思いをすることがあります。最も良いのは、そもそも低温やけどを起こさないことです。少しの注意で、リスクは大幅に減らすことができます。
暖房器具の正しい使い方
カイロや湯たんぽ、電気毛布などは、長時間、皮膚の同じ場所に直接触れ続けないようにすることが絶対条件です。カイロは肌に直接貼らず、必ず衣服の上に貼り、時々貼る場所を変えるようにしましょう。
湯たんぽは厚手のカバーを付け、さらにタオルで包むなどの工夫をし、布団が温まったら外に出すか、足から離れた場所に置くようにします。
ホットカーペットの上で直接寝てしまうのも大変危険で、タイマー機能を活用し、就寝時には電源が切れるように設定するなどの工夫が有効です。
暖房器具使用時の安全チェック
| 器具 | 安全な使い方 |
|---|---|
| 使い捨てカイロ | 肌に直接貼らない、就寝時は使用しない、時々位置をずらす |
| 湯たんぽ | 厚手のカバーとタオルで二重に包む、布団から出す |
| 電気毛布・あんか | 就寝前に布団を温め、寝るときは電源を切るか、温度を最も低く設定する |
就寝時の注意点
睡眠中は感覚が鈍り、熱さにも気づきにくくなるため、低温やけどが最も起こりやすい時間帯です。電気毛布や電気あんかをつけたまま眠るのは避けましょう。
どうしても寒い場合は、就寝前に布団を温めておき、眠るときにはスイッチを切る習慣をつけてください。湯たんぽも同様に、布団の中に入れっぱなしにしないことが重要です。
寝返りをうてない乳幼児や高齢者、疲労がたまっている方や泥酔状態の方の周りでは、家族など周りの方が注意を払うことが大事です。
低温やけどに関するよくある質問
最後に、低温やけどに関して患者様からよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 低温やけどは放置しても治りますか?
-
軽症であれば自然に治ることもありますが、放置は推奨しません。
低温やけどは見た目以上に深くまで損傷している可能性があり、自己判断で放置すると、気づかないうちに重症化したり、細菌感染を起こして治療が困難になったりする危険性があります。
特に水ぶくれができている場合や、皮膚の色が変わっている場合は、必ず医療機関を受診してください。
- 水ぶくれは自分で潰してもいいですか?
-
絶対に自分で潰してはいけません。水ぶくれの膜は、傷口を外部の刺激や細菌から守る重要な役割を担っています。
潰してしまうと、強い痛みを伴うだけでなく、感染のリスクが非常に高くなり、傷跡が残りやすくなる原因にもなります。
もし自然に破れてしまった場合も、無理に膜を取り除かず、清潔なガーゼで保護して速やかに受診してください。
- 傷跡は必ず残りますか?
-
やけどの深さによります。表皮のみの損傷であるI度熱傷であれば、跡形なくきれいに治ることがほとんどです。真皮にまで達するII度以上のやけどになると、傷跡が残る可能性が高くなります。
しかし、早期に適切な治療を開始し、治療後も医師の指導のもとで保湿や紫外線対策などのアフターケアをきちんと行うことで、傷跡を最小限に抑えることは可能です。
- どのくらいで治りますか?
-
治療期間もやけどの深さによって大きく異なります。症状が軽ければ数日から2週間程度で治癒しますが、深い場合は数ヶ月単位の治療が必要になることもあります。
皮膚移植などの手術が必要な重症例では、リハビリテーションを含めて半年から1年以上かかることもあります。焦らず、医師と相談しながら根気強く治療を続けることが大切です。
以上
参考文献
Yoshino Y, Ohtsuka M, Kawaguchi M, Sakai K, Hashimoto A, Hayashi M, Madokoro N, Asano Y, Abe M, Ishii T, Isei T. The wound/burn guidelines–6: Guidelines for the management of burns. The Journal of dermatology. 2016 Sep;43(9):989-1010.
Suzuki T, Hirayama T, Aihara K, Hirohata Y. Experimental studies of moderate temperature burns. Burns. 1991 Dec 1;17(6):443-51.
Kimura Y, Sumiyoshi M, Samukawa KI, Satake N, Sakanaka M. Facilitating action of asiaticoside at low doses on burn wound repair and its mechanism. European Journal of Pharmacology. 2008 Apr 28;584(2-3):415-23.
Fukunishi K, Maruyama J, Takahashi H, Kitagishi H, Uejima T, Maruyama K, Sakata I. Characteristics of bath-related burns in Japan. Burns. 1999 May 1;25(3):272-6.
Sasaki J, Matsushima A, Ikeda H, Inoue Y, Katahira J, Kishibe M, Kimura C, Sato Y, Takuma K, Tanaka K, Hayashi M. Japanese Society for Burn Injuries (JSBI) clinical practice guidelines for management of burn care. Acute Medicine & Surgery. 2022 Jan;9(1):e739.
Leach EH, Peters RA, Rossiter RJ. Experimental thermal burns, especially the moderate temperature burn. Quarterly Journal of Experimental Physiology and Cognate Medical Sciences: Translation and Integration. 1943 May 22;32(1):67-86.
Choi MS, Lee HJ, Lee JH. Early intervention for low-temperature burns: comparison between early and late hospital visit patients. Archives of plastic surgery. 2015 Mar;42(02):173-8.
Atiyeh BS, Gunn SW, Hayek SN. State of the art in burn treatment. World journal of surgery. 2005 Feb;29(2):131-48.
Cuttle L, Kempf M, Liu PY, Kravchuk O, Kimble RM. The optimal duration and delay of first aid treatment for deep partial thickness burn injuries. Burns. 2010 Aug 1;36(5):673-9.
Beloff A, Peters RA. Observations upon thermal burns: the influence of moderate temperature burns upon a proteinase of skin. The Journal of Physiology. 1945 Mar 28;103(4):461.