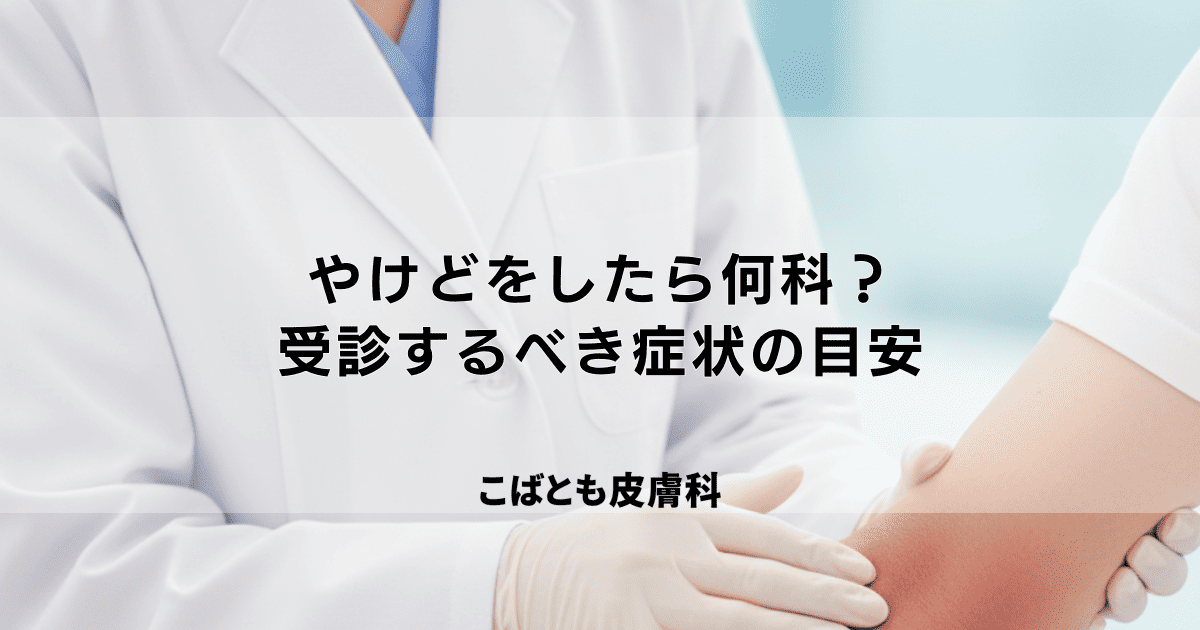日常生活の中で、熱いお茶をこぼしたり、調理中の油がはねたりと、やけどは誰にでも起こりうる身近な怪我の一つです。
突然の出来事に動揺し、どう対処すれば良いのか、特に病院へ行くべきか、そして何科を受診すれば良いのか分からず不安になる方も多いでしょう。
軽いものだと思って放置した結果、跡が残ってしまったり、感染症を起こしたりするケースも少なくありません。
この記事では、やけどの重症度の見分け方から、いざという時の正しい応急処置、皮膚科と形成外科のどちらを選ぶべきかという判断基準まで、分かりやすく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
やけどの基礎知識-深さと重症度の見分け方
やけどを負ったとき、まず気になるのがその重症度ではないでしょうか。見た目の派手さだけでなく、皮膚のどの深さまでダメージが及んでいるかによって、対処法やその後の経過が大きく変わります。
やけどの深さは3段階に分類される
やけどは、皮膚の損傷がどの深さまで達しているかによって、3つの度数に分類します。
Ⅰ度熱傷は最も軽いやけどで、皮膚の最も外側にある表皮のみが損傷を受けた状態で、日焼けのように皮膚が赤くなり、ヒリヒリとした痛みを伴いますが、通常は数日で跡を残さずに治ります。
Ⅱ度熱傷は、表皮とその下の真皮まで損傷が及んだ状態です。強い痛みと共に水ぶくれができ、真皮の浅い層までの損傷(浅達性Ⅱ度)と、深い層までの損傷(深達性Ⅱ度)に分かれます。
深達性Ⅱ度の場合、治癒までに時間がかかり、跡が残る可能性があります。
Ⅲ度熱傷は最も重いやけどで、皮膚の全層(表皮、真皮)と、さらにその下の皮下組織まで損傷が及んだ状態で、神経も破壊されるため、痛みを感じにくくなることがあり、皮膚は白や黒っぽく変色し、硬くなります。
この状態では自然治癒は難しく、専門的な治療が必要です。
やけどの深度と主な症状
| 深度(度数) | 主な症状 | 治癒までの期間の目安 |
|---|---|---|
| Ⅰ度熱傷 | 皮膚の赤み、ヒリヒリする痛み | 数日 |
| Ⅱ度熱傷 | 強い痛み、水ぶくれ(水疱) | 1~4週間以上 |
| Ⅲ度熱傷 | 痛みは少ないか無い、皮膚が白または黒く変色 | 数週間~数ヶ月 |
症状で判断する重症度のサイン
やけどの重症度は、深さだけでなく、その範囲や部位によっても総合的に判断し、注意が必要なのは、やけどの範囲が広い場合です。
成人の場合、体表面積の10%以上(手のひら1枚分が約1%)にⅡ度以上のやけどを負った場合は、入院治療が必要になることがあります。
また、顔、手足、関節、陰部などの特殊な部位のやけどは、機能的な問題や美容的な問題につながりやすいため、範囲が狭くても重症として扱います。
さらに、子供や高齢者は皮膚が薄く、同じ温度でも重症化しやすいため、より慎重な判断が求められます。煙を吸い込んだ可能性がある気道熱傷や、糖尿病などの持病がある方のやけども、専門的な管理が必要となる重症例です。
やけどの原因と起こりやすい状況
やけどの原因は様々ですが、主に4つのタイプに大別できます。最も多いのが、熱湯や油、スープ、蒸気など高温の液体や気体に触れることで生じる温熱熱傷で、家庭内での調理中や食事中の発生が多いです。
次に、ストーブやアイロン、湯たんぽなどに直接触れてしまう接触熱傷があります。
低温熱傷(低温やけど)もこの一種で、カイロや電気毛布など、体温より少し高い温度のものに長時間触れ続けることで、皮膚の深い部分まで損傷してしまい、痛みを感じにくいため、気づいた時には重症化していることが多いです。
その他、酸やアルカリなどの化学薬品が皮膚に付着して起こる化学熱傷や、コンセントや落雷などで感電して生じる電撃熱傷もあります。
原因によっても重症度や対処法が異なるため、何によってやけどをしたのかを正確に把握することが大切です。特に化学熱傷や電撃熱傷は、見た目以上に内部の損傷が激しい場合があるため、ただちに専門医の診察を受ける必要があります。
やけどをしたらまず行うべき応急処置
やけどをしてしまった直後の数分間の対応が、その後の治り方や跡が残るかどうかを大きく左右します。パニックにならず、落ち着いて正しい応急処置を行うことが何よりも大切です。
冷やすことが基本-正しい冷やし方と時間
やけどをしたら、何よりもまず流水で患部を冷やしてください。
水道水で、痛みが和らぐまで最低でも15分から30分程度、衣服の上からでも構わないので、すぐに冷やし続けることが重要で、やけどの進行を食い止め、痛みを軽減し、腫れを抑えることができます。
冷やす際は、氷や保冷剤を直接当てるのは避けてください。冷やしすぎると血行が悪くなり、かえって皮膚の回復を妨げる凍傷のリスクがあります。
流水を直接当てることが難しい部位の場合は、清潔なタオルやガーゼを濡らして当てる方法でも構いません。広範囲のやけどの場合は、冷やしすぎによる低体温症に注意が必要です。
子供や高齢者の場合は、全身が冷えすぎないよう注意しながら患部を冷やし、体が震えるなどの症状が見られたらすぐに中断し、清潔な布で体を覆い保温しながら医療機関へ向かいましょう。
軽度のやけどのセルフケア期間目安
| やけどの深度 | 応急処置後の状態 | セルフケアでの改善目安 |
|---|---|---|
| Ⅰ度 | 赤みと軽い痛みのみ | 2~3日 |
| 浅達性Ⅱ度(小範囲) | 小さな水ぶくれ、痛み | 約1週間 |
| 深達性Ⅱ度以上 | 大きな水ぶくれ、強い痛み、または痛みがない | セルフケアではなく受診が必要 |
応急処置でやってはいけないこと
やけどの際、良かれと思ってやったことが逆効果になる場合があります。昔からの言い伝えや誤った知識による対処は、症状を悪化させたり、感染症の原因になったりするため絶対にやめてください。
アロエや味噌、油などを塗る民間療法は、患部を不衛生にし、感染のリスクを高めるだけです。また、消毒液は刺激が強く、やけどで傷ついた皮膚の細胞をさらに傷つけ、回復を遅らせる可能性があります。
応急処置の基本は、清潔な流水で冷やすことだけと覚えておきましょう。薬を塗るのは、医療機関で診察を受けてから、医師の指示に従うのが原則です。
- アロエや味噌などを塗る
- 消毒液を直接かける
- 水ぶくれを無理に破る
- 氷や保冷剤を直接当てる
- 粘着力の強い絆創膏を貼る
水ぶくれができた場合の対処法
Ⅱ度熱傷で見られる水ぶくれ(水疱)は、やけどによって傷ついた皮膚を守るための重要な役割を担っています。
内部の液体には、傷を治すための成分が含まれており、外部からの細菌の侵入を防ぐバリアの役目も果たしているため、水ぶくれは故意に破らないのが原則です。
もし自然に破れてしまった場合は、中の液体を清潔なガーゼでそっと拭き取り、めくれた皮膚は無理に剥がさずに、そのままの状態で患部を保護し、速やかに医療機関を受診してください。
自分で水ぶくれを破ると、そこから細菌が侵入し、感染症を起こすリスクが高まり、また、治りが遅くなったり、傷跡が残りやすくなったりする原因にもなります。
水ぶくれが大きく腫れて痛みが強い場合や、関節など動かす部位にできて生活に支障が出る場合も、自己判断で処置せず、医師に相談することが大切です。
病院へ行くべきやけどの症状-受診の目安
応急処置をしても、本当にこのまま様子を見ていて良いのか、それとも病院へ行くべきなのか、判断に迷うことも多いでしょう。ここでは、どのような場合に医療機関の受診が必要になるのか、症状や状況を基にした判断基準を解説します。
迷わず救急車を呼ぶべき危険な状態
やけどの中には、生命の危険に関わる緊急性の高い状態があり、次のような症状が見られる場合は、ためらわずに救急車を呼んでください。
まず、やけどの範囲が非常に広い場合で、成人の体表面積の10%以上、子供なら5%以上がⅡ度以上のやけどを負った場合は、全身の状態に影響を及ぼすショック状態に陥る危険性があります。
また、火災などで煙を吸い込み、顔や鼻毛が焦げている、声がかすれている、呼吸が苦しそうな場合は、気道を熱傷している可能性があります。気道熱傷は、喉が腫れて窒息する危険があるため、極めて緊急性が高い状態です。
さらに、意識が朦朧としている、ぐったりしている場合や、高圧線や落雷による電撃熱傷、爆発などを伴うやけども、体の内部に深刻なダメージを負っている可能性があるため、速やかな救急搬送が必要です。
- 広範囲のやけど(成人の体表面積10%以上)
- 顔や首、気道のやけど(声がれ、呼吸困難)
- 意識障害がある
- 電撃熱傷や化学熱傷
- 乳幼児や高齢者の広範囲熱傷
診療時間内に受診を検討すべき症状
緊急性は高くないものの、専門的な治療が必要となるやけどもあります。水ぶくれができたⅡ度熱傷や、痛みを感じないⅢ度熱傷の場合は、自己判断で対処せず、診療時間内に医療機関を受診しましょう。
水ぶくれの大きさが500円玉より大きい場合は、感染のリスク管理や適切な処置が必要で、また、やけどの部位も重要な判断基準です。
顔、手、足、関節、陰部などのやけどは、日常生活の動作に関わる機能障害や、見た目の問題(瘢痕拘縮など)につながる可能性があるため、範囲が小さくても専門医の診察を受けることが推奨されます。
さらに、糖尿病や膠原病などの持病がある方、ステロイド薬を内服している方は、免疫力が低下しており、感染症を起こしやすく、傷の治りも遅くなる傾向があるため、軽いやけどでも早めに受診してください。
数日経っても赤みや痛みが引かない、悪化するような場合も受診のサインです。
受診の緊急度を判断する目安
| 緊急度 | 主な症状・状況 | 推奨される行動 |
|---|---|---|
| 非常に高い | 広範囲、気道熱傷、意識障害、電撃熱傷 | すぐに救急車を要請 |
| 高い | Ⅱ度以上、顔・手足・関節のやけど、持病あり | 当日~翌日に受診 |
| 中程度 | Ⅰ度だが痛みが強い、数日経っても改善しない | 診療時間内に受診を検討 |
やけどの範囲が広い場合の判断基準
やけどの範囲を判断する簡単な目安として、手掌法(しゅしょうほう)というものがあり、これは、患者さん自身の手のひら(指の部分も含む)の大きさを、体表面積の約1%とする考え方です。
自分の手のひら10枚分の範囲にやけどを負った場合、体表面積の約10%に相当します。この方法はあくまで簡易的な目安ですが、受診すべきかどうかを判断する際の一助です。
成人では体表面積の10%以上、子供や高齢者では5%以上のⅡ度以上のやけどは、入院が必要となる可能性が高い重症例と判断されます。
乳幼児は体のサイズが小さいため、少しの範囲でも重症になりがちで、マグカップの熱湯を胸にこぼしただけでも、体表面積の5%以上に達することがあります。範囲の判断に迷った場合は、過小評価せずに、医療機関に相談してください。
やけどは何科を受診するべきか-皮膚科と形成外科の役割の違い
いざ病院へ行こうと決めたとき、次に悩むのが皮膚科と形成外科、どちらを受診すれば良いのかという問題です。どちらもやけどの治療を行っていますが、それぞれの専門性や得意とする領域には違いがあります。
症状や部位、患者さんが何を重視するかによって、適切な診療科は異なります。
皮膚科が適しているやけどのケース
皮膚科は、皮膚そのものの病気やトラブルを専門とする診療科で、比較的範囲が狭く、軽症から中等症(Ⅰ度から浅達性Ⅱ度)のやけどの治療を得意としています。
赤くなっているだけ、あるいは小さな水ぶくれができた程度のやけどであれば、まずは皮膚科を受診するのが一般的です。
皮膚科では、やけどによる炎症を抑え、感染を防ぎ、皮膚が本来持つ治癒力を最大限に引き出すための薬物療法(塗り薬など)が中心となります。傷跡をできるだけきれいに治すためのスキンケア指導や、色素沈着に対する治療なども行います。
手術を必要としない保存的治療で改善が見込めるケースの多くは、皮膚科の領域です。
- 赤みやヒリヒリ感のみのⅠ度熱傷
- 比較的小さな水ぶくれを伴うⅡ度熱傷
- 手術を必要としない保存的治療が中心の場合
- やけど後の色素沈着や皮膚炎の相談
形成外科の受診が推奨される場合
形成外科は、体の表面の形や機能を、手術などの外科的な手法を用いて治療することを専門とする診療科です。重症のやけど、特に皮膚移植(植皮術)などの手術が必要となるⅢ度熱傷や、広範囲の深達性Ⅱ度熱傷の治療を得意としています。
また、顔や手、関節など、機能的にも美容的にも重要な部位のやけども形成外科の専門領域です。
このような部位は、傷跡が引きつれ(瘢痕拘縮)を起こし、動きの制限や変形につながる可能性があるため、初期治療から傷跡のことまで見据えた専門的な管理が重要です。
やけどが治った後の、目立つ傷跡(肥厚性瘢痕やケロイド)の修正や、引きつれの改善を目的とした手術も形成外科が担当します。よりきれいに治したい、機能的な問題を解決したいという希望が強い場合は、形成外科への相談が適しています。
皮膚科と形成外科の役割分担
| 診療科 | 得意とするやけど | 主な治療法 |
|---|---|---|
| 皮膚科 | 軽症~中等症(Ⅰ度、Ⅱ度)、範囲が狭いもの | 外用薬(塗り薬)などの保存的治療 |
| 形成外科 | 重症(深達性Ⅱ度、Ⅲ度)、広範囲、特殊部位 | 手術(皮膚移植など)、傷跡の治療 |
どちらを受診すべきか迷ったときの判断材料
皮膚科と形成外科のどちらを受診すべきか迷った場合は、まずは身近なかかりつけの皮膚科に相談してみるのが一つの方法です。皮膚科医が診察し、保存的治療で対応可能か、あるいは形成外科での専門的な治療が必要かを判断してくれます。
必要であれば、適切な形成外科を紹介してもらえるでしょう。やけどの範囲が広い、水ぶくれが大きい、顔や手のやけど、あるいは最初から傷跡が心配な場合は、はじめから形成外科の受診を検討するのも良い選択です。
総合病院などでは皮膚科と形成外科が連携していることも多く、院内でスムーズに適切な診療科へつないでくれることもあります。最終的には、どちらの科でも初期対応は可能です。
子供や高齢者のやけどで注意すべき点
やけどは誰にでも起こりますが、注意が必要なのが子供と高齢者です。子供は好奇心旺盛な行動から、高齢者は身体機能の低下から、それぞれ特有の状況でやけどを負いやすい傾向があります。
また、両者ともに皮膚が薄くデリケートであるため、大人であれば軽症で済むようなやけどでも重症化しやすいというリスクを抱えています。
子供の皮膚の特徴とやけどのリスク
子供の皮膚は大人に比べて非常に薄く、バリア機能も未熟なので、同じ温度のものでも、大人より短時間で、より深いところまで熱が到達してしまい、重症のやけどになりやすいです。
また、子供は体の大きさに比べて体表面積の割合が大きいため、比較的狭い範囲のやけどでも全身状態に影響が出やすいという特徴があります。
好奇心が強く、危険を予測する能力がまだ発達していないため、テーブルの上の熱い飲み物をひっくり返したり、炊飯器やポットの蒸気に手を伸ばしたりといった、家庭内での事故が後を絶ちません。
痛みに対する反応も大人とは異なり、うまく症状を伝えられないこともあり、保護者が見ていないところで起きた小さなやけどが、気づかないうちに悪化しているケースもあるため、日頃から注意深く様子を見守ることが重要です。
子供がやけどをした場合は、範囲が狭くても、大人が思うより重症である可能性を念頭に置き、早めに医療機関を受診してください。
子供に多いやけどの原因
| 順位 | 原因 | 具体的な状況 |
|---|---|---|
| 1位 | 熱湯・汁物 | 味噌汁、スープ、カップ麺をこぼす |
| 2位 | 調理器具・暖房器具 | アイロン、ストーブ、炊飯器の蒸気に触れる |
| 3位 | お茶・コーヒー | テーブルの上の飲み物をひっくり返す |
高齢者がやけどをしやすい理由と重症化リスク
高齢になると、加齢に伴う様々な身体機能の変化により、やけどのリスクが高まります。
まず、皮膚が薄くなり、乾燥しやすくなるため、熱によるダメージを受けやすくなり、また、感覚機能が低下し、熱さや痛みを感じにくくなるため、低温熱傷のリスクが非常に高まります。
こたつや湯たんぽ、電気カーペットなどで長時間同じ姿勢でいるうちに、気づかない間に皮膚の深い部分まで損傷してしまうケースが多く見られます。
さらに、運動機能の低下により、熱いものを持った際に手元がふらついたり、とっさの危険回避が難しくなったりすることも、やけどの原因となります。
糖尿病などの持病を抱えている方も多く、血行障害や免疫力の低下から、一度やけどをすると非常に治りにくく、感染症を合併して重症化しやすい傾向があり、認知機能の低下がある場合は、火の不始末などにも注意が必要です。
- 感覚の低下による低温熱傷
- 運動機能の低下による転倒・失敗
- 持病による治癒能力の低下
- 認知機能の低下による火の元の管理
- 皮膚の菲薄化による重症化
やけどの跡を残さないための治療とセルフケア
やけどの痛みが落ち着くと、次に気になるのは跡が残らないかということでしょう。顔や手足など、人目につきやすい場所のやけどは、美容的な観点からも大きな悩みとなります。
やけどの跡を最小限に抑えるためには、初期治療はもちろんのこと、治癒過程におけるセルフケアや、治った後のアフターケアが非常に重要です。
医療機関で行う専門的な治療法
やけどの跡をきれいに治すためには、まず、創部を湿潤な環境に保ち、感染を防ぐことが基本です。医療機関では、やけどの深さや状態に応じて、様々な外用薬(塗り薬)や創傷被覆材(ドレッシング材)を使い分けます。
感染のリスクがある場合には抗菌作用のある軟膏を、肉芽の形成を促したい場合には成長因子を含む軟膏を使用するなど、専門的な判断に基づいた治療が行われます。
水ぶくれの処置や、壊死した組織の除去(デブリードマン)なども、感染を防ぎ、皮膚の再生を促すために重要な処置です。
やけどが深い場合や、治癒が長引く場合には、傷跡が硬く盛り上がったり(肥厚性瘢痕)、引きつれたりするリスクが高まります。
そのような場合は、ステロイドの局所注射や内服薬、圧迫療法などを組み合わせて、傷跡の増殖を抑える治療を行うこともあります。
重度のやけどで皮膚の欠損が大きい場合には、自身の他の部位から皮膚を移植する植皮術が必要となることもあります。
やけど治療で用いられる外用薬の例
| 薬剤の種類 | 主な目的 | 代表的な成分 |
|---|---|---|
| 抗菌薬含有軟膏 | 感染の予防・治療 | スルファジアジン銀など |
| 創傷治癒促進薬 | 皮膚の再生を促す | トラフェルミン(bFGF)など |
| 保湿・保護剤 | 皮膚の乾燥を防ぐ | 白色ワセリンなど |
自宅でできるアフターケアのポイント
医療機関での治療と並行して、自宅で行うセルフケアも傷跡の管理において大切で、医師の指示に従い、処方された薬を正しく塗り、ガーゼ交換などを清潔な手で行うことが基本です。
傷が治り、新しい皮膚が再生してきた段階では、保湿と保護が特に重要になります。再生したての皮膚は非常にデリケートで乾燥しやすく、バリア機能もまだ不完全です。
保湿剤をこまめに塗り、皮膚の潤いを保つことで、かゆみや突っ張り感を和らげ、健やかな皮膚の再生をサポートし、また、傷跡の部分は衣類などで擦れないように注意し、物理的な刺激を避けることも大切です。
かゆみが出た場合でも、掻きむしってしまうと皮膚を傷つけ、色素沈着や傷跡の悪化につながるため、冷やしたり、保湿剤を塗ったりして対処しましょう。
食生活では、皮膚の材料となるタンパク質や、再生を助けるビタミン、ミネラルをバランス良く摂取することも、内側からのケアとして有効です。
- 医師の指示通りの処置
- 再生した皮膚の徹底した保湿
- 物理的な刺激(摩擦)を避ける
- かゆみがあっても掻かない
- 栄養バランスの取れた食事
紫外線対策の重要性
やけどの跡をきれいに治す上で、紫外線対策は最も重要なセルフケアの一つです。やけど後の皮膚は、炎症の影響でメラニン色素が生成されやすい状態にあり、紫外線を浴びると炎症後色素沈着というシミのような跡が非常に残りやすくなります。
色素沈着は一度できると消えるまでに長い時間がかかったり、場合によっては半永久的に残ってしまったりすることもあります。傷が治り、皮膚が再生してからも、少なくとも3ヶ月から半年間は、徹底した紫外線対策が必要です。
外出時は、日焼け止めをこまめに塗り直す、帽子や日傘、長袖の衣類などを活用する、紫外線が強い時間帯の外出を避けるなどの対策を心がけましょう。
やけど跡の種類と特徴
| 傷跡の種類 | 見た目の特徴 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 炎症後色素沈着 | 茶色いシミのような跡 | 紫外線、摩擦などの刺激 |
| 肥厚性瘢痕 | 赤くミミズ腫れのように盛り上がる | 治癒過程での過剰なコラーゲン生成 |
| 瘢痕拘縮 | 皮膚が引きつれて動きにくい | 関節部などの深いやけど |
傷跡の改善に向けた選択肢
適切なケアを行っても、やけどの深さや体質によっては、どうしても傷跡が残ってしまうことがありますが、残ってしまった傷跡に対しても、改善を目指すための様々な治療法があります。
赤みや盛り上がりが続く肥厚性瘢痕やケロイドに対しては、ステロイド含有テープの貼付や、ステロイドの局所注射、レーザー治療などが行われます。
茶色い色素沈着に対しては、ハイドロキノンなどの美白外用薬や、ビタミンCの内服、レーザー治療や光治療などが有効な場合があります。
また、傷跡の引きつれによって関節が動かしにくいなどの機能的な問題が生じている場合には、瘢痕を切り取って縫い直したり、皮膚移植を行ったりする形成外科的な手術が検討されます。
紫外線対策グッズの比較
| 対策グッズ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 日焼け止め | 手軽に広範囲をカバーできる | 塗り直しが必要、肌に合わない場合がある |
| 衣類・帽子 | 物理的に紫外線を遮断、効果が持続 | 覆えない部分がある、夏場は暑い |
| 日傘 | 顔や上半身を広くカバーできる | 手がふさがる、照り返しは防げない |
やけどに関するよくある質問
ここでは、やけどの治療やセルフケアに関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- やけどは冷やしすぎてもいけないのですか?
-
やけどの応急処置で最も重要なのは冷やすことですが、氷や保冷剤を直接患部に長時間当て続けるなど、過度に冷やすことは避けるべきです。
強い冷却は血管を収縮させ、血流を悪化させることで、かえって皮膚組織の損傷を深めたり、治りを遅らせたりする可能性があり、また、凍傷を起こす危険性もあります。
広範囲のやけどを冷やす場合は、低体温症のリスクも考慮しなくてはなりません。応急処置の基本は、痛みが和らぐまで清潔な流水で15分から30分程度冷やすことです。
- 水ぶくれは自分で破っても良いですか?
-
水ぶくれは、傷ついた皮膚を外部の刺激や細菌から守る天然の絆創膏のような役割を果たしていて、内部の液体には傷の治癒を促す成分も含まれています。
自分で無理に破ってしまうと、保護機能が失われ、傷口から細菌が侵入して感染症を起こすリスクが非常に高くなり、また、傷跡が残りやすくなる原因です。
もし自然に破れてしまった場合は、めくれた皮膚は剥がさず、清潔なガーゼで保護して医療機関を受診してください。水ぶくれが大きくて痛みが強い場合も、自己判断せず医師に相談することが大切です。
- 市販の薬を使っても問題ないですか?
-
ごく軽いやけど(赤くなっているだけのⅠ度熱傷)であれば、市販の非ステロイド性抗炎症薬含有の軟膏などが有効な場合もありますが、やけどの深さや状態を正しく判断するのは専門家でなければ難しいです。
水ぶくれができているⅡ度以上のやけどの場合、自己判断で市販薬を使用すると、症状を悪化させたり、アレルギー反応(かぶれ)を起こしたり、受診した際の医師の診断を困難にしたりする可能性があります。
まずは医療機関を受診し、医師の診断に基づいて処方された薬を使用するのが最も安全で確実な方法です。
- 跡が残るかどうかはいつ頃わかりますか?
-
皮膚の表皮のみが損傷したⅠ度熱傷であれば、通常は跡を残さず数日で治り、真皮の浅い層まで達した浅達性Ⅱ度熱傷も、適切に治療すれば跡は残らないか、残ってもごく軽微な場合が多いです。
しかし、真皮の深い層まで損傷した深達性Ⅱ度熱傷や、皮下組織まで達したⅢ度熱傷の場合は、何らかの跡が残る可能性が高くなります。
通常、治癒してから3ヶ月から半年くらいまでの期間は、傷跡が赤く硬くなる時期(成熟期)であり、この時期のケアが最終的な傷跡の状態に影響します。
最終的な傷跡がどのような状態に落ち着くか分かるまでには、少なくとも半年から1年程度の期間が必要です。
以上
参考文献
Yoshino Y, Ohtsuka M, Kawaguchi M, Sakai K, Hashimoto A, Hayashi M, Madokoro N, Asano Y, Abe M, Ishii T, Isei T. The wound/burn guidelines–6: Guidelines for the management of burns. The Journal of dermatology. 2016 Sep;43(9):989-1010.
Sasaki J, Matsushima A, Ikeda H, Inoue Y, Katahira J, Kishibe M, Kimura C, Sato Y, Takuma K, Tanaka K, Hayashi M. Japanese Society for Burn Injuries (JSBI) clinical practice guidelines for management of burn care. Acute Medicine & Surgery. 2022 Jan;9(1):e739.
Inoue Y, Kishibe M, Kuroyanagi M, Sato Y, Nemoto M, Hayashi M, Hirose T, Matsushima A, Morita N, Yoshimura Y, Sasaki J. Japanese Society for Burn Injuries Burn Registry 2011: 10‐year Analysis Report. Acute Medicine & Surgery. 2025 Jan;12(1):e70088.
Tagami T, Matsui H, Moroe Y, Fukuda R, Shibata A, Tanaka C, Unemoto K, Fushimi K, Yasunaga H. Antithrombin use and 28-day in-hospital mortality among severe-burn patients: an observational nationwide study. Annals of Intensive Care. 2017 Feb 20;7(1):18.
Kumakawa Y, Kondo Y, Hirano Y, Sueyoshi K, Tanaka H, Okamoto K. Characteristics and clinical outcomes of patients with combined burns and trauma in Japan: Analysis of a nationwide trauma registry database. Burns. 2024 Sep 1;50(7):1719-25.
Kumagai N, Nishina H, Tanabe H, Hosaka T, Ishida H, Ogino Y. Clinical application of autologous cultured epithelia for the treatment of burn wounds and burn scars. Plastic and reconstructive surgery. 1988 Jul 1;82(1):99-108.
Tonegawa-Kuji R, Yamagata K, Kanaoka K, Wakamiya A, Inoue YY, Miyamoto K, Miyamoto Y, Kiyohara E, Kusano K. Maximum burn prevention practice vs conventional care after direct current cardioversion treatment: The BURN-PREVENTION trial. Heart Rhythm. 2024 Oct 1;21(10):2060-2.
Morita S, Higami S, Yamagiwa T, Iizuka S, Nakagawa Y, Yamamoto I, Inokuchi S. Characteristics of elderly Japanese patients with severe burns. Burns. 2010 Nov 1;36(7):1116-21.
Kimura Y, Sumiyoshi M, Samukawa KI, Satake N, Sakanaka M. Facilitating action of asiaticoside at low doses on burn wound repair and its mechanism. European Journal of Pharmacology. 2008 Apr 28;584(2-3):415-23.
Fujiwara H, Isogai Z, Irisawa R, Otsuka M, Kadono T, Koga M, Hirosaki K, Asai J, Asano Y, Abe M, Amano M. Wound, pressure ulcer and burn guidelines–2: Guidelines for the diagnosis and treatment of pressure ulcers. The Journal of dermatology. 2020 Sep;47(9):929-78.