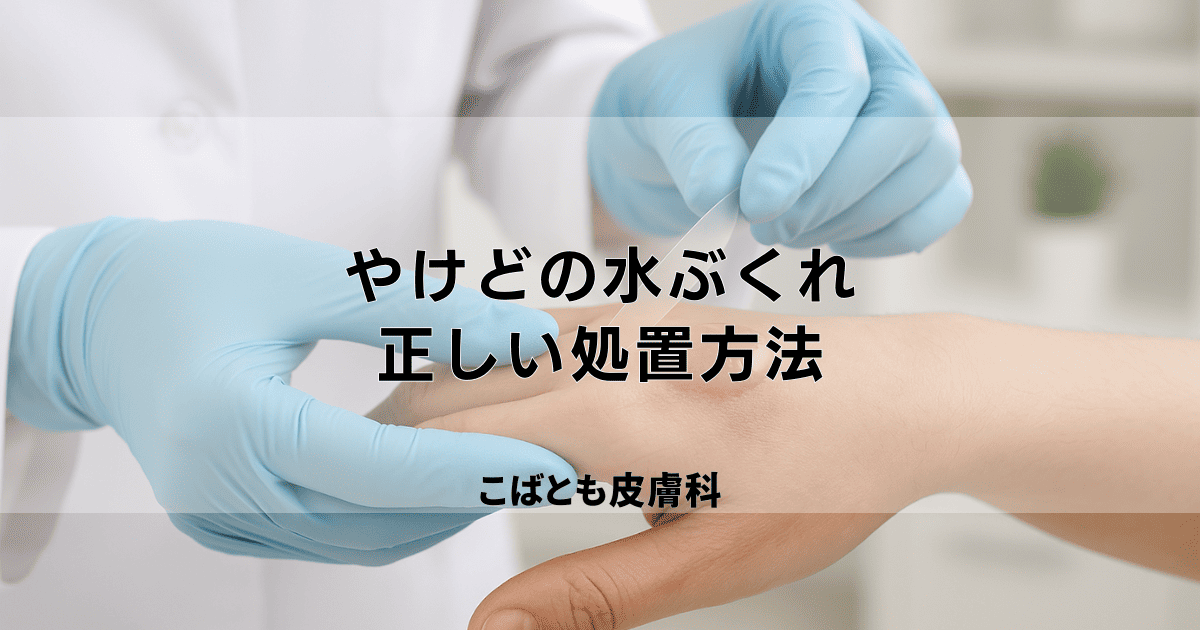料理中の油はねや、熱いお茶をこぼしてしまった時など、日常生活の中でやけどは誰にでも起こりうる身近な怪我です。
ヒリヒリとした痛みに加え、ぷっくりと膨らんだ水ぶくれができると、これを潰すべきか、そのままにしておくべきか、どう対処すれば良いか迷う方は少なくありません。
間違った処置は、治りを遅らせるだけでなく、感染症を引き起こしたり、跡が残りやすくなったりする原因にもなります。
この記事では、やけどの深さの見分け方から、いざという時の正しい応急処置、最も気になる水ぶくれへの適切な対応、跡をきれいに治すためのケア方法まで、詳しく解説します。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
まずは知っておきたい やけどの深さと水ぶくれの関係
やけどの重症度は、皮膚がどの深さまでダメージを受けたかによって決まります。水ぶくれができるかどうかは、深さと密接に関係しています。ここでは、やけどのレベルと水ぶくれができる理由について説明します。
やけどの重症度を判断する3つのレベル
やけどは、損傷の深さによって医学的にⅠ度、Ⅱ度、Ⅲ度に分類されます。Ⅰ度は皮膚の最も外側にある表皮だけのやけどで、赤みとヒリヒリした痛みが主な症状です。水ぶくれはできず、日焼けなどがこれにあたります。
Ⅱ度は、表皮とその下の真皮にまで及ぶやけどで、強い痛みと水ぶくれ(水疱)の形成が特徴です。家庭で起こるやけどの多くがこのⅡ度に分類されます。
Ⅲ度は、皮膚の全層、時には皮下組織まで損傷が及んだ最も重いやけどで、皮膚は白や黒っぽく変色し、神経も破壊されるため痛みを感じないこともあり、緊急の医療処置が必要です。
やけどの深度別分類
| 深度 | 損傷を受けた皮膚の層 | 主な症状 |
|---|---|---|
| Ⅰ度(表在性) | 表皮 | 赤み、痛み、腫れ(水ぶくれなし) |
| Ⅱ度(部分層) | 表皮と真皮 | 強い痛み、赤み、水ぶくれ |
| Ⅲ度(全層) | 皮膚全層、皮下組織 | 皮膚の白色・黒色化、痛みなし |
なぜ水ぶくれはできるのか
水ぶくれは、Ⅱ度熱傷の典型的なサインです。熱によって皮膚の細胞が損傷すると、体は傷ついた組織を修復し、外部の刺激から守るために、血液の液体成分である血漿(けっしょう)を染み出させます。
この液体が、ダメージを受けて剥がれかかった表皮の下に溜まることで、水ぶくれが形成されるのです。水ぶくれは皮膚が自己治癒しようとしている証拠であり、傷を保護するための天然の絆創膏のような役割を果たしています。
水ぶくれの中の液体は何?
水ぶくれの中を満たしている透明または少し黄色がかった液体は、滲出液(しんしゅつえき)と呼ばれます。この液体は、単なる水分ではありません。
傷の治癒を促進する様々な成長因子や、白血球などの免疫細胞を豊富に含んでいて、傷口の乾燥を防ぎ、細菌の侵入をブロックし、新しい皮膚の再生を助けるという非常に重要な働きを担っています。
このため、水ぶくれをむやみに破るべきではないとされるのです。
水ぶくれができないやけどもある
Ⅰ度の軽いやけどでは水ぶくれはできず、赤くなるだけで数日で治癒します。一方で、最も重いⅢ度のやけどでも水ぶくれはできません。
これは、皮膚の全層が破壊されてしまい、液体を溜めておくための表皮の屋根構造そのものが失われてしまうためです。水ぶくれができていないからといって、必ずしも軽症とは限りません。
皮膚の色が白っぽくなっていたり、黒く焦げていたり、痛みを感じない場合は、重症である可能性が高いため、直ちに医療機関を受診してください。
やけど直後に絶対やるべき応急処置
やけどを負ってしまったら、その直後の数分間の対応が、その後の治り具合や跡の残りやすさに大きく影響します。パニックにならず、冷静に適切な応急処置を行うことが何よりも大切です。
すぐに冷やす その重要性と正しい方法
やけどをしたら、何をおいてもまず冷やすことが最優先で、すぐに流水で患部を冷やしてください。
冷やす目的は、単に痛みを和らげるだけではなく、熱によるダメージが皮膚の深層へ進行するのを食い止め、やけどの範囲が広がるのを防ぐという重要な役割があります。
水道の蛇口から直接、勢いを弱めた流水を患部に当て続けるのが最も効果的です。
氷や保冷剤を直接当てるのは、冷やしすぎて凍傷を起こす危険があるため避け、もし流水が使えない状況であれば、濡れタオルなどで冷やすことも有効です。
正しい冷却方法のポイント
- 清潔な流水(水道水)を使う
- 水圧は弱めにする
- 患部全体をしっかりと冷やす
- 氷や保冷剤は直接当てない
冷やす時間の目安
どのくらいの時間冷やせば良いのかは、やけどの程度や範囲によって異なりますが、一般的には痛みがある程度和らぐまで、最低でも15分から30分程度は冷却を続けることが推奨されます。
途中で冷やすのをやめてしまうと、皮膚の内部に残った熱で再びダメージが進行してしまうことがあります。ヒリヒリとした痛みが落ち着くまで、根気よく冷やし続けることが肝心です。
ただし、広範囲のやけどを長時間冷やしすぎると、体温が下がりすぎてしまう低体温症のリスクがあるため、特に小さなお子様や高齢者の場合は注意が必要です。
冷却時間の目安
| やけどの範囲 | 冷却時間の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 指先など狭い範囲 | 15分~30分 | 痛みが和らぐまで続ける |
| 手のひら程度 | 20分~30分 | 流水で継続的に冷やす |
| 広範囲 | 5分~15分 | 低体温症に注意し、濡れタオルで覆う |
衣服の上からやけどした場合の注意点
熱湯や熱い油などが衣服の上からかかってしまった場合、慌てて服を脱ごうとしてはいけません。熱で皮膚と衣服がくっついてしまい、無理に脱ぐと皮膚まで一緒に剥がしてしまう危険があるからです。
このような場合は、衣服の上からそのまま流水をかけて冷やしてください。十分に冷やして熱が取れた後、ハサミなどで衣服を慎重に切りながら、ゆっくりと取り除きます。
もし皮膚に張り付いてしまっている部分は、無理に剥がさずにそのままで医療機関を受診しましょう。
やってはいけないNGな応急処置
昔からの言い伝えや誤った情報に基づいて、不適切な処置をしてしまうケースが後を絶たず、症状を悪化させるだけでなく、感染のリスクを高めるため絶対に避けてください。
アロエや味噌、油などを塗る民間療法は、患部を不潔にし、感染源となる可能性があります。
また、消毒液(アルコールやマキロンなど)は、やけどで傷ついた細胞をさらに傷つけ、治癒を妨げることがあるため、自己判断での使用は推奨されません。応急処置は、あくまでも清潔な水で冷やすことに徹してください。
やけどの水ぶくれ 潰すべきかどうかの判断基準
やけどの応急処置後、多くの人が直面するのが水ぶくれをどう扱うかという問題です。ぷっくりと膨らんだ水ぶくれは見た目にも気になり、つい潰したくなる衝動に駆られるかもしれません。
しかし、その行動が治癒にどのような影響を与えるのか、専門的な視点から理解しておくことが重要です。
原則として水ぶくれは潰さない
皮膚科の基本的な考え方として、やけどでできた水ぶくれは、意図的に潰すべきではありません。水ぶくれの膜(表皮)は、その下の傷ついた真皮を外部の細菌や刺激から守る天然のバリアとして機能しています。
また、内部の滲出液には傷の治癒を促す成分が豊富に含まれていて、この理想的な治癒環境を、わざわざ壊す必要はないのです。
水ぶくれを温存することが、感染を防ぎ、痛みを和らげ、最終的に傷跡をきれいに治すための最善策であると考えてください。
なぜ潰してはいけないのか 感染リスクと治癒の遅れ
水ぶくれを潰してしまうと、保護されていた傷口が露出し、空気中の細菌が侵入しやすい状態になり、傷が化膿する感染症のリスクが格段に高まります。
感染を起こすと、治癒までの期間が長引くだけでなく、炎症が深くまで及ぶことで、色素沈着や肥厚性瘢痕(ひこうせいはんこん)といった目立つ傷跡が残りやすくなります。
また、治癒に必要な成長因子を含んだ貴重な滲出液も失われてしまうため、皮膚の再生が遅れる原因にもなります。
水ぶくれを潰すことのデメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 感染リスクの増大 | 皮膚のバリアが破壊され、細菌が侵入しやすくなる |
| 治癒の遅延 | 治癒成分を含む滲出液が失われ、皮膚の再生が遅れる |
| 痛みの増加 | 傷口が直接外部の刺激にさらされるため、痛みが増す |
| 傷跡のリスク | 感染や炎症により、跡が残りやすくなる |
自然に破れてしまった場合の対処法
注意していても、日常生活の動作の中で水ぶくれが意図せず破れてしまうこともあり、その場合は、慌てずに適切な処置を行いましょう。まず、石鹸をよく泡立て、ぬるま湯で患部を優しく洗い、清潔にします。
破れた水ぶくれの皮は、無理に剥がさないでください。この皮も、まだ傷口を保護する役割を持っています。清潔なガーゼでそっと水分を拭き取った後、ワセリンなどの軟膏を塗り、傷を保護するための被覆材(ドレッシング材)で覆います。
もし、赤みや腫れ、痛みが強くなる、あるいは膿が出るなどの感染の兆候が見られたら、速やかに皮膚科を受診してください。
医療機関で水ぶくれを処置する場合
原則として水ぶくれは潰しませんが、例外的に医療機関で処置を行う場合があります。
水ぶくれが非常に大きく、関節の動きを妨げるほどパンパンに張っている場合や、破れそうなほど緊満が強く、かえって痛みの原因になっている場合です。
このようなケースでは、医師が清潔な環境下で、滅菌された針や注射器を用いて、中の液体だけを慎重に抜き取る(穿刺する)ことがあります。
処置により、圧力が下がって痛みが和らぎ、意図せず大きく破れてしまうのを防ぐことができます。自己判断で針を刺すのは感染のリスクが非常に高いため、絶対にやめましょう。
自宅でできる水ぶくれの正しいケア方法
水ぶくれを潰さずに保護しながら、いかにして治癒を促のか、ここからは、ご家庭でできるスキンケアの方法について解説します。適切なケアは、感染を防ぎ、痛みを軽減し、最終的に傷をきれいに治すためにとても大切です。
患部を清潔に保つ
やけどの傷をケアする上で、最も基本となるのが清潔を保つことです。1日に1回を目安に、石鹸をよく泡立て、泡で患部を優しくなでるように洗います。ゴシゴシと擦るのは厳禁で、水ぶくれを破らないように、細心の注意を払いましょう。
洗浄後は、ぬるま湯のシャワーで泡をきれいに洗い流します。洗浄により、古い軟膏や汚れ、細菌を取り除き、傷を清潔な状態にリセットすることができ、洗った後は、清潔で柔らかいタオルで、押さえるようにして水分を拭き取ります。
適切な被覆材(ドレッシング材)の選び方
洗浄後の傷を保護するために、被覆材(ドレッシング材)を使用します。従来の乾いたガーゼは、傷口の滲出液を吸い取ってしまい、乾燥させることで治癒を妨げたり、交換時に新生した皮膚を剥がしてしまったりすることがありました。
現在では、傷口の潤いを保ちながら保護する、湿潤療法(モイストヒーリング)の考えに基づいた様々な被覆材が市販されています。ハイドロコロイド素材のものは、特に水ぶくれのない浅いやけどに適しています。
水ぶくれがある場合は、非固着性のガーゼやシリコンガーゼの上に、通常のガーゼを重ねて保護するのが一般的です。
主な被覆材の種類と特徴
| 種類 | 特徴 | 適した状態 |
|---|---|---|
| ハイドロコロイド | 傷の潤いを保ち、治癒を促進 | 水ぶくれのない浅いやけど、小さな傷 |
| 非固着性ガーゼ | 傷にくっつきにくく、交換時の痛みが少ない | 水ぶくれがある場合、滲出液が多い傷 |
| フィルム材 | 透明で防水性がある。傷の観察が容易 | ごく浅い傷、水ぶくれの保護 |
軟膏やクリームの正しい使い方
被覆材を貼る前に、医師から処方された軟膏や、市販のワセリンなどを塗布します。軟膏には、感染を防ぐ抗生物質入りのものや、皮膚の炎症を抑えるステロイド入りのものなど、症状に応じて様々な種類があります。
医師の指示に従って適切なものを使いましょう。軟膏を塗る目的は、傷口の保湿と保護で、患部に直接チューブの先をつけず、清潔な綿棒などに取ってから、優しく塗り広げてください。
被覆材の交換頻度と注意点
被覆材の交換は、基本的に1日1回、洗浄と合わせて行います。ただし、滲出液で被覆材が汚れたり、濡れたりした場合は、その都度交換してください。交換の際は、まず丁寧に手を洗い、清潔な状態で行うことが感染予防の観点から重要です。
被覆材を剥がすときは、皮膚を傷つけないようにゆっくりと行いましょう。新しい皮膚は非常にデリケートなので、優しく扱うことを常に心がけてください。
交換時に強い痛みを感じたり、傷の周りが赤く腫れてきたりした場合は、感染のサインかもしれないため、皮膚科医に相談してください。
やけどの跡をきれいに治すためのポイント
痛みが引き、水ぶくれが治まってきた後も、やけどのケアは終わりではありません。ここからのケアが、最終的に傷跡が目立たなくなるかどうかを左右します。
多くの人が望むきれいで滑らかな皮膚を取り戻すために、治癒の最終段階で意識すべき大切なポイントをいくつか紹介します。
湿潤療法の考え方
近年、傷の治療における主流となっているのが湿潤療法(モイストヒーリング)です。これは、傷口を消毒して乾かすという従来の考え方とは異なり、傷から出る滲出液が持つ治癒能力を最大限に活かす方法です。
傷口を乾燥させずに適度な潤いを保つことで、痛みも少なく、皮膚の再生がスムーズに進み、跡が残りにくいことが分かっています。
これまで解説してきた、洗浄と軟膏、被覆材によるケアは、湿潤療法の考え方に基づいています。傷口を乾かさないことが、きれいな治癒への近道です。
湿潤療法と従来療法の比較
| 項目 | 湿潤療法 | 従来療法(乾燥) |
|---|---|---|
| 傷の状態 | 潤いを保つ | 消毒して乾燥させる |
| 治癒速度 | 速い | 遅い |
| 痛み | 少ない | 強い |
| 傷跡 | 残りにくい | 残りやすい |
紫外線対策の重要性
やけどの跡が治りかけている時期の皮膚は、非常にデリケートで、色素沈着を起こしやすい状態にあります。
この時期に紫外線を浴びると、メラニン色素が過剰に生成され、茶色っぽいシミのような跡(炎症後色素沈着)が残ってしまうことがあります。色素沈着は、一度できると消えるまでに長い時間がかかります。
傷が上皮化(薄い皮膚で覆われること)したら、外出時は必ず日焼け止めを塗る、衣類やサポーターで患部を覆うなど、徹底した紫外線対策を少なくとも3ヶ月から半年は続けることが、きれいな肌色を取り戻すために極めて重要です。
栄養と生活習慣の役割
新しい皮膚は、私たちが食事から摂取する栄養素を材料にして作られます。傷の治りをサポートするためには、バランスの取れた食事が欠かせません。
特に、皮膚の主成分であるタンパク質(肉、魚、大豆製品など)や、コラーゲンの生成を助けるビタミンC(果物、野菜など)、皮膚の健康を保つビタミンA(緑黄色野菜など)や亜鉛(牡蠣、レバーなど)を意識して摂取すると良いでしょう。
また、十分な睡眠をとり、喫煙を控えることも、血行を促進し、皮膚の再生能力を高める上で大切です。
皮膚の再生を助ける栄養素
- タンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)
- ビタミンC(パプリカ、ブロッコリー、キウイフルーツ)
- ビタミンA(にんじん、かぼちゃ、ほうれん草)
- 亜鉛(牡蠣、レバー、牛肉)
かゆみが出たときの対処法
傷が治る過程で、かゆみが生じることがよくありますが、これは、皮膚が再生する際にヒスタミンなどの物質が放出されるために起こる生理的な反応です。
しかし、ここで我慢できずに掻きむしってしまうと、せっかく再生してきたデリケートな皮膚を傷つけ、炎症をぶり返したり、傷跡が残る原因になったりします。
かゆい時は、掻く代わりに冷たいタオルで冷やしたり、保湿剤を塗って皮膚の乾燥を防いだりするのが有効です。
かゆみが非常に強い場合は、皮膚科でかゆみ止めの内服薬や外用薬を処方してもらうこともできますので、我慢せずに相談してください。
こんな症状はすぐ病院へ 皮膚科受診の目安
ほとんどの軽いやけどは適切なセルフケアで対応できますが、中には専門的な治療が必要なケースや、危険なサインが隠れている場合もあります。自己判断で様子を見ているうちに、手遅れになってしまうこともあり得ます。
ここでは、どのような場合に医療機関、特に皮膚科を受診すべきか、その具体的な目安について解説します。
やけどの範囲が広い場合
やけどの重症度は、深さだけでなく範囲も重要な判断基準で、大人の場合で体表面積の10%以上、子どもの場合は5%以上のやけどは、入院治療が必要となる可能性があります。
体表面積の目安として、患者さん自身の手のひらの大きさが約1%に相当します。
手のひらを超える範囲のⅡ度熱傷や、それより狭くてもⅢ度熱傷が疑われる場合は、セルフケアで対応できる範囲を超えているので、速やかに医療機関を受診してください。
受診が必要なやけどの範囲の目安
| 対象 | 受診を強く推奨する範囲 |
|---|---|
| 成人 | 体表面積の10%以上(手のひら10枚分以上) |
| 小児 | 体表面積の5%以上(手のひら5枚分以上) |
顔や関節など特殊な部位のやけど
顔、首、手足の指、関節部分、陰部などのやけどは、特殊部位と呼ばれ、特に注意が必要です。顔や首のやけどは、腫れによって気道を圧迫する危険性があるほか、傷跡が残りやすく美容的な問題も大きくなります。
また、手足の指や関節のやけどは、治癒の過程で皮膚がひきつれ(瘢痕拘縮)、動きに障害が残る可能性があります。
手足の指や関節をやけどした場合は、範囲が狭くても専門的な管理が必要となるため、早期に皮膚科や形成外科を受診することが重要です。
強い痛みや感染の兆候がある場合
市販の痛み止めを飲んでも収まらないような強い痛みが続く場合や、感染の兆候が見られる場合は、直ちに受診が必要です。
感染のサインとは、傷の周りが赤く腫れ上がる、熱を持つ、痛みが日ごとに増していく、膿が出る、悪臭がする、といった症状です。感染を放置すると、全身に細菌が回る敗血症などの重篤な状態に陥る危険もあります。
注意すべき感染のサイン
- 傷の周りの赤み、腫れ、熱感の増強
- 痛みが時間とともに強くなる
- 黄緑色の膿が出る
- 傷から不快な臭いがする
- 発熱や悪寒など全身の症状
子どもや高齢者のやけど
小さなお子様やご高齢の方は、皮膚が薄く、成人に比べて重症化しやすい傾向があります。また、自身の症状を正確に伝えられないことや、持病(糖尿病など)の影響で治りが悪いこともあります。
特に乳幼児のやけどは、範囲が狭く見えても、体に対するダメージの割合は大人より大きくなり、脱水にも陥りやすいため、より慎重な対応が必要です。
子どもや高齢者がやけどをした場合は、軽症に見えても、念のため一度医療機関に相談することをお勧めします。
やけどと水ぶくれに関するよくある質問
最後に、やけどや水ぶくれのケアに関して、患者さんから日常の診療でよくいただく質問と回答をまとめました。
- 水ぶくれの液体を自分で抜いてもいい?
-
ご家庭にある針や安全ピンは滅菌されておらず、それを使って水ぶくれを破る行為は、傷口に細菌を持ち込むことにほかなりません。感染のリスクが非常に高く、かえって治りを遅らせ、傷跡をひどくする原因になります。
水ぶくれの中の液体は、傷を治すための大切な成分です。どうしても水ぶくれの張りが強くて痛い、破れそうだという場合は、自己判断で処置せず、皮膚科を受診して清潔な環境で適切な処置を受けてください。
- どんな被覆材を使えばいい?
-
市販の被覆材には様々な種類があり、どれを選べば良いか迷うかもしれません。
水ぶくれができていない浅いやけどや、すでに水ぶくれが破れてしまった小さな傷には、ハイドロコロイド素材のものが適しています。
大きな水ぶくれが破れずに残っている場合は、傷にくっつきにくいシリコンガーゼやワセリンガーゼで覆い、その上から吸収パッドや通常のガーゼを当てて保護するのが良いでしょう。
判断に迷う場合は、薬剤師や皮膚科医に相談するのが最も確実です。
- やけどの跡は完全に消えますか?
-
やけどの跡がどの程度残るかは、やけどの深さに大きく依存します。表皮のみの損傷であるⅠ度熱傷や、真皮の浅い層までのⅡ度熱傷であれば、適切なケアを行えば跡形なく治ることがほとんどです。
しかし、真皮の深い層まで及ぶ深達性Ⅱ度熱傷や、Ⅲ度熱傷の場合は、残念ながら何らかの跡(皮膚の色の変化やひきつれなど)が残る可能性が高くなります。
ただし、初期治療と、その後の紫外線対策や保湿ケアを根気よく続けることで、跡を目立たなくしていくことは可能です。
- 痛みが続くのはなぜ?
-
やけどの痛みは、熱によって皮膚にある知覚神経が刺激されたり、損傷したりすることで生じます。通常、冷却することで痛みは和らぎ、治癒とともに徐々に軽快していきます。
しかし、数日経っても痛みが改善しない、あるいは一度引いた痛みが再び強くなってきた場合は注意が必要です。これは、細菌感染を起こしているサインかもしれません。
感染による炎症が神経をさらに刺激し、痛みを起こしている可能性があります。我慢せずに皮膚科を受診してください。
以上
参考文献
Hasegawa M, Inoue Y, Kaneko S, Kanoh H, Shintani Y, Tsujita J, Fujita H, Motegi SI, Le Pavoux A, Asai J, Asano Y. Wound, pressure ulcer and burn guidelines–1: Guidelines for wounds in general. The Journal of Dermatology. 2020 Aug;47(8):807-33.
Ono I, Gunji H, Zhang JZ, Maruyama K, Kaneko F. A study of cytokines in burn blister fluid related to wound healing. Burns. 1995 Aug 1;21(5):352-5.
Sasaki J, Matsushima A, Ikeda H, Inoue Y, Katahira J, Kishibe M, Kimura C, Sato Y, Takuma K, Tanaka K, Hayashi M. Japanese Society for Burn Injuries (JSBI) clinical practice guidelines for management of burn care. Acute Medicine & Surgery. 2022 Jan;9(1):e739.
Uchinuma E, Koganei Y, Shioya N, Yoshizato K. Biological evaluation of burn blister fluid. Annals of plastic surgery. 1988 Mar 1;20(3):225-30.
Murphy F, Amblum J. Treatment for burn blisters: debride or leave intact?. Emergency Nurse. 2014 Apr 30;22(2).
Sargent RL. Management of blisters in the partial-thickness burn: an integrative research review. Journal of burn care & research. 2006 Jan 1;27(1):66-81.
Swain AH, Azadian BS, Wakeley CJ, Shakespeare PG. Management of blisters in minor burns. British medical journal (Clinical research ed.). 1987 Jul 18;295(6591):181.
SARANTO JR, RUBAYI S, ZAWACKI BE. Blisters, cooling, antithromboxanes, and healing in experimental zone-of-stasis burns. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 1983 Oct 1;23(10):927-33.
Shaw J, Dibble C. Management of burns blisters. Emergency medicine journal. 2006 Aug 1;23(8):648-9.
Weigand DA. How to treat skin cuts, bruises, burns & blisters. Diabetes in the News. 1993 Jan 1;12(1):36-8.