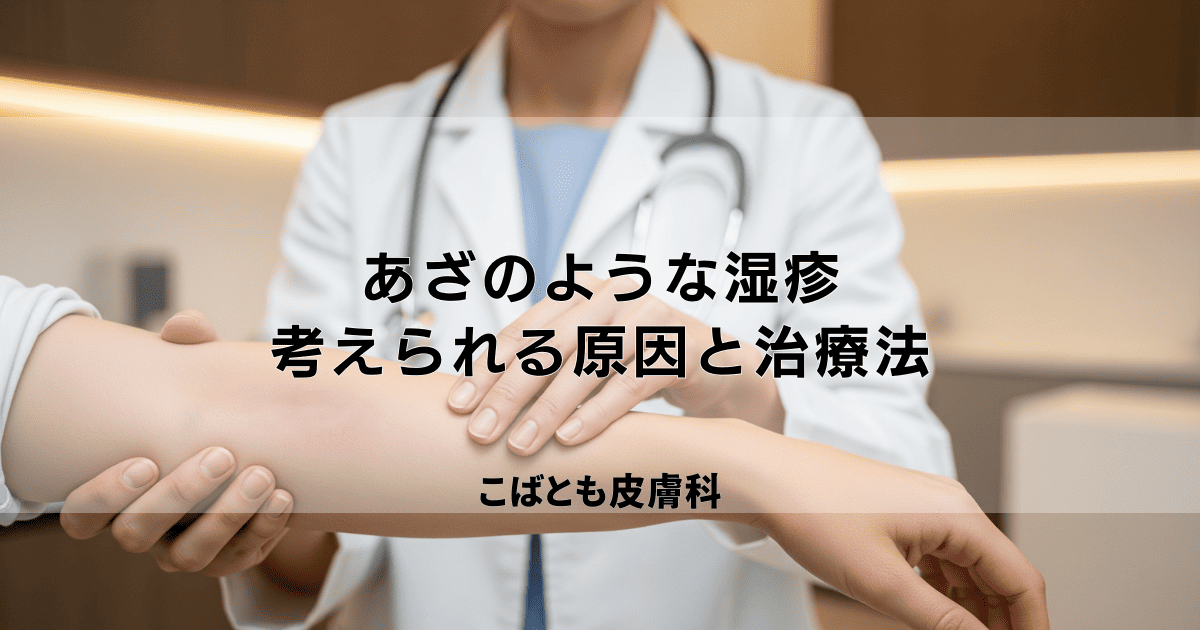ふと気づくと、腕や足に青あざのような、あるいは茶色いシミのような湿疹ができていて、不安に思った経験はありませんか。
ぶつけた記憶もないのに現れたり、かゆみや痛みを伴ったりすると、一体これは何だろうと心配になるものです。
この記事では、あざのように見える湿疹の正体について、考えられる代表的な疾患、原因、そして皮膚科で行う専門的な検査や治療法まで、詳しく解説していきます。
この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士
こばとも皮膚科院長
2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。
こばとも皮膚科関連医療機関
もしかして病気?あざと湿疹の見分け方
体にできた色の変化が、打ち身によるあざなのか、それとも皮膚の病気である湿疹なのか、ご自身で判断するのは難しい場合があります。しかし、いくつかのポイントに注目することで、ある程度の見当をつけることが可能です。
色や形の違いに注目する
まず、患部の色や形をよく観察することが大切です。一般的な打ち身によるあざ(内出血)は、時間の経過とともに色が変化していく特徴があります。
最初は赤紫色や青紫色だったものが、次第に緑色っぽくなり、最後は黄色や茶色になって薄れていき、形も、ぶつけた部分を中心にぼんやりと広がっていることが多いです。
湿疹や皮膚の病気の場合は、色の変化が乏しかったり、特定の形を維持し続けたりする傾向があります。赤みがずっと続いたり、輪郭がはっきりした円形であったり、小さな点状の出血が集まっていたりするなど、その特徴は様々です。
あざと湿疹の一般的な見た目の違い
| 項目 | 一般的なあざ(内出血) | あざのような湿疹 |
|---|---|---|
| 色の変化 | 時間経過で変化(青→緑→黄) | 変化しにくい、または特有の色調 |
| 輪郭 | ぼんやりしていることが多い | はっきりしている、または点状など様々 |
| 盛り上がり | 通常は平坦か少し腫れる程度 | 少し盛り上がる、または平坦なものもある |
痛みやかゆみの有無を確認する
次に、自覚症状の有無も重要な判断材料で、打ち身によるあざは、押すと痛みを感じるのが一般的です。これを圧痛(あっつう)と呼び、ぶつけた直後が痛みのピークで、時間とともにおさまっていきます。
あざのように見える湿疹では、かゆみを伴うことが非常に多いのが特徴です。チクチク、ピリピリとした刺激感や、熱っぽさを感じることもあります。
中には痛みやかゆみがほとんどない疾患もありますが、かゆみがある場合は湿疹の可能性をより強く考えます。
症状が出ている期間を振り返る
いつからその症状があるのか、期間を振り返ることも診断の助けになり、打ち身によるあざは、通常1週間から2週間程度で自然に消えていきます。
もし、数週間にわたって症状が続いている、あるいは一旦消えたように見えても同じような場所に繰り返し現れるという場合は、単なるあざではない可能性が高いでしょう。
症状の経過を記録しておくと、皮膚科を受診した際に、医師が診断する上で非常に有力な情報となります。
セルフチェックの限界と専門医の重要性
ここまでご自身で確認できるポイントを説明しましたが、これらはあくまで目安です。中には、重大な内臓の病気が原因で皮膚に症状が現れているケースも稀にあります。
あざのような湿疹は見た目だけでは判断が難しく、確定診断には専門的な知識と経験が必要です。自己判断で様子を見たり、市販薬を塗り続けたりすることで、かえって症状を悪化させてしまうこともあります。
少しでも気になる症状があれば、安易に自己判断せず、必ず皮膚科専門医に相談することが重要です。
あざのように見える湿疹の代表的な疾患
あざと見間違いやすい皮膚の症状は、いくつかの疾患に分類できます。ここでは、皮膚科の診療でよく見られる代表的なものをいくつか取り上げ、それぞれの特徴を解説します。
色素性紫斑(単純性紫斑・老人性紫斑)
色素性紫斑は、皮膚の毛細血管から微小な出血が起こり、赤血球が血管外に漏れ出すことで生じます。漏れ出た赤血球中のヘモグロビンが分解され、ヘモジデリンという鉄を含む色素となって皮膚に沈着するため、茶色っぽいあざのようです。
すねや足の甲によく見られ、かゆみを伴うことが多く、複数の小さな点状の出血が集まって大きな斑に見えます。
単純性紫斑は若い女性に、老人性紫斑は高齢者の方の腕や手の甲に見られ、わずかな刺激で内出血しやすくなることが原因です。
- 単純性紫斑
- 老人性紫斑
- アレルギー性紫斑病
血管炎
血管炎は、皮膚の血管に炎症が起こる病気の総称で、炎症によって血管の壁がもろくなり、血液が漏れ出して紫斑(出血斑)ができます。少し盛り上がりのある紫斑(触知可能な紫斑)が特徴的で、すねに見られることが多いです。
発熱や関節痛、腹痛などの全身症状を伴うこともあり、注意が必要です。アレルギー反応や感染症、薬剤などが原因となることがあります。
血管炎には様々な種類があり、皮膚だけでなく内臓の血管にも影響を及ぼすことがあるため、皮膚科での正確な診断と、場合によっては内科など他科との連携が大事です。
あざのように見える主な疾患の特徴
| 疾患名 | 主な症状 | 好発部位 |
|---|---|---|
| 色素性紫斑 | 点状の出血、茶褐色の色素沈着、かゆみ | すね、足の甲 |
| 血管炎 | 少し盛り上がった紫斑、全身症状を伴うことも | すね |
| 固定薬疹 | 円形の赤い斑、水ぶくれ、色素沈着 | 全身どこにでも |
固定薬疹
固定薬疹は、特定の薬剤を服用するたびに、体の決まった場所に繰り返し皮膚症状が現れる病気です。円形から楕円形の境界がはっきりした赤い斑点ができ、中心部が少し暗い色調になったり、水ぶくれ(水疱)を伴ったりすることもあります。
症状がおさまった後には、茶色っぽい色素沈着が長期間残るため、あざのように見え、原因となる薬剤を再び服用すると、同じ場所に症状が再発するのが最大の特徴です。原因薬剤としては、解熱鎮痛薬や抗菌薬などが知られています。
接触皮膚炎(かぶれ)
植物や金属、化学物質など、特定の物質が皮膚に触れることで炎症を起こすのが接触皮膚炎、いわゆるかぶれです。原因物質に触れた部分に、かゆみを伴う赤いブツブツや水ぶくれができます。
炎症が強く、掻き壊したりすると、皮膚の下で内出血を起こしたり、炎症が治まった後に色素沈着が残ったりして、あざのように見えることがあります。
原因がはっきりしていることが多いですが、気づかないうちに原因物質に触れているケースも少なくありません。
あざのような湿疹の主な原因
あざのような湿疹がなぜ現れるのか、背景には様々な原因が考えられます。皮膚の症状は、体の内側からのサインであることも少なくありません。
血管の脆弱性によるもの
皮膚の下にある毛細血管がもろくなる(脆弱になる)と、わずかな刺激でも血液が漏れ出しやすくなり、紫斑や内出血の原因となります。血管の脆弱性は、加齢によって自然に起こることがあり、老人性紫斑の主な原因です。
また、ビタミンCの不足や、ステロイド薬の長期使用なども血管の壁を弱くする要因となり得ます。特別な病気がなくても、体質的に血管がもろい人もいます。
症状を引き起こす主な原因の分類
| 原因の分類 | 具体的な要因 | 関連する主な疾患 |
|---|---|---|
| 血管の脆弱性 | 加齢、ビタミン不足、薬剤(ステロイド) | 老人性紫斑、単純性紫斑 |
| アレルギー反応 | 薬剤、食物、感染症、金属、植物 | 血管炎、固定薬疹、接触皮膚炎 |
| 物理的な刺激 | 衣類の摩擦、圧迫、掻き壊し | 色素性紫斑、接触皮膚炎 |
アレルギー反応によるもの
体には、外部から侵入してきた異物を攻撃して体を守る免疫という仕組みがあり、この免疫が、特定の物質に対して過剰に反応してしまうのがアレルギー反応です。
薬剤、食物、ウイルスや細菌などがアレルゲン(アレルギーの原因物質)となって血管炎を起こしたり、特定の薬剤が固定薬疹の原因になったりします。
免疫の働きに異常が生じ、自分自身の血管を攻撃してしまう自己免疫反応が関与することもあります。
- 解熱鎮痛薬
- 抗菌薬
- 降圧薬
- 抗てんかん薬
薬剤の影響によるもの
アレルギー反応とは別に、薬剤そのものの作用や副作用によって、あざのような症状が出ることがあります。
血液をサラサラにする薬(抗血小板薬や抗凝固薬)を服用していると、血が止まりにくくなるため、わずかな打撲でも大きな内出血になったり、紫斑ができやすくなったりします。
また、固定薬疹のように特定の薬剤が原因で皮膚症状が繰り返し起こる場合もあり、新しく薬を飲み始めてから症状が出た場合は、薬剤の影響を考えることが必要です。
物理的な刺激や摩擦によるもの
きつい下着や衣類による締め付け、長時間の正座による圧迫、皮膚を強く掻きむしることなど、外部からの物理的な刺激が原因で毛細血管が破れ、点状の出血や紫斑が生じることがあります。
皮膚が薄く血管がもろくなっている高齢者や、血流が滞りやすい下腿(すね)では、このような外的な要因で症状が出やすい傾向にあります。自分では気づかないうちに、日常生活の中の些細な刺激が原因となっていることも珍しくありません。
あざのような湿疹への対処法
気になる症状が現れたとき、すぐに病院へ行けない場合もあるかもしれません。ここでは、皮膚科を受診するまでの間、症状を悪化させないためにご自身でできる応急処置や注意点について説明します。
安静と冷却
症状が出ている部分に熱っぽさや腫れ、痛みがある場合は、炎症が起きている可能性があります。このようなときは、患部を安静に保ち、保冷剤や氷をタオルで包んだもので優しく冷やすと、炎症や痛みを和らげる助けになります。
ただし、冷やしすぎは血行不良を招く可能性もあるため、1回15分程度を目安にしてください。また、マッサージをしたり、温めたりする行為は、内出血や炎症を助長する可能性があるので避けましょう。
刺激を避けるスキンケア
患部は非常にデリケートな状態です。衣類による摩擦や、掻きむしるなどの刺激は、症状を悪化させる一番の原因となるので、ゆったりとした服装を心がけ、爪は短く切っておきましょう。
入浴時には、ナイロンタオルなどでゴシゴシこすらず、低刺激性の石鹸をよく泡立てて、手で優しく洗うようにします。
洗浄後は、保湿剤を塗って皮膚のバリア機能を保護することも大切で、外部からの刺激を受けにくい健康な皮膚状態を保つことができます。
市販薬を使用する際のポイント
| 成分の種類 | 期待できる作用 | 注意点 |
|---|---|---|
| 抗ヒスタミン成分 | かゆみを抑える | 眠気が出ることがある |
| 非ステロイド性抗炎症成分 | 炎症を和らげる | 接触皮膚炎を起こすことがある |
| ステロイド成分 | 強い炎症を抑える | 自己判断での長期使用は避ける |
市販薬を使用する際の注意点
かゆみが強い場合など、市販の塗り薬を使いたくなるかもしれませんが、原因がはっきりしない段階で薬を使うことにはリスクも伴います。もし市販薬を試すのであれば、まずは薬剤師に相談し、症状に合ったものを選んでもらいましょう。
ステロイド配合の薬は炎症を抑える作用が強いですが、原因によっては症状を悪化させたり、副作用を招いたりすることもあります。
数日間使用しても改善しない、あるいはかえって症状が広がった場合は、すぐに使用を中止し、皮膚科を受診してください。
- 症状が数日経っても改善しない
- 症状の範囲が広がってきた
- かゆみや痛みが強くなってきた
- 水ぶくれやただれができてきた
- 発熱や倦怠感など全身の症状がある
症状が悪化する場合の受診の目安
セルフケアを行っても症状が改善しない、または悪化する場合には、速やかに皮膚科を受診する必要があります。特に、発熱や関節痛、倦怠感といった全身症状を伴う場合や、症状が急激に広がっている場合は、早急な対応が必須です。
放置することで、色素沈着が長く残ってしまったり、背景にある病気が進行してしまったりする可能性があります。不安なまま過ごすよりも、専門医に診てもらうことが、心身の負担を軽減する最も確実な方法です。
皮膚科で行う検査と診断の流れ
皮膚科を受診すると、医師は様々な角度から症状を観察し、原因を突き止めていきます。正確な診断を下すために、どのような診察や検査が行われるのか、流れを知っておくと、安心して受診できるでしょう。
問診で伝えるべき情報
診察は、まず問診から始まり、医師は、患者さんからの情報をもとに、診断の手がかりを探します。
いつから、どこに、どのような症状があるのか、といった基本的な情報に加え、かゆみや痛みの有無、症状の変化、思い当たる原因、過去にかかった病気や現在治療中の病気、アレルギーの有無など、できるだけ詳しく伝えることが重要です。
服用している薬やサプリメントがあれば、お薬手帳など内容がわかるものを持参すると診察がスムーズに進みます。
問診で医師に伝えると良い情報
| カテゴリ | 具体的な内容 | 伝えるポイント |
|---|---|---|
| 症状について | いつから、どこに、どんな症状か | 写真などで経過を記録しておくと分かりやすい |
| きっかけ | 思い当たること(ケガ、薬剤、食事など) | 症状が出る直前の行動を振り返る |
| 既往歴・服薬歴 | 治療中の病気、アレルギー、服用薬 | お薬手帳やサプリメントの現物を持参する |
視診と触診による診察
問診の次は、医師が実際に患部の状態を観察する視診と、手で触れて確認する触診を行い、皮疹の色、形、大きさ、分布、表面の状態(カサカサしているか、ジクジクしているかなど)を詳しく見ます。
さらに、指で触れてみて、硬さや熱っぽさ、盛り上がりの程度、押したときの痛み(圧痛)の有無などを確認します。診察で得られる情報は非常に多く、多くの皮膚疾患は視診と触診、そして問診の内容を総合することで診断が可能です。
ダーモスコピー検査
ダーモスコピーは、ダーモスコープという特殊な拡大鏡を使って、皮膚の表面だけでなく、少し深い部分の色素の分布や血管の状態を詳しく観察する検査です。皮膚にゼリーを塗り、拡大鏡を当てて観察し、痛みは全くありません。
検査によって、内出血によるものか、色素沈着によるものか、あるいは血管の異常によるものかなどを、より詳しく評価することができ、特に、色素性紫斑やほくろとの鑑別などに威力を発揮します。
血液検査や皮膚生検
視診やダーモスコピーでも診断が難しい場合や、全身の病気が疑われる場合には、さらに詳しい検査を行います。
血液検査では、炎症の程度やアレルギーの有無、血液の固まりやすさ、肝臓や腎臓の機能などを調べ、内臓の異常が隠れていないかを確認します。
また、確定診断のために皮膚生検を行うこともあり、これは、患部の皮膚を局所麻酔した上でごく小さく(数ミリ程度)切り取り、顕微鏡で組織の状態を詳しく調べる検査です。
検査により、血管炎の種類を特定するなど、より正確な診断が可能になります。
皮膚科での専門的な治療法
診断が確定したら、原因と症状に合わせて治療が始まります。治療の目的は、現在ある症状を和らげること、原因を取り除き、再発を防ぐことです。
ステロイド外用薬・内服薬
湿疹や血管炎など、皮膚に炎症が起きている場合には、炎症を強力に抑えるためにステロイド薬を使用することが治療の基本です。症状が皮膚に限局している場合は、主に塗り薬(外用薬)を用います。
症状が広範囲に及んでいたり、全身症状を伴ったり、外用薬だけでは効果が不十分な場合には、飲み薬(内服薬)を使用することもあります。
ステロイド薬は医師の指示通りに適切な量と期間で使用すれば、非常に効果的な薬で、自己判断で中止したり、量を変更したりしないことが大切です。
主な治療薬の種類と作用
| 薬剤の種類 | 主な作用 | 対象となる主な疾患 |
|---|---|---|
| ステロイド薬 | 抗炎症作用、免疫抑制作用 | 血管炎、接触皮膚炎、重度の色素性紫斑 |
| 抗ヒスタミン薬 | かゆみの原因物質をブロック | かゆみを伴う多くの皮膚疾患 |
| 止血薬・血管強化薬 | 血管を丈夫にし、出血を予防 | 単純性紫斑、老人性紫斑 |
抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬
かゆみが強い場合には、原因となるヒスタミンの働きをブロックする抗ヒスタミン薬の飲み薬が処方されます。かゆみは、掻き壊しによる症状の悪化や色素沈着の増悪につながるため、抑えることは治療において非常に重要です。
また、アレルギー反応が関与していると考えられる場合には、抗アレルギー薬を使用し、過剰な免疫反応を抑えます。薬には眠気が出やすいタイプと出にくいタイプがあるので、ライフスタイルに合わせて医師と相談して選択します。
原因薬剤の中止と変更
固定薬疹や薬剤によるアレルギー性血管炎など、特定の薬剤が原因であることが判明した場合は、原因薬剤の使用を中止することが最も重要な治療です。原因薬剤を中止すれば、新たな皮疹は出なくなり、既存の症状も徐々に改善していきます。
ただし、持病の治療のためにその薬がどうしても必要な場合もあり、その際は、処方している主治医と連携を取りながら、アレルギー反応を起こしにくい別の種類の薬に変更することを検討します。
- 色素性紫斑の色素沈着
- 血管炎後の色素沈着
- 固定薬疹の色素沈着
レーザー治療
炎症がおさまった後に残った茶色い色素沈着に対して、美容的な観点から治療を希望される場合には、レーザー治療が選択肢となることがあります。
色素沈着の原因であるヘモジデリンやメラニンに反応する特定の波長のレーザーを照射することで、色を薄くする効果が期待できます。
ただし、レーザー治療は保険適用外となることが多く、また、すべての色素沈着に効果があるわけではありません。治療の適応や効果、リスクについては、医師と十分に相談した上で判断する必要があります。
治療後の注意点と再発予防
皮膚科での治療によって症状が改善した後も、良い状態を維持し、再発を防ぐためには、日々のセルフケアがとても大事です。ここでは、治療後や症状が落ち着いているときに心がけたい注意点について説明します。
処方された薬の正しい使い方
医師から処方された薬は、指示された用法・用量を必ず守ってください。特にステロイド外用薬は、良くなったからといって自己判断で急にやめてしまうと、症状が再燃(リバウンド)することがあります。
医師の指示に従って、徐々に薬の強さや回数を減らしていくことが大切です。飲み薬についても同様で、決められた期間、きちんと飲み続けることが再発防止につながります。
日常生活でのスキンケアのポイント
| 場面 | ポイント | 具体的な行動 |
|---|---|---|
| 入浴時 | 優しく洗う | 低刺激性の石鹸を使い、手で泡洗浄する |
| 入浴後 | 保湿を徹底する | 水分を拭き取ったらすぐに保湿剤を塗る |
| 衣服 | 刺激の少ない素材を選ぶ | 木綿など柔らかい素材を選び、締め付けを避ける |
日常生活でのスキンケアのポイント
皮膚のバリア機能を正常に保つことは、あらゆる皮膚トラブルの予防の基本で、毎日の保湿ケアを習慣にしましょう。
お風呂上がりは皮膚が乾燥しやすいため、タオルで優しく水分を押さえるように拭き取った後、すぐに保湿剤を全身に塗るのが効果的です。
また、紫外線は皮膚にダメージを与え、色素沈着を濃くする原因にもなるので、外出時には日焼け止めを塗る、帽子や日傘を利用するなど、紫外線対策も忘れずに行ってください。
再発のサインを見逃さない
一度良くなったとしても、体質や生活習慣によっては、再び同じような症状が現れる可能性があります。固定薬疹やアレルギーが関与する疾患では、原因物質に接触することで再発します。
どのような状況で症状が出やすいかを自分自身で把握しておくことも予防につながります。もし、治療した場所に再び赤みやかゆみ、点状の出血など、再発を疑うサインが見られたら、早めに皮膚科を受診してください。
よくある質問
ここでは、あざのような湿疹に関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 治療期間はどのくらいですか?
-
治療にかかる期間は、疾患の種類や重症度、治療への反応性によって大きく異なります。
軽度の色素性紫斑や接触皮膚炎であれば、数週間から1ヶ月程度の治療で改善することが多いですが、血管炎などで内服薬による治療が必要な場合は、数ヶ月単位での治療になることもあります。
また、炎症がおさまった後の色素沈着が完全に消えるまでには、半年から1年以上かかることも珍しくありません。
- 費用はどのくらいかかりますか?
-
費用は、検査内容や治療法によって変わります。通常の診察と外用薬・内服薬の処方であれば、健康保険が適用され、自己負担額(3割負担の場合)は数千円程度が一般的です。
血液検査や皮膚生検などの詳しい検査を行う場合は、追加で数千円から1万円程度の費用がかかることがあります。
レーザー治療など、保険適用外の自費診療については、医療機関によって料金設定が異なるため、治療を開始する前に確認することが必要です。
- 放置するとどうなりますか?
-
軽症の色素性紫斑など、時間とともに自然に改善していくものもありますが、多くの場合、放置すると何らかのリスクを伴います。
かゆみを伴う湿疹を放置すると、掻き壊して皮膚に傷がつき、細菌感染(二次感染)を起こすことがあります。
また、血管炎のように全身の病気の一症状として皮膚に症状が出ている場合、放置すると内臓などに重篤な合併症を起こす危険性もあります。
見た目の問題としても、炎症が長引くほど色素沈着が濃く、消えにくくなる傾向があります。早期の受診が重要です。
- 子供にも同じような症状は出ますか?
-
お子さんにも、あざのような湿疹が見られることがあり、代表的なものに、アレルギー性紫斑病(IgA血管炎)があります。
主に幼児から小学生くらいのお子さんに見られる血管炎の一種で、足やお尻に少し盛り上がった紫斑がたくさんできるのが特徴です。
腹痛や関節痛を伴うことも多く、腎臓に影響が出ることもあるため、小児科や皮膚科での適切な診断と管理が必要です。他にも、打ち身や虫刺され、アトピー性皮膚炎の掻き壊しなどが原因であざのように見えることもあります。
お子さんの皮膚に気になる症状を見つけたら、まずは専門医に相談してください。
以上
参考文献
De Moor R, Koroki Y, Wu DB, Yu DY, Tohyama M, Ohyama C. A retrospective study on the incidence, management and risk factors of skin rash in patients with advanced prostate cancer in Japan. BMC urology. 2023 Apr 28;23(1):73.
Furue M, Yamazaki S, Jimbow K, Tsuchida T, Amagai M, Tanaka T, Matsunaga K, Muto M, Morita E, Akiyama M, Soma Y. Prevalence of dermatological disorders in Japan: a nationwide, cross‐sectional, seasonal, multicenter, hospital‐based study. The Journal of dermatology. 2011 Apr;38(4):310-20.
Katayama I, Kohno Y, Akiyama K, Ikezawa Z, Kondo N, Tamaki K, Kouro O. Japanese guideline for atopic dermatitis. Allergology International. 2011;60(2):205-20.
Saito R, Matsuoka Y. Granulomatous pigmented purpuric dermatosis. The Journal of dermatology. 1996 Aug;23(8):551-5.
Nishioka K, SARASHI C, KATAYAMA I. Chronic pigmented purpura induced by chemical substances. Clinical and Experimental Dermatology. 1980 Jun;5(2):213-8.
Clark WG, Jacobs E. Experimental nonthrombocytopenic vascular purpura: a review of the Japanese literature, with preliminary confirmatory report. Blood. 1950 Apr 1;5(4):320-8.
Toshihiko N. Current status of large and small vessel vasculitis in Japan. International journal of cardiology. 1996 Aug 1;54:S91-8.
Kobayashi S, Fujimoto S, Takahashi K, Suzuki K. Anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis, large vessel vasculitis and Kawasaki disease in Japan. Kidney and Blood Pressure Research. 2010 Nov 10;33(6):442-55.
Sada KE, Yamamura M, Harigai M, Fujii T, Dobashi H, Takasaki Y, Ito S, Yamada H, Wada T, Hirahashi J, Arimura Y. Classification and characteristics of Japanese patients with antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis in a nationwide, prospective, inception cohort study. Arthritis research & therapy. 2014 Apr 23;16(2):R101.
Shiohara T, Mizukawa Y. Fixed drug eruption: easily overlooked but needing new respect. Dermatology. 2002 Jul 7;205(2):103-4.