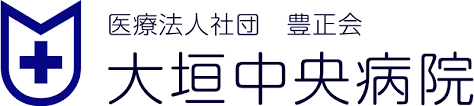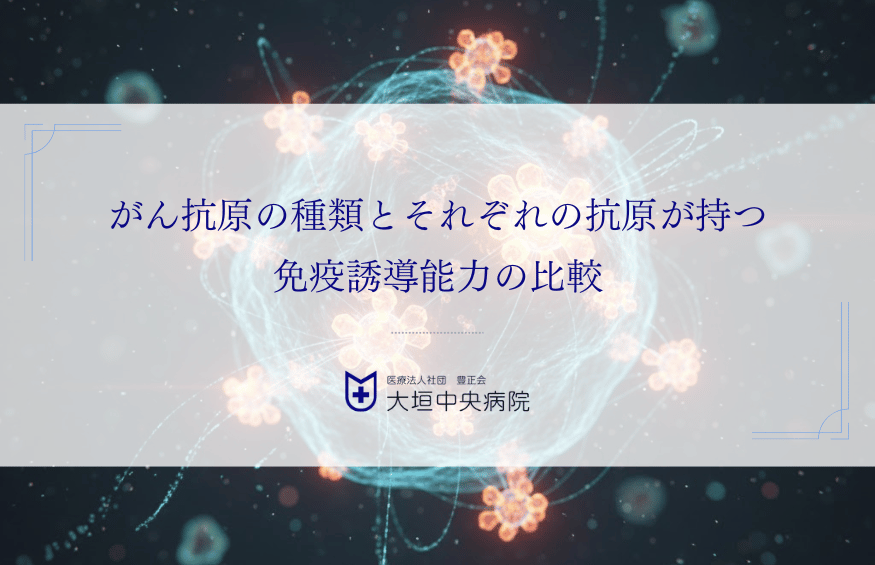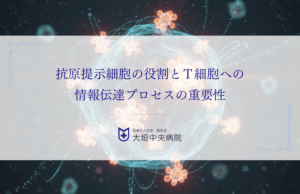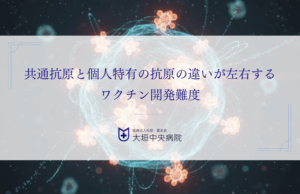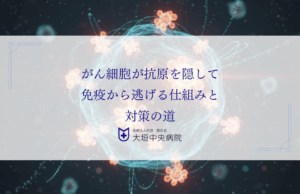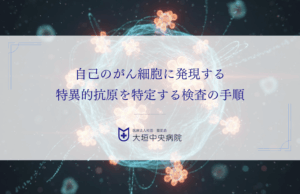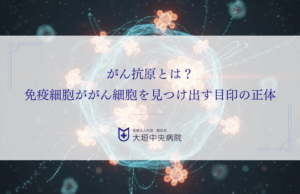がん治療において、免疫の力を利用する「がん免疫療法」が注目を集めています。その中核を担うのが、免疫細胞に攻撃目標を教える「がん抗原」です。
しかし、一口にがん抗原と言っても、その正体は多種多様です。患者さんご自身の遺伝子変異に由来する独自の抗原から、多くのがん患者さんに共通して発現する抗原、さらにはウイルス由来のものまで存在します。
治療の成否を分けるのは、どの抗原を標的にするかという選択です。それぞれの抗原は、免疫細胞を呼び覚ます強さ(免疫原性)や、正常細胞への影響の度合いが異なります。
本記事では、主要ながん抗原の種類を整理し、それぞれの特徴と免疫を誘導する能力の違いについて詳しく解説します。
ご自身の治療方針を検討する上で、正しい知識を持つことが納得のいく選択へとつながります。
がん抗原の基礎知識と分類の重要性
がん細胞の表面に提示される目印であるがん抗原は、免疫システムが「排除すべき敵」として認識するための重要な手がかりとなります。
この目印の種類によって、免疫反応の強さや特異性が大きく変わるため、治療戦略を立てる上で分類の理解が重要です。
免疫システムが敵を見分ける仕組み
私たちの体内に備わる免疫システム、特にT細胞と呼ばれるリンパ球は、常に体内をパトロールしています。
T細胞は、細胞の表面に提示されている小さなタンパク質の断片(ペプチド)をチェックし、それが「自己(自分自身の正常なもの)」か「非自己(異物)」かを判断します。
がん細胞には、正常な細胞には存在しない、あるいは極めて微量しか存在しない特有のタンパク質断片が現れます。これこそががん抗原です。
免疫細胞がこのがん抗原を「非自己」と認識して初めて、がん細胞への攻撃命令が下ります。したがって、抗原が「いかに正常細胞と異なっているか」という点が、免疫を強く刺激する鍵となります。
主要ながん抗原のカテゴリー
がん抗原は、その発生由来や発現パターンによっていくつかのグループに分けられます。
大きく分けると、遺伝子変異によって新しく生まれた抗原、本来は精巣などにしかないはずの抗原、正常細胞にもわずかにあるが増えすぎている抗原、そしてウイルス感染によって持ち込まれた抗原などです。
これらの分類を知ることは、どのタイプのワクチンや治療法が自分の体質やがんの状態に適しているかを判断する材料となります。
分類による特性の違い
それぞれのカテゴリーには明確なメリットとデメリットが存在します。例えば、ある抗原は攻撃力が非常に高いものの、作成に時間がかかる場合があります。
一方で、別の抗原は多くの患者さんにすぐに使える利便性がありますが、免疫反応の持続性が課題となることもあります。
医師が治療計画を提案する際、どの抗原をターゲットにしているかを知ることで、期待できる効果や想定される副作用のリスクをより深く理解できるようになります。
主な分類の名称
- ネオアンチゲン(新生抗原)
- がん精巣抗原(CTA)
- 分化抗原
- 過剰発現抗原
- ウイルス抗原
ネオアンチゲンが持つ高い特異性と免疫原性
ネオアンチゲンは、がん細胞に生じた遺伝子変異によって新しく作り出された異常なタンパク質であり、正常細胞には存在しないため、極めて強力な免疫反応を引き起こします。
個人の遺伝子変異に由来する完全な異物
がん細胞は増殖を繰り返す中で、遺伝子のコピーミスを起こし、変異を蓄積します。この変異によって生じたタンパク質のアミノ酸配列は、生まれつき持っている正常な配列とは異なります。
免疫システムは、生まれた時から体内にあるものを「自己」として寛容し、攻撃しないように教育されています。
しかし、ネオアンチゲンは後天的に発生した完全に新しい配列であるため、免疫システムはこれを明確な「異物(非自己)」として認識します。
そのため、正常細胞を誤って攻撃するリスクが理論上極めて低く、がん細胞だけを狙い撃ちにする理想的な標的となります。
強力なキラーT細胞の誘導
免疫細胞の中でも、がん細胞を直接破壊する能力を持つのがキラーT細胞です。ネオアンチゲンを標的とした場合、このキラーT細胞の誘導効率が非常に高いことが分かっています。
正常細胞にも存在する抗原を標的にした場合、免疫システムは暴走を防ぐためにブレーキをかけがちですが、ネオアンチゲンに対してはそのブレーキがかかりにくいためです。
この特性により、近年注目されている免疫チェックポイント阻害薬の効果予測因子としても、ネオアンチゲンの数が重視されています。
個別化医療としての側面
ネオアンチゲンは患者さん一人ひとりの遺伝子変異に依存するため、他人と同じものは基本的に存在しません。
したがって、ネオアンチゲンを標的とする治療は、患者さんごとのがん組織を採取し、遺伝子解析を行ってオーダーメイドでワクチンなどを作成する必要があります。
これは高い効果が期待できる反面、製造にかかる時間やコストが課題となります。しかし、その手間をかけるだけの価値がある強力な免疫誘導能力を持っています。
正常抗原とネオアンチゲンの認識の違い
| 比較項目 | 正常細胞由来の抗原 | ネオアンチゲン |
|---|---|---|
| 免疫の認識 | 自己(攻撃を抑制) | 非自己(強く攻撃) |
| 正常組織への影響 | 副作用のリスクあり | 極めて低い |
| 治療の個別性 | 多くの人で共通 | 完全オーダーメイド |
| 免疫誘導力 | 中〜弱 | 極めて強い |
がん精巣抗原(CTA)の広範な発現と安全性
がん精巣抗原は、通常は精巣や胎盤などの限られた組織にのみ発現しているタンパク質ですが、がん化すると様々な種類のがんで発現するようになり、安全かつ有効な標的として機能します。
発現部位の限定性による安全性
がん精巣抗原(Cancer-Testis Antigen)という名前の通り、この抗原は健康な成人では精巣(男性)や胎盤などにしか存在しません。
重要な点は、精巣は「免疫特権部位」と呼ばれ、免疫細胞の攻撃対象になりにくい特殊な環境にあることです。また、細胞表面に抗原を提示するためのMHC分子(HLA)が精巣細胞にはほとんど発現していません。
つまり、全身の免疫システムから見れば、精巣にあるこの抗原は見えない状態にあります。
したがって、がん細胞でこの抗原が発現した場合、免疫細胞はそれを攻撃しますが、精巣は攻撃を受けないため、重篤な副作用を避けることができます。
多くのがんで共有される標的
ネオアンチゲンが個人ごとに異なるのに対し、がん精巣抗原は多くのがん患者さんで共通して見られます。
例えば、NY-ESO-1やMAGE-A4といった抗原は、食道がん、肺がん、膀胱がん、悪性黒色腫など、多岐にわたるがん種で発現が確認されています。
このため、オーダーメイドではなく、あらかじめ準備された製剤を使用する「既製品(オフ・ザ・シェルフ)」としての治療開発が可能になります。多くの患者さんが恩恵を受けやすい抗原タイプと言えます。
免疫原性の高さと臨床応用
本来発現しないはずの場所(がん細胞)に現れるため、免疫システムにとっては異物として認識されやすく、比較的高い免疫原性を持ちます。
これまでに数多くのがんワクチン臨床試験が行われており、その安全性と一定の効果が実証されてきました。
特に、強力なT細胞受容体(TCR)を用いた遺伝子改変T細胞療法などの標的としても有望視されており、現在も活発に研究開発が進んでいます。
代表的ながん精巣抗原と関連するがん
| 抗原名 | 特徴 | よく見られるがん種 |
|---|---|---|
| NY-ESO-1 | 最も免疫原性が高い一つ | 食道がん、卵巣がん、滑膜肉腫など |
| MAGE-A4 | 歴史的に研究が進んでいる | 肺がん、食道がん、膀胱がんなど |
| KK-LC-1 | 日本での発見、胃がんで高発現 | 胃がん、肺がん、乳がんなど |
分化抗原と自己免疫反応のリスク管理
分化抗原は、特定臓器の正常細胞にも存在するタンパク質ががん細胞でも維持されているものであり、組織特異的な治療が可能ですが、正常組織への攻撃リスクを考慮する必要があります。
組織の起源を反映する抗原
細胞が特定の臓器や組織へと成熟(分化)する過程で発現する特有のタンパク質を分化抗原と呼びます。がん細胞になっても、その起源となった組織の特徴を残している場合にこの抗原が見られます。
代表的な例として、悪性黒色腫(メラノーマ)におけるMART-1やgp100、前立腺がんにおけるPSAなどが挙げられます。これらは、その臓器由来のがんであることを示す明確な目印となります。
正常細胞との区別が困難な課題
分化抗原の最大の問題点は、その臓器の正常な細胞も同じ抗原を持っていることです。
例えば、悪性黒色腫の治療としてメラニン色素に関連する分化抗原を標的にして免疫を強く活性化させると、がん細胞だけでなく、正常な皮膚のメラニン細胞も攻撃を受けてしまうことがあります。
その結果、白斑(皮膚の一部が白くなる現象)などの自己免疫疾患に似た症状が現れることがあります。
これは免疫が正しく働いている証拠でもありますが、生命維持に不可欠な臓器の抗原を標的とする場合には、重篤な副作用につながるリスクがあります。
効果と安全性のバランス
分化抗原を標的とする場合、医師は治療効果と副作用のバランスを慎重に見極めます。
皮膚の色素脱失のように生命に直結しない副作用であれば許容されることもありますが、肺や心臓などの重要臓器に関連する分化抗原を標的にすることは困難です。
しかし、特定の組織に限定して攻撃を集中させたい場合には有効な選択肢となり得ます。
免疫誘導能力としては、正常細胞にもある「自己」の成分であるため、通常はネオアンチゲンほど強力ではありませんが、適切なアジュバント(免疫増強剤)などを組み合わせることで治療効果を高める工夫を行います。
分化抗原のメリットとリスク
| 視点 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| メリット | 特定のがん種で高率に発現する | 診断マーカーとしても利用可能 |
| デメリット | 正常組織への誤爆(副作用) | 標的臓器の重要度による |
| 免疫誘導 | 自己寛容により抑制されやすい | 強力な活性化手段が必要 |
過剰発現抗原の汎用性と免疫学的課題
過剰発現抗原は、正常細胞にも微量に存在するものの、がん細胞で爆発的に増えているタンパク質であり、多くのがん種で標的にできる汎用性を持ちますが、免疫の寛容を突破する工夫が必要です。
量の違いを認識させる戦略
がん細胞は無秩序に増殖するために、増殖シグナルに関連するタンパク質を異常に多く作り出すことがあります。例えば、HER2(ハーツー)やWT1、CEAなどがこれに該当します。
これらのタンパク質自体は正常な細胞にもわずかに存在しますが、がん細胞ではその数が数十倍から数百倍にも達します。
この圧倒的な「量」の差を利用して、免疫細胞に「これは異常事態だ」と認識させ、がん細胞を優先的に攻撃させるのがこのタイプの狙いです。
広範ながん治療への適用
過剰発現抗原は、特定のがんだけでなく、多種多様ながんで共通して見られることが大きな強みです。WT1タンパク質などは、白血病から固形がんまで幅広く発現していることが知られています。
そのため、一つのがん抗原ワクチンが、乳がん、胃がん、肺がんなど、異なる臓器のがん患者さんに適用できる可能性があります。
多くの患者さんにとって治療の選択肢となりやすい、アクセスの良さが特徴です。
自己寛容の壁とその克服
正常細胞にも少ないながら存在するため、免疫システムはこれらの抗原に対して「弱い自己」として認識しており、攻撃を控えるような仕組み(免疫寛容)が働いています。
そのため、単に抗原を投与するだけでは、強い免疫反応が起きにくい傾向があります。
この壁を越えるために、免疫細胞を強力に刺激する薬剤を併用したり、抗原の構造を一部改変して免疫細胞に見つけやすくしたりする技術が開発されています。
高い発現量という特徴を活かしつつ、いかに免疫のブレーキを外すかが治療成功の鍵を握ります。
よく知られる過剰発現抗原の例
- WT1(白血病、肺がん、膵臓がんなど多岐にわたる)
- HER2(乳がん、胃がん、食道がんなど)
- CEA(大腸がん、胃がん、肺がんなど)
- MUC1(膵臓がん、乳がんなど)
- p53(変異型だけでなく野生型の過剰発現も含む)
ウイルス抗原による強力な免疫反応の誘導
ウイルス抗原は、ウイルス感染が原因で発生したごく一部のがんにおいて、ウイルス由来のタンパク質を標的とすることで、ネオアンチゲン同様に強力かつ特異的な免疫反応を引き起こします。
完全な異物としての認識
一部のがんは、ウイルス感染が発症の引き金となっています。
子宮頸がんや中咽頭がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)、肝細胞がんの原因となる肝炎ウイルス(HBV, HCV)、成人T細胞白血病の原因となるHTLV-1などが代表例です。
これらのがん細胞からは、ヒトの遺伝子にはないウイルス由来のタンパク質が発現しています。免疫システムにとって、これらは混じりけのない「完全な異物」です。
そのため、自己寛容の影響を全く受けず、非常に激しい攻撃反応を誘導することができます。
予防と治療の両面でのアプローチ
ウイルス抗原の特徴は、がんになる前の予防段階から活用できる点です。HPVワクチンやB型肝炎ワクチンは、ウイルスに対する免疫を事前につけることで、感染を防ぎ、結果としてがんを予防します。
すでにがんが発症してしまった場合でも、がん細胞がウイルス抗原を出し続けている限り、それを標的とした治療用ワクチンや免疫療法が高い効果を発揮する可能性があります。
ウイルス由来のがんであることは不幸なことですが、免疫療法の観点からは「明確な標的がある」という有利な状況とも言えます。
適用できるがん種の限定
ウイルス抗原を標的とした治療は非常に強力ですが、当然ながらウイルス感染が関与していないがんには使えません。
日本人のがん全体で見ると、ウイルス関連がんは全体の数割程度です。
自分が罹患しているがんがウイルス由来のものかどうかを検査で確認することが、この強力な治療戦略を選択するための第一歩となります。
主なウイルスと関連がんおよび標的抗原
| ウイルス | 関連するがん | 標的となる抗原例 |
|---|---|---|
| HPV | 子宮頸がん、中咽頭がん | E6、E7タンパク質 |
| HBV / HCV | 肝細胞がん | ウイルス表面抗原など |
| EBV | 悪性リンパ腫、上咽頭がん | EBNA1、LMP2 |
| HTLV-1 | 成人T細胞白血病 | Taxタンパク質 |
抗原タイプ別免疫誘導能力の総合比較
これまで解説した各抗原の免疫誘導能力を比較すると、非自己としての性質が強い抗原ほど免疫を強く活性化させますが、汎用性や製造の難易度とはトレードオフの関係にあります。
「非自己」の度合いが強さを決める
免疫誘導能力の序列を決める最大の要因は、免疫システムがどれだけその抗原を「異物」とみなすかです。
この観点から見ると、ウイルス抗原とネオアンチゲンがトップクラスの強さを誇ります。
これらはヒトの正常な遺伝子セットには存在しない配列を持つため、T細胞による認識が鋭敏で、排除しようとする働きが強く出ます。
一方で、過剰発現抗原や分化抗原は、元が正常細胞由来であるため、免疫原性という純粋な強さでは一歩劣る傾向にあります。
治療選択における現実的な解
免疫誘導力が強ければ強いほど良い治療かというと、必ずしもそうとは限りません。ネオアンチゲンは強力ですが、解析と製造に数ヶ月を要することもあり、進行の早いがんには間に合わないリスクもあります。
対して、WT1などの過剰発現抗原やがん精巣抗原を標的とした治療は、あらかじめ製剤化できるため、診断後すぐに治療を開始できる利点があります。
また、複数のがん抗原を組み合わせて投与することで、互いの弱点を補い合い、相乗効果を狙う「カクテル療法」のようなアプローチも研究されています。
これからの抗原選択の視点
現代のがん免疫療法では、単一の抗原に頼るのではなく、患者さんのがん細胞がどの抗原をどれくらい出しているか(発現プロファイル)を詳細に調べることが標準になりつつあります。
強力なネオアンチゲンが見つかればそれを、見つかりにくい場合や急を要する場合はがん精巣抗原や過剰発現抗原を利用するなど、状況に応じた柔軟な使い分けが進んでいます。
自分のがんが持つ「顔つき(抗原のパターン)」を知ることが、納得のいく治療への近道です。
抗原タイプ別の免疫誘導力と特徴のまとめ
| 抗原タイプ | 免疫誘導力 | 正常細胞への影響 |
|---|---|---|
| ウイルス抗原 | 極めて強い | なし |
| ネオアンチゲン | 非常に強い | 極めて低い |
| がん精巣抗原 | 強い | ほぼなし(精巣以外) |
| 過剰発現抗原 | 中程度 | 低いが注意が必要 |
| 分化抗原 | 中〜弱い | あり(標的臓器による) |
よくある質問
がん抗原や免疫療法について、患者さんやご家族から寄せられることの多い疑問についてお答えします。
- 複数のがん抗原を同時に標的にすることはできますか?
-
はい、可能です。実際に、複数のがん抗原を混ぜて投与する多価ワクチンや、複数の抗原を標的とする治療法は積極的に研究されています。
がん細胞は賢く、一つの抗原だけを攻撃されると、その抗原を隠して攻撃から逃れようとする性質(抗原消失)を持っています。
複数の抗原を同時に狙うことで、がん細胞の逃げ道を塞ぎ、治療効果を高め、再発を防ぐ効果が期待されています。
- 自分の体にどのがん抗原があるか、どうすれば分かりますか?
-
がん組織の一部を採取して調べる「病理検査」や「遺伝子パネル検査」、あるいは血液中の成分を調べる検査によって確認します。
近年では、がん組織の遺伝子を網羅的に解析することで、ネオアンチゲンの有無や、WT1やNY-ESO-1などの抗原がどれくらい強く発現しているかを調べることが可能になってきています。
治療を受ける医療機関で、抗原検査が可能かどうか相談することをお勧めします。
- 免疫誘導力が弱い抗原だと、治療効果は期待できないのでしょうか?
-
決してそのようなことはありません。
抗原単体の免疫原性が弱くても、免疫反応を補助する薬剤(アジュバント)を工夫したり、免疫のブレーキを外す免疫チェックポイント阻害薬と併用したりすることで、十分な治療効果を引き出せることが分かっています。
抗原の強さだけで決まるのではなく、免疫環境全体をどのように活性化させるかという総合的な戦略が重要です。
- ネオアンチゲン治療は誰でも受けられますか?
-
理論上はどのがん種でもネオアンチゲンが発生する可能性がありますが、実際に治療に適した質の良いネオアンチゲンが見つかるかどうかは個人差があります。
一般的に、紫外線やタバコなどの影響で遺伝子変異が多く蓄積しているがん(メラノーマや肺がんなど)の方が見つかりやすい傾向にあります。
一方で、変異の少ない小児がんなどでは見つけるのが難しい場合もあります。事前の遺伝子解析によって、適用の可能性を判断します。
参考文献
HERBERMAN, Ronald B. Immunogenicity of tumor antigens. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Reviews on Cancer, 1977, 473.2: 93-119.
BLANKENSTEIN, Thomas, et al. The determinants of tumour immunogenicity. Nature Reviews Cancer, 2012, 12.4: 307-313.
SMITH, Christof C., et al. Alternative tumour-specific antigens. Nature Reviews Cancer, 2019, 19.8: 465-478.
SCHMIDT, Maike; LILL, Jennie R. MHC class I presented antigens from malignancies: A perspective on analytical characterization & immunogenicity. Journal of proteomics, 2019, 191: 48-57.
DAVDA, Jasmine, et al. Immunogenicity of immunomodulatory, antibody-based, oncology therapeutics. Journal for immunotherapy of cancer, 2019, 7.1: 105.
FINN, Olivera J. Human tumor antigens yesterday, today, and tomorrow. Cancer immunology research, 2017, 5.5: 347-354.
HAEN, Sebastian P., et al. Towards new horizons: characterization, classification and implications of the tumour antigenic repertoire. Nature Reviews Clinical Oncology, 2020, 17.10: 595-610.
JÄGER, D.; JÄGER, E.; KNUTH, A. Immune responses to tumour antigens: implications for antigen specific immunotherapy of cancer. Journal of clinical pathology, 2001, 54.9: 669-674.
JHUNJHUNWALA, Suchit; HAMMER, Christian; DELAMARRE, Lélia. Antigen presentation in cancer: insights into tumour immunogenicity and immune evasion. Nature Reviews Cancer, 2021, 21.5: 298-312.
VIGNERON, Nathalie. Human tumor antigens and cancer immunotherapy. BioMed research international, 2015, 2015.1: 948501.
がん抗原の役割に戻る