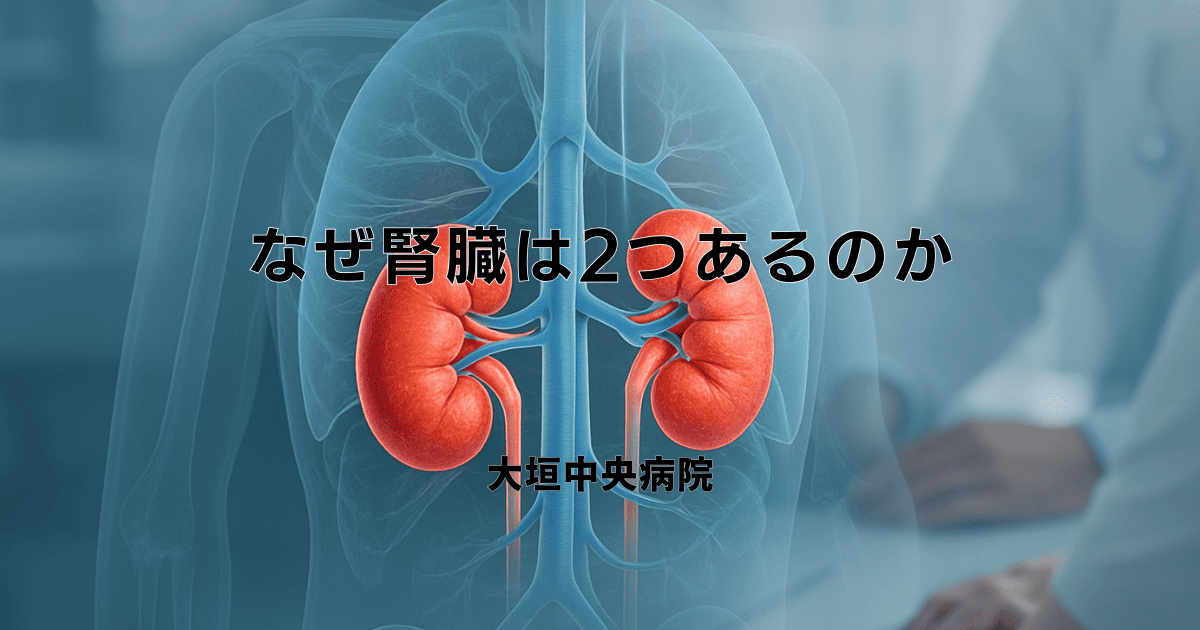私たちの身体には腎臓が左右に2個ずつ存在しています。なぜわざわざ腎臓二つが備わっているのか、意外と知られていないかもしれません。
老廃物や水分バランスを調節する重要な器官として機能する腎臓は、身体の健康状態を保つうえで欠かせない存在です。もしも腎機能が低下すると、血液をうまくろ過できず、将来的に透析が必要になる場合もあります。
この記事では、腎臓2つある理由や構造・役割だけでなく、機能低下の原因や生活習慣との関わり、透析との関係などを幅広く解説し、患者さんご自身や大切な人の腎臓を守るための考え方をまとめました。
人体における腎臓の基本構造
腎臓なぜ2つ備わっているのかを理解するには、そもそも腎臓がどのように構成されているのかを知ることが大切です。豆のような形状と左右一対の存在感は広く知られていますが、その内側には複雑な組織構造があります。
まずは腎臓の部位や特徴を押さえてみましょう。
腎臓の主な部位の概要
腎臓の構造は大きく分けて皮質・髄質・腎盂の3つに区分されます。皮質には糸球体やボーマン嚢が集まり、髄質にはヘンレ係蹄などが並んでいます。そして腎盂は尿が集まるスペースです。
尿を生成する仕組み
尿の生成には、血液が糸球体でろ過される過程が欠かせません。老廃物とともに水分や電解質がボーマン嚢に移動し、その後、ヘンレ係蹄や集合管で再吸収と分泌を経て最終的に尿として形をととのえます。
血液ろ過と再吸収のバランス
腎臓二つそれぞれが毎日何百リットルもの血液をろ過することで、体内の老廃物と余分な水分を尿として排出します。一方で、身体に必要な電解質や栄養素は再吸収するため、体内環境が極度に乱れないようにコントロールをしています。
腎臓とホルモン分泌
腎臓には血圧調節や赤血球を増やすホルモン生成など、多面的な役割が詰まっています。レニンやエリスロポエチンなどがその代表例で、ただのろ過器官に留まらない点が腎臓の特徴といえるでしょう。
腎臓の主な部位と特徴
| 部位 | 特徴 | 役割 |
|---|---|---|
| 皮質 | 糸球体やボーマン嚢が分布 | 血液をろ過する起点になる |
| 髄質 | ヘンレ係蹄や集合管が並ぶ | 水分と電解質の再吸収を調節する |
| 腎盂 | 尿が集まる場所 | 尿を膀胱へ送り出す |
腎臓が担う主要な役割
腎臓2つあることで、身体には多様なメリットがあります。老廃物の排出はもちろん、水分・電解質バランスの調節や血圧のコントロール、ホルモン分泌など、私たちが健康に生きるうえで重要な働きを複合的に支えています。
老廃物と毒素の排出
食事で取り込まれた栄養素や水分は必要分だけが体内で利用され、残りは老廃物や毒素として排出しなければなりません。腎臓はこれらをろ過し、尿として排出する重要なフィルターとして機能します。
水分バランスの維持
人体は約60%が水分で構成されていますが、その量は常に一定ではありません。飲水や食事で得た水分、発汗や呼吸で失った水分を腎臓が調整し、むくみや脱水から身体を守ります。
電解質の調節と血圧管理
ナトリウム・カリウム・カルシウムなどの電解質は、筋肉や神経の働きにとって重要です。腎臓二個の働きによってこれらのイオン濃度を適切に保ち、レニン・アンジオテンシン系によって血圧をコントロールします。
ホルモン産生による全身への影響
エリスロポエチンは赤血球の産生を促し、レニンは血圧の調節に寄与します。また活性型ビタミンDを生成し、骨の健康維持にもかかわるなど、多彩なホルモン作用が身体全体に波及します。
腎機能維持に役立つポイント
- 塩分のとりすぎを控える
- 十分な水分摂取を心がける
- たんぱく質量に留意する
- 規則正しい生活リズムを保つ
腎臓機能と関わる主な役割一覧
| 役割 | 具体的な内容 | 健康への影響 |
|---|---|---|
| 老廃物排出 | 尿生成による排出 | 有害物質や余分な水分の排泄 |
| 水分バランス維持 | 過剰または不足分を調整 | むくみ・脱水の予防 |
| 電解質調節 | ナトリウムやカリウムなど | 筋肉や心臓機能を安定させる |
| 血圧管理 | レニンを介した血圧調節 | 高血圧や低血圧のリスク低減 |
| ホルモン分泌 | エリスロポエチンなど | 赤血球増加や骨強度への影響 |
腎臓なぜ2つあるのかについて
腎臓2つある理由は、単純なバックアップ機能だけにとどまりません。一見すると左右同じように働き、どちらかが損傷しても残る腎臓で代償可能というイメージが強いですが、実際はより複雑です。
二つ存在する背景には、効率的なろ過機能や生命維持にかかわる複数の要素が絡んでいます。
バックアップ機能の側面
片方を傷めたときに、もう片方がある程度カバーできるというのは事実です。片側を摘出しても一定の機能を保てる場合があるのは、腎臓二個の余力がもともと大きいからです。
しかし、一方で片側に頼りきった状態が長く続くと、将来的に透析が必要になるリスクも高まります。
体液量の多さへの対応
人間の体内では血液だけでなく細胞外液・細胞内液など多量の水分が常に循環しています。腎臓二つで効率よくろ過・再吸収を行うことで、体液量の微妙な変化にも柔軟に対応できます。
老廃物の連続的排出
腎臓は24時間休まず働き続ける臓器です。腎臓なぜ2つ用意されているかを考えると、常時ろ過とホルモン調節を行うには高い処理能力が求められることがわかります。
二個同時に活動するからこそ、身体をきれいに保つサイクルを途切れさせずに機能できます。
免疫やホルモン産生への寄与
血液を効率的にろ過するだけでなく、赤血球を増やすエリスロポエチンや血圧を調整するレニンなど、多岐にわたるホルモン産生を行う必要があります。腎臓二つが連携してこそ、全身の代謝バランスを細やかにコントロールできます。
腎臓が2個あることで期待できる利点
| 利点 | 具体例 |
|---|---|
| 処理能力の向上 | 毎日の老廃物排出や水分調整が効率化 |
| 機能低下時の代償作用 | 一方にトラブルがあってももう一方が補う |
| ホルモン産生の安定 | 血圧調節・造血など複数の仕組みを安定させる |
腎臓機能の低下が起こる原因
腎臓二つあっても、生活習慣や疾病の影響によって機能が低下することがあります。腎臓の障害は初期段階で症状が出にくい特徴があり、気づいたときには大きく機能が落ちているケースも珍しくありません。
生活習慣の乱れ
高塩分の食生活や過度の飲酒、喫煙などが重なると、腎臓への負担が増大します。血圧の上昇や血管障害を引き起こしやすくなり、結果として腎臓にダメージを与えます。
糖尿病や高血圧との関連
糖尿病や高血圧は腎機能低下の大きなリスク要因です。血糖値や血圧が慢性的に高い状態が続くと、腎臓の細い血管にも負担がかかり、やがてろ過能力が落ちてしまう場合があります。
加齢による変化
人間が加齢するにつれて全身の臓器機能は少しずつ衰えますが、腎臓においても同様です。加齢に伴う腎機能の低下は避けにくい部分がありますが、日々のケアや定期的な検査で進行を緩やかにすることが重要となります。
薬剤性の腎機能障害
抗生物質や鎮痛薬など、一部の薬剤によって腎機能が損なわれるケースがあり、医師は処方の際に腎機能を考慮します。自己判断で長期にわたって薬を乱用することは危険です。
腎機能低下の主な原因と対策
| 原因 | 具体的な対策 |
|---|---|
| 高塩分食 | 減塩により血圧負担を軽くする |
| 肥満 | 適度な運動で体重をコントロールする |
| 慢性高血糖 | 血糖値を定期的に測定し食事療法を取り入れる |
| 喫煙 | 禁煙で血管損傷を防ぐ |
| 薬の乱用 | 医師や薬剤師の指示を守る |
透析が必要になる仕組み
腎臓がろ過機能を担う臓器である以上、機能が大幅に落ちたときは透析で血液を人工的にろ過しなければなりません。透析は体外循環で不要物を取り除く血液透析や、自宅で行いやすい腹膜透析などがあります。
腎不全への進行
腎機能が著しく落ち、GFR(糸球体ろ過量)が一定の値を下回ると腎不全と診断されます。この状態になると毒素や余分な水分を十分に排出できず、体内に有害物質が蓄積します。
血液透析と腹膜透析
血液透析は血液をダイアライザーという装置に通し、老廃物と水分を除去する方法です。一方の腹膜透析はお腹の中にカテーテルを入れ、透析液を用いて腹膜をろ過膜とする方法です。どちらも腎臓二つの代わりとなる大切な治療です。
透析生活と合併症
透析を長く続けると、骨や血管などに負担がかかり、合併症が出現しやすくなります。そのため、透析を開始する前から腎臓をなるべく保護する考え方が大切です。
透析治療へ至らないための意識
高血圧や糖尿病の管理、塩分摂取の制限、早期受診など、腎臓がダメージを受けないように予防的な取り組みを継続することが望まれます。腎臓なぜ2つあるかを理解し、それぞれをケアする意識が将来の透析回避につながります。
透析に関わる治療法の特徴
| 治療 | 方法 | 利点と注意点 |
|---|---|---|
| 血液透析 | 専用の装置で血液をろ過 | 週3回通院が必要になるが、体液調整が安定しやすい |
| 腹膜透析 | 腹腔を透析の場として利用 | 在宅で行いやすいが腹腔感染リスクがある |
腎臓2つあることと日常生活の関係
腎臓二個が正常に働いていると、自覚症状がほとんどないまま健康を支える存在になります。とはいえ、一旦バランスが崩れると高血圧・むくみ・貧血などさまざまな症状が現れ、生活の質に影響を及ぼす場合があります。
食事管理と腎臓の健康
日常的に摂取する食品の塩分量やたんぱく質量は、腎臓を支えるうえで重要です。味付けが濃くなりがちな方は、調味料を見直したり、外食中心の方はメニュー選択を工夫して余計な負担を減らすと良いでしょう。
水分摂取のバランス
水分を取らなすぎると脱水状態になりやすく、腎臓への血流が減少します。一方で過度に摂取するとむくみや血圧上昇を招きやすいため、体調や季節に合わせて適量を意識することが必要です。
運動習慣の効果
軽いウォーキングやストレッチは血流を向上させ、腎臓二つに栄養や酸素を行き渡らせます。過激な運動ではなく、継続できる有酸素運動を習慣化するのが大切です。
ストレスと腎機能
ストレスが増えると血圧も上昇し、腎臓に悪影響が及ぶことがあります。適度な休息やリラックス方法を取り入れて、自律神経やホルモンバランスを安定させることが望ましいです。
腎臓を保護するための生活習慣
- 塩分を控えた食事を心がける
- 定期的な運動で血流を促進する
- 十分な睡眠で回復を助ける
- ストレス対策として趣味やリラックス法を取り入れる
腎臓二個を守るセルフケアのポイント
腎臓の健康維持は日頃の習慣づくりが大きく左右します。腎臓二つがそろって機能している間に、できるだけ良いコンディションを保つことが将来の透析予防にもつながります。
食事と栄養管理
特に気をつけたいのが塩分やたんぱく質の過剰摂取です。日本人の食卓は味噌汁や漬物など塩分を多く含むものが多く、日頃から意識しないと高塩分になりがちです。
タンパク質も過剰に取ると腎臓負担が大きくなるため、野菜や果物とバランスをとることが肝要です。
血圧と血糖のコントロール
高血圧は腎臓機能を弱める大きなリスクファクターであり、糖尿病も同様に腎臓の血管を傷めます。定期的な血圧測定や血糖値チェックを行い、医師に相談しながら生活習慣や投薬を調整することが必要です。
定期検査の意義
腎臓はダメージを受けても症状が出にくい臓器なので、定期検査による早期発見が重要です。尿検査や血液検査でクレアチニンや尿タンパクなどを確認し、異常を感じる前に対処を始めることが望まれます。
腎臓と塩分・水分の関係
身体にとって塩分は必要量を守れば味方になりますが、過剰になると血圧を上げて腎臓のろ過機能を低下させます。また水分摂取が少なすぎる場合も、血液が濃縮され腎臓に負担が及ぶため、適切な摂取量を心がけてください。
自宅で気をつけたい観察項目
| 観察項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 体重の増加 | 短期間で急に増えた場合はむくみや水分過剰を疑う |
| 尿の色や回数 | 極端に濃い色や回数の減少は脱水や腎不全の兆候かもしれない |
| 血圧測定 | 普段より高い傾向が続くなら要注意 |
| 浮腫 | 手足やまぶたのむくみは腎機能低下のサインになり得る |
よくある質問
腎臓なぜ2つ存在するのか、また透析に関する不安を抱えている方は多いようです。よく寄せられる質問をいくつか紹介します。
- 腎臓二つとも悪くなったら必ず透析が必要ですか?
-
両方の腎臓機能が大幅に低下した場合は、透析を行う可能性が高まります。腎機能を維持するために早めの受診と対策が不可欠です。
- 片方の腎臓を失ったらすぐに腎不全になるのでしょうか?
-
健康なもう片方の腎臓が残っていれば、すぐに腎不全になるとは限りません。ただし、1個だけでは余力が少なくなるので、従来以上に生活習慣の改善と定期チェックが大切です。
- 血液透析と腹膜透析の違いはどれくらいありますか?
-
血液透析は病院で専門の装置を使って行う方法で、週3回ほど通院するのが一般的です。腹膜透析は自宅で行いやすい反面、腹腔の感染リスクを管理する必要があります。
それぞれのライフスタイルに合った選択を医師と相談することが望ましいです。
- 健康診断で腎機能の低下を指摘された場合、どんな行動を取ればいいですか?
-
血液検査や尿検査の詳細結果を確認し、まずは医師の指示に従うことが重要です。運動・食事・水分量などの生活習慣を見直し、重症化を防ぐためにも早めに専門的なケアを開始してください。
役立つ日常管理のポイント
- 血圧と体重を定期的に記録して変化を把握する
- 食事の塩分やカロリー量を見直す
- 疲れをためないように睡眠の質を上げる
- 不安や疑問があれば医療機関へ早めに相談する
病院受診時に確認しておきたい項目
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 検査数値 | クレアチニンや尿タンパク、eGFRを把握する |
| 治療計画 | 投薬や食事指導など今後のケアプラン |
| 生活習慣 | 運動や食事、水分バランスの指導 |
| 合併症リスク | 糖尿病や高血圧のコントロールも含める |
以上
参考文献
SMITH, Homer W. Comparative physiology of the kidney. Journal of the American Medical Association, 1953, 153.17: 1512-1514.
NATOCHIN, Yuri V. Evolutionary aspects of renal function. Kidney international, 1996, 49.6: 1539-1542.
BARANSKI, Andrzej. Basic Anatomy of the Kidney, Ureters and the Urinary Bladder, and Their Functions. In: Kidney Transplantation: Step-by-Step Surgical Techniques. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 1-32.
GALLARDO, Pedro A.; VIO, Carlos P. Functional anatomy of the kidney. In: Renal Physiology and Hydrosaline Metabolism. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 7-28.
SMITH, Homer William. The kidney: structure and function in health and disease. Oxford University Press, 1951.
DRESSLER, Gregory R. The cellular basis of kidney development. Annu. Rev. Cell Dev. Biol., 2006, 22.1: 509-529.
COSTANTINI, Frank; KOPAN, Raphael. Patterning a complex organ: branching morphogenesis and nephron segmentation in kidney development. Developmental cell, 2010, 18.5: 698-712.
ECKARDT, Kai-Uwe, et al. Evolving importance of kidney disease: from subspecialty to global health burden. The Lancet, 2013, 382.9887: 158-169.
AIELLO, Leslie C.; WHEELER, Peter. The expensive-tissue hypothesis: the brain and the digestive system in human and primate evolution. Current anthropology, 1995, 36.2: 199-221.
WEBSTER, Angela C., et al. Chronic kidney disease. The lancet, 2017, 389.10075: 1238-1252.