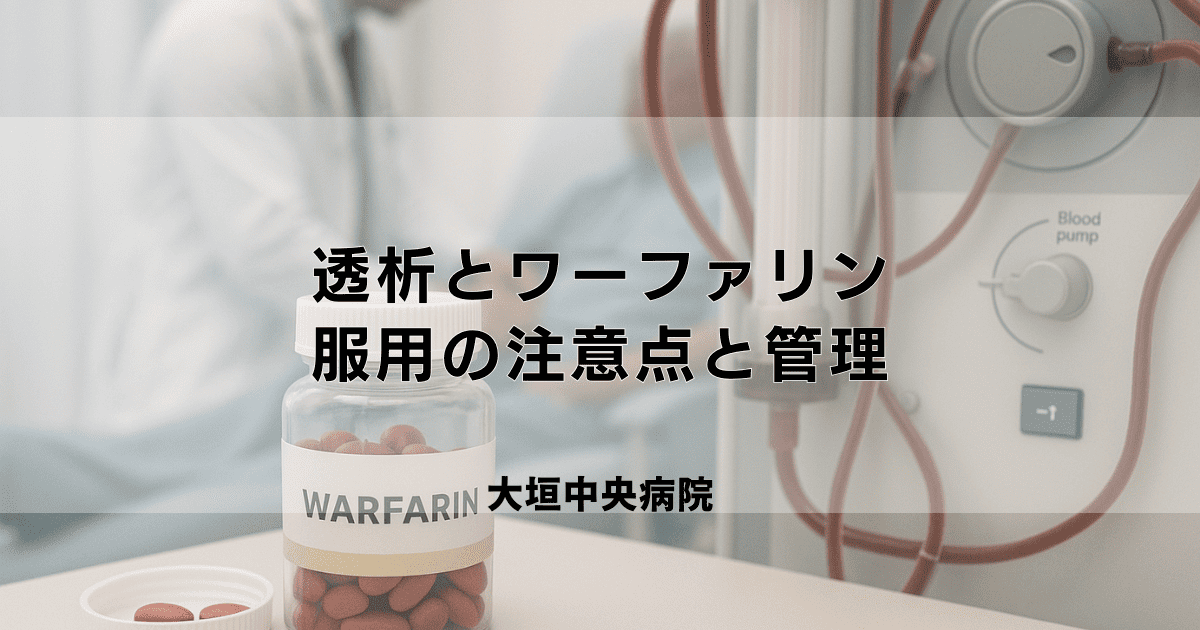透析治療を受けながら、ワーファリンというお薬を服用している方も少なくないでしょう。
ワーファリンは血液を固まりにくくする重要な薬ですが、食事や他の薬の影響を受けやすく、透析患者さんにおいては、より一層きめ細やかな管理が求められます。
なぜ透析患者さんにワーファリンが必要なのか、そして、服用にあたっては何に気をつけるべきなのか。
この記事では、ワーファリンの基本的な働きから、透析患者さん特有の注意点、食事や日常生活での管理のポイントまで、分かりやすく解説していきます。
ワーファリンとはどのような薬か
ワーファリンは、数十年にわたり世界中で使用されてきた歴史のある薬です。その名前を聞いたことがある方も多いでしょう。
まず、この薬がどのような働きを持ち、なぜ重要なのか、その基本的な役割について理解を深めることが、安全な服用の第一歩となります。
血液を固まりにくくする抗凝固薬
ワーファリンは、血液をサラサラにする薬と表現されることがありますが、より正確には血液の凝固、つまり固まる働きを抑える薬の抗凝固薬です。
私たちの体には、出血した際に血を固めて止血する仕組みがありますが、何らかの原因で血管の中で血液が固まりやすくなると、血の塊(血栓)ができてしまいます。ワーファリンは、血栓ができるのを防ぐために用いる重要な薬です。
血栓は、いわば血管の中にできるかさぶたのようなもので、これが血流をせき止めてしまいます。
なぜ血液が固まるのを防ぐ必要があるのか
血管の中でできた血栓は、それ自体が血流を妨げるだけでなく、血流に乗って移動し、脳や心臓、肺などの重要な臓器の血管を詰まらせることがあります。
これが脳梗塞や心筋梗塞、肺塞栓症といった、命に関わる重篤な病気(血栓塞栓症)の原因となります。ワーファリンを服用する大きな目的は、危険な血栓塞栓症を予防し、生命と健康を守ることです。
ワーファリンが働く仕組み
血液が固まるためには、ビタミンKという物質の働きによって作られる、複数の凝固因子と呼ばれるタンパク質が必要です。ワーファリンは、肝臓でこのビタミンKが働くのを妨げることで、凝固因子が作られるのを抑えます。
凝固因子が十分に作られなくなると、血液が固まるまでにかかる時間が長くなり、血液が固まりにくい状態を維持し、血栓の形成を防ぎます。効果が現れるまでに数日かかり、また効果が切れるのにも時間がかかるのが特徴です。
ワーファリンの作用点
| 物質 | 役割 | ワーファリンの作用 |
|---|---|---|
| ビタミンK | 肝臓で血液凝固因子を作るのを助ける。 | このビタミンKの働きを阻害する。 |
| 血液凝固因子 | 血液を固めるために働くタンパク質。 | 結果として、凝固因子の産生が抑制される。 |
他の抗凝固薬との違い
近年、ワーファリン以外にも直接経口抗凝固薬(DOAC)と呼ばれる新しいタイプの抗凝固薬が登場しています。
DOACは、食事の影響を受けにくく、効果が安定しているという利点がありますが、腎機能が低下している患者さんでは使用が難しい場合があります。
透析患者さんにおいては、長年の使用実績があり、投与量の細かい調整が可能であること、また薬価が比較的安いことなどから、現時点でもワーファリンが選択されることが多いのが実情です。
どちらの薬が適しているかは、患者さん一人ひとりの状態を総合的に判断して決定します。
なぜ透析患者さんにワーファリンが必要になるのか
透析治療を受けている患者さんは、そうでない方と比べて血栓ができやすい、あるいは血栓予防が特に重要になる特定の状態を合併しやすい傾向があります。ここでは、透析患者さんがワーファリンを服用する主な理由について、解説していきます。
心房細動による脳梗塞の予防
心房細動は、心臓の中の心房という部屋が不規則に細かく震える不整脈の一種です。
心房がうまく収縮しないため、心房内で血液がよどみ血栓ができやすくなり、血栓が脳に飛んで血管を詰まらせると、重篤な脳梗塞(心原性脳塞栓症)を引き起こします。
透析患者さんは、体液量の変動や電解質の異常、心臓への持続的な負担などから心房細動を合併しやすく、予防のためにワーファリンが広く用いられます。
シャント閉塞の予防と治療
透析治療の生命線であるバスキュラーアクセス(シャント)は、繰り返す穿刺や血流の変化により、血管の内膜が厚くなったり、血栓で詰まったり(閉塞)することがあります。
特に、シャントトラブルを繰り返す患者さんや、人工血管を使用している患者さんでは、閉塞予防目的でワーファリンを使用することもあります。
また、閉塞してしまったシャントをカテーテル治療や手術で再開通させた後に、再閉塞を防ぐ目的で処方されることもあります。
シャントトラブルとワーファリン
- シャント狭窄・閉塞のハイリスク者への予防
- シャント血栓除去術後の再閉塞予防
- 人工血管グラフトの開存率向上
その他の血栓・塞栓症のリスク
心房細動以外にも、透析患者さんはさまざまな血栓・塞栓症のリスクを抱えています。例えば、心臓の弁の病気(弁膜症)や、心機能が低下した心不全、足の静脈に血栓ができる深部静脈血栓症などです。
疾患によってできた血栓が、体の重要な部分に飛んでいくのを防ぐためにも、ワーファリンによる抗凝固療法が必要となります。
透析患者における血栓ができやすい背景
透析患者さんは、なぜ血栓ができやすいのでしょうか。背景には複数の要因が複雑に関与していて、腎機能の低下に伴う尿毒症環境は、血液の性状を変化させ、凝固を促進する因子を増やします。
また、透析治療そのものによる血液への物理的な刺激や、除水による血液濃縮、そして多くの患者さんが合併している動脈硬化や心機能低下などが、総合的に血液が固まりやすい状態を作り出しているのです。
透析患者の血栓形成リスク因子
| 分類 | 具体的な因子 |
|---|---|
| 疾患・合併症 | 心房細動、心不全、動脈硬化、糖尿病、高血圧 |
| 治療関連 | 透析回路との接触、シャント血管への刺激、除水による血液濃縮 |
| 身体的要因 | 高齢、長期臥床、低栄養状態、炎症の持続 |
ワーファリンの効果を測る指標 PT-INR
ワーファリンは効きすぎると出血の危険性が高まり、効かなすぎると血栓予防の効果が得られないという、治療域の狭い薬です。そのため、薬の効果が適切な範囲にあるかを定期的に血液検査で確認することが極めて重要になります。
PT-INRとは何か
PT-INR(ピーティー・アイエヌアール)は、プロトロンビン時間国際標準比の略で、血液の固まりやすさを世界共通の基準で示す指標です。
プロトロンビン時間(PT)は、血液が固まるまでの時間を測定するものですが、この値は検査に用いる試薬によって変動してしまいます。
そこで、この試薬による差をなくし、どの施設で測定しても同じ基準で評価できるように国際的に標準化したものがINRです。
健康な人のPT-INRは約1.0であり、ワーファリンを服用するとこの数値が大きくなり、数値が大きいほど、血液が固まりにくい状態であることを意味します。
なぜ定期的な測定が重要なのか
ワーファリンの効果は、食事内容や他に服用している薬、体調の変化など、さまざまな要因で変動するため、一度決めた量を飲み続けていれば良いというわけではありません。
治療開始時や薬の量を変更した時、体調を崩した時などは、頻繁に測定が必要になります。
状態が安定すれば、月に1回程度の測定となりますが、定期的にPT-INRを測定し、その値に応じてワーファリンの投与量を微調整することで、常に治療目標の範囲内に効果をコントロールし続けることが重要です。
目標とするPT-INRの範囲
目標とするPT-INRの値は、ワーファリンを服用する目的となる疾患や、患者さんの年齢、出血リスクなどを考慮して個別に設定します。
一般的に推奨されているのは、心房細動による脳梗塞予防の場合、70歳未満では2.0から3.0、70歳以上では1.6から2.6の範囲です。
透析患者さんにおいては、出血リスクも高いため、より慎重な目標設定が求められ、場合によってはこれよりも低い目標値とすることもあります。
疾患別の一般的なPT-INR目標値
| 対象疾患 | 目標PT-INR | 備考 |
|---|---|---|
| 心房細動(70歳未満) | 2.0 – 3.0 | 血栓予防効果と出血リスクのバランスをとる。 |
| 心房細動(70歳以上) | 1.6 – 2.6 | 高齢者は出血しやすいため、目標値をやや低めに設定。 |
| 静脈血栓塞栓症 | 1.5 – 2.5 | 疾患や治療期間により目標値は異なる場合がある。 |
PT-INRに影響を与える要因
PT-INRの値は非常にデリケートで、さまざまな要因によって変動します。食事に含まれるビタミンKの量が最もよく知られていますが、それ以外にも多くの要因があります。
PT-INRを変動させる主な要因
- 食事(ビタミンKの摂取量)
- 他の薬剤との相互作用(併用薬)
- アルコールの摂取(特に多量飲酒)
- 体調の変化(発熱、下痢、嘔吐など)
- 肝機能の状態
透析患者さんにおけるワーファリン服用の注意点
透析患者さんがワーファリンを服用する場合、腎機能が正常な方とは異なる、特別な配慮が必要です。出血のリスクが高まる一方で、長期的な副作用にも注意を払いましょう。
出血リスクの増大
透析患者さんは、尿毒症の影響で血小板の機能が低下しており、もともと出血しやすい傾向があり、そこにワーファリンを服用することで、さらに出血のリスクが高まります。
消化管出血や脳出血は重篤な合併症につながるため、細心の注意が必要です。シャント穿刺後の止血に時間がかかることも、出血リスクのサインの一つで、わずかな出血の兆候も見逃さず、早期に対処することが大切になります。
血管石灰化への影響
血管石灰化とは、血管の壁にカルシウムが沈着し、血管が硬くもろくなる状態です。透析患者さんは、リンやカルシウムの代謝異常により、血管石灰化が進行しやすいことが知られています。
ワーファリンは、ビタミンKの働きを抑えますが、ビタミンKは血管の石灰化を抑制するタンパク質(マトリックスGlaタンパク質)の活性化にも関わっています。
そのため、ワーファリンの長期服用が血管石灰化を助長する可能性が指摘されており、注意深い観察が必要です。
透析による薬の除去
ワーファリンは、ほとんどが血液中のアルブミンというタンパク質と強く結合しているため、透析治療によって体外に除去されることはほとんどありません。
透析日と非透析日で服用量を変える必要はなく、毎日決められた量を服用することが基本です。自己判断で服用を調整することは危険ですので、絶対にやめましょう。
他の薬剤との相互作用
ワーファリンは、非常に多くの薬と相互作用を起こし、効果を強めたり弱めたりすることが知られています。透析患者さんは、降圧薬やリン吸着薬、ビタミン剤など、多くの薬を併用していることが多いため、特に注意が必要です。
市販の風邪薬や痛み止め、漢方薬でも影響が出ることがあり、新しく薬を始める場合や、中止する場合には、必ず主治医や薬剤師に相談してください。
ワーファリンと相互作用を起こす主な薬剤の例
| 作用 | 薬剤の例 |
|---|---|
| 効果を強める薬 | 一部の抗生物質、抗真菌薬、痛み止め(NSAIDs)、脂質異常症治療薬など |
| 効果を弱める薬 | 一部の抗てんかん薬、ビタミンK製剤、結核治療薬など |
食事における重要な注意点 ビタミンKとの関係
ワーファリンの管理において、食事は非常に重要な要素です。特に、ビタミンKという栄養素との関係を正しく理解することが、薬の効果を安定させるための鍵となります。
ビタミンKがワーファリンの効果を弱める理由
ワーファリンはビタミンKの働きを阻害することで効果を発揮するため、食事からビタミンKを大量に摂取すると、ワーファリンの作用が打ち消されてしまい、薬の効果が弱まってしまいます。
その結果、血液が固まりやすくなり、血栓症のリスクが高まることになります。この関係を理解することが、食事管理の基本です。
ビタミンKを多く含む食品
ビタミンKは、主に緑色の濃い野菜や海藻類に多く含まれています。
特に納豆は、食品としてビタミンKを多く含むだけでなく、腸内で納豆菌がビタミンKを産生するため、極めて含有量が多く、ワーファリン服用中は原則として摂取を禁止します。
また、クロレラや青汁といった健康食品もビタミンKを豊富に含むため、注意が必要です。
ビタミンKを特に多く含む食品の例
- 納豆
- 青汁、クロレラ
- パセリ、しそ、春菊、ほうれん草(おひたし)などの緑黄色野菜
- 海苔
食事管理の基本的な考え方
ワーファリン服用中の食事で最も大切なのは、ビタミンKの摂取量を毎日できるだけ一定に保つことです。
特定の食品を完全に禁止するのではなく、ビタミンKを多く含む食品を一度に大量に食べたり、逆に全く食べなくなったりといった、極端な食生活を避けることが重要です。
毎日バランスの取れた食事を心がけ、食生活を大きく変える際には、事前に主治医や管理栄養士に相談しましょう。
サプリメントや健康食品の注意点
自己判断でサプリメントや健康食品を摂取することは、非常に危険です。中には、ビタミンKや、ワーファリンの効果に影響を与える成分が含まれているものがあります。
例えば、セント・ジョーンズ・ワート(セイヨウオトギリソウ)はワーファリンの効果を弱め、イチョウ葉エキスやEPA/DHAは効果を強める可能性があります。
何か新しいものを始めたい場合は、製品の成分表を持って、必ず主治医や薬剤師に安全性を確認してください。
日常生活で気をつけるべきこと
ワーファリンを安全に服用するためには、薬や食事の管理だけでなく、日々の生活の中でも注意すべき点がいくつかあります。ここでは、出血のサインや怪我の予防など、日常生活における注意点を解説します。
出血のサインを見逃さない
ワーファリンが効きすぎると、体のあちこちで出血しやすくなります。ささいな出血のサインを見逃さず、異常を感じたらすぐに医療機関に連絡することが重要です。
注意すべき出血のサイン
| 部位 | 具体的なサイン |
|---|---|
| 皮膚 | ぶつけた覚えのない青あざ(皮下出血)、歯ぐきからの出血、鼻血が止まりにくい |
| 消化管 | 黒い便(タール便)、血便、吐血 |
| 尿路 | 血尿(赤色やコーラ色の尿) |
| 頭蓋内 | 突然の激しい頭痛、めまい、手足の麻痺、ろれつが回らない |
転倒や怪我の予防
ワーファリン服用中は、小さな怪我でも出血が止まりにくくなったり、大きな内出血を起こしたりする可能性があります。特に頭を強く打つと、命に関わる頭蓋内出血を引き起こす危険があります。
日常生活では、転倒しないように足元に注意し、滑りにくい履物を選ぶ、浴室に手すりや滑り止めマットを設置するなどの工夫が大切です。また、刃物を使う際は注意し、怪我の危険性が高いスポーツなどは避けましょう。
他の医療機関を受診する際の注意
透析施設以外の病院や歯科医院を受診する際には、必ずワーファリンを服用していることを医師や歯科医師に伝えてください。抜歯などの出血を伴う処置や、内視鏡検査、手術を受ける際には、ワーファリンの管理が非常に重要になります。
お薬手帳を常に携帯し、正確な情報を伝える習慣をつけましょう。
自己判断での服薬中止は絶対にしない
ワーファリンは、血栓症という命に関わる病気を予防するための重要な薬です。出血が心配だからといって、自己判断で服用を中止したり、量を減らしたりすることは絶対にやめてください。
薬の効果がなくなると、脳梗塞などのリスクが急激に高まります。服用に関して不安や疑問がある場合は、必ず主治医に相談し、指示に従いましょう。
よくある質問(Q&A)
最後に、ワーファリンの服用に関して、患者さんからよく寄せられる質問と回答をまとめました。
- 薬を飲み忘れた場合はどうすれば良いか
-
飲み忘れに気づいた時間によって対応が異なります。もし、いつもの服用時間からそれほど時間が経っていない場合(半日以内が目安)は、気づいた時点ですぐに1回分を服用してください。
次の服用時間が近い場合や、翌日になってから気づいた場合は、忘れた分は服用せず、次の服用時間に通常通り1回分だけを服用します。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
判断に迷う場合は、自己判断せず、主治医や薬剤師に電話で相談しましょう。
- 納豆は本当に食べてはいけないのか
-
ワーファリンを服用している間は、納豆の摂取は原則として禁止です。納豆は、ビタミンKを非常に多く含むだけでなく、腸内で納豆菌がビタミンKを作り出すため、ワーファリンの効果を著しく弱めてしまいます。
ひきわり納豆や、におわない納豆なども同様です。一口でも食べると、数日間にわたって薬の効果に影響を及ぼす可能性があるため、厳格に避ける必要があります。
- 市販の風邪薬や痛み止めを飲んでも良いか
-
自己判断で市販薬を服用することは避けてください。
市販の総合感冒薬や解熱鎮痛薬の中には、ワーファリンの効果を強め、出血のリスクを高める成分(アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬など)が含まれていることがあります。
風邪をひいた場合や、頭痛・歯痛などで薬が必要な場合は、まず主治医やかかりつけの透析施設に相談し、ワーファリンとの併用が可能な薬を処方してもらうか、安全な市販薬について薬剤師に確認してから購入してください。
- ワーファリンに代わる新しい薬はないのか
-
近年、直接経口抗凝固薬(DOAC)という新しいタイプの薬が登場しています。DOACはワーファリンと比べて食事制限がなく、効果が安定しているという利点があります。
しかし、DOACは主に腎臓から排泄されるため、腎機能が著しく低下している透析患者さんでは、安全に使える薬が限られています。
現時点では、特定のDOACが透析患者さんにも使用可能となっていますが、適用は患者さんの状態を慎重に評価して判断します。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
Hayashi M, Abe T, Iwai M, Matsui A, Yoshida T, Sato Y, Kanno Y, Warfarin Study Group. Safety of warfarin therapy in chronic hemodialysis patients: a prospective cohort study. Clinical and experimental nephrology. 2016 Oct;20(5):787-94.
Hasegawa H. Clinical assessment of warfarin therapy in patients with maintenance dialysis-clinical efficacy, risks and development of calciphylaxis. Annals of Vascular Diseases. 2017 Sep 25;10(3):170-7.
Yodogawa K, Mii A, Fukui M, Iwasaki YK, Hayashi M, Kaneko T, Miyauchi Y, Tsuruoka S, Shimizu W. Warfarin use and incidence of stroke in Japanese hemodialysis patients with atrial fibrillation. Heart and vessels. 2016 Oct;31(10):1676-80.
Kimachi M, Furukawa TA, Kimachi K, Goto Y, Fukuma S, Fukuhara S. Direct oral anticoagulants versus warfarin for preventing stroke and systemic embolic events among atrial fibrillation patients with chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017(11).
Wakasugi M, Kazama JJ, Tokumoto A, Suzuki K, Kageyama S, Ohya K, Miura Y, Kawachi M, Takata T, Nagai M, Ohya M. Association between warfarin use and incidence of ischemic stroke in Japanese hemodialysis patients with chronic sustained atrial fibrillation: a prospective cohort study. Clinical and experimental nephrology. 2014 Aug;18(4):662-9.
Nochaiwong S, Ruengorn C, Awiphan R, Dandecha P, Noppakun K, Phrommintikul A. Efficacy and safety of warfarin in dialysis patients with atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis. Open Heart. 2016 Jun 16;3(1).
Yang F, Hellyer JA, Than C, Ullal AJ, Kaiser DW, Heidenreich PA, Hoang DD, Winkelmayer WC, Schmitt S, Frayne SM, Phibbs CS. Warfarin utilisation and anticoagulation control in patients with atrial fibrillation and chronic kidney disease. Heart. 2017 Jun 1;103(11):818-26.
Kleinow ME, Garwood CL, Clemente JL, Whittaker P. Effect of chronic kidney disease on warfarin management in a pharmacist-managed anticoagulation clinic. Journal of Managed Care Pharmacy. 2011 Sep;17(7):523-30.
Holden RM, Clase CM. Reviews: Use of Warfarin in People with Low Glomerular Filtration Rate or on Dialysis. InSeminars in dialysis 2009 Sep (Vol. 22, No. 5, pp. 503-511). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
Chen HY, Ou SH, Huang CW, Lee PT, Chou KJ, Lin PC, Su YC. Efficacy and safety of direct oral anticoagulants vs warfarin in patients with chronic kidney disease and dialysis patients: a systematic review and meta-analysis. Clinical drug investigation. 2021 Apr;41(4):341-51.