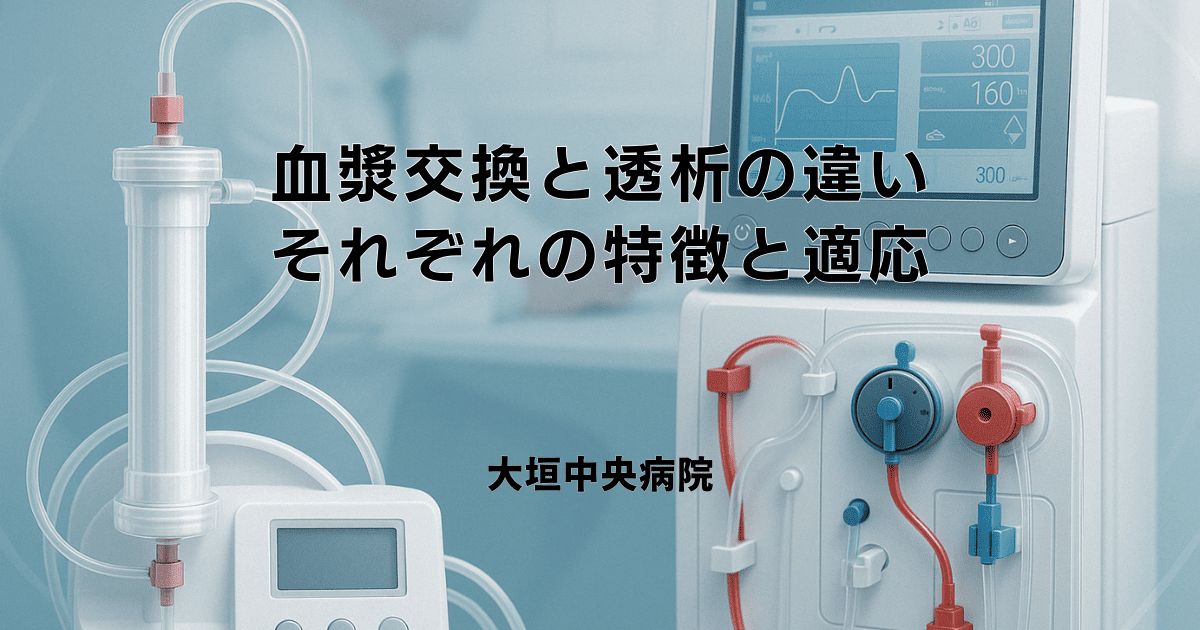慢性腎臓病や自己免疫疾患などの治療を考えるとき、血液浄化を目的とした血漿交換や透析について知ることは非常に大切です。
複数の選択肢がある中で、どのような機序で身体の負担を軽減するのか、そしてどのような疾患に適しているのかを理解することが重要です。
血液のろ過方法や取り除く物質の種類は方法ごとに異なるため、医療従事者の説明だけでは不十分と感じる方もいるかもしれません。
本記事では両者の違いと適応をわかりやすく整理し、受診や治療の選択を考えるうえでの一助となる情報をお伝えします。
血漿交換と透析の概要
血液を浄化するための方法として血漿交換や透析があります。多くの患者が「血液をきれいにする」という漠然としたイメージを持っていますが、実際には異なる原理で有害物質や余分な成分を取り除きます。
初めに、血液浄化の基本となる考え方と、血漿交換および透析の全体像を示します。
血液浄化とは
血液浄化は、体内にたまった老廃物や余分な水分、あるいは異常な免疫因子などを外部で取り除く治療法です。腎臓が十分に機能しないと、老廃物や過剰な水分が体内に蓄積し、さまざまな症状を引き起こします。
自己免疫疾患の場合は、病気の原因となる免疫関連物質を排除する必要があることもあります。血液浄化はこうした症状の進行を抑制するために行う方法のひとつです。
血漿交換とは
血漿交換療法は、血液中の液体成分である血漿を分離し、特定の物質を除去したうえで新しい血漿製剤やアルブミン液などと置き換える方法です。
自己免疫疾患をはじめとした病態で用いられ、主に血漿中の病的な因子(自己抗体など)を除去する目的があります。たとえば劇症筋無力症や重症例の免疫性神経疾患などで検討されることが多いです。
透析とは
透析は、主に腎臓機能が低下した患者のために老廃物や余分な水分を取り除く血液浄化法です。大きく分けて血液透析と腹膜透析がありますが、一般的には血液透析を指すことが多いでしょう。
透析装置の中で半透膜を介して老廃物や水分を除去するのが血液透析です。慢性腎不全や末期腎不全の治療として広く行われており、日常的な通院や在宅治療の選択肢が存在します。
血漿交換と透析の目的の違いをまとめた一覧
| 比較項目 | 血漿交換 | 透析 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 病的因子(自己抗体など)の除去 | 老廃物・余分な水分の除去 |
| 対象疾患 | 自己免疫疾患など | 慢性腎不全など |
| 交換するもの | 血漿成分 | 水分・老廃物 |
| 主な治療頻度 | 病状による不定期 | 定期的(週○回など) |
| 実施場所 | 主に入院環境 | 透析センターや在宅 |
血漿交換の仕組みと特徴
血漿交換は、血漿中に含まれる特定の有害物質を効率的に除去できる点が大きな特徴です。特に自己免疫疾患のように、血液中の免疫グロブリンや自己抗体が症状を悪化させる場合に適用されることが多いです。
この治療では、血液を体外に循環させながら血球成分と血漿成分に分離し、血漿部分だけを捨てて別の液体に置き換えます。
分離の方法
血漿交換は遠心分離方式とフィルター方式の2つが代表的です。遠心分離方式は血球と血漿を遠心力によって分離し、フィルター方式は半透膜や膜フィルターを利用して血漿と血球を分けます。
いずれの方式でも必要以上に血球を捨てないよう工夫されているため、大量出血に相当するようなリスクは低めです。ただし、交換用のアルブミン液や血漿製剤を使うため、それに伴うアレルギー反応や感染症のリスクを注意します。
対象疾患と効果
血漿交換は、自己免疫性疾患に代表される症状に対して高い効果が期待できます。免疫性神経疾患、劇症筋無力症、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーなどを含む幅広い病態で検討されます。
病的因子が血漿に存在する場合、除去によって症状が軽快するケースがあります。また、難治性の血液疾患や急性中毒などで一時的に毒素や病原物質を除去したい場合にも利用されることがあります。
血漿交換のメリットとデメリット
血漿交換は病的因子を短時間で集中的に除去できるため、病状が急激に悪化している場合に救急的に実施することもあります。
一方で、交換用の血漿製剤などを使用するためコストが高くなりやすく、複数回にわたって行う場合は合併症のリスクに注意します。特に、血漿製剤によるアレルギー反応や感染症は看過できない要素です。
血漿交換の基本的な流れに関連する用語一覧
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 血液ポンプ | 血液を体外に導き出すための装置 |
| 分離デバイス | 遠心やフィルターで血漿と血球を分離 |
| 交換液 | アルブミン液や血漿製剤など |
| 抗凝固剤 | 血液の凝固を防ぐ薬剤 |
| モニタリング | 血圧や脈拍、凝固指標などを随時確認 |
透析の仕組みと特徴
透析は、主に腎臓機能が低下した場合に老廃物や余分な水分を除去する治療法です。血漿交換との大きな違いは、病的因子そのものを直接取り除くというより、身体の代謝産物や水分を持続的に管理していく点です。
慢性期の腎機能不全患者が長期にわたり行うことが多く、患者の生活習慣に密接に関連します。
血液透析の仕組み
血液透析ではダイアライザーと呼ばれる装置が使われます。半透膜を通して血液と透析液を循環させることで、体内の老廃物や過剰な電解質を除去し、水分バランスを調整します。
半透膜は分子量に応じて選択的に物質を移動させるため、必要な成分を保ちつつ不要な物質だけを外へ排出できます。週3回程度、1回につき4時間前後の透析を行うことが多いですが、患者の状態によって頻度や時間は異なります。
腹膜透析との違い
透析は、血液透析だけではなく腹膜透析も代表的です。腹膜透析では、自分の腹膜を半透膜として利用するため、自宅で行うことも可能です。
一方で腹膜炎などの合併症に注意が必要となることから、医師と話し合いながら治療方法を選ぶ必要があります。通院が困難な方や小児に対しては腹膜透析を検討するケースが多いです。
透析のメリットと負担
透析は慢性的な腎不全の進行を抑制し、身体の状態を維持するうえで大切な位置を占めます。定期的に通院することで、血液状態を細かくチェックしながら生活習慣にも気を配るようになる方が少なくありません。
一方、透析のための通院スケジュールによる生活の制約や、透析シャントの管理などの身体的負担に悩む方もいます。加えて、透析中の血圧低下や倦怠感などの症状に関する対応策が必要となるケースがあります。
透析に用いられる装置や用語に関する一覧
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| ダイアライザー | 血液透析の要となる半透膜を内蔵した装置 |
| 透析液 | 老廃物や電解質を交換するための液体 |
| バスキュラーアクセス | 血液を効率的に取り出すための血管ルート(シャントなど) |
| UF(超ろ過) | 水分除去の操作 |
| クレンメ | チューブの開閉を行う器具 |
血漿交換と透析の適応となる病気
血漿交換透析違いを理解するには、それぞれどのような病気に使われるかを把握することが重要です。前の項目で概略を示しましたが、より具体的に適応となる病気を見ていきます。
血漿交換の主な適応疾患
血漿交換は、自己免疫や免疫調整を目的とする病態で選択されることが多いです。たとえば多発性硬化症の急性期、劇症筋無力症、重症膠原病の合併症、ギラン・バレー症候群、重症型免疫性血小板減少症などで実施される場合があります。
免疫グロブリンや自己抗体が症状の悪化要因となると判断した場合に用いられ、薬物療法だけでは十分に改善しないケースで検討されます。
透析の主な適応疾患
透析は慢性腎不全や末期腎不全で最も多く実施されます。急性腎不全の一時的な対処として行う場合もありますが、ほとんどは慢性的に行うイメージが強いでしょう。
糖尿病性腎症や高血圧性腎硬化症など、さまざまな原因で腎機能が低下した結果、老廃物や余剰水分の排出が難しくなったときに必要となります。高カリウム血症や体液量過多など、緊急の問題があれば早急に導入することもあります。
治療方針の違い
血漿交換は一度の処置で病的因子を大きく取り除き、症状を急激に改善させる場合があります。しかし短期的な効果にとどまりやすく、免疫の過剰反応が続くと再度実施する必要が出てきます。
一方、透析は慢性的な腎機能不全に対応するため、長期間の継続を前提とした治療計画が組まれることがほとんどです。それぞれの特性を踏まえて治療方針を決定することが求められます。
血漿交換と透析が用いられる主な疾患の比較一覧
| 疾患 | 血漿交換 | 透析 |
|---|---|---|
| 劇症筋無力症 | ○ | △(主目的ではない) |
| 慢性腎不全 | △(特定例のみ) | ○(代表的) |
| ギラン・バレー症候群 | ○ | ×(主目的にはしない) |
| 糖尿病性腎症 | △(特殊例) | ○(頻繁に行う) |
| 重症膠原病 | ○ | △(病態次第) |
血漿交換透析違いのポイント
血漿交換と透析の違いは、病的因子を除去するのか、老廃物や水分を管理するのか、といった治療目的だけではありません。実施環境や頻度、患者のQOL(生活の質)への影響など、多方面にわたって相違点があります。
ここではいくつかの観点をさらに掘り下げます。
有害物質の対象
血漿交換は自己抗体などの特異的な分子を除去するのが得意です。透析はクレアチニンや尿素窒素などの代謝産物を取り除くことに優れています。
両者は取り除く対象が異なるため、同じ患者であっても病気の進行具合や病態によっては両方の方法を組み合わせるケースがあります。
治療の頻度と通院
血漿交換は症状にあわせて不定期に行うことが多く、急性期に集中して数回実施する場合と、定期的に間隔を空けながら行う場合があります。
一方、透析は慢性的な腎不全が対象となる場合が多く、週に複数回の通院または在宅での透析が必要です。スケジュール面での負担は透析のほうが大きいと感じる患者が多いでしょう。
保険適用や費用
血漿交換も透析も保険適用がありますが、血漿交換は交換用の製剤が高価であり、疾患の性質上、入院環境で行うことが多いです。透析は患者数が多く、医療費補助制度も充実しているため、長期間通院するケースを想定した仕組みがあります。
とはいえ、医療費に関しては個々の患者や自治体の制度によって変わります。
血漿交換と透析を比較する要点一覧
| 観点 | 血漿交換 | 透析 |
|---|---|---|
| 主な対象物質 | 自己抗体・免疫因子 | 代謝産物(クレアチニンなど) |
| 頻度 | 病態に応じて不定期 | 週複数回が一般的 |
| 治療期間 | 短期集中 or 必要に応じて | 慢性的・長期 |
| 必要な環境 | 入院管理が多い | 透析施設 or 在宅 |
| 主な費用要因 | 血漿製剤などのコスト | 透析装置や消耗品 |
血漿交換と透析の効果と負担
患者が治療を選ぶ際には、その効果だけでなく身体的・精神的負担も大きな考慮材料です。血漿交換と透析の両者は目的も異なるため、メリット・デメリットの観点も変わります。
身体的な影響
血漿交換は短期間で劇的に症状が軽快する可能性がありますが、血漿製剤の使用に伴うアナフィラキシーや感染症に用心します。また、一時的に血圧が下がったり、体内のタンパク質バランスが崩れたりすることがあります。
透析は長期にわたって週3回ほど実施するケースが多く、透析時の低血圧や不均衡症候群(体液シフトによる頭痛、吐き気など)に気を配る必要があります。
精神面への影響
血漿交換は症状改善が早い場合があり、患者にとっては大きな希望となります。一方、自己免疫疾患のように再燃を繰り返す病態では、何度も血漿交換を受ける可能性があるため、精神的な負担も考えられます。
透析では、通院スケジュールに合わせた生活リズムを確立する必要があり、それに慣れるまでに精神的ストレスを感じることがあります。ただし、生活リズムが安定するほど体調管理もしやすくなる点をメリットに挙げる患者もいます。
家族やサポート体制
どのような治療でも家族や周囲のサポートがあると心強いでしょう。血漿交換では入院期間が必要になることが多く、家族の負担が一時的に増加する可能性があります。
透析では長期的・定期的な通院が中心ですが、在宅透析を選ぶ場合は家族によるサポートが必要となる場合があります。
- 治療スケジュール調整に家族が関わる
- 家族の理解が治療継続のモチベーションにつながる
- 投薬管理や食事制限などでの協力
治療効果と負担に関する比較一覧
| 内容 | 血漿交換 | 透析 |
|---|---|---|
| 効果の速さ | 比較的早く症状改善 | 徐々に状態を維持 |
| リスク | 血漿製剤アレルギーなど | 低血圧や透析不均衡など |
| 心理面 | 病態急変への不安 | 生活リズムへの制限 |
| 経済的負担 | 製剤コストが高い場合あり | 長期継続で費用総額が高額化する |
| サポート | 入院中心 | 通院中心 or 在宅 |
治療を選ぶ上での注意点
血漿交換と透析のどちらが適しているかは、患者の病態や診断内容、生活環境に左右されます。医師とよく相談し、自分の身体だけでなく社会的背景も含めて考えることが大切です。
医師との相談
治療方針を決定するためには、主治医とのこまめなコミュニケーションが重要です。検査結果や症状の変化を踏まえ、どのタイミングで治療を開始するのか、どのくらいの期間を想定するのかを把握しましょう。
特に血漿交換は緊急性の高い場合に行うこともあるため、病状が急変した際の対応をあらかじめ相談しておくと安心です。
合併症や副作用
血漿交換と透析のどちらの治療でも合併症や副作用のリスクはあります。血漿交換では血漿製剤による感染症やアナフィラキシー反応が、透析ではシャント感染や低血圧、電解質異常などが挙げられます。
小さな変化を見逃さず、早めに医療者へ伝えることが悪化を防ぐポイントになります。
生活習慣や社会復帰
透析を選ぶ場合は、週に複数回の通院や食事・飲水制限などが加わります。仕事や学業との両立を考えるときには、通院先の場所や治療時間についてもよく検討する必要があります。
血漿交換は入院で実施するケースが多く、急性期の激しい症状がある場合は仕事を一定期間休む可能性があります。どちらの治療も社会復帰に向けたスケジュール管理が大切です。
治療選択時に考慮したい要素一覧
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 病状の急性度 | 急性期の重症度が高いなら血漿交換を検討 |
| 腎機能の状態 | 慢性的な低下なら透析が重要 |
| 生活リズム | 通院頻度や入院の長さ |
| 経済的・制度面 | 保険適用や医療費補助の有無 |
| 家族のサポート | 在宅療法の可否や協力体制 |
- 医療ソーシャルワーカーとの連携
- 看護師や臨床工学技士のサポート体制
- 必要なときの介護サービスの利用
よくある質問
血漿交換と透析の違いを理解していても、実際の治療選択にはさまざまな疑問が生じます。以下では、患者やそのご家族から多く寄せられる質問を取り上げます。
- 血漿交換と透析を同時に受けるケースはある?
-
特定の疾患において両方の治療を組み合わせる例があります。たとえば腎機能が重度に低下している一方で、自己免疫疾患による急性症状を抑えたい場合、両方を組み合わせて相乗効果を狙います。
ただし、体力的な負担や費用面の問題があるため、慎重な判断が必要です。
- 血漿交換の治療期間はどのくらいが目安?
-
急性期の症状を抑えるために集中して数日から1~2週間ほど行う場合や、慢性疾患の一環で定期的に行う場合など、病態に応じて大きく変わります。治療効果や再燃リスクを見ながら医師が適宜判断します。
- 透析になったら一生続けなければならないの?
-
腎機能の回復が見込めない慢性腎不全の場合、多くは継続が必要です。腎移植などの選択肢もありますが、すぐに移植が可能とは限りません。
一方、急性腎不全では一時的に透析を行い、腎機能が回復すれば中止できるケースもあります。
- 生活習慣で治療効果は変わる?
-
大きく変わります。自己免疫疾患であれば、ストレスを減らし睡眠を十分に確保することが症状の安定につながります。透析患者であれば、食塩やカリウムなどの管理が治療成績に反映されます。
医師や管理栄養士の指導を受けながら、日々の習慣を整えることが大切です。
以上
透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )
参考文献
SECK, Sidy M.; BERTRAND, Dussol; BOUCAR, Diouf. Current indication of plasma exchanges in nephrology: a systematic review. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation, 2011, 22.2: 219-224.
CLARK, W. F. Plasma exchange for renal disease: evidence and use 2011. Journal of Clinical Apheresis, 2012, 27.3: 112-116.
HILDEBRAND, Ainslie M.; HUANG, Shih-Han S.; CLARK, William F. Plasma exchange for kidney disease: what is the best evidence?. Advances in Chronic Kidney Disease, 2014, 21.2: 217-227.
SCHAEFER, Betti, et al. Safety and efficacy of tandem hemodialysis and plasma exchange in children. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2014, 9.9: 1563-1570.
WILLIAMS, Mark E.; BALOGUN, Rasheed A. Principles of separation: indications and therapeutic targets for plasma exchange. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2014, 9.1: 181-190.
FERNÁNDEZ-ZARZOSO, Miguel; GÓMEZ-SEGUÍ, Inés; DE LA RUBIA, Javier. Therapeutic plasma exchange: review of current indications. Transfusion and Apheresis Science, 2019, 58.3: 247-253.
CLARK, William F., et al. Plasma exchange when myeloma presents as acute renal failure: a randomized, controlled trial. Annals of internal medicine, 2005, 143.11: 777-784.
REDDY, Sudheer Kumar, et al. Plasma exchange for paediatric kidney disease—indications and outcomes: a single-centre experience. Clinical kidney journal, 2015, 8.6: 702-707.
GASHTI, Casey N. Membrane‐based therapeutic plasma exchange: a new frontier for nephrologists. In: Seminars in Dialysis. 2016. p. 382-390.
SAMANCI, Nilay Sengul, et al. Patients treated with therapeutic plasma exchange: a single center experience. Transfusion and Apheresis Science, 2014, 51.3: 83-89.