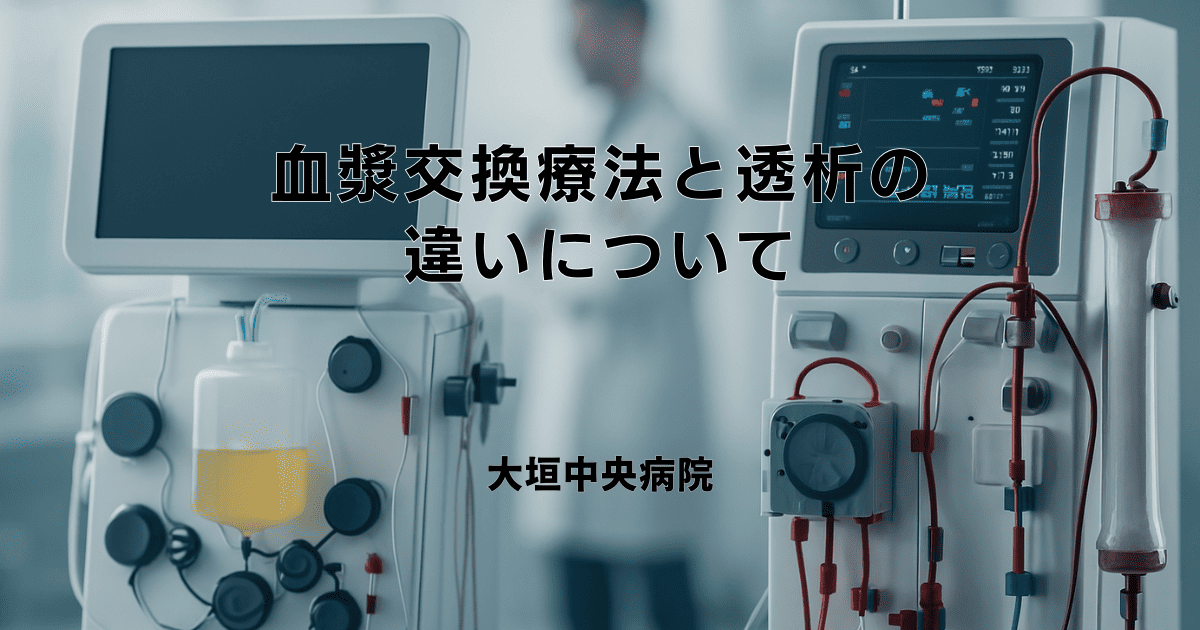血液を浄化する治療として、血漿交換療法や透析が広く行われています。腎臓の機能が低下している方や自己免疫疾患などで有害物質の排出がうまくいかない方にとっては、こうした治療が欠かせません。
ただし、血漿交換療法と透析では目的や適応疾患、治療方法が異なるため、「どちらを選んだらいいのか」「どのような効果があるのか」と迷うこともあります。
この記事では、それぞれの治療の特徴や選択基準、日常生活への影響をわかりやすく解説します。
血漿交換療法と透析の基本概要
血漿交換療法と透析はいずれも体内の有害物質を除去する治療ですが、具体的な仕組みは異なります。
どちらの治療を選ぶかは疾患や患者さんの状態によって変わりますが、大まかな違いを理解しておくと治療計画を立てる際に役立ちます。
血液のろ過と成分除去の考え方
血液を浄化する方法には、主に「ろ過」と「置換」の考え方があります。透析は主に血液中の老廃物や余分な水分を除去し、電解質バランスを調整します。
一方、血漿交換療法は血漿を分離して特定の有害物質を含む成分を取り除き、新しい代用血漿を補充する方法です。
血漿交換透析違いを把握しておくと、自分の症状や診断結果に合った治療法を選びやすくなります。
血漿交換療法の概要
血漿交換療法は、血液中の血漿部分だけを取り除き、代わりに新しいアルブミン液や血漿製剤を補充する仕組みです。自己免疫疾患などで原因となる抗体を下げたり、毒素や病的な免疫複合体を除去したりする目的があります。
高脂血症や重症筋無力症など特定の疾患で用いられることが多く、血液科での専門的な管理が重要になります。
透析療法の概要
透析には血液透析と腹膜透析の2種類がありますが、主に腎臓の機能が低下して老廃物や水分調整がうまくいかないときに実施します。
機械を用いて血液を体外に導きダイアライザと呼ばれる装置で老廃物と余分な水分をろ過するのが血液透析で、腹膜透析は腹腔内に透析液を入れて老廃物を除去します。
日常生活に影響しやすく、自己管理も必要なため、医療スタッフとの連携が欠かせません。
それぞれの目的
血漿交換療法は自己免疫性疾患や免疫が関与する病気に用いて、原因となる成分を直接除去して症状の改善を目指します。
透析は腎不全の患者さんにとって、人工的に腎機能を補う治療で、老廃物や余分な水分を除去し体内環境を整えます。疾患のタイプや目的、急性か慢性かによって大きく選択肢が変わります。
血漿交換と透析の主な治療目的
| 治療法 | 主なターゲット | 使用目的 |
|---|---|---|
| 血漿交換療法 | 自己免疫性疾患や特定の病態の原因物質 | 抗体や病的蛋白質の減少 |
| 血液透析 | 老廃物や余分な水分 | 腎機能低下時の排泄補助 |
| 腹膜透析 | 老廃物や余分な水分 | 在宅でも腎機能を補助しやすい |
血漿交換療法を選ぶ理由
血漿交換療法は自己免疫疾患をはじめ、急性期に原因物質を集中的に除去したい状況で選ばれます。血漿を一度取り除いて必要な代用物質を補充するため、特定の疾患に深くアプローチできる点が特徴です。
血中有害物質の除去と治療対象
血漿交換療法は、血中に存在する免疫複合体や不要なタンパク質を取り除きやすい利点があります。
特に、血漿中に溶け込んでいる抗体や自己免疫反応を惹起する分子などをスピーディに取り除くことができるため、重症例や急速に進行する病気に対応しやすいと考えられます。
治療の対象疾患と適応条件
血漿交換療法は、重症筋無力症や慢性炎症性脱髄性多発神経炎、劇症肝炎など、免疫や毒素が深く関与する疾患で選ばれます。適応かどうかは医師の診察や検査結果によりますが、急性増悪を伴う自己免疫疾患や高脂血症などが代表的です。
日常生活における症状のコントロールが難しい方や薬物療法だけでは改善が得られにくい場合にも検討されます。
血液科での取り組み
血漿交換療法の実施にあたっては、専門の血液科医が患者さんの血液成分や免疫学的指標を詳しく評価します。血漿交換の頻度や交換量、補充するアルブミン製剤や血漿製剤の種類などを総合的に判断し、合併症のリスク管理も行います。
治療開始前や経過観察中に血液検査や血圧・出血傾向のチェックを重ね、安全性を担保する仕組みを整えています。
血液事業学会の動向
血液事業学会などの研究やガイドラインの改訂によって、血漿交換療法の適応範囲や推奨される手技が見直されることがあります。病院ではそうした学会発表の情報を踏まえ、適切な手法と安全対策を検討します。
学会がまとめる診療ガイドラインでは、疾患ごとの治療方針や副作用対策などを更新しており、それが医療現場での実践に反映されています。
主な疾患別にみる血漿交換療法の適応例
| 疾患名 | 適応の有無 | コメント |
|---|---|---|
| 重症筋無力症 | 適応になることが多い | 免疫介在性疾患。症状の急速改善を狙う |
| 劇症肝炎 | 場合によって適応 | 高アンモニア血症・肝不全の改善を支援 |
| 高脂血症 | 適応になることがある | LDLコレステロール過多やアポBの除去に有効 |
| 免疫性神経疾患 | 適応になることが多い | GBS、CIDPなど免疫関連疾患で症状緩和を期待 |
透析を選ぶ理由
透析は腎不全や腎機能低下による尿量減少、血中老廃物蓄積などが原因で治療が必要な方に行います。慢性腎不全になると、人工的に腎機能を補わないと体内の毒素が排泄されず、深刻な症状に陥るリスクがあります。
腎機能低下と末期腎不全
腎臓は血液をろ過して尿をつくり、有害物質や余分な水分を排泄する役割を担います。腎機能が慢性的に悪化すると、末期腎不全の段階で透析が必要になる可能性があります。
これまでの病歴や糖尿病、高血圧といった基礎疾患を持つ方は、透析治療を視野に入れて早めに専門医に相談するとよいでしょう。
透析の種類(血液透析・腹膜透析など)
透析には大きく分けて血液透析と腹膜透析があります。血液透析は週に数回、医療機関や自宅に設置した透析機器で行い、血液を体外に取り出してダイアライザという膜を通して老廃物と水分を取り除く方法です。
一方、腹膜透析は腹腔内に透析液を注入し、腹膜をフィルターとして老廃物を除去する方法で、自己管理や操作手順を習得すれば自宅療法として続けられます。
治療のメリットと負担
透析療法では、腎機能低下で排出しきれなくなった老廃物や水分を取り除けるため、体調の安定が期待できます。一方で、透析に必要な通院や機器管理、食事制限などの負担も無視できません。
自己管理が欠かせないため、主治医や看護師、栄養士との綿密なコミュニケーションが大切になります。
透析療法のメリットと注意点
| 項目 | 血液透析 | 腹膜透析 |
|---|---|---|
| メリット | 管理を医療スタッフに任せやすい | 在宅で行える |
| 注意点 | 通院の頻度が多くなる | 交換操作の習得や感染対策が必要 |
| 適切な実施場所 | 病院または在宅の専用装置 | 自宅(専用スペース要) |
生活習慣の見直し
透析を行う場合、毎日の水分や塩分、カリウム・リンなどの摂取量の管理が欠かせません。透析前に比べて飲食の自由度が下がることも多いため、生活習慣の見直しが早期から必要です。
適切な栄養バランスを確保するため、専門の栄養指導を受けながら体調管理を続ける方が多くいます。また、日常的な運動や休息のバランスを整えることも透析患者さんにとって重要です。
血漿交換透析違いの治療効果とリスク
血漿交換療法も透析も、体内の有害物質を除去して症状を改善することに主眼を置いていますが、適応する疾患が異なり、リスクや合併症にも違いがあります。
血漿交換療法に伴う合併症
血漿交換療法では、血漿除去時に血圧低下や凝固異常が生じることがあります。また、置換用のアルブミンや血漿製剤に対するアレルギー反応も起こり得るため、術中・術後の注意が必要です。
頻回に行うと、血漿成分の喪失により一時的に体内の免疫バランスが乱れる可能性もあります。
透析特有の合併症と対処
透析(特に血液透析)では、透析中の血圧低下、倦怠感、頭痛、透析後の筋肉のけいれんなどがよくみられます。また、長期的には二次性副甲状腺機能亢進症や骨代謝異常なども生じやすいです。
腹膜透析においては、腹膜炎やカテーテル関連感染などのリスクがありますが、正しい手技と衛生管理で回避できる可能性は高まります。
共通する注意点
いずれの治療でも、血管アクセスの確保や体外循環を扱うため、出血リスクや感染リスクは共通課題となります。針の穿刺やカテーテルの管理には十分な衛生対策が必要です。
体力的・精神的な負担の軽減を図るためにも、医療者としっかりコミュニケーションをとりながら進めることが大切です。
経過観察の重要性
血漿交換療法や透析は一度始めれば終了ではなく、長期的に定期的な経過観察を続けることが重要です。血液検査や病状の変化、合併症の有無などを確認しながら治療方針を調整します。
治療後の副作用が出た場合や体調に変化があった場合は、すぐに担当医へ相談し、必要に応じて対策を講じる流れが望ましいです。
合併症に関するリスク比較
| 項目 | 血漿交換療法 | 透析 |
|---|---|---|
| 術中の血圧低下 | 発生しやすい場合あり | 血液透析中に起こることが多い |
| 感染 | カテーテル挿入時などに注意 | シャント部や腹膜透析カテーテル管理が重要 |
| アレルギー反応 | 補充製剤への過敏反応 | 透析装置に用いる材料へのアレルギーはまれ |
| 長期的な骨代謝異常 | 可能性は低い | 長期透析患者で慢性的な骨代謝異常が生じることあり |
医療機関での検査と準備
血漿交換療法や透析を受ける際には、事前の検査や準備が欠かせません。どのような検査を行い、どの程度の通院や入院が必要かを事前に把握しておくと、治療に対する心構えがしやすくなります。
事前検査の内容
血液検査はもちろん、胸部エックス線、心電図、腹部エコー、場合によっては血管の状態を評価する検査などを行います。血漿交換を行う場合は凝固機能の評価や血液型の確認、感染症のチェックが念入りに実施されます。
透析であれば、血管アクセス(シャント)の作成や腹膜透析カテーテルの挿入前検査も重要です。
機器や環境の整備
血漿交換療法では血漿分離用の装置とアルブミン製剤や血漿製剤を準備し、透析ではダイアライザや透析液などを用意します。
医療機関では感染対策や安全管理の観点から、専用の部屋や装置の定期メンテナンスを行い、治療の質を維持します。
血液浄化装置と必要資材
| 治療法 | 主な装置 | 必要資材 |
|---|---|---|
| 血漿交換療法 | 血漿分離装置 | アルブミン製剤、血漿製剤 |
| 血液透析 | ダイアライザ | 透析液、血液回路 |
| 腹膜透析 | 自動腹膜灌流装置 | 透析液、カテーテル |
専門スタッフの役割
血漿交換療法では医師や看護師だけでなく、臨床工学技士などが装置の操作やメンテナンスを行います。
透析の場合も、透析看護の専門知識を持った看護師が患者さんのバイタルサインの管理や針の穿刺を担当し、臨床工学技士が透析機器を適切に操作します。各分野の専門家が連携することで、安全に治療を進めることが大切です。
心身のサポート体制
長期的に治療を続ける場合、メンタルサポートやリハビリなどの多職種連携も視野に入れます。特に自己免疫性疾患は再燃リスクがあり、透析は長期通院が前提となります。
医療チームや家族と相談しながら、無理なく治療を継続できる環境づくりを整えることが大切です。
治療を受ける流れ
血漿交換療法や透析をどのようなペースで受けるのかは、疾患の状態や患者さんの都合によって変わります。一般的な流れを把握しておけば、実際の治療をイメージしやすくなるでしょう。
通院頻度と治療時間
血漿交換療法は週1回から数回、状態が急性期の場合はもっと短い間隔で行うケースがあります。1回あたりの治療時間は2〜3時間ほどですが、準備や待ち時間を含むと半日を要する場合もあります。
透析は通常、血液透析なら週3回程度、1回あたり4時間前後が目安です。腹膜透析は1日に複数回の交換作業か、夜間の自動装置を使うなど手法によって異なります。
治療間隔と所要時間の目安
| 治療法 | 週あたりの回数(例) | 1回の所要時間(例) |
|---|---|---|
| 血漿交換療法 | 1〜3回 | 2〜3時間 |
| 血液透析 | 3回 | 4時間程度 |
| 腹膜透析 | 毎日または夜間装置 | 30分〜数時間 |
自宅管理が必要なケース
腹膜透析を選ぶ場合は、自宅での管理が中心になります。透析液の交換作業や衛生管理を自分で行う必要があり、最初は医療スタッフから手技指導を受けながら練習します。
血漿交換療法は主に入院や通院での実施が中心ですが、一部在宅型の治療が研究されることもあります。
体調管理と経過観察
定期的に血液検査で貧血や電解質バランスをチェックします。透析患者さんは体重増加や血圧変化を記録する習慣が重要になり、血漿交換療法を受けている方は免疫力や感染リスクなどを意識します。
自己観察と医療機関の検査を合わせることで、トラブルを早期発見しやすくなります。
受診時のチェック項目
治療日や受診日に医師や看護師が確認するポイントとしては、以下のようなものがあります。
- 血圧や体重、脈拍などのバイタルサイン
- 皮膚の状態やシャント(またはカテーテル)部位のトラブルの有無
- 食事内容や水分摂取量
- 疲労感やめまい、その他の自覚症状
こうした項目を細かく記録することで、治療効果や合併症の有無を早期に把握します。
日常生活のポイント
血漿交換療法や透析を受けることになっても、日常の暮らしを工夫して維持することは可能です。治療と並行して生活習慣や仕事、家族との時間をうまく両立させるためのヒントをまとめます。
食事と栄養管理
透析患者さんの場合、食事内容に気を配ることが非常に大切です。塩分や水分の制限だけでなく、カリウムやリンの摂取量に注意しなければいけません。
血漿交換療法を受けている方も、免疫バランスや代謝に考慮した栄養摂取を心がけると回復を促進しやすくなります。
管理栄養士による指導を受ける際には、自分の嗜好や生活リズムを正直に伝え、その上で調整した献立を組んでいく流れが一般的です。
運動と身体活動
運動は血行を良くし、筋力や体力の維持に役立ちます。腎不全や自己免疫疾患でも、適度な運動を継続することが病状コントロールにプラスに働く場合があります。
ただし、過度の運動はかえって疲労や筋肉障害を起こす可能性があるため、担当医と相談しながら無理のない運動量を設定するとよいでしょう。
日常生活で取り組みやすい運動の例
- ウォーキングや軽いジョギング
- ストレッチ体操
- ヨガや太極拳などの緩やかな動作
- 自宅での軽い筋力トレーニング
仕事や学業との両立
治療に時間がかかる上、体調も日によって変動しがちです。それでも周囲の理解と支援があれば、仕事や学業を続けることは可能です。特に透析患者さんは通院日や治療時間を考慮し、勤務時間の調整や在宅ワークを活用する場合もあります。
血漿交換療法を受ける方は、治療回数によっては入院期間が長引くケースもあるため、事前に職場や学校と相談しておくと安心です。
家族や周囲のサポート
治療が長期化するほど、一人で抱え込むと精神的・肉体的負担が大きくなります。家族や周囲に情報を共有し、通院や入院時のサポートを得られるようにしておきましょう。
特に自己免疫疾患や透析治療では日々の管理が欠かせないので、身近な人の理解と協力が治療継続を支える大きな力になります。
生活面で意識したい点まとめ
| 項目 | 内容 | 重要性 |
|---|---|---|
| 食事制限 | 塩分・水分・ミネラルバランスの調整 | 透析患者は特に必須 |
| 運動 | 軽めの有酸素運動やストレッチ | 血行促進とストレス軽減 |
| 仕事・学業 | 通院と両立可能な環境づくり | 時間調整や在宅勤務の活用 |
| メンタルサポート | ストレス管理や家族・友人との連携 | 長期治療の負担を和らげる |
Q&A
- 血漿交換療法と透析は同時に行うことはあるのでしょうか?
-
特定の病態で、血漿交換と透析を組み合わせることもあります。
たとえば、重症の免疫複合体性腎炎で腎機能が低下しているケースでは、両方を活用して血漿中の異常成分を素早く除去しながら、透析によって老廃物や水分を管理することがあります。
ただし、同時実施の負担も大きいので、患者さんの状態や治療目標を医師とよく相談して決める流れです。
- 血漿交換療法はどのくらいの期間続ける必要がありますか?
-
自己免疫疾患などでは、急性期や症状の悪化期に集中して行う場合が多いです。症状が落ち着いた後に定期的に行うケースもあれば、1度の集中治療で終了するケースもあります。
主治医の判断や疾患の経過に応じて治療回数や期間を調整します。
- 透析が必要かどうかの判断はどのように行われますか?
-
腎機能を示す血液検査(クレアチニン、推算GFRなど)や尿量、症状の有無などで総合的に判断します。
糖尿病や高血圧が原因で徐々に腎機能が下がる方は、血液科や腎臓内科で定期的に検査を受け、腎機能が一定値以下になった段階で透析を検討します。
また、透析導入前にシャント造設などの準備が必要なため、早めに相談することが望ましいです。
- 治療費はどのようにカバーされますか?
-
血漿交換療法も透析も、高額療養費制度や医療保険によって一定の自己負担軽減措置があります。人工透析を受ける場合は障害者手帳の申請などで自己負担がさらに軽減される仕組みが整備されています。
治療にかかる費用や保険手続きは、医療ソーシャルワーカーや市区町村の窓口に相談すると具体的な案内が得られます。
以上
参考文献
CLARK, William F., et al. Plasmapheresis for the treatment of kidney diseases. Kidney international, 2016, 90.5: 974-984.
OCAK, Ilhan; COLAK, Mustafa; BILICI, Bilge Nur. Comparative Analysis of Plasmapheresis Versus Plasmapheresis Combined With Continuous Renal Replacement Therapy in Adult Liver Failure: A Retrospective Observational Study. In: Transplantation Proceedings. Elsevier, 2025.
KOZANOĞLU, Ilknur; SAHIN, Osman; KIS, Cem. Comparison of Double-Filtration Plasmapheresis and Plasma Exchange. In: Problem Solving in Apheresis Medicine. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. p. 179-182.
CID, Joan, et al. Comparison of plasma exchange procedures using three apheresis systems. Transfusion, 2015, 55.5: 1001-1007.
ZHANG, Defeng, et al. Efficacy of three plasma exchange methods in improving renal insufficiency after kidney transplantation and the in-duction of plasma exchange related adverse reactions: a comparative study. Chinese Journal of Blood Transfusion, 2024, 37.7: 742-747.
SECK, Sidy M.; BERTRAND, Dussol; BOUCAR, Diouf. Current indication of plasma exchanges in nephrology: a systematic review. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation, 2011, 22.2: 219-224.
WARD, David M. Conventional apheresis therapies: a review. Journal of clinical apheresis, 2011, 26.5: 230-238.
AHMED, Sadiq; KAPLAN, Andre. Therapeutic plasma exchange using membrane plasma separation. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2020, 15.9: 1364-1370.
FERNÁNDEZ-ZARZOSO, Miguel; GÓMEZ-SEGUÍ, Inés; DE LA RUBIA, Javier. Therapeutic plasma exchange: review of current indications. Transfusion and Apheresis Science, 2019, 58.3: 247-253.
HANSRIVIJIT, Panupong; GHAHRAMANI, Nasrollah. Combined rituximab and plasmapheresis or plasma exchange for focal segmental glomerulosclerosis in adult kidney transplant recipients: a meta-analysis. International Urology and Nephrology, 2020, 52: 1377-1387.